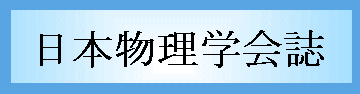
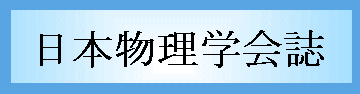
このページでは,物理学会誌「新著紹介」の欄より, 一部を, 紹介者のご了解の上で転載しています.
ただし,転載にあたって多少の変更が加わっている場合もあります. また,価格等は掲載時のもので,変動があり得ます.
World Scientific, Singapore and New Jersey, 1998, xxi+510p., 30.5×21.5cm, \22,200
1989年に刊行されたドイツ語版の拡張英訳版である. 著者は生物学を中心とする在野の研究者で, 造形芸術活動も行っている.
Symmetryは, 日本では対称あるいは対称性という翻訳語を通じての理解が根底にあり, 哲学事典にその項目がなくとも奇異な感はない. しかし, 西欧文化では, 事情が異なるようである. 科学と芸術をつなぐ重要なキーワードとして機能している. 具体的にこの観点を日本に伝えた書であるWeylのSymmetry(1952, 邦訳1957)を思い浮かべれば, 本書のイメージは一応想像できるが, A4判で500頁を超える大著であり, 話題はいっそう多岐に及ぶ. また, 精密科学が根底でない点が基本的に異なり, 特に, 進化という観点で自然と芸術を貫こうという柔らかいアプローチである. いずれにしても, 我が国における形の学際研究(形の科学会, 形の文化会会, 高次元科学会)および提携関係にあるsymmetryの学際研究とともに, D u rer, Kepler, Goethe, Haeckel, D'Arcy Thompsonなどに代表される形態学を軸とする総合的な学問の試みの流れに属する.
本書は数層の構造をもつ大著である. 例えば, 15章のうちページ数で3分の1を超える第11章は, 洞察力の獲得に至る人間の知覚系の進化を論じ, 利き腕・利き目についての実験に触れた後, 複数絵の両眼立体視を議論する. 大きさ, 形, 色など, 左右の対象物間の対称性をさまざまに崩した十数種の実験を論じる. その中には多義図形など左右の調和に苦しむ場合もある. 興味深いが, 言葉の問題もあり, 状況が完全には把握できなかった. そして芸術の話に移る. 辞書を片手に言葉に忠実に理解しようというのは, かなり煩わしい. 非常におおざっぱに筋道をいうことはできるが, 部分の詳細や論理をもう少し深く書けと要求されると断りたくなる. 物理の論文に対しても含めて, 私の一般的態度であるが, 読みにくい他人の論文は, 必ずしも著者の論旨に沿う理解にこだわらない. その論文に何らかの魅力を感じるならば, 自己流の解釈に努める. 収穫があった場合にはその影響に応じた敬意を著者に対して払う. このデンで表現するならば, あまりこだわらずにパラパラめくって眺めているうちに, 何かのヒントが得られたり, アイデアが掴めたり, といったことが期待できそうな本ではある. 最後に, このデンでの収穫を論として書くならば以下のようになる.
別の物事の間に共通点を見ることがsymmetryの本質である. 何事かを共通点と見なせば, 群論のような論理構造が用意されており, 科学の強力な手段となる. ある限定された条件下でならば, 可能性を網羅し, 他の可能性を論理的に否定することも可能である. これが精密科学におけるsymmetryの威力である. しかし, このような狭い意味でのsymmetryには半端はなく, all or nothingである. そして, 空間全体を対象とするなど科学的あるいは数学的な理想化, モデル化が前提となっている. 現実との対応が埒外にあり, かつ重要であることには心する必要がある.
さて, 精密科学ともっと柔らかい対象を扱う学問との間には, こうしたギャップが生じてしまう. 「共生」 が強調される時代の学問にとって無視できない問題である. 精密科学にとって, symmetry概念のいっそうの有効化が必要なのは, 新しい共通点が見える視点の発見と, 狭いsymmetry概念緩和の努力ではなかろうか?
一方, 近代科学は定説を決定して進み, 既知領域が単調に増えて未知領域が単調に減ると思いがちである. しかし, 発展しつつある近代科学の途中から参加した日本と, 最初から関わっている社会とでは, さまざまな事情が違うと思う. 私が感じる違いの一つは専門家と在野研究者との関係である. より正確には, 正統という認知を得ていないものに対して率直に評価しえない風土である. 分化して進化・発展を遂げた現代科学の先端で判断すれば, 専門家と在野科学者の水準が違うのは当然である. しかし, 「将来の先端」 がいかにして形成されるのかを考えるならば, 常識を変えなければならない. ベンチャービジネス云々で期待されることの本質とも関わろう.
ページの頭に戻る
岩波書店, 東京, 1999, 426p., 15×10.5cm, 本体760円
いよいよ量子力学史研究に踏み込まれたか. 本書の編訳者山本義隆氏のこれまでの科学史関係の業績を知る人なら誰でもまずそう思うに違いない. それでは, なぜいまボーアの論文集なのか.
ボーアの名は一般にはほとんど知られていないが, 物理学界における影響力という点ではアインシュタインを凌ぐほどである. とくに量子力学の形成におけるボーアの役割は大きく, その解釈に関してはボーアの相補性の考えに基づく 「コペンハーゲン解釈」 が主流となっており, こんにちほとんどの教科書はこの解釈の立場で書かれている. ‘ほとんどの学生は, 基本的な問題に疑問を抱く余裕もなく, 計算処方の習得に追われている.’ (‘ ’内は編訳者からの引用)それでも, 量子力学の試験に満点を取り, 論文を量産するのに何の支障もきたさない. いまさらボーアを読む必要があろうか.
よく知られているように, 相補性の考えは, アインシュタインによる批判に悪戦苦闘してこたえながら, ボーアが練り上げ精密化し深化していったものである. ボーアとアインシュタインの間には自然観, 物理学観において根本的な違いがある. ボーアとしてはアインシュタインの批判をことごとく論破したが, アインシュタインはそれに納得したわけではなく自分の基本的な考えを変えることはなかった. コペンハーゲン解釈はいまでこそ正統的解釈として確立しているが, 今後もずっとこの解釈が絶対的に正しいという保証はない. ‘あるものが歴史的に形成されたものであることを知ることは, それが歴史的に相対化される日がいつかくるかもしれぬという可能性を認めることでもある.’
だからこそ, いま量子力学の基礎を見直す必要があるのではないか. 原典に立ち戻ってボーアの思想を熟読することは, 物理学者, 哲学者, 科学史家, ばかりでなく, 若い人たちにとっても, また20世紀の思想を考える人にとっても, 十分意味がある, と山本氏は強調する. 他方で, 権威のあるものを鵜呑みにするな, という警告も発せられている. いずれにせよ, 山本氏は, 地道な科学史研究が最も説得力ある現代科学批判になりうるということを知っている人である.
量子力学形成後の量子力学に関するボーアの論文ほとんどすべてが訳出され, その第1巻である本書には量子力学の解釈・相補性の考えに関する論文16編(特別に, 国連への公開書簡が含まれる)が年代順に収録されている. 出版予定の第2巻には量子力学形成の歴史や回顧が収録されるという. すべての論文に注釈がつけられ, 巻末の 「ボーア-アインシュタイン論争」 と題する解説は, 論文を読むのにも役立つ.
ボーアの文章は難解なことで定評がある. 翻訳にはさぞご苦労されたにちがいない. 心から敬意を表したい.
ページの頭に戻る
海鳴社, 東京, 1999, 286p., 21×15cm, 本体2,400円
地球は物質的にはほぼ閉鎖系であり, 熱的には開放系である.
しかし、これだけの認識では環境問題を論ずるには不十分であるばかりか, 誤った議論に陥る危険がある, というのが著者の主張である.
環境問題の主役は生態系であり, 物理学がここにどのように関与しているかを明らかにすることが, 環境問題の正しい理解につながる. そもそも生物体は, シュレーディンガーの言葉を借りれば, “負のエントロピーを食べて生きている“存在であって, エントロ ピーを考慮せずに, 生態系ひいては環境問題を論じることはできない, と著者はいう.
「エントロピー増大則」 の大原理に従う宇宙の中で, 生物がいかにして局所的にエントロピー減少を実現しているのか. 著者はこのプロセスの中で 「低エネルギー, 低エントロピー源」 としての水の果たす重要な役割に注目する. 水は生体に低エントロピー源として採り入れられ, 水蒸気になって体外に放出される時に生体からエントロピーを取り去る. 水蒸気は高空で凝固 してふたたび低エントロピーの水になるが, その際, 高エントロピーのエネルギーである赤外線を宇宙空間に放射する. 地球自身は高エネルギー・低エントロピーの太陽光を宇宙空間から受け取り, 低エネルギー・高エントロピ ーの赤外線を放出することによって, 生態系の維持に貢献している.
食糧や太陽光などの高エネルギー・低エントロピー源は生体を構築・維持するために不可欠であるが, その過程が順調に行われるためには, 生体外へのエントロピーの廃棄がなされなくてはならない. そのことが正しく理解されていないと著者は歎く.
学生時代, 熱力学をあまり真面目に学ばなかった評者は, 熱力学が生物の物理学であることの革命的な意義を恥ずかしながらこの書によって初めて認識した. この書は著者が信州大学と高 千穂商科大学で行った講義ノートに基づいており, 説明は平易ではっと気づかせられる実例に満ちている. 単位質量あたりの太陽が発する熱と同じ質量あたりの人間が発する熱とはどちらが大きいか, などという例題は意表をつく. それにこの書は学生との共同作業である, という著者の授業風景を彷彿とさせる暖かみが感じられる書物でもある.
学生の理科離れが憂慮されている現在, 身近でしかも物理的洞察に満ちたこの書の一読を教師の各位にも薦めたい.
ページの頭に戻る
サイエンス社, 東京, 1999, vi+165p, 本体1,857円
この紹介の原稿を書いているとき著 者高林氏の訃報に接した. 謹んでご冥福を祈る.
今まで他人の本を読んでその評を書 くということはしたことがなかったが, 今春この本を示されたとき, これは読んでみたいと思った. 謹厳な真摯な著者が量子力学をどのように解釈しているか知りたかったのである. 手にしてみるとなかなかの, 読み応えのある力作である.
まず第1章のプロローグに始まる数章で量子力学の基本的構成を, 著者の考えに従ってまとめてある. 著者がもっとも力を入れた部分であろう. 量子力学を一応履修して, それを自分なりにまとめようとする学生は読んでみるべきである. 決して読みやすくはない. 数学的公理論的にまとめてあるのでなく, むしろ哲学的な文体である. 意味のわかりにくいところもある. しかしそれで構わないのである. 本書は教科書ではない.読者は内容を既に理解しており, それを如何にまとめ, 表現するかが問題なのである.
第6章以降は調子が変わり変換および対称性の理論が述べられる. ユニークな大作ではあるが,この著書の真髄はやはり初めの量子力学の構成の部分にあると言うべきであろう.
序文に書いてあることだが, 著者は量子力学を極めて深遠な難しいものとし, それに正面から向かって格調高い文体でまとめたのである. 量子力学が 難しいかに関し, 著者の考えには個人的には賛成できない. 著者に物理的論争を挑んだのだが, 返事を頂けずに終わってしまった. 詳細は新著紹介の範囲を超えるので別の機会に譲る.(本号p. 211「談話室」参照)
繰り返しになるが, この本は量子力学とは何かを深く考えたい読者に勧めたい. 表紙にFor Senior & Graduate Coursesとあるが, Senior courseの学生には読みこなすのが無理かもしれない. むしろSenior(年寄り)向けと言うべきだろう.
ページの頭に戻る
Birkhauser, Basel and Boston, 1999, xviii+434p., \8,430
LiseMeitner'と聞いて何を思い浮かべるだろうか? EinsteinはMeitnerをドイツのCurie夫人と評したと言われるが, Meitnerの知名度はCurie夫人のそれと比較すると頗る低い. 一方, 近年ジェンダー論的観点で書かれたMeitnerの伝記では,1) 彼女が研究者として受けた女性差別が指摘され, Meitnerは原子核分裂の発見に貢献したにもかかわらず‘ノーベル賞を受賞できなかった女性’として描かれている. 本書は科学史家によって書かれたMeitnerの伝記であり, 著者は多数の文献をもとに, 原子物理学の発展という文脈の中でMeitnerの業績を評価している. 特に原子核分裂が発見される以前にMeitner-HahnチームとSoddyやJoliot-Curie夫妻との間でなされた研究上の争いは, 放射能研究が当時の開拓的分野であったことを物語り興味深い. しかしやはり本書でも原子核分裂発見にまつわるノーベル賞受賞の話題が一つの焦点になっている. 1) C.ケルナー: 『核分裂を発見した人』 (晶文社, 1990), U.フェルシング: 『ノーベル・フラウエン』 (学会出版センター, 1996)
MeitnerとHahnの超ウラン元素に関する共同研究の延長上に原子核分裂が発見されるが, それを確認する以前, 1938年の春にユダヤ系のMeitnerはナチから逆れるためドイツ脱出を強いられた. 2) 1938年末, Meitnerは甥のFrischとともに原子核分裂について最初の物理的説明を行うが, 1944年のノーベル化学賞はHahnのみに与えられた. Meitnerは原子核分裂が発見された際, その場にいなかったのである. 著者は亡命以前にMeitnerがHahnとの共同研究で果たした役割と, 亡命後彼女が手紙でHahnに与えた物理的解釈の重要性を主張する. さらにMeitnerの亡命先であるノーベル研究所所長のSiegbahnが彼女の研究を高く評価しなかったこともノーベル賞受賞を妨げた要因の一つとして挙げている.
著者はまたMeitnerの人道的側面を強くうちだそうと試みている. そしてMeitnerが原爆研究には全く関与せず, 原爆投下のニュースには驚愕したこと, Hahnをはじめナチの下で働いたドイツの物理学者たちを激しく非難したことなどをその裏づけとしている. しかし本書では, Meitnerが生涯親しくした甥のFrischが英米の原爆開発に専念したことに対する彼女の意見にはふれていない. 原爆作製に携わった物理学者の責任をMeitnerはどう考えているだろうか? 著者がヒューマニストとしてのMeitnerを強調するがゆえに気になる点である.
2) 西尾成子: 『現代物理学の父 ニールス・ボーア』 (中公新書, 1993)pp.203-209
朝日新聞社,1999, 327p., 21.5×15.5cm, 2,900円
この本は,量子計算機の提唱者として有名なドイッチュが,科学全体について、自らの考え方を披露した本である.論文でも教科書でもないので,読者が納得できるように論理が展開されることを期待してはいけない.だから,著者が,「…と考えるしかない」と書いていても,なぜそう考えるしかないのか読者には解らない,という部分がたくさんある.歴史を論じた書物を読むときに時として読者が感じる,あのいらいらである.その点を承知して,いらいらせずに読むことができる人には,それなりに楽しめる本だと思う.
この本でドイッチュが主張したいことの骨子は,第1章に書かれている.以下にその要約を述べるが,なにぶんにも,上述のように論理的に明確な本ではないので,正しく要約できないかもしれないが,ご容赦願いたい.
まず,「覚える」「予測あるいは記述する」「説明する」の3つの区別が強調される.世界中の百科事典に並べられている事実をそっくり「覚える」ことができたとしても仕方がない.科学者(特に理論家)は,「理解」したいのだ.(ここまでは大方の賛同を得られるだろう.)その「理解」の内容だが,ドイッチュによると,S.ワインバーグを含む科学者達は,「道具主義者」であり,こう考えているそうだ:『科学理論の目的は,実験の結果を予測することであり,説明などなくても良い.』ドイッチュは,これでは理解することにならないことを,どんな実験の結果も予測できる装置を手に入れても実験結果を理解できはしない,という例で示している.そして,『理論にとっては「説明」の能力が至高であり,予測能力は副次的なものに過ぎない』と言う.さらに,これを踏まえて,『理解が説明的な理論を通して表れるために,そしてこうした理論が持つ一般性のために,記録された事実が急激に増大したとしても,理解されたことを全て理解することは,必ずしも困難さを増さない.』という.その,理解されたことを全て理解できる普遍的な理論を,ドイッチュは,「万物の理論」と呼んでいる.これは,素粒子論で言うところの万物の理論とは別物である.素粒子論で,重力を含む量子論を万物の理論と呼ぶのは,世界の複雑で多様な現象を単一のレベルの基本的な要素に還元して説明しようという,還元主義に立脚しているが,ドイッチュによると,それは「低レベルの予測的理論」である.例えば,弦理論から心理学を導くことは,到底無理だからである.ドイッチュの言う万物の理論は,心理学・生物学・政治学のような「高いレベルの科学」を含み,それらは,『高レベルの単純性が低レベルの複雑性から出現する』という,ドイッチュの言うところの「創発性」に立脚する.この意味での万物の理論を構成する4つの『主要な撚糸』として,ドイッチュは,量子論,認識論,計算理論,進化論をあげている.
最初に述べたように,かなり癖の強い本で,読むのが疲れるかもしれないが,第1章だけ読んでみるのも良いかもしれない. (2000年4月3日原稿受付)
ページの頭に戻る
丸善,東京,1999, x+222p, 19×13cm, 1,600円(パリティブックス)
「現代物理学は三つの宇宙,すなわち'天体宇宙''火の玉宇宙''量子宇宙'をその課題にしている.三つの宇宙はそれぞれ,天体構造・エネルギー,物質起源,時空起源について研究するものであり,それぞれに三つの物理,すなわち宇宙物理(素粒子から流体まで何でも含まれる),原子核・素粒子物理,量子重力・起弦理論,などが対応する」.これは本書の中で述べられている著者の考え方であり,これらの三つの宇宙がすべて取り上げられている.ここで,'天体宇宙'とは銀河・銀河団など宇宙内部の様々な構造を指すものであり,'火の玉宇宙'はビックバン宇宙であり,また量子宇宙はインフレーションシナリオや時空の起源に関するものである.
まず火の玉宇宙について歴史的な背景にも触れながら,現代物理学(原子核・素粒子物理学)とビックバン宇宙との関わりが解説されている.とくに,宇宙背景放射の'温度'とは何か?,また宇宙膨張とは何が膨張しているのか?など,基本的ではあるが一般にはあまり触れられることの少ない問題が取り上げられていて興味深い.ダークマター問題では元素起源についてより詳細な考察が求められること,密度ゆらぎから構造形成にいたる道筋の解明には,「手に余る情報の過剰から,背後にある筋をどう見抜くか」が問われていることが指摘されている.また,インフレーションシナリオは,素粒子物理の標準理論を'超えた'ところにその出発点を持っていること,およびこのシナリオは地平線問題や平坦問題の'解決'よりも,密度ゆらぎに関する量子真空起源説が評価されるなど,このシナリオに関する著者の興味深い見方が提示されている.量子宇宙では,時空起源を議論するにあたって時間空間の'あるなし'を扱うには,従来の物理での時間空間的な描像の解体と脱時間空間化の訓練が必要であることが強調され,その訓練のための簡単なモデルが紹介されている.
自然科学という観点から見たとき宇宙論には,考察の対象が'宇宙'というたった一つの存在であること,人類が直接科学的な活動を行う舞台である地球に比べて,宇宙が時間・空間的な意味ではるかに大きな存在であること.という二つの特有な事情が内在している.自然科学は,自然界にたった一つしか存在しないものを対象にすることは稀である.また地上の経験を基にして得られた物理法則が,宇宙の遠く離れた銀河でも成立つことについての直接的な検証もない.従来の宇宙論は,「われわれの経験できる範囲に比べて,時間・空間的にはるかに大きな存在である宇宙の,すべての場所・あらゆる時代において,人類の経験事実を基礎にして確立した物理法則が成立つ」ことを前提にして,宇宙の様々な構造を議論し,そこから得られた結論を観測と比較する,という方法をとることで,宇宙論の特殊性にもかかわらずそれを自然科学の対象にしてきたのである.このような観点から見れば,時間・空間の起源というような問題は従来の宇宙論の守備範囲を超えるものと言えるが,著者はそこにも宇宙論のあらたな展開の可能性を期待しているように見受けられる.本書中の文章,"「宇宙論は物理学でやっているのしかないでしょう?」という問に対して,単純に「違うでしょう」と答える"という見解は,これらの期待を表したものと受け取れる.
本書は,この研究分野を開拓しこれまで中心的な役割を果たされてきた著者による,宇宙論の到達点とその課題の総括であると同時に,現在の宇宙論の在り方に関する含蓄のある評論でもある.非専門家は勿論,宇宙論についてもう一度深く考えてみたいと思っている専門家の方にも,是非一読をお勧めしたい一冊である.
(2000年3月17日原稿受付)
ページの頭に戻る
Princeton Univ. Press., Princeton, New Jersey, 1999, xiv+494p., 24×16cm,4,760円
側聞だが,21世紀は生物学の時代だそうだ.また物理学の終焉という言葉も耳にする.しかしここでその是々非々を論ずるつもりはない.(この本の著者が第26章で物理学の危機について論じている.)いいたいのは,似たような雰囲気が19世紀末の物理学者の間にもあったということだ.もちろん違っているところもある─今日いわれている中には,物理学がもはや科学の主役ではなくなったというニュアンスが含まれているのに対して,19世紀末のそれは,物理学はもうほとんどやりつくしたという達成感がみなぎっていたことだ.しかしこの期待が裏切られる新発見がたて続けになされた.X線,電子,放射能の発見である.そこで著者は世紀末の実験分野での諸発見から説き起こしている.したがって,題名の「量子世代」が暗示するような量子論史の本ではないし,20世紀物理学の幕開けをPlanckの量子仮説から始めるのでもない.また単なる学説史に偏することなく,理論と実験の関係にも言及し,社会・政治・文化というコンテクストの中で,制度としての物理学が(統計データやグラフを多用して)分析されている.
本書は四部からなる.第1部は19世紀末から第一次大戦までで,量子論,相対論,低温物理学などが論じられ,工業技術と物理学の関係にもふれられている.第2部は第一次大戦後から始まり第二次大戦で日本に原爆が投下されるところで終わる.量子力学,核物理学などが扱われるが,ワイマール共和国,ナチズムの時代の物理学についても語られる.またこの時代の物理学は,Bohrなど哲学志向の物理学者たちが活躍したことでも特徴づけられる.第3部は大戦後からスーパーカミオカンデにおけるニュートリノの質量検出までの時期を扱っている.この間,物理学は巨大科学への道をたどっていく.東西冷戦下のアメリカの物理学の隆盛が,軍事予算に依存した潤沢な研究費にあったことが指摘されるが,対立国のソ連の状況についてはあまり分析されいない.これは旧ソ連に関してまだ秘密事項資料が多いせいだと思われる.第4部は総論で,20世紀とともに始まったノーベル賞についても紙幅が割かれている.
本書程度の厚さで20世紀物理学の全体像を描こうとすると,どうしても広く浅い内容になってしまう.したがってさらに深く知りたい事柄については,巻末の文献解題からたどっていくしかない.それから,著者自身の研究成果も盛り込まれてはいるが,大部分は他の関連二次文献に依拠しているので,その分野の歴史研究が十分なされているかどうかで,解説内容にも粗密がでてしまう.また20世紀の後半については現時点ではまだ生々しいところもあり,21世紀の歴史家の評価を俟つべき部分もある.ともあれ,同種の本のほとんどが物理学者の手になるものが多い中で,中堅のデンマーク人物理学史家による一書として貴重である.(2000年6月5日原稿受付)
ページの頭に戻る
大月書店, 東京, 1998, 341p., 本体3,600円
青少年の理科離れが指摘されて久しい.一つの原因は我々の身近にある機械で使われている技術が高度になりすぎたためと考えられる.私の子供のころはラジオの構造も簡単で,分解して調べたり,自分で組み立てたりして,電気への興味をかきたてられたし,おもちゃも単純で,力学についての感覚を身に付けることができたのではないかと思っている.ところが,今では分解することさえも困難なものがあふれている.とはいえその一方で,我々や子供たちの身近にあり,依然として100年前と変わらない物が存在する.それは楽器である.本書は科学と音楽を一つの学科として習い,物理学者に成長したテイラー教授が,イギリス王立研究所で行ったクリスマス講演をもとにまとめた本であり,主に楽器を物理的に考察したものである.著者の指摘のように,物理学者には音楽好きが多く,なかには楽器の演奏が上手い人がいる.このような人の中にはある程度科学的に理解しやすい楽器を扱うことによって,物理が得意になった人もいるのではないかと考えるのは間違えだろうか.
さて,本書は一般人向けのクリスマス講演に基づいた本だから,音と楽器に関する様々な側面を具体的な例や,デモンストレーションを用いて説明し,読者の科学的好奇心を満足させるように書かれている.楽器は三つの族に分類され,それぞれの原理が解説される.即ち,特定の高さの音を出す部分を寄せ集めて作られたピアノを典型とする第1族の楽器,振動体の長さを変えて音階を作る弦楽器を典型とする第2族の楽器,最後に一つの振動体の倍音を用いるポストホルンのような第3族の楽器である.もちろん我々物理屋はこれらの楽器の原理はある程度わかっている.しかし,場合によっては,普通物理の講義でするような非常に単純な説明では実際の楽器をちゃんと理解できないということも明らかにされ,楽器の物理の奥深さを実感させられる.また,触ったり,眺めたりして原理の推測ができる楽器ばかりではなく,人間の声や,最近の電子楽器についての説明もあり,更にはコンサートホールの音響学についても解説されていて,興味深く読むことができた.本書は楽器の物理に興味のある物理屋と,青少年が理科に興味を持つように楽器を題材にしてみようと思う物理屋双方に有益な本だと思う.ただし,本書で紹介されているデモンストレーションの多くは様々な機器を用いるもので,容易に再現できるものではないということは指摘しておきたい.
本書は物理の専門家が翻訳したものでないので,まれに標準と違う訳語が使われていることがある.それに違和感を感じる人のために最後に原著をあげておく.C. Taylor: Exploring Music―The Science and Technology of Tones andTunes, Institute of Physics Publishing, Bristol and Philadelphia, 1992.
(2000年7月5日原稿受付)
ページの頭に戻る
World Scientific, Singapore and New Jersey, 1999, v+156p., 21.5×14.5cm, 7,800円
[大学院向・一般向]
著者Mehraは,Rechenbergと共著の大著The Historical Development of Quantum Theory(全6巻,Springer, 1987)の著者として広く知られている.本書は,Einsteinの科学思想の特徴や根源を種々の角度から論じた書である.特に重点がおかれるのは,量子力学に対するEinsteinの考え(現行の量子力学はアンサンブルについての統計理論でしかない,微視的世界についての本来の理論は統一場理論の延長線上に求められる)の根拠である.
本書の表題に含まれるPhysicsand Realityは,本文中でしばしば引用されるEinstein自身の論文名でもある.このように本書の特徴は,Einsteinを初めと,Bohr, Born, Pauli等の著作から非常に多くの引用がなされるという点である(ただし,数式はあまり含まれていない).その意味で,本書は極めて資料性高い著作ではあるが,その分だけ読み難い本でもある(筆者は,記述上,文法上の誤りを,何カ所か見出した).
本書では,第1章で前期量子論に始まる量子力学の成立過程が略述され,第2章でEinsteinの貢献が概観される.第3章では波動力学の成立に関連するSchrodingerとのやりとり,第4章では量子力学の解釈についてのBohrとの論争,第5章では量子力学の完全性批判についてのEPR論文,第6章では波動関数の確率解釈に関するBornとのやりとりがとり上げられる.さらに, 最後の第7章では,Mach,Hume,Kant等の哲学者との関連性や,Planck,Poincare等の科学思想との関連性が論じられる.
引用が多いということもあって,著者Mehra自身の主張は,本書の中で,はっきりとは表に浮かび上がってこない.実際に,本書の結びの言葉は,「本書では,Einsteinの物理学と実在に関する思想の織物の形成に関連すると思われるいくつかの撚り糸を追ってきただけである」となっている.
ただし,言えることは,同種の著作である『神は老獪にして・・・』(産業図書,1987)の著者Paisが,はっきりと「量子力学に対するアインシュタインのテクニカルな反対は根拠のないものである」という立場に立っているのに対して,本書の著者Mehraは,より公平な立場に立っている,という点である.実際,Fine著『シェイキーゲーム』(丸善,1992)などでは,Einsteinの量子力学批判の有効性が論じられているのである.
わが国の物理学は,Bohrの許で研鑚を積んだ仁科芳雄の伝統の許に形成されたと思われる.物理理論において観測者という特別な存在の必要性を認めないEinsteinの科学思想に触れたい方々に,本書をお薦めしたい.
(2000年8月9日原稿受付)
ページの頭に戻る