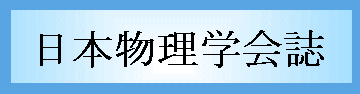
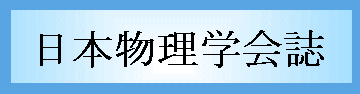
このページでは、物理学会誌「新著紹介」の欄より、一部を紹介者のご了解の上で転載しています。 ただし、転載にあたって多少の変更が加わっている場合もあります。 また、価格等は掲載時のもので、変動があり得ます。
保江邦夫著、高橋 康監修
量子場脳理論入門;脳・生命科学のための場の量子論
サイエンス社、東京、2002、vi+196 p., 25.5×18 cm, 本体1,876円(臨時別冊・数理科学SGCライブラリ-25)
武 田 暁
物質と心の問題は物理学を学ぶものにとって誰しもできれば理解したいと考えている問題である。著者は物理学の基礎理論である量子場の理論に基づかずに心の働きの要である記憶や意識の問題を理解することはできないと主張している。そのために脳科学者や生物学者に量子場理論の内容とその効用を分かりやすい形で提供することが本書の目的のひとつとされている。
本書の3/4を占める量子場理論の解説は非常に良く整理された解説であり、場の理論の教科書としても十分通用するものと思われる。特に巨視的物質と場の量子論の章は場の理論に日頃親しんでいる者にとってもなかなか興味深く書かれている。それでも脳科学の研究者に場の量子論を学ぶことを強いるのは、素粒子の超ひも理論を万物の根源理論であると主張して実験物理学者に学ぶことを強いるのに似た面があることは否めない。むしろ、心の問題に興味のある理論物理学者や数学者に読んで貰いたい本である。
本書の後半の部分が本題の量子場脳理論の解説であり、著者は量子場理論と脳科学の知識を縦横に駆使して華麗な議論を展開する。主な議論の対象は記憶とは何かというテーマであり、今日の脳科学の記憶に関しての中心的なドグマである、記憶は多数のニューロンで構成されるニューラルネットワークの結合の仕方の中に貯えられているという考えに対抗して、ある種の広がった量子場の中に貯えられると主張している。量子場の真空状態とそれに伴う自発的対称性の破れ、南部-ゴールドストーン粒子、ヒッグス機構等々の場の理論特有の概念が記憶との関連で登場してくる。
量子場脳理論の創始者である梅沢博臣氏の考えが本書の随所に紹介されている。同氏が心の働きを理解するのに量子場理論が必要と考えたのは、人間の膨大な記憶容量とそれら記憶が長期に保持されることを理解するには量子場理論の真空状態を個々の記憶と対応させることが鍵であり、量子場理論の真空状態の多様性が記憶容量を説明し、真空状態に伴う自発的対称性の破れが真空の安定性、すなわち記憶の長期保持をもたらすという発想である。
この発想を受け継いで記憶の場として具体的な量子場を提示したのが著者をはじめとする治部氏らの研究者である。本書では量子場としてニューロンの細胞膜外部あるいは内部の水分子の電気双極子場と電磁場を取り上げ、それら互いに作用する量子場の基底状態として記憶が保持されると仮定する。この基底状態は50ミクロン程度の広がりを持つマクロな量子状態であり、細胞膜の膜タンパク質等の状態により制御され、神経細胞やシナプスの活性化の様子を反映して記憶が植え込まれたり書き替えられたりする。
量子場理論が今日の色々な脳機能の基礎を与えるべきであるという考えは正しいとしても、その間を結びつけるには相当のギャップがあり、具体的なモデルを提案されるとどのようにしてモデルの正当性を実証するかという難問に直面する。評者は梅沢氏とは学生時代から親しく付き合っていたので、梅沢氏が量子場脳理論を高度な知的ゲームとして楽しんで提出されたものと想像していた。しかし、その場を具体化して提示されると如何にして理論の正当性の実験的証拠を確立するか等の疑問は随所に起きてくる。
素粒子の超ひも理論は壮大な知的ゲームではあるけれど実験物理学とは無縁の存在との意見をしばしば聞かされるが、同様な量子場脳理論に対する批判は脳科学者の世論であることも事実である。しかし、超ひも理論に含まれる幾つかの新しい概念はいずれは何らかの形で正当化されるという予感がするのと同様に、量子場脳理論に示されている幾つかの概念は或いは何時か正当化されるかもしれないという思いもする。
物理学の歴史を眺めると、全く異なる発想で提出された一見相反する理論が実は同一内容の理論であり、同一の物理現象を異なる言葉で語る違いに過ぎないことが示されたこともある。本書の短期記憶の形成と長期記憶への植込、異なる記憶の統合、等々の際に考慮されている細胞膜と量子場との相互作用、異なる記憶領域を結びつける際の細胞内微小管の役割等を読んでいると多くの最近の脳科学の知見が取り入れられており、案外に量子場理論と通常のニューロンを基礎とする脳理論とは異なる言語で語られる同一理論にいずれ近づいていく気もしないではない。いずれにしても物質と心の問題に興味を持つ会員諸氏にひとつの知的ゲームとして楽しんで本書を読んで頂くことをお薦めする。 (2003年8月18日原稿受付)ページの頭に戻る
M. Veltman
Facts and Mysteries in Elementary Particle Physics
World Scientific, New Jersey and Singapore, 2003, viii+340 p., 23×15.5 cm, US$48.-
仲 滋 文 〈日大理工〉
ベルトマンは場の理論の世界的権威の一人であり、優れた教育者でもある。1931年にオランダで生まれ、ユトレヒト大学で学位を得て後セルンのフェローを皮切りに幾つかの大学で研究職を経験してユトレヒト大学の教授となり、ここで同大学が生んだもう一人の場の理論の権威であるトゥフートを育て、1999年にトゥフートと共に「電弱相互作用の量子論的構造の解明」に対してノーベル物理学賞を授与されている。本書は、このような理論物理学の泰斗が教育的情熱を傾けて書いた素粒子物理の解説であり、読んで面白くないわけがない。
本書は、タイトルに “事実とミステリー” とあるように、高エネルギー物理学の確実な達成事実をこの分野に興味を持つ幅広い読者に伝えようとするもので、まず現在の標準模型を解説し、しかる後に量子力学の本質である状態の混合から始めて、素粒子の理論と実験の発展を殆ど数式を用いない平易な解説にまとめたものである.当然ながら、未だ事実ではない「大統一」や「ブレン」などの話は全く出てこない。
また、本書は白色と黄色のページが交互に現れる、工夫を凝らした構成になっている。白色のページは、素粒子模型や背景にある場の理論の解説、実験原理の解説等に当てられ、一方黄色のページでは、それぞれの内容で鍵となる科学者や実験装置の説明が補足されている。白色のページは、平易な説明とは言え内容は章を追って専門的になり、ベルトマン自身が関わったトップ・クォークの質量の話で盛り上がる仕掛けになっている。従って、白色のページを最後まで興味を持って読みこなす読者は、素粒子物理学に下地のある方々と言える。
一方、黄色のページには歴史的な論文の一部や様々な科学者のエピソード(例えば、陽電子が時間を逆行する電子とする考え方はファインマン以前にステュッケルベルグが出していたが、ファインマンのノーベル賞を祝うパーティに「私のノートを返して下さい」というステュッケルベルの電報が届き、どうやらそのジョークの発信元はゲルマンらしいと言う話など)が掲載されていて、一般読者でも、これを拾い読みすれば科学史的読み物として十分に楽しめる。ここには、マックウエルから現代に至る多数の科学者の写真が添えられ、日本人では小林誠、益川敏英、南部陽一郎、それにスパークチェンバーの開発者である福井崇時らの諸氏が登場する。これらの顔ぶれからも、ベルトマンが伝えようとする素粒子物理学の一端が窺える。
本書は、一冊で二つの楽しみ方ができる本であり、真に優れた理論家の解説は、数式を必要としないことを実感できる本である。 (2003年7月23日原稿受付)ページの頭に戻る
蔵本由紀
新しい自然学; 非線形科学の可能
岩波書店、東京、2003、xiv+184 p., 18.5×13 cm, 2,300円(双書 科学/技術のゆくえ)
金 野 秀 敏 〈筑波大機能工〉
この本は、科学技術のゆくえ [全13巻] と題する双書の一冊であり、岩波講座「科学/技術のニューフロンテイア」に収められている「開放系の非線形現象」の内容を拡充し、さらにそこで展開した考察の土俵から二、三歩踏み出して、科学の知と人間のもろもろの知とのバランスの問題の考察をも試みている意欲作である。
「科学描写の構造」と題する1章では、科学的自然観に対する通念を再検討し、その見解のあらましを述べている。「天体の運動や極微の量子現象の予測や描写などの限られた分野での成功例が大きく宣伝されているが、ごく身近な世界の現象に関する疑問には答えることができず、予測や記述にはとても成功しているとはいえない分野が多い」のは賢明な諸氏にとって明白な事実であろう。そこで著者は現代科学のもたらした、いびつな通念や自然観の根源を浮き彫りにする視座として、縦軸にM. ポラニーの「周辺制御の原理」(「創発」概念に密着した概念)、横軸に「述語的統一」を設定する。その「周辺制御の原理」や「述語的統一」などの視座概念の背景や意味、それにより明らかになる科学描写の本質的構造が述語統一的に述べられている。
「非線形科学から見る自然」と題する2章において、著者は科学の現状の欠陥を緩和する動きが観察される非線形科学に焦点を絞り、「新しい自然理解の視点、自然描写の新しい胎動」を(数式なしで)いきいきと紹介する。不可逆現象・非線形現象とは何か、非平衡開放系としての熱対流現象にかかわる散逸構造と平衡構造の違い、対称性の自発的破れや散逸構造における対称性の自発的破れ、非平衡系の隠喩としての活性-抑制因子系、振動と興奮の類縁関係とBZ反応のインパクト、非平衡開放系の低次元の散逸力学系によるモデル化、構造安定性とカタストロフィーの視点、分岐現象の普遍性と分岐点近傍での自由度の逓減、相互作用するリズムの世界と自己組織化、カオスの源泉の歴史的背景、ローレンツの偉業の中身、離散力学モデルが教えること、自然現象と時空スケールの階層性と多スケール世界の物理とフラクタル概念、などとの関連性が明らかにされている。
「知の不在と現代」と題する3章では、科学技術の進歩がもたらした生活の豊かさと、それと引き換えに失ったものに目をとめ、別種の知の貧しさを指摘する。この科学の領域における知の不均衡の問題は、人間の知のありかた一般に拘わりをもつ。そこで、科学の知に向けられている典型的な批判を検討する。まず、藤沢令夫の「ギリシャ哲学と現代」に注目し、サイエンテイフィック・マテリアリズムに内在する問題点と関連して、藤沢が論じた「事実と価値」、「物質と生命」、「物と知覚」、「部分と全体」に関する私見を述べている。締めくくりとして、物理学と心の接点としての、自我や意識の介入による広がった波動関数が収縮する問題、脳科学における「心脳問題」、「心の解明」に関連した言葉の魔術の問題、2元論的思考法に対する危険性、「生死」に関する観念の問題について考察している。このような考察を経て、科学的な語り以外の様々な語りを持つ文化が今求められていることを指摘する。さいごに、物語的な知によって適切に答えられるべき問いが、不当に抑圧されている状況は豊かな時代とは言いがたく、「現代の 『知のアンバランス』 の究極の姿をここに見る」と結んでいる。
(物理的)科学全体のありかたが根本から問われている今日、科学の現在の姿を新しい視座から考察しており、読み終えてみると、何か「すがすがしいもの」を感ずる。そして、「創発的諸性質もまた孤立分断的に切り出さなければならない」や「原理的に答えのない問いに対する 『語り』 を見出すことによる 『適切な意味の形成』」というメッセージが「心」に残った。
学部学生や一般向けの本であるが、決してやさしい本ではない。学部の学生にとっては、1章や3章は「行間が読めない」かもしれないし、「馴染のない概念」を持つ用語の意味がすぐにはつかめず、理解するのに時間を要するかもしれない。しかし、2章はまだ非線形科学を知らない学部の学生でも、非線形科学最先端で行われている研究の風景をイメージできるだろうし、また、関連した入門書も紹介されているので併読すれば、理解が飛躍的に高まることが期待される。研究者諸氏にとっても、本書で展開されているような考察を行う時間を作ることはたいへん有益であろうし、科学的記述の構造を深く理解することは研究にもフィードバックされると期待される。 この本は、偏りを是正した「新しい自然学」を形成する道を探る著者の開拓者としての「心の叫び」であり、また、若い学部学生や非線形科学の研究者を目指す諸氏に対する、長旅の出発の際に贈る「餞の言葉」でもあるように思える。 (2003年5月26日原稿受付)ページの頭に戻る
C. M. Braams and P. E. Stott
Nuclear Fusion; Half a Century of Magnetic Confinement Fusion Research
Institute of Physics Pub., Bristol and Philadelphia, 2002, xvi+328 p., 24×16 cm, \12,910
山 田 弘 司 〈核融合研〉
核融合に関する研究・開発を包括的に記述した書籍は初学者向けの入門やハンドブック的な色彩の濃いものが多い。その中で本書は、ベーゼらによる恒星内の核融合反応の発見からトカマク実験の進展、ITER(国際熱核融合実験炉)計画に至る2001年末までの編年体形式の科学史的整理の部分(1, 2章および6-9章)と、トカマク以外の3つの磁場閉じ込め形式である開放系、ピンチ、ステラレータについての研究成果を紀伝体形式で記述した部分 (3-5章)をバランスよく配分し、全体として非常に分かりやすい「読み物」となっている点が出色である。結果として題するところの「磁場閉じ込め核融合研究の半世紀」についてそれ以上でも、それ以下でもない内容を要領良くまとめることに成功している。著者は過去40年間、磁場閉じ込め核融合に従事してきた古参かつその実績により尊敬を集めている欧州のお二人の研究者である。そのキャリアと600に及ぶ参考文献に見られる調査が本書を可能とした。専門分野での方言を避けることや、略称などが用語集として巻末にまとめてあることなど、専門家でない方に読みやすいように配慮が適切になされており、また、磁場閉じ込めの基礎となる多くの物理概念について簡便な説明を試みている囲み記事は専門家にとっても自分の理解を見直すことに役立つと考えられる。
「無知の時代から今日の理解まで、多様な異なった研究路線があり、他の方法ではなく、少なくとも現在の主流であるトカマクに集中することがなぜ今、有益と考えられるのかについて述べたい」と言う前書きの一文が著者の狙いを端的に表しており、それは幾分の偏りやこだわりは残るにせよ、現在の核融合研究者の多くが同意できるものであろう。また、トカマク代替方式についても多くのページを割いていることや、「核融合の究極の可能性について推測されることを学んでいく最善の方法は目の前の可能性を実行に移すことである」と記述されているように、トカマクによるDT(重水素・三重水素)燃焼の実証は必要条件ではあるが、他の形式の優れた点を伸ばしていくことによって十分条件たることも主張されている。
「核融合はその歴史上、最も決定的な点に至った。エネルギー技術として発展させるのか、基礎研究プログラムとしてゆっくり進むのか」という問題意識は現在、全ての核融合研究者が共有しているものであろう。実際、世界の核融合研究の一翼を担う日本においても科学技術・学術審議会学術分科会が実験研究のプラットフォームを限定し重点化を進める提言を行っている。本書を読み、先達の労苦を改めて思うとともに、新しいパラダイムの上に研究・開発がさらに進展することを願う。 (2003年1月17日原稿受付)ページの頭に戻る
R. Foot
Shadowlands; Quest for Mirror Matter in the Universe
Universal Publisher, Parkland, 2002, viii+235p., 21.5×13.5 cm, $25.95
安 田 修〈都立大理〉
本書はSFのような題名を掲げてはいるが、素粒子論における標準模型の拡張の一つである鏡像対称模型(ミラー模型)を一般向けに解説した(一応)真面目な書物である。左右非対称な標準模型のゲージ群SU(3)×SU(2)×U(1)をSU(3)×SU(2)×U(1)×SU(3)×SU(2)×U(1)に拡張し、我々の世界である左巻のセクターと鏡像の世界である右巻のセクター(のセクター)を入れ換える変換に対して理論が不変であることを要請したものが鏡像対称模型である。実は鏡像対称模型は1956年のリーとヤンのパリティ非保存の論文の最後のパラグラフで既に示唆されていたのだが、1991年に著者らメルボルンのグループが再発見し、以来著者らは精力的にこの模型についての研究を行っている。鏡像対称模型が潜在的に説明し得る現象としては、安定なミラーバリオンによって構成されるダークマター(ミラー物質)の存在、ミラー物質によって構成されるミラー恒星やミラー惑星の存在、光子-ミラー光子混合によるオルソポジトロニウムの寿命の標準模型の予言からのずれ、ニュートリノ-ミラーニュートリノ混合によるニュートリノ振動(実質的に不活性ニュートリノ振動で現在では実験的には不利になってきている)の存在等がある。1章・2章が序にあてられ、3章でミラー恒星、4章でミラー惑星、5章でオルソポジトロニウム、6章でミラー物質によるツングスカ異変の解釈、7章・8章でニュートリノ振動がそれぞれ説明され、9章にまとめが与えらている。もともと本書は一般向けに書かれたもので、高校生でも読めると著者は言っており、各章ともある程度self-containedに書かれている。標準模型の拡張の議論をしているだけに、種々の現象に対してまだ立証されていない解釈も与えられている反面、素粒子論や天文学における最近の成果ならびに昔の興味深い歴史的事実も色々紹介されており、専門外の人がそれらの話題を知るのにも役に立つ本である。欲を言えば、特に英語が母国語でない人にとっては本書を一気に一日で読むことは難しいので、本文とは別に素粒子論や天文学関係の用語解説と索引が巻末にあれば一層読みやすいのではないかと思われた。著者のRobert Foot氏とは評者が米国でポスドクをしていた時に知り合って以来のつき合いで、これまでに不活性ニュートリノによるニュートリノ振動等に関して共同研究をしたことがある。評者に比べて何倍ものユーモアのセンスと毒舌を持つ著者は、本書においてもあちこちでユーモアと毒舌を遺憾なく発揮しており、それを読んでいるだけでも評者には面白いと思われた。 (2002年11月27日原稿受付)
金森順次郎
大阪と自然科学
国際高等研究所,2001, 76 p., 12.5×18.5 cm, 700円(高等研選書15)
寺 倉 清 之 〈産総研〉
この小さい本は、我が国の物性理論研究における重鎮である金森順次郎によって書かれたものである。高温超伝導体の発見以来、遷移金属酸化物の研究が急激な進展を遂げている。こうした研究の基盤となる、超交換相互作用、協力的ヤーン・テラー効果、電子相関、などの重要な物理概念に対して、著者による記念碑的な論文はあまりによく知られている。一方、著者は大阪大学の総長を6年間務め、大阪大学の存在基盤の強化に多大の貢献をしたことも付言しておく必要がある。このことが、本書の執筆に強く結びついていると思われるからである。題名にある「大阪」は、確かに本書の重要なキーワードであり、江戸時代からの大阪における自然科学研究の発展を、我が国における、また世界における「大阪」の位置づけをしつつ、要領よく記述している。従って、科学史の一断面としても興味深い内容になっている。しかし、物事の本質を見極め、精緻な論理で一般性のある理論の展開をする著者によるものであれば、,本書が単に「大阪」における自然科学発展の歴史を記述するに留まるはずもない。本書において著者が随所に述べる、自然科学に対する見解は、非常に示唆に富んだものであり、実利をあまりにも強調する現在においては、時代と社会への重大な警鐘となっている。特に、9章から最終章の11章にいたる3章では、P. W. Andersonによる“More is different"を引用しつつ、科学と技術、基礎研究と応用研究、研究の本質的原動力、等についての著者の考えが理路整然と述べられていて、大いに学ぶところがあると同時に、胸の透く思いがする。(1カ所、今となっては汚点となってしまったと思われるのは、10章において例のシェーンらの仕事がポジティブな意味で引用されていることである。いずれ、この部分は改訂版において何らかの処置がなされることになるだろう。)
本書の内容が、「大阪」に重点があり、大阪とは直接に関係のない者にはやや距離感を抱かせることを懸念する。しかし、敢えて言えば(というより、むしろ著者の真意に違いないが)、「大阪における自然科学研究」は,「官制の自然科学研究」の対句になっており,研究および研究支援における自主性・主体性の重要性を具体的に指摘することとなっている。その背景には、1724年に大阪町人が発起人となって創設された懐徳堂が、自然科学研究につながる合理的精神を育む役割を果たしたこと、1838年に緒方洪庵により創設された適塾が,幾多の変遷を経て1931年の大阪帝国大学の創立につながったことなどがある.大阪帝国大学の創立に際してのみならず、大阪大学の発展における重要な段階において、地元財界の精神的、資金的支援が必須の役割を果たしてきたようである。我々の世代、およびそれ以後の者が実感できる関西の財界による学術研究支援の例としては、谷口財団による谷口シンポジウムがあるが、これは谷口豊三郎の私財によるものである。現在のせせこましい科学技術振興政策に対して、「本物の学問」を支援しようとした、谷口豊三郎の高 な理想と広大な気宇が伝わる8章の記述は感銘深い。
なお、本書は一般書店ではほとんど販売されておらず、購入は国際高等研究所のホームページ(http://www.iias.or.jp/top/home j.html)から行うことができる。 (2002年11月 1 日原稿受付)谷畑勇夫
宇宙核物理学入門
講談社、東京、2002, 252 p., 18×12 cm, 本体900円(ブルーバックス)
土 岐 博 〈阪大核物理センター〉
全てはビッグバンから始まったとの書き出しで、宇宙の発展を原子核を議論しながら語っていく非常にユニークな原子核の入門書です。ビッグバンの証拠は原子核の存在比に刻まれています。それは宇宙の温度がある程度まで下がらないと原子核が存在できないことと、クーロンの斥力のために温度が下がりすぎると、原子核の変換ができなくなるという理由からきています。ビッグバンの後の冷却期に、その温度帯をどれだけのスピードで通過したかの痕跡を原子核の存在比に化石のように刻み込むことになります。まさに本の副題である、元素に刻まれたビッグバンの証拠です。
この説明は原子核を理解する人にとっては良くわかります。わからない人は是非この本を手にしてください。原子核をこれだけ正確に、式を使わないで、丁寧であり、しかもそんなにも長くなく説明しきっているのは、著者の原子核に対する深い洞察力があることに所以します。
前半は原子核の説明に使われています。目に見えない物質を見るために簡単な形状を仮定して、原子核の発見の実験を直感的に説明するのは見事です。原子核の大きさをどのように測るのかなどに簡単で典型的な密度分布を仮定して議論しています。圧巻は著者自身の活躍の場である不安定核の研究で得られた結果の説明で、これまでの常識が次々と塗り替えられていくのは痛快です。著者は「これまでの原子核物理は山あり谷ありの地形をただ単に谷の部分だけを観察して体系づけられたものである」と言い切り、新しい原子核の姿が出てくることは当然のことであると説明しています。まさに、原子核物理のルネッサンスが起こっている現場をこの本は簡単な言葉で説明しています。
後半は十分に原子核の知識を読者に説明した上で、ビッグバンでの元素合成の様子とその必要なデータがまさしく今実験室で作られている様子が語られています。水素やヘリウムなどの元素が宇宙には多いことが宇宙は熱い状態から冷えてきていることの証拠となっています。もっと重い元素は太陽のような星の中での原子核反応で生成されます。それで到達できるのは鉄までで、我々の大好きな金などの重い元素は、爆発的な現象の中で生成されます。もう一つの自然の大演技であるスーパーノバ(超新星爆発)です。スーパーノバがどの頻度で起こるのかは、宇宙の歴史を教えてくれます。まさに、元素がわかれば宇宙がわかるとの主張の原点はここにあります。
興味深いのはこれらの爆発的宇宙現象は物質の存在形態の全てを使っているとの事実です。我々が原子核の地形の谷の部分だけを歩いていては、宇宙で起こっている現象を理解することはできないのです。そこで、日本の理化学研究所では世界のトップを走る装置を使いながら山の尾根の部分にまで到達して、原子核の性質を研究しています。人類の叡智は宇宙の叡智に近づいてきたといえます。その部分をまさしく実験室で自分の目で見ている人が、遠く離れた宇宙の営みを見てきたように我々に語りかけてくれます。
原子核の入門書として、さらには宇宙物理の原子核の絡む現象の入門書として非常に丁寧で、親切で、しかもそんなに時間を使わないで理解させてくれる本として、多くの人に推薦できる本になっています。物質の存在形態に興味を持つ全ての科学を目指す学生や科学の魅力にひきつけられている一般の読者にお勧めできる本です。原子核の研究者には必読の本です。 (2002年 9 月20日原稿受付)J. Stachel
Einstein from ‘B' to ‘Z'
Birkhauser, Boston, 2002, xi+556 p., 24×16 cm, \17,460 (Einstein Studies Vol. 9)
板 垣 良 一 〈東海大総合教育センター〉
アインシュタイン(1879-1955)生誕百年を祝う歴史的な大事業として 『アインシュタイン全集』 がプリンストン大学出版部から1987年に刊行され、現在まで30巻の予定のうち8巻まで刊行されている(websiteはhttp://www.einstein.caltech.edu)。この全集の1, 2巻目の編集責任者が本書の著者のスタッチェル(1928-)である。ユダヤ系物理学者の彼はボストン大学教授,アインシュタイン研究センター長であり、Twentieth Century Physics (1995)(『20世紀の物理学』 丸善、1999)に「相対性理論の歴史」という見事な論文を執筆している。本書はスタッチェルの37の論文、書評などをおさめるが、書名がfrom ‘B' to ‘Z'で ‘A' to ‘Z'でないのは、アインシュタインのすべてを網羅していないことを意味する。本書は、アインシュタインの人間的側面、全集の編集、アインシュタインの研究の概観、特殊相対論、一般相対論、量子力学、アインシュタインと学者達、書評の8つの部分からなる。アインシュタインの妻ミレーヴァの特殊相対論への貢献はあまり考えられないこと、彼のユダヤ人意識が第一次大戦後大きく高まること、全集の編集では遺産管財人のO. NathanとH. Dukasが「聖人アインシュタイン」のイメージの維持のために編集部や出版部と裁判を起こしたこと、重力場の方程式の先取権争いでヒルベルトはアインシュタインの論文を見てこの方程式に到達した可能性が高いこと、アインシュタインはフリードマン宇宙を「物理的に意味なし」と当初記していたこと、4次元連続体は場のactual homeで、粒子にはpotential homeとしながらも、連続体なしに不連続体を定式化できないか考えたこと、1912年にリッチテンソルをふたつに分けて正しい重力場の方程式に到達したが弱い重力の近似でニュートンの重力が導けないと勘違いしたこと、重力レンズの可能性は1912年に出していたが注目されなかったこと、特異点のない解が物質や放射の原子的量子的構造を再現できる古典的場の理論を探し求めていたことなどが述べられている。本書においてマイケルソン - モーリーの実験が光速度不変の原理ではなく、相対性原理の証明につながると指摘されているのは良い。また、アインシュタインとNewton, Eddington, Infeld, Lanczos, Bose, Pauliらとの関係を述べているのはユニークであるし、A. Pais, A. Folsingの伝記についての書評も含まれている。しかし、記述内容に注意が必要なR. Clark, A. Reiser, Ph. Frankらの伝記を多く使っていること、マッハとアインシュタインの関係については記述が通一遍であること、索引がないことなどには不満が残る。もうすぐ2005年を迎えるが、この年は1905年の特殊相対論成立から100年後、1915年の一般相対論成立から90年後、1955年の没後50年の記念すべき年に当たる。このようなことから、彼の論文や新資料を丹念にたどって思考の道筋を明らかにし、彼にまつわるの多くの伝記的誤解を解く本書はアインシュタイン研究の模範を示しているといえよう。(2002年 9 月 3 日原稿受付)
R. T. Hammond
From Quarks to Black Holes; Interviewing the Universe
World Scientific, Singapore and New Jersey, 2001, xiii+174 p., 25×17 cm, \5,880
水 本 好 彦 〈国立天文台〉
日本では若い世代の理科離れが問題になっているが、これは日本だけの現象ではなく世界のグローバル化の波にのってじわじわと広がっているような気がする。大学では自然科学分野では物理学特に素粒子物理学の研究室の人気は低落の一方である。かろうじて天文や天体物理学研究室が固定的人気を維持している。自然科学の人気を何とか挽回しようと対策が考えられているが、自然科学のおもしろさを若い世代に伝えることが第一歩だろう。
本書は、「クオーク」、「ブラックホール」という一昔前の科学少年少女なら何となく心がわくわくするキーワードに今の流行の「宇宙」を加えて、直訳すれば「宇宙のインタビュー:クオークからブラックホールへ」という題名で興味をそそる工夫をしている。題名から想像できるように素粒子物理学と天体物理学を関連して解説する一般向け解説書である。著者のT. Hammondはアメリカのノースダコタ州立大学の紐理論研究者である。宇宙の構成要素を人物に見立てて次々とインタビューしていく形をとって、紐理論と真空の本質について解説を試みている。付録として用語解説まで付いている凝りようでありユニークな構成となっている。単なる解説書ではなく、分からないことへの好奇心を誘いおもしろさを伝えようという著者の意気込みが感じられる。
最初のインタビューは炭素原子で始まり、炭素原子の宇宙での誕生から惑星系の形成と地球での物質循環という一連の流れを炭素原子の旅として語らせている。これが物理の世界を事物の関連と流れとしてこれから解説していくというイントロダクションになっている。木星、ブラックホール、恒星、彗星、渦巻き銀河、クエーサ、中性子星というマクロな登場人物と、炭素原子、電子、フェルミオンとボゾン、ニュートリノ、水素原子、クオークなどのミクロな登場人物、および、ニュートラリーノとタキオンという際物の3種類が入れ替わり立ち替わり出てくる。登場の順番は一見脈絡がないようであるが、重力理論、量子論、超対称性を縦糸に、4つの力を横糸にインタビューは進行していく。一方、マクロな登場人物は脇役となってしまった感がある。最後の中性子星までの流れに必然性があまりないようだが、最近の宇宙物理の中で最もホットな話題でありほぼ50年前の発見以来ずっと謎であるガンマ線バーストを扱っている。中性子星に「人は解けない問題に直面したときに最大の力を発揮するものだ」と言わせているところは面白い。その後に最後の2つ:紐理論と真空へのインタビューが配置されていて、紐理論の研究者である著者の紐理論に対する意気込みと想いが込められているように感じる。
個々のインタビューの中に著者は疑うことや別な観点から物事を見ることの重要性をちりばめている。たとえば、タキオンは「因果律は成り立つのか、自由意志があると思うから因果律が破れるているように見えるのではないか」と読者を挑発する。また、水素原子は「古典物理学の決定論に従うと宇宙の中で生じる事象の情報で宇宙は溢れかえってしまい、宇宙はそのような情報を持ちきれないから、宇宙は不確定性原理または量子論によって情報量を適度に保っている」という私見を述べて驚かせる。
本書は素粒子物理学と天体物理学を関連して解説する一般向け解説書の中でも気楽に流し読みができ、それなりに本質が分かったような気がするものとなっている。一般向けに口語で書かれているため専門書の英語に慣れている読者にはかえって読むのに苦労するところがあるかもしれないが一読に値するだろう。(2002年 8 月26日原稿受付)
ページの頭に戻る