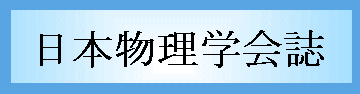
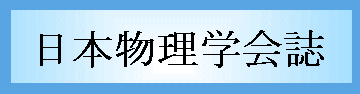
このページでは、物理学会誌「新著紹介」の欄より、一部を紹介者のご了解の上で転載しています。 ただし、転載にあたって多少の変更が加わっている場合もあります。 また、価格等は掲載時のもので、変動があり得ます。
A. Goldhaber, R. Shrock, J. Smith, G. Sterman, P. van Nieuwenhuizen and W. Weisberger, ed.
Symmetry and Modern Physics; Yang Retirement Symposium
World Scientific, New Jersey and Singapore, 2003, ix+291 p., 25.5×17 cm, 10,600円
藤 川 和 男〈日大理工〉
本書はC. N. Yang教授の退官記念シンポジウムの講演録である。いうまでもなくYang教授は基礎物理学に多くの業績を残し、またニューヨークのロングアイランドの小さな町であるStony Brookに新しい研究グループを起こし、研究および教育にグループとしても大きな貢献をしたことで知られている。日本人研究者も過去に短期的および長期的に数多くStony Brookを訪問した。素粒子論研究者が数の上では多数を占めると考えられるが、Yang先生の研究分野の広さを反映して、例えば、久保亮五先生なども訪問され特別講演等をされている。
さて、シンポジウムはYang教授の物理学全体を貫く重要な概念である「対称性(Symmetry)」を中心テーマとしていたが、講演の多くはそれにこだわらない多方面の分野を網羅したものであった。
非Abel的なゲージ場理論であるYang-Mills場の物理的な成功に関しては、 Stony BrookにゆかりのあるZinn-Justin, 't Hooft, Veltman, W. Bardeen, T. T. Wu らが講演を行った。 ゲージ場理論と数学の関連に関しては、 S. T. Yauが話をした。 Stony Brook出身の人たちとしては、S. C. Zhang, L. Alvarez-Gaume, B. Sutherlandらが講演をした。
またYang教授の研究に関連した実験として、 W. Ketterle がボース・アインシュタイン凝縮の話をし、日立の外村彰さんがAharonov-Bohm効果に関係した講演をした。いずれも見事な講演であり、丁寧に書かれた講演録が本書に収録されている。 F. Dysonのバンケットでの挨拶は本書の最初に収録されている。第2次世界大戦の直後に渡米しシカゴでフェルミらの指導を受け、プリンストンの高等研究所で研究員として本格的な研究を始め、 Yang-Mills場の発見とパリティの破れの予言という2つの記念碑的な業績を上げたYang教授が、他方ではアメリカ国籍を獲得し後に中国とアメリカとの国交回復に貢献し、さらに香港の中国への返還に立ち会った一中国人としてのYang教授の一生を概観するものであった。第2次世界大戦の後に世界の中心に躍り出たアメリカを象徴するように、当時のシカゴ大学のほぼ同年代の学生からLee-Yang, Steinberger らのノーベル賞受賞者をはじめ、物理学の多くの分野の指導者を輩出したのは圧巻であり、またこれらの多くの人たちがシンポジウムに参加していた。
本書は、これだけを読んで物理学の特定の分野の深い理解が得られるという性質のものではないが、最近数多く出ている記念シンポジウムの議事録に比して、講演者の顔ぶれが豪華であること、物理学とはいかにあるべきかというYang教授の信念をよく反映したものであることに特徴があり、物理学科の図書室等で多くの人たちに読んで欲しい本である。
なおこのシンポジウムの最後に、Stony Brook の Institute for Theoretical Physics (ITP) が今後 C. N. Yang Institute for Theoretical Physics (YITP)と改名されることが紹介された。このITPを過去に何度も訪問し、研究上で多くの啓発とか励ましをいただいた評者にとっては、訪問者をいつも笑顔で迎えてくれた一人の巨人がいなくなったというのは一抹の寂しさを感じさせるものがある。このシンポジウムの記録は、ある意味でのアメリカンドリームと物理学の古きよき時代の記念碑でもある。 (2004年7月26日原稿受付)ページの頭に戻る
佐藤文隆
孤独になったアインシュタイン;グーテンベルクの森
岩波書店、東京、2004, vi+200 p, 19.5×13 cm, 1,800円
早 田 次 郎 〈京大理〉
佐藤さんは数年前までは京都大学天体核研究室教授であり、これが「おもて」の顔であった。この研究室には中間発表会と称する研究発表・討論の場がある。 当時、 僕が(おそらく誰もが)一番楽しみにしていたのは彼の「うら」 の顔であった。 彼は 「とり」 として縦書きの学問的な話をするのが常であった。科学者は坊主か?職人か?というような言い回しもそのとき聞いた。人の惹きつけ方を実によく心得ている。「横書きのものは縦になって読み、縦書きのものは横になって読む。」という自学の習慣がこのような思考を生むのだろうか?
その佐藤氏が「グーテンベルクの森」 (広辞苑によると、 グーテンベルクはドイツ人で活版印刷術の発明家とある。)というシリーズもののうちの一冊として本を書いた。運よくその書評を頼まれたわけである。しかし、簡単に引き受けたことをすぐに後悔した。次から次へと難解な言葉が出現する。諦めて、まず第2部「自学自習のすすめ」から読むことにした。ここには「おもて」の顔からみた縦書きの世界がある。教科書について、著名な物理学者のエピソード、新しい情報伝達の手段であるインターネットアーカイブのことなど気軽に読める部分と思想としての科学、ワンランク上の教養などちょっと重い部分からなる。自然科学の研究者も、研究生活での経験も含めた人生全体の精神生活の豊かさを希求すべきなのだろう。
第1部「孤独になったアインシュタイン」は「うら」の顔から見た横書きの世界である。「車中の学問」でせっせと仕入れた知識が佐藤氏の中で咀嚼され生き生きとしている。かなりの教養を要するという点では読み込むことはしんどいかもしれない。幸いに巻末に文献がたくさん載っていて勉強しようと思えばできる。主題のアインシュタインの「ずれ」についての考察も興味深いが、現在の科学研究における思想の欠如が論文レベルの創造力まで衰退させているという指摘のほうが心に残る。21世紀の科学と科学者が如何なる方向に向かうべきか、我々は20世紀の歴史から読み取るべきなのかもしれない。 アインシュタインうんぬんについてはうまく読みきれなかった。が、「思考固定防止」の効果が心地良かった。真意については、ぜひもっと教養のある読者に解読してもらいたい。佐藤氏の「おもて」の人生と「うら」の人生をちょっと覗いてみることができるという意味では一読の価値あり。 (2004年6月21日原稿受付)ページの頭に戻る
H. C. Berg
E. Coli in Motion
Springer-Verlag, New York, 2003, xii+134 p., 24×16 cm, \20,280 (Biological and Medical Physics Biomedical Engineering)
山 崎 義 弘 〈早大理工〉
E. coli(大腸菌)の運動メカニズムに関し、特にその走化性について、これまで行われてきた(実験的)研究を広範にわたって簡潔にまとめた書である。本書の内容は、大腸菌の走化性に関し、マクロな視点での研究(コロニー形成)からミクロな視点へと移行し、鞭毛の回転モーターの特性にまで及ぶ。まず、微生物学の歴史に関するレヴュー(第2章)から始まり、 集団運動として走化性を特徴づけるため、寒天培地上でのコロニー形成に着目する(第3章)。 そして、 走化性をより厳密に調べる方法としてcapillary assayを紹介し、走化性と個体群密度の関係に言及する。また、寒天培地の栄養濃度に依存したコロニーの形態(菌が密集したスポットの配列)について述べられており、数理科学の観点から興味深い内容も含まれる。続いて、細胞1個の運動性へと話は進んでいく(第4〜7章)。水の粘性抵抗を受けた菌は直進運動と不規則な回転運動を繰り返し、ランダムウォークをしていること、菌の運動は、らせん状をした鞭毛を構成するフィラメントが回転することにより得られるが、フィラメントの回転方向に応じて、菌が直進するか、のたうちまわるような回転をするかが決定されること、そして、フィラメントの回転方向が変化する割合は、走化性に関わる化学物質の濃度によって変わることが、イオン導入法等の実験結果を交えて示されている。そして、さらに走化性のメカニズムを探るべく、細胞の内部へと話は進む。第8章で、単細胞生物である大腸菌の構成要素を簡単に説明し、その後の章で鞭毛モーターの特性に対する分子レベル、遺伝子レベルでの研究について解説している。まず、突然変異体を作ることによって特定された、モーターを構成する蛋白質に関わる遺伝子を紹介し(第 9 章)、 次いで走化性に関する遺伝マップと遺伝子配列について解説し、走化性を示す系を構成・操作するために必要な遺伝子がいまや本質的にすべて明らかになっていることに言及する(第10章)。 さらに、 蛍光エネルギー移動を利用した実験から明らかとなった、陽子の輸送が引き起こすモーターの出力に関する非線形的な振舞を示し、新たな理論的枠組みを構築する必要性を説いている(第11章)。最後に、モーターの性能(例えば、モーター速度の電圧依存性、トルク生成など)に関する最近の知見がまとめられている(第12章)。 本書の内容は、 大腸菌が持つ走化性の解明という点で首尾一貫しており、また、微生物学の教育を受けていない研究者を対象に書かれているので、分子生物学や遺伝子学等の詳しい知識がなくとも十分理解できるであろう。
ページの頭に戻る
藤田英一
金属物理博物館
アグネ技術センター、東京、2004, viii+294 p., 21×14.5 cm, 2,800円
深 井 有〈中大理工〉
この本では金属を自然から取り出して使いこなそうとした営みがいかに人類の自然認識を拡げてきたか、これがやがて近代物理学と結びついて「金属物理」となり、いかに現在の材料科学と物性物理学に発展・分化してきたかという流れが多くの人たちの挿話を交えて語られている。藤田英一氏には「金属物理-材料科学の基礎」(アグネ技術センター、1996年)という著書があって、本書はその姉妹篇である。著者によれば、内容は前著に沿い、それを敷衍あるいは脱線したもの、ということになる。広い範囲の人々に、楽しみながら、金属物理の事の起こりと発展の道とその哲学を伝えるのが目的とされている。
これは単なる「金属の物理学」の本ではない。金属の性質を電子論と転位論をもとに解明しようとする取り組みが従来の冶金学に大きな変革をもたらしつつあった戦後の一時期、その分野は「金属物理」と呼ばれて新鮮な魅力に溢れていた。わが国では1955年にアグネ社から雑誌「金属物理」が発刊され、それが後に「固体物理」と改題されて発展的に消滅するまでの10年間がほぼその時期にあたる。設備も研究費も乏しい時代だったが、この雑誌にはまさに開けようとしている学問への熱い思いが漲っていた。雑誌「金属物理」の終刊に際して編集責任者の橋口隆吉先生(東大冶金教室)は書いておられる。…雑誌「金属物理」は発刊当初から内容を金属の物理学に限定せず広く固体全般の物理学を包括するように努めてきた。物理学者にも冶金学者にも換言すれば基礎研究者にも応用研究者にも興味をもたれるものでありたいと願ったからである。しかし、この10年間に学問は、特に中間領域は大きく変化して「金属物理」という言葉は陳腐化し材料科学や物性工学にとって代わられようとしている…。
藤田氏は1950年に冶金学科を卒業し、その後、物理的手法を駆使して金属材料の研究に携わってきた、いわば「金属物理」の時代の数少ない生き証人である。その藤田氏が半世紀後に著した2冊の本にあえて今や死語となった「金属物理」 の名を冠したのには、 これから材料科学に携わる人たちに「金属物理」の時代の精神を伝えたいという願いが込められているのだと筆者は思う。温厚な著者は声高には言わないが、すぐに役に立つことばかりがもてはやされる昨今の風潮への静かな意思表示とも受けとられよう。また、この分野を拓いてきた先達へのtributeでもあるに違いない。
この書評は書名の解題に終始してしまったが、これでよいのだと思っている。これが藤田氏より10年後に「金属物理」の余光の中で学生時代を過ごした世代の一つの務めと考えるからである。 (2004年5月12日原稿受付)ページの頭に戻る
M. リカール、T. X. トゥアン、菊池昌実訳
掌の中の無限;チベット仏教と現代科学が出合う時
新評論、東京、2003, xxvii+415 p., 21.5×15 cm, 本体3,800円
国府田隆夫
パストゥール研究所F. ジャコブのもとで学位を取り、前途有望な分子生物学者の途につきながら、 “点描法の絵に小さな点を添えるだけの研究” を諦め、チベット仏教の僧侶となったフランス人M. リカール(以下[M])と、サイゴンで仏教徒の家に生れ育ち、高校までフランス系教育を受けて米国に渡り、現在、ヴァージニア大学で宇宙物理学の研究教育に当たっているアジア出自の科学者T. X. トゥアン(以下[T]: M, T共に50歳半ば)が、ピレネー山中の夏期大学で語り合った対談集である。異色の顔合わせと言っていい。
原著副題は “ビッグバンから覚りへ:Du Big Bang a l'Evevil” で、19章からなる対話と、それを総括するM, T双方の結論からなる。両者の対話は終始、一方からの問題提起(内容解説を含む)を他方が受け、ワンバウンドのラリーのような誠実で余裕のある対話が続くが、時に厳しい対立も露わになる。最初に “なぜ科学者と対話しようとするんですか” と [T] が問い、 “現実の性質を探るのは、仏教哲学者の第一の務めです。…私にできるのは、ただ自分の強い関心をひいたいくつかの考え方を、及ぶ限り科学者と分けもつことなのです” という答が返される。他方、[T]は19歳で入学したカルフォルニア工科大で、 “実に偉大な科学者、専門の天才でありながら普段の生活では最低の人間でありうる” という現実にショックを受け、 “人間倫理の上で科学を補完するのが仏教なりその他の宗教だと思う” という期待から、この異色の対話に臨む。
話題は、相対論、量子論とEPR逆説、ビッグバン説、遺伝子科学、時空論、カオスなど、現代科学の最先端と哲学および倫理が鋭く切り結ぶ広範な領域に及ぶ。仏教には認識論、存在論に対する独自の哲学的性格がある。かつてハイゼンベルグは、 “この前の大戦以来、日本からもたらされた理論物理学への大きな科学的貢献は、極東の伝統における哲学的思想と量子論の哲学的実体の間に、何らかの関係があることを示しているのではあるまいか。…素朴な唯物論的な思考法を通ってこなかった人たちの方が、量子論的なリアリテイの概念に適応することが、かえって容易であるのかもしれない” と書いた。1) 量子論に限らず、現代科学の広い分野で、「固有の実体性」か「現象の相互依存性」かという西と東の視点から、世界観、物質観、生命観が具体的に論じられる。そこで使われる主要な科学用語と仏教用語の簡潔で適切な解説に本文に先立つ12頁が割かれ、「対話」 の内容の理解を助ける。 章を追って読み進む必要は必ずしもない。まず序文と巻末の「科学者の結論」、「僧侶の結論」を用語解説を参照しながらざっと読み、ついで、興味をもった話題の章に移る読み方が、この異色の対話の全貌を掴むには有効かもしれない。訳文は流麗で対話の雰囲気をよく伝え緩みがない。文系(比較文学)の訳者は、科学と仏教に関する内容に関して、一流の専門家の教示を求め、物理学では池内了、高田誠二の両氏に謝意を表している。
“「科学は精神性(スピリチュアリテ)なしには正しい働きはできない。精神性は科学なしには存在しえない。しかし人間は、真の人間であるためにその両方を必要とする」という科学者の結論は、私たちの出発点であろう。この地点から歩み出そうとする意欲的な若者の読者が一人でも多いことを・・・” という「訳者あとがき」のメッセージに評者も心から賛同し、精神的に若くあらんとする広い範囲の会員の一読を勧めたい。参考文献
1) M. ハイゼンベルグ:「現代物理学の思想」、河野伊三郎、富山小太郎訳、みすず書房(1989) p. 210.
(2004年5月18日原稿受付)ページの頭に戻る
岩崎民子
知っていますか? 放射線の利用
丸善、東京、2003, viii+220 p., 18.5×12.5 cm, 本体1,300円
神谷 富裕 〈原研〉
本書は、普段われわれが知らないところで驚くほど放射線というものが利用されていることを数多くの具体例を挙げて紹介し、その性質や有用性をこれまた具体的にわかりやすく解説し、またどのように取り扱えば安全であるかも教えてくれる。
まず読者は、現代社会において、日々の食生活や医療、半導体や自動車等の産業界、あるいはまた考古学や犯罪捜査に至るまで、人々が既に好むと好まざるとにかかわらず放射線というものがかなり自分の身近にあることに驚くことであろう。写真や図表を駆使してX線、 ガンマ線、 電子線あるいはイオンビームといった多様な放射線がいかに使われているかが、幾分専門的な内容も含めて詳細に紹介されている。こうして「放射線」という言葉にとかく拒絶反応を起こしがちな「一般」の人々にも、努めてその有用性を訴えかけている。また、最近大学入試問題に取り上げられたことも実例とともに紹介しており、別の意味でも放射線についての学習を動機づけする工夫が施されている。しかし、とかく専門家の「推進論者」 にありがちな、 放射線利用の安全性、有用性のみをひたすら強調するのではなく、著者は公正な立場から、これを利用する場合のリスクを科学的に正しく読者に理解させようとする努力も惜しんでいない。この点で、どのような読者も(知識の有無、利用に対する賛否にかかわらず)、安心して読み進むことができるであろう。
次に読者は様々な事例を通じて、「放射能」との意味の違いを含めて放射線とは何か、身近に接する放射線の量、利用の歴史、利用技術の経済効果まで、定量的なデータに基づく知識を与えられる。本書の最大の目的はここにあると思われるが、膨大な実例の紹介であるにもかかわらず、きわめて要領よくコンパクトにまとめられているので、退屈することなく読み進められるはずである。
タイトルの中の「知っていますか?」という問いかけにも現れているとおり、本書は、放射線利用に関する啓蒙書として書かれたものである。したがって、知ってほしいという強い願望がひしひしと伝わってくる。だが、本書はそれだけを読者に求めているのではないことが最後まで読み進むと気づくのである。筆者は、読者に対し、未来の放射線利用に望みを持つこと、そしてやはり放射線というものは誤って扱えば危険であるというおそれを持つことも求めている。
考えてみれば、驚くようなことでも、それを知っただけでは「本当に!、ああそう」で終わってしまいがちであるが、夢を見ると同時におそれを知ることが、「どうしたものか」という意識を触発し、未来に向けての放射線利用に関する推進力となることであろう。筆者は、そのことを控えめに読者に語りかけているように思われる。 (2004年2月15日原稿受付)ページの頭に戻る
M. G. Kanatzidis, S. D. Mahanti and T. P. Hogan, ed.
Chemistry, Physics and Materials Science of Thermoelectric Materials; Beyond Bismuth Telluride
Kluwer Academic, Dordrecht, 2003, x+317 p., 25.5×17 cm, \30,650 (Fundamental Materials Research)
小口 多美夫 〈広大院先端〉
本書は、“Beyond Bismuth Telluride"と題した熱電材料に関するワークショップのプロシーディングスをまとめたものである。熱電材料は1950年代、半導体を主たるターゲットとした活発な研究の結果、Bi-Te系で高い性能指数ZT〜1を示すことが発見され、 その後30年間はそれをしのぐ物質は見いだされなかった。90年代になって、新たな物質群に対する高いZTの探索が試みられるようになり、その最近の研究アクティビティーが本書にコンパクトにまとめられている。
性能指数はZT=S2σT/κと与えられ、熱電能Sと電気伝導度σが大きく、 熱伝導度 κ が小さな系で高い値が実現される。金属やドープされた半導体でよく成り立つヴィーデマンフランツ則に従うと、σと熱伝導度への電子の寄与κeは比例するので、 物質探索としては S が大きく熱伝導度の格子の寄与 κp が小さい物質を探すことになる。
Sは、ボルツマン理論によると、電子の伝導を支配する因子(状態密度と散乱の緩和時間)のエネルギー依存性がフェルミ準位周りで大きな非対称性をもつときに大きくなり得る。すなわち、物質設計の意味では、フェルミ準位近傍に特異な電子状態もしくは散乱過程が実現されればよいことになる。また、電子の伝導を適度に維持しつつ、音響モードのフォノン伝播を乱すことが必要になり、 Phonon-Glass-Electron-Crystal (PGEC)という設計指針が生まれ、単純な半導体の範囲ではBi-Te系がこれに叶う物質であったわけである。
本書で紹介されている将来有望な熱電材料の物質候補は一見多岐にわたっているように見えるが、伝導を担う電子系からなるかご状もしくは層状の構造を基礎とし、その隙間に重い元素を挿入もしくはキャリアを制御できる原子をドープした物質系が中心となっている。伝導を担う電子系に関しては、強い電子相関によるフェルミ準位近傍に狭いギャップ構造の実現を狙った物質に新しい展開が見られる。
従来の物質・材料関連のワークショップではあまり見られなかった流れが、第一原理計算からの寄与である。物質科学では、複雑な構造の安定性を議論し、電子状態の基本的な性質を知るために第一原理計算は重要な役割をもっている。しかしながら、本書の中でも示されているように、伝導に関する理論は、現段階ではボルツマン理論の緩和時間一定の近似の範囲であり、強相関系への適応のための理論展開が今後期待される。
本書は、熱電材料の最近の進展を知る意味でタイムリーな本である。また、熱電材料にとどまらず新しい物質系の探索に対していくつかのヒントが含まれていると思われる。広く物性物理に関わる研究者にはお勧めの良書である。 (2004年4月9日原稿受付)ページの頭に戻る
山下芳樹、池田幸夫
文化として学ぶ物理科学;新しい学びの場を求めて
丸善、東京、2003, vi+190 p., 21×15 cm, 本体2,300円
井上 直也 〈埼玉大理〉
“文化として学ぶ” と添えられたタイトルに惹かれて本書を手に取る読者も少なくはないのではなかろうか。本書においては底流に一貫して、物理科学史の理科教育への積極的な導入を求める姿勢が見てとれる。
近年、中・高校生世代を中心とした理科離れを危惧する声は広く聞かれるところであるが、その原因が学習内容を理解できないことにあり、とりわけ現在の物理教育における物理現象のモデル化、法則・計算に重点を置いた、煩雑で興味を後押ししない無機的な取り扱いにあるとすれば、それを改善する一つの試みとして、近代物理学に至るまでの物理学的発見・自然現象の理解についての歴史的経緯といった題材を織り交ぜた、有機的な教育方法の導入が効果的であることを本書では説いている。古くは紀元前にさかのぼり、ニュートンに至るまで、歴史の中でなされてきた自然現象に対する理解の転換、また法則の発見を、それ以前のものと対比した上で、人間の自然観・科学観に対する歴史的変遷として、ここでは “文化的” 教材と位置づける。
本書ではまず、物理教育を行う側、受ける側双方(学生、教諭)の声を例示し、それを受け物理教育の目的と方法について問題提起を行っている。それを背景にして、事例研究と題して「地動説」「ケプラーの法則」「慣性の法則」等を掲げて、前述した新しい物理教育の方法を50ページを超える紙幅の中で具体的に述べている。 “地動説ありき” から始めて天体の運動に関わる自然現象の理解を深めるか、天動説の理解をふまえた上で地動説への展開を行うか、 “ケプラーの法則ありき” で惑星運動は記述できるが、学者としてのケプラーがそれを導くに至る道程は自然に対する好奇心を高めるための一助とならないか、 “慣性の法則” はそれを説明するに多くの言葉を要さないが、慣性に関わる理解が歴史的な自然観の違いに密接に関係していることを例示することは慣性の意味を物理的に実感する上でも意義深いのではないのか、等々、その具体的な講義の展開方法に新鮮さをも感じうる点が多い。その上で著者の言う “文化としての科学史” を含めた “複眼的” な視点からの物理教育が学生たちの自然観育成や理科に対する好奇心の発芽に大きく寄与し、理科教育の目標に十分かなうもの、として締めくくっている。
初・中等教育において、より多くの学生に、自然の探求に興味を持たせ、とりわけ物理学を志すきっかけを与えるような教育法を模索することは大学教官にとっても関心を持つべき課題であろう。限られた授業時間の中で成し遂げないといけない教育目標を、理想と現実の中でどのように実現するか、その一つの具体的な方法を詳述した書である。 (2004年1月22日原稿受付)ページの頭に戻る
F. Schweitzer
Brownian Agents and Active Particles, Collective Dynamics in the Natural and Social Sciences
Springer-Verlag, New York, 2003, xvi+420 p., 24×16 cm, \11,750 (Springer Series Synergetics)
山崎 義弘〈早大理工〉
多数の構成要素(エージェント)からなる系の集団的振舞を、シミュレーションにより明らかにする方法論および自然科学・社会科学などへの応用について、筆者が1992年から10年間行ってきた研究をまとめた書である。(ミクロな)構成要素の集団からは単純に推測できない性質が、外場や要素間どうしの相互作用により、(マクロな)系全体の振舞としてどのように現れるかについて考察するにあたり、著者は次のような方法論を採用している。まず前提として、構成要素の運動がブラウン運動であると仮定する(第 1 章)。 従って、構成要素の時間発展はランジュバン方程式に従うものとし、その上で、マクロな現象を再現するのに必要最小限な自由度・相互作用項等を導入していき、現実の実験・現象と比較することを試みている。
分子動力学法など物理で用いられるモデルと本質的に異なる点は、構成要素が内部自由度を有していることであろう。第2章では、内部自由度として構成要素が持つエネルギーを導入する。このエネルギーのおかげで要素は自走し、自ら意思を持つことが可能となる。これは、昆虫や細胞といった生物群の集団運動を考える場合に必要な自由度と考えられる。また第3章以降では、エネルギー以外の様々な内部自由度について紹介し、さらに他の構成要素との相互作用を反応拡散的に時間発展する場として捉え、要素と場との相互作用に置き直してマクロな集団運動を再現しようと試みている。
本書において取り扱われている現象は多岐にわたっている。第3章では生物群の凝集過程や、反応拡散系で観られる螺旋やスポットパターンを再現し、モデルの有用性について議論をしている。 第4, 5章では、ネットワークの自己組織化について紹介している。特に第5章では、ランダムウォークを元にしたモデルを考え、バクテリアのコロニー形成や、アリがえさまでたどり着く経路の時間発展などを例として挙げている。他にも、道のない(立ち入りできる)芝生上での、歩行者による通路の形成(第6章)、最適化に基づく道路の形成(第7章)、都市集合体のフラクタル性や形成モデル(第8章)、就業者と失業者を要素としてみた集積の経済(第9章)、個人を要素とした意見の集約(第10章)といった現象が取り上げられている。
取り扱っている現象が既存の物理学の枠組みに収まっているとは言えないため、専門外の読者にとって用語などが煩雑に感じる面は否めないが、考え方は一貫していて、非線形動力学や統計物理学の輪講などにも適しているであろう。 (2004年1月26日原稿受付)ページの頭に戻る
山本義隆
磁力と重力の発見;1. 古代・中世、2. ルネサンス、3. 近代の始まり
みすず書房、東京、2003, 1: v+324 p., 2: v+318 p., 3: v+352 p., 19.5×13.5 cm, 本体1 & 2: 2,800円、3: 3,000円
江沢 洋
接触による普通の力と違って、磁石は距離を隔てて鉄片を引くように見える。古代ギリシャの哲学者たちは、この磁力を目に見えない粒子を介した近接作用とみるか、霊的な遠隔作用とみるかの二通りの思想を生み出した。本書は、ここから説き起こし、磁力が魔術とみなされた中世から、イスラム社会(そこに伝えられていたギリシャ科学)との接触による十三世紀の転換、十五世紀の思弁的魔術から十六世紀の経験的・数学的・実践的な魔術への脱皮(自然界は諸事物とそれらの相互作用からなり人は観察によりその力を知ることができる)を経て、ケプラーが惑星の運動を太陽の磁力に帰しつつも観測データに助けられて彼の三法則を発見し、やがてニュートンが「私は仮説を立てません」といって重力の機構の追究を放棄し惑星の運動の三法則を解析して重力を厳密な数学的法則に従わせることにより魔術的な遠隔作用をひとまず合理化するまでを、原典に直接あたりながら精細に跡づけたものである。それだけに新事実の発掘、通説の誤りの指摘も多い。たとえば、近代電磁気学の出発点とされてきたギルバートの 『磁石論』 (1600)が無視した先行者デッラ・ポルタの存在(『自然魔術』、1558)。さらに時代時代の思潮の社会的・技術的背景にも細かい目配りを忘れていない。
著者は言う。「これまでの物理学史が見落していた、あるいは過小に見積もっていた部分にあえて照明を当てることは、物理学、ひいては近代科学そのものの成立根拠を改めて問い直すことに繋がるのではないか。」この企ては大きな成功をおさめた。ここにギリシャに始まり一七世紀に結実する自然に関する思想史というか広く文化史とさえいえるものが展開されたのである。必然的に、新しい視点も多く提出されている。「一六世紀の文化革命」と著者が呼ぶ知の世界の地殻変動の指摘もその一つである。この時代に大学とは無縁な技術者や職人が俗語で科学・技術書を書き始めた。技術者ステヴィンは宣言した。「科学を築き上げるには経験に基づく大量の知見が入用だ。多くの人々の参画が必要で、それには各々の国の言葉を使わねばならない。」確かにガリレオも多くの著作をイタリア語で書いた。そしてニュートンの太陽系の理論も、その延長上にあったともいえるだろう。フックをはじめとする大学の外のグループとの議論に負うところが大きかったからである。
こうして本書は、近代科学の成立根拠を問い直すことにより社会の学問に対する姿勢に-とりわけ理科と文科の分離が進む現在の日本社会に対する-大きな示唆を発掘した。これは専門の研究者集団の外で「手探りで勉強を続けながら」書かれ、それゆえにこそ独創的な仕事となった。パピルス賞、毎日出版文化賞、大仏次郎賞に輝いた。 (2004年1月22日原稿受付)ページの頭に戻る
弘岡正明
技術革新と経済発展;非線形ダイナミズムの解明
日本経済新聞社、東京、2003, xiii+372 p, 15×22 cm, 本体5,200円
大内 伊助
本書は、景気変動や経済発展が技術革新に深く関わっているだけでなく、それ以前の物理学、化学、生物学など基礎科学の進展に根差していて、これらが横軸に時間、縦軸に成熟度をとったシグモイド型のロジスチック曲線で説明できることを多岐にわたる事例で検証し、現状の認識や将来予想にも役立つことを論じた、極めてスケールの大きい労作である。
技術革新が景気変動の原動力であることは、1926年にシュンペーターによって最初に指摘されており、また、技術革新による製品の普及が、生物の個体の増殖や伝染病の広がりを表すロジスチック式(dy/dt=ay( y0−y). 後者の例では、 y0: ある地域の人口、 y: 時間 t において未感染の人口)と同じ式で表されることは、グリリケスが1957年に言い出したことであるが、著者はこれに「軌道」という概念を導入し、技術革新が3つの軌道からなることを論証する。すなわち、1)技術革新の結果としての製品普及を表すロジスチック曲線である‘普及軌道’と、 2) それの数年、乃至、数十年前に同じ形の曲線を描く‘開発軌道’、 3) さらにその数十年前に、基礎研究が形成する‘技術軌道’(これは、開発軌道が始まるまでは認識できないことが多い)が存在するという事実を明らかにした。ロジスチック曲線の時間軸はマイナス無限大からプラス無限大の時間にわたるが、縦軸の成熟度がごく0や1に近い極端な過去・未来を除くと、いずれの軌道も有限の時間幅の間に収まっていることが重要である。例えば、18世紀の蒸気機関の開発軌道のタイムスパンは60年程度、半導体素子は25年程度である。このような技術革新の非線形性とダイナミズムの実証が本書の中心課題である。
いままでの経済学では殆ど取り扱われなかった‘技術軌道’にまで踏み込んだ議論をし、その他、各所で新しい視点の取り扱いがされているのは、著者が高分子化学の研究者であるという経歴に由来する。こういった斬新な分析が可能となったのも、企業において、基礎研究から工場建設、研究主幹から通産省の次世代基盤技術研究組合の研究リーダーまで歴任、交互共重合の理論で高分子学会賞受賞という実績を有する著者が、定年前に転じた神戸大学経済学部以後の15年間の仕事を集約したものが本書であるという背景を知ればなるほどと納得がいく。
全体の構成は序章と3部からなる。序章である第1章は背景と目的の他に、第I, II, III部の要約が28ページにわたって記されており、本書の輪郭をうかがうことができる。
第I部‘技術革新の普及と経済発展’では、まず従来の経済学(計量経済学、ケインズ経済学…)で技術革新がどのように扱われてきたか、1957年のグリリケスの指摘以来、新技術による製品の普及がロジスチック曲線に従うことがどのグループによって検証されてきたかといったことが述べられ、ロジスチック曲線の取り扱い、適用の具体例などが述べられている。そして、いくつかの製品普及曲線が集中してコンドラチェフ景気波動の上昇期を形成していることを指摘する。コンドラチェフ(1926)以外にも、 キチン(1923), クラーク (1843), ジュグラー (1862) などの景気波動があり、これらとシュンペーター(1939)の景気循環論などの関係も紹介される。また、過去230年にわたるエネルギー、運輸、情報通信のような基幹イノベーションとコンドラチェフの波動との関係が論じられる。さらに、1929年の大恐慌の経緯と成因に関するガルブレイス(1956)他、多数の人の議論が紹介され、日本の経済発展やバブルとその崩壊についての解釈もまとめられている。第I部は経済学に疎い向きにはよい勉強になる。
第II部‘技術開発のダイナミズムと新産業の形成’は、5つの章からなり、本書の中心部分を形成する。上で述べた技術革新の3つの軌道の存在を合成染料、農薬などいくつかの例で詳しく検証、提示する。特に、特許数や上市件数の代わりに、開発技術の時系列分布からその技術開発の動向を示すロジスチック曲線の推定が可能であることを主張する。このことを承認した上で、第1次産業革命以来の半導体素子や高温超伝導に至る40件余の技術革新について各軌道の様相を検討し、コンドラチェフ波との関連など論じている。3つの軌道のうち、‘開発軌道’は産学協同、ベンチャービジネスの開始、市場開拓、製造への技術移転など各々のタイミングにとって重要な役割を果たしており、これをエレクトロニクスや自動車分野の例も含めて検証、議論し、また、この時点での政府の役割をアジア各国の対応も含めて論じている。また、既存産業が技術革新をどのように取り込んで融合していくか、成熟期における企業の対応などについても論及する。
第III部‘非線形ダイナミズムの本質と次世代展開’は一口に言うと第II部の補強と延長であるが、最初の章では、自然科学のみならず、経済学などにおいても軌道があり、有限の期間に成熟する非線形事象であることを検証する。専門の応用化学以外に物理学、生物学から経済学に至る該博な知識と洞察が現れていて感嘆させられる。ロジスチック曲線を表す微分方程式の吟味にも1章を割いている。最後の2章は本書の総仕上げであり、21世紀への技術予測と長期展望を議論し、一方で、技術革新における非線形性、タイミング、それに知識の伝播の重要性を強調して結んでいる。
時に荒削りの議論もあり、‘技術軌道’の‘成熟度’を表す縦軸の基になる量やそのばらつきに関する考察など物理屋なら気にする点もあるが、全体としてのユニークさ、視野の広さは抜群である。巨大プロジェクトを企画・推進する人を含め、個々の基礎科学に従事する者も、時には、本著者のような壮大な見方もしてみたいものである。なお、本書によって、著者は京都大学から2つ目の学位、博士(経済学)を授与されている。 (2003年9月8日原稿受付)ページの頭に戻る
G. Vitiello
My Double Unveiled
John Benjamins Pub.、Amsterdam and Philadelphia、2001、xviii+361 p.、22×16 cm、US$49.95 (Advances in Consciousness Research、vol. 32)
江沢 洋
これは脳の量子力学の数式なしの解説である。脳の記憶や学習の機作が場の量子論にあるといったのは、おそらくL. M. Ricciardi-梅沢博臣(1967)が最初であろう。それはC.I.J. Stuart-高橋 康-梅沢(1978)によって展開され、その後の発展につながった。この本は、それを解説し著者自身による研究について述べている。
脳のはたらきは、(ヒトの場合1010 もある)ニューロンを結ぶ回路網を電気信号がかけめぐると見る立場から研究され、記憶はニューロンのクラスターの状態に印加されたパターンとされてきたが、Ricciardi-梅沢は、それでは病気や切開に耐えて記憶が生き残ることが理解できないとし、また脳がはたらいているとき遠く離れたニューロンの間に相関が見られることを考慮した。さらに、脳が活動しても記憶が乱されないことから、脳の活動と記憶を分離する必要があるとして、何かある多数の “単位” の多体問題を場の量子論の対象とみて破れた対称性の基底状態に記憶を対応させることを提唱した。対称性の破れに伴うGoldstone-南部ボソンがボース-アインシュタイン凝縮した状態である。これは、記憶はホログラムのようにして脳全体に分布するのだという K. H. Pribram の説(1971) にも合う。著者は、ニューロンを囲む水分子の多体問題を考えているようだ。
記憶することはいろいろある。そのそれぞれに一つずつ破られるべき対称性が対応するとRicciardi-梅沢は考えたが、その必要はないと著者Vitielloはいう。どうやら、破れた対称性の基底状態は無限に縮退しているから、ということのようだ。いずれにせよ、外部からの刺激によって一つの基底状態が実現する。これが学習である。学習のときと同様な刺激がくれば対応する基底状態に励起が起こり、記憶を呼び覚ましたことになる。同時に二つのことを思い出すことがなく(想起は直列的に起こり)、また一つのことから他のことが連想されるのは(一つの基底状態に対応する刺激が、他の基底状態に対するものと似ていることがありうるので)この考えを支持する。
では、この本の表題にいう My Doubleとは何か? 脳は常に外の世界と相互作用する開いた系で、必然的に散逸系である。したがって、と著者はいう。梅沢の熱場の理論形式を採用して場Aに対してその鏡像ともいうべきAを導入して系の自由度を2倍にしなければならない。Doubleとはこのことであり、著者の研究のポイントであるらしいが、この辺の論理はこの本を読んだだけでは評者にはわからなかった。原論文にあたる必要があるようである。
脳の働きを数式も図もなしに解説しようとした著者の努力を多とする。われわれ物理屋には数式も図もあった方がありがたいが、脳に好奇心をもつ方々の挑戦を期待する。 (2003年8月21日原稿受付)
ページの頭に戻る
高田誠二
「単位」がわかる
丸善、東京、2003, viii+122 p., 18×13 cm, 本体1,600円(理科年表読本)
仁藤 修〈農工大工〉
本書は普段何気なく使っている単位を最近のニュースや身の回りの生活の中から着目し、その一つ一つとそれらの関係を解き明かしている。1960年に国際度量衡総会で採択された国際単位系(SI)が、全ての単位でようやくなじみ始めた感がする昨今であるが、そのSIについても基本単位、固有の名称で表される組立単位があり、物理量はそれらの組み合わせであるからなかなか複雑である。その上、非SIであってもSIと併用が認められているものもあれば、推奨されない単位もある。
単位について長年携わってきた筆者がSIのほとんどを取り上げてその合理性、有用性を説き、非SIについてはそれがなぜ使われ続けているのかを解説していて興味深い。例えば、ノットや船舶トン数、血圧の水銀柱ミリメートル、角度の度、分、秒などの非SIの話題があり、電力のkWhをJで表す利点の説明も説得力がある。数式が最低限しか使われていないので、理科年表読本として厳密さを求める読者には物足りなさが残る。また可視光の波長範囲など個人差があるにせよ本の中でも統一がとれていなかったり、有効数字が不揃いだったり、多少厳密さに欠けるところもある。単位の歴史を説きそれを理解することのおもしろさについて書かれたもので教科書ではないと言われればその通りで、読み物として一気に読んでしまう魅力がある。(2003年9月8日原稿受付)
ページの頭に戻る