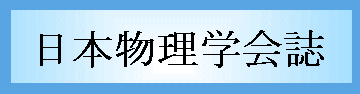
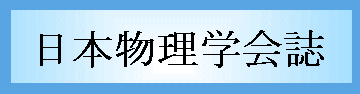
このページでは、物理学会誌「新著紹介」の欄より、一部を紹介者のご了解の上で転載しています。 ただし、転載にあたって多少の変更が加わっている場合もあります。 また、価格等は掲載時のもので、変動があり得ます。
岩波書店、東京、2005、 xiv+235 p.、 19.5×14 cm、 本体1、800円[一般書]
和田昭允
物理学は越境する; ゲノムへの道
永 山 國 昭、喜多山 篤 〈岡崎統合バイオサイエンスセンター〉
N「K君、最近こんな本が出たけど、読んでみますか?」
(1日後)
K「N先生、あの自伝、とても面白かったです、一気に読んでしまいました。ここ数十年の現代科学史としても、とても読み応えがありました。ヒトゲノムの解読競争には日本がこんな風にかかわっていたなんて、全然知りませんでした。」
N「実は和田先生は僕の師匠でね、恩師の自伝の書評を書くのは、ちょっとやりにくい。だから、第三者的視点からの感想も聞きたかったんだよ。この本の中身の半分ぐらいは、僕も断片的には知っていたけど、改めて全体像を見ると言葉を失うところが多く圧倒されました。」
K「そうですね、明治の元勲の流れを引く学者家系の出で、戦前の小学生が自分の家で化学実験するところもすごいですけど、 Lavoisierまでたどれる科学者の系図を示されたときは驚きました。」
N「和田先生は、学習院から東大の化学をでて、ハーバードで生物物理を研究し、お茶大を経て東大の物理学教室に戻られた。この部分が第1章、第2章に詳しいけど、当事の東大物理教室をとても懐かしんでおられる。刺激的でしかも自由という雰囲気が先生に活力を与えていたように思う。」
K「物理学が越境するっていうより、和田先生が越境している印象ですね。」
N「そういうことだと思う。」
K「すごく地味なDNAのらせん・コイル転移の溶液物性の実験データから、自然の生物設計原理、つまり遺伝情報(生命条件)と構造安定(物理条件)の関係性を見抜くなんて、すごいですね。これが、最終的にゲノム塩基配列の決定という大事業につながっていくんですよね。」
N「第5章、第6章が圧巻です。1980年代当時、まだDNAの塩基配列決定はRIを使ってX線フィルムを目で読んでいたような時代に、ヒトゲノムが完全解読されてしまう今の時代を実感していたことが伺える。」
K「でも、そういうあまりに先を見過ぎた研究方針は、まわりが理解できなかったりしますよね。そのことがいわゆる日本のゲノム敗北につながったことを苦渋を交え伝えているように見えますが。」
N「『和田の悲劇』 と私が呼んでいる部分は先生が最も書きたかったことではないかと思います。そういう意味でも、国の科学技術に関わる政策決定者には、是非読んでもらいたい。」
K「そうですね、同じ過ちを再び繰り返さないためにもその悲劇を定量化して、この本でのもう一つの主張「暗黙知を形式知に変換」しなければなりませんね。」
N「しかし第7章に詳しい理研ゲノム科学総合研究センター所長としての劇的な復活劇は、国内での不遇が、海外からの高い評価でひっくり返ったという印象を持ちます。」
K「ハーバード大時代の研究、東大時代の研究を通じて作り上げた国際的な人的ネットワークがプラスに作用したということでしょうか。」
N「この本に通奏低音として流れている物質世界と生命世界をつなぐという壮大なテーマも単なる夢物語で終わらせていない。ゲノム解読問題へのかかわり方にも先生独自の戦略性が現れている。理研時代はその意味で研究人生の集大成だったのでしょうね。」
K「それにしても、ゲノムプロジェクトの核心であるDNA配列決定ロボティックシステムの投稿論文(Analytical Chemistry)がrejectされた顛末もすごいですね。結局editorに当てた手紙が、米国の博物館に入り、ゲノム研究史の1頁として歴史に残った。もう一つ不思議なのはどうしてこんな風に、昔の細かいことを明解に書けるんでしょうか。」
N「私が知る限り、和田先生は学問的な文書だけでなく、個人的手紙、大学運営の文書、学会関連の文書、国家プロジェクト文書など大事にされていた。そのことがこの本の執筆を可能にしたのだと思うとともに、学者の家系の基礎体力を感じるよ。」
K「ところで本の副題のゲノムへの道ですが、何故この道を選んだのでしょうか。」
N「そこはこの本の読み方にかかわるが、和田という越境する個性を時代が後押ししたようにも思えます。すなわち物理学という学術の本流と生命科学という清新な流れの衝突を自らが体現していった結果だと思う。」
K「これを読んだ高校生や大学生ぐらいの若い人はどんな感想を持つんでしょうかね。この自伝で紹介されたような学問上のスゴイことはとてもできないと思うんじゃないかと心配しますよ。」
N「しかし先生はこの本の中で、個人の持つ潜在能力はそれぞれに非常に大きいものがあると言っている。そしてそれを出し切るには自らが新しい問題を見出し、いやむしろ作り出し、それに全力でぶつかることだと。
若い人にはこの本をそのようなロールモデルとして読んで欲しい。」
(2005年8月19日原稿受付)
シュプリンガー・フェアラーク東京,2004, xi+423 p., 21.5×15 cm, 本体\4,500[一般書]
R. L.サイム 著,米沢富美子 監修,鈴木淑美 訳
リーゼ・マイトナー; 嵐の時代を生き抜いた女性科学者
郷 農 靖 之 〈理化学研究所〉
本書は「核分裂」の発見に本質的な貢献をしたにもかかわらず、ユダヤ系ゆえにナチスの迫害を受け、女性故に差別を受けて、ふさわしい栄誉を受けることのなかったリーゼ・マイトナーの生涯を描いたものである。
マイトナーの生涯は、種々の粒子が発見され、原子模型が確立し量子力学が完成すると云う、自然科学が急速に進歩した時代と重なっており、多くの歴史上著名な科学者達との交流が描かれている。マイトナーの研究生活はベルリンのカイザー・ウィルヘルム研究所でのオットー・ハーンとの30年以上にわたる共同研究が主であった。彼女をオットー・ハーンと引き合わせたのは、量子論のマックス・プランクであった。当時、女子の大学入学がやっと認められるようになったばかりで研究者の世界も男性ばかりの時代だった。そんな中で、マイトナーは物理学者であったが、同じ年齢の化学者オットー・ハーンと当時始まったばかりの放射線に関する研究を共同で行った。
やがて1930年代になってヒットラーが現れて、ナチスのユダヤ人排斥が始まると、同年代のアインシュタインは早々にドイツを去り、残るユダヤ系の人々も職を追われた。マイトナーはそれでも研究の場を去ることができず何とかベルリンに踏み止まろうと努力したがついには職を去らざるを得なくなった。
60歳のマイトナーはニールス・ボーアの世話でスウェーデンに亡命し、ノーベル実験物理学研究所で研究を続けることになった。しかしながら、研究所長のマンネ・シークバーンは女性蔑視から徹底的に冷たく扱い、研究の場所は与えたが助手をつけず、研究費もほとんど与えなかった。
それでも共同研究者であったベルリンのハーンとシュトラスマンとは手紙で研究の議論をし、マイトナーからは研究上の種々の示唆が与えられた。誰もが想像もしなかった「核分裂」はこの手紙を通した共同研究の成果であり、実験的に核分裂を実証したのはハーンとシュトラスマンの業績であるが、それに理論的解釈を与えたのは、マイトナーと当時コペンハーゲンに滞在していた甥のフリッシュであった。
しかしながら、ユダヤ人と共同研究していることが公になるとハーンの立場も危うくなるとかで、ハーンはその後「核分裂」は純粋に化学的に発見したものであり、物理学の貢献は無いとして物理学者であるマイトナーの貢献を否定した。
1944年度にはオットー・ハーンがノーベル化学賞を受賞したが、ハーンの主張と当時ノーベル賞の審査委員であったマンネ・シークバーンの「マイトナーには受賞させない」と云う努力によって遂にマイトナーはノーベル賞を受賞出来なかった。
マイトナーがベルリンを離れた後のハーンの取った態度は時代背景のせいでもあったとは言え、いささかやりきれない思いがする。
本書では2度の大戦に、マリー・キュリーやマイトナーを始めとする著名な科学者がどのように振る舞ったか描かれており、その弱さも垣間見え、科学に従事する者に参考になる。
又、多くの著名な科学者の人生が描かれており、若者にも興味深く読めるものに仕上がっているが、若者にはこの値段が、いささか高価に思えるかもしれない。
(2005年6月29日原稿受付)
O. Gingerich
The Book Nobody Read; Chasing the Revolutions of Nicolaus
Copernicus
Walker & Company, New York, 2004, xii+306 p., 21×15 cm, $10.2[一般書]
池 田 秋 津 〈静岡理工科大理工〉
1959年にケストラーは「夢遊病者たち-変遷する宇宙観の歴史」という本を著して、バビロニアの時代からニュートンに至るまでの宇宙観を語った。その中でケプラーは好意的かつ肯定的に描かれているが、ガリレイとコペルニクスについての記述は冷たい。コペルニクスの大著De Revolutionibus orbium celestium libri sex(天体の回転について、以後De Revと略記)の節は “The Book Nobody Read(誰も読まなかったあの本)” という見出しを持つ。これが本書のタイトルになっている。著者オウエン・ギンゲリッチは著名な科学史家であってハーバード大学の科学史と天文学の教授を長くつとめた。
ギンゲリッチが1970年にエディンバラで手に取ったDe Revの初版本には、ぎっしりと書き込みがされていた。彼はその後、 De Rev を有する図書館、 大学、修道院、個人を世界中に訪ね、初版本(1543)と第二版本(1566)の「国勢調査」をはじめた。彼が手にとって調べ写真に収めたのは総数601冊に上る。De Revの発行部数を初版400〜500、 第2版500〜600と彼は推測している。従って約60%が現存し、彼の調査の対象になったことになる。彼は余白への書き込み、巻末に挿入された個々人のノートを丹念に読む。書き込みから、それを所有した人がどういうことを考えたかを知る。実視、考察、確認というプロセスを繰り返し、誰が所有したか、誰に受け継がれたか、というようなことを、30年にわたって調べ歩いた。筆跡を誰のものと同定するために多言語にわたる古書、手紙、手稿も調査する。ある人が余白に書いたコメントを別の人が自分の本に書き写すということがしばしば見られる。同じコメントが数冊に現れていることから、どういう人の間に交流があったか、がわかる。 そのコメントも “Ego (私)” という一人称で始まっていれば、そこが源流である。コピーする人は一人称では書かないからである。アメリカで手に取った本の書き込みから、以前ヨーロッパで見た本に抱いた疑問が解けることがある。そうして彼は再びヨーロッパに飛んで、それを確認する。そういうわけだから、一期一会ではなくて、数回にわたって訪問を繰り返した本も多い。わずかな手がかりをつなぎ合わせて全貌を明らかにしていく推理小説のような過程が実に面白い。実際この本は、盗まれたコペルニクス初版本の裁判の場面から始まっている。FBIやinterpolなど日常の我々には無縁な世界に言葉が及ぶ。
ケプラーの使った本には克明に読んだあとが残っている。彼の師であったメストリン、地動説に立って天文表を作ったラインホルトも克明に読んでいる。面白いことに、強烈なコペルニクス信奉者であったあのガリレイの所蔵本には読んだ形跡が無い。但しガリレイは1620年に出されたローマ教皇庁の指示に従って丁寧に修正削除を書き入れているそうである。
De Revを予備知識無しに開くと、びっくりする。読者へ、という短い文章がまずあって「地球が動く、とこの本には書いてあるが、それは計算を容易にするための仮説であって、本当に動くと主張しているのではないし、そんなことはありそうでもない」と書いてある。冒頭で地動説が否定されている! 実はこれを書いたのはコペルニクスではない。印刷の面倒をみたOsianderというルーテル派の神学者が、宗教界からの攻撃を避けようとして勝手に挿入した驚くべき文章である。「Osianderが書いた」ことを公表したのはケプラーである。初版から60年以上経っていた。彼はいかにしてそれを知ったのか? 彼の使っていたDe Revからそれが明らかになる。
この本は物理学や天文学の専門家を対象に書いたものではなくて一般の読書人を対象にしている。しかし地球中心説、周転円、太陽中心説、コペルニクス、チコブラーエ、ケプラー、ガリレオ、などという概念や名前に物理の人は親しんでいるから、一般読者よりも深く理解できる。
太陽中心理論でなければならない、とコペルニクスが考えるにいたった根拠は何か、明快に書いてある本はあるようで、無い。そういう事情も影響してか、コペルニクス理論にはいくつもの間違った伝説がまつわりついている。例えば、 15〜16 世紀には天動説は観測と理論を合わせるために数多くの周転円が必要になり混乱のきわみにあった、という伝説。あるいは、詳細な観測データの前に天動説は無力であることが明らかになった、という伝説。ギンゲリッチは、天動説の計算でたくさんの周転円を用いた事実は無いこと、正確さという意味ではコペルニクス理論と天動説の間に優劣はなかったことを指摘している。ケストラーの「誰も読まなかったあの本」というきめつけに対してギンゲリッチは、He was wrong。 Dead wrong。 と結論している。
居ながらにしてDe Rev初版本が見られることを本書に関連してお知らせしておきたい(Octavo社刊CD-ROM $40)。 これには E。 Rosen による英訳も入っている。De Revは六巻からなっていて、第一巻の日本語訳は岩波文庫から出ているが、この日本語訳には難解な箇所がかなりある。そういうときにはこの英訳で対応箇所を読むとわかることが多い。このCD-ROMはお買い得であろう。
(2005年8月11日原稿受付)
佐藤文隆
雲はなぜ落ちてこないのか
岩波書店,東京,2005, xii+238 p., 19.5×13.5cm, 本体2,300円[一般書]
櫻 井 敬 久 〈山形大理〉
「雲をつかむようなはなし」ではなく「雲をつかむ」話である。いや話ではなく自然を見る論理的思考の試行である。いやいや、これでは硬い評になってしまう、深くも読める楽しい科学エッセー集である。この本の表題と著者を見ると宇宙物理からなぜ雲なのかと、一瞬の戸惑いと共にしかし覗いてみたいという欲望に駆られると思う。
我々は日々を暮らしているとき、ときにふと自然の美しさに感動したり、ムクムクと疑問が沸いてきたりすることがあるが、まず著者は「雲はなぜ落ちない?」という疑問の背景を探る。そして、感覚から発する疑問と科学的知識をもっていることから発する疑問に腑分けして話が始まる。もちろん、感覚をただ感覚だからといって切り捨てるようなことはしない。視覚から光の性質へそして見え方に話が進み、また一方でエネルギーの抜き方の話が出てくる。物理学は自然現象の中からそこにある基本法則を引き出すのだと習った。しかし、著者が書いている、複雑さの中に規則性を探して「基礎、基本」で読み解く訓練を身近な自然で行うべきということは教育でも研究でも常に心の中にフィードバックしておくべきことであろう。
この本は、雲はなぜ落ちてこないのか、にはじまり、地球環境を太陽系で考える、宇宙と素粒子・原子核、そして宇宙にドラマを追って、までの4部からなっている。著者は身近な自然から遠い世界へと構成を考えていると思われるが、自然を物理(科学?)を使って読み解いていくことを意識して書かれているのでどの章でも敷居なく入っていける。第一部には雲の他に色からはじまり光と視覚作用の科学を述べている。しかし、ここには原始の時代に人がみていた星空へのダイナミックな自然感覚は知識の獲得によって失われていくのではないかといった著者の躊躇のようなものが推察される。人はこの折り合いをどのようにして着けていくのだろうか。
第2部では物理学では陽には出てこない気候変動を太陽エネルギーの地球での流れとしてとらえている。雲と宇宙線や気候変動と太陽活動など第2部の内容は、地球環境のことを考えるとき物理の専門家にも参考になる。第3部には生物による元素のリサイクルといった視点など、この一般的な標題から想像するよりはるかに新しく面白い情報が詰まっている。第4部はドキュメンタリーである。超新星 1987A が与えた衝撃や宇宙環境へ飛び出しての実験など研究の最前線の臨場感がひしひしと伝わってくる。
すーっとも読めるが深く読もうとすると物理の基本知識を総動員する必要がある。高校生から物理の専門家まで何回でも読み返せる本である。
欲張りの評者としては気候変動についての更なる掘り下げが次に出ることを期待したい。
(2005年6月16日原稿受付)?アグネ技術センター,東京,2004, iv+220 p., 21.5×15.5 cm, 本体3,000円[一般書]
平林 真
本多光太郎 マテリアルサイエンスの先駆者
近 桂一郎
本書は本多光太郎(1870〜1954)没後50年の記念事業の一つとして出版されたもので、本多の著作の一部、および本多について既発表の論考を編集したものを主な内容としている。まず、本書特に河宮信郎の論説によってまとめると、本多は(1)磁性、金属材料の研究者および研究グループの指導者として、巨大な業績を残した。彼自身の代表的な仕事には単体の磁化率の精密な測定と周期律表に基づく整理がある。また膨大な本多グループの成果から代表を一つ挙げると高木弘-本多による KS (永久磁石) 鋼の発明がある。 (2) 旧制中学校、高等学校、大学で広く使われた物理の教科書の著者であった。また東北大金研の講演会とその報告集などを通して、研究成果の公開に熱心であった。(3)東北帝國大学鐡鋼研究所(東北大金研の前身) を創立し、 所長を永く勤めた。この研究所は産業界と密接な関係を持ち、成果を企業に供与する一方、人件費を含む運営費のかなりの部分を寄付などで賄なっていた。
上述のように多くの側面で超人的な活動をした人物について、それらがどのように行われたか、互いにどう関連していたか、は研究、開発に関わる人に関心のある問題である。しかし本多の全体像はすでに漠然としている。石川悌次郎「本多光太郎伝」(日刊工業新聞社、1964)は本多の人物像を活写しているが、事実について正確か否か疑問があるという。本多は生前すでに伝説に包まれた人であった。またその研究手法に対する評価は、本多の後期の弟子ないし孫弟子に当たる人々の間でも二分していた。
このような状況の下で、本多についての従来の研究、本多に関する重要な資料を集めた本書の出版は意義のあることである。内容は4つの章と著作目録、年譜からなる。編者による現段階でのまとめ(第 1 章)に続いて。 第 2 章は本多の著作からの抜粋である。紙数が限られているが、本多の方法をうかがうことができる。「第3章 本多光太郎研究」は本多の仕事を全体にわたって再評価しようとした、河宮、勝木渥の1970年代の論考、KS鋼の開発事情を再検討した小岩昌弘の論説の要約などをまとめていて貴重である。「第4章本多光太郎の遺産」は直接本多を知る諸家の回想、本多に関する資料の現状報告、現代の視点から本多の成果、方法を評価した論説などからなる。
総じて、面白く、ときに重い主題を含む本である。研究の方法、研究の組織化とその体制、企業との協力などについて、自分の足元を見直すきっかけを読者に与えてくれるかも知れない。
(2005年6月13日原稿受付)岩波書店,東京,2004, xi+335 p., 19.5×13 cm, 本体3,800円[一般書]岩波書店,東京,2004, xi+335 p., 19.5×13 cm, 本体3,800円[一般書]
武田 暁
脳は物理学をいかに創るのか
保 江 邦 夫 〈ノートルダム清心女子大人間複合科学〉
「これは武田流物理学そのものではないか!」
魅力的な題目の本が出版された。しかも、今日まで素粒子理論の牽引役を務めて下さった武田暁先生が著者とくれば、手に取る前から心躍る。だが、巻末には「本書の題名に挑発的な題をつけたが、本当に説得力のある答を見出すにはまだ先の長い道程がある。あるいは絶対に答の見出せない設問であるかもしれないし、また答が見つからない方がよいような気もする」とある。
ならば、不当表示ではないかと憤慨する心配はないと思うが、蛇足を承知で念を押しておく。本書を注意深く読み進むならば、自ずと「脳は物理学をいかに創るのか」が分かるはずだ。無論、読み終わってすぐにとはいかない。現代脳科学の最先端が見事に盛り込まれた内容。そのすべてを論理で読み進めば「脳は物理学をいかに創るのか」理解できると考えるのは短絡的に過ぎる。
初めて武田先生に接したのは、量子力学の授業でのこと。だが、基本原理から出発し演繹で突き進む手法は最小限に止め、様々な具体例を丁寧に説き進むという武田流物理学に馴染めず、落ちこぼれとなった。無論、講義だけではない。定評ある場の理論や素粒子論の教科書も、武田流で貫かれている。これが二度目の武田流物理学との出会いだ。そして、三度目の正直が脳科学の分野。研究集会で武田流脳科学を目の当たりにし、自ずと分かった。「これは武田流物理学そのものではないか!」と。そして、量子力学の講義を明確に思い出しながら、すべてを理解できた。そう、武田先生は学生自らの脳の働きによって自ずと量子力学が理解できるよう、厳選された具体例の丁寧な解説に終始する役に徹したのだ。
だが、先生自らのご経験に裏づけされているとはいえ、このような武田流のやり方によって学生自らの脳の中に物理学が創り出されていくことを、どう理解したらいいのだろうか? 多くの方に共通の疑問かもしれない。
今回、武田先生は本書を通じてその理由を丁寧に教えて下さっている。そう、「脳は物理学をいかに創るのか」という題は、本当は「学生の脳は物理学をいかに創るのか」となるはずだったのだ。物理学の様々な具体例の解説が外部刺激となって、それが学生の脳組織のどこにどのようにして蓄えられ、どのあたりで神経回路が特化していくことにより徐々に物理学そのものについての理解あるいは把握が形成されていくのか…そのすべてが最新の脳科学研究の具体例を選りすぐって説き進むという、やはり慈愛のこもった武田流のやり方で講じられているのだ。だからこそ、確信を持っていえる。読後の心地よさを幾夜か通して体験すれば、必ずや自ずと分かる日が訪れることを。「脳は物理学をいかに創るのか」という難問の答が。
(2005年6月14日原稿受付)
ページの頭に戻る
岩波書店, 東京, 2005, x+183 p., 17×10.5 cm, 定価(税込)740円(岩波ジュニア新書493)[一般書]
戸田盛和
アインシュタイン16歳の夢
並 木 雅 俊 〈高千穂大教養〉
アインシュタインが誕生した1879年から、彼がプリンストンに移り住んだ1933年までの間、物理学は大きく変わった。このほぼ真中に、奇跡の年がある。前半は怒涛の時代であった。
1879年は、マクスウェルの亡くなった年であり、ボルツマンの師ステファンが熱放射の法則を発表した年である。マイケルソンとモーリーの実験が1887年、マクスウェルの予言した電磁波がヘルツによって実験的に示されたのが1888年、 それにこの本(以下、 『16歳』)の書名にある‘16歳’は X 線の発見の年である。この翌年から、ウラン放射能(1896年)、 電子(1897年)、 それにラジウム(1898年)と発見の年が続いた。そして、ケルヴィン卿の金曜講話「熱と光の力学理論を覆い隠す2つの雲」が、1900年 4 月27日1)(『16歳』 では、1904年ボルチモア講演となっている)に行われ、プランクの量子仮説(1900年12月14日)を経て、20世紀が明けた。
戸田先生は、 『16歳』 で、 物理学の世紀としたアインシュタインの生涯(重点は青少年期)、奇跡の年の論文の解説、一般相対論の話、それらに関わる物理学を紹介している。
ジュニア新書の読者対象も考慮して、光速度の話をするとガリレオ、レーマー、フィゾーの測定法の紹介、光は波か、粒子かの話題ではニュートン、ホイヘンスの考えたこと、それに場の話が出てくるとファラデー、マクスウェルの研究に触れている。読者への心づくしであろう。
『16歳』 の骨組みは、朝永の言葉2)を道しるべとしてつくられている。 ‘芽’である‘16歳の夢’が、力学と電磁気のなかにあった矛盾を明白にし、奇跡の年に‘花’となった、として文にリズムをもたせている。アインシュタインの‘芽’、‘茎’、それに‘花’をやさしく解説した物理の本でもある。
この3つのキーワードの中でも、おもちゃ好きの戸田先生らしく、 ‘芽’の大切さを唱えている。アインシュタイン5歳の時の方位磁石への驚き、12歳の頃のピタゴラスの定理(戸田先生は、彼の証明を推理している)との出会い、アーラウ時代の‘光速度で光の波を追いかけたら’という「16歳の夢」、これらがすべて、 ‘茎’を経て‘花’となった。28歳の時の‘自由落下をする人は重力を感じない’も、少しニュアンスが異なるがこれに通じる。新鮮な疑問や驚きが物理を創ったことを納得させ、知的好奇心を刺激し、読み手を科学の世界へと誘う。実に巧みである。
それに、アインシュタイン26歳の奇跡の年までに重点をおいたことは、世代同調効果もあって、若い読者が感情移入しやすいばかりか、20世紀物理学の醍醐味も無理なく伝わるのではないだろうか。
今年は、世界物理年である。この書は、青少年に物理の楽しさを伝えるよき素材を提供してくれている。もちろん、会員諸氏が読んで十分に楽しめる本でもある。
注
1)講話の内容は、Lord Kelvin: Phil。 Mag。 2
(1901) 1-40にある。
2)ふしぎだと思うこと これが科学の芽です/よく観察してたしかめ そして考えること これが科学の茎です/そして最後になぞがとける これが科学の花です。
(2005年5月25日原稿受付)
ページの頭に戻る
新著紹介
アグネ技術センター,東京,2004, viii+180 p., 21×15 cm, 2,000円[一般書]
小岩昌宏
金属学プロムナード; セレンディピティを追って
石 川 征 靖 〈東大名誉教授〉
本書は、雑誌 『金属』 に2000年 4 月から「金属学プロムナード」と題して寄稿したほぼ独立した内容の14編を単行本にまとめたものである。私は超伝導体や磁性体の基礎物性の専門で、少し分野は異なるものの金属との付き合いが結構長いせいもあり書評を気軽に引き受けてしまったが “セレンディピティを追って” という副題には最初少々戸惑った。それはともかくとして、晩年に造幣局長官に就任して金属学への興味を示したニュートンの話、KS鋼などの永久磁石材料の開発と特許申請にまつわる日本の2研究グループ間の “係争”、 レントゲンやアレニウスのノーベル賞授与にまつわる少々 “血なまぐさい” 逸話など私にとってはそのほとんどが “初耳” の話で金属学研究の歴史の裏話に引き込まれて一気に読み通せた。このほかにも飛行機の機体用構造材料として知られているジュラルミン発見の逸話や元素発見の歴史、ニッポニウムと命名されるところだったレニウムの話など元素名の由来、固体物理の教科書にも登場するモット、ヒューム・ロザリー、パイエルスなどの研究にまつわる話が私たちには馴染みの薄い文献や古い手紙や雑誌などから発掘され紹介されている。なかでもノーベル賞受賞者のエピソードや選考過程での授与妨害などの逸話がとりわけ面白かった。受賞者のエピソードは当然としても授与妨害までも資料として残っているとは少々驚いた。このような発掘作業はかなりの忍耐が要求される仕事で著者の文献検索の地道な努力は敬服に値する。 “セレンディピティ” というちょっぴり不慣れな言葉についても、その語源と意味に関して諸説があるそうで最後章で詳しく紹介されている。ちなみに私も手許のランダムハウス英英辞典を引いて調べてみるとイギリスのウォルポールという人が 『セレンディップの3人の王子』 という寓話から3人の王子が有した能力を “セレンディピティ” と名づけたとあり、スリランカのアラブ名がセレンディップであるとされていることから私なりに “推察する” と、ペルシャ語の古い寓話をウォルポールが翻訳紹介した話と考えるのが妥当なようである。何はともあれ “セレンディピティ” とは彼が “定義” したように偶然の発見から重要な事実を汲み取る “能力” “才能” のことで、単なる偶然性はあまり強調されるべきではないように思われる。科学史に関する文献を丹念に発掘していけばこういうノーベル賞がらみのどろどろした逸話などはいくらでも出てくるだろうし、また同じようなことが今なお続いているのではないかと思うと複雑な気持ちになるのは私だけであろうか。本書に収録された逸話はそのほとんどが金属学にまつわるものだが、研究の合間に気軽に読める教養書と言っていいだろう。
(2005年3月3日原稿受付)
シュプリンガー・フェアラーク東京、2004、 xvi+206 p。(上巻)、v+133 p。(下巻)、18×13 cm、 本体1、900円(上巻)、1、600円(下巻)[一般書]
F.ディアク、P.ホームズ著、吉田春夫訳
天体力学のパイオニアたち; カオスと安定性をめぐる人物史 上・下
樽 家 篤 史 〈東大院理〉
日本語タイトルを見ると、 “天体力学” とあるので、一見、宇宙関係の啓蒙書かな、と思うかもしれないが、副題「カオスと安定性をめぐる人物史」からわかる通り、本書は、カオス・ハミルトン力学系の発展とその礎を築いた人々の物語がまとめられた本である。
ハミルトン力学系、あるいはカオス力学系というと、一般物理・数理物理的な学問というイメージでとらえてしまう人もいるかもしれないが、そもそも、そういう学問が切り拓かれた背景には、天体力学の存在があった。いや、天体力学があってこそ、生まれたといっていい。そこには、逆2乗則の力が支配する天体の運動に思いを馳せ、困難な未解決問題に挑んだ当時の人々のドラマが詰め込まれている。本書は、アンリ・ポアンカレに始まり、コルモゴロフ、アーノルド、モーザーらのKAM理論の成立に至るまでのカオス力学系の発展史を、一人一人の人物に焦点をあてて紹介したものだ。
本書の特徴は、力学系理論の先駆者たちが、どういう経緯で問題に取り組み、いかにして新たな理論を築いていったかを、深く掘り下げて説明している点であろう。当時の社会的および知的環境の再現にまで注意を払っているあたりは、力学系理論に対する著者らの思い入れが伝わってくるだけでなく、こうした理論が、何人もの先駆者たちの業績の積み重ねの上に成り立っていることを実感させてくれる点で、大河小説っぽくて楽しんで読める。
力学系理論の発展史が中心テーマとなっているためか、本書における天体力学の扱いは、かなり数理物理的だ。特に、長きにわたって未解決問題だった、パンルヴェ予想と非衝突特異点の存在証明の下りは (第 3 章)、 正直のところ、非物理的で現実味のない純粋数学の話としてしか印象が残らなかった。しかし、見方を変えると、これほどまで逆2乗則の力に固執し、その数理的側面を厳格にとらえようとした人々のおかげで (?)、 今日の力学系理論が成り立っているわけでもあり、天体力学の果たした役割はきわめて大きかったことが、こうしたエピソードからうかがいしれる。ところで、天体力学は、現在、太陽系外惑星系の発見という世紀の大発見を経て、今また脚光を浴びている。遠く離れた世界で織りなされる逆2乗則の物理現象をつきつめることで、さらなる発見のドラマが繰り返されることを期待したいところだ。
本書は、一般書としての立場から、数式を一切使わず、力学系理論に関する説明を試みている。逆にそれが仇となって、かえってわかりづらくなっている箇所が多々見受けられる。特に上巻で、幾何学的観点からカオスの本質について説明を試みた章は、一般書としてはやや難易度が高そうに思えた。ただ、本書の冒頭・訳者あとがきにも記されている通り、最初は軽く読みとばして、わからない点は後でじっくり考える、というスタンスで読んで欲しいということなので、とりあえず気楽に構えて読み進めればよいであろう。それでも不満な点が残れば、本書を離れ、より専門的な書物へ移行すればよいわけだし、とにかく、力学系理論の歴史的成り立ち、天体力学の奥深さに気軽に触れることができる点では、ユニークな本である。一度読んでみるといいと思う。
(2005年2月25日原稿受付)イザベル・シャバンヌ著、岡田 勲・渡辺 正訳、吉祥瑞枝監修
キュリー夫人の理科教室
丸善、東京、2004、 128 p。、 21×15 cm、本体1、500円[一般書]
坂東昌子 〈愛知大一般教育〉
「ある日、祖父が物置きの整理を思いつく、物置にあったもののひとつが、祖父の妹イザベル・シャバンヌの書類かばん、祖父が手渡すその中身を火にくべる役目の私は、黒いファイルに目をとめた。それは、マリー・キュリーがしてくれた物理の授業で、イザベルがとったノートの束だった。私はファイルとノートを祖父からゆずり受けた。」とレミ・ランジュバンがそのいきさつを語っている。共同授業で最年長だったイザベル・シャバンヌが書いた記録が、あやうく灰と化す寸前に見つけられ世に出たのだ。それが目の前にある。実験室で赤ちゃんを抱いてノートを見ているマリー・キュリーが描かれている表紙のこの本である。
この本には、13歳ぐらいだったイザベルのメモが原文のまま、掲載されている。手書きの図も字も几帳面で丁寧に書かれている。まさにまぼろしの実験室の再現である。授業は2年間続けられたそうであるが、そのほとんどは、空気と水に関する実験である。具体的には、真空と空気の違い、空気の重さを実感する、気圧・水道・ポンプ・アルキメデスの原理、重さを測る、固体や液体の密度を測る、いろんな形をしたものの密度を測る、再びアルキメデスの原理、船が浮くわけ、卵を浮かせる、気圧計をつくる、という10回の授業である。子供たちが、空気の存在をどうして知るのか、そして大気圧をどう測るのか、重さと比重の違いをどのように認識するのか、浮力の機構は?…など、生き生きとした会話も出てきて、よく準備され考えられた授業展開である。マリー・キュリーは何をするにもきちんと準備をした人に違いない。
それでも、びっくりしたのは、水銀などを平気で使っていたことである。このままこの本がこの世に出たら間違って同じ実験をする人が出てこないかな?と疑問に思ったが、そこには配慮の行き届いた訳者の註がついていた[18ページ註に「今学校で水銀は使えない」とある]。
今は、子供の理科教室は各地で花盛り、なかでも『Let's try 理科実験(函館東高校の渡辺教諭)』などには、身近な道具でできる実験が260も紹介されている。それも丁寧な図(吉田和歌子画)がついている。むしろ、この本の貴重な意義は、実験授業が今からほぼ100年も前、理科実験がまだ教育の現場で確立していなかった頃の試みが紹介されていることにあるだろう。なかでも、ここにある実験の中で特に面白いと思ったのはアルキメデスの実験で、水を入れた容器を天秤のさらに載せて、左右を釣り合わせておき、その中に硫黄の固まり(どうして硫黄なのかな?)を沈める。すると釣り合っていた天秤が容器の方に傾く、重くなったのである。しかし、そのあとが面白い。硫黄が沈んでいる体積分だけ、つまり硫黄が押し出した水だけがあふれ出るように工夫しておき、その水を取り除けば、今度は再び釣り合うということも実験して見せているのである。はじめに入れた水の高さより高くなった分の水があふれ出る容器をつくるのは、今なら、プラスチック製の容器を使えば、ガラスよりずっと簡単だな、などと思いながら読むと楽しい。
キュリー夫人の実験自体は、今の理科の先生たちがご覧になれば、もっとうまい方法があると思われるかもしれないと思う。そして実験に改良を重ねて分かりやすく簡単な装置で作って下さると、一層面白いだろうな、などと思う。
この本の解説には、当時のフランスの理科教育の状況が紹介されている。この解説から分かるのは、フランスの教育は複線コースで、一般市民とエリート階級とは分かれていたことである。この頃のフランスではエリートだけが機会を与えられた。大学研究者の子供たちに限られてはいたかもしれないが、大学の実験室でこういう授業を受けたのである。ひょっとして、これが雛形になって、今日の理科教室にその精神が受け継がれてきたのかもしれない。
ノーベル賞級の先生に教えてもらった子供たちは大いに啓発されたに違いない。そういえば、これを見習ったのかどうかははっきりしないが、名古屋大学で坂田昌一先生の発案で、理科授業をしていたことがあるらしい。そこで科学の芽を育てられた女性が何人か研究者の道を歩んでいる。この実験授業のノートをまとめたイザベルは後に化学技術者になったし、マリーの長女イレーヌは物理学の道に進んだ。当時女性が科学の道に進むことは今よりはるかにまれであっただろうから、この理科教室の意味は大きかったのだろう。男の子はいつか科学へ導く機会を学校で経験するだろうが、女の子にとっては偏見を取り払う希有な機会だったのだろう。
ある物理実験のかたが、「小学校のとき古本屋で理科実験の本を見つけて、それを立ち読みしていた。あるとき思い切って、『これを僕のこの本と交換してくださいませんか』と頼んだら、本屋さんが『そんなにほしかったらあげるよ』といってくださり、夢中になって実験したのを覚えている」といっておられて、この古本屋の主人みたいな人もいたのだなと思った。いい親、いい先生、いい近隣、みんなが機会をつくってくれていて、その中から自分の感性にあう生き方を見つけるのだろう。フランスのエリートをみていると、その環境を自らつくる努力をしていることに感動する。この素晴らしい実行力とその組織の見事さの成果を、できるだけ多くの子供たちが享受できるような環境が保障されれば、科学好きの子供たちがもっと増えるだろう。
今年は世界物理年、こういう活動を広げていけたら、とつくづく思う。 (2005年1月11日原稿受付)
嶺重 慎、小久保英一郎編
宇宙と生命の起源;ビッグバンから人類誕生まで
岩波書店、東京、 2004、 x+240 p。、 17×10。5 cm、本体 820 円(岩波ジュニア新書 477)[一般書]
佐藤文隆 〈甲南大理工〉
ビッバンから人類誕生までのストーリーが聞けるというはなかなか魅力的な企画・表題である。実態は宇宙や惑星の科学者が中心で生物と人類は付け足しである。学会誌の読者である研究者や教師にはこの話題で最近の各分野の動向を手短につかめる便利な本である。最近はジュニア新書の読者層に話をする機会も多いと思うが、そんなときには、自分の話のテーマに直接関係なくても、世間でポピュラーなこの話題での研究の現状を知っておく勉強用に便利であろう。講義や学会発表と違って、聴衆が熱心であるほど、どんな質問が飛び出すか分からない。
しかしこれで「ジュニア新書」が本来はターゲットにしている層に何が伝わるかを考えると気になる。編者も言うように「広い」から説明不足で更なる勉強の導入という言い訳は分かる。各章ごとに専門家が別々に書いているのだから、理科的に伝わることは多くは期待できない。「気になる」のはそのことではなく、この企画者が自覚症状もなく青少年に植え付けることになるあるイデオロギー、すなわち「はじめに」で編者が書いている、宇宙はビッグバンから始まり、「そのとき、みなさんも含めてこの世界のもとはすべてそこにあったのです」というものである。
私は研究のひとつの動機としてそういうシナリオを作ろうとするのはなかなか野心的でいいと思う。しかしこの本は様々な「起源」に関わる各学会分野の研究報告集である。構成や一部の文章に先走った言葉も散見されるが、内容を理解すれば、「野心」よりは「手堅い」もので、だから「便利」なのである。しかし理科的に理解しない人たちには看板だけが一人歩きする危惧がある。
評者は数多くの宇宙の一般書を書いてきたが、そこでは身近かな自然からだんだん、精神的に遠い、ビッグバンを導入する順番で研究の歴史を述べるようにした。ビッグバンのような全ての日常言語が誤解語である話から始めるのは適当でない。「身近に感じてはいけないもの」への感覚をスポイルするだけであると考えたからである。勿論、ビッグバンから説き起こす一般書も海外には多いし、読み物としては当然あっていい。様々な「思い」を科学を動員して紡ぎ出すことは科学研究とはまた別の創造活動である。残念ながらと言うか幸いにと言うか、この本はそういうものではない。
なお5 pの「フリードマンというお坊さん」は間違い。ル・メートルと混同。
(2005年1月24日原稿受付)
A. パイス著,杉山滋郎,伊藤伸子訳
物理学者たちの20世紀; ボーア,アインシュタイン,オッペンハイマーの思い出
朝日新聞社,東京,2004, 732 p., 19.5×13.5 cm, 本体3,800円[一般書]
小 林 てつ郎
本書はA. Pais, A Tale of Two Continents-A Physicist's Life in a Turbulent World, xvi+511 p., 1997の全訳である。パイスを科学史家として知る方も多いだろうが、もとは戦後ほどなくから1970年代まで、最先端で研究し続けてきた素粒子現象論の第一人者であった。 デヴュー論文 「凝集力場の理論」で、繰り込み理論の幕開けに導いた「坂田C中間子論」と独立に同じ問題に取り組んでいる。1950年代半ばには「K0 K0混合の理論」の優れた業績によってよく知られている。 訳書名が不適切と思われるが、これはパイスの自伝なのである。著者は「私が、 私が」流の自伝を嫌い、 自らは舞台の袖にあって、狂乱怒涛の20世紀の歴史を背景とする舞台上に自身と深く関わった巨人たちを登場させる。時宜に適って自らも劇中の人となり、物理学の進展と公私さまざまな人々との悲喜こもごもの出会いを語る壮大なドラマを演出して生涯を顧みる。700頁を超す長丁場も読者をして巻を措く能わざらしめる。登場するアインシュタイン、オッペンハイマー、パウリ、ディラック、ノイマン、サハロフ、ラビ、カザルス、ワイツマン(化学者、初代イスラエル大統領)、 パノフスキー (ピーフの父、美術史学者)等の名前を一瞥しただけで、豪華絢爛たる舞台が想像できよう。パイスはこれらの人々との深い人格的な交わりと緊張に満ちた知的交流を通して自らを語っている。また個人的な問題では、自らの内奥をさらけ出して率直に苦悩を訴え、あるいは身体中に溢れるような歓びを表している。その人間的誠実は読者に強い感動を呼び起こす。本書はおのずとパイスの歩みと重なる戦後30年の素粒子物理学の歴史の生きた証言でもある。 構成は、第1部(1-13章)「ヨーロッパ」、第2部(14-33章)「アメリカ」となっている。 パイスは1918年、アムステルダムでポルトガル系ユダヤ人を父とし、中東欧系ユダヤ人を母として生まれた。妹が一人。敬虔な「正統派ユダヤ教」の家庭であった。8、 9歳の頃、厳格な律法ゆえに信仰から離れるが「離散ユダヤ人」の強烈な自己認識は生涯変わらない。 アムステルダム大学を卒え、ユトレヒト大学のローゼンフェルトの下で博士号を得る。占領下ドイツの政策で、ユダヤ人に対して博士号授与を認める最終日1941年 7 月14日ぎりぎりの 7 月9日パイスは晴れて博士となった。 ほどなくユダヤ人収容所送りが始まる。パイスは地下に潜った。この苦しい孤独の中で研究を続け、読書にふける姿は胸を打つ。危険を察知する度に所を変えたが、遂に5回目の隠れ家で1945年 3 月初め、ゲシュタポに逮捕されて刑務所に送られる。 第1部の圧巻は処刑直前の釈放の場面である。隠れ家の手配をはじめ、パイスの潜行中の物心両面を支え続けていたのは、親しい女性の旧友ティネッケと彼女の母である。非ユダヤ人の彼女は死中に活を求めて、単身クラマースからハイゼンベルグ宛のパイス釈放に尽力を乞う手紙の控えを手に、ゲシュタポ高官を訪ねた。もし求められたら自分の身を差し出す覚悟で。彼は手紙を読み、助命嘆願を聞くと、直ぐ電話を取り「ユダヤ人パイスを釈放せよ」と命令したのである。ドイツ降伏の直前4月末の日のことであった。収容所で死んだ妹のことがトラウマとなって、戦後長い間パイスを苦しめる。 物理学者パイスのキャリアは1946年 1 月からのコペンハーゲン生活に始まる。ボーアと彼の家庭に温かく受け入れられて研究生活に入ることができた。文字通りボーアは以後パイスのよき師父として支え、励ましたのである。 「いつでも戻っておいで」というボーアの言葉を背に、パイスは1946年 9 月プリンストン高等研究所ポストドックとしてアメリカの土を踏んだ。1948年オッペンハイマーの高等研究所所長就任はパイスの運命を変えたのである。彼のパイスに対する信頼は絶大で、パイスも十分それに応え得た。所長の片腕として、自分の研究、世界中から選び抜かれて集ったbest and brightの若者の相手、時折訪れるボーア、ディラック、パウリらとの議論、国内外の会議、セミナーへの招聘等八面六臂の活動に精根を傾ける。その間には「オッペンハイマー事件」(23章)も抱えて。21、 24章を中心とする新粒子発見時代の条りは、同時代を経験した者には懐かしく臨場感溢れる記述である。ゲージ理論、QCDの時代はロックフェラー大学に移り、科学史に次第に深く関わっていく。 「二つの大陸」の含意は単純ではない。第一には勿論地理的概念であるが、読書家で広く深い人文学的教養を持つパイスである。最終章をBC 5世紀のピンダロスの詩「メネア」でしめくくっている心情を察するに、安手な「二つ」ではあり得ない。最終章に篭められた著者の21世紀への思いと共に、第二、第三の意味は読者への宿題であろう。 苦言を一つ。読みやすいが杜撰な翻訳である。専門書はともかく、概して一般書の翻訳について寛大に過ぎるところがないだろうか。とくに訳者の専門外のことに関しては、身近の専門家に質すのは当然であろう。本書にはその跡がない。柔らかい(非常に低エネルギーの、以下括弧内が正しい語)ガンマ線、 混合粒子(粒子混合)、 真空分(偏) 極、 飛跡のこぶ (折れ曲がり)、 接触を持つ変換群(一定位相を持つ変換群)、高次の項(高階微分)等々。これは一例。英文の誤読も少なくない。パウリやハイゼンベルグの没年を知れば間違うはずのない時制の誤訳には驚く。訳者の一人のようにアメリカ生活を知る者なら犯すはずのないと思われるミス、年号など原書の明らかなミスの未訂正等々。 但し 『ベニスの商人』 を 『オセロ』 と正したのはお手柄。ドイツ語の詩の訳も頼りない。僅かのドイツ語の中に2カ所も間違いがあっては困る。*1 敢えて公にして一般書の翻訳への注意を喚起したい。 (2004年12月28日原稿受付)
J. オグボーン,M. ホワイトハウス編,笠 耐,西川恭治,覧具博義監訳
アドバンシング物理;新しい物理入門
シュプリンガー・フェアラーク東京,東京,2004, vi+232 p., 27×19.5 cm, 本体3,500円[学部向・一般書]
佐 藤 博 彦 〈中大理工〉
夜空にあふれる街の灯りが天体現象の神秘に触れる機会を奪い、電子工学や情報工学の発展が時計やラジオなどの「原理がわかる」機械を次々とブラックボックスに変えていく。物理学の進歩が生んださまざまな技術により、子供たちが「物理」を感じる機会はかえって失われてはいないだろうか。子供たちにとって現在の物理の教科書は十分に魅力あるものだろうか。
「アドバンシング物理」は、英国の4分の1の高等学校で実際に使用されている教科書“Advancing Physics"の翻訳であり、原著を作り上げたのは、なんと英国の「物理学会」(Institute of Physics)である。実に1億円を超える予算と3年の歳月が費やされたことからも、初等、中等教育段階からの物理離れを学会が深刻な問題として受け止め、真剣に取り組んでいることがわかる。
章のタイトルを列挙すると、1.イメージング、 2.センサー、 3.信号を送る、 4.材料をテストする、 5.物質の内部を見る、 6.波の振る舞い、 7.量子的振る舞い、 8.空間と時間の地図を作る、9.次の運動を計算する、 となっている。物理の教科書としては大変「型破り」な章立てであるが、読み返すうちに、これは現代の高校生の興味の対象を分析し、十分な戦略のもとに意図されたものなのだと納得がいく。
最初に登場する図は、胎児の超音波像である。現代の子供たちは生まれる前から物理と無関係ではないことを伝えようとしているのかと深読みしてしまったが、ここでは測定の最も基本である「見る」ということについて考えさせるのが目的である。超音波の性質と画像処理の技術により、眼で見えないものを「見る」仕組みが丁寧に説明されている。他にも、ブラックボックスと思われていた身近な機器の仕組みを説き明かしながら物理の本質へと迫っていく。
本書では微積分を含む高度な数字はほとんど登場せず、むしろ丁寧なイラストや写真を用いて、直感的、視覚的に現象を深く理解できるように配慮されている。しかし、内容のレベルは決して低いとはいえない。特に7章では、ファインマンの経路積分の考えから量子論にアプローチしている。適切な指導がないと高校生がこれを理解するのは大変だろうが、量子計算機の実現性が高まる現在、これは最も適切な量子論の説明法かもしれない。
速度や加速度、運動方程式などの「定番」 の力学は 8 章以降でようやく登場する。比較的あっさり書かれているような印象を受けるが、以下に述べるようにこれはCD-ROM教材と併用することを前提としているからである。
現代の高校生は、当たり前のようにコンピュータに囲まれて生活している。この資源を用いない手はないだろう。「アドバンシング物理」 は、 原著に付属しているCD-ROM教材を用いることにより真価を発揮する。(残念ながら、CD-ROMの日本語版が出版される予定は今のところないようであるが、英語版を入手する方法は本書に載っている。)
CD-ROMには本書に書ききれなかった膨大な解説記事が含まれている。これを全部プリントアウトすると教科書の量をはるかに超える。また、付属のソフト “Modellus" では、 自分の入力した数式に従う物体の運動を画面の中で観察することができる。放物運動はなぜ2次関数に従うのか、ということを天下りの知識ではなく、試行錯誤しながら直感的、体験的に理解することができる。(もちろんこれはバーチャルな「体験」だが、現代の高校生は画面の中の現象を現実だと思い込むことはきっと得意だろう。)
さらに別のソフトは、パソコンをストレージオシロやスペクトラムアナライザに変えてしまう。自分の声や楽器などの音の波形やスペクトルを観察することにより、波動に関するさまざまな法則が手に取るようにわかるに違いない。家庭で手軽にこのような実験をすることは、十年前では考えられなかっただろう。
2000年に原著が出版されてから、日本国内では、「アドバンシング物理研究会」が発足し、一部の高校や大学の現場での実践の試みが行われてきた。本書は、研究会で用いる「資料」として監訳者および有志の高校教員が無償で翻訳を行ったものが元になっている。図書の仕上がりは美しく、ページも原著とほぼ完全に一対一に対応している。価格は原著とほとんど変わらない。これらは翻訳本としては異例のことであるが、関係者の熱意によるものだろう。
物理学を学ぶための動機付けという観点から考えると、本書は大学初年級向けの講義の教材としても十分に役立つと考えられる。また、新鮮な話題が多いので、一般向けの読み物としての面白さも多く含んでいる。
食わず嫌いのまま「物理」を学んでこなかった人たちが大勢を占める社会がやってきたとき、私たちは自らの存在意義を説明することができるだろうか? 専門に関係なくさまざまな立場の会員の方々に本書を読んでいただき、物理離れ対策に関する前向きな議論が大いに盛り上がっていくことを期待する。
(2004年9月27日原稿受付)
土井正男、滝本順一
物理仮想実験室
名古屋大学出版会、名古屋市、2004, vi+288 p., 21×15 cm, 本体4,200円[一般書]
山 崎 義 弘〈早大理工〉
古典力学、電磁気学、量子力学等の講義で勉強する物理現象を数値シミュレーションで再現することが、現在においては、いとも簡単に行われている。書店に行けば数多くの関連した書籍が並び、またインターネット上では、主にJavaを使ったリアルタイムシミュレーションができるHPもたくさんある。本書も、物理現象の数値シミュレーションに関する書であるが、他の書籍と一線を画す特徴がある。それは、この書で紹介されているGourmetというシミュレーション環境では、3次元空間の運動を、非常に簡単な手続きで再現でき、さらにアニメーションとして視覚化できる点である。実際利用してみると、プログラムを組んでいる時点では、視覚化やアニメーションの手続きに頭を悩ませる必要がほとんどなく、きわめて便利な環境であると感じた。Gourmetにおける使用言語は、Pythonであるが、CやJavaなどの言語に慣れ親しんでいれば抵抗なく受け入れられるであろう。本書には、物理の各分野における基本的な現象がプログラミングの例題として数多く取り上げられており、本書を購入して、インストールすればすぐに、例題となっている現象を再現することができるし、また、例題を修正することで、簡単に興味のある現象の3次元アニメーションを実行できる。本書は10章から構成されており、最初の3章で、Gourmetの紹介とPythonによるプログラミングの簡単な解説を行っている。第4章以降で、力学・電磁気学・波動・量子力学・統計力学・力学系の各分野における例題を取り扱っている。力学におけるコマの3次元空間での運動や電磁気学における電場・磁場の3次元表現、力学系におけるアトラクタなどが簡単に視覚化できるのは、やはり魅力的である。そして、第10章では大規模のシミュレーションをする際のGourmetの利用について簡単に述べている。最後に、実際利用してみて、いくつか気づいた点があるので、以下で紹介して書評を終わりにしたい。(1)評者は古典力学の講義中に何度か利用したが、パソコンのメモリが足りないからか、アニメーションを実行すると強制終了することが度々あった。 Gourmetの動作環境は192 MB以上となっているが、256 MBでも不足なのではないかと感じた。 (2) CやJavaなどの言語に慣れ親しんでいて既にシミュレーションを行ったことのある方にとっては、Gourmetを利用するよりも、 自らプログラムを組んだ方が手っ取り早いと感じられるかもしれない。 しかし、 Gour-
metを使えば3次元空間の現象を簡単に計算機上で再現できるので、問題としている現象に応じて使い分けるのが良いのではないだろうか。
(2004年7月13日原稿受付)
江沢 洋
物理は自由だ [1]力学(改訂版),[2]静電磁場の物理
日本評論社,東京,2004, [1] viii+290 p., [2] x+242 p., 25.5×18 cm, 本体[1] 2,900円,[2] 2,800円[学部向,一般書]
並 木 雅 俊 〈高千穂大〉
高校物理の教科書には、自由がない。「何か奥歯にものがはさまったような書き方」で、すっきりしない。そのうえ、学習指導要領等の制約のためなのか、読者と一緒になって考えようという姿勢がみられない。おそらく、ほとんどの方々はそう感じていたと思う。しかし、教科書だから面白くなくても仕方ない、と壁をつくりそれ以上追求することを止めてしまったのではなかろうか。著者はそう考えず、拘り、これを執筆の動機とし、この閉塞した状況から脱出を試みた。物理は自由でなくてはならない、と唱えて。
それに、 (高校では) 物理と数学を別物としており、微積分を使ってはいけないというところも気に入らない。翼は数学なのだから、こんなことでは自由に飛べない。
そのうえ何か急いでいる。そんなに急いで先に進んでしまっては、面白さが伝わってこないし、「わからないことは物理の宝」であることに気がつくこともできない。
『力学』 は、 12年前に初版がでて、 多くの方に愛され、今回改訂版がでた。この機会に誤植を正し、旧版にあった「座談会」を省いて、「読者からの手紙・著者の返事」が掲載されている。そこには、「これが読める高校生は日本全国で1、000人くらいはいるでしょうか。その他の百数十万人はどうしたらよいのでしょう」という中山正敏さんとの質疑応答や「本書のような自由な本を教科書にする学校があってよいわけですし、本書(と続編)をゆっくり勉強できたら大学の卒業証書を与えてくれてもいいのではないか」という戸田盛和さんの書評もある。
本書は、上記から察することができるように考えながら読む本である。物理という言葉を知ったばかりの、通常の高校生が読んですぐにわかる本ではないし、受験参考書とは似ても似つかぬ別物である。
『静電場』 だけで一冊の本である。「急がない自由」 が守られている。 一つひとつの記述から碩学の江沢さんの考えを学ぶことができ、実に面白い。高校/大学初年級の教科書にはない構成である。自由はここにもあった。ローレンツ力も、ビオ-サヴァールの法則も早々と登場させ、ルイス-トルーマン・パラドックスを論じる。初学のものにパラドックスを紹介すると混乱を生じる、とは考えず、「パラドックスは、これからの勉強のために貴重な財産だ」と捉えた。クーロンの法則と重ね合わせの原理は、史的説明、ファインマン流など様々な視点からの考察がある。「静電場の物理では、点電荷の間の力を与えるクーロンの法則を 『点電荷のつくる場』 の原因として捉えたものと 『場の重ね合わせの原理』 が基本である。他は、これから導かれる」で1本の筋が通され、すっきりしている。読後、何か利口になった気がした。爽やかである。
著者が対象とした、考えることの好きな生徒ばかりではなく、物理学の全体が見渡せなくなった時の本でもあり、書類書きの毎日を過ごす事務屋化してしまった大学人の頭をやわらかくし、物理屋に戻してくれる本でもある。『電磁場の動力学』、『相対論と量子論』、それに 『統計力学と物性論』 が続編である。楽しみである。
(2004年7月16日原稿受付)