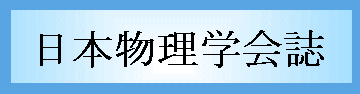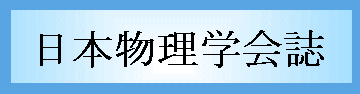このページでは、物理学会誌「新著紹介」の欄より、一部を紹介者のご了解の上で転載しています。
ただし、転載にあたって多少の変更が加わっている場合もあります。 また、価格等は掲載時のもので、変動があり得ます。
G. Gompper and M. Schick, ed.
Soft Matter; Volume 1: Polymer Melts and Mixtures, Volume 2: Complex Colloidal Suspensions
Wiley-VCH, Weinheim, 2005, Vol. 1: xi+285 p, Vol. 2: xiii+287 p, 24.5×17.5 cm, 各Vol. 119 EURO[大学院向・専門書]
Vol. 1 ISBN-10: 3-527-30500-9, ISBN-13: 978-3-527-30500-1
Vol. 2 ISBN-10: 3-527-31369-9, ISBN-13: 978-3-527-31369-3
川 勝 年 洋 〈東北大理物理〉
ここ数年の間に「ソフトマター物理」に関する入門書や教科書が続々と出版されるようになった。ソフトマターとは、高分子・コロイド・界面活性剤・液晶等の、従来の固体物理学の研究対象からはみ出したやわらかい物質群の総称であり、ソフトマターの研究は、これまで物理、化学、生物、工学等の非常に広い分野で並行して進められてきた。このような多岐にわたる研究分野の現状を把握するには、1冊の書物では到底不可能である。GompperとSchickの手による本シリーズは、 ソフトマターの各分野での第一線の研究者による基礎事項の解説と過去から現在までのその分野の研究のレビューを集めたシリーズである。このシリーズの目指すものは、臨界現象の分野で非常に成功を収めた 「Phase Transitions and Critical Phenomena」(Academic Press)のシリーズと同様のものである。本稿にて紹介する第1巻(高分子濃厚系)、第2巻(コロイド分散系)のほかに、現時点ではすでに第3巻(コロイド濃厚系の秩序現象)が出版されており、第4巻(膜構造関係)も近々出版される運びであると聞いている。
本シリーズの第1巻の内容は、高分子濃厚系の動力学の中性子散乱実験(Wischnewski と Richter)、 高分子の相分離現象の静的自己無撞着場理論の方法論の解説 (Matsen)、 および自己無撞着場理論と高分子鎖のモンテカルロ・シミュレーションをリンクする方法に関する解説(Mueller)である。一方の第2巻の内容は、棒状のコロイド粒子系の秩序構造の実験 (Dogic と Fraden)、高分子とコロイド混合系の場の理論(Eisenriegler)、 流動場の中の棒状コロイド粒子系の統計力学・流体力学理論(DhontとBriels)となっている。それぞれの章は、最初に初学者のための導入として理論的背景や実験手法の教科書的な説明が与えられ、その後に著者らの最新の研究を中心としたその分野の研究のレビューが述べられるという形式になっている。各章の難易度はかなりまちまちであり、特に後半部分では相当専門的でテクニカルな事項の解説を与えている章も多い。したがって、本シリーズは、この分野を初めて学ぶ大学院生や研究者が「ソフトマター物理学」を概観しようとする際の入門書としてよりも、研究テーマをある程度絞った段階で、その分野の研究の現状とテクニックを学ぶための指南書として非常に有用であると思う。
(2007年8月16日原稿受付)
ページの頭に戻る
福田誠治
競争やめたら学力世界一; フィンランド教育の成功
朝日新聞社,東京,2006, xii+250 p, 18×12.6 cm, 本体1,200円[一般書]
ISBN 4-02-259897-2, ISBN 978-4-02-259897-4
勝 木 渥 〈「科学と人間」研究庵〉
教育関係者の間で、いま、フィンランドの教育が熱い関心を呼んでいる。それはフィンランドが、経済協力開発機構 (OECD) が実施した 2 度の国際学力調査(PISA)でトップクラスの成績を上げ、いまや「学力世界一」と目されているからである。では、フィンランドの教育の特徴はどこにあるのか。
著者は1950年生まれ、東大教育学研究科博士課程を修了、現在都留文化大文学部比較文化学科の教授であるが、2005年に足繁くフィンランドを訪れ、実際の教育現場の視察・見学、教育関係者との率直・詳細・執拗な質問・討論を通して、フィンランドの教育の姿を明晰かつ具体的に把握して、それを本書で紹介した。
本書は 《5頁の序・五つの章(1~5)・7頁の跋・14頁にわたる註・12頁にわたる「近年の学力問題史年表」》 からなっている。
1。「PISAの測った学力」(分量39頁)では、PISAを含むこれまで行われた国際学力調査を簡単に概観した後に、特にPISAの学力調査がやや詳しく説明されている。すなわち、国別・地域別平均得点の国際比較のデータの提示、例示した四つの設問のねらいの説明・各設問への回答の国際比較、総合的読解力・数学的リテラシーにおける習熟度レベル別割合の国際比較等。そして、PISAが学力調査とともに行った生活実態調査とも関連づけつつ、学力調査のすべてにわたって高い成績を示したフィンランドに注目する旨が述べられている。
2。「世界一の秘密」(分量61頁)では、フィンランドの教育制度と、その基礎にある教育理念、それの確立に至る歴史的過程が詳述されている。その教育方法論の中心にあるのは、異質生徒集団と社会構成主義学習ということであり、その特徴は①平等教育、②自ら学ぶことが教育の基本、③教師が働きやすい職場、④権利としての教育を包みこんだ福祉としての教育という点にある。
このような教育理念と制度の確立には30年に及ぶ歴史的営為の蓄積があった。すなわち、1960年代から1970年代にかけて北欧諸国で福祉国家の概念が確立され、それの具現化としての教育行政が志向された。フィンランドでは1972年に分岐型教育制度(11歳で進学向きと就職向きに教育内容を分ける)が廃止され、総合制学校へ転換されたが、習熟度別クラス編成は残存した。この校内選別は、これに反対する教師たちによって1972年から82年にかけて徐々に廃止されていき、1985年に、完全廃止された。反対の理由は、低学力クラスが主として低い社会的経済的背景を持つ男子生徒で構成され、社会的経済的格差を反映したものとなっていることにあった。
3。「フィンランドの子どもたちはなぜよく学ぶか」(分量25頁)と、4。「フィンランドの教育背景」(分量55頁)では、子供のいる現場--教室や図書館や地域--で、教育活動がどのように行われているかが、たくさんのスナップ写真も添えて詳しく報告されており、読者が実際の教育の様相を具体的に思い描くことができるものとなっている。
上のフィンランド教育の理念と状況は、日本の戦後初期の新教育運動と相通ずるものがあるように感ぜられる。新教育運動は1958年学習指導要領が官報に掲載されて法的拘束力を持つようになってから、やがて終息してしまった。
5。「世界標準の学力に向けて」(分量35頁)ではPISAの理念を通じて見られる教育観についての、最近の国際的な動向が詳しく説明されている。学力調査で明らかにしようとしているものは、生徒が身につけた知識の量ではなく、社会に出て使える力、実践的能力(コンピテンシー、competency、 competencies)であるが、このコンピテンシーという概念について、いろいろな面からの解説を試みている。
日本の社会的通念とは大いにかけ離れたフィンランドの教育理念(これはPISAの理念と相通じている)・教育制度であるが、日本の教育の体質改善のための貴重な示唆を与えてくれる。物理教育・科学教育あるいは教育一般に関心を持つ会員の必読文献の一つとして推奨したい。
(2007年2月13日原稿受付)
ページの頭に戻る
五家建夫
宇宙環境リスク事典
丸善出版サービスセンター,東京,2006, vi+194 p, 21×15 cm, 本体2,095円[大学院向]
ISBN 4-89630-206-0
浅 井 佳 子 〈情報通信研究機構〉
本書の題名にある「宇宙」という語は、和英辞書に記載されるuniverse、 cosmos に続く 3 番目の space に相当し、地球大気圏の外側にある空間を示す。「宇宙環境」 という語は、 我々が日常生活を営む地上とは全く異質で非日常的な空間である宇宙を人類活動の場として捉えた新語で、標準の和英辞書にはまだ載っていないが、space environmentと英訳する。宇宙で起こる現象は、真空や微小重力等よく知られた特徴に起因するものだけではない。宇宙が厳密には真空でないために起こる現象として、希薄な大気や宇宙に充満する荷電粒子に起因する現象がある。地球磁場や太陽活動に影響されるプラズマや放射線は、宇宙機の本体や精密部品に作用して機器故障や動作異常の原因となる上、人体など生命体へも影響する。これら自然現象の他、人為的現象である宇宙ゴミ(デブリ)による衛星破砕などの被害も深刻である。
本書は、苛酷な宇宙環境で起こる自然現象や人為的現象、それらに起因する宇宙機搭載機器への影響、宇宙飛行士への影響までを網羅している。著者がリスク(危険)管理の観点からまとめたと書いているとおり、宇宙環境リスクと呼べる諸事象とその要因を丁寧に解説しているため、内容は宇宙環境の科学書に比べて工学的かつ実用的である。競争的な技術開発に伴って機器性能が年々向上しており、その一方で、機能向上による新たな障害が発生しているという。宇宙開発では、プロジェクト経費が大きいためリスク管理は重要課題である。宇宙開発はまさに現代のフロンティア最前線なのだと、本書を読んで実感できる。
著者は、 旧宇宙開発事業団(NASDA)、 現在の独立行政法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)にて、 長年人工衛星の開発に携わり、多々ある衛星障害の中でも帯電現象の研究において、日本国内の第一人者である。本書は、宇宙開発の現場で百戦練磨してきた著者の集大成ともいえる。出版年の昨年は、人類初の人工衛星の打上げからちょうど半世紀である。今日では衛星放送をはじめとして実用衛星利用が日常生活にすっかり定着している。本書は、題名通りに宇宙環境でのリスク事象を列挙しつつ、コンパクトにまとめ上げているので、「宇宙space」に興味ひかれる者にとっては読本としても面白い。ただし、本文内には単語対応の索引がないため、 「事典」 として機能しにくいのが、本書の一つ残念な点である。近い将来、日進月歩する宇宙開発研究の最新情報を加えながら内容が研鑽され、名実ともに「事典」として活用できる形に再版されることを望む。
(2007年7月31日原稿受付)
ページの頭に戻る
レオナルド・サスキンド著; 林田陽子訳
宇宙のランドスケープ
日経BP, 東京,2006, 546 p, 19×13.5 cm, 本体2,200円[一般書]
ISBN 4-8222-8252-X, ISBN 978-4-8222-8252-3
須 藤 靖 〈東大院理物理〉
宇宙論で最近話題となっているキーワードは? と問われれば、個人的には、 ダークエネルギー(宇宙定数)、 ブレインワールド、余剰次元、人間原理、マルチバース、あたりを挙げることになる。私は素粒子論にはおそろしく疎いのであるが、それでも、ひも理論、Dブレーン、 カラビ・ヤオ多様体、 ランドスケープ、などという言葉は頻繁に耳にすることが多い。この本は、ひも理論のランドスケープという言葉の生みの親であるサスキンドが、それを軸として、上述の素粒子論と宇宙論の最新の話題について解説した優れた啓蒙書である。
本書の主張の要旨はこうだ。ひも理論は 10500 個もの異なる極小値を持つよ
うな複雑な地形(ランドスケープ)を持つ。この谷底の一つ一つが、独自の物理法則と自然定数を備えた宇宙として実在する。それらが総体としてメガバース(著者はmultiverseという単語の響きが気に入らず、あえてmegaverseという言葉を使うというメモを最終ページに付け加えている)をなし、我々の存在する universe は、 10500 個もの気の遠くなるような数の中から知的生命の存在を可能とするような奇跡的な条件を満たした具体例である。このひも理論のランドスケープこそ、これまで単なる哲学的意味しかもたなかった人間原理が実際に機能することを保証する。と同時に、自然に予想される大きさの120桁以下しかない(にもかかわらず0ではない)ダークエネルギー(宇宙定数)の大きさの不自然さを解消してくれる。
人間原理は好き嫌いがはっきり分かれる考え方である。本書では、宇宙のランドスケープという発見によって、 物理学者が、それまでごく一部の宇宙論研究者だけしか考えていなかった人間原理を認めるようになった、と解釈できるような記述があるが、それは事実に反している。*1 素粒子論研究者*2は人間原理を忌み嫌うことが多い(多かった)のは事実である。一方、宇宙論研究者の間では、人間原理は以前よりかなり受け入れられた考え方であったといえる。
この本の主張自体は決して著者のオリジナルなものではない。しかし素粒子論の専門家で ありながら、最先端の難しいテーマをわかりやすく説明する著者の筆力にはただただ驚嘆するのみだ。この類の啓蒙書の場合、自分が良く知っている事柄については、「あまりにも陳腐な説明だなあ」、「こんな面白みにかける言い方しかできないものか」という批判的な思いばかり募り、不愉快になることが常である。しかし、この本は、おもわずなるほど、と感じさせられる明快な説明が散りばめられている。また、全編に優れたユーモアのセンスが満ちあふれている点も読後感を爽快にさせてくれる理由でもある。例えば、 「計算結果と実験結果が、 1桁違うのは不運、2桁は災難、3桁は恥」、「一般相対論が物理学の美しさコンテストで優勝するとしたら、一番醜い賞はXXX物理学が受けるべきだ」、*3「宇宙の終末は熱い死と冷たい死のどちらになるのかと3人の若い宣教師に尋ねると、彼らはすべて私次第だと言った」、「ひも理論家と違って、宇宙論者はたいていエレガンス-唯一性という病気に感染しない」など、楽しい表現がてんこ盛りである。
さて全く個人的な話で恐縮だが、本書を読んで最も驚いた(がっかりした)ことに長岡半太郎の切手が図として掲載されていた。とある理由で長岡モデルを自分の研究発表のイントロとして紹介することが多いのだが、外国では長岡半太郎は全く知られていないことに衝撃を受けた。このため、拙著*4に彼の切手と原論文の最初のページを掲載し、密かに自慢していたのである。*5 本書には「長岡半太郎のことは最近日本人の友人から教えられた」という記述があるので、本会会員のどなたかが著者に教えたのではあるまいか。
後半やや脱線気味となったことをお詫びしつつ、学部学生から研究者まで、分野には関係なく自信を持ってお勧めできる啓蒙書であると結論して終わりとしたい。
(2007年8月16日原稿受付)
ページの頭に戻る
上坪宏道,太田俊明
シンクロトロン放射光
岩波書店,東京,2005, viii+98 p, 19×13 cm, 本体1,470円(岩波講座 物理の世界 ものを見るとらえる6)[大学院向]
ISBN 4-00-011182-5; 978-4-00-011182-9
澤 博 〈KEK物構研〉
本書は、シンクロトロン放射光研究の全体像を見通せるように、取り上げたトピックスについて必要最小限の記述にとどめる代わりに、全体を大変コンパクトに書かれている。シンクロトロン放射光を利用したことがない人には、どんなことができるのかを平易に紹介してあることから、入門書的な性格の著書と位置づけられるが、下記のような理由で放射光ユーザーにも一度は手に取って頂く価値があるのではないだろうか。
実験的物理学の基本の一つは再現性である。現代のように、手法が細分化され装置の性能が格段に上がってくると、再現実験による検証が困難となってくる。本書で取り上げているシンクロトロン放射光はある意味で夢の光であり、研究者は他の手段では得ることが難しい、質的に異なる測定結果を得ることができる。したがって、その成果は絶大な影響力を持つといっても過言ではない。この観点から、放射光を利用する研究者は、その発表データの信頼性を十分検討したうえで解釈・発表を行う必要があることは、改めていうまでもない。放射光分野の研究者にとって本書は自分自身の研究手法について書かれている部分だけを読むと、物足りない感想を抱くかもしれない。しかし、一方でこのような研究者が専門分野以外の事象について十分な知識を持っているとは限らない。専門化した特定の測定方法にとらわれて、複数の手法での検証を行うことがおろそかになっている例も見受けられる。放射光ユーザーの方は、放射光利用の全体像に対して本書のような情報を持って研究に臨む必要があるのではないであろうか。
本書の構成では、放射光の発生、反射・屈折、散乱・回折、吸収・分光を原理から具体例を交えた応用まで述べている。さらに、最後には近い将来建設される自由電子レーザーについても書かれている。放射光は波長が変えられる極めて強い光であり、さらに偏光度も制御できる点で通常の X 線源とは全く異なった性質であることが、様々な分野にとって重要な情報を提供してきた。しかるに、この光はアンジュレーターと呼ばれる装置からの光でさえ準単色光に過ぎず、カオス光と呼ばれる。日本の計画しているこの自由電子レーザーの発する光は、波長が0。1 nm以下、輝度がSPring-8の108の完全コヒーレンス光で、実に数百フェムト秒のパルス光である。この新しい光はあまりに特殊で現在の放射光のすべての分野に適用できるわけではないが、一方で全く新しい観測技術が提案されることも想像に難くない。新しい手法開発が今後積極的に行われるであろうタイミングで、現状の放射光利用を概観し、さらに将来の新しい手法開発や物理概念の展開に思いをはせるのもまた一興ではないであろうか。
(2007年6月27日原稿受付)
ページの頭に戻る
K. Becker, M. Becker and J. H. Schwarz
String Theory and M-Theory -A Modern Introduction-
Cambridge Univ. Press, 2007, xvi+739 p, 24.8×17.6 cm, £45.00[大学院向・専門書]
ISBN-13978-0-521-86069-7 ISBN-100-521-86069-5
米 谷 民 明 〈東京大学院総文〉
まず、著者らを紹介しておこう。二人のBeckerは、ドイツ出身で90年代中盤のポストドク時代からアメリカで活躍している双子姉妹研究者。一方、Schwarzは、言うまでもなく、弦理論の草創期から中心的な役割を果たし続けてきた最も代表的な人物である。
弦理論の教科書としては、87年に出版されたGreen-Schwarz-Wittenの2巻本が、長年にわたってほとんど唯一の包括的な解説として大きな役割を果たしてきた。 98年には、 Polchinski の 2 巻本が出て、GSWに代わる役割を担ってきた。90年代後半は弦理論の「第2次革命」と呼ばれる目覚ましい展開がなされた時期で、現在もその波が続き、これまでの発展を取り入れた新しいタイプの本が望まれるのだが、本書はこうした要望をかなり満たす充実した内容を備えている。本書の特長としてはそれに加えて、弦理論を効率的に学びできるだけ早く最先端の話題を理解し研究に進むのに役立つ速習コース的な工夫もされている点を挙げることができる。
1 Introductionでは、歴史にも触れながら、重要な概念あるいはキーワードを説明し、それらがどの章で取り上げられるかという概観を与える。そして、2 The bosonic string から 7 The heterotic stringまでは、90年代半ばまでにほぼ確立された弦理論の大要が述べられる。8 M-theory and string dualityから11 Black holes in string theory、 12 Gauge theory/string theory dualitiesに至る、 後半約 2/3 (400 ページを超える)は、よりトピックス的ないくつかの話題が、ごく最近の発展を取り入れつつ丁寧に解説されている。各節の記述は、だいたい最初の数ページで、基本概念を説明した後に、Exercise、 Solutionという仕方で、具体的な性質を計算しながら進む。これは初学者にとっては親しみやすく、輪講ゼミ等で読み進めるには好都合な形式だろう。各章の終わりには、Homework problemsがあるが、その解答は専用Web pageに用意されていて、読者は必要に応じて参照できるように配慮されている。
取り上げる話題が広範囲にわたっているので、テーマによっては多少物足りないと感じる部分もあるのはやむを得ないが、全般的にはこれだけの内容をよくここまで盛り込み、読みやすい形に仕上げたものと思う。欲を言うと、この種の「教科書」としては望み過ぎかもしれないが、参考文献がもう少し充実しているとさらに役立つ本になっただろう。いずれにしても、ここ数年相次いで弦理論に関係した専門書・教科書が出版されている中でも、本書は最も標準的なものであって、弦理論、特にその最近の発展に興味を持つすべての人に推薦できる。
(2007年7月24日原稿受付)
ページの頭に戻る
橋本幸士
Dブレーン; 超弦理論の高次元物体が描く世界像
東京大学出版会,東京,2006, ix+206 p, 21×14.8 cm, 本体2,400円(UT Physics 2)[学部向]
ISBN 4-13-064101-8; 978-4-13-064101-2
鈴 木 久 男 〈北大理〉
超弦理論にあこがれる学生は多い。これは相対性理論にあこがれる延長上のことであろう。ところで、相対性理論については、私が学生時代の頃よりも教授法が発達し、ずいぶん勉強しやすくなっている。現在、大学1年生レベルで、本格的な特殊相対性理論は十分学べるし、がんばれば一般相対性理論まで学習が可能だ。一方、超弦理論というとそうはいかない。実際、素粒子論の学生でも、超弦理論の勉強には修士1年をついやすくらいの年季が必要なのである。修士は、将棋で言えば奨励会と同様であり、ここで脱落していく学生は少なくない。したがって、本格的な教科書は、素粒子論プロ養成用の本という位置づけとなる。一方で、世の中にはそこまでして勉強したくないという大多数の物理ファンが圧倒的に多い。そのため、こうした層のためには、本格的に勉強しなくても、ある程度超弦理論を楽しむ本が必要となる。また、こうしたファン、あるいは知っておきたいという人は学会員の中にもいるだろう。
ところが、ファンのための本というのは元来非常に難しい。それは、弦理論の意味を正確に理解するためには、分厚い教科書のような記述が必要となってしまうからである。このため、学部生レベルでは、完全にわからないのが当然であり、それでもわかったつもりとなる必要がある。しかも、曖昧ながらもわかるために、十分なイメージとともに他の類似のものが必要であるが、新しいものには必ずしも類似品が見つかるとは限らない。このため、より正確を期して数学を多くすると、物理よりも数学に気を取られすぎることになる。学部学生レベルの本は、その専門用語と数学の使用のさじ加減が非常に難しいのである。新しい概念をわからせるには、わかった人にとっては無駄となる部分が必要なのである。
さて、今回紹介する本についてみてみよう。 この本は、 Dブレーンについての最近の発展までをまとめた本である。 とはいえ、 このDブレーンと言われても何かわからない読者もおられることかと思うので以下に簡単にまとめてみよう。
弦理論は、輪ゴム型や、輪ゴムを切り開いた形をした弦が振動し、この弦が基本粒子とみるという理論である。たとえば、弦が一方方向に伸び縮みしておりその端にプラスとマイナスの電荷がついていると振動により電場と磁場が変動する。この弦が伝播したものが、光子であり、光に偏光方向があることが、弦の振動で説明できる。これが弦理論の基本的なアイデアである。また重力子は二つの偏光方向を持つがこれも輪ゴムのような弦の振動として説明ができる。このような見方は、弦が単体で安定な状態での記述であるが、この弦が絶えず分裂や融合を繰り返すときにどのように見えるのであろうか? 1995年頃、弦同士の結合が強いと、弦の複合状態として、膜などの次元が高い物体が素励起状態として重要となることが明らかになってきた。そのような膜(membrane)には弦の端が束縛され、膜以外の方向には、固定端すなわち、 ディリクレ (Dirichlet) 境界条件となることから、そのような物体は D ブレーンと呼ばれている。 そして、最近10年間くらいの超弦理論の発展はこのDブレーンが中心であったといっ
てもよいだろう。
紹介する本書の構成は、大まかには D ブレーンそのものの説明に関係するパートとその応用とに別れている。とりあえず本を開いてみると、まず本全体のまとめの章から始まる。これは、大変よい判断である。読んでいてどこに連れて行かれるかわからないと不安に感じる読者に対する配慮であろう。
それでは前半を読んでみる。この本ではソリトンの記述から入っている。ブレーン自身の理解にはその類似物でイメージをつかむのが理解の早道となる。そのため、本書ではブレーンの説明の前に、ソリトンの解説が有用であるという賢明な判断をしている。ただし、最初に出てくる例は、場の理論を学んでいない学生には何をやっているのか理解するのは難しい。もっともこれは学部生を念頭においてのことであるので、この紙面を読んでいる学会員なら問題なく読めるはずだ。
次に、読み進めるにつれ、読者が最も気になると思われるのが、前半の3章の D ブレーンの説明まででは、 専門用語の説明が多くなり、1回読むくらいでは覚えきれなくなることだろう。この本では何回か読めば覚えられるくらいまでに専門用語は削られている。ただし、これはあくまで本格的な専門書との比較の問題であることをあらかじめことわっておこう。専門用語に慣れることが本書を読む上で特に重要な要素である。その反面、この本だけの説明で本当に専門用語がわかるかと言うと実はわからない部分も多い。したがって、本書を読むとき、あまり深く考えずにイメージ優先で第3章まで適当に読むのが賢明だろう。実際、イメージできない専門用語は、後半を読むのにそれほど必要ではないので、わからないことを深刻に考えなくても十分である。
さて、第4章までブレーンの基本的性質を説明した後、ブレーンワールド、インフレーション、ブラックホールのエントロピー、そしてQCDとの関係についての説明が続く。特にこの第5章以降の説明から筆者の語り口が実に良くなっていく。もちろんそれは、内容そのものに迫力があることにも起因している。全体の流れも軽快である。本書を気楽に読むつもりなら、最初から第5章以降だけ読んでいっても良いと思う。まず5章以降を読んでから、もう一度最初から読み、必要専門用語をそこそこ理解するように努めたるのが一つの手だ。最初のまとめの章も読みやすくなる。
さてようやく最終章にたどりついた。この最後の章では、 現状の D ブレーンの問題点を列挙している。 今、 Dブレーンの完全な量子化あるいはその完全な記述法がわかっていない。そのため、現在までにわかっていることは非常に限られたことである。それでも真実らしき片鱗が見えているというのがこの本の後半の主な内容だったわけだ。特に素人向けの本では、超弦理論を誇大に宣伝する傾向があるが、これは本の売れ行きを良くするためにある程度は仕方がない。一方、この本では、現状の弦理論の欠点を正確に指摘して、その中立性を保っている。このことは、これからの学部学生の教育のために非常に重要なことである。それは問題点の指摘により、やる気のある学生は、マニア的な勉強意欲でなく、新たに作り出したいという研究意欲をかき立てられることになるからである。この本により、学部生が超弦理論により感心を持ち、将来独創的なアイデアをもたらす一助となることを期待したい。
この本は、 Dブレーンの最近までの発展を非常に良くまとめてある良書であるので、学会員が気軽に読むのに適していると言える。
(2007年2月1日原稿受付)
ページの頭に戻る
I. Herbut
A Modern Approach to Critical Phenomena
Cambridge Univ. Press, 2007, xi+210 p, £35.00, US$65.00[学部・大学院向]
ISBN-13 978-0-521-85452-8 ISBN-10 0-521-85452-0
小野田繁樹 〈理研〉
学部レベルの熱統計力学、量子力学、固体物理学などの基礎的理解があれば、短期間で集中的に読破できる凝縮系物理学の理論の教科書である。著者が2005年に東工大で集中講義を担当された期間にまとめられたようである。極めて理路整然としており、物性理論を志す学部4年生から大学院生には打って付けであろう。短いながらに、物理学の基礎的概念である秩序変数や自発的対称性の破れと、これを扱う理論的手法(平均場理論から繰り込み群に基づく相転移の臨界現象の理論まで)を、数学的に丁寧に解説している。Ginzburg-Landau-Wilson paradigm の本質を理解するだけでなく、相転移における topological defect の重要性を垣間見ることもできる。
相転移、秩序変数、平均場理論、臨界現象とスケーリング則の導入的説明に始まり、 Ginzburg-Landau-Wilsonの有効場の理論に基づいた繰り込み群の綿密な解説が展開される。次章のU(1)ゲージ場と結合した超伝導転移の理論も、他書には見られないほど丁寧に記述されている。さらに、空間次元を下げ、下部臨界次元での非線形σ模型による解析、XY模型におけるKosterlitz-Thouless転移と渦糸自由度を解説し、読者の関心をtopological defectへと誘う。Heisenberg模型におけるスカーミオン励起にも触れている数少ない教科書の一つでもある。XY模型と格子QEDの双対性、 そして、Bose Hubbard模型に対する超流動絶縁体転移と量子相転移の解説で幕を閉じる。いくつかのレビュー論文を除けば、本書ほど数式を追いやすいように数学的にも懇切丁寧に記述した教科書は見つけ難い。 特に、 φ4模型やボーズ・ハバード模型における量子相転移については、実際の計算を最も親切に説明している教科書といっても過言ではない。
極めて短い紙面で、読者を近年の物性理論の研究の前線へ誘う分、当然そぎ落としている部分も少なくない。ランダム系、液晶についての記述はないし、量子相転移についてのトピックも極めて限られている。これらは他書で補う必要があろう。
兎にも角にも、本書は相転移と臨界現象の研究の面白さを初学者に短期間で伝えるという観点で、極めて優れた教科書である。読者に理解の具合を確認させるため、教育的な演習問題と略解を提示することにも抜かりがない。クセのない、飽きのこない一冊である。
(2007年7月30日原稿受付)
ページの頭に戻る
末崎幸生
脂質膜の物理
九州大学出版会,福岡市,2007, vi+152 p, 21.5×15 cm, 本体4,200円[学部・大学院向]ISBN 4-87378-927-3; 978-4-87378-927-9
谷 口 貴 志 〈山形大工〉
ふと立ち寄った本屋で、タイトルが目に飛び込んできたのが本書「脂質膜の物理」であった。近年、ソフトマター関連の本がいくつか出版されているが、 「脂質膜」 という用語が直接タイトルに入った物理の教科書を今まで見かけたことがなかったからである。この本で扱っている脂質膜、広い意味で、両親媒性分子(一つの分子内に、親水部と疎水部を有する分子)の系の物理というとあまり馴染みがない読者も多いと思うが、この分野はコロイド界面科学として非常に歴史の古い分野である。このような系は、日常の身の回りのありとあらゆるところで見かける。例えば、洗剤、化粧品、マヨネーズなど、また、生物の基本構造である細胞膜の系もそうである。
さて本書であるが、脂質分子が織り成す多様な現象を統計物理学の観点から取り扱っている本である。コロイド界面科学(化学)としては、既に多くの教科書があるが、「この両親媒性分子を含む系の示す多様で複雑な性質を、何故?、どんなメカニズムで、といった物理的な言葉や思考で理解しようとするとき、あまり適当なテキストが見つからない」と著者が「はしがき」の中で述べているように、評者も物理を学ぶ者として今までの本は現象の扱いや説明がしっくりこないものが多いと感じていた。本書は、首尾一貫して統計物理学による扱いで現象を説明することに注力しており、この点においても、また、コロイド界面科学の本としてもユニークな存在であるといえる。本書は、 7 章から構成されている。 1 章で、脂質分子が水溶液中や水の表面で示す多様な会合構造や表面(吸着、ラングミューア)単分子膜について概観し、表面圧力と表面張力の概念と、表面張力の様々な測定法について述べている。2章では、吸着単分子膜を統計物理的に解析し、その熱力学的関係式の導出が行われている。第3章では、まずミセルの会合形成を熱力学的に扱い、臨界ミセル濃度の導出、その後に脂質二重膜が作るベシクルの安定性について議論している。3章の後半では、著者がユタ大学医学部で関わった麻酔薬と脂質膜との相互作用について書かれている。「麻酔を物理で」というと、物理で扱うには複雑すぎる現象ではないかと思われるのではないかと思う。評者もそう思いながら読み進めていたが、麻酔作用は膜の主転移(固体膜-液膜)の温度を下げるという現象と相関がある(つまり、物理化学現象として扱える)ことが具体的な例を挙げながら詳しく説明され、麻薬物質の違いによる転移の様相の違いが統計物理を使ってうまく説明されるところは非常に面白く時間を忘れて読めた。4章は、膜の電気的特性として、膜の電気抵抗、イオン選択性膜の平衡電位などについて述べられている。5章は、膜の形態を記述する曲げ弾性エネルギーについて、詳しく述べられている。なかでも著者が疑問を持ち、その値に関して長年議論してきたサドル曲げ弾性定数については、詳しくその意味と弾性論との関係、 Petrov の理論モデルによる導出等が書かれている。その結果に関して、 この分野の著名な研究者であるWeizmann研究所のサフラン氏との論争の話は興味深い。膜の形態に関するもう一つの内容として、Pearling不安定性の話が述べられている。6章では、膜系の相転移を扱う理論モデルと数値計算に関する内容が述べられている。7章では新しい話題として著者による研究から、ベシクルにタンパク物質(タリン)を添加したときの膜面上での孔の形成とカップ状ベシクルへの変形をタリン分子の膜への吸着平衡を統計物理的に解き議論している。また、脂質と胆汁酸混合系、膜電位をコントロールすることにより膜を変形させるFlexso-electric効果、多成分脂質膜のラフト構造について述べられている。
本書全体を通して、著者が長年の研究の中で扱った系の話が各章の内容に合わせて折り込んであり、そこでの論争や著者が疑問に思ったこと、また研究に対する姿勢までが読み取れて最後まで飽きさせない内容であった。また、両親媒性分子が呈する多様な現象には未解決の問題が多く、それらが著者の観点から各章の随所で述べられている。この分野の研究者のみならず膜や界面科学の分野を学ぼうとする物理の院生にお薦めしたい一冊である。
(2007年7月4日原稿受付)
ページの頭に戻る
斯波弘行
基礎の固体物理学
培風館,東京,2007, vii+261 p, 21.5×15.5 cm, 本体3,600円[学部・大学院向]ISBN 978-4-563-02272-3
齋藤理一郎 〈東北大院理〉
本書は、 物理学会 JPSJ の編集長として改革に手腕を発揮された斯波先生による、学部大学院向けの固体物理の教科書である。膠着した状況から問題点を抽出、改革に向け誰の目にも明快な解を示し実行するのは、先生の美学であろう。その美学が教科書になった。
固体物理の教科書を著すのは、容易ではない。範囲が広く、現在でも急成長の分野であるからである。基礎は残さねばならぬ、新しい物理を入れたい、本を厚くすることはできぬ、執筆のまとまった時間が取れない、という膠着した状況の中で、爽やかな風のように明快な教科書を執筆されることは俗人の及ばぬところである。
本書の内容は、原子の電子状態から固体へのつながり、固体の電子状態、伝導電子の物性、半導体、固体の光学的性質、磁性、超伝導と250頁の本の中に見事に固体物理のテーマ約50が入っている。吟味されたおかずがコンパクトに並ぶ、料亭の会席弁当のようである。この本を重箱の隅まで読み、式の導出を含め勉強してくれれば、大学院の修士の学生が持つ知識として十分である。加えて式の意味を考えるのであれば、本書だけで読者は本の著者が望むレベルまで達することができよう。これにさらに付け加えるとすれば、本書の各テーマと実験との接点を理解することであろう。先生の美学は、実験との接点をあえて選択しなかったようである。
電子状態の説明でカーボンナノチューブの電子状態を取り入れたのは、『固体物理の生きた教材だから(まえがきより)』 であり、 大変興味深い。 R。 Saito の図も使われている。 書評者も実は教科書の題材としてナノチューブを狙っていて、ネタを取られてしまった感じも否めない。金属と半導体のどちらかのナノチューブができる話では、エッセンスだけが見事に抽出されている。ここのみならず、著者によって各項目が十分に吟味されていることが、各式に対する注意点として散見することからわかる。 このあたりが、 Web検索で得られるところの情報と本質的に違うところで、授業や教科書が単に情報を伝える媒体ではないぞ、という主張を聞くようで、大いに共感するところである。情報の氾濫する社会での、『教科書で考える価値』はますます高まるばかりである。
書きたいことを書き、売れる本を作ることは至難の業である。良書の本質は、やはり時間をかけて吟味しまとめ上げることに尽きる。訳書が中心であった固体物理学の教科書も、これから日本の著者による特徴ある教科書が多く出て、選択する時代に突入したといえる。
(2007年7月6日原稿受付)
ページの頭に戻る
光物性研究会組織委員会編
光物性の基礎と応用
オプトロニクス社,東京,2006, xvii+411 p, 21×14.8 cm, 7,140円[大学院向・専門書]
井 上 純 一 〈物質・材料研究機構〉
『光物性の基礎と応用』 (以下, 本書)の表題に含まれる “光物性” 分野は,光と物質の相互作用を研究対象とし,日本物理学会では主に領域5が該当する.しかし,光物性は現象も物質も限定しないことから,これと何らかの接点を持つ研究領域も多い.したがって,光物性に属する項目をコンパクトにまとめた書の需要は高いと想像される.
光物性の広範を詳細に扱った良書に 『光物性ハンドブック』(朝倉書店)がある.刊行は1984年であり,先達の目を持ってしてもその後の発展を予想できなかった項目もあるなどして,「光の世紀」(本書序文)と位置づけられた今世紀的視点から見ると,残念ながらというか喜ばしいというか,加筆・改訂が望まれる箇所も出てきた.そこで本書に21世紀版光物性ハンドブック的役割を期待するのだが,さて.
本書は月刊オプトロニクス誌の連載を単行本化したものである.各章10~15ページからなる全25章はそれぞれ独立した内容で,一話完結型になっている.各回ごとに執筆者が異なる連載をまとめた書物で懸念される事柄に,全体の一貫性がある.そのような観点から本書を眺めてみよう.まず,術語の不統一などが若干見られるものの,章間の相互参照はおおむね良好である.詳細な索引が付されるなど,連載のコピーを束ねただけのものにはない内容的付加価値が加えられており,単行本化の意義は十分にある.しかしながら,本書の生い立ちを反映してか,各章のスタンスは大きく異なっている.その章が扱う内容にも依存するのであろうが,例えば,該当項目全般のバランスのとれたレビューになっている章あり,実際に実験する場を想像させるような臨場感あふれる記述で,通常の文献ではなかなかお目にかかれないtipsを含む章あり,執筆者の主宰する研究室紹介に相当する章ありと,光物性らしくスペクトルは非常に広い.本書が想定する「それぞれの分野を学びたい人には良い入門書となり,関連分野の研究者には有益なレビュー」(本書序文)となることは,章によっては前者,章によっては後者,という状況になっている.
しかし,広範な題材の現状を手軽に把握できることは非常に貴重である.分量的な制限もあり,今世紀版ハンドブックとまではいかないものの,光物性分野の生き生きとした状況を伝えるには十分な内容になっている.この意味で, 『光物性ハンドブック』 とは相補的な関係にあると言え,すでに十分な知識と経験をお持ちの研究者の方も一読されることを勧める.また,価格を考えると購入を気軽に勧めることには若干の躊躇があるが,光に少しでも関係する研究分野の大学院生の方々で,興味と知識のスペクトルを広げたいと考える向きには本書が適している.
(2007年6月27日原稿受付)
ページの頭に戻る
M. Palevsky
Atomic Fragments-A Daughter's Questions
Univ. of California Press, Berkeley, 2000, xiv+289 p, 23.6×16 cm, 34.95 US弗[一般書]
市 川 芳 彦
湯川先生,朝永先生の生誕100年を記念していろいろな催しが実施されているこの頃,親しく先生たちの謦咳に接することのできた私たちの世代と,間接的に両先生の教えに触れる世代を結ぶ絆を強めるには如何したらよいのだろうか,などという思いに捉えられながら,この半世紀の出来事に思いをめぐらせていた時,編集部からこの本についての紹介を依頼された.2000年の出版であるから,新著紹介の枠からははみ出しているけれど,日本の中でほとんど知られていないこの本を物理学会誌に紹介することは意味があることと考えお引き受けした.
著者の父,ハーリー・パレヴスキーは,ロスアラモス研究所における原子爆弾開発マンハッタン計画に若いエンジニアーとして参加し,戦後核物理学の学位をとりブルックへヴンの研究所に勤めた.彼が亡くなる間際まで拘り続けていた原子爆弾のヒロシマ,ナガサキへの投下についての疑念を,マンハッタン計画に従事した当事者との対話を通して明らかにしたい,という思いを「娘からの質問」という副題に込めたこの本は,彼女の世代が,父たちの世代の人々の声を聞き,後の世代へ語り継ぐユニークな役割を果たしている.
序章で著者自身の生い立ち,母と父への思い,特に父が持っていた原子爆弾開発に参加したという屈折した心情を父からの遺産として受け止め,1994年12月,ハンス・べーテに会おうと決意する経緯を述べる.第1章,ハンス・A・べーテ,副題のTough Doveは「ローズ夫人は私のことをハト派だというけれど,私は頑固なハト派だ」とクスクス笑ったべーテ自身の言葉である.べーテとの対談の後,次に誰の話を聞いたら良いかアドヴァイスを求めた著者は,テラーの名前を告げられ,リベラルな立場をとる自分が果たしてどのような対談を実行できるだろうかと感じた当惑を正直に書き綴る.第2章 エドワード・テラー,物理学の祭司長.第3章 フィリップ・モリソン,歴史の目撃者.第4章 デヴィッド・ホーキンス,ロスアラモスの年代記編者.第5章 ロバート・ウイルソン,物理学者のプシュケ.第6章 ジョセフ・ロートブラット,パグウォッシュの草分け.第7章 ハーバート・ヨーク,内側の物語.と綴られる対話をたどりながら,各章の終わりに記されている著者の覚書は,これらの対話で語られた言葉を反芻し内省するなかで,彼女の心の中に湧き上がる波打つ思いを伝え,評者の胸をゆさぶる.
最後の章,エピローグの最後のページ.1995年8月6日,サンタ・バーバラで開かれたヒロシマの50周年平和集会でステラ・マツダの千羽鶴の踊りが舞われ,参加者が詩を朗読する.原子爆弾についての一日中の熱心な討論に疲れた著者の心をよぎった思いを,「私は知りたい, お母さん, 私は知りたい,お父さん,私たちは又,お会いできるのかしら?」と語りながら,すすり泣いた著者に,集まりが終わったあと,インドから参加した一人の紳士が近づいてきて「家族をそんなにも愛しているアメリカ人を発見して嬉しい」,「多くのインド人は,アメリカ人は両親を敬わないと思っているけれど,そうではないことを知って嬉しい,」と彼は語った,という言葉で終わる.
各章の終わりには,補足説明として118項目245行の覚書を補い,約240編に及ぶ引用文献リストを基にして書き上げられたこの本に込められた著者の思いを,限られたページで伝えることはできないが,一つだけ評者が幾度か読み返している箇所をここに記しておきたい.
エドワード・テラーはワシントンで水爆の開発をアピールして,ロスアラモス研究所に対してリヴァモア研究所を創設することに成功したが,その初代所長に任命されたハーバート・ヨークとの対談で,日本が唯一の被爆国として, 「ヒロシマを繰り返さない」 と主張し,訴えることに対して,それは「A-bomb nationalism」であるという批判があることについて,著者が質問している.それに対するヨークの答えをここに記す字数の余裕はないが,パグウォッシュ会議にも参加している彼の考えについては,ヨーク自身の著書
Making Weapons, Talking Peace; New York, Basic Book, 1987
Race to Oblivion, a Participant's View of the Arms Race, New York, Simon & Schuster, 1970
等を注意深く読む必要があると思う.
ロートブラットとパグウォッシュ会議のことについて著者が語り合っている第6章で,ハーリー・パレヴスキーが1958年オーストリア,キッツビューへルで開かれたパグウォッシュ会議に参加したときの,小川岩男さん,クリシュナン,トンプソンなどとの写真が貴重な映像として,評者の目をとらえたことも書き記しておこう.
ロートブラットも2005年8月31日に亡くなり,この本の対談者として生存するのはヨーク一人となった今,改めて聞き語りの手法により時代の証言を体系化した著者の偉業に深い敬意を表してこの稿を終える.
終わりにこの本を評者に貸与してくださった土江真樹子 元 名古屋テレビ・ディレクターに謝意を表したい.
(2007年6月26日原稿受付)
ページの頭に戻る
ステファニア・マウリチ著; 沢田昭二監訳,高田 愛訳
1つの爆弾 10の人生
新日本出版社,東京,2007, 230 p, 19.5×13.5 cm, 本体2,400円[一般書]
市 川 芳 彦
イタリアの新進科学ジャーナリスト,ステファニア・マウリチが2004年ミラノの出版社から刊行して2005年Citta di Cecina賞を受賞した「Una bomba, dieci storiel」の翻訳が今年2月に出版された.マンハッタン計画,ヒロシマ・ナガサキへの原爆投下,ソ連の原爆開発,水爆実験,から核不拡散条約,北朝鮮の核実験に至るこの60年に及ぶ一連の流れの中で,これらの問題に関わった当事者たちの直接の声を記録しておこうという企てが起きるのは当然であろう. 「娘からの質問」 という形で展開されたパレヴスキー女史の数年に及ぶ努力はAtomic Fragmentsという著書に結実しているが,このマウリチ女史の著書は,ヨーロッパという舞台でそのような聞き取り調査を進めているという意味で,非常に貴重な労作であり,今回日本語に翻訳されたことは,喜ばしいことである.
第1部で60ページを割いて著者は「原爆の歴史のあらまし」を述べているが, 本書の題名, 「1つの爆弾」に関するドイツ,イタリア,デンマーク,イギリス,フランスにおける核物理学者の動きを克明にたどり,アメリカを主舞台として展開される原爆開発の背景をジャーナリストとしての視点から明らかにしようと密度の高い論考を展開する.
ワイツゼッカー,べーテ,ロートブラット,等との対話を記録している第2部「10の人生」が本書の中心であるが,評者は本書を読んで初めて知った事柄が少なくないことを告白しなければならない.
ドイツでの原爆開発の状況,特にハイゼンベルクの役割などについてK. F.フォン・ワイツゼッカーの話(第1話)を聞いた後,ボーアが米国を訪問した際の逸話などについて,物理学の長老ハンス・べーテに聞く(第2話).ポーランドからイギリスに出張している間にヒトラーのポーランド侵攻が始まり,帰国できなくなったロートブラットは「私は亡命ポーランド人ではない」とパレヴスキー女史に語っているが,ロスアラモス研究所のマンハッタン計画から離脱して,後にパグウォッシュ会議の活動に献身する彼は,核廃絶では十分でない,戦争自体を廃絶する必要がある,と主張している(第3話).広島の廃墟を最初に訪れたアメリカ人の一人モリソンは,マッカーシズムの狂気の中で冷戦の平和的解決を主張し続けた(第4話).
べーテ,モリソン,ロートブラットの3人に対する「聞き語り」については,パレヴスキーとの対話による記述と比較してじっくりと読み比べてみることに評者は強い興味をそそられる.しかし,本書の特徴は,ワイツゼッカー,コーエン,沢田,ホール夫妻,サグデイエーフなどとの対話が記録されていることであろう.
サム・コーヱンは,中性子爆弾の開発に従事し,ヴェトナム戦争で中性子爆弾を使用していれば米国は敗退することはなかった,と主張している物理学者であることを,評者は本書によって初めて知ったことを告白しておきたい.評者は,この14ページの短い第5話の部分だけでも,このように考えている人物が現実にいるのだということを知るためにも,是非目を通して欲しいと思う.第6話,被爆者としての沢田昭二との対話については,評者は率直に著者マウリチの質問が十分に練られていないと言いたい.この点については,沢田自身が監訳者としての前書きに被爆体験を持つ物理学者の責任について書き記している言葉を逆にイタリア語の原著に反映して欲しいと思う.しかし,第7話; ホール夫妻についての記述には評者は衝撃を受けた.ソ連の原子爆弾開発に関連して,評者はローゼンバーグ夫妻,フックスなどのスパイ行為などについては聞いていたが,本書で「テッド・ホールがソ連最初の原爆の製造を手助けした人物である」という文章を読んで改めて事の真実を明らかにすることの難しさを知った.この項目ではテッドの夫人が2003年4月にイギリス・ケンブリッジで書き下ろしたメモが20ページ余りに綴られている.第8話のサグデイエフとの対話については,評者がプラズマ・核融合分野での日本とソ連邦の間の共同研究の推進の現場で親しく交流し,ソ連崩壊後,アメリカで会うことのあったサグデイエフの言葉として,とりわけ強い感慨を禁じえない.水爆の開発に従事し,国防問題でケネデイからクリントン政権までの多くの政権で顧問を務めている政府の当事者としてのR.ガーウインとの第9話,最後に第10話で,マンハッタン計画における女性たちの活動についてオーククリッジ研究所に勤めていたエレン・ウィーバーとの対話が記されている.ここで交わされている対話の意味については,原爆とかマンハッタン計画など,特定のプロジェクトにおける問題としてよりも,もっと広い視点から検討されるべきであろう.
一つだけ,フィリップ・モリソンの項目で,モリソンがハンス・べーテ賞を「道理に基づいて発言するまともな人びとが勝利できるという,一貫し,かつ影響力ある信念を貫いた」功績に対して受賞したという記述があるが,彼が受賞したのは,何か別の名称の賞ではないかという疑問が残るということを注意しておきたい.
予定の字数を相当に超えてしまったので,改めて本書を読み直してみた.いろいろな箇所に,読んでいてこの主張はこれでいいのか? そうなのか?と気にかかる言葉が浮かび上がってくる.この本を何人かの仲間たちと読みながら,討議を深めることができれば,核廃絶,恒久平和への道を具体化する力になるのではなかろうか?
(2007年6月26日原稿受付)
ページの頭に戻る
佐藤文隆
異色と意外の科学者列伝
岩波書店,東京,2007, viii+130+4 p, 18×13 cm, 本体1,200円(岩波科学ライブラリー127)[一般書]
川 合 葉 子
物理学や数学が大学で重視されなかった時代に,科学で業績を上げた人々はどういう職業でその研究を支えていたのだろうか.それはその個人が生きた時代の制度にかかわると本書の著者は考える.コペルニクスで始まるこの列伝の人選びはこういう目線で行われた.コペルニクスは僧職についていたし,フラウンホーファーはガラス工場の技術者であり,メビウスは天文台長であった.
近代科学の成立史を知っていれば,こういう経歴は意外ではない.しかし,昔もいまと同じ制度の下で研究をしていたと錯覚している現代の科学者が多いと,著者は心配する.そこで第2章では,電磁気の単位に名前を残しているヴォルタ,オーム,ファラデー,テスラなどの異色な経歴とその時代の制度とのからみを紹介している.著者の文章は読みやすい.しかも小見出し一つで時代や場所の設定が変わる.話がわき道にそれるのも元に戻るのも自在である.私たちは突然1927年コモ湖畔で開かれたヴォルタ没後100年記念の国際会議に立ち会わされる.そこで夏の学校の歴史を教えられるのである.
第3章は制度そのものが主題である.まず,「ドイツ純粋数学の勃興」.ナポレオン軍による侵略の後,プロシアでは国家統一を目指す啓蒙運動が起こった.教育改革が運動の中心にすえられ,ギムナジウムなどの中等教育で数学が必修科目になった.多数の数学専門教師が必要となり,その養成機関として,大学でも数学は独立した教科となり,教授が置かれた.数学の専門職集団ができ,研究も熱心に行われ,投稿論文の掲載誌の発行もこの時期に始まったという. 支えた運動は新人文主義,「改革のテーマは人間としての自己の自立であった」と著者は紹介している.
ついで 「理論物理学者の起源」. ここではケンブリッジ大学の数学トライパス試験をめぐる社会の反応と,国づくりを意識した人材養成大学の嚆矢としてのベルリン大学の創設が欧米社会に与えたインパクトを取り上げる.大学の制度と社会的地位が変わってきた中で理論を専業とする,例えばプランクのような物理学者が現れるようになったと著者は言う.章の最後にイギリス物理学会の伝統を転換させたラザフォードを取り上げている.
第4章では著者がこだわりを持つ3人の大物科学者に焦点を当てている.その一人目がロード・ケルヴィン,すなわちウィリアム・トムソンである.旧第三高等学校以来保存されて京都大学に引き継がれた物理機器の中に,トムソンのパテントで製造された「反射検流計」が存在していたことから話が始まっている.
この物理機器の調査は私たちのグループが行ったもので,私たちの著書の出版には著者の後押しが大きな力となっており,本書でも参考文献に入れていただいている.深謝の他はない.しかし本書の99ページの引用は正確でないので,この機会に訂正をさせていただきたい.
トムソン反射検流計の元の記述は「タムソン氏レフレクチングガルバノメートル」,刻印は「ELLIOTT BROS LONDON No1016」であった. 本書に紹介された刻印は,同時に購入された「トムソングレーデッド電流計」に対するものである.また「ガルバノメトリー」は電流測定法という意味になり,機器の名前にはならない.著者が極めて忙しい日程の中で書き下ろしたのが本書であり,そのための誤りであろうと思う.
「科学と国家」 を副題とした第 4 章で,著者が最も力を入れたのはオッペンハイマーであろうと思う.残念ながらそこに言及する余裕がない.
著者はなぜそれほどまでに制度にこだわるのか.それは著者が歴任してきた役職から見えてきた科学と,あるいは科学者と社会とのかかわりにある種の危機感を感じているからのようである.それを著者は科学が直面している「転換期」 と表現している. その認識から歴史を振り返ったとき,それぞれの転換期に直面した科学者なり,その群像があった.本書はこれらの科学者の物語を綴ったものである.著者はその豊かな国際交流の経験を土台にして,科学者と社会とのかかわりを「制度」の問題に限定したために,叙述に緊張感を持たせることに成功し,興味深い物語になっている.多くの方に読んでいただきたいものである.
(2007年7月2日原稿受付)
ページの頭に戻る
吉田善章
新版 応用のための関数解析; その考え方と技法
サイエンス社, 東京, 2006, ix+235 p, 21×15 cm, 本体 1,900 円 (SGC Books M2) [一般書・大学院向]
及 川 正 行 〈九大応力研〉
本書は、関数解析を実際に使った仕事を行っている著者が、関数解析の理論を現実的な問題と結びつけて解説することを目的として書かれたものである。想定されている読者は学部高学年から大学院生というところである。関数解析というと、線形代数の無限次元への拡張、フーリエ解析、量子力学の数学的枠組み等々に関係して関心を持つ学生も多いであろう。数学科では基礎科目の1つとして当然カリキュラムに組み込まれているであろうが、他の学科や工学部では関数解析がカリキュラムに組み込まれることはまれであろう。したがって、自分で本を読んだり、輪講したりして勉強することになる。私自身も、リュステルニク-ソボレフの 「関数解析入門」 や加藤敏夫の 「位相解析」などを輪講した。しかし、使わないと忘れてしまうもので、本書を読む際にもスムースに理解できないことが多々あった。本書は230頁の中に、基礎的事柄(第2章「空間と位相」、第3章「作用素」)から実際に使われる場面(第4章「関数空間と微分方程式」、第5章「ベクトル場の理論」、 第6章「非線形問題」)までを盛り込んでいる。そのため、基礎的事柄の題材は第4章以降で必要となるものにかなり絞られている。 また、「定理の結果を知ることより、証明の道筋や技法にこそ学ぶべきものが多い」という著者の考えから基本的な定理の証明はほとんど与えられているが、全体的な記述の仕方は丹念に積み上げるやりかたとは違う。ルベーグ積分も説明なしに使われている(このあたりは初心者は加藤敏夫の「位相解析」あたりで補うと良いかもしれない)。 その代わり、 第 1 章で関数解析ではどういうことが問題になるのか、どこが難しいのかといったことが語られているし、定理の説明にしても意味や位置づけを解説してくれている。これらは私にはかなり有益であった。初めて関数解析を学ぼうとする人に本書を薦めようとは思わない。本書は関数解析の基礎的な事柄を一通り学んで、関数解析を応用してみたいと考えている人には一読の価値があるであろう。実際に応用する場面でどういう定理や性質が利用されるのかが具体的に示されているからである。こうした点は通常の関数解析の教科書には見られない本書の特色である。 また、 第 4~6 章の内容自体が有益だと感じられる読者も多いと想像される。私にはベクトル場のポテンシャルによる表現可能性やHamilton力学系と保存則などは特に有用であった。最近、藤田 宏「理論から応用への関数解析」岩波書店(2007)、 岡本 久・中村 周「関数解析」 岩波書店 (2006) が出版されている。私は中身を見ていないが、これらもそれぞれ期待できそうである。
(2007年5月28日原稿受付)
ページの頭に戻る
S. R.ワート著; 増田耕一,熊井ひろ美訳
温暖化の 〈発見〉 とは何か
みすず書房,東京,2005, 262+xxi p., 18×12.8 cm, 本体2,800円[学部向・一般書]
矢 吹 哲 夫 〈酪農学園大環境システム〉
この新著紹介を書いている最中IPCC(気候変動に関する政府間パネル)第4次報告が出され、今世紀中の地球気温の上昇予測値について第3次報告より厳しい値が示された。また、温暖化の原因が人為起源の温室効果ガスの増加とほぼ断定された。しかし、一方で地球温暖化の定説に対する根強い慎重論が科学者の間にあることも事実である。
本書の著者であるスペンサー・R・ワートは、1942年に生まれ、1968年に物理学と宇宙物理学で博士号を取得し、その後1971年から科学史の分野に転向したという経歴の持ち主である。本書は、 この著者が物理学者として “真理” を追究する同じ眼差しで地球温暖化の歴史を綴ったものである。本書に登場する研究者の数はざっと数え上げただけで92人に上るが、著者は特に中心的役割を果たした研究者に多くの紙面を割くということはせず、気候変動の解明に努力した人々に平等にスポットをあてようという姿勢を貫いている。著者自身巻末で「気候変化の科学における最重要論文のうちほぼ1、000編の間で点と点をつなぐことを試みた。」と述べていることも頷ける。その際特に印象的なのは、著者自身が「気候変化の物語は様々な物語が平行して進んでいる。」と語っているように、気候変化に対するたくさんの研究者たちまたは研究グループの事実解明の努力を巧みな遠近法を用いながら浮かび上がらせていくその筆の運びである。そのため、時には事象の記述が時間的順序に従っていないこともあり、始めは読者も戸惑いを覚えるかもしれないが、すぐに時間的順序より論理的順序を尊重するという著者の意図を理解するだろう。このことが、本書を平板な事実の列挙とは一味違った読みごたえのある “温暖化” の科学史にしている。
本書で語られる物語の始まりは、第1章の「気候はいかにして変わりうるのか?」で示されている。それは、地球規模の巨大な気候変化が何万年単位の時間スケールで生じるという「斉一説」と、短期間の劇的変化の形で生じうるという「天変地異説」の対峙である。物語開始当初は前者が支配的であり、よほど大きな動因が働かない限り気候の大きな変化は生じないという “安定性信仰” が 『自然の巨大な力の中であまりにも弱々しい人類の活動が、地球全体を支配しているつりあいを乱すことができるとは、ほとんど誰も想像できなかった。』 と著者に書かせている。しかし物語が進んでいく中で、この “安定性信仰” は多くの研究者たちの独立した研究努力の中で揺らぎ始め、気候の破局的変化が生じうるという “不安定性の脅威” へとって代わられていく。気象現象が本質的に非線形現象であることに由来する気候の劇的変化の可能性への認識について、その認識に至る多くの議論と発見の歴史が、本書の第3章 「微妙なシステム」、 第4章「目に見える脅威」、第6章「気まぐれな獣」の中で詳細に述べられている。その中には、ローレンツによる気象現象に潜む “カオス” の発見も含まれている。このような物語の大筋の中で、例えば気候学に物理学の基本法則を導入したロスビーや気候モデルの構築に貢献した真鍋淑郎博士の理論的努力と、大気中のCO2濃度の持続的上昇の裏づけを初めて与えたキーリングの観測的努力を交叉させながら、異分野にまたがる 『67カ国の数千人の科学者が参加した協調努力』(第2章「可能性を発見」)を描き出す。
著者は多くの説を真偽判定の俎板に載せたまま、次々と話題を転じていく。本書のこのような描き方は、物理学会員にとっては科学的に慎重な姿勢として好感を持てるものであろうが、同時にこの本の指し示す「温暖化の発見」の結末が未完のまま終章を迎えるのではないかという予感を脳裏によぎらせる。実際に、最終章である第8章の「発見の立証」の冒頭で著者は、『出来事の説明が現時点に近づくにつれて、それは歴史とは呼べなくなっていき、他の何かに似てくる-それはジャーナリズムかもしれない。』 と述べ、さらに 『この最終章は下書きのようなものでしかありえないということに用心してほしい。』 と読者に注意を喚起している。その上で、しかし著者は一つの結末に向かって足早に進んでいく。終章で「人為起源の温室効果ガスが原因で地球温暖化が進んでいる可能性が高い。」 という IPCC の第 3 次報告に一気に収斂していく展開には、それまで科学者としての慎重な筆の進め方に好感を覚えつつ忍耐強くついていった一読者として若干の戸惑いを禁じえなかった。
しかし、 巻末の 「本文を振り返って」で著者自身が述べている次の二つの記述には、改めて本書全体を貫く著者の姿勢として共感を覚えた。一つは、『科学者が確かな知識を追求する際に必要な原則は、①意見の相違に耐えて公の議論の場であらゆる合理的な主張の発言を認めること。②たとえ他の点について意見が一致しないことに同意していても、重要な点については意見の一致を求めて徹底的に話し合うこと。』 である。もう一つは、『気候の場合、確実な答を待つことは永遠に待つことを意味する。新たな病気や武装侵略に直面したときは、さらに多くの研究が終わるまで決断が延ばされることはない。利用できる最善の指針を用いて行動を起こすものだ。』 である。
結論として、本書は地球温暖化を巡る科学的議論を公平に一望できる好個の書であることは間違いないので、是非一読されることをお薦めする。
(2007年2月15日原稿受付)
ページの頭に戻る
大沢文夫
飄々楽学; 新しい学問はこうして生まれつづける
白日社,東京,2005, 346 p, 19.5×13.5 cm, 本体2,400円[一般書]
田 中 晋 平 〈広大総合科学〉
この本は日本の生物物理学の創始者の一人である物理学者大沢文夫氏の60年間にわたる研究の流れを本人が随筆風に記したものである。日本に限らず世界において、いわゆる「コロイド」の物理が注目されているが、著者はコロイド粒子間相互作用の重要なメカニズムの一つ、 いわゆる「Asakura-Oosawa potential」の発見者である。本書によるとこれは著者のごく初期(1950年代) の仕事であると同時に、 その後の大沢流理論において常に意識される「ミクロな相状態間の相互作用」仮定の先駆けであった。さらにその後書かれた著書「Polyelectrolytes」はまさにこの精神の結晶であり、高分子電解質の複雑な現象を、目に見える形でモデル化して議論した名著である。現在のコロイド物理学はこれらの理論無くしては語れず、著者の先行性には驚きを禁じ得ない。
本書は主には著者の研究とその周辺の生物物理学の発展の経緯を述べたものである。このような超一流の研究者の成功談を読んでも、例えば筆者のような駆け出しの凡夫には応用のしようもない。しかし、よく読むと随所に後進を励ます言葉やアドバイスがちりばめられている。曰く「何を質問すべきか、質問そのものを発見することが大事であり、それには何年もかかる」、「わからなくてやみくもに取ったデータから科学としての奥行きが生じる」、「研究を急いで評価してはいけない」等々。本書後半以降では、生物の「階層性」、「ゆらぎ」、「自発」や「状態論」等、今後の生物物理の向かう方向に対する本質的な議論と提案が多くなされている。本書全体にわたって具体的な研究テーマも多く提案されており、これらの提案に鋭く反応できる読者の方もたくさん居られようと思う。
(2007年2月6日原稿受付)
ページの頭に戻る
須藤 靖
ものの大きさ; 自然の階層・宇宙の階層
東京大学出版会, 東京, 2006, ix+182 p, 21×14.8 cm, 本体 2,520 円 (UT Physics)[一般書・学部向]
早 田 次 郎 〈京大院理〉
この本は、物理学の魅力を分かりやすく伝えるために企画された「UT Physics」シリーズの第1巻である。著者の話のうまさはよく知っているつもりであったが、挿話や薀蓄を交えながら展開される話の面白さには改めて感心させられた。物理「学」の楽しみを教えてくれる好著である。
「学」 の楽しみにも階層がある。 素数2、 3、 5、 7、 11、 13、…という無味乾燥にも思える数字の羅列にロマンを感じる人もいれば、リーマン予想のような深い真理に魅せられる人もいる。これら一見無関係な素数とリーマン予想の関係は、より神秘的であり、それを知る楽しみは絶大である。本書で語られる、微視的世界と宇宙の階層にも似た楽しみがある。物理の話となると、数字に長さや重さの単位がついて俗っぽくなりはするが、その代わり、そこには具体的な「もの」と結びつく力強さがある。それぞれの階層に存在する「ものの大きさ」は鑑賞に値する。そして、一見無関係に思える様々な「ものの大きさ」が物理法則によって深く結び付けられるさまは神秘的でさえある。これが本書の核となる部分だ。
宇宙の物質組成が物理学と精密観測の成果として語られる部分では、地上には存在しないダークエネルギーが宇宙のほとんどを占めているという不思議な事実が強調されている。微視的世界の常識が宇宙スケールでは通用しないというのだ。背後にはどんな神秘が隠されているのだろうかと想像せずにはいられない。
第6章で解説されている人間原理もまた数の神秘のひとつの側面である。もっとも、個人的には人間原理はあまり感心しないが。この本の付録の薀蓄は大好きである。落語にでも出てきそうな「不可説不可説転」が何を意味するかを知りたい方は是非、付録を見ていただきたい。
本書の特徴は、網羅的、辞書的なというよりは、じっくり味合うことに重きを置いている点であろう。また、本書と類書の違いは題材の選択の差にもある。特に、系外惑星に関する部分は興味深い。
岡潔は春宵十話の中で「よく人から数学をやって何になるのかと聞かれるが、私は春の野に咲くスミレはただスミレらしく咲いているだけでいいと思っている。・(中略)・私についていえば、ただ数学を学ぶ喜びを食べて生きているというだけである」と言い切る。数学を物理学(窮理学?)に置き換えれば、著者の「科学する心」の主張と重なる。本書は多くの人に楽しんでいただきたい1冊である。
(2007年1月9日原稿受付)
ページの頭に戻る
J. T. Blackmore, R. Itagaki, S. Tanaka, ed.
Ernst Mach's Science; Its Character and Influence on Einstein and
Others
Tokai Univ. Press, Hadano, 2006, 304 p, \6,500[一般書]
伏 見 譲 〈埼玉大院理工〉
マッハは19世紀後半から20世紀初頭にかけてプラハとウィーンで活躍した実験物理学者・科学哲学者・感覚生理学者・物理学教育者である。音速を単位とする速さマッハ数で一般に知られているが、物理学界では、ニュートン力学を根底において批判した著作で有名で、その批判はアインシュタインの一般相対性理論を先導した。また、レーニンが「唯物論と経験批判論」を書いてマッハ哲学の浸透を防止しようとしたほどマッハの認識論は影響力があったことも知られている。本書は、マッハの哲学ではなく、広範な科学研究とその学界への影響に焦点を当て、紹介し批判した論文集である。マッハと同時代の論文から、現代の視点で回顧した論文まである。編集者による書き下ろし論文も多く、マッハの科学研究の全体像とその現代的位置づけが理解できるようになっている。近年日本ではマッハに関する研究が哲学者廣松渉の先導で盛んであるが、まとまった単行本が発行されるのは初めてのことである。英語圏のマッハ研究の第一人者で親日家の Blackmore が編集者に参加し、英文で発行された。日本の読者には少し不便だが、グローバリゼーションの当然の結果であろう。
衝撃波の研究を中心とする実験物理学の章はvon Karmanの論文をはじめとして迫力がある。衝撃波の音源として電気スパークを利用してタイミングを制御し、また高速飛行物体の衝撃波をシュリーレン法で可視化した瞬間写真で解析してその本質を解明した。現在に通ずる可視化技術の開拓者であり、超音速ジェット機や原爆の衝撃波で半世紀後にその物理の偉大さが再確認された。研究用装置も創るが、講義用のデモ実験装置も創る。講義を真剣に行うことは物理の基礎を自ら再検証することであり、この態度が、古典力学の根底的批判につながったと思われる。J。 D。 Norton「マッハの原理」の章は、アインシュタインが定義したマッハの原理と、マッハが実際に述べたこととの食い違いの科学史的解説で興味深い。ニュートンが絶対空間を想定したとき援用した回転するバケツの水の実験を、相対性で解釈するための宇宙論的原理の解説である。
マッハがW。パウリの名づけ親だったというようなゴシップ記事も多く、読みやすい。ちなみに、マッハ・ツェンダー干渉計は息子で医者のルドビッヒ・マッハの発明であり、彼が如何に親孝行者であったかが描かれている。マッハの作った実験装置の図が多数載っているが、残念なことに説明不足で、マッハの創意が物理学徒の読者に伝わらない。学者の肖像写真も多数載っていて興味深いが、ガリレオを2ページも載せるなど編集が少し散漫である。
(2007年1月9日原稿受付)
ページの頭に戻る
スティーブン・ワインバーグ著; 本間三郎訳
新版 電子と原子核の発見
筑摩書房,東京,2006, 429 p, 15×10.5 cm, 1,500円(ちくま学芸文庫)[一般書]
村 田 次 郎〈立教大理〉
本書は、専門の科学者以外の教養人が教科書的な学習の試練に耐え抜く必要なく、自分たちの時代における画期的な科学上のアイデアや発見について知りたいであろう、という仮定で書かれた20世紀前半の物理学に関する非常に正確な啓蒙書である。内容はワインバーグが数学や物理学の教育を受けていない学生を対象に行った講義をもとにしているため、表現が婉曲すぎて一見入門的という印象を受ける。しかし私は、本書は決して入門書ではなく極めて良質の本来の意味での啓蒙書であると考えている。
1986年に本書の旧版が日経サイエンス社から出版されており、今回は文庫化に合わせて2003年の新版原書からの翻訳となっている。原書および旧版は、上質紙に高品位の美しい写真がふんだんに使われたハードカバーの書物である。初版から20年を経て、今回ようやく文庫化された意味は大きいと考えられる。繰り返しになるが本書は決して物理を目指す学生のための入門書ではなく、一般の知識人が「科学の基礎知識が不足しているために、文化の偉大な部分から切り捨てられているということは、一種の悲劇でさえあると思う。」 というワインバーグの強い危機感のもとに書かれたものであり、物理の学生だけが手に取るのでは本来の意味をなさないからである。
一方で、旧版とともに本書の翻訳をされた本間三郎先生は訳者あとがきに、一般の人のみならず自然科学関係の学者や研究者にもぜひ読んでもらいたい、それぞれのレベルのそれぞれの期待に決してそむかないことを約束できる、と述べられている。全く同感である。我々研究者は多くの場合、すでに確立した知識として教科書に書かれた内容の発見当時の歴史的事実に疎い。著者ワインバーグ自身も講義を始めた頃、20世紀の物理学についてわずかな知識しか持っていなかった、と述べている。本書は現場に居合わせた人が、その時点でどの程度の知識まで持っており、どのような現象に出合ってどう考えたのか、という物語で構成されている。また、トムソンの比電荷の測定実験では生データの表まで紹介されるなど、極めて具体的に研究現場の臨場感が再現されている。今では子供でも知っている電子や原子核のような概念がいかに獲得されたかという史実は、我々は本来細部まで熟知しておくべきものである。 文庫化された今、「私たち自身が新しい発見を生み出すため」(本文より)には、物理の研究者、学生には本書は必読とさえ思える。
最後になるが、大変残念なことに本稿執筆中、訳者である東大名誉教授 本間三郎先生の訃報が伝えられた。本間先生の核研現役時代、大学院進学に関して相談に伺ったことを思い出していた最中の出来事だった。正確な翻訳で本書を世に広めて下さったことに感謝しつつ、ご冥福をお祈りしたい。
(2007年1月9日原稿受付)
ページの頭に戻る
池内 了
池内 了編
寅彦と冬彦; 私のなかの寺田寅彦
岩波書店,東京,2006, xix+255 p, 18.5×14 cm, 本体2,100円[一般書]
高 田 誠 二 〈久米美術館〉
物理学者としてだけでなく文筆家としても個性的な活動を展開し続けた寺田寅彦は、昨今また、何度目かの賑わいを出版界に招き寄せているようだ。気づいたものを挙げれば、①池内 『寺田寅彦と現代-等身大の科学をもとめて』、 みすず書房、 ②大森一彦編 『寺田寅彦』(人物書誌大系)、日外アソシエーツ(紀伊国屋書店)、③山田一郎 『寺田寅彦 妻たちの歳月』、 岩波書店、 ④池内編 『懐手して宇宙見物』(大人の本棚)、 みすず書房-という具合で、 まさに文運隆昌の感。とりわけ②は書誌研究成果の総集であり、そのお蔭で私たちは「寺田についてこれまでに発表された活字史料」を存分に調べ上げることができる。
さて、それらと肩を並べて、本書は読書界に何を提供してくれるのか? 書誌②や作品選集④とも違い、また個人による研究書①③とも違って、本書は「諸分野の専門家の寄稿を集めた多角的な論集」の形をとっている。担当者の専門は、編者の宇宙物理学を筆頭に、 創作 3 者、 俳句、 詩、 メディア文化論、映画論、行動生態学、システム-進化論-デザイン論、 地震学、 理論物理学と多彩で、それぞれが「私のなかの寺田」を語る。
こうして本書は、①~④のいずれとも違う滋味と緊張感を湛えるものとなった。キーワード的な例示(と出典記載)をすれば、アームチェア・ディテクティブの発想に立つ推理(「病院の夜明けの物音」)、皇后陛下の学習題材となった寺田作品 (『団栗』)、 モンタージュ映画と連句俳諧の相関(『映画時代』)、物理の話題では電車の混み方・椿の落ち方の非線形論など。加えて編者の「あとがき」は、本名・寺田寅彦と筆名・吉村冬彦との使い分けに寄せて、「連想」論を展開している。
寺田を扱う論集は過去にも何回か見られたが、顔ぶれは概ね同時代人か弟子たちと、偏っていた。本書は「寺田談義21世紀版」の皮切りにふさわしい新鮮さに満ちている。
ただ、話を物理に引き寄せると、気懸かりは残る。「懐手(ふところで)して宇宙見物」という句が本書の表紙(カバーの下) に引用されているが、 この句は④では書名にさえ使われており、上(かみ)の句「好きなものいちごコーヒー花美人」とともに、寺田の耽美的(セレブ?)な内面の表現として(好意的に)扱われているかに見える。しかし実験科学者が「懐手」で仕事を達成できるだろうか。電車の込み方を調べるにはストップウォッチを握る、椿の落ち方を模擬するには紙で模型を作って落とす、そもそも若き寺田の X 線干渉実験は、結晶と蛍光板を手で動かして初めて成功したのだ。
手の働きを第一義と考える実験家と懐手の見物を享受する風流人と、両者をそれぞれ寺田寅彦と吉村冬彦とに対応させて、彼の複旋律的な活動を評価し直す―この種の二重らせん的考察こそが、本書のタイトル 『寅彦と冬彦』 にふさわしかったのではないか。
(2006年11月15日原稿受付)
ページの頭に戻る