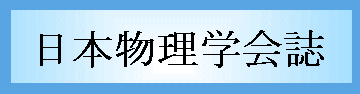
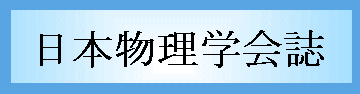
このページでは、物理学会誌「新著紹介」の欄より、一部を紹介者のご了解の上で転載しています。 ただし、転載にあたって多少の変更が加わっている場合もあります。 また、価格等は掲載時のもので、変動があり得ます。
J. K. Bhattacharjee and S. Bhattacharyya
Non-Linear Dynamics Near and Far from Equilibrium
Springer, India, 2007, vii+304 p, 24.5×16.5 cm, $169.00 (Springer and Hindustan Book Agency, 2007)[専門書・大学院向]
ISBN-13 978-1-4020-5387-0
ISBN-10 1-4020-5387-8
早 川 尚 男 〈京大基研〉
本書は古典的非平衡現象の数理的側面について書かれた大学院生向けの教科書である.そのカバーする分野は,非平衡ダイナミックスの基礎,動的くりこみ群, モード結合理論, KPZ 方程式を中心とした界面成長のダイナミックスに加えて乱流,高分子までに及び,それらを300ページ程の分量に収めている.現在,非平衡物理を専攻しようという学生に手頃な教科書は数少なく,この分量の小冊子であれば評者の書いた教科書のように初等的内容に終始するか,計算経過を省略し,網羅的に結果のみを紹介するモノグラフになりがちである.評者が本書を手に取る前には,後者のように,個々の掘り下げを犠牲にしつつ多くの題材を網羅的に紹介したものと予想したのだが,その予想は良い意味で裏切られた.
本書で紹介されている題材は複雑な計算が必要であるにもかかわらず,論文等の紹介でお茶を濁すことなく著者がしっかりと計算を行っている点で本書を評価できる.つまり本書は他書や論文を見る必要はない自己完結の書である.従って計算の労を惜しまない読者はここで紹介された題材の一通りの計算法を習得できることになっている.また最後の一章として中途半端に紹介されている高分子の項を除き,多数の題材が有機的に結合しており,通読によって初学者でも非平衡物理のイメージを明確に持ち得る点でも評価できる.もちろん,実験の紹介がない上に,本書を読み進める上で,ひたすら計算を要求されるので,本書を読みこなすには高いモチベーションと相当な根気が必要である.逆に言えば,実験家や手っ取り早く結果を知りたい忙しい人,計算の背後にある物理的本質を知りたい人には本書は向かない.
本書を理論家向けの教科書と限定しても,相当に個性的であり,読み手によって好き嫌いが分かれるであろう.実際,くりこみ群を用いた計算を紹介するのに1ループの平衡の臨界指数の計算を省略し,2ループの臨界ダイナミックスの計算の詳細を紹介している点にバランスの悪さを感じる読者も多いだろう.そうでなくてもあまり見通しもなく,計算式の洪水にうんざりする読者は多いと思われる.また少なからぬ点に誤植が見られ,指数関数等に斜体を使う記載法に据わりの悪さを感じるだろう.さらに言えばそれなりに他の題材と結合しているとは言え,乱流を論じるには本書の記述では不十分であり,乱流を勉強するのであれば,乱流の専門的教科書を紐解くことを勧める.他の部分でも,スタンダードな手法の習得や物理的直観を磨くには,他の本や論文を読む必要があると思われる.これらの欠点を把握した上で,モダンな非平衡物理の大学院生向けの教科書として本書を推薦したい.
(2008年8月11日原稿受付)
上田正仁
現代量子物理学-基礎と応用
培風館,東京,2004, viii+245 p, 21.0×15.5cm, 本体3,500円[専門書,学部・大学院向]
ISBN 978-4-563-02265-9
加 藤 岳 生 〈東大物性研〉
量子力学の基礎に関して,ここ20年間大きな発見や発展が続いた.ボーズ-アインシュタイン凝縮〓(BEC)〓の実現や,量子光学技術の発達,量子情報処理の登場など, 20 年前には予想できなかったような展開が続いており,今現在も活発な研究が行われている.しかしながら,これらの発展を踏まえた量子物理学のまとまった教科書は長く現れなかったように思う.ここでは,この分野で活発な研究を行ってきた上田氏による意欲的な教科書を紹介したい.
本著は大きく基礎編(第1章から第3章)と応用編(第4章から第7章)に分けることができる.著者のまえがきにもあるように,応用編は各章が独立しており,どの章から読み始めても差し支えないようになっている.まず基礎編では量子力学や場の量子化の復習から始まる.大きな流れは標準的な教科書に近いが,随所でとりあげられる話題は特色あるものが多い.例えば,不確定性関係を軸にした話題(非可換観測量の同時測定,スクイズド状態),観測理論(POVM測定),位相演算子などがそうである.
第4章は主に光の干渉効果について,第5章は原子と光の相互作用についての解説が行われる.ここでは基礎編で解説した電磁場の量子化を巧妙に駆使して,興味深い話題を可能な限り記述している.この部分は,場の量子論の具体的な応用例として,大変よい教材になっており,とても印象深い.
第6章は巨視的量子効果について,関連する話題(超流動・超伝導)を取り上げながら解説が行われる. BEC を例にしながらも,非対角長距離秩序についての一般論も議論されている.難しい計算を避け,簡潔な議論によってこの現象の本質に迫るという姿勢が貫かれており,超流動・超伝導への優れた導入となっていると思う.
第7章は量子情報の説明にあてられる.様々な話題を取り扱いつつも,適切で本質的な例を提示することで,極めて簡潔で要を得た説明になっていると思う. この章で, EPRペア, 量子テレポーテーション,量子アルゴリズムなどの基礎を概観できる.
総合的に判断して,本書は量子物理学分野に興味を持つ学部生・大学院生に最適な教科書であると考える.最近の研究についての解説と,基礎的な解説のバランスが大変よく,類書にはない解説が多々含まれる.ゆえに,学生だけでなく,(というよりは, むしろ学生より)量子物理学を概観したい研究者・量子力学の授業を持つ教育者にも向いていると思う.事実,私もこの本を一通り読み終えて,バラバラだった知識が統合されるような感覚を味わうことができた.同時に,膝をはたと打つ場面もたびたびあった.すべての研究者におすすめの一冊である.
(2008年8月24日原稿受付)
湯川秀樹著,小沼通二監修
「湯川秀樹 物理講義」を読む
講談社,東京,2007, 175 p, 26×18.5 cm, 本体1,800円[学部向]
ISBN 978-4-06-154293-8
坂 東 昌 子
本書は,湯川先生が日大で行われた3日間の講義記録である.講義録そのものはすでに出版されていたが, 10 人の多彩な方々の感想あるいはコメントが付いている.
一般に,湯川先生の授業を受けた学生達の評価は2つに分かれていた.私は面白くなかった組に入る.教養から3回生になって,専門の講義では量子力学の授業が始まる.その時,量子力学の講義を担当されたのが湯川先生だった.古典力学が頭にこびりついている私にとって,量子力学の真髄を理解するのは大変だった.湯川先生の講義は,この「物理講義」に掲載されている第3日目の講義内容,ラプラスやシュレディンガーの猫みたいな話が多かった.正直言って,学部生には,その深遠な意味は理解できず,行ったり来たりする講義に困惑したのを覚えている.でも,科学者の先取の気風や,なんでも根本から考える姿勢だけは覚えている.私のような平凡な学生は,問題も解けないし,古典力学から量子力学への飛躍の真髄が理解できなかった.
反対に,湯川先生の講義が面白いと感じた友人達は,未開拓の問題に取り組む進取の気風や先生の深い思索に感動したのだと,今,この「湯川秀樹 物理講義」を読んで悟った.自ら完成させた理論に満足せず,さらに遠くを見据えていたニュートンやアインシュタインの気持ちがわかる先生ならではの,開拓の歴史,その過程の躍動が至るところに見え隠れする.おざなりの科学史ではない.
続けて,第2日と第3日は,物質とそれが置かれている空間,この2つの間に「場」があり,それが遠隔力と近接力という2つの「力」の概念を通して語られる.湯川先生が一生追い求められていた問いは時空とは何か,そこに置かれた素粒子の構造は?であった.時空と物質,力と場,その基本概念をめぐって語られるお話は,今もなお追い続けられている核心に迫る問いである.物質の究極の姿として「物質の運動を理解するには原子論が必然的」と説かれた先生が,その先に時空の原子論への思いを持ち続けられた確かな足跡がこの最後の講義には残されている.若者や他分野の方々のコメントには,この感動が表れている.
この講義をされたのは1974年,湯川先生は67歳,このあと病で入院を繰り返しながらも,核廃絶を訴え続けられた.講義の行われた当時を,もう一度振り返ってみた.当時,素粒子論は激動期だ.ばらばらに捉えられていた3つの相互作用がゲージ理論に収斂するうねりが押し寄せていた.講義の第1日目からずっと突き詰め,核心に迫ろうとする鋭い目があるのに,先生はゲージ理論に一切触れられていない.しかも,それは次々と発見される素粒子の現象を見事に統一する方向へと突き進んで,標準理論へと収斂していった.先取の気風を持ち,時空と物質,そこに介在する場という概念を深く追及された先生が,その只中にあってこのうねりを察知できなかったのか.この歴史の1ページは私自身にも重い問いである.素粒子仲間の間では,率直に語ることが慣わしであるが,この本での専門に近い方々のコメントにはそこをすり抜けたように思われる.
ひょっとして,コメンターも先生自身もあえて触れられなかったのか.先生が生きておられたら聞いてみたいものだ.
(2008年7月29日原稿受付)
P.-G.ドゥジェンヌ,F.ブロシャール-ヴィアール,D.ケレ共著; 奥村 剛訳
表面張力の物理学-しずく,あわ,みずたま,さざなみの世界-
吉岡書店,京都,2008, xi+294 p, 21×15 cm, 本体4,800円[大学院・学部向]
ISBN 978-4-8427-0345-9
藤 原 進 〈京都工芸繊維大院工芸〉
葉の上の小さな 「しずく」, シャボン玉の 「あわ」, 池に小石を投げてできる「さざなみ」. これらはみな, 子供の頃誰しも心引かれたであろう,表面張力が関係した現象である.本書は,このような毛管現象に関して,学部上級生以上を対象に書かれた本である.「まえがき」にも述べられているように,定量的な説明よりもむしろアイデアの説明・基本原理の概要の提示に重点が置かれており,静水圧とラプラス圧の知識および大学 1, 2 年の数学の知識で十分読み通すことができるように配慮されている.
第1章では,表面張力や濡れといった毛管現象に関する基礎的事項の説明が行われ,続く第2章において,毛管現象におよぼす重力効果が議論される.ここでは,毛管長なる長さの尺度が現れるが,これは本書の至る所で顔を出す.第3章では,表面の欠陥と関連した三重線(三相が接する境界線)の履歴および周縁弾性が詳しく説明される.第4章では,液体薄膜を研究する際に重要となる長距離力(分子間相互作用)についての考察が行われ,表面エネルギーに関係した分離圧が導入される.第5章と第6章では,薄膜の各種不安定性や波,さざなみ,さらには,三重線の移動や振動,完全な濡れなど,毛管現象の動力学が扱われる.第7章では,表面から液体薄膜が自発的に後退する撥水について,豊富な実験例を示しながら解説される.第8章では,界面活性剤の基本的性質が述べられた後,その応用例や石鹸膜,シャボン玉の詳細な解説が行われる.最後の2章では,組織表面や多孔媒質の濡れ,化学的勾配や熱勾配下での輸送現象など,実用面で非常に重要となる最先端の話題が取り上げられる.
本書の特徴は,以下のような点である.(1)原語のフランス語から直接日本語に訳されていることもあり,とても読みやすく,特に前半部においては訳注が豊富(1つの訳注が半ページを占めることもある!)なため,数式をフォローすることが比較的容易である.(2)著者らが提唱する,複雑な数学的取り扱いをできるだけ避け,直感的理解と新しい見方をもたらすことを可能にする「印象派」物理学を,豊富な実例をもって体感することができる.ただし,より詳しい厳密な取り扱いについては, 章末の専門書(例えば, J. Israelachvili: Intermolecular and surface forces, Academic Press, New York, 1985)や原論文を参照する必要がある.(3)第2版で付属されたCDには,ショートムービーが200近く含まれている. 訳者によれば,「小学生の子供が夢中になって何時間も見続けてしまう」ほど魅力的とある.試しに,小学1年生の息子と一緒に見てみたところ,石鹸膜や水滴のムービーなどどれも面白く,途中からは息子が自分でマウスをクリックして,夢中で見ていた.さらには,その日以来,お風呂ではシャボン玉に関する(台所実験ならぬ)「浴室実験」が始まり,週末になると朝早くから「パソコンでシャボン玉見たい!」と言ってムービーを見ている.このことからも分かるように,「子供が何時間も見続ける」というのは決して誇張ではなく, 「理科嫌い」 な人たちにもぜひ本書を勧めていただきたい.
(2008年9月2日原稿受付)
佐藤洋一監修,信定 薫,斎藤恭一
理系たまごの英語40日間トレーニングキット
アルク,東京,2006, 4分冊,21.5×15.0 cm, 本体6,500円(理系たまごシリーズ1)[大学院・学部向]
ISBN 978-4-7574-0958-3
田 中 啓 文 〈阪大理〉
英語の習得という意味において,やる気のない人間に何をやらせても全く身にはつかないが,いざやる気になったときには教材によって差が出てきてしまう.特にテクニカルタームに初めて接する理系初心者にとってはいかにやる気にさせるか,そしてやる気になったときにいい教材であるのか,がその後の理系英語吸収に差が出ると思われる.それを念頭に「理系たまごの英語40日間トレーニングキット」を論評する.
本書は英語学習書籍に力を注ぐ(株)アルクから出版された理系学部1-2年生を対象にした英語教材で,Kit-1~4の箱入り 4 分冊である. 構成は Kit-1 が基礎編(p. 107), 2が発展編(p. 143), 3が学習ナビブック(p. 111), 4がインタビューブック(p. 31)となっている.1-2は理系英語に初めて接した人を対象に,CDで発音を押さえながら,理系の特殊な表現を学習していく内容で,視覚聴覚を駆使していることから習熟度も悪くないと思う.特にKit-1では「単位」を扱っていたり,数式の読み方を扱っていたりして,なかなかこれまでの英語学習では触れなかったであろうものの,研究活動を進める上で必須の項目を扱っており評価できる.Kit-2は1つのテーマごとに色々な問題が出されていて飽きさせない作りにはなっている.しかし,章ごとで分野が大きく異なることから,興味のないテーマの章には取り組みにくいかもしれない.例えば生物実験の項目を物理学科の人間が実際に興味を持って取り組むだろうか? 当然何でも知っているに越したことはないのだろうが「理系英語をオールラウンドで知っていれば,いろんな研究者とディスカッションもできるだろうし,研究者の武器になる」とは,やはり研究活動をある程度経験しないと出てこない発想であろう.さらに,本書に3巻のエピソード集が必要なのかと考えさせられた.このパートは「英語トレーニング」とはほとんど関係ないが,多くの理系研究者が共感できるであろう英語にまつわるエピソードのみで構成されているので,学生にとっては非常に参考になる.私も英語に関して苦労したところなどには共感するところが多かったので,最初はいい企画だと思った.しかしながら,実際の学生の反応は一概にそうではなかった.どうも知らない世界のことをいくら面白おかしく述べられても理解できない上,いつまでたっても苦労するような話で,「一生懸命やってもこの程度か…」と言った感じの漠然とした失望感が先に来るようである.Kit-4のインタビューはとても面白かった.優秀な研究者であっても英語には皆同じような努力が必要だったのだと知ることができ,ちょっとした安堵感とやる気を学生読者にもたらすのではないだろうか.以上のことから,本書はやる気にさせる教材でもあるし,研究に最低限必須の項目を扱っておりかつ,学びやすくまとまっていると思う.ただ,税込6,825円と値段が高いのでKit-1, 2, 4をまとめて1冊とし,普通の書籍として半分程度の価格に抑えて世に出す方が,学生を相手にするにはよさそうだ.
(2008年7月13日原稿受付)
M. Kardar
Statistical Physics of Particles、
Statistical Physics of Fields
Cambridge University Press, Cambridge, 2007, xx+320 p, 24.5×19.0 cm, US$75.00[大学院向]
ISBN 978-0-521-87342-0
Cambridge University Press, Cambridge, 2007, xx+359 p, 24.5×19.0 cm, US$75.00[大学院向]
ISBN 978-0-521-87341-3
早 川 美 徳 〈東北大理〉
表紙の砂丘の写真に目を引かれ,粉体関係の随分とまとまった教科書が出たものだと思い,手に取った.開いてみると,扱われているトピックの多くはオーソドックスな統計力学の教科書であった. 評者が M. Kardar の名前を初めて知ったのは,自己アフィンフラクタルな界面成長の数理モデルとして有名な KPZ (Kardar-Parisi-Zhang) モデルの論文で,非可逆な界面成長の問題を,繰り込み群の手法を使ってエレガントに解いてみせた仕事として良く知られている.この本は,その著者がMITで実践してきた大学院講義の内容を, 学生の強い勧めもあって, 2 分冊の教科書としてまとめたものだそうだ.
最初の分冊 “Statistical Physics of
Particles"は,物理系の学部レベルの熱統計力学に,大学院のトピックを融合させたような内容,他方の“Statistical Physics of Fields"では,臨界現象が,繰り込み群の方法を中心に,計算技術的な内容にまで立ち入って述べられている.
この本を読んでいると,著者のすぐれた教師ぶりが随所に感じられる.例えば,トピック毎に理解目標が明示されている点,内容を通じての「難しさ」が上手にコントロールされ,無理なステップが生じないように注意が払われている点は,授業を担当する身としても参考になる.さらに,欧米の教科書では珍しいことではないけれども,バラエティーに富んだ問題が用意されており,基本的な問題については,かなり詳細な解答が添えられている.解答部分だけで,全体の1/4~1/3程度の分量にもなろうか.
それぞれの巻の内容を簡単に見ておこう.“Particles"は,熱力学の復習から始め,統計力学に入る直前に,以降のモーメント計算などで必要となる確率論を「つなぎ」として配置している点がユニークである.続いて,気体運動論が述べられ,ミクロとマクロを橋渡しした後に,古典粒子系の統計力学が導入される.次いで,相互作用のある系の扱いについて,クラスター展開,ビリアル係数の計算,相転移の平均場理論などが続き,量子系の統計で終わる.
“Fields"の巻は,それ単独で,繰り込み群の方法の良い指南書として使える.連続場を使った現象の記述から始めて, Ginzburg-Landau型のハミルトニアンと相転移,スケーリングと繰り込み群の基本的な考え方,ダイアグラムを使った摂動計算,ε展開へと段階を追って展開される.その途中で,散乱実験と相関関数との関係や,ガウス型の汎関数積分など,理解を助けるための「サブルーチン」的なトピックについても紙数が割かれている.さらに,代表的な格子モデル,高温/低温展開とモデルの双対性,二次元系の振る舞いなどが詳しく紹介される.おしまいの二つの章は,散逸系のダイナミクスや前述のKPZモデル,ランダム媒質中の有向パスを経路積分に応用したいくつかの例が述べられており,いずれも著者の研究分野と関連が深く専門的な内容である.
このように,概念的な理解のみならず,具体的な計算の処方箋の習得までを目指す者,特に理論系の大学院生にとって,「使える」2冊と言えよう.
(2008年7月1日原稿受付)
中井 仁,伊藤 卓
検証「共通1次・センター試験」
大学教育出版,岡山,2008, vii+212 p, 21.5×15.5 cm, 本体2,200円[一般書]
ISBN 978-4-88730-825-1
笠 潤 平 〈香川大〉
世界史などの未履修問題のような学校ぐるみの学習指導要領無視が広がるほど,日本の高校教育に対して大学入試が強い影響を及ぼし続ける中で,センター試験は前身の共通一次試験から数えると30年目を迎え,その運営システムは巨大化し,近年は私大による利用も急速に増えている.
本書は, 05 年に開かれた学術会議の理学振興研究連絡委員会によるシンポ「共通1次・センター試験の四半世紀を考える」を契機として同試験の批判的検討を集めた論集である.編者の伊藤卓氏の総論に始まり,大学への影響,高大接続の中での働き,高校教育への影響など同試験のさまざまな側面について,各論者が自由に論じ,イギリスやフィンランドとの比較なども盛り込み,根本的改革策をはじめ多くの問題提起を含んでいて,非常に面白かった.論者は13名にのぼる.筆者もこの10数年,高校物理と大学入試の関係を物理教育学会などで議論する輪に加わってきたが,個人的には,共通一次成立時他の事情(細矢治夫氏),センター試験の数学と東北大の2次試験の数学の成績間の相関のなさの分析(森田康夫氏),マークシートの中で数学を考えさせることの限界の指摘(上野健爾氏)などが興味深かった.高校教育への影響を論じた香本明世氏・中井仁氏の文章は現場の感覚として妥当である.また,大学と学生自らの「輪切り的序列化」の問題を有山正孝氏他が指摘する.一方,英国のように探究活動を評価対象に位置づけるという樋口真須人氏の問題提起は筆者も賛成である.
さて,センター入試改革は,日本の入試問題全体の批判と改革の一環でなければならない.入試問題全体のありようが今まで通りならば,たとえセンター入試が廃されても,ある範囲の約束による問題解法の習熟を高校理科の主目的と生徒が受け取る現状は変わらない.それでは高校理科教育がいきいきとしたものにはならない.第2にその入試改革は高校側と大学側の関係者の真剣な協力関係がなければできない.この点では物理教育学会による各地域の入試問題懇談会は,入試問題のフィードバック機能を果たし,両者の信頼関係を生み出している.実際,共通一次開始当時の物理の問題は,時として難問も含むものだったが,その後,多くの人々の努力により,高校の通常の授業への影響を意識するものに明らかに変わっていった.われわれはこの上に立って,次の世代の教育は自分たちで考えるという物理関係者のコミュニティの意識が高校物理の改革を生み,それに合わせた評価・試験制度のあり方を俎上に載せていくという道を目指すべきだろう.その中で本書でなされているような努力を真にいかしていくことができるだろう.
(2008年7月13日原稿受付)Springer, 2008, xiv+333 p, 24.0×16.0 cm, £79.95[大学院向]
H. Haken
Brain Dynamics, 2nd Ed. An Introduction to Models and Simulations
ISBN 978-3-540-75236-3
金 丸 隆 志 〈工学院大〉
本書は1970年代から1980年代にかけて「シナジェティクス」という概念で一世を風靡したハーケンによる脳科学に関する教科書の第二版である.ハーケンは「シナジェティクス」以後も旺盛な研究活動を続けており,奈良・山口訳「脳機能の原理を探る(2000)」や奈良訳「情報と自己組織化(2002)」をご覧になった方も多いだろう.本書は近年脳科学で話題となっている「ニューロンの活動間に見られる同期現象」の理論解析を主なトピックとしており,微積分と微分方程式の知識があれば読み進められるよう配慮されている.
まずは脳科学の簡単な解説(ニューロンの構造,視覚皮質における同期現象など)と,デルタ関数やノイズの数学的取り扱いの解説から幕を開ける.ここで,本書の図にはシナプスと軸索と樹状突起の関係について誤解を招くものが複数あり,本書が第二版であることを考えるとやや残念である.引き続く理論解析の対象となるのはハーケンが灯台モデルと呼ぶニューロン結合モデルにおける同期現象であるが,これ は Tsodyks, et al. (1993) や Treves (1993)が解析した「指数関数型のシナプス後電位で相互作用する積分発火ニューロン振動子集団の同期」とほぼ同じであり,その集団ダイナミクスの厳密な解析が展開される.この計算過程は詳細に記述されており,説明不足と思われる部分は章末問題とその解答,という形で補足されている.そしてその結果を踏まえた連想記憶モデルの解析へと進む.情報のキャリアとしては各素子の周波数(ただしノイズ除去能力は弱い),発火頻度,位相の3つが選択でき,現実の脳がそのように動作しているかはともかく,理論的な可能性としては興味深い.その後,位相振動子やホジキン・ハクスリー方程式に関する補足的な章がいくつか続く.
以上簡単に紹介したが,この分野の現在までの進展を鑑みれば,「シナプス後電位形状への依存性」,「フォッカー・プランク方程式や位相応答などによる解析」,また「これらの解析結果をそのまま実験結果と対応づけて良いのか」など,取りあげて欲しかった話題はいくつかある.これらは参考文献としてもあまり紹介されていないので,その他の教科書や原著論文を当たる必要があろう.しかし,教育面を重視して書かれたと思われる本書にそこまでを期待するのは贅沢かもしれない.
「最近の学生はすぐ計算機に頼って…」 とお嘆きの方や,理論に強く応用分野を探している大学院生に,本書をゼミや輪読の教科書として採用することを勧めたい.
(2008年6月14日原稿受付)東京大学出版会,東京,2008, xiii+160 p, 21.0×15.0 cm, 本体2,400円[一般書]
嶋作一大
銀河進化の謎 宇宙の果てに何をみるか
ISBN 978-4-13-064103-6
山 田 亨 〈東北大院理〉
来年は,ガリレオが宇宙に望遠鏡を向けてから400年を祝う世界天文年である.ガリレオの小さな望遠鏡を出発点に,より大きく高性能の観測装置が登場するたび,宇宙についての認識は大きく広がってきたわけだが,ガリレオの「太陽系の発見」,ウィリアム・ハーシェルの「わが銀河の発見」,そして,20世紀の大望遠鏡による,時空としての「宇宙の発見」,などになぞらえれば,1990年代後半からの,ハッブル宇宙望遠鏡やすばる望遠鏡などの地上巨大望遠鏡による成果は,「宇宙史の発見」とも言えるのではないだろうか.劇的に変化する宇宙の姿を,その年齢の大半の期間にわたって捉えることがはじめて可能になったからである.そして,その主役は「進化する銀河」だろう.我々が「観測する」宇宙の歴史とは,宇宙の膨張とあいまって成長する密度ゆらぎの発展の中で誕生し,ときにその姿形を変えてゆく銀河の歴史であるからだ.
本書は,このような宇宙における「銀河の形成と進化」について,現在の我々の理解の到達点を,広範に,しかし平易に解説している良書である.筆者は,主に「宇宙における構造形成」という視点から,銀河の分布,そしてその形成と進化について第一線で研究成果を挙げている専門家だが,本書においては,「規則的であり,かつ多様である」銀河の世界をわかりやすく整理し,そして,1990年代半ばから本格化した宇宙初期に至る遠方銀河についての観測的研究の「骨太な」成果を描き出そうとしている.銀河の歴史を現象論的に理解するためには,まず,「銀河とは何か」を理解しなければならない.著者は,現在の宇宙における銀河の性質の多様性と一般性を天体物理学の基礎知識とともに要領よくまとめ,そしていよいよ遠方銀河の観測へと読者を導いてゆく.遠方銀河の観測はなぜ可能になったのか.そして,どのようにして我々は無数とも思える多数の銀河の中から,最遠方の銀河を見つけ出すのか.
高校生から大学生に向けて書かれた入門書であるが,一方,いわゆる「宇宙論」に興味を持つが,博物学的な天文学には詳しくない方にも,一読をおすすめできるだろう.本書によって,より鮮明かつ具体的な「宇宙史」の担い手の姿を知ることができるからである.また,現代人の「教養」として,我々の起源としての銀河の歴史をひもといてみたい,という方にもうってつけであるだろう.
入門書であるための自重ではあろうが,各項目がこれまでの研究の発展を丁寧になぞっている反面,それらを超えた全体的な理解についての記述には若干の物足りなさも覚える.もっとも,著者は,銀河の形成と進化についての我々の理解は「登山にたとえると未だ五合目」であると言い,頂上に達したときには,「さらに思いもかけない光景が広がっているかもしれない」とも言う.この慎重さが本書を良書たらしめている所以ではあるが.
(2008年6月16日原稿受付)
石黒武彦
科学の社会化シンドローム
岩波書店,東京,2007, iv+122 p, 18.2×13.0 cm, 本体1,200円[大学院,研究者向]
ISBN 978-4-00-007471-1
木 村 初 男
21世紀に入って最先端科学分野で実験データのねつ造や改ざんという不祥事が相次ぎ,科学者の世界を脅かした.著者は,国立の研究所と大学で基礎研究に携わってこられたシニアの物理学者であるが,科学や技術が社会にがっちり組み込まれた今日,科学コミュニティは社会からのビジネスライクの要求にスムーズに乗れずに,生活習慣病のような「悩ましい」問題を抱えるようになったと言う.本書はその症候群を「科学の社会化シンドローム」と名づけ,実態と背景を6章にわたって根源的なところから論評した.
序章と1章では,「科学システムを蝕むガン」である不祥事の横行が詳細に分析される.アメリカ・ベル研究所の「有能な」ポスドク研究者によるナノテク最先端分野の「画期的」研究,韓国ソウル大の「最高科学者」ファン教授グループによる再生医療革新につながる研究など,有力雑誌「サイエンス」や「ネイチャー」などに掲載され関係分野の研究者に大きなインパクトを与えた論文が全てねつ造データによることが明るみに出た.近々5年ほどのうちにニュースになった研究不祥事の一覧表によれば,分野別件数は医科学が多いが物理・化学分野も例外ではなく,国別でも日本7件,アメリカ4件,韓国,ノルウェー,中国各1件とグローバルだ.「横行するねつ造論文の特徴は,科学的内容は月並みだが実現すれば大きな技術的利益が期待されるもの」だという著者の指摘を傾聴したい.これは科学者コミュニティが偽造論文をやすやすと受け入れてしまった理由にもつながる.以下の章では問題の根源を考えていく.2章では論文審査のピアレビューシステムがうまく機能しなくなった問題を検討し,3章と4章では,科学技術基本計画が主導する「科学と社会の新しい関係の構築」の政策が,日本の科学者に競争性という強い縛りをかけている実情を解明する.5章ではポスドク1万人計画や,国立大学の法人化等の政策が,研究環境を大きく変質させ,人材養成にも困難をもたらしている実態を報告し「集るところにはバブルをつくるように研究費が集る.これは研究者の資金にたいする感覚を粗っぽいものにする」と警告する.6章では,科学,特に物理科学の行方についての著者の考察が述べられる.「科学には,社会の価値観とはほとんど無縁の領域で,自律的な論理で発展する良質なコアがあり,その維持・育成が不可欠だ」と強調するところに著者の憂慮が現れている.
この本は軽装版だが,問題は網羅的に取り上げられており,短文で全容を紹介するのは難しい.物理学会も行動規範の策定やポスドク問題への取組を進めている現在,会員の皆さん,特に研究リーダーや若手研究者には一読をお勧めしたい.
(2008年1月7日原稿受付)
R. E. Walstedt
The NMR Probe of High-Tc Materials
Springer, Berlin and Heidelberg, 2008, xii+267 p, 23.9×15.9 cm, $209.00 (SPRINGER TRACTS IN MODERN PHYSICS 228)[大学院向・専門書]
ISBN 978-3-540-75564-7
石 田 憲 二 〈京大院理〉
近年,物性研究において物質内を原子核レベルで調べる核磁気共鳴(NMR)実験の重要性は固体物理の研究者に広く認識されるようになってきている.実はこの一因となったのが,銅酸化物高温超伝導体でなされた数々のすばらしいNMR実験, そしてその実験から引き出された銅酸化物超伝導体の物理性質(強い反強磁性ゆらぎの存在,d波超伝導,擬ギャップ的振る舞い等)によるものであろう.本書は銅酸化物高温超伝導体, 特にYBa2Cu3O7-x(YBCO7-x), YBa2Cu4O8(Y248), La2-xSrxCuO4(LSCO: x)においてなされた銅(63,65Cu), 酸素(17O), イットリウム(89Y)核のNMR実験の経緯,実験結果の紹介や解説を意図して書かれたものである.
本書の構成は,第一章で高温超伝導体の紹介や各章の要約の後,第二章に主として NMR の専門家以外を対象とした NMR の基礎的な解説がなされている.扱っている内容は(1)基本的なNMRスペクトルの構造, NQR/NMRの観測, 核スピン-スピン緩和時間T2, 共鳴線のシフト,核スピン-格子緩和時間T1の定義と解説,(2)単純金属や第一種超伝導体における共鳴線シフトと緩和時間の振る舞い,(3) d-バンド金属における d 電子の超微細相互作用,軌道によるシフト,T1への効果,そして第二種超伝導体の3d金属や金属間化合物(特にVやV化合物)を例にとった混合状態における共鳴線の構造やシフト,T1の温度や磁場依存性などで,これら多岐にわたる内容が約50ページによくまとめられている.固体物理,特に超伝導を専門とする NMR の研究者であれば一度は勉強したことのある内容がよく整理され,まとめられているのがとてもありがたい.また著者は,通常金属やそこで起こるs波超伝導を解説することにより,次の章から登場する銅酸化物超伝導が如何にそれらとかけ離れた振る舞いをするのかを,読者に印象付ける意図を持っているものと推察する.
第三章から本題の銅酸化物高温超伝導体における NMR の実験結果についてであり,高温超伝導体発見から2-3年間でなされた NMR の実験結果について時系列的に紹介されている.ここで は 主 に YBCO7 の Cu, O, Y 核の
NMR の結果が示され,その後銅酸化物超伝導体のCu2+の超微細相互作用のモデルである, Mila-Rice-Shastry (MRS)のモデルが紹介されている.サイトによるT1の温度依存性の違いや,Cuサイトのナイトシフトと1/T1の関係など,混迷していた初期の NMR の結果が,このモデルによって見事に理解されたことが解説されている.またT1と波数(q)依存性を持つ動的帯磁率の虚部( χ (q, ω))との関係,高温超伝導体の超伝導状態のシフトとT1がd波モデルで説明できることが,発見初期に出されたMonien-Pinesのモデルをもとに解説されている.
第四章では酸素欠損を持つYBCO6.6 と Y248 の NMR の結果を中心に,銅酸化物超伝導体の重要な問題の一つである低ドープ領域での「擬ギャップ」について紹介されている.最適ドープからドーピング量を減らすにつれ, NMR の実験結果に 1) 静的帯磁率には室温から減少するギャップ的な振る舞いが現れ,2) YやOの1/T1Tは帯磁率と似た振る舞いをするのに対し,Cuの1/T1Tは超伝導転移温度Tcより十分上の温度でブロードなピークを示し,3)高温から減少する帯磁率や1/T1Tの振る舞いに,Tcで明確な異常が現れず連続的に超伝導状態の減少につながっていく振る舞いが観測される.これらの結果について原著論文のデータや解析をもとに解説がなされている.またNMRでみられる擬ギャップの振る舞いと,その後発見された他の測定による擬ギャップの振る舞いとの比較がなされている.
第五章では,T1を用いて議論された磁気励起の様々なモデルが紹介されている.三章で紹介したMRSのモデルによって,CuサイトとYやOサイトのT1の温度依存性の違いが単一バンドの励起で理解されることが示され,またこのモデルによりT1の振る舞いと動的帯磁率のq依存性についての関係が示された後は,多くの動的帯磁率のモデルがT1の実験結果をもとに議論された. それらの中でもUldry-Meier モ デ ル, Millis-Monien-Pines
(MMP)モデル,Hubbardモデル等が紹介されている. また超伝導状態の T1 やナイトシフトの振る舞いについては,Bulut-ScalapinoによりなされたHubbardモデルの計算が紹介され,実験結果が電子相関Uも含んだd波超伝導のモデルでよく説明されることが示されている.
第六章では,帯磁率のq依存性を知ることができるもう一つの NMR の物理量である T2 の Gaussian 成分 (T2g) が紹介されている. Pennington-Slichterのモデルに基づき,核スピン間の反強磁性ゆらぎを介しての相互作用とT2gの関係, T2gと帯磁率のq依存性( χ (q, 0))について解説がなされた後,常伝導,超伝導状態のT2gの振る舞いが紹介され,それらの結果と理論モデルとの比較がなされている.またT1とT2gにみられるscalingや,MMPモデルに基づくそれらの物理量とスピンゆらぎのパラメーターの関係,磁気相関長について紹介されている.最後に,特にLSCOについてNMRの結果と中性子非弾性散乱の結果との比較がなされている.
これらのように,NMRの基礎は勿論のこと,銅酸化物高温超伝導に関して発見当初から90年後半までに発表された膨大な論文の中から,重要なNMRの結果,NMRの解釈のモデルが約270ページによくまとめられているのが本書の特徴である.著者が記述しているように超伝導が出現しているCuO2面の銅と酸素のNMRの結果から動的帯磁率の波数依存性まで詳細に議論されたのは銅酸化物超伝導体のケースが初めてであり,これらの実験結果や解析を学ぶことにより,NMRの有用性が認識できるものと思われる.またここで取り上げられている銅酸化物超伝導体で用いられた議論は,既に他の酸化物にも広く応用されている.
以上の理由から本書は幅広い固体物理の研究者にお勧めすることが出来るが,これから固体物理のNMRを専門に勉強する大学院生に特に強くお勧めしたい.本書の有用性は,私の研究室の大学院生は,NMRでわからないことがあると私に尋ねるよりこの本を借りていくことから推測して頂きたい.
(2008年4月16日原稿受付)東京大学出版会,東京,2007, xvi+408 p, 21×15 cm, 本体3,800円[大学院向・学部向]
清水 明
熱力学の基礎
ISBN 978-4-13-062609-5
小 嶋 泉 〈京大数理解析研〉
この本の書評を仰せつかったのは,以前,田崎晴明著 『熱力学; 現代的な視点から』 の書評をお引き受けした縁によるのだろう.「今日熱力学を,統計力学に従属しそれ自体で独立の価値を持たない 『古い』 学問と見なすのが現代物理学での 『常識』 のようだ」と書いたその折(2000年夏)から早や8年近く経つ.古い「業界意識」に「殴り込み」を掛ける気魄で書かれた(失礼!)のが「田崎本」や「佐々本」だったとすれば,その洗礼を受けた世代が既に第一線で活躍中の今,少なくとも若手の抱く熱力学イメージは既にversion up済みに違いない(どなたかそれを裏付けるようなデータをご存知なら,是非ご教示下さい!).大野克嗣さんやLieb-Yngvasonが仕掛けたそういう「熱力学見直し」の歴史的流れの中にこの「清水本」を置いてみれば,月並みな表現ながら「隔世の感」を禁じ得ない:「相手を説き伏せる意気込み」の時代が過ぎ,あらゆる可能なversionsを吟味し尽くして洗練された定式化を選び(例えば,1.3熱力学の様々な流儀,及び,巻末参考文献参照),「痒いところに手が届く」ゆとりを随所で味わう段階に来た,という意味で.こんな不用意な言い方では非難の板挟みに会うかも知れない(:十分練って書いたものを青臭い「意気込み」で割り切るのはけしからんとか,類書にない独自の視点をいくつも盛り込んだ熱き情熱を評価すべしとか)が,「理論の完成度」に拘る点で両者に共通した著しい特徴があることは言を俟たない:田崎本が「一個の完成された理論体系としての熱力学」という視点を重視するように,清水本にも,《最初に「要請」…を示し,そこから演繹的にすべての結論を導いていくスタイル》 を強調して,《現時点で「適用範囲ができるだけ広く,なおかつできるだけ強い」公理系を提案したつもり》 との自負がある(清水明氏ホームページの「しみずの雑記帳」07-04-18.html参照).
無理を承知で敢えて一言に要約するなら,可能な限り「熱」を表に出さず,専ら可視的で制御可能なマクロの力学変数を用いて熱的過程を書き切ろうと試み,そのとき書き切れずに残されるresidual factor(残留因子)として「熱」を扱うのが田崎本.それに対し清水本は,最初からミクロとマクロという二つのレベルの存在と相違を認めて(第1, 2, 3章の各々冒頭近くを参照),両者の相互関係をコントロールする核心概念をエントロピーSに見出し,その「自然な引数」となる示量変数への依存性に基づいて熱力学固有の本質を全て統制しようとの姿勢を貫く(第3, 4章以降).ここに見られる興味深い「交叉現象」として,力学変数にこだわる田崎本でさえ自変数の扱いを許した熱力学固有の温度Tに対し,《熱力学を正確にやろうとしたら,相加変数(示量変数)だけを基本的な変数にとらないといけない.このことをきちんと述べている教科書は,僕の本以外では,田崎さんの教科書だけ》(上記サイトの07-08-21.html)との原則に忠実な清水本は,示強変数Tを降板させ(内部)エネルギーUを自変数に取ってS=S(U; X1, …, Xt)(またはU=U(S; X1, …, Xt)) を基本に据える.これに基づく相転移点・三重点での縮退を含まない相図の扱いの提示 (Sec.15.3「エントロピーの自然な変数で見た相図」)と共に,示量変数と示強変数を入れ替えるルジャンドル変換の正確な扱い(第11章ルジャンドル変換) によって自由エネルギー(Helmholtz, Gibbs)の特異性の由来を上記視点から系統的に説明していることは注目に値する.
ともかく,読み始めてみれば,熱力学の理解に当たって重要な,あるいは,「微妙な」ポイントが至るところで懇切丁寧に説明されているのに感じ入る:例えば,Sec.5.7「離散変数での微分や 『わずかに異なる平衡状態』 の意味」を味読されたし! とりわけ私が好きなのは, 《SB(U, V, N) [: Boltzmann
entropy]の漸近形がS(U, V, N)になる…実際には,
S(U, V, N)
=V V →∞ lim SB(V u, V , V n)V
×(u=U/V, n=N/V) (16.4)
により, 有限のVについてS(U, V, N)を計算しているのである.だからこそ,統計力学で求めたS(U, V, N)を用いて, 有限のVについて熱力学で相転移を論じることができるのである(…). もしもVが無限大でないと相転移が議論できないなどと思ってしまったら…》,というエントロピーの漸近的振舞と熱力学的極限に関わる物理的議論(Sec.16.1)である.「お気に入り」ついでに「天ん邪鬼」まで呼び出せば,あまり親切過ぎて若い読者が“spoil"され,自分の頭で考えることを止めてしまわないか? ということが心配になり始める.
このうえ「無い物ねだり」が許されるなら,本書で明快に示された熱力学の普遍性が圧倒的なだけに,それを支える示量変数の「相加性」が決して無前提に成り立つ性質ではなく,例えば長距離力や自己相似性を特徴とする現象領域での非加法構造の存在およびそれとの「棲み分け」というopen problemの指摘があれば,更に教育的だったのではなかろうか?
(2008年4月14日原稿受付)ソフトバンク クリエイティブ株式会社,東京,2007, 244 p, 17.0×11.0 cm, 本体952円(サイエンス・アイ新書)[学部向・一般書]
福江 純,粟野諭美
宇宙はどこまで明らかになったのか-太陽系の誕生から第二の地球探し,ブラックホールシャドウ,最果て銀河まで-
ISBN 978-4-7973-3731-0
井 岡 邦 仁 〈KEK素核研〉
天文学はこれまで人類の自然観を幾度となく覆してきた.例えば,地動説から天動説への転換や宇宙膨張の発見などである.では,この近年にはどのようなパラダイムシフトがあったのだろうか? 本書は,その発展の最前線を一般の人でも分かるように紹介し,宇宙の魅力を余すところなく伝えている.扱うテーマは,太陽系以外の惑星系の発見から,宇宙一明るい爆発であるガンマ線バースト,そして宇宙のほとんどを占めていることが判明したダークエネルギーなど,多岐にわたる.ここ10年の宇宙の研究における主なブレークスルーを網羅しているといえる.
本書には一般の読者向けの配慮が随所になされている.文章は平易で,誰にでも理解できる.専門用語はできる限り解説されているし,式も出てこない.こう書くと,ブルーバックス的なものをご想像されるかもしれない.ところが実は全く違うコンセプトで書かれている.特に,通常本に書かないような最新の研究まで紹介されている.最新の結果というものは,研究が進むにつれて色あせたり,時には覆されたりするものである.そのような危険を冒してでも,最新の研究を伝えたいという意気込みが感じられる.さらに,読者の理解の助けになるように,カラフルな写真や絵がほとんど全ての見開きに載っている.それをパラパラ見ているだけでも宇宙への想像が膨らむ.それでいて値段は1,000円と大変お手頃である.
最近の宇宙の研究は目覚ましいものがある.一人の研究者が全分野の進展をフォローすることはほぼ不可能になってきている.そういう点でいえば,一般の人のみならず研究者まで非常に幅広い読者が楽しめる内容といえよう.最新の情報まで紹介されているので,他分野の課題を知る最も効率的な手段となりうる.
本の前半では,宇宙の知識が全くない人のために宇宙の基礎を編者が概観し,後半では,8つの最先端をそれぞれの分野の専門家が解説している.基本的に好きなところから読める.冒頭には各著者のプロフィールが紹介されており,個性を前面に押し出したスタイルをとっている.個人的に知っている方も多いので,私は2倍楽しませていただいた.各人が自分の専門を語るので,現場の熱気が直接伝わってきて面白い.
さらに痛快なのが,明らかになった事実だけではなく,進歩とともに生まれた新しい謎を躊躇せずつまびらかにしている点である.研究者が堂々と分かりませんと言うのは心地よいものだ.研究すればするほど新しい謎が生まれる,これこそが宇宙の最大の魅力の一つであろう.ぜひ一読をお勧めしたい.
(2008年4月30日原稿受付)日本評論社, 東京, 2007, 342 p, 21.0×15.0 cm, 本体2,400円(シリーズ 現代の天文学I)[一般書]
岡村定矩,池内 了,海部宣男,佐藤勝彦,永原裕子編
人類の住む宇宙
ISBN 978-4-535-60721-7
石 岡 俊 也 〈神奈川大〉
日本天文学会は創立100周年の記念事業として,「シリーズ現代の天文学」全17巻の刊行を昨2007年より始めた.本書はこのシリーズの第1巻であり,全体の序論として編集されたものである.近年進歩の著しい天文学の読みやすい入門書となっている.
本書は6章で構成されている.第1章は天文学の歴史(池内了),第2章はビッグバン論に基づく宇宙の始まりと現在(佐藤勝彦,郷田直輝),第3章は元素の起源(望月優子,佐藤勝彦),第4章は太陽および太陽以外の恒星の惑星系(向井正,中澤清,海部宣男),第5章は地球の自然と人間の活動(永原裕子編集,阿部豊,松田佳久,浜野洋三,松井孝典,住明正),第6章は時間,時刻,暦の話(岡村定矩,福島登志夫)となっている(括弧内は執筆者).以上の執筆者の数からも伺えるように,各分野の専門の方々による,最新の研究成果を踏まえた入門書である.
宇宙の起源,すなわち時間と空間の誕生とはいかなるものか,筆者のごとき素人(専門は物性)にも,いや素人なるがゆえに,関心がある.第2章にはいくつかの起源論が紹介されているが,筆者にとってはどの起源論も奇想天外なものに感じられて,なるほどとは納得しづらい,というのが正直なところである.どのようにして宇宙が誕生したかはさておき,初期宇宙の急激なインフレーションから始まる進化論は,インフレーション論の提唱者自身による記述であり,第3章の元素の起源論をも含めて,筆者にも然もありなんと思われるものである.今から30年以上前に聞いていたビッグバン宇宙論は,筆者の理解では(1)宇宙原理(一様等方な宇宙)の仮定,(2)宇宙は開いている(広さが無限でいつまでも膨張をつづける)か,閉じている(広さが有限でそのうち収縮に転ずる)かは不明,というものであった.それが本書では,(1)宇宙の地平線の内側の世界はほぼ一様等方平坦だが,その向こう側の世界まで考えると,宇宙原理は成り立っていない,(2)宇宙の膨張は加速している(開いている),と変化している.
20世紀後半以降の観測技術,情報処理技術の進歩により,宇宙に関する知識が著しい速さで増加しつつある.これが現代天文学の特徴であろう.この進歩は上記のすべての章の記述に反映されているが,中でも第4章と第5章が筆者には特に興味深く思われた.すなわち,地殻変動や気象等の地球の自然が,他の諸惑星の自然との比較において,より深く理解可能となったこと,いいかえれば,地球に関する科学が惑星科学の中に位置づけられたこと.また,つい最近迄,太陽系以外の惑星系についての知識は皆無といってよい状態だったが,今や「惑星系学」が可能な時代となったことが,わかりやすく説得力をもって解説されている.
地平線の内側の宇宙は全宇宙のごく一部であるが,その内側の宇宙については恒星のみならずそれを廻る惑星の姿も知られるようになってきた.宇宙についてのこの認識を,「人類の住む宇宙」なる言葉で編者たちは表現されたのであろうと思う.理系,文系を問わず,多くの人に推薦したい本である.
(2008年4月22日原稿受付)World Scientific, Singapore, 2007, xi+199 p, 24.5×16.5 cm, $49.00[大学院向・専門書]
S. D. Bass
The Spin Structure of the Proton
ISBN-13: 978-981-270-947-9
ISBN-10: 981-270-947-9
宮 地 義 之 〈東工大理工〉
本書のタイトルである「陽子スピンの構造」は,場の理論である量子色力学(QCD)に基づく陽子構造の研究において,現在までのおよそ20年間にわたりもっとも注目されてきた問題の一つである.欧州原子核研究機構で行われたEMC実験は,1988年に「陽子を構成するクォークのスピンを足し上げても陽子スピン(1/2)の2割に満たない」ことを報告した.この驚くべき実験結果が陽子スピン構造の研究の端緒となり,理論・実験の両面で様々な試みがなされている.本書ではこの20年間の研究成果が概観されている.これまでに陽子構造についての書籍はいくつか出版されているが,陽子スピンを中心に,関連分野の話題も含め,広範にかつ簡潔にまとめられているのが本書の特徴である.
第1・2章では,陽子スピン構造の研究に不可欠な,偏極深非弾性散乱,核子構造関数およびパートン分布関数等が導入される.最近のスピン依存構造関数の測定結果に加え,スピンに依らない非偏極実験からの結果も網羅されている.第3~8章では,光学定理やQCD和則等から,特にスピン依存構造関数のモーメントに関する理論的解釈が与えられている.GDH和則や核子形状因子といった陽子スピン物理に関連する分野についても,それらの最近の実験成果を紹介するとともに理論的にも考察されている.第9・10章では,構造関数に基づくパートン構造に関する研究について触れられている.第11~14章では,陽子スピンの構造をより詳しく探るために進められている様々な試みが示される.陽子スピンのクォークフレーバー構造,グルーオンスピンの役割については,最近の実験結果を中心に偏極深非弾性散乱・偏極陽子衝突による研究が紹介されている.クォーク・グルーオンの軌道角運動量に関する先駆的な研究についても,トランスバーシティーや一般化されたパートン分布関数等に関する実験結果が紹介されている.第15章には将来的な実験的研究の提案もなされている.
最先端の実験結果を広く網羅している一方で,前半の構造関数の理論的解釈には場の理論についての知識を若干必要とする.後半部分はより実験結果の紹介に重点がおかれているが,欲を言えばもう少し理論的説明があるとバランスがよかったか.とはいえ,陽子スピンの構造に関する研究を開始する学生および若手研究者が,この20年間での成果と現在取り組まれている理論的・実験的課題を把握するのに適切な参考書であるのではないだろうか.またこのテーマを専門としない研究者にも,「陽子スピンの構造」に関する研究を概観出来るものとしてお勧めしたい.
(2008年4月28日原稿受付)
共立出版,東京,2006, xxxi+428 p, 21.5×16 cm, 本体5,200円[専門書・大学院向]
K. Falconer著; 服部久美子,村井浄信訳
フラクタル幾何学
ISBN 978-4-320-01801-x
高 安 秀 樹 〈ソニーCSL〉本書は,フラクタル幾何学に関する学部後半から大学院・研究者向けの教科書である.ニュートン以来,自然科学の常識だった微分可能性を根底から覆した世界観を提示したフラクタルも,1980年代後半の大ブームから20年を経て,研究者レベルではなかば当たり前のものになっている.しかし,微積分に関する本が無数にあることと比較するとフラクタルに関する教科書は依然として層が薄く,若い世代の学生や研究者がフラクタルに絡んだ現象に興味を持ったときに,何を読んで基盤となる知識を身に付ければよいか迷うところだと思われる.そういう意味において本書の役割は極めて大きい.数学的にしっかりしたフラクタル幾何学の入門書は本書しかないといってもよいからである.基本的な導入から丁寧に書かれているので,意欲があれば学部の新入生でも読みこなすことはできるし,演習問題も充実しているのでゼミの輪講などには最適であろう.
特に,フラクタルに絡んだ自然科学の研究のなかではあいまいにされがちな,様々な次元の定義とその性質をきちんと評価している部分は,さすが,数学者の書いた教科書ならではのしっかりした内容になっている.
また,物理学との接点として重要な非線形力学系におけるアトラクターのフラクタル構造に関する章は,簡単な写像の問題から複雑な問題までよくまとまっているので,カオス現象に関心のある人は一読の価値がある.
ただ,フラクタル現象の研究への入り口としては幾何学の他に,統計学があり,物理学との接点としては後者を軽視することはできない.パーコレーションの問題やブラウン運動に関することも一通りの紹介はあるものの,残念ながら物理学的なものの見方はしておらず,自然現象とのつながりが希薄で物足りない記述に留まっている.特に,最後の物理学への応用の部分に関しては,フラクタル成長,乱流,フラクタルアンテナ,ファイナンスと項目は盛りだくさんだが,これらのキーワードに期待して読んだ読者はがっかりする内容かもしれない.とはいえ,本書はあくまで「新しい解析学の流れ」という数学の教科書のシリーズの中の一冊であるから,物理学的な視点をこれ以上要求することは,酷なことかもしれない.もし,本書と同じくらいの質と量を伴った「フラクタル統計学」というようなタイトルの教科書が執筆されれば,フラクタルに関する研究の二つの入り口が揃うことになるのであるが….
(2008年3月31日原稿受付)こうち書房,東京,1997, 125 p, 21.0×14.7 cm, 本体1,200円[一般書]
(A)首都圏大学非常勤講師組合編、(B)大学非常勤講師問題会議編
大学教師はパートでいいのか-非常勤講師は訴える、 大学危機と非常勤講師運動
ISBN 978-4876473885
こうち書房,東京,2000, 270 p, 21.0×14.7 cm, 本体2,000円[一般書]
ISBN 978-4876474691
鳥 塚 潔 〈東大物性研〉
日本物理学会は,若手研究者の就職を支援する取り組みを始めた.しかし,支援の主たる対象者は若手ポスドクないしはポスドク予備軍であり,非常勤講師の専任化については学会はこれまで関心を示してこなかった.現在大量に存在している非常勤講師は,「35歳以下」という条件をクリアできない若くないポスト・ポスドクである.非常勤講師制度は大学教育の観点からは決して正常なものとは言えず,低賃金労働に追いやる公正ならざる制度であることを考えると,学会の今回の取り組みの一環として考えて欲しいと思い,上記A, B 2書を紹介する.
大学教員には大きく分けて2種類ある.一つは,教授,准教授などの専任教員であり,もう一つは非常勤講師である.非常勤講師とは1年契約を繰り返す,授業だけを業務とする教員のことである.非常勤講師には,i)本務校のある専任教員が他大学で行なう場合もあるが,ii)弁護士など大学外に本業を持つ者,iii)大学などを定年退職した者が行なうこともあり,さらにiv)大学院やポスドク修了者が専任のポストを見つけるまでの足がかりとして行なう場合もある.iv)の専業非常勤講師は,全非常勤講師の約3割くらいと言われ,全国で約1万人いると推定されている.一時的のつもりが10年,20年と続き,いつまでも専任になれない非常勤講師が数多くいる.
A書では,「序にかえて」と「I覆面座談会 ホンネで語る大学非常勤講師」で,非常勤講師は無権利状態にあることが述べられている.まず,①非常勤講師の賃金は非常に安く,専任教員の1/6~1/10しかない.さらに,②ボーナスも退職金もなく,社会保険や年金も全額自分持ちであること,③研究を行ないたくても,研究費を大学から出してもらえないこと,④授業を行なう際に教材が必要であったとしても,それは自分持ちであること,⑤大学がカリキュラム改変を行なうなどして,その非常勤講師はもう不要となれば雇い止め(契約満了後に更新をしないこと)にされることもあること,などが切々と語られている.続く「II私たちは訴える」には,非常勤講師や非常勤講師問題を直視する専任教員ら8人の報告や手記が掲載され,巻末には非常勤講師組合の紹介が続いている.
B書では,「非常勤講師の正当な処遇を求める」と題した日本科学者会議の1999年の定期大会声明,及びユネスコが提唱した「高等教育の教育職員の地位に関する勧告」が冒頭で紹介されている.どちらも,定常的に雇用される非常勤講師の労働条件の改善を求めている.第一章では,非常勤講師は,大学で授業を行なう資質のある学者が少なかった明治時代,帝国大学の教授が私学で出張講義を担当したのが起源だと紹介されている.現在では,少子化の影響による経営難のため人件費を抑えようとする大学が多く,私立はもちろん国公立大学でも専任教員の数を減らしている.そのため専任教員だけではカリキュラムすべて埋めることができず,非常勤講師を大量に雇用するようになった.大学の歴史的変遷の中で非常勤講師が増えた理由をこのように説明している.専任教員数と非常勤講師数の比は,私立大学では1 : 1~1 : 3くらいである.第二章では,自然科学,語学など分野ごとの立場で非常勤講師問題が論じられている.特に,筑波大学の女性語学教師スキルムントさんの事件は衝撃的だった.彼女は白血病で休職していたが,あるとき上司の教授から雇い止めを通告された.理由を聞くと「余命2年だから」とのこと.この上司は職権濫用して医師から本人でさえ知らない医療情報を入手し,それを雇い止めの理由とした.それでも東京地裁は,外国人教師は任期つき契約だから解雇を正当とする判決を下した.こんなことがあると,大学には表ざたにならないすごい隠し事があるのかも,と疑いたくなる.キャンパスセクハラ問題なども第三章でとりあげられている.第四章では,労働経済学の専任教員が,大学における総人件費(パイ)が一定のとき,そのパイを専任教員と非常勤講師で分け合うことになるが,非常勤講師だからという理由だけで少ない分け前でいいのか,と問題提起している.「均等待遇」と「同一価値労働同一賃金」の原則が熱く語られている.今日の日本社会では,派遣やパートなどの非正規雇用労働者が1,730万人(総務省の労働力調査)に達し,低賃金の不安定雇用が広がっている.大学は,今日の格差社会の縮図なのである.
大学に勤務する多くの物理学会員がいることであろう.そこでの非常勤講師の実態を見ようともせずに,「若手研究者の就業支援」を語ることはできまい.自分の職場をもっと良く見て実情を知るべきであろう.A, B書とも発行されてから約10年を経ているが,今でも状況は変わっていないので一読する価値は十分にある.B書は出版社では品切れになっているが,検索機能を使えば,どこの大学図書館にあるかがわかる.
(追記: 本誌63巻6号pp. 461-464に「ある非常勤講師の場合」という記事が載っているので,併読を勧める.)
(2008年4月21日原稿受付)共立出版,東京,2007, x+239 p, 21×15 cm, 本体2,700円[大学院向]
日本表面科学会編
ナノテクのための物理入門(ナノテクノロジー入門シリーズIII)
ISBN 978-4-320-07172-8
渡 邉 聡 〈東大工〉
本書は,物理学以外を専門とする研究者や大学院生を対象に,ナノテクノロジーにおける物理を概説したものである.本書の前書き等でも述べられているように,ナノテクノロジーは様々な学問の融合分野である.この分野の研究者の多くは,自分の専門外の学問分野について知る必要性を痛感しているであろう.この意味で本書は大変時宜を得ている.本書のシリーズである「バイオ入門」「化学・材料入門」「工学入門」も同様であり,本学会員はこれらにより魅力を感じるかもしれない.
しかし,専門外の研究者や大学院生に理解しやすく物理を概説するというのは容易ではない.本書についても,これに成功したかというとやや疑問が残る.しかし後述するように,別の意味で本書は大いに推薦に値する.
1章と2章では,ナノ領域での相互作用を扱っている.電磁気的相互作用,共有結合相互作用といった見出しから基礎的かつ馴染みの話ばかりかと思うと,巨視的な物体間や固体表面-孤立粒子間のファンデルワールス相互作用についての丁寧な記述等,私には新鮮な内容も織り込まれていた.続く3章,4章では,摩擦が扱われている.この馴染み深い現象の理解がナノ領域での研究により一新されていることが述べられると共に,「超潤滑」に関する最近の話題が紹介されている.5章から9章までは走査プローブ顕微鏡やナノ電子ビーム,放射光によるナノ物性測定を取り上げているが,精密測定を可能にする技術上の要にも踏み込んだ,特色ある書きぶりである.続く2章では固液界面のナノ領域を扱っているが,電極近傍の電解質イオンの振舞いや溶液中での2物体間に働く力等について,興味深い記述が続く.最後の章はナノスケール系の電気伝導現象にあてられており,基礎から最近の話題まで,大変要領よくまとめられている.
以上の内容は,編者の専門を反映して走査プローブ顕微鏡に関する話題に偏っている感はあるものの,「摩擦」「電気伝導」等の馴染み深い概念に対してナノスケールの研究で新しい世界が開けていることを感じさせ,新鮮に感じられる部分が予想外に多かった.
「物理学以外を専門とする研究者等への物理入門」という点では,物理が苦手な読者には理解しにくいと思われる記述が多々あった.他方内容は,伝統的な物理の教科書に拒否反応を起こす読者の興味をそそる可能性がある.この点で編者の目論見はある程度達成されていよう.評者が興味を惹かれた部分には従来なら化学等の他の学問分野で扱われる内容も多かったが,これも編者の目論見なのか,あるいは著者らが分野横断的な視点や考え方を既に有しているからなのか….
ともあれ本書は好著であり,多くの方にぜひ一読を勧めたい.
(2008年4月16日原稿受付)講談社,東京,2007, 234 p, 17.5×10.5 cm, 本体880円(ブルーバックス)[一般書]
篠原久典
ナノカーボンの科学; セレンディピティーから始まった大発見の物語
ISBN 978-4-06-257566-9
中 山 敦 子 〈新潟大超域〉
一個人の好奇心が世紀の大発見へと発展を遂げるしくみに欠かせないモノは,様々な分野の科学者によるほぼ同時多発的なセレンディピティー(本来の意味は,偶然にも幸運を発見できる能力)の施行であるようだ.
今ではすっかり有名になった“C60"や “カーボンナノチューブ”.これらの研究は,意外にも炭素の材料科学には無縁そうな天文学,宇宙物理学の研究に端を発している.20世紀末は奇しくも電子顕微鏡の開発,機器分析化学の発展,計算機のめざましい進歩と普及が相まって,人間の微小なモノに対する関心がこれまでになく高まり,結果として世界中の研究者を巻き込むこととなった.本書には,『ナノカーボン科学』 ブームの火つけ役である“C60"がどのようにして発見され,科学界にデビューしたかが,筆者の目を通じて詳細に紹介されている.我こそが“Prof. C60"の名を勝ち取りたいという研究者たちの野心も随所に垣間見られる.
純粋な天体物理の興味から始まったクロトーとスモーリー,カールらによる炭素クラスターの共同研究は,C60の発見で目的が一変する.この発見の1年前にC60を生成するも,その存在にすぐには気がつかなかった米石油会社エクソンの研究グループ,大量合成に成功したクレッチマーやハフマン.前半のC60発見ものがたりの部分では,この研究にのめり込んでゆく彼らの様子が生々しく伝えられている.話を読み進めると,C60発見の15年も前に「超芳香族」というタイトルでC60分子生成の可能性を示唆していた大澤を含め,彼らは実に目に見えない線で繋がっていることがわかる.
後半部では,日本人科学者とフラーレンの関わりについて述べられている.私が小学生のころは,図書室の書棚の伝記コーナーには外国人科学者が幅をきかせていたように記憶している.だから,子供心に科学とか技術とかの発見の話はある種,お伽噺的であって日本からは遠い国での出来事に感じていた.ふと気がつけば,自分はこの本に登場する人物と「会った」ことがある,「議論した」ことがある,「共同研究をした」ことがある.それがとても不思議に思えた.そして,そのような尊くも身近な人たちの,成功談にとどまらない実験の苦労話が,私にはとても興味深かった.
この本を読む以前は,本来は器用なはずの日本人が 『ナノカーボン科学』 への参入に遅れをとったことについて,次のように考えていた.西洋画では立体を三次元的に,また,対称形を基本として描こうとするが,浮世絵に代表される日本画では,二次元的に置き換えて,かつ,非対称形の構図で描こうとする傾向があると聞く.そういった昔からある民族的な美意識の違いが背景にあって,日本人は立体をイメージするのがあまり得意ではないのだろうか? と.しかし,それは私の考え違いであり,電子顕微鏡写真を見てナノチューブやC60の存在を明らかにしたのは日本人が最初であるし,C60発見の前にナノチューブの存在もわかっていたという事実を知った.そう,日本人はアピールが足りないのだろう.そういえば,十数年前に,何度か,講演会で来日したクロトーを見かけたことを思い出した.毎回,緑色のシャツを着ていて,「この人はこの服しか持っていないのだろうか?」と知人に話したところ,「彼は緑色のシャツを何枚も持っていて,自分を印象づけるために意識的にやっているのだ.」ということを聞き(本人には確認していないが…),唖然としたことを覚えている.
『ナノカーボンの科学』 において,今のところ日本人ノーベル賞受賞者は出ていないけれど,彼らの功績が世界の頂点にあるのは世界中が認めるところである.この話の続編が出版されるのもそう遠くはないと思っている.
(2008年1月31日原稿受付)講談社,東京,2007, 263 p, 15.4×10.6 cm, 本体900円[一般書]
高田誠二
単位の進化; 原始単位から原子単位へ
ISBN 978-4-06-159831-7
国府田隆夫以前,物理学概論や総合科目の授業の始めに,古代ギリシアのエラトステネス,ヒッパルコスが地球外周や月までの距離を三角法で推定した話を紹介してきた.基線長に使われた単位(スタジオン)をメートルに換算すると,その推定値は現在知られている値とそう違わないこと,1989年にEUが打ち上げた天文観測衛星には頭文字でHIPPARCOSという名が付けられたことなどである.だが, “原始単位” という知の古層の探索には立ち入らなかった.
本書を読んで,単位という概念は文化と文明の基礎に他ならならず,文理融合教育には最適の主題だったことを改めて知った.かかる認識不足は評者だけではあるまい.この事態を正すため本書の筆者が払った努力は並々でない.その跡は,アポロ11号と基地の間の交信記録で始まる序章から明らかである.ア-ムストロング船長が,刻々と眼下に迫る月面の様子を “高度225メートル-700フィート…” と遥かな地球の基地に冷静に送信した.この感動的なエピソードを著者は次のように書く.『現代離れした “原始単位の進化” を知らざればアポロ交信の意味を解し得ず』 (p. 18).
「原始」から「原子」への偉大な単位の進化と躍進の中にも,今なお不合理ないくつもの単位が巣くっている.その素姓を知ることは科学だけでなく文化そのものを理解することだと,様々な事例を挙げて筆者は説き明かす.まことにその通りだろう.卑近な例だが,昔,米国の研究所でインチ目盛り方眼紙に苦労した.その図面で装置を作ってくれた職工さんの人柄のよさと腕前の確かさを懐しく憶い出す.
序章に続く第一話「単位の博物史」から第十三話「原子単位の世界」と後章からなる全体を通して,数々の興味深い史実が単位の時代的変遷を追って通史的に語られる.ひとつだけ例を挙げよう.惑星軌道の法則で知られるケプラーは球体を最密充填する数理幾何学問題でも知られている(たとえばG.スピ-ロ,「ケプラー予想」青木薫訳,新潮社(2005)参照).それが厳密に解けたのは1998年だったという話も毎年の授業で定番の話題だった.そのケプラーは優れた度量衡行政感覚の持主でもあり,その名を冠した多能標準器の製作者でもあった.その人間像と中世ドイツ社会の状況が,第五話「ドナウのほとりの天文学者」に活写されている.
原本は1970年に講談社ブルーバックスの一冊として出版され,毎日出版文化賞を受けた.本書はその文庫版だが,内容はいささかも古びていない.SI接頭語にゼタ,ヨタ(1021, 24)やゼプト, ヨクト(10-21, -24)が加わり(1991), “単位の進化” は今も続いている.日常感覚を離れた超巨大,超微小の時空世界では,量子揺らぎや不確定性を考慮した視点から単位や計量の意味を改めて問わねばならないだろう.“単位の偉大な躍進” とその “古い足跡” を知る意義は一層大きくなるに違いない.会員一般の一読を勧めたい “新著” である.
(2008年2月18日原稿受付)吉岡書店,京都市,iii+66 p, 21×14.5 cm, 本体750円[大学院・学部向]
中井浩二
実験の作法と安全
ISBN 978-4-8427-0341-1
近 桂一郎
著者が自分の勤務する大学での物理実験の副指導書として書いた本である.序文によると,実験には「理屈をいう前に頭や体が動いてしまうくらい,しっかり」身につけるべき「作法」がある.この作法と安全,さらにその基本にある‘こころ’が本書の主題である.内容は具体的であり,著者の経験に基づいている.机上の教育論ではない.
「第I部 物理実験の「作法」」はノート,グラフ,精度と有効数字,論文と報告書など,実験で必須のことがらをとりあげ,その中から「実験をしながら考える」,「予断を持たずに,実験結果を謙虚に受け止め,十分に吟味する」など,実験の進め方を説く.これらは実例に裏付けられていて,お説教に陥らない.続く「第II部 体験的安全講義」は火傷,化学薬品,高電圧,真空と高圧などについての安全をとり上げる.項目ごとに大先生(たとえば湯川秀樹)のエピソードを糸口にして,実際的でしかも物理に結びついた注意を述べる.さらにその後で,安全は「規則や規制だけでは護れ」ないとして,実験者の「モラル(道徳)」と「モラール(士気)」を強調する.この二つのことばは本書のテーマで,くりかえし現れる.「第III部 社会との関わり」は,まず放射線を例にして,作業者の安全と並んで社会の安全が問題であることを指摘する.続いて科学者・技術者のモラルとモラール,科学者の社会に対する責任と貢献を一般的に論じる.この部分の著者の主張,たとえば「人類を精神的汚染から守るものは,「学問」と「芸術」である」,には異論があろう.その上で,モラルの教育が「大学の実験室からはじまる」という指摘は,注目すべき発言と思う.
総じて,すぐれた物理実験入門であり,また,受難の時代にある物理実験への弁証論でもある.その特徴は,実験をする人の立場から具体的な問題を扱っていることである.多くの実験指導書も始めの部分を同じ主題に充てているが,しばしば教える側,あるいは管理する側からの記述に偏っている.
この本は,実験の科目や指導書を作り直すときのヒントを与えてくれる.また,新たに研究実験を始める学生への手引きとしても有効である.これらの場合,指導者も,自分がどのように実験をし,結果をまとめているか,さらにそれらの活動が社会とどう関わっているか,などについての反省を迫られる.本書をこのまま実験の副指導書に使うこともできよう.そのときには,学生との整合をどうとるかが,指導者にとっての問題になる.
なお,酸素ボンベの口が「逆ネジになっている」という31ページの記述は誤りである.
(2008年1月25日原稿受付)シュプリンガー・ジャパン,東京,2007, 300 p, 21×15 cm, 本体3,800円(World Physics Selection: Readings)[学部向・一般書]
C.サットン著; 鈴木厚人訳
ニュートリノでめぐる素粒子・宇宙の旅
ISBN 978-4-431-70996-1
福 田 善 之 〈宮城教育大理科教育〉
ニュートリノと言えば,2002年度の小柴昌俊先生とR. Davis, Jr.博士が「天体物理学とくに宇宙ニュートリノの検出に対するパイオニア的貢献」によりノーベル物理学賞を受賞したことが記憶に新しいが,その歴史は素粒子物理学の創生期である1930年代までさかのぼる.本書は1992年にオックスフォード大学のC.サットン氏により著されているが,1998年のスーパーカミオカンデ(SK)による大気ミューニュートリノ振動の発見や2001年のSNOとSKによる太陽ニュートリノ振動の発見とカムランドの原子炉ニュートリノによる電子ニュートリノ振動の確立,更に2003年のK2K実験によるミューニュートリノ振動の検証やカムランドによる世界初の地球ニュートリノ検出など,近年のニュートリノ物理の劇的な進展には当然ながら触れられていない.しかし,訳者の鈴木厚人先生により随所に的確な注釈を入れられているため,正確な情報を得ることができる.
鈴木厚人先生は,本書にも記載されている超新星爆発SN1987Aから発せられたニュートリノバーストの発見や太陽ニュートリノを観測したカミオカンデに参加しておられた.当時,太陽ニュートリノ観測の決め手であった20インチ光電子増倍管の高性能化や標的である純水に残存しているバックグラウンドの除去等は,鈴木厚人先生が精力的に携われており,本書にこの辺りのエピソードも含まれていると更におもしろい書物になったかもしれない.
本書の特徴はニュートリノの理論的必然性による誕生から実験による知見が広がる様子を「歴史」と「人物」に焦点をあてながら展開し,物語風に捉える工夫がなされている点であり,大学教養課程程度の学生には格好の入門書と言える.だが,それにも増して1990年代までの約60年間に物理学者達がアイデアと情熱を持ってニュートリノの謎を追いかける様子が細かに描かれており,その臨場感は専門ではない研究者にとっても興味が湧くのではないだろうか.20世紀末から始まった劇的なニュートリノ研究の成果は,実はそれまでになされた研究者達の驚くべき好奇心と行動力が支えになっていることを,改めて実感させられる良書である.
(2008年2月5日原稿受付)Springer, Heidelberg, 2007, xii+388 p, 24×16 cm, US$199.00 (Topics in Applied Physics Vol. 105)[大学院向・専門書]
K. Rabe, Ch. H. Ahn, J.-M. Triscone, eds.
Physics of Ferroelectrics: A Modern Perspective
ISBN 978-3-540-34590-9
勝 藤 拓 郎 〈早大理工〉
私のように特に強誘電体研究を専門にしているわけではない人間のところにこの本の書評が回ってきたのは,マルチフェロイクを始めとする分野を跨いだ研究の進展によって,他分野の研究者にとっても強誘電体の基礎的な知識が必要になっていることを反映しているのであろう.この本がそうした観点から書かれたというわけではないが,“A Modern Perspective"という副題からわかるように,典型的な強誘電体の教科書とはかなり異なった書かれ方ではある.まず,日本の強誘電体の本なら一番強調されるであろうソフトフォノンの話は一切出てこない.また,水素結合型強誘電体なども出てこないし(出てくるのはほとんどすべて酸化物強誘電体である),最近流行のリラクサーの話もない.正統的な話としては,強誘電転移のランダウ理論がかろうじて出てくる程度である.一方,強誘電体メモリーなどの応用に際して重要になる問題,たとえば分極疲労やリークの問題についてもほとんどページは割かれていないし,圧電性能に関するも記述も少ない.本書で解説されているのは,ランダウ理論の他には,ベリー位相を用いた分極の理論,第一原理計算による予測,磁性と強誘電性が共存したマルチフェロイク,強誘電体薄膜の作製方法,薄膜におけるサイズ効果とドメインの振舞い,である.また,ランダウ理論に関しては,代表的な強誘電体における具体的なパラメータ値が巻末に掲載されている.
各章の中では,ベリー位相を用いた分極理論の章と,ランダウ理論による相転移の記述の章が分かり易く書かれている.特にベリー位相に関しては,比較的最近の話ということもあって他の本では見られない内容であり,かつ提唱者であるVanderbilt本人による解説という点でも一読の価値がある.また,薄膜作製方法の章には,PLD, スパッター,MBEについてそれぞれの専門家による詳しい記述があり,実際に強誘電体薄膜をつくる人にとって参考になるであろう.マルチフェロイクの章は(書かれた時期が早いこともあるのだろうが)比較的あっさりしているので,詳細な解説を期待される向きには肩透かしになるかもしれない.
強誘電体の物理といっても,ソフトフォノンのように純粋な学問的興味に基づくものから,分極疲労のように応用上の問題から生まれたものまで幅広い.本書は,ちょうどその中間をついたものともいえるが,さてこれだけで強誘電体が理解できるかというとやはり心許なく,各自の必要に応じてもう一冊(あるいはそれ以上)の教科書が必要になりそうである.というわけで,値段の高さ(200ドル)が気にならない人であれば,他の教科書と並べて一冊揃えておくのもよいであろう.
(2008年2月26日原稿受付)
World Scientific, Singapore, 2007, xv+194 p, 27.7×21.6 cm, US$31.00[大学院向]
A. Sessler and E. Wilson
Engines of Discovery; A Century of Particle Accelerators
ISBN: 13 978-981-270-071-1, ISBN: 10 981-270-071-4
木 原 元 央かつて加速器の本といえば, M. Stanley Livingston(Lawrenceの学生としてサイクロトロンを最初に成功させた)の “High-Energy Accelerators" (Interscience Publishers, 1954)が手頃な入門書であり,J. P. Blewettと共著の “Particle Accelerators" (McGraw-Hill, 1962)が数少ない専門書として読まれた. また, Dover の Classics of Science Seriesの一冊として出版された“The Development of High-Energy Accelerators" (1966)では,Livingstonの解説付きで加速器の重要な原著論文が編集されており,大変重宝した.一般向けに出版された“Particle Accelerators: A Brief History" (Harverd University Press, 1969)もまた名著であった.Livingstonは加速器の偉大な研究者であるとともに,教育者,啓蒙家であった.今では,加速器の本は決して少なくないが,そのようななかで本書の刊行にはどのような意義があるだろうか.
著者のAndrew Sessler(米)は,加速器の理論的研究で一時代をリードし,研究所長もつとめた人物である.社会問題にも多大の関心を寄せている.Edmund Wilson(英)はCERNを中心に活躍した理論家で,CERN Accelerator Schoolを組織して世界中の若手の教育に情熱を傾けている人物である.
1970年代以降,加速器のエネルギー・フロンティアはシンクロトロンからコライダーへと移っていくが,Sessler は (C. Pellegrini と と も に)
Livingstonの先例に倣い,コライダーに関する重要な原著論文に解説を加え,アメリカ物理学会のKey Papers in Physics Seriesの一冊として“The Development of Colliders" (1994)を編纂している.そして今回,Wilsonと共著で本書が刊行されたわけであるが,評者はこの本に接し, SesslerにLivingstonの衣鉢を継ぐ偉大な「語り部」の姿を見る思いがする.本書は加速器の発達の歴史を,それに関わった「人物」に関するエピソードと重ねつつ,読者に読ませようとしている.これは科学の姿を後代に伝える上で重要なことである.新しい原理の発見や技術開発の成功に至る試行錯誤が描かれており,おもしろい.このような本が可能になったのは,著者の学識と(それ以上に重要なことは)幅広い交友関係のお陰であり,余人をもってしては困難であったであろう.著者自身にも,今ここで書いておかねばという熱い思いがあったのではなかろうか.
本書には加速器に関する入門的な説明はないので,ある程度の予備知識を持って臨んだ方が,本書の面白さは倍加するであろう.それを前提として考えると,本書は大学院生向きであり(素粒子をやろうという学生なら一度は眺めてもいい),研究者向きである.それに加えて,大学で物理の教育に携わっている教官にもぜひ目を通してもらいたいと思う.評者の経験から,大学低学年の教材の一つに加速器の発達の歴史を取り上げるのは悪くないと思っている.加速器は,本書のタイトルが示すように, “Engines of Discovery"であり,学生の科学への興味を刺激するのに格好のテーマである.
また,科学ジャーナリストにもお勧めである.もちろん,科学史研究者には貴重な資料である.加速器は現在では,素粒子分野だけでなく放射光,中性子のような物性の分野でも新しい計画が進んでいる.本書の後半部分において加速器の現在と将来について概括的な解説がなされているので,全体像を把握する上で一読の価値がある.このような本は,ぜひ大学の学科の図書室に備えることをお勧めする.
(2008年1月9日原稿受付)アグネ技術センター,東京,2007, xiii+440 p, 21.5×16 cm, 本体5,000円[大学院向,専門書]
佐川眞人,浜野正昭,平林 眞 編集
永久磁石-材料科学と応用-
ISBN 978-4-901496-38-4
藤 森 啓 安 〈電気磁気材料研〉
近年の工業用永久磁石は,アルニコ,フェライト,SmCoからFeNdBへと急速に変わってきている.性能が大幅に上がったためである.本書は,その強力永久磁石ネオマックスFeNdBに焦点を当てながら,永久磁石の発明・改良の歴史,物理,材料科学技術,応用について詳細に解説した専門書である.大学院初学者の入門書,また,研究者,技術者の座右の書として最適である.
本書の構成は,I序論:永久磁石の発展と歴史, II基礎編: 基礎物性, 保磁力,III材料編:アルニコとFe-Cr-Co磁石,フェライト磁石とそのボンド磁石,希土類磁石とそのボンド磁石,IV評価・応用編:磁石の測定と安定性評価,磁石の磁気回路と設計,磁石の応用の4編13章から成り,加えてV付編:JIS規格,単位,用語,磁石寸法比とパーミアン係数などの資料が付記されている.現在第一線で活躍中の専門家12名が各章を分担執筆している.充実した内容である.
I編の序論は,ネオマックスの発明者である佐川眞人氏とその発明にヒントを与える結果となった講演をした浜野正昭氏が執筆している.まず1章で佐川氏が自身の発明から応用開発までの苦労と感激を振り返りコメントしており,本書の導入に強力な印象を与えている.当時,アモルファス金属などの新素材ブームの中,永久磁石の分野ではSmCoの性能向上が頭打ちになり次のブレークスルーを模索しCo系からFe系に関心が移っていた.しかし磁化も結晶磁気異方性も大きいFe系希土類化合物は見つからなかった.佐川氏は,そのような時,日本金属学会・希土類研究会の講演で浜野氏が「Fe系希土類化合物ではFe-Fe間の距離が近いのでキュリー点が低く磁化は大きくない」と指摘したことを聞き,それならCやBを添加して距離を広げたらどうかと考えたと云う.それがネオマックス研究の始まりであったと氏は振り返っている.時を同じくして,アメリカの研究者達もFe系希土類物質で磁石特性を見出し始めており,1983年の3M国際会議で佐川氏とアメリカグループの同時発表となった.本書の紹介者は,丁度,その会議にアモルファス軟磁性の発表で出席しており,佐川氏とアメリカグループの熱気溢れる発表を聞く機会に出会った.本書12ページに載っている佐川氏講演の写真は昨日のように思い出す光景である.佐川氏は,発見だけに留まらず,むしろそれまでよりも何十倍も大変な実用化を成し遂げ新強力永久磁石ネオマックスFeNdBを完成させた.本多光太郎のKS磁石,三島徳七のMK磁石,加藤与五郎・竹井武のOP磁石に次ぐ久しぶりの日本発の歴史的快挙である.
このように日本は永久磁石では世界を常にリードしているが,2章ではその歴史を上述の浜野氏が纏めている.MK磁石が基になってアルニコ磁石が開発され,同時に,単磁区磁石の原理が解明された経緯,OP磁石と同じ頃Baフェライトが開発された経緯,その後希土類磁性の基礎研究が進んでSmCo磁石が開発され,暫く後にFeNdBネオマックスが出現して今日に至った経緯,等々を磁石の基本から材料の技術問題にも言及しながら解説している.他の磁石も挙げて丁寧に記述している.この序論だけで磁石の全体像を把握することができる.しばしば磁石の強さを最大エネルギー積で示すが,本書でも図示されており,それによるとネオマックスのエネルギー積はKS, MK, OP等の約60倍,Baフェライトの約10倍,アルニコの約8倍,SmCoの約2倍にも及ぶ.如何に強力であるか,数センチ角のネオマックス磁石でパチンコ玉大鉄ベアリング数100個を持ち上げるデモンストレーションから実感できる(表紙と内表紙の写真).
さて本論であるが,II編の3章でまず磁性の起源および物質の磁性を復習し,次いで磁石に関わる磁性体の磁気構造と磁気異方性,多結晶や微粒子のヒステリシス磁化過程,保磁力,最大エネルギー積,磁区構造などの原理と機構をモデルを示しながら議論している.併せて,磁石材料の作製法の基本を解説している.中でも希土類・鉄族化合物の結晶構造・電子構造・磁気構造の関係,および,磁化・キュリー温度・結晶磁気異方性の大きさについての議論は強力磁石を考える上で有益である.さらに保磁力の問題を改めて4章で取り上げ,単磁区・多磁区構造と磁壁のピン止め挙動などの詳しい考察を行なっている.
III編では,代表的な磁石を取り上げ,実際の磁石特性を具体的に論じている.5章は金属合金磁石の代表であるアルニコ(Al-Ni-Co-Fe系)とそれと類型のFe-Cr-Co系の説明である.これら合金では状態図の特徴からスピノーダル2相分解を起こし,その結果,単磁区構造微粒子が形成され高保持磁力が得られる.あらゆる磁石の基本を成す単磁区理論を明快に説明している.Fe-Cr-Coのスピノーダル分解組織写真は,極めて鮮明に典型的な単磁区構造を映し出しており,教育的効果も大である.次にフェライト磁石について,6, 7章で焼結磁石,ボンド磁石の実際を説明している.フェライト磁石は現在でもネオマックスよりも多量に使われている重要な磁石である.最後に8, 9章で希土類磁石を取り上げ,希土類・鉄族化合物の結晶構造と磁性,それらの相図と相分離,Sm-Co系磁石(SmCo5, Sm2Co17)とFe14Nd2B系磁石の組成,組織,特性,ならびに,それらの鋳造磁石,粉末焼結磁石,ボンド磁石の実際を解説している.この8, 9章は本書のハイライトであり,現在の最先端の研究状況を知ることができる.例えば,FeNdBは磁化が大きい割にはキュリー温度が低いのでDyを添加してそれを改善しているが,Dyは希少資源であるので他に変わる方法がないか,最近の重要研究課題になっている.ところで,FeNdBの高磁化と低キュリー温度の関係は丁度インバーと類似していて興味深い.本書ではこのような物性的興味にも言及している.
IV編は永久磁石の特性評価と応用に当てられ,10章では磁石のヒステリシス減磁曲線の直流およびパルス測定法,ならびに,熱ゆらぎ磁気余効,磁化の温度特性,磁気異方性トルクの一連の測定法と解析法を記述している.磁石研究で必要不可欠な実験技術が網羅されている.11章では応用に必要不可欠な問題として磁気回路について述べている.磁石を用いたデバイスの多くは永久磁石と鉄ヨークから成り,その磁束の磁路は,電源と導線の電気回路にアナロジーである.そのモデルに立ってデバイスの磁界設計法を論じている.12, 13章では具体的な応用としてモーター,ボイスコイル(VCM), 磁気共鳴断層装置(MRI), リニアモーターを取り上げ永久磁石の機能と効果を解説している.
最後のV編では,A項で永久磁石のJIS規格,B項で磁気の単位,C項で磁気物理量の用語,D項で磁石寸法とパーミアンス係数のグラフについて纏めている.磁石の実験,解析,応用設計,使用にあたって役立つ資料である.
以上,本書が取り上げている内容の概要を紹介した.強力永久磁石ネオマックスFeNdBの応用は急上昇を続けているが,それに伴い新たな研究課題も生じている.本書はさらなる発展を促す一助となるに違いない.
(2008年1月16日原稿受付)
Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2007, 550 p, 24.7×17.4 cm, £45.[大学院向,専門書]
J. Rammer
Quantum Field Theory of Non-equilibrium States
ISBN 978-0521874991
北 孝 文 〈北大理〉
本書は実時間Keldyshグリーン関数を用いた非平衡摂動展開に関する教科書で,500ページを越す大著である.著者はこの分野でよく知られた研究者で, 1985年の博士論文が翌年にReviews of Modern Physics 誌 [Vol. 58, p. 323]に掲載され,Keldyshグリーン関数法を習得したいと思う研究者が必ず目を通す文献となっている.また,2004年には,同じ著者による「Quantum Transport Theory」という本も出ている.まず,1章と2章がいわゆる「第二量子化」に当てられ,50ページを割いて詳しく解説されている.専門家は読み飛ばすこともできる.一方,初学者にとっては,概念的な記述が多く,やや難解かもしれない.3章でSchrodinger表示とHeisenberg表示が解説され,遅延・先進・Keldyshグリーン関数などの様々なグリーン関数が導入される.著者も認めているが,この段階で多種類のグリーン関数が出てくるのは,初学者の混乱を招く可能性がある.また,T積を用いた時間推進演算子の導出は「Quantum Transport Theory」の記述に委ねられている.4章と5章が非平衡摂動展開の解説で,本書における方法論の中心である.4章で閉じた往復時間経路上の摂動展開が説明され,Wickの定理の証明や自己エネルギーおよびDyson方程式の導入が行われる.5章では,前章の摂動展開を通常の時間-∞<t<∞に還元することが行われ, 2×2の行列Green関数とそのDyson方程式が説明される. 3章で導入した様々なGreen関数も,ここでその意味がより明らかになる.この4章と5章は,基本的に上記のReviews of Modern Physics誌の記述を踏襲しており,特に新たな内容や記述の改善は見当たらない.6章は線型応答理論の実時間摂動展開を用いた書き換えである.7章は量子輸送方程式(Boltzmann方程式)の導出で,Dyson方程式に勾配展開を施し,さらに準粒子近似を適用するという標準的手法が用いられている.8章では超伝導の準古典方程式が扱われている.9章ではSchwingerの汎関数微分法を用いた場の量子論の再構築が行われ,10章では有効作用の方法に基づいて弱く相互作用するボーズ凝縮系が考察される.11章では主に線型応答理論の範囲内で不規則系が扱われる.最後の12章では,超伝導量子渦の動力学が,現象論的モデルに揺らぎを導入するという方法で論じられる.まとめると,非平衡グリーン関数法の方法論に関する説明では上記のReviews of Modern Physics誌の記述を踏襲している.また,応用面で扱われている主題は広範多岐で道具立ても厳しいが,平衡状態の松原グリーン関数など他の平易な手法でも計算できる内容が多い.評者は非平衡グリーン関数法に大きな可能性を感じているのであるが,本書が「非平衡グリーン関数を使って何の御利益があるのか?」との素朴な問いに明快な答えを用意してくれなかったのは残念である.
(2008年1月8日原稿受付)日本評論社,東京,2007, viii+291 p, 21×15 cm, 本体4,300円[大学院向,専門書]
佐古彰史
超対称ゲージ理論と幾何学; 非摂動的アプローチ
ISBN 978-4-535-78468-0
伊 藤 克 司 〈東工大院理工〉
この本は超対称性を持つゲージ理論の非摂動効果に関する話題,特にSeiberg-Witten理論から最近の重要な成果であるNekrasovの公式までについて解説している.著者の佐古氏は素粒子論の研究室の出身であるが,その後は数学の研究室で研究を続けられている位相的場の理論の専門家である.最近の超弦理論と超対称ゲージ理論に関係する非摂動効果に関する進展は著しいものがあり,多くの興味深い成果が得られている.それは,超対称性や双対性という性質をめぐり多くの理論物理学者や数学者が協力し得られてきたものである.その広がりは多岐にわたるが,専門家以外はこの発展の興奮を味わう機会はなかなかないであろう.非専門家にもその一端を感じさせてくれるのがこの本である.
SeibergとWittenは1994年の論文において,N=2超対称ゲージ理論の低エネルギー有効理論を特徴付けるプレポテンシャルと呼ばれる量を楕円曲線の周期の情報で非摂動効果まで含め完全に決定した.その後この理論を超弦理論におけるDブレインと双対性の枠組みで実現する試みが行われた.さらにその結果はソリトン理論,位相的場の理論,位相的弦理論,同変コホモロジーと固定点定理,非可換時空上のインスタントンの構成等の手法と組み合わされて結実したのがNekrasovの公式である.この公式は,グラビフォトン場による補正を含むプレポテンシャルをあらわな形で求めた驚異的な式である.
まえがきにもあるように,この本は著者の数学者向けの集中講義に基づきそれを膨らませて書かれた本であるということである.従って,この本では物理的な背景の解説は大きく省かれ,教科書というよりは講義録のスタイルに近い形になっている.これはページ数からいってやむをえないことであろう.
第1章は場の理論の速習コースで,場の理論のキーワードを数学者向けに翻訳しながら超対称性までを説明している.第2章は電磁双対性を中心としたSeiberg-Witten理論の解説である.第3章はN=2理論をツイストして得られる位相的場の理論からN=4理論の分配関数に関するVafa-Wittenの理論まで,第4章は非可換空間上の場の理論と非可換時空上のインスタントン解のADHM構成まで,第5章は非可換空間とN=2超対称ゲージ理論でNekrasovの公式に至るまでの解説となっている.第1章から第3章までは一般的な解説,第4と5章は,著者の論文の内容が詳しく解説されている.
本書はこの分野の概観をつかむには丁度良い長さだと思う.内容について詳しく読み込んだりゼミ等でテキストとして使う時には,原論文をそばにおいて批判的に読んでいくのが効果的だと思う.
(2008年1月8日原稿受付)Oxford Univ. Press, Oxford, 2007, xiii+591 p, 24×16.5 cm, US$150.00 (Oxford Science Publications, Oxford Series on Synchrotron Radiation 7)[大学院向・専門書]ISBN: 978-0-19-851017-8
W. Schulke
Electron Dynamics by Inelastic X-ray Scattering
石 井 賢 司 〈原子力機構放射光〉
物質の性質を知るために光に対する応答を調べるという手法は古くから行われてきたものである.その歴史において,新しい光源の出現が革新的な測定技術を生み出してきたが,X線領域でも同様である.従来,X線を用いた散乱実験と言えば回折を利用した結晶構造解析が主なものであった.しかし近年の放射光光源の発展により桁違いに高輝度のX線が利用できるようになったことで,より強度の弱い非弾性散乱を利用して物質の電子状態,電子ダイナミックスを研究することが現実的なものとなってきた.現在,SPring-8(日本),APS(アメリカ),ESRF(フランス)などの第三世代と呼ばれる大型の放射光施設では,X線非弾性散乱用のビームラインがいくつも建設され研究が行われている.
本書は黎明期の頃からX線非弾性散乱による固体,凝縮系の研究に携わってきたW. Schulke教授によって書かれ,Oxford Series on Synchrotron Radiationの一冊として出版されたものである.序文には1988年から出版の計画があったと書かれているが,第三世代の放射光の利用が成熟期に入り,X線非弾性散乱による研究が活発となった今,まさに機を得て世に出たと感じる.X線非弾性散乱の本としては1991年に出版されたE. Burkelの“Inelastic Scattering of X-ray with Very High Energy Resolution"があるが,それと比べてみてもこの十数年での発展の目覚ましさがよくわかる.
X線は主として電子の電荷によって散乱され,その散乱強度は物質中の電子電荷の動的相関関数に対応するが,散乱時のエネルギー・運動量変化の大きさ,さらにある場合には利用するX線自体のエネルギーによって観測される励起状態が当然変わってくる.本書ではこれらに従って分類し,価電子励起,内殻電子励起(X線ラマン散乱),コンプトン散乱,共鳴非弾性X線散乱,と章立され,最後にX線非弾性散乱全体を通した一般的な理論の章が加えられている.各章では,基本概念,実験装置とともに豊富な実験結果が示されており,X線非弾性散乱の初心者やこれから実験を行ってみたい者にとっては極めて有用な教科書となるであろう.実験装置に関する説明も十分にあるので,実際に放射光施設で実験を始めるときの戸惑いも少なくなるのではないだろうか.さらに,本書の特徴としてreferenceが充実している点が挙げられる.2005年あたりまでのほとんどすべての論文等が引用されており,この分野の過去の成果を概観するための辞典としての利用も可能である.一方で,分野外の方には,ざっと読んでいただくだけでも,X線非弾性散乱で何が測れるのか,どういう物理量が得られるのか,を知っていただくことができると思う.
最後に,最近ではX線非弾性散乱の重要な一領域となっているフォノンの観測,及び,軟X線の非弾性散乱については,残念ながら本書の対象範囲外となっていることを付記しておく.
(2008年1月28日原稿受付)
科学倫理検討委員会編
科学を志す人びとへ
化学同人,京都,2007, vi+152 p, 23.9×18.5 cm, 本体1,800円[一般書]
ISBN-10: 4759811397, ISBN-13: 978-4759811391
青 木 勇 二 〈首都大理工〉
社会に大きな影響を与える科学の分野において,研究成果発表または資金使用の不正が近年頻々と発生していることに起因して,科学倫理の重要性が高まってきている.このような状況の中で,将来の科学を担う若者に,科学研究活動の仕組みやルールをきちんと理解してもらうことは,大学教育の一つの役割であろう(私が所属する大学でも,大学院GP事業の一環として,科学倫理教育に取り組み始めた).しかし,倫理教育のプロではない我々教員が,研究の現場で学生を正しく指導することはなかなか難しい(私を含めて,多くの大学教員の学生時代には,科学倫理の教育プログラムの類はカリキュラムに存在せず,研究室内における研究活動の現場で,指導教員や先輩から口コミで行動指針を伝授されただけ,という方が多いのではないだろうか).また近年盛んになってきた産学協同研究を行う際には,様々な難しい規則が付随する.本書は,これから研究者になろうとする若者の手引書として執筆されたものであるが,大学教員にとっても良い教科書になると思うので,ここに紹介したい.
本書では,「科学とは何か」と題して,データの取り扱いから研究費の申請まで,科学活動の中身を見直しながら,研究をどう進めるべきか,そこで発生しうる不正や不適切な行為は何かわかり易く解説される.さらに,科学の望ましい進歩のためには研究業績の評価が不可欠であるが,その仕組み(ピアレビュー,SCIデータベース,インパクトファクターなど)は正しく理解し活用されなければならないことなど,我々がきちんと認識しておくべき事柄が説明される.
社会科学的な切り口で,「社会における科学の位置づけ」やその構造を分析する見方は面白い.競争,業績評価に基づく研究資金配分などが組み込まれた,現在の科学研究のシステムは,科学が合理的に発展することを目指して発展的に作られてきた.しかし,この科学と社会の間の複雑な境界において,ゆがみや問題が発生しやすい状況にあることが指摘される.この両者の間で「適正な関係を模索し続けることが求められる」と締めくくられ,簡単には解が得られない複雑な状況にあることが認識させられる.
不正を防止するために,どのような分析や活動が実際に行われているかについては,最近の文献とともに豊富な具体例が紹介されており,世界的な動きを理解することができる.特に,“Publish or Perish"というフレーズで表現される競争的研究環境の先進国である米国では,FFP, QRP, RCRなどの省略語を用いながら不正の度合いが分析整理されたり,e-learningを含む教育プログラムが開発されていたりする点は興味深い.
過去の様々な事故の原因を分析し教訓として活かす手法が「失敗学」(JSTの「失敗知識データベース」参照)として知られているが,科学活動の不正においても,同様な分析や情報の公開が有益だろう.本書では,ベル研究所でのシェーンの高温超伝導論文捏造を始めとする幾つかの事例が紹介され,どうすれば防ぐことができたのか議論される.巻末に掲載された「困った時のQ&A」は,直面する可能性のある具体的な問題に対して,解決方法のアドバイスが与えられており,若い学生や研究者にとって有益だろう.これらの幾つかは,2007年に定められた本会の行動規範(学会誌Vol. 62, No. 10, p. 792)の骨格を,具体的に肉付けし,より身近なものにするという意味で重要だろう.
本書は,日本学術会議の科学倫理検討委員会での討議内容をもとに,著名な物理学者を含む執筆者によるものであり,物理学の研究事情を踏まえた科学倫理を考える上で内容に違和感はない.
倫理教育と言えば,不正行為に焦点を当てたネガティブな側面が中心になりがちだが,「新たな研究のアイデアはファンシーでなければならない」と若者を勇気付け,指導者には「若者を育て独立させる指導者の責任と重要性」を説き,科学者コミュニティーのあるべき姿を指し示す本書の建設的な側面は,読者にエネルギーを与えてくれる.
(2008年1月24日原稿受付)
川畑有郷
固体物理学
朝倉書店,東京,2007, vii+232 p, 21.5×15.5 cm, 本体3,200円(物理の考え方3)[学部向]
ISBN 978-4-254-13743-9
遊 佐 剛 〈東北大理物理〉
「固体物理学」というと固体の物性を扱う学問であるわけで,材料で分類しただけでも金属,半導体,磁性体,超伝導体,誘電体などなど,とにかく幅が広い.したがって,固体物理,物性物理というタイトルの本は名著と呼ばれるものから,名著の解説? と思われるものなど,英文,和文ともにたくさんあることは,このページを読んでくださっている読者の皆さんであれば,ご存じのことであろう.初版が約50年前にさかのぼるキッテルの固体物理の教科書などはいまなお更新され続けていて驚かされる.
さて,本書は物性理論の分野で多岐にわたって活躍をされている川畑有郷氏が,理論や実験的な研究の独創性を重視して書かれた学部向けの本で,特に第一線の研究者が感じる新しくて独創的な発見の楽しさや重要さを読者に伝えようというスタンスから書かれている.固体物理のさまざまなトピックスが比較的短い解説で明瞭に書かれているため,それぞれのトピックのエッセンスを直観的に掴みたいと考えている学生諸君に有効活用してもらえるのではないだろうか.
もちろん,もう少し物理に立ち入って本質的に理解するためには,さらなる専門書をあたらなくてはいけないことはいうまでもないことだが,専門的な固体物理の本をかじったあとで本書を読んでみると,固体物理のそれぞれの分野をつなぐ横糸のようなものが,よりよく理解できるようになるかもしれない.
最近の物性研究のホットなトピックも随所にちりばめられていて楽しい.たとえばカーボンナノチューブ,フォトニック結晶など,これまで大学の授業オンリーの生活から脱却し,研究室に配属されて研究生活をスタートした学生諸君には身近に読めるのではないかと思う.
(2008年1月9日原稿受付)
産業技術総合研究所
きちんとわかる計量標準
白日社,東京,2007, 435 p, 18.8×13 cm, 本体1,500円(産総研ブックス02)[一般書]
ISBN 978-4-89173-118-2
髙 田 誠 二 〈久米美術館〉
「計量」とは,本書pp. 11~14によれば「はかる道具で何らかの量をはかること」,また「計量標準」とは「計量の標準あるいは基準」,「現代社会における経済と産業の基盤」であり,JISなどの工業標準とは別物である.
さて,12章より成る本書の狙いは「計量標準の研究の最先端」を「きちんとわかる」ように語ることであるわけだが,私は,以下,4つの立場を区別しつつ本書を紹介たいと思う.
①本学会の一会員の立場で:この種の記事を載せる誌面は,1960年代には本誌にも何回か用意されたのだが,その後は応用物理,計測,計量史の学会誌のほうに重点を移した感がある.この事情を顧みるだけでも,本書はここでの推奨に値すると言いたい.
②研究者OBの一人の立場で:私は1980年に計量標準研究の現場を離れ,それ以後の進展とくに「長さの単位メートルの定義」の革命的変更は,活字で知ったものの,数値の由来や実験技法の細部の「耳学問」は不可能になった.加えて2001年には日本の研究組織に大きな動きがあり,人脈頼りの情報獲得は困難さを増した.
こうした不可能さ・困難さに直面していた私は,本書を通じて一挙に最先端の状況を総括することができた-長さ標準「メートル」と時間標準「秒」の分野に関しては周波数コム(comb)という新技法,質量標準「キログラム」を体現する原器については,一方ではその安定性の極限的な確認,他方ではアボガドロ定数またはプランク定数による新標準摸索の趨勢,更には,超音波,標準物質のような,斯界でも新しい課題への果敢な取組み等々.
私のこうした開眼と同類の印象は,本書の読者すべての脳裏にさまざまな形で刻み込まれるであろうと信ずる.
③一読書人の立場で:表現(トレーサビリテイ,黒体といった用語,国際単位系の全貌など)の面では,「わかりやすくする」ための一層の工夫とりわけ「索引」制作の配慮があればよかったのではないか.
④現役の科学技術史研究者の一人の立場で:現場最先端の研究者は,歴史を顧みる暇など持たぬと言うだろうが,「メートル」に付きまとう299 792 458という数値をはじめ,歴史に触れてこそ「わかる」事柄も多々ある.温度標準をボルツマン定数に依拠して考え直すという発想では,エントロピー概念の位置づけが気になる.また,トレーサビリティのような「計量の社会的機能」に関しては科学技術社会論や計量史の学会での議論も活発になった.現場の方々からの発言も期待したい.
(2008年1月9日原稿受付)
J. P. Freidberg
Plasma Physics and Fusion Energy
Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2007, xvii+671 p, 25×18 cm, \16,717, £75.00
(US$135.00)[大学院向]
ISBN-13: 9780521851077
長 山 好 夫 〈核融合研〉
本書はFreidberg教授のMITでの講義ノートである.各章末には問題がある.理学系と言うより工学系大学院の教科書だと思った.B5版667頁の大著であるが,文学的表現も難しい単語もなく,2行以下の短いセンテンスで淡々と書かれている.数式は第一原理から数学的に導いているわけではなく,理解を助けるために使用しているといった風である.数学を重んじるなら,輸送理論の専門家が書いた教科書(R. Hazeltine and J. Meiss: “Plasma Confinement," Addison-Wesley, 1992)を脇に置いて読むと良いかもしれない.
第一部は炉工学に関するもので,従来のプラズマ・核融合の教科書では最初の8頁(宮本健郎:「核融合のためのプラズマ物理」,岩波書店,1976)ないし14頁(J. Wesson: “Tokamaks," Oxford, 1987)で記されている内容である.それが108頁と大幅に拡充されており,ITER時代の教科書とはこういうものかと思った.はじめに,核融合エネルギーの背景として,世界のエネルギー事情について石炭,原子力から風力,太陽エネルギーまで概観する.自己点火についてはパワーバランスという名の小節で,0次元パワーバランス方程式を用いてローソン条件だけでなく熱不安定や最小出力まで論じており,実践的である.核融合反応の物理については,核融合反応断面積や衝突断面積を(量子論を使わず)古典的に計算し,教育的(直感的)である.第一部の最後は簡単な炉設計論である.数式を用いてブランケットの厚さや超伝導コイルの厚さなどを計算し,熱出力2 GWの無印トカマク炉の主要諸元を導く.以後折に触れて物理を無印トカマク炉に適用し,物理と炉工学の接点とする.
文章には説得力がある.例えば「ブランケット内では中性子の速度は5.5 cmで減衰するため,熱中性子との反応断面積の大きなLi6(天然では7.5%しか含まれていない)と核反応し,トリチウムを生成する」とのくだりで目から鱗が落ちた.しかし,エネルギー事情については図もなく,核融合会議開発戦略検討分科会報告書(http://www.aec.go.jp/jicst/NC/senmon/old/kakuyugo/siryo/siryo136/siryo2.htm)の「第1章 核融合エネルギーの将来像」の迫力はない.炉工学に関しては専門書(関雅弘:「核融合炉工学概論」,日刊工業新聞社,2001)とは比べるベくもない.第一部については良くも悪くもプラズマ物理学者の著作である.
第二部は核融合のためのプラズマ物理学であり,プラズマの閉じ込めと安定性が記述されている.はじめに全体を概観し,各種の周波数やデバイシールドなどを軽く紹介する.そして,クーロン衝突を含めた磁場中の単一粒子の運動を84頁かけて展開する.これは核融合プラズマ物理学で重要な新古典拡散理論や改善閉じ込めの理解にはどうしても必要だからである.これも従来の教科書よりはるかに充実している.
次はMHD(電磁流体力学)である.MHDの基礎である二流体モデルから始める.続いてトカマクだけでなくθピンチやZピンチ,ヘリカル等を例に取り,またフープ力など各種の力を分類し,51頁かけてMHD平衡を説明する. そして37頁かけて理想MHD不安定性を説明する.ここでも各不安定性の物理的描像を図示しながら概観する.ティアリングモードも高速イオン励起不安定性の記述もないが,炉設計上は不要と考えたのだろうか.MHDの締めくくりに応用編として,ダイポールからステラレータまでの各種核融合プラズマ閉じ込め配位を116頁で説明する.トカマクは円形断面からSTまで書かれている.非円形度や逆アスペクト比によるqなどの各種パラメータの近似式があるのは良いが,ベータ限界の近似式がないのは炉設計にとっては不満である.バルーニング-キンク不安定性,導体シェル効果などの記述があるのもやはり最新の教科書である.
輸送については85頁かけて説明する.まず,面倒な輸送理論への免疫を付けるべく目的とする輸送方程式(フーリエの熱伝導方程式)の形を示す.次に,ランダム運動や粒子の衝突の原理を図と式で説明し,拡散係数と熱伝導係数を導く.円筒トカマクについて加熱も入れた拡散方程式を解いてみるので教育的である.そしてトカマク炉に応用する.新古典輸送理論もできるだけ直感的に説明する.しかし,ポロイダル断面の射影の図だけであり,トロイダル方向の運動の図がないのでは説明が苦しい.とはいえ,数式の豊富なHazeltine and Meissの本では図もなく直感的理解は不可能だし,図の豊富なWessonの本もブートストラップ電流の説明は貧弱であるので,本書が一番まともかもしれない.輸送理論の次に実験的なスケーリングが示され,新古典輸送理論とは温度依存性が逆であると述べる.
実質的な最後の章では,加熱と電流駆動を99頁かけて解説する.NBIの項では必要事項(ビームの侵入長,中性化効率)がまとまっている.しかし,NBI駆動電流がない.一方,高周波による加熱と電流駆動については量が多いようだが,ランダウダンピング,Xモード,小数イオン加熱,低域混成波電流駆動,等々波動物理には学ぶべき項目が多いのであって,簡潔で要を得た記述である.
最終章は核融合研究の将来と題して,ITERについて主に記述する.本書は大変分厚いのだが重要事項をいくつか書いていない.まずプラズマ壁相互作用関係はほとんどない.また乱流理論と閉じ込め改善の物理も貧弱である.トカマク回路論も触れていないので位置不安定性のフィードバック制御については記述がない.炉工学では第一壁の耐中性子束,ダイバータの熱流束などの重要課題には踏み込んでいない.だから,最終章で説く核融合研究の将来像もITERより先には踏み出しておらず,したがってSTにも理解がない.
とはいえ本書の欠点は専門書で補えばよい.本書は核融合プラズマの物理的描像を直感的に理解させようとする点が優れており,学生に分かってもらおうと一所懸命講義するFreidberg教授の姿が目に浮かぶようである.学生だけではなく,教員にとっても核融合の講義の参考にすると大変役に立ちそうだし,研究者の手元に置いても損はないと思う.なお,Freidberg教授の旧著の〓“Ideal Magnetohydrodynamics,"
Plenum Press (1987)の中古本には新刊の4倍の値が付いている.
(2007年11月27日原稿受付)
安藤恒也,中西 毅
カーボンナノチューブと量子効果
岩波書店,東京,2007, viii+74 p, 19×13 cm, 本体1,300円(岩波講座 物理の世界 物質科学の展開3)[学部・大学院向]
ISBN 978-4-00-011126-3
山 本 貴 博 〈東理大理〉
本書のタイトルにある「カーボンナノチューブ」はその名の通り,炭素原子のみからなる管状物質で,直径は数ナノメートル,長さは数マイクロメートルに及ぶ.ナノチューブはその特異な構造を反映したさまざまな興味深い性質を持つことから,物理学や化学の枠にとどまることなく,電子工学や生命科学など幅広い分野で活発に研究・開発されている.書店に足を運べばナノチューブを銘打つ本が啓蒙書から専門書までずらりと並んでいるが,本書のようにナノチューブの基礎物性を理学の立場から解説した邦書は意外と少ない.
本書は岩波書店から出版されている小冊子シリーズの1冊であり,カーボンナノチューブが示す特異な量子現象,とりわけ電子状態,光学現象,電気伝導現象に関して著者らの理論研究成果を中心に解説したものである.理論中心ではあるものの,難解な数式を多用することなく物理的描像が簡潔明快に説明されているので,専門家でなくても楽しく読み進めることができる.
さて本書の具体的内容であるが,第1章では,ナノチューブの構造とその記述法が要領よくまとめられている.第2章では,グラフェンを連続体と見なし有効質量近似を行うことによって,グラフェン上を運動する電子が質量ゼロのディラックフェルミオン(=ニュートリノ)と見なされることが説明されている.その結果,グラフェンを丸めてつないだ構造であるナノチューブ上を運動する電子は,アハラノフ・ボーム磁束が貫いた円筒上を運動するニュートリノと見なすことができる.本書は一貫して,このニュートリノ描像に基づきナノチューブに特有の量子現象を解説している.特に,金属ナノチューブにおける後方散乱の消失とそれに伴う理想コンダクタンスの説明は見事である.
また本書は,実験データが各章でバランスよく紹介されている.8章ではナノチューブのトランジスタへの応用例がいくつか紹介されており,ナノチューブ研究分野において基礎研究と応用研究が密接に連携しながら発展している様子が伝わってくる.この有機的な連携こそナノチューブがナノサイエンス・テクノロジーの中心的役割を担うゆえんであろう.しかしながら最終章で著者らも指摘するように,わが国のナノチューブ研究は応用上の興味が先行しがちであり,実験とその解析においてまだまだ粗さが目立つものが多いのも事実である.本書の中でも今後解決すべき課題や現在研究進行中の課題がいくつか挙げられており(例えば,多層ナノチューブの層間相互作用効果など),ナノチューブ基礎研究分野の現状と課題が活々と伝わってくる.この点は通常の教科書とは異なる特記すべき本書の特徴である.
以上の理由から,本書は幅広い読者層にお勧めすることができるが,特に,これからナノチューブの専門家を志す大学院生には,ナノチューブ量子物性を概観する入門書として本書を推薦する.
(2007年10月1日原稿受付)
R. P.ファインマン,M. A.ゴットリーブ,R.レイトン著; 戸田盛和,川島 協 訳
ファインマン流物理がわかるコツ
岩波書店,東京,2007, xiii+190 p, 21.5×15.5 cm, 本体2,800円[学部向]
ISBN 978-4-00-005955-8
石 井 廣 湖
「ファインマン物理学」は周知のようにファインマンがカリフォルニア工科大学で行った講義をまとめたもので,発刊以来40年以上の長きにわたり世界中で愛読されてきた教科書である.その序文の中で「どうやって問題を解くかという講義を3回,また回転系の講義に続く慣性航法についての講義が1回あるが,これらは残念ながら省いた」と記していた.序文のこの文章に動かされた二人の著者(ゴットリープと, 『ファインマン物理学』 の共著者の一人故レイトンの子息ラルフ・レイトン)が当時の録音テープを探し出しまとめあげたのが本書である.ユーモアにあふれ学生に語りかけるそのままの形で記されているので,滑らかな日本語訳も相まって,ファインマンの講義を教室で聴いているかの思いを起こさせる.
この4回の講義は授業に困難を感じる学生を対象にした補講で,ファインマンが物理をどう学ぶか学生(読者)に語りかけてくる.
初めの三つの講義は,物理を学ぶ基礎として,まず微積分やベクトルの基礎の要点を復習をし,公式の暗記と反復練習を奨める.次いで,どうしたら物理がわかるようになるか,どうやって物理の問題を解くかについて,それは公式に何かを当てはめてできるようなことではなく,いろいろな問題の意味がわかるようになるまで繰り返しやることで身につくことだと述べて,いくつもの例題を提示しさまざまな角度から解いていく.題材は力学からとられているが,簡単な機械の動作からロケットや惑星の運動,パイ中間子の質量の決定へとテーマが広がっていく.問題を解いていく説明のなかに,計算する前に推論をして答えを予想せよ,計算結果を実際に起きていることと比較せよ,等々の考え方のコツがちりばめられている.
講義の進め方で興味深かったのは,説得力のある説明をずっと進め結論を導いたあとで, “本当にそうかな?” と問いかける.そして “この考え方は不十分で答えは正しくない,実際はどうなのかの 「感覚」 を持って欲しい” と注意して,改めて正解に到達し直してみせる.学生のレベルに戻って一緒に考えるユーモラスで教育的なやり方である.
4番目の講義は,回転運動の物理が技術にどう応用されているか学生が興味を持てるように,ジャイロスコープの原理と応用が実演を通して詳しく語られる.そして話は天文学と量子力学での角運動量にも及んでいく.
このように本書は問題を解きながら物理の学び方を語り,物理を学ぶ学部学生にはうってつけの読み物である.なお,対象は物理の苦手な学生となっているが,最高レベルの学生が集まったカルテクでの話であって講義内容の水準は高い.物理の得意な学生はますます物理に引き込まれていくに違いない.しかし,そうでない学生には少し難しいのではないだろうか.
ファイマンは, 「教える」 ことを抜きにして自分は研究者として生きていけないと,エッセーの中で述べている.彼のなかでの研究と教育のあいだのフィードバックの重要性を語るものだが,それは本書においても,教育への熱意として,また内容の深さ・広がりとして表れている.そのどちらも学生に物理への興味を喚起する極めて大切な要件だ.昨今の学生の物理離れ,学力低下の状況のなかで物理教育に携わる方々にはぜひ一読をお奨めしたい.
なお,本書には付録として「ファインマン物理学はいかにして生まれたか」 が 『ファインマン物理学』 の共著者の一人サンズによって書かれていて科学史的にも興味深い.
(2007年12月11日原稿受付)
広瀬立成
物理学者,ゴミと闘う
講談社,東京,2007, 230 p, 17.5×10.5 cm, 本体720円(講談社現代新書)[一般書]
ISBN 978-4-06-149887-7
井 野 博 満
著者の広瀬さんは1938年生まれで私と同年である.私と同じ東京都町田市に住んでいる.そこでゴミ問題に取組んだ活動をされている.その活動グループのことは話には聞いていたが,広瀬さんのことは全く存じ上げていなかった.この本を読んだあと,一度,あるゴミ問題の集会で広瀬さんと顔を合わせたが,自己紹介をする機会を逸し,そのままになっている.広瀬さんが町田でゴミ問題について活動をされているのに対し,私は何もしていないという負い目をちょっと感じている.
さて,この本は,著者が定年退職を2年後に控えたある日,近くに住む主婦3人の訪問を受け,それまでの「高エネルギー物理学」分野という「たこ壷」から顔を出してゴミ問題に関わることになった経緯から書き始められている.ゴミ問題に関わることになっていろんな本を読んで勉強するうちに,地球環境の基本的なしくみを理解する法則がすでに物理学のなかで議論されていることに気づいた, という.「エントロピー増大の法則」に関わる議論である.それを知って霞がすーっと消散していくのを感じたと書かれている.また,ケニアのマータイさんが3R (reduce, reuse, recycle)キャンペーンのなかで「もったいない」という日本語を使ったことにも感銘を受けたという.
本書は,第1章 地球をまるごと把握する,第2章 基本法則は教えてくれる,第3章 生命を宿す星・地球のしくみ,第4章 「捨てる心得」-持続可能な地球のために,第5章 「もったいない文明」の夜明け,終章「もったいない社会」はソフトランディングで,となっている.
第1章の始まりは, 「たこ壷思考」 から「ふろしき思考」へとある.伝統的な物理学研究者から,環境問題を包括的な視点で把握するための「ふろしき思考」への転換が書かれている.生命系の理解から自然界の物質循環とそれができない人工物質とが対比される.第2章は熱力学第一法則・第二法則のやさしい解説,第3章はエントロピー論に基づく地球システムの理解が紹介される.第4章以降がゴミ問題に当てられ,町田市での著者らの活動を織りまぜながらその解決の方向を探っていく.ここが本書の白眉と言えるだろう.
ここに展開されている著者の主張はおおむね私たちが以前からエントロピー学会で考え,議論してきた内容に沿っている.書かれている内容は著者のゴミ問題への取り組みの活動を除いてさほど目新しいものではない.エントロピー論の考え方が,広瀬さんのようなエントロピー学会外の方にも支持され影響力を持ったということはうれしいことだが.
少し物足りない点を言えば,1-3章で紹介されているエントロピーを基礎とした物理学の考え方は,4章以降のゴミ問題の解決法を探る上で欠かせぬ視点であるにしても,コストや人手あるいは利潤追求の経済システムという直面する現実のなかでどこまで通用するのか,その矛盾を書いて欲しかった.市民活動の中で考えていくということでしょうけれども.
ちょっと考えさせられてしまうのは,3人の主婦の訪問をきっかけに「たこ壷思考」 から 「ふろしき思考」 へ飛躍した,と書かれているが,広瀬さんは長い現役時代に公害問題や環境問題をどう考えておられたのか,ということである.意地悪い質問をするようだが,「たこ壷」で研究してきた「高エネルギー物理学」という専門分野と「ふろしき思考」で発見した世界とは全くつながっていなかったのだろうか.物理学でつながっていると言えば言えるが,私が問いたいのは2つの仕事に関わる価値観の問題である.広瀬さんの場合,専門分野の研究と環境問題での問題意識がどのような関係にあったのだろうか.
本書からは,楽しみながら生き生きと社会的活動をされている著者の様子が伝わってくるが,あまりに前向きで現役時代を含めた物理学者の生き方の悩みは感じられない.広瀬さんは,私と同じ市に住んでおられるので,私が家庭という「たこ壷」から顔を出せば,どこかでお会いする機会がありそうだ.いつか話を伺いたいと思う.
(2007年11月5日原稿受付)
S. N. Ahmed
Physics and Engineering of Radiation Detection
Elsevier, Academic Press, Amsterdam, 2007, xxiv+764 p, 24×16 cm, $95.00[大学院向・専門書]
ISBN13: 978-0-12-045581-2 ISBN-10: 0-12-045581-1
村 上 哲 也 〈京大理〉
「放射線」というと今でも世間一般では危険なものと思われがちであるが,近年「放射線治療」を筆頭に「放射線」の恩恵を受ける機会が急速に増えている.実際,毎年のように「放射線計測の進展」にだけ焦点を当てた国際会議が数多く開かれている.本書の著者は,このように凄まじい早さで発展し続けている分野のスペシャリストとして,「放射線計測」の技術的な側面だけでなく,その背景にある物理原理をカバーする新しいタイプの教科書作りに果敢に挑戦している.最初の章では,伝統的な放射線計測の教科書と同じように放射線の性質と放射線源を主に扱っているが,斬新なことに何とLaserを光子源というくくりの中に登場させている.これ以外にも,これまでの教科書ではほとんど登場する機会のなかった液体検出器のために短いながら1章を割いたり,データ解析に使われる汎用のソフトウェアーについて独立した1章を使って説明を試みたり,随所に工夫が見られる.
最後まで目を通してみて分かったが,本書は,“…Engineering…"という題名からすぐに連想してしまうような,素粒子・原子核・宇宙物理の実験を企画する物理屋を主な読者と想定した教科書ではない.むしろ,最近日本国内ではその数が少ないことから論議をよんでいる医学物理士,それに医学物理士の教育に携っている教員をそのターゲットとしているように思われる.医療現場での応用が急速に進んでいる放射線の “Position Sensitive Detection and Imaging" に独立した 1 章を割り付けていることや,“Dosimetry and Radiation Protection"の章に多くのページを割いていることからも,そういう著者の意図が汲み取れる.もちろん,“Imaging"については,素粒子・原子核・宇宙物理の実験分野でも技術開発が急で,この話題を扱った点で本書は歓迎されるだろうが,もう少し踏み込んだ技術面の記述があれば良いのにと思うのは評者だけだろうか.
本書の特徴の1つに,どの章から読み始めても無理なくその内容が理解できるように,基本的なことが繰り返し書かれていることがあげられる.加えて,例題を多く取り入れ,本文中で説明,導出された式の具体的な数値計算を読者が自然に行えるようにしてある.この工夫によって,本書の実用性はかなり高くなっている.例題の部分は,背景色が少し暗く設定されて目立つようにしてある.各章末にはかなりの数の練習問題が用意されていて,全体の理解を助ける役目を果たしている.しかし,非常に残念なことに,本書には単純な校正ミスも含め100カ所余りのエラーが見受けられる.特に致命的なのは,例題の中で位取りが間違っていたり,代入している数値が不適当であったりして,最終的な答えが正しくないものがいくつかあることであろう.本書を参考書として使う人は細心の注意が必要である.著者の新しい試みが報いられるためにも,早期にこれらのエラーの修正が施された改訂版が出されることを切に祈る.
(2007年10月22日原稿受付)
Cambridge Univ. Press, 2007, xx+515 p, 25×18 cm, £45.00 (US$80.00) [大学院向・専門書]
M. Dine
Supersymmetry and String Theory; Beyond the Standard Model
ISBN-13: 9780521858410
川 村 嘉 春 〈信州大理〉
本書は超対称性と弦理論の現象論に関する第一人者である Michael Dine 教授がカリフォルニア大学サンタ・クルーズ校および国内外のスクールで行った講義をもとにして作成したものである.執筆の主な意図はこれから研究生活を迎えようとする大学院生に対して,その準備の手助けを提供することにある.高エネルギーの素粒子反応に関する豊富なデータの蓄積と驚嘆すべき物理現象の発見が期待されるLarge Hadron Collider (LHC)の稼動が間近に迫ったこの時期に出版されたことは真に当を得ている.
本書は付録を除いて,3部構成になっている.第1部のテーマは「標準模型」である.標準模型に関する摂動論的性質や現象論の他に,非摂動論的性質,大統一理論,磁気単極子,テクニカラー模型などが紹介されている.第2部のテーマは標準模型を超える物理の有力候補である「超対称性」についてである.超対称性とその破れ,超対称性標準模型,超対称性大統一理論,超対称性に関する動力学について明解な解説がなされている.さらに,宇宙論や天文物理学に関する話題も取り上げられている.第3部のテーマは「弦理論」である.様々な弦理論,コンパクト化の機構,非摂動論的性質などが要領よく紹介されている.さらに,余剰次元についても取り上げられている.このように標準模型を出発点として,最近の発展を含めて素粒子理論全体を概観するような教科書は他に例がなく貴重な図書である.将来,「超対称性」や「弦理論」が物理学者の必須アイテムとなった場合,本書の価値は長く維持されるに違いない.
標準模型はその成立からおよそ30年もの間,(様々な問題をはらみながら)素粒子物理学の最先端の理論として君臨し続けている.LHCが標準模型を超える物理の解明に対して,その突破口となる可能性が高い.そこで,どんな物理が明らかになるのか? 宇宙に関する謎は解けるのか? 弦理論の尻尾を掴まえられるのか? などなど,興味は尽きない.本書を読破すれば,ワクワクする気持ちを抑え切れなくなるのではないかと思うくらい興味深い内容を網羅した本である.ただし,広範な題材を扱い,技術的な面よりも本質の説明に重点を置いているため,(一を聞いて十を知る学生にとっては十分であるが,そうではない学生にとっては)本書だけでは十分な理解が得られないと思われる箇所がある.一を学んで十を理解するための訓練の題材とするのもよし,原論文やレビュー論文などにその都度当たるのもよし.いずれにせよ,準備する価値は十分にあると思う.なぜなら,活躍の舞台がすぐそこにあり,このような機会はそうたびたび訪れるものではないからである.
(2007年10月17日原稿受付)NHK出版,東京,2007, 653 p, 19×14 cm, 本体2,900円(一般書・学部向)
L. Randall著; 塩原道緒訳; 向山信治監訳
ワープする宇宙; 5次元時空の謎を解く
ISBN 978-4-14-081239-6
千 葉 剛 〈日大文理〉
本書はLisa Randall著「Warped Passages: Unravelling the Universe's Hidden Dimensions」 の邦訳である. われわれの住む3次元空間は高次元時空に埋め込まれた「面」(ブレーン)であるとするブレーンワールドを解説したものである.著者は,余剰次元を用いた超対称性の破れの新しい機構(anomaly mediation)を提唱したことでも著名な素粒子物理学者であるが,本書のテーマでもあるワープした(曲がった)余剰次元を用いて,素粒子物理学における階層性問題や余剰次元のコンパクト化の問題に関して新しい解決を試みるモデル(ランドール・サンドラムモデル)を提唱したことでも著名である.
中身は,数式なしとはいえ,かなりしっかりした教科書風のつくりになっている.各章の終わりには覚えておくべき事柄をまとめてある.本書は6部構成となっていて,最初の部では次元・余剰次元・ブレーンについてたとえ話を使いながらわかりやすく紹介してある.それに続いて相対性理論・量子力学の概観,素粒子の標準理論とそれを超える試み,ひも理論とブレーン,ブレーンワールド,と進んでいく.素粒子論の部分は標準理論の成立・その諸問題と標準理論を越えた理論の試みがコンパクトにまとめられていて,現代素粒子論への良い解説ともなっている.
世界文学を読むときに登場人物のメモがないと苦労するように,著者の提供する相対性理論・量子力学・素粒子論(標準理論・大統一理論・超対称理論・超ひも理論)の膨大な知識の山に,読者は最初,戸惑いを覚えるかもしれない.その山を登り終えると,著者自身によるワープした(曲がった)余剰次元の話題にたどりつける.途中,研究上の個人的な体験がそこかしこにちりばめられていて,豊富なたとえ話とともに読者を飽きさせないように工夫されている.ところどころに見受けられる訳のぎこちなさは許される程度のものである (アノーマリー仲介 (anomaly mediation), 共同作業(collaboration)等).数式を用いていないとはいえ,本書に書かれている内容を深く理解しようとすれば,理系の学部生でも歯ごたえのあるものかもしれない.学部のゼミのテキストとしても使ってもよさそうだ.また,科学研究をめぐる物語としても読めるであろうから,専門家・非専門家を問わず興味深く読めるはずである.
本書は「きれいな本」である.これは何も著者の容貌とは関係ないことだが,流行歌の一節に続いて童話風の物語を挿入する各章のつくり方しかり,装丁しかり.薄ピンク色の表紙は本屋の理系の書棚の中ではひときわ目立つ.思わず手にとって見たくなるであろう.
(2007年9月13日原稿受付)
西成活裕
渋滞学
新潮社, 東京, 2006, 251 p, 19×12.8 cm, 本体1,200円(新潮選書)[一般書・学部向]
ISBN 4-10-603570-7 ISBN 978-4-10-603570-8
中原明生〈日大理工〉
本書は,車の渋滞という日常的に身近に体験する現象が人間の社会活動特有のものではなく実は物理的法則で表せる普遍的な現象であることをわかりやすく一般向けに解説しています.
著者の西成氏は,非線形波動の数理的な研究で著名な方ですが,そのユニークな語り口で親しまれ,最近,テレビの様々な科学番組で「渋滞学」について熱く語っている姿は学会員のみなさんもご覧になっていると思います.
本書の構成は,まず「1.渋滞とは何か,2.車の渋滞はなぜ起きるのか」から始まり,車の渋滞のメカニズムについて,高速道路の渋滞の観測データと数理モデルのシミュレーション結果を比較しながら,わかりやすく説明しています.
次に,「3.人の渋滞,4.アリの渋滞,5.世界は渋滞だらけ」では,渋滞は,人間の避難行動,アリの行列だけでなく,工学的にはインターネット・粉粒体の流れ,医学的には体内の血液・リボゾーム・分子モーターの流れなど,いたるところで起きる普遍的な現象であることを様々な具体例を用いて解説しています.
そして最後に,「6.渋滞学のこれから」ではこれまでに得られた渋滞学の考えや知識を今後どのように様々な分野に応用していけるか語ってくれています.
この本は,一般向けにわかりやすく書いてあるだけでなく,これからこの分野に進もうという若い学生さんにも研究の指針を示す良書だと思います.
現在の理科離れの教育現場では,ゆとり世代の若い学生さんには「物理は難しくとっつきにくい」と避けられがちですが,この「渋滞学」の本を読んで,物理的な考え方がいかに身近な現象の理解と応用に役立つか,その面白さと重要性をわかって欲しいと思います.
朝倉書店,東京,2007, xv+662 p, 26.5×19 cm, 本体28,000円[大学院向]
石渡信一,桂 勲,桐野 豊,美宅成樹編
生物物理学ハンドブック
ISBN 978-4-254-17122-8
宗 行 英 朗 〈中央大理工〉
本書の構成は,第0章 生物物理学の問うもの; 第1章 蛋白質; 第2章 核酸と遣伝情報系; 第3章 脂質二重層,モデル膜; 第4章 細胞と生物物理; 第5章 神経生物物理学; 第6章 生体運動; 第7章 光生物学; 第8章 構造生物物理,計算生物物理; 第9章 生物物理化学・方法論; 第10章 概念,アプローチ,方法,となっている.第1章から第3章までが基本的な生体分子ごとの分類,4章から7章までが,おおよそ生命現象のうち生物物理的に見て興味深いもののピックアップ,8章から10章までが方法論・理論的アプローチ中心の章立てとなっている.なんとなく様々な階層の話題が雑然と並んでいるような印象を受けるところもあるが,それがかえって生物物理の活気のある猥雑さを表しているような気がする.評者の独断と偏見で書かせていただくならば,第1章から第7章までは,どちらかというと生物学,生化学的知識をもとに,どのように生物物理学分野での研究が展開されつつあるかを理解することに,第0章と第8章以降はどちらかというと,模索的な部分を含めて物理学ないし,物理化学的知識・手法を生物物理学にどのように生かしていくか,その展望に関する現在の状況を理解することに役立つように思われる.生物物理の分野は研究対象,研究方法とも非常に広い範囲にわたっている.興味のある研究対象を生物ないし生体物質の示す現象の中から見つけて,そこに踏み込もうとするとき,本書の前半に書いてあるようなことが今まで進んできた研究のお手本,あるいは自分がこれから手がけようとする対象に対する基礎知識のまとめとして役に立つであろうし,現在の研究対象に対して自分が用いている方法論,理解の枠組みに不足を感じるときには本書の後半に書かれているようなことがヒントになると思う.評者は最初から最後まで読んだわけではないが,後半の部分によりひかれるものを感じた.また,幅広い分野に対して横断的な知識・理解を得ておくことが,さらに現在行っている研究の発展のきっかけとなることも期待できる.そのようなときに本書は,ちょっと自分の専門とは離れているけれど,「これってどうなの?」というようなことを思ったときにも便利であると思う.
記述は良くも悪くもわかりやすい.良くも,というのは文字通り良い意味で,文章のスタイルは各執筆者によってかなり違っているが,いずれも読者のことを考えて親切に書かれているという意味である.悪くも,というのは本書の性格からして仕方のないことと思うが,方法論や理論の突っ込んだ説明が欲しいと思うところも,わりとあっさりとした解説になっているところが見受けられることである.その代わり書いていることが難しすぎてチンプンカンプン,という印象を受けることはほとんどない.そしてほとんどの項目に参考文献のリストがつけられているので,詳しくはそれらを参照という意味であろう.研究を志す者を対象にしてコンパクトにまとめるならば,当然の書き方だろう.取り上げられている項目としては,雑誌の特集記事やシリーズものの解説書などにあるものと重なるところもあるが,往々にしてこれらの書物に書かれる記事が著者の研究結果を中心とした解説で,ややもすると広く一般的な知識を伝えるものではないことが多いのに対し,本書はスタイルは個性的であるものもあるが,内容はおおむね標準的といえる解説がなされていると感じた.そのためいちいち疑いながら読む必要がなく,安心感がある.教科書に準じる「ハンドブック」という形にふさわしい書き方だと思う.このような点は学問領域全体を俯瞰しようという編集者の意図が生きている.ただ,若干項目の書き方の詳しさにはばらつきがあって,実のところ読んでみても,項目としてあげられた事項の効用が書かれているだけで,中身がよくわからないような記事もあったが,参考文献がついているので,それを読めば理解できるであろう.
一つ残念だったのは,索引,特に欧文索引があまり充実していないことである.ハンドブックであるからこの点は仕方がないかもしれないが,本書は辞書的に使われる場面も多いと思われる.論文を読んでいて,知らない英単語,あるいは通常の辞書の意味では解釈できない単語を生物物理の文脈で捉えたいことは多いだろう.しかし本書の欧文索引はそのような用途には少し役不足な気がする.項目によっては,その項目から一つも英語での表現が索引に抽出されていないのではないかと思うようなところもあった.日本語の説明文の中に英単語が頻繁に挟まると読みにくくなるのも事実であるが,何とかひとくふう欲しかった.
本書は図書館の本棚に鎮座させておくべき本というよりは,日常的に手に取ってみたいものである.ハンドブックというには大きくて,カバンに入れて電車の中で読む,というようなスタイルには向かないが,研究室のテーブルの上にいつも置いておいて,議論をするときに知識レベルで確かめたいことが出てきたときや,論文の背景になる基本的な知識を手っ取り早く整理したいときなどにも便利そうである.
(2007年10月9日原稿受付)朝倉書店,東京,2007, viii+596 p, 22×15.5 cm, 18,000円[学部・大学院向・専門書]
M. Le Bellac, F. Mortessagne and G. G. Batrouni著;
鈴木増雄,豊田 正,香取眞理,飯高敏晃,羽田野直道訳
統計物理学ハンドブック-熱平衡から非平衡まで-
ISBN 978-4-254-13098-0
安 田 千 寿 〈琉球大理〉
統計物理学は,多数の基本的な部分から構成される系の性質を理解する上で有用であるため,従来の物理学だけでなく,化学,生物学,情報科学,経済学などの様々な分野で用いられており,これからもその範囲は広がると思われる.そのため,統計物理学の広い範囲を俯瞰でき,必要に応じて参照できるようなハンドブックは有用であろう. 本書は, 2004年に発行された‘Equilibrium and Non-Equilibrium Statistical Thermodynamics'を統計物理学の分野でも著名な研究者が邦訳したものである.
「ハンドブック」 と聞くと, どのような本をイメージするだろうか? 非常に広い範囲の内容が辞書的にまとめられ,その分野をすでに勉強した人が必要な事項を簡単に参照できる本だろうか? ここで強調したいことは,本書がこのようなハンドブック的特徴だけを有しているわけではないことである.そもそも原著のタイトルには,‘Handbook'の文字はない.
本書には,平衡系と非平衡系,そして数値的計算手法に関する内容までもが約600頁の中に実にバランスよく含まれ,ハンドブックとしての役割を果たしている.具体的には,熱力学,古典統計,量子統計,臨界現象,繰り込み群,モンテカルロ法,局所平衡状態,輸送現象,線形応答などが含まれる.訳者も前書きで述べている通り,原著者が統計物理学を専門とする研究者ではないことが,本書をこのようなバランスのよい内容にしているのかもしれない.また,各章の内容は多数の節で短く分けられ,必要な事項を参照しやすいようにしてある.用いる数学に関する付録や参考文献の紹介も充実している.
一方,本書はいわゆるハンドブックにとどまらない.一つの章は,本文,基本問題・研究課題で構成されている.本文では,その章に関する内容が適当な定式化を用いて論理的に解説されており,読者がその定式化の範囲内で理解できるように配慮されている.また,各章の内容も有機的につながるような解説がなされている.例えば,第一章では,熱力学と後の章で述べられる統計力学の関係を明確にするために,エントロピー最大の原理を仮定した定式化を採用し,抽象的だが簡潔な説明を与えている.しかしながら,そのために言及できない項目も出てくる.その点に関しては,異なる見方や理解の仕方があることを本文中で注意したり,漏れた項目を基本問題や研究課題で取り上げている.基本問題や研究課題では,式の導出から本格的な課題まで様々なトピックスが具体的に与えられている.特に,評者にとっては中性子星やクォークに関する課題が新鮮であった.
このように,本書は統計物理学の広い範囲を網羅したハンドブックとなるだけでなく,統計物理学の初学者にとっても教育的な本となっている.
(2007年10月19日原稿受付)朝倉書店,東京,2007, vi+256 p, 21.5×15.5 cm, 本体4,800円(朝倉化学大系10)[大学院向・専門書] ISBN 978-4-254-14640-0
徂徠道夫
相転移の分子熱力学
阿 竹 徹 〈東工大応セラ研〉
分子熱力学とは耳慣れない言葉であるが、著者が2003年3月の御定年まで務められた大阪大学大学院理学研究科附属分子熱力学研究センターの名前に使われている。本書で著者が述べておられる文章をお借りすれば、マクロな熱力学量を原子・分子のミクロな次元の事象に積極的に関連づけることを意図したものであるとのことである。そこではミクロな知見と化学熱力学で得られるマクロな知見を、統計力学、量子力学を媒介として相補的に照応させることによって、物質世界の理解が一層深まるものと期待されている。 本書はそのような視点のもとに、一般の読者を想定して書かれているが、いわゆる物理化学の教科書とは異なり熱力学そのものの解説はされていない。著者が生涯をかけて進めてこられた物理化学物性分野の研究成果がまとめられたものである。物質が機能を発現するメカニズムをエネルギーとエントロピーの観点から理解することを目指し、熱力学がいかに役立っているかを示したいという著者の意欲が示された書である。本化学大系は単著を原則とし、著者の個性を重んじる編集方針とのことであるが、その意味で単著の利点がいかんなく発揮されたものといえよう。 最初の3章は1。分子熱力学とは、 2。熱容量とその測定法、 3。相転移、 である。この部分は本書の導入部に当たるが、教科書的ではなく、本書を読む上で必要な熱力学とその測定法が簡潔にまとめられている。 次の2つの章は4。分子結晶と配向相転移、 5。液晶における相転移、である。ここでは分子の凝集状態における配置と配向の秩序に注目した相転移について、著者の多くの研究成果が実例としてあげられ、詳細に説明されている。 次の6章以降は6。分子磁性と磁気相転移、 7。スピンクロスオーバー現象と相転移、 8。電荷移動による相転移、 9。サーモクロミズム現象と相転移、である。これらの章こそは著者の研究業績の中核を成すものであろう。多くの実例があげられ、詳細な説明がされている。基本的には本書全体に亘っていることであるが、断熱型熱量計を用いた精密熱測定による熱容量(比熱)、 エンタルピー、 エントロピー、自由エネルギーなどの熱力学関数値の絶対値の決定、とりわけ熱測定によってのみその値を得ることができるエントロピーの重要性が語られ、それが著者の研究成果において鮮やかに実証されていることは圧巻である。 本書は物性分野の限られた部分について、一人の著者の経験に基づき一貫したまとめ方のもとに著されたものであり、単著の利点が生かされたものとして評価できる。他方、単著であるための誤解や欠落も見受けられるが、やむを得ないことであろう。一人の著者によりそのライフワークがまとめられたというユニークな書であると同時に、熱力学がどのように研究に用いられているかを具体例で理解できる好著として一読をお薦めしたい。 (2007年8月23日原稿受付)
中根良平,仁科雄一郎,仁科浩二郎,矢崎祐二,江沢 洋編
仁科芳雄往復書簡集; 現代物理学の開拓 I コペンハーゲン時代と理化学研究所・初期 1919-1935
II 宇宙線・小サイクロトロン・中間子 1936-1939 III 大サイクロトロン・ニ号研究・戦後の再出発 1940-1951
みすず書房,東京,2007, xix+587 p (pp. 879-1465)+175 p, 21.5×16 cm, 本体15,000円[一般書・専門書] ISBN 978-4-622-07263-8
岡 本 拓 司 〈東大総合文化〉
駒込の日本アイソトープ協会には、日本の原子物理学の開拓者であり、現在はおそらくクライン-仁科の公式を通してその名を知られている仁科芳雄が、生前理化学研究所(理研)で執務室としていた部屋が愛用の机や黒板ごと保存されている。この机の中には、仁科がやりとりした書簡を中心とする重要な資料が保管されていたが、長い間、その事情を知っているのは何人かの関係者に限られていた。 ニールス・ボーアの下で量子力学の創成期を含む足かけ6年のあいだ研究に従事し、帰国してからは理研で理論・実験の両面で量子力学に基づく最新の物理学研究を指揮し、戦後は理研や学術会議の指導者としての重責をになった仁科の文書類の公開は、仁科個人に関心のある人々はもちろん、科学の現代史の研究全般に関わりをもつ人々にも強い刺激を与えるものであることが予想されていたと思われるが、さまざまな理由から資料の全貌は明らかにされてこなかった。本書は、仁科の机の中から見つかった書簡類を中心とする1、400点あまりの資料を活字におこしたものである。日本における自然科学、とくに物理学の研究・教育の展開に関心のある人々、歴史の中で科学の果たした役割に興味のある人々にとっても読み応えのある書物となろう。 本書全体は書簡集であるが、第1巻の冒頭と第3巻の末尾には解説がある。特に第3巻末尾の解説は仁科の学問面の活動に関する評伝といってもよい詳細なものである。さらに、各文書には丁寧な注が付されており、両方を読むことで仁科の活動や当時の日本の科学界についての理解が深まるようになっている。歴史の研究をしてみれば分かるが、膨大な書簡群も、個人のものを見ているだけではそれらの間の脈絡は十分には理解できない(幸いに仁科の場合は自分の書いた手紙の多くについて写しが残されているが)。 本書も、 新発見の書簡群のみならず、GHQ文書などのその他の多様な関連資料の調査と採録によって成り立っており、また、それらの文書が、前後に置かれたものが互いに理解の助けになるよう配列されている。書簡集は通常、歴史の研究者が必要に応じてひも解く程度に扱われるものと思われるが、本書は、全3巻を通してひとつの読み物を構成しているともいえる。 本書以外のものからの知識も援用して、たとえば以下のような物語を読み取ることができる。仁科の物理学者としての経歴は、理研の研究生となったことから始まったが、この措置は長岡半太郎と鯨井恒太郎の合議で決まった。仁科の留学は、理研から派遣されていた菊池泰二がイギリスで客死し、これに代わって仁科が送られたことにより実現したが、この決定は長岡によってなされたものと思われる。本書には、菊池に代わって派遣されることを夢想した土井不曇と仁科との交流を伝える書簡もある。先達の配慮で物理学研究を開始した仁科は、帰国してからあとは、自身の研究を、後進を育成しながら進めていくという役割をにない、朝永振一郎、湯川秀樹らの庇護者ともなった。この世代の成果が海外で評価される際にも、仁科の影響はあったかもしれない。1940年に湯川が初めてノーベル賞に推薦されたとき、推薦状を寄せたのは、長岡半太郎と、仁科のコペンハーゲンでの共同研究者の一人、D。 Costerであり、ノーベル賞委員会で中間子論の評価書を書いたのは、やはり仁科をよく知る I。 Waller であった。 本人も意識しないところで学問の伝統は受け継がれていく。書簡の宛名と差出人の名前を眺めているだけでそのことが意識される書簡集である。 (2007年9月3日原稿受付)日本評論社,東京,2007, 244 p, 21.5×15.5 cm, 本体2,100円(シリーズ現代の天文学8)[大学院向] ISBN 978-4-535-60728-6
小山勝二,嶺重 慎編
ブラックホールと高エネルギー現象
山 崎 了 〈広大院理〉
この本は、天文学会創立100周年記念出版事業として、天文学・宇宙物理学のすべての分野を網羅する教科書「シリーズ現代の天文学」 の第 8 巻である。本書では、ブラックホール(BH)、 中性子星、白色矮星などの、小さな領域に質量が密集した「コンパクト天体」と、これらに関連する高エネルギー天体現象についてふれている。特に、あまりにも強い重力のため光でさえ脱出できない天体であるBHにスポットがあてられている。BHは、定義より、「我々には見えない天体」なので、BHをどうやって観測するのかと思われる方がいるかもしれない。しかし、本書を読めば、BH天体は実に多彩な活動を我々に見せてくれることがわかるであろう。 第1章から第3章では、コンパクト天体についての説明と、コンパクト天体の重力によって落ち込むガスの作る降着流・降着円盤、またコンパクト天体と降着円盤の系が生み出すジェットについて解説されている。白色矮星や中性子星とBHの類似点・相違点をみることでコンパクト天体の中で最も謎を秘めたBHのもつ特異性を浮かび上がらせている。また、ジェット生成は宇宙物理学における大きな未解決問題の一つである。本書で紹介されているどの理論モデルも一長一短で確定的ではないが、それゆえに最新の一進一退の研究の現状が伝わってくる。 第4章・第5章では、高エネルギー宇宙線、ニュートリノ、一般相対性理論によって予言される重力波、そして宇宙最大の爆発現象にして最大級の謎のひとつであるガンマ線バーストについて解説されている。ニュートリノに関する章では観測装置についての説明がやや冗長か。また、高エネルギーニュートリノについての記述がないことが残念である。 第3章までの話の流れに対して、第4章・第5章の関連がつかみにくい読者がいるかもしれないので、ここで補足しておく(書かれてはいるのだがもう少し関連性を強調しても良いかと思った次第)。ガンマ線バーストの正体は、最新の研究により、BH誕生の瞬間に伴う天体現象なのではないかと考えられるようになった。その際、ニュートリノや重力波が放射されることが理論的に予言されている。誕生したばかりのBHから相対論的ジェットが放出され、そこからガンマ線や高エネルギー宇宙線が生成される。また、超新星爆発は中性子星誕生の瞬間であり、爆発後数千年くらいまでの若い超新星残骸は宇宙線加速器であると考えられている。 本書は世界で研究されている高エネルギー天文学・高エネルギー宇宙物理学の大半がカバーされている。第2章・第3章では天文学特有の言葉を用いた博物学的な議論も見られ、不慣れな読者にはとっつきにくいかもしれない。しかし、宇宙には数多くの異なる高エネルギー天体現象があり、それらの背後には、降着円盤、ジェット、粒子加速などの普遍的な物理過程があると捉えてほしい。また、特殊及び一般相対性理論、電磁流体力学、原子物理学、素粒子物理学、プラズマ物理学などを駆使して手の届かない遠方の天体現象に挑む様子を感じ取っていただけると思う。値段も良心的なものとなっており、高エネルギー宇宙物理学を志す学生・院生はもちろん分野外の方にも一読をすすめたい。ただし残念なことに、紹介されている参考文献の数が少なく、さらに詳しく勉強しようと思う場合、若干不便であろう。 (2007年10月1日原稿受付)サイエンス社,東京,2006, vi+166 p, 25.5×18 cm, 本体1,819円[大学院生向] 雑誌 05470-11
太田信義,坂井典佑
超対称性理論; 現代素粒子論の基礎として
今 村 洋 介 〈東大理物理〉
本書は場の理論についての基本的な知識を前提とした超対称性理論についての入門書です。超対称性は統計性の異なる二種類の粒子,ボゾンとフェルミオンの間の対称性で,標準模型を超える統一模型の構築において重要な役割を果たしています。また,近年のゲージ理論の強結合領域のダイナミクスについての理解の深まりは,超対称性理論の持つ特有の性質を用いることで得られたものです。従って超対称性理論は現象論を学ぶ上でも場の理論そのものの性質を研究する上でも重要です。これらを学ぶ学生が短時間で超対称性理論の基礎を身に着けるために適した本であると思います。 本書は大きく3つの部分に分けることができます。まず最初の3つの章で,超対称性を持つ理論のラグランジアンの構成法や,非繰り込み定理,質量和則など, 一般の4次元N=1超対称性理論の性質について解説されています。次の二つの章は,現象論的な応用についてで,超対称性が統一模型の構築にどのような役割を果たすのかがまとめられています。具体的にはSU(2)×U(1)対称性の破れに関係したセクターのスペクトル (W, Z 粒子やヒッグス場の質量)に関する議論や,統一模型と陽子崩壊の関係などが与えられています。最後の3つの章はやや趣が異なり,4次元N=1以外の超対称性理論について解説されています。 本書では,超対称性のダイナミカルな破れ,ソフトな超対称性の破れがどのように隠れたセクターから現れるかという媒介機構,サイバーグ・ウィッテンの厳密解を初めとした,超対称性理論の非摂動論的な性質などについては詳しく解説されていません。しかし,そのような話題は本書の範囲外とすることでコンパクトにまとまっていて,ファインマンルールを用いた振幅計算やヒッグス機構程度の場の理論の基礎を学んだ学生であれば楽に読むことができるでしょう。超対称性理論の計算を行う際に常に問題となるスピノールの取り扱いについても付録にさまざまな公式とともにまとめられていて,大体の式は読者がフォローすることができるようになっています。 本書の特色として,N=2の高い超対称性を持つ理論やその高次元理論との関係が比較的詳しく述べられているということが挙げられます。これらの理論は近年の超対称性理論の進展においてしばしば現れ,特にサイバーグ・ウィッテンの厳密解や弦理論を用いた超対称性理論の構成,解析などを理解するうえで不可欠なものです。さらに,超場形式を用いた N=2 超対称性理論の構成法が付録に与えられていますが,現在この話題についての解説を行った教科書はほとんど無く,この点も本書の特色といえるでしょう。 (2007年9月12日原稿受付岩波書店,東京,2002, x+80 p, 19×13 cm, 本体1,300円(岩波講座 物理の世界 統計力学1)[学部・大学院向]
蔵本由紀 ミクロとマクロをつなぐ; 熱・統計力学の考え方
吉岡大二郎 マクロな体系の論理; 熱・統計力学の原理
宮下精二 相転移・臨界現象; ミクロなゆらぎとマクロの確実性
田 崎 晴 明 〈学習院大理物理〉
百ページ前後の小冊子八十数冊で物理のほぼ全体をカバーしようという岩波の新機軸の講座のなかの統計力学関連の三冊である。 蔵本氏の著書は、いわば熱・統計力学のコンパクトなレジュメである。熱力学の基本からBECまで、よくぞここまでと思うほど、多くのテーマを凝縮して述べている。熱・統計力学を駆け足で復習したいという読者には適切な本だろう。その反面、入門者が読むにはいささか敷居が高い。エルゴード性に関して長い説明があるが、ハミルトン系で自明に成立する事実と、大自由度系でのみ成立するはずの性質が混然と記述されているのは残念である。ミクロとマクロの関連について本質的な業績のある著者なのだから、テーマを絞り著者の視点を伝えることでこそ「単なる知識ではなく、基本的な考え宮下氏の著書は、スピン系を中心にした相転移と臨界現象への入門書である。統計力学を一通り学んだ読者には気楽に読める本であり、また、講義で相転移を取り上げようという教員にとっても示唆に富む本であろう。ただし、題材の選択が、著者の世代のスピン系研究者の趣味に偏り過ぎている感は否めない。2次元スピン系の相転移のトポロジーによる描像という、かなり専門的なテーマが詳述されているのが端的な例である。加えて、肝心の3次元のスピン系にまでトポロジーの議論を適用してしまうという本質的に誤った記述があることはきわめて残念だ。 吉岡氏の著書は、構成も内容もよく練られた好著である。まずマクロな系の本質である大数の法則を明快に述べ、統計力学の原理を導入。標準的な理想気体への応用の直後にゴム弾性を扱い、統計力学の広がりを実感させる。そして統計力学の形式を整備したあとで、熱力学を概観する。文章もこなれていて読みやすく、統計力学を本格的に学ぶ前に一通りの見通しを持ちたいという方におすすめできる。また、講義を行なう側にも多くのヒントを与えてくれるだろう。(ただし、前書きにある「エントロピーの定義について、『なぜ』 と問うのは適切ではない」という宣言には評者は決して賛成できない。) 三冊を駆け足で紹介したところで、小冊子からなる講座の意義を問いたい。物理学へのアプローチが多様化しているのは事実だが、多様化や細分化をそのまま反映して物理を「切り売り」することは学問にとっても自殺行為になるのではないだろうか? 本講座の統計力学についていえば、三人が独立に執筆したため重複が多く、全体としての統一感の欠けるものになったと思う。たとえ分冊にするにせよ、一人の著者が(あるいは複数の著者が十分に合議し)じっくりと全体の統一性を保ちながら執筆した方が、あらゆる意味で有効だったはずだ。深く豊かな物理学の世界をわかりやすく伝える努力は絶対に必要である。しかし、それは、単に皆でよってたかって小冊子を書くといった安易な方法では実現されないと思う。われわれ自身ができるだけ広く深く物理を学び、それを最良の形で伝えるための不断の努力をするという、古くからの方法こそが最良の解だと信じる。 (2003年9月3日原稿受付)