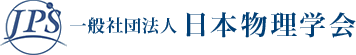第20 回(2015年)論文賞授賞論文
本年度の日本物理学会第20回論文賞は、論文賞選考委員会の推薦に基づき、本年2月14日に開催された第581回理事会において審議し、次の5編の論文に対して与えられました。表彰式は3月23日の午前、第70回年次大会の総合講演に先立ち、総合講演会場である早稲田大学早稲田キャンパス大隈記念講堂 大講堂において行われました。


上田選考委員会委員長による選考経過報告 兵頭会長より表彰状を授与される受賞者
| 論文題目 | Energy Dependence of KN Interactions and Resonance Pole of Strange Dibaryons |
|---|---|
| 掲載誌 | Prog. Theor. Phys. (2010) 124 (3): 533-539 |
| 著者氏名 | Yoichi Ikeda,Hiroyuki Kamano and Toru Sato |
| 授賞理由 | 原子核や核物質中の反K中間子(K)の性質を解明することは、ハドロン物理学における大きな課題の一つとなっている。特に、深く束縛したK原子核の可能性が赤石・山崎により2002年に指摘されて以来、ハドロン間相互作用の理解や高密度物質の状態方程式へのインパクトから、K原子核に関する実験的および理論的研究が活発に行われている。これまで複数の実験施設において深い束縛を示唆する結果が報告されているが、K原子核との確証は得られていない。理論的には、散乱実験で情報が得られない閾値以下のエネルギーにおけるKN相互作用が明らかでない事、KNとπΣのチャネル結合を含む厳密な多体計算が困難であったこと等から、最も単純なK原子核であるKNN においても大きな不定性が存在していた。 本論文では,KNとπΣのチャネル結合を取り入れた3体系のFaddeev方程式を解き、KN N-πΣN系の複素エネルギー空間における共鳴極の位置が初めて精密に計算された。その結果,KN相互作用のエネルギー依存性の取り扱いの違いによって,束縛状態の深さが大きく変わることが見出された。この結果は,これまでの理論計算における束縛エネルギーの予言値に10〜100 MeV程度の大きな不定性があった原因を明らかにし,その後の研究に重要な指針を与えるものとして,国際的にも高い評価を受けている。K原子核の研究は、KN閾値のすぐ下にあるバリオン共鳴Λ(1405)とも関連し,分子構造型の新しいハドロン共鳴状態の性質を解明する鍵ともなる。また、K原子核の生成探索実験はJ-PARCのハドロンホールにおける主要実験の1つになっており,今後の進展に関心が集まっている。以上のように,本論文はハドロン物理学の重要な課題である反K中間子原子核の理論的研究に重要な寄与をした論文であり、日本物理学会論文賞にふさわしい業績であると認められる。 |
| 論文題目 | Breaking Tri-Bimaximal Mixing and Large θ13 |
|---|---|
| 掲載誌 | Prog. Theor. Phys. (2011) 126 (1): 81-90 |
| 著者氏名 | Yusuke Shimizu, Morimitsu Tanimoto, and Atsushi Watanabe |
| 授賞理由 | 太陽ニュートリノ欠損や大気ニュートリノ異常の実験によって、異なる世代の間でニュートリノが振動する現象の実在が確定し、その結果、ニュートリノの質量とニュートリノ世代間の混合角が新しい物理量として注目を集めるようになった。さらに加速器を用いたニュートリノ実験の進展によってこのニュートリノ質量と混合角の決定は精密実験の段階に到達している。現在までの実験データの全体的特徴はクォークの場合と大きく異なるパターンを示しており、3世代のニュートリノのtri-bimaximal mixingという考え方を第一近似として良くとらえることができた。このtri-bimaximal mixingは非アーベル的離散対称群A4に基づいて導くことができ、その結果、第一世代と第三世代の間の混合角θ13 が零になるという予言が得られることが知られていた。しかし、近年のニュートリノ実験はこの値が零でない可能性を示唆していた。本論文では,非アーベル的離散対称群A4のもとで許される新たな寄与の存在を指摘し、その結果、leading orderでtri-bimaximal mixingが破れて、混合角θ13 は小さいが零でない値となることを示した。さらに、この考え方を用いて、ニュートリノ質量と混合角の定量的な解析を模型の詳細によらずに具体的に遂行した。ニュートリノ実験の進展によって、この模型の予言を検証することが間もなく可能になると期待されていたが、実際にその後のT2K長基線実験、原子炉からのニュートリノを観測するdouble Chooz実験、また最近のDaya Bay実験、RENO実験などのデータによって、θ13 = 0.1という小さいが零でない値が確認された。 ニュートリノ質量と混合角の解析において、非アーベル的離散対称性を用いた模型は注目を集めている。著者たちのグループの先行研究も含む一連の流れの中で、本論文は実験結果が確定する前に正しい予言をしていたことは注目に値する成果である。以上の点から日本物理学会論文賞にふさわしいと考える。 |
| 論文題目 | Chern Numbers in Discretized Brillouin Zone: Efficient Method of Computing (Spin) Hall Conductances |
|---|---|
| 掲載誌 | J. Phys. Soc. Jpn. 74, pp. 1674-1677 (2005) |
| 著者氏名 | Takahiro Fukui, Yasuhiro Hatsugai, and Hiroshi Suzuki |
| 授賞理由 | 固体中の電子のトポロジカル状態は,電子物性の新しい理解のあり方として,あるいは将来的な応用にもつながりうる新物性発現の指針として注目され,その研究は物性物理学の理論研究における大きな潮流となりつつある。特に最近では具体的な物質を想定したモデル計算や第一原理に基づく電子状態計算を使って,トポロジカル状態を実現する新物質の提案まで行われるようになってきた。 これらの計算でトポロジカル状態かどうかを理論的に判定するには,逆格子空間での積分量で表されるトポロジカル数(Chern Number)の計算が不可欠であるが,従来用いられていた離散化による数値積分手法は,ゲージ不変性に関する基本的困難に加え,積分に用いる離散点の数に対する収束性が極めて悪いこと,すなわち多くの離散点の情報が必要であることが深刻な問題となっていた。 これに対して本論文は,格子ゲージ理論の手法を応用して,離散点の情報を用いてゲージ不変性を破ることなくトポロジカル数の計算を実現し,かつ,その収束性を改善する方法を提案した論文である。新手法は簡単かつ実装が容易で,効果は劇的であり,トポロジカル状態の研究に本質的な寄与をする手法提案である。本論文は発表後10年が経過しているが,近年急激に認知度が上がり,当研究分野で世界中の研究者によって幅広く活用されるようになった。アイデアの斬新さにおいても,トポロジカル絶縁体・超伝導体の分野への貢献度の高さにおいても秀でており,日本物理学会論文賞に相応しい卓越した論文である。 |
| 論文題目 | Superconductivity and Structural Phase Transitions in Caged Compounds RT2Zn20 (R = La, Pr, T = Ru, Ir) |
|---|---|
| 掲載誌 | J. Phys. Soc. Jpn. 79, 033704 (2010) |
| 著者氏名 | Takahiro Onimaru, Keisuke T. Matsumoto, Yukihiro F. Inoue, Kazunori Umeo, Yuta Saiga, Yoshitaka Matsushita, Ryuji Tamura, Kazue Nishimoto, Isao Ishii, Takashi Suzuki, and Toshiro Takabatake |
| 授賞理由 | 重い電子系は電子間相互作用が重要な強相関電子系の代表例の一つであるが、電子間相互作用の効果は準粒子の大きな有効質量として表わされる。YbCo2Zn20は最も大きな有効質量をもつ物質として知られている。その構造上の特徴は希土類元素が16個のアルミニウムで作られる籠の中に閉じ込められていることである。この構造は1-2-20構造と通称されている。重い電子系はしばしば超伝導の舞台となるが、1-2-20構造を持つ物質で超伝導を示すものは知られていなかった。 著者たちは希土類元素としてランタンおよびプラセオジムを含む1-2-20構造を持つ物質群の単結晶を育成し、LaRu2Zn20, LaIr2Zn20およびPrIr2Zn20が超伝導を示すことを発見した。ランタンを含む二つの物質は通常のBCS型の超伝導体と考えられるが、PrIr2Zn20有効質量は極めて大きい。 亜鉛の籠の中にいるプラセオジムイオンは非クラマース縮退をしていると考えられ大きな有効質量はその縮退に起因すると期待される。その後の研究により、この物質の超伝導は四重極秩序状態で起きていることが明らかになった。 以上のように1-2-20構造での超伝導の発見を報じた本論文は、多極子由来の重い電子系とそこにおける超伝導と云う新たな研究テーマの先駆けとなった論文で、物理学会論文賞にふさわしい業績である。 |
| 論文題目 | Structural Quantum Criticality and Superconductivity in Iron-Based Superconductor Ba(Fe1-xCox)2As2 |
|---|---|
| 掲載誌 | J. Phys. Soc. Jpn. 81, 024604 (2012) |
| 著者氏名 | Masahito Yoshizawa, Daichi Kimura, Taiji Chiba, Shalamujiang Simayi, Yoshiki Nakanishi, Kunihiro Kihou, Chul-Ho Lee, Akira Iyo, Hiroshi Eisaki, Masamichi Nakajima, and Shin-ichi Uchida |
| 授賞理由 | 鉄系高温超伝導体の発見は、近年の物性物理学における最も大きなブレークスルーの一つである。この超伝導の発現機構に関しては、従来型の電子格子相互作用ではないというコンセンサスはあるものの、未だに解明されていない大きな謎が残っている。最も大きな問題の一つは、スピンの自由度と軌道の自由度の超伝導に果たす役割である。実際、この系ではスピンと軌道自由度の強い結合により、軌道の物理と磁性が強く絡み合う。この系に共通する特徴の一つは、磁気相転移点の直上で軌道秩序を伴う正方晶から斜方晶への構造相転移が起こることである。そして超伝導転移温度は、これらの相転移の消失した点(量子臨界点)の近傍でしばしば最も高くなり、このことは量子臨界点にともなう量子ゆらぎと高温超伝導が密接に関わっていることを示している。したがって磁気的な量子臨界点と軌道秩序の量子臨界点のどちらが高温超伝導の引きがねとなっているのかは、超伝導発現機構の解明における鍵となる問題であり、現在最も大きな論点の一つとなっている。 本論文で吉澤らは、BaFe2As2に電子をドープしたBa(Fe1-xCox)2As2に対して広い組成範囲で系統的に超音波の実験を行い、正方形から斜方晶への結晶変形に対応する弾性定数 C66 の詳細な測定を行った。その結果、超伝導転移温度が最大となる組成において、C66の逆数で構造揺らぎの指標である弾性コンプライアンス S66(=1/C66)が最も大きくなる、つまり最も大きな格子のソフト化が起こることを発見した。この結果は、超伝導と結晶構造あるいは軌道のゆらぎの強い関係を示唆する。さらにS66が磁気量子臨界点近傍の磁化率の特徴と極めてよく似た振る舞いを示すことから、軌道に関する量子臨界点と磁気量子臨界点が密接な関係を持つことを示した。本結果により、鉄系超伝導体において軌道ゆらぎと磁気ゆらぎのどちらが本質的でどちらが副次的なものであるか、解明されたわけではない。しかしながら軌道自由度の与える効果が広い温度領域と広いドープ域にわたって重要であることを示した本論文は、日本物理学会論文賞にふさわしいと考える。 |
日本物理学会第20回論文賞授賞論文選考経過報告
日本物理学会第20回論文賞選考委員会*
本選考委員会は2014年11月の理事会において構成された。日本物理学会論文賞規定に従って、関連委員会等に受賞論文候補の推薦を求め、11月下旬の締め切りまでに、21件18編の論文の推薦を受けた。推薦された論文の中に選考委員会委員を共著者とする論文があったので、選考委員会規定に従って当該委員は辞任し、追加委員が指名された。18編の論文については、原則として選考委員1名と外部委員1名の2名による閲読を依頼したが、選考委員に適任者が見当たらないものについては外部委員2名に閲読を依頼した。
2015年2月12日の選考委員会では全選考委員が出席し受賞候補論文の選考を進めた。それまでに提出されていた閲読結果に基づき、各論文の業績と物理学における貢献について詳細に検討した。その際、対象論文の発表された時期及び種別について、論文賞規定に記述されている原則と例外規定についても検討がなされた。その結果、上記5編の論文が第20回日本物理学会論文賞にふさわしい受賞候補論文であるとの結論を得て理事会に推薦し、同月の理事会で正式決定された。
*日本物理学会第20回論文賞選考委員会
委員長:上田和夫
副委員長:坂井典佑
幹事:藤井保彦
委員:加藤礼三,久野良孝,斎藤 晋,田口善弘,常行真司,初田哲男,平野琢也,松田祐司