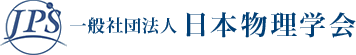会誌Vol.67(2012)「新著紹介」より
このページでは、物理学会誌「新著紹介」の欄より、一部を、紹介者のご了解の上で転載しています。ただし、転載にあたって多少の変更が加わっている場合もあります。また、価格等は掲載時のもので、変動があり得ます。
坂田昌一コペンハーゲン日記;ボーアとアンデルセンの国で
坂田昌一著,坂田昌一コペンハーゲン日記刊行会編
ナノオプトニクス・エナジー出版局,東京,2011,276p,19×13 cm,本体2,000円[一般向]ISBN 978-4-7649-5522-6
紹介者:中村 真(京大理)
2003年から2005年にかけて,私はニールスボーア研究所にポスドク研究員として在籍した.滞在中に誕生した長女の記念撮影で訪れた写真館の主人から「坂田教授を知っているか」と尋ねられた時には,「もちろん」と答えつつも,私が物心ついた時には既に他界されていた大先生のお話だけに,何か遠い世界の話を聞かされている印象を持った.同時に,坂田先生の滞在当時のご様子はいかがなものだったのか,純粋な興味を感じたのを憶えている.自分が生まれる前に滞在されたという時間的隔たりと,全く同じ場所に自分も滞在しているという空間的接点が,坂田先生を遠くて近い不思議な存在にしていた. 本書を手にするうちに,この「遠くて近い」坂田先生が,どんどん私に接近してきた.本書に収められているデンマークの写真の風景は,私が2003年頃に見た風景と全く変わらない.「夕食後ティボリに行く」などの生活の記録は,まるで自分の日記のようであり,思わず頷いてしまう.そして読み進めるうちに,ある事実に気がついた.先生がコペンハーゲンに滞在された時の年齢は,まさに現在の私の年齢なのだ.どおりで息子さんに宛てた手紙の内容に親近感がわくはずだ.先生の存在が急激に近くなる. 坂田先生から現在の私が学ぶことができるとしたら,どのようなことであろうか.ヨーロッパの実験施設を訪問し,実験の話を積極的に聞くかと思えば,パウリに電話をかけて議論の約束をとりつけている.このような積極性を私も見習いたい.しかし,私が最も感銘を受けたのは,社会における物理学者の役割に関する認識である.当時は日本での原子炉の建設が議論されはじめた時期であり,先生が,物理学者の立場からその是非について真剣に考えておられる様子を,本書から読み取ることができる.「先般来,日本に原子炉をつくろうなどという話がありましたが,あれは子供の火なぶりににた危険なことだと思います.日本にも仁科博士が丁抹*から持ってかえられ,湯川・朝永両博士らにより育てられた基礎物理学の貴重な芽があります.この芽を大切に育て上げることこそ日本の原子科学者の正統な使命ではないでしょうか.」という,先生の新聞記事の一節を目にした時,2012年に生きる私は,考え込まずにいられなかった. 本書は,1954年に坂田先生がデンマークに滞在された際の日記を中心とした記録集であり,日記の他に家族への書簡や,新聞に掲載された記事などを含む.これだけの詳細な記録を編纂された関係者に敬意を表したい.本書の大半は先生の日常生活の記録ではあるが,その行間を読み解くうちに,物理学者として様々なことを考えさせられる.我々物理学者は,偉大な先達や異なる視点を持つ同業者との自由闊達な研究交流から大きな刺激を受けるものだが,坂田模型発表前年のコペンハーゲン滞在が,先生の帰国後の大きな成果に向けた重要な刺激となったのではないか,そんな空想すら可能にしてくれる.本書には,単なる記録集を超えた不思議な味わいがある. (2012年6月20日原稿受付)
原子力をめぐる科学者の社会的責任
坂田昌一著,樫本喜一編
岩波書店,東京,2011,x+319p,19×13 cm,本体2,600円[一般向]ISBN 978-4-00-005324-2
紹介者:平田光司(総研大融合推進セ)
本書は坂田昌一博士(1911-1970)の生誕100年にあわせて刊行され,科学と社会をめぐる坂田の論考をほぼ年代順に集めたものだ. 本書に集められた論考の多く(27編中21編)は原子力,原子核研究に関する学術会議の動きを坂田が解説したものであり,坂田の学術会議への思いが伺われる.本書冒頭の論考「日本学術会議第一回総会に出席して(1949)」では発足したばかりの学術会議への期待を述べ「何よりもまず学問の政治に対する幇間性をぬぐいさり,その自主性を回復することにつとめなければならない」と結論されている.しかし,現実は逆の方向に進み,それに抵抗して坂田は同じ主張を何度も繰り返すことになったと思われる.はやくも「科学者の苦悩(1954)」では「研究費の増額を求めることをのみ急いで学問の魂ともいうべき学問の自由と独立をまで売り渡すことのないよう,厳にいましめなければならない」と,原子力予算をめぐる研究者の動きを批判した. 学術会議は早い段階で原子力研究の三原則(自主,民主,公開)を勧告した.これは平和利用に徹するためであった(「三原則と濃縮ウラニウム(1955)」).しかし,原子力の安全性のためにも三原則が重要であり,原子力推進の組織とは独立した民主的な組織が,公開の議論によって安全を保障できるようにすることを要求した(「原子炉の安全審査機構はこれでよいか(1960)」).三原則は原子力にとどまるものでなく,「学術会議そのものの性格」だ,とも述べている(「科学と現代(1968)」).原子力と三原則に関する論考が本書の中心である.それらの議論の多くが今日でも有効であることには驚くばかりである. 編者の見識の確かさを伺わせるのは,原子力に直接関係しない,基礎研究の大型化に関する論考も取り入れていることだ.「初心忘るべからず」(1967)は素粒子研究を対象としたもので,ここでも施設の大型化にともなって,学術会議の理想が崩されていく可能性を指摘している.ほとんど最後となる論考「科学の論理と政治の論理―学術会議20年」(1968)では学術会議の影が薄れてきたことを指摘し「原因は会員にもある.会員の中にさえ自ら学術会議の墓穴を掘るような行動をとって恥じないばかりか,そのことを意識すらしていない人がある」と書いている.本書がカバーしている1949年から没年まで,坂田は学問の自主性を確立し社会的責任を果たすべく奮闘したが,逆風は強まるばかりだと感じていたに違いない. 坂田は科学者の平和運動にも積極的に参加した.それに関する重要な論考も数点収録されている.原子力に関する議論の背景には常に核兵器への懸念があったことが伺える.坂田への評価はさまざまにあり得るだろうが,原子力(さらに社会)と科学者について議論する場合,かならず参照すべき論考を本書は集めていると言えるだろう. (2012年6月9日原稿受付)
坂田昌一の生涯;科学と平和の創造
原著者:西谷 正
鳥影社,長野,2011,477p,22×16 cm,本体3,200円[一般向]ISBN 978-4-86265-326-0
紹介者:植松英穂(日大理工)
没後42年目にして坂田の生涯が出版された.執筆者の西谷は名古屋大学の物理学科の出身であるが,直接坂田から教わったことはないと言う.E研(坂田が率いる研究室)で学んだ益川が序文で「本書は,実に丹念に資料を掘り起こして記述されている.一読に値する.」と書いていることから,弟子からみても違和感のない坂田の生涯が記されていると思われる. 坂田は1911年,ラザフォードによる原子核の発見の年に生まれ,物理の研究を始めたのは,すでに量子力学ができあがり,原子核物理学の革命の年と言われる1932年の頃であった.この年,中性子,陽電子,重水素が発見され,サイクロトロン,コッククロフト-ウォルトンの装置が実用化された.当然のことのように,坂田は最先端の物理として原子核・素粒子の世界へ入り,そしてクォークを提案したゲルマンにノーベル物理学賞が授与された翌年(1970年)に亡くなった.このことから分かるように,坂田は歴史的に大変興味深い素粒子論形成時代の落とし子であったと言えよう. 坂田の名は,'湯川・朝永・坂田'として,あるいは'クォーク模型の先駆者'として知られているが,他の分野の研究者から見ると忘れ去られているように思われる.坂田は研究以外にも,教室の民主的運営改革,講座制廃止と研究グループ制の導入,武谷三段階論の強力な推進者としても知られていて,本書ではこれらのことを詳細に追求しつつ,科学者による平和運動についても記しているところが興味深い. ここで,坂田の影響力の大きさを示す例をあげさせていただきたい.坂田の教室民主化改革は全国の多くの物理学科の運営に影響を与えたが,特に評者の所属する物理学科は坂田と関係が深い.日大理工の物理学科は湯川の進言により創設され,湯川の指名によりE研助手で坂田の一番弟子であった原治が1957年に創設責任者として赴任したことに始まり,それ以来名古屋大の物理学科を模範として運営してきている. 原は旧制一高出身であったが,東京帝大に行かず,一高教授玉木英彦の強い薦めで坂田のいる名古屋帝大に進学した.後日彼は,玉木と坂田の共謀であったのではないかと懐古していた.坂田は素粒子論研究を強力に進めるため,E研に優秀な学生を集めようとしていたのであろう. 原は,湯川の研究方法がロマンティック,直感的であるのに反し,坂田はヘーゲル哲学にもとづく方法論を基礎に据え,一歩一歩論理的につめてゆくというタイプであったと回顧し,坂田と湯川を生きていく上での最後のよりどころとして敬愛していた.本書を読めば原が感じたような坂田の人間像を理解できるのではないかと思われる.最期に,坂田がゲルマンのノーベル物理学賞受賞をどのような思いで聞いていたのであろうか,本書で是非扱って欲しかった. (2012年5月29日原稿受付)
「場の量子論」第1巻;量子電磁力学
「場の量子論」第2巻;素粒子の相互作用
F.マンドル,G.ショー著,樺沢宇紀訳
第1巻
丸善プラネット,東京,2011,viii+266p,21×15 cm,本体5,800円[大学院・学部向]ISBN 978-4-86345-081-3
第2巻
丸善プラネット,東京,2011,vi+287p,21×15 cm,本体6,000円[大学院・学部向]ISBN 978-4-86345-082-0
紹介者:菅原 祐二(立命館大理工)
本書の紹介記事の依頼があったとき,学生の頃に初版の原書を読んだことがあったため気楽に引き受けたのであるが,今回第2版になって内容が大幅に増えていることに気づき驚いた. 一言で述べると,本書は初学者向けの相対論的な場の量子論の教科書である.まず初版から変わらない内容を簡単に紹介すると,特殊相対論の復習から始まり,自由なクラインゴルドン場・ディラック場の正準量子化,更には電磁場の共変的量子化を経てQEDのファインマン図の導出へと至る.具体的なQEDの振幅の計算について初学者にも親切に解説されており,「輻射補正」の章では,内容は若干不足気味ながら繰り込み理論の考え方も解説されている.後半では,対称性の自発的破れからワインバーグ・サラム理論(電弱標準理論)までが半ばダイジェスト的に紹介されている.おそらく初版の際の著者の意図は,「technical detailに深入りせずに場の量子論や素粒子論のエッセンスをわかりやすく解説する.」といった点にあったかと考える. さて第2版であるが,主に経路積分とQCDに関する基本的な解説が大幅に加筆された.実を言うと,初版ではQCDについて書かれていない点が少々物足りない気がしたのだが,この改訂によって,初版の精神は生かされつつ,単なる入門書を超えた,より「標準的」な場の理論のテキストに近づいたと言えよう.QCDの量子化についての解説は経路積分とファデエフ・ポポフの方法に基づくオーソドックスなものであり,「漸近的自由性」の章では必要最小限ながら繰り込み群についても解説されている.電弱理論に関しても内容が厚みを増しており,ニュートリノ振動やヒッグス粒子に関する記述がupdateされた点も有難い.(丁度この紹介記事を準備している頃,「ヒッグス粒子らしい粒子の発見」という大ニュースが飛び込んで来ました!) 本書の特色として,場の理論の枠組みをsystematicに解説した専門書と言うよりは,「現実の素粒子物理にバランスよく題材を求めた初学者向けの教科書である.」と言うことができよう.決して「オールインワン」のテキストではないが,大学院初年級または学部4年程度の素粒子論を志す学生,または手っ取り早く素粒子の標準模型について理解したいとお考えの非専門家の諸兄にお薦めできる良書であると考える. (2012年7月12日原稿受付)
宇宙のダークエネルギー;「未知なる力」の謎を解く
原著者:土居 守,松原隆彦
光文社,東京,2011,253p,18×11 cm,本体760円[一般向]ISBN 978-4-334-03642-3
紹介者:辻川 信二(東理大理)
本書は,現在の宇宙を支配するダークエネルギーについて,一般向けに執筆された啓蒙書である.ダークエネルギーとは,宇宙の加速膨張の源となる未知のエネルギーであり,1998年に超新星の観測からその存在が指摘された.本書の構成は2部に分かれており,第1部と第2部がそれぞれ,ダークエネルギーの理論的,観測的側面について解説されており,勝手な想像であるが,第1部が松原氏,第2部が土居氏によって主に執筆されたと推測される. 第1部ではまず,ビッグバン宇宙論と宇宙進化に関する基礎から出発して,ダークエネルギーの性質に関する解説へと話を進めている.数式をほとんど用いておらず,一般向けにも分かりやすく書かれている.ダークエネルギーの候補として理論的に考えられているものは,宇宙項,スカラー場,修正重力理論,宇宙の非一様性に基づくものなどであり,本書ではこれらの全てについて触れられている.量子論で現れる真空のエネルギーが,ダークエネルギーのスケールと桁違いに異なるという宇宙項問題は,ダークエネルギーの有効な理論模型の構築の困難さと切り離せない根本的な問題点であり,本書では宇宙項問題に関して多くのページ数を割いて解説を行っている.一般の読者にとって,理論模型の解説の章はやや難しいかもしれないが,それぞれの模型が何を意味しているかは,専門外の読者にも雰囲気が伝わると思う. 第2部ではまず,天体望遠鏡とCCDカメラを用いた天体観測の手法と赤方偏移に関する解説から始めて,超新星を用いたダークエネルギーの測定へと話を進めている.Ia型超新星が,なぜ標準光源として宇宙膨張の測定に適しているかに関する詳しい説明があり,超新星を効率的に見つける手法に関しても触れられている.この辺りは,私のような理論寄りの研究者が読んでも勉強になる.Perlmutter氏らが1997年に公表した超新星観測の新しい手法は,Riess氏,Schmidt氏らのグループにも用いられ,2つのグループは独立に,1998年に宇宙の加速膨張を発見した.後に2011年度のノーベル物理学賞の受賞へとつながるこれらの研究の過程が,本書に詳細に書かれており,非常に興味深い. また,超新星だけでなく,宇宙背景輻射,バリオン音響振動,銀河団の数,重力レンズなどの様々な独立な観測からもダークエネルギーの存在が検証されているが,そのそれぞれに関して,第2部の第3章で分かりやすく解説されている.さらに最後の章では,ダークエネルギーの観測の現状と将来の展望について述べられている.本書は一般向けであるが,研究の現場を肌で感じ取ることができるような良書であり,宇宙論を専門とする研究者にも勧めたい一冊である. (2012年7月1日原稿受付)
Heisenberg in the Atomic Age; Science and the Public Sphere
原著者:C. Carson
Cambridge Univ. Press,New York,2010,xvi+541p,24×16 cm,$92.00[一般向]ISBN 978-0-521-82170-4
紹介者:後藤 邦夫(学術研究ネット)
20世紀の大物理学者Werner Heisenberg(1901-1976)の新たな伝記である.ただし,既刊のCassidyの"Uncertainty"やPowersの"Heisenberg's War"(いずれも邦訳あり)などとは異なり,既刊書ではあまり扱われなかった第二次大戦後の活動に重点がおかれている.すなわち,Max Planck Gesellschaft,原子力委員会,フンボルト財団,学術研究評議会などで果たした指導的な役割や,ドイツ核武装反対のゲッチンゲン宣言や「オーデル・ナイセ以東の領土権放棄」を提唱して論議を呼んだチュービンゲン・メモランダムへの彼の積極的関与に多くのスペースが割かれている. 当然のことながら,本書の記述は戦後の西ドイツの政治史(それは同時に社会史でもある)をも含む.そのさいの「陰の主役」が副題のPublic Sphereである.「公共圏」と訳されるこの概念の原語はÖffentlichkeitであり,18世紀の領邦分立時代のドイツで,権力を振るう国家とは別に「教養ある富裕な都市の民」(ビュルガーは「市民」と訳されるがブルジョワと同義である)が公共的機能を担う政治的空間を形成する可能性を期待して唱導された.Kantが定式化したこの古典的概念を1960年代初頭のマスメディアと大衆民主主義の時代に再定式化したのがフランクフルト学派のHabermasであり,「市民と科学者のコミュニケーション」をめぐる現代的課題につながるのである. 本書では,Heisenbergがまさに「教養ある富裕な都市の民」の末裔として,古典的公共圏の「市民」にふさわしく行動したとされる.量子力学の建設,場の量子論の開拓,S行列の提唱を経て非線形スピノル場方程式に及ぶ彼の物理学研究は,それ自体が哲学的・文化的行為であり,多くの一般的著作も同様であったとする.その姿勢は科学技術政策への関与や政治的発言においても一貫していたが,古典的公共圏自体の解体に伴い,彼の学問は巨大科学と化した素粒子物理学の主流から外れてゆき,科学技術政策の主導的地位からも退出することになったという.しかし,変貌する新たな公共圏への可能性を求め,Habermasらとも交流し,リベラル左派の立場をとり,Willy Brandtの社会民主党政権とその「東方政策」を歓迎するにいたる.本書は,おびただしい書簡を含む膨大な資料や,ヒトラー体制下の行動の率直な回顧を含む著書『部分と全体』などの精密な「解読」を通じて,このようなHeisenbergの半生を分析している.先行研究に対する評価や反証も丹念である. 本書の構成は必ずしも時系列を追わず,文化的活動(物理学研究と講演・著作活動)と政治的活動(研究所運営,科学政策への関与,社会的発言),ナチ時代の核研究問題に関する言説,などがテーマ別に整理され,最後を「公共圏における科学的理性」という1章で結ぶ.そこでは右にHeidegger,左にフランクフルト学派を配した戦後西ドイツの思想潮流が概括され,そのなかでのHeisenbergの遍歴が総括される.重視されるのはリベラル左派のHabermas的公共圏の思想であるが,「公共圏における科学」の可能性については,それを認めない立場を含め更なる検討が必要であろう. 本書は歴史書であるが,「社会と科学」という現代的課題を扱った力作である.それは同様に「戦後」を生きてきた私たち自身のテーマでもある.デジタル社会のもとで「フクシマ」問題に直面し,「市民社会と科学技術」について考察を深めなければならない現在の日本で多く読まれることを期待したい. (2012年5月25日原稿受付)
磁性入門
原著者:上田和夫
裳華房,東京,2011,ix+167p,21×15 cm,本体2,700円(物性科学入門シリーズ)[大学院向]ISBN 978-4-7853-2918-1
紹介者:佐久間 昭正(東北大院工)
著者は1980年代から,我が国のお家芸である磁性と超伝導の理論研究を牽引してきた第一線の研究者である.表紙は一見すると昨今の学部1,2年生向けの入門書のような雰囲気を呈しているが,著者が言うように,本書は学部4年生以上を対象としたものである.長年の風雪の中でリファインされてきた現代の磁性理論を,贅肉をそぎ落とした形で簡潔に説明してくれている. 一般に学部の物性物理学の講義において,磁性は後半の章に回されることが多いが,今日の物性物理学の研究現場は磁性物理に関するバックグラウンドなしでは一歩も進めない状況下にあるといっても過言ではなかろう.重い電子系は言うに及ばず,電荷の自由度にスピン自由度を絡めたスピントロニクス,銅酸化物系や鉄系の超伝導発現機構など,磁性は現在の物性研究の中枢を支える重要な概念である.最近,磁性に関する教科書が多く出版されているのをみると,磁性も成熟期に入ったかという印象が持たれるが,本書はここからが磁性理論の本番であることを主張しているように思える. 内容は6章から成り,150ページほどの中に磁性理論のエキスが詰まっている.第1章は「磁性の古典論と量子論」,第2章は「原子・イオンの磁性」,第3章は「遍歴電子のモデル」,第4章は「磁性絶縁体の理論」,第5章は「遍歴電子系の磁性理論」,そして最終章は「磁性と超伝導―結びに変えて―」である.また,各章には適切な問題が用意されており,本文の理解を助けている.第1章から第3章までは磁性の定番と言える内容であるが,第4章から第6章まで進めば,現在の物性物理学の最前線からの風景をのぞくことができる. 第4章の「磁性絶縁体の理論」はハイゼンベルグ模型に代表されるスピン系の話題である.実際の磁性体の多く(特に強磁性体)は金属であるが,スピン系の模型は磁性の低エネルギー励起や相転移現象を理解するうえで格好の舞台装置となっている.本書でも分子場理論から始まってスピン波理論,GL理論,繰り込みとスケーリング則を経て量子相転移という順で説明がなされている.量子相転移の節では,ハルデインギャップ(本書ではホールデンギャップ)やRVB状態など低次元系の低エネルギー励起に関する説明が簡潔になされ,銅酸化物系の高温超伝導発現機構との関連で読者の関心をうまく導いている. 第5章の「遍歴電子系の磁性理論」では,我が国で育った線形応答理論やそれを利用したスピン揺らぎ理論がわずか30ページ余りで過不足なく説明されている.特に自己無撞着繰り込み(SCR)理論の説明においては,ハートリー・フォック近似(HFA)と乱雑位相近似(RPA)のそれぞれに対してのSCR理論の(補正理論としての)位置づけが明解に記されており,著者ならではの要を得た記述になっている.また,本章の最後に,磁性体の量子臨界点近傍における諸物性の非フェルミ液体的な温度依存性がSCR理論によって記述し得ることを述べ,さらにこのシナリオが重い電子系や銅酸化物系の超伝導発現機構に密接に関係することを最終章「磁性と超伝導―結びに変えて―」で主張している.勿論,著者が言うように,ここから先は研究現場である.入門書といえども研究の最前線への誘導に抜かりがない. 以上,話題は豊富であるが,文章全体が簡にして要を得ているので飽きる前に章が終わるという安堵感がある.これなら意欲をそぐことなしに初学者の琴線に触れる内容となろう.初学者はもちろんであるが,第一線の研究者もぜひ一冊手元において,今日の磁性理論の構造を確認されることを勧めたい.特に,若い研究者が本書を道しるべに,上記のような未知領域に道を築いてくれることを期待したい. (2012年5月21日原稿受付)
Quantum Measurement and Control
原著者:H. M. Wiseman and G. J. Milburn
Cambridge Univ. Press,New York,2010,xvi+460p,26×18 cm,$86.00[専門・大学院向]ISBN 978-0-521-80442-4
紹介者:沙川 貴大(京大白眉)
近年,量子光学系など多彩な量子系において,精密な量子測定と量子制御が可能になっている.その際,散逸や測定の効果でダイナミクスが非ユニタリになることが多い.マルコフ過程の場合は,量子マスター方程式によって非ユニタリ過程を記述できることが知られている.さらに,環境が連続的にモニターされている量子連続測定の場合は,量子軌跡(quantum trajectory)によって系の時間発展を記述することができる.量子測定の結果をリアルタイムで用いた制御である「量子フィードバック制御」を解析するうえでも,量子軌跡は重要な役割を果たす. 量子フィードバック制御は,古典最適制御理論の拡張として,1980年代にBelavkinによって提案された.その後,1990年代に量子光学の観点から量子フィードバック制御の理論が大きく発展したが,そのときに中心的な役割を担ったのが本書の著者であるWisemanとMilburnであった. 本書は量子フィードバック制御の初めての本格的な教科書である.内容は,著者らが構築した理論の解説はもちろんのこと,量子測定の入門的な解説から比較的最近の研究の紹介まで,広範囲に及んでいる.ただし,マルコフ過程の解説が中心であり,非マルコフ過程はほとんど扱われていない. 第1章は量子測定の,第2章は量子推定の入門である.第3章は量子マスター方程式の解説にあてられている.第4章では,ホモダイン測定・ヘテロダイン測定を中心に,量子軌跡が解説されている.具体例としては,量子ドットの連続測定が挙げられている.他の標準的な教科書の一つであるBreuerとPetruccioneの"The Theory of Quantum Open Systems"(Oxford, 2002)と比べると,本書には,伊藤公式の量子版(非可換版)に相当する関係式が積極的に用いられているという特色がある. 第5章と第6章で量子フィードバック制御が解説されている.状態ベースの量子フィードバック制御を理解する上では古典制御理論の知識が必要になるが,その解説に多くの紙数があてられていることも本書の特色である. 第7章では量子情報処理への応用が述べられている. 本書は,入門的な解説からテクニカルな理論的内容,さらに関連する実験系の解説まで,幅広くカバーしている教科書である.量子光学や量子情報の理論家と実験家の両方に,本書を推薦したい. (2012年5月11日原稿受付)
"測る"を究めろ!;物理学実験攻略法
原著者:久我 隆弘
丸善,東京,2012,ix+218p,21×15 cm,本体2,200円[大学院・学部向]ISBN 978-4-621-08514-1
紹介者:佐々田 博之(慶大理工)
本書は学部低学年を対象とした物理実験の手引書ではあるが,子供と犬の漫画が描かれたカバーと同様,内容もこれまでの類書とは大きく異なる.誤差や最小自乗法からはじまる類書が多い中,本書は「とにかくまず測ってみよう」と著者自身が重力加速度を家庭で手に入る道具を使って様々な方法で測定し,これを題材に展開していく.そこで生じる問題点を「不確かさ」の取り扱い等のアイテムを入手して解決していく.「物理実験」というアドベンチャーゲームの攻略本というスタイルを取っているが,内容はけっして軽薄なものではなく,必要性が明らかになった後に,物理量の表記法(高校教科書記法から国際的に認められた記法へ)やSI(International System of Units)から測定法,ロックインアンプまでの広範な基礎知識が解説され,実験書として十分価値がある.実際に著者が測定を行っているだけに,実験家らしい工夫やオーダーエスティメーションも随所にあり,先人の実験の工夫にも言及しており類書に例がない.実験系の大学院生も是非読んでほしい. 「不確かさ」,「Aタイプの不確かさ」,「Bタイプの不確かさ」が従来の「誤差」,「偶然誤差」,「系統誤差」に代わって使われるようになってから久しい.これらの概念は分かりやすいものではないが,本書には著者の実験データに即した具体的な説明があり有益である.また,本書のコラムで「真空の誘電率」,「真空の透磁率」に代わり「電気定数」と「磁気定数」となったことを取り上げているが,会員の皆さんはご存知だろうか.最新の光格子時計や微細構造定数の時間変化の超精密計測についても解説されており,学生実験を担当する大学教員はもちろん物理に携わるすべての人にも役立つ. デジタル測定器がアナログ機器を席巻する昨今,学生実験も例外ではない.本書では著者がデジタルオシロスコープを自作し,音の実験を行ってみせている.周波数特性,トリガー機能,過渡現象と初歩的な電子回路の入門書としても役立つ.デジタルオシロスコープとアナログオシロスコープの比較も具体的で,前者の優位を述べている.一方,デジタル測定器の普及で測定値の変動が目に見えにくくなっている.測定値のばらつきへの感性が鈍化するのではないかと心配するのはアナログ世代の杞憂だろうか. 本書は著者自身が行った実験を取り上げているため,物理実験の手引書には珍しく読み物としてもおもしろい.考えてみれば実験研究は次々と現れる妨害を排除しながら進んでいくゲームかもしれない.お手軽で失敗のない3分クッキングのような学生実験の手引きと言うより,研究者が読むべき書かもしれない. (2012年4月28日原稿受付)
Advances in Atomic Physics; An Overview
原著者:C. C.-Tannoudji and D. G.-Odelin
World Scientific,Shingapore,2011,xxv+767p,25×18 cm,$98[専門・大学院向]ISBN 978-981-277-496-5
紹介者:井上 慎(東大院工)
まず,念のために本の「物理的」側面から紹介しておくと,非常に分厚い本である.本文だけで700ページ以上ある.しかし数式がそれほど多いわけではない.むしろ挿絵も豊富でカラーのものも多く,全体に読みやすく仕上がっている.では内容について述べよう. 著者の二人は原子物理の研究者で,特にCohen-Tannoudji博士は1997年のノーベル物理学賞の受賞者である.その彼が,「この60年間の間に目覚しい発展を遂げた原子・分子・光物理("AMO physics")の全体像を紹介するために書いた」のが本書である.触れられている内容は,輻射場と原子の相互作用,ラムゼー干渉,光ポンピング,レーザーを用いた超精密分光,多光子過程と非線形分光,レーザー冷却とトラップ,極低温の衝突とフェッシュバッハ共鳴,原子波干渉計,ボース・アインシュタイン凝縮とフェルミ縮退気体,パリティ対称性の破れ,冷却原子を用いた強相関の物理,量子もつれと量子情報...と非常に多岐にわたっている. 当然,これだけ分野が広くなると,全体像をつかむことは困難になる.この問題は特に新しく足を踏み入れた若い研究者にとって深刻である.著者は特にそのような若い研究者を助けるべく,本書を書いたと序文に書いている.筆者もこの動機には深く同意するものであるし,実際にこの本を読んでみて,その動機は十分に内容に反映されていると感じている.次にこの本に目を通してみた感想を2, 3述べたい. 「どこから読み始めても面白い.」 主観的な感想だが,これがこの本の一番の特長に思えた.「どこから読み始めても」という部分は多少,理由があると推測している.即ち,著者は謝辞で「本書はパリ大学で1973年から2004年にかけて行った講義を下敷きにしている」と述べている.そのため,本文中で相互参照にしている部分が非常に少なく,各章が独立しているのである.「一般的な背景として」書かれた第2章は28ページ(ページ数にして全体の4%!)しかなく,各章の文章はその章で話題になっている物理現象に非常によくフォーカスされている.そしてその説明がうまいこと! 実際,筆者が長い間理解したかったことがうまく説明されている部分に出会ったことが何回もあった(熱分布中の気体を伝わるスピン波,量子情報の手法を使った分光法,ボース凝縮の平均場の直感的説明,など). 「深入りはしていない.」 膨大な種類の物理現象が触れられているが,各事象に対し,エッセンスの説明だけに集中するように常に注意が払われている様子が見て取れる. 「事象の紹介の順番が独特である.」 60年にわたる進展を統一的に扱おうとしているので,歴史的な発見の順序を全く無視して並べなおしている部分もあり,筆者も改めて勉強になった.原子の光の吸収の選択則における角運動量保存からすぐさま光の軌道角運動量の話に入ったり,磁場トラップ,光トラップといった保存力のトラップの話の延長として原子に対してゲージ場をつくる話を登場させるのは著者でないとできない芸当である. もちろん,野心的な試みなので,あら捜しをすればきりがない.フランスのグループが重要な役割をした仕事の記述が多いのはご愛嬌であろう.その代わりに不自然に記述が少ない題材も散見される.しかしこれだけ広範囲の分野の全体像を提供しようとすること自体がそもそも普通は考えられないことである.著者は広大な分野を縦横無尽に行き来し,十分に楽しめる題材をたくさん提供することに成功したと思う.最後は,1997年のもう一人のノーベル賞受賞者,W. D. Phillips博士が「前書き」に使った言葉でこの新著紹介の〆としたい.Bon appetit(さあ召し上がれ!) (2012年4月19日原稿受付)
Neutrons in Soft Matter
原著者:T. Imae, T. Kanaya, M. Furusaka and N. Torikai, ed.
Wiley, New Jersey, 2011, x+654p, 24×17 cm, $149.95[専門・大学院向]ISBN 978-0-470-40252-8
紹介者:遠藤 仁 (原子力機構)
今年はチャドウィックの中性子の発見から,ちょうど80年である.その後,フェルミらがウラン235を用いて核分裂連鎖反応を制御することに成功し,「原子力」の利用につながったことを考えると,科学の歩んだ道程に様々思いを巡らせることになるのだが,一方,熱・冷中性子が物質の原子レベルでの構造とダイナミクスを研究する上で X 線と並ぶ極めて強力なプローブであることが物性研究において直ちに認識され,既に前世紀半ばには「中性子散乱」という分野が確立されるに至った.当初,固体物性の研究に用いられることが主であった中性子散乱は,中性子源と回折・分光装置の発展と共に,近年では生体・コロイド物質に代表されるソフトマターの研究においても強力な手法として多く用いられるようになっている. 本書は,中性子散乱を用いて「ソフトマター」の物性研究を行っている第一線の研究者たちのアンソロジーであり,中性子散乱を様々な角度(実験・理論・装置)から俯瞰することができる内容となっている.読者対象として,実際に中性子散乱を用いてソフトマターを研究している大学院生以上を想定しており,小角散乱・反射率・時間飛行法を用いた非弾性分光装置・中性子スピンエコー分光器・イメージングなどの回折計・分光器・分析装置が,ソフトマターの構造とダイナミクスに関する最新の研究成果と共に紹介されているので,これらの装置や測定原理について詳しく知りたい方々にとって良い教科書となるであろう.更には J-PARC等の中性子源に関する詳細な記述もあり,根源から原理を知りたい人の欲求も満たしてくれる.難を言えば,章節別に著者が異なることによる一連の読み物としての不整合(原理原則が繰り返し出てきたり,理論が導入無しに突然現れたり等)の為,読んでいて少々フラストレーションを感じる部分もあり,初学者向けの教科書としては使い難いかもしれない.しかしながら,同じことを述べてはいても著者それぞれの表現は微妙に異なり,自然科学の研究とはいえ,やはり個性の発露として研究成果が有るのだと妙に納得した.(個人的には冒頭のMezeiの概論は簡潔で素晴らしいと思った.) 中性子が,物質の固い柔らかいを問わず,その本質と多様性を微視的な視点から解き明かす為の極めて強力な道具であることを,本書は鮮やかに示している.(もちろん中性子散乱は万能の実験手法ではないが.)専門家やソフトマターを他の手法で研究している物性研究者は勿論,散乱法を研究手段に用いている全ての物性研究者に読んで頂けたらと思う. (2012年4月6日原稿受付)
Introduction to Quantum Optics; From the Semi-classical Approach to Quantized Light
原著者:G. Grynberg, A. Aspect and C. Fabre
Cambridge Univ. Press, New York, 2010, xxix+665p, 26×20 cm, £45.00[大学院・学部向]ISBN 978-0-521-55112-0
紹介者:平野 琢也 (学習院大理)
本書はフランスの著名な3名の研究者による最新の量子光学の入門書である.飛躍的な発展を続けている量子光学分野をバランス良く学ぶための現時点で最良の書であろう. 物質と電磁場の相互作用を量子論により記述するとき,原理的に3つの方法がありうる.物質のみを量子論により取り扱うか,電磁場のみを量子論で取り扱うか,あるいは,物質も電磁場も量子論で扱うかである.1つめの処方箋は,半古典(semi-classical)論と呼ばれており,非常に多くの光学現象を正しく記述できることが知られている.例えば,レーザーの動作や光電効果も,物質のみを量子化すれば,電磁場をマクスウェル方程式に従う古典的な波動として扱っても,説明することが可能である. 本書の特徴の1つめは,半古典論に紙幅を割いていることである.本書は三部構成となっており,第1部が半古典論,第2部が光の量子論,そして第3部では,これらの応用として,非線形光学とレーザー冷却が紹介されている.光を量子化して取り扱うことにより半古典論よりも広い範囲の現象を説明できるわけであるが,著者たちは,だからといって,半古典論を忘れても良いという印象を与えたくないと述べている.半古典論も間違いなく役に立つもので,ちょうど,惑星の運動を記述するのに量子論を用いないのと同様に,光の量子論を必要としない光学現象も多い.そうすると,どのような場合に光の量子論が必要であり,あるいは有益であるのかという感覚を養うことが重要になる.本書はまさにそのような感覚を養うことを意図して構成されている. 2つめの特徴は,章(Chapter)と多数の補足(complement)から成り立っていることである.この形式により,本質的な部分を短時間で学びたい読者は章だけを読み,必要に応じて補足を参照するという読み方が可能である.補足の内容は,例えば第1部では,ファブリーペロー共振器やガウスビーム光学など実験を行う場合には必須となる知識や,半古典論による光電効果の説明などである. 本書の特徴の3つめは,第一線の研究者により,多数の重要なテーマについて,基礎から説き起こし,その本質に迫ることを目指した解説が展開されていることである.著者の一人であるAspectはベルの不等式の実験的な検証により非常に著名であるが,本書ではもちろん,エンタングルした光子対やベルの不等式について,基礎から実際の実験まで説明されている.量子情報については,Philippe Grangierが量子暗号や量子コンピュータを解説した補足を書いている. 本書の対象は電磁気学と量子力学が既習の学部上級生以上である.この本は元々フランス語で出版されたテキストを拡張して英語版にしたもので(著者の一人Grynbergは英語版の準備中に逝去された),Ecole PolytechniqueやEcole Normale Supérieure等で実践されているフランスの高等教育の一端を垣間見ることができるという点でも本書は興味深い. (2012年4月6日原稿受付)
磁性の電子論
原著者:日本磁気学会編,佐久間昭正著
共立出版,東京,2010,vii+343p,22×16 cm,本体5,000円(マグネティクス・ライブラリー2)[大学院向]ISBN 978-4-320-03469-3
紹介者:赤井 久純 (阪大院理)
過去,磁性理論に関する和書は幾冊かの名著がある.例えば,金森順次郎「磁性」(培風館),芳田 圭「磁性」(朝倉書店),守谷 亨「磁性物理学」(朝倉書店)などは磁性を勉強あるいは研究するものにとって座右の書である.これらの書物は実際に磁性理論を創り上げ,世界をリードする磁性理論の黄金時代を築きあげた人たちによる,自身の成果に基づく教科書である.そのため,それぞれが強い個性を持っており,一見,易しそうに見えて(特に金森順次郎の教科書),良く読むと極めて難解である.結局,関連する論文等を読みこなしながら,なんとか消化して,ようやく自分自身の理解にたどりつかなければ中々ものにすることができない.と,磁性理論の勉強を始める大学院の学生には常々そのように言っている. しかし,佐久間氏の教科書はこの常識を少し覆すものである.この教科書は磁場中の電子の運動から始まって,一応標準的なスタイルはとりつつも,徐々に高度な内容へと進み,多体論的アプローチやスピン揺らぎの理論,第一原理計算にいたるまでが網羅されている.決して大部とは言えないこの一冊の教科書に,一体,これだけの内容を理解できる形でまとめあげることができるのだろうかと心配になるが,不思議なことに初学者にも明快に理解できるように書かれている.また,固体電子論の基礎と銘打った付録がついており,これを学んだだけでもこの教科書や固体電子論・磁性に関する論文を読むのに十分な下地を得ることができる. おそらく,著者自身がかつて磁性理論を学び苦労した経験をもとに,先達の仕事を新たな視点からみなおしつつ,自身の新しいアイデアを盛り込み,これを教科書としてまとめあげられた成果ではないかと想像する. 最初に挙げた古典的な教科書には多くは取り上げられていない内容で本書に取り上げられている話題は,実効的交換相互作用や第一原理電子状態計算であり,1980年以降進展が著しい視点である.多分,最近の大学院学生にとってはこちらの方がなじみ深いかもしれないが,その背後にある磁性の標準理論を良く知って臨まなければ,「学んで思わざれば則ちくらし」になりかねない.その意味で,バランスよく構成された本教科書は磁性理論をはじめようとする大学院学生や,磁性理論を専門とはしない研究者にも強く推薦できる好著である. (2012年3月12日原稿受付)
自然現象と物理法則のあいだ;物理の本質は公式だけではわからない
原著者:鹿児島誠一
丸善,東京,2011,vi+134p,21×15 cm,本体1,600円[学部・一般向]ISBN 978-4-621-08330-7
紹介者:為ヶ井 強(東大院工)
本書は,物理をある程度習った高校生または学部学生を対象とした"読み物"である.と言うのも,本書の内容は科学雑誌"パリティ"に連載された(2009年4月~2010年3月)内容を加筆・修正したものである.とは言え,そこには通常の基礎物理の教科書に欠落している自然現象の抽象化と数理的簡単化,モデル化の過程が,様々な例を用いて平易な言葉で記されている.同著者によるいくつかの教科書と同じように,基礎的な事項が丁寧に分かり易く説明されている所に本書の特徴がある.物理の教科書の中には,完全性・内容の充実度を追う余り,そこに書かれている物理法則等の意味・成り立ち,他の物理分野との関係が初学者にとってブラックボックス化しているものが少なくない.物理とは「物のことわり」の学問であるから,そこで扱われる「法則」は基本的であり厳密なものばかりであるかと言うと,もちろんそうではない.第1章で議論される「クーロンの法則」,「フックの法則」,「摩擦の法則」の比較は,初学者にとって,物理の教科書に出てくる「法則」にも様々な厳密さ・成り立ち・意味が有ることを明快に示している.また,「フックの法則」に代表される調和振動子が,例えば時計の正確さを決めていること,またそのずれに当たる非線形性が物質の熱膨張の原因となることを簡単な考察から明快に示している.本書では,力学,熱力学,電磁気学,量子論,相対論とほぼ全ての物理の基礎分野を僅か130ページの中に納めている.しかし,そのスタイルはユニークであり,例えば,「ヤモリとコウモリはなぜぶら下がれる?」と言うタイトルを用いて,ニュートン力学から量子論への橋渡しをする点等は,朝永先生もびっくりする量子論への導入であろう. さて,ここまで書いて,本新著紹介の意味について考えてみる.明らかに本書が対象としている読者は物理学会誌の読者ではない.したがって,上記の紹介がこれらの対象に触れることはほとんどないであろう.しかし,基礎に重きを置く大学物理教育と物理の最先端を紹介する科学雑誌への執筆の両方に長年携わってきた著者が,その間の溝を難しい数学を駆使せず埋めた初学者向けの本啓蒙書は,長年物理を研究してきた本会誌読者にとっても物理に対する新たな視点を与えるものとして役立つのではないだろうか? 少なくとも,今後の初等物理教育の大いなる参考となることは間違いない. (2012年3月15日原稿受付)
生物リズムと力学系
原著者:郡 宏,森田善久
共立出版,東京,2010,xi+171p,22×16 cm,本体2,800円(シリーズ・現象を解明する数学)[大学院・学部向]ISBN 978-4-320-11000-7
紹介者:青木 高明(香川大教育)
本書はリミットサイクル振動の位相記述に関して,物理学者である郡氏と,数学者である森田氏が共同執筆された入門的教科書である.リミットサイクル振動は,本書の題名にもある生物リズム,例えば心臓の拍動や概日リズム,歩行やホタルの発光,あるいは神経系の振動的活動といった生物の示すリズム現象のみならず,電気回路やレーザー,化学反応など広く非平衡開放系に見られる自律的なリズム振動である.これらの生物・化学・工学システムでは,多振動子間の相互作用による集団同期現象が観察されるが,リミットサイクル振動は一般に非線形微分方程式で記述されるため,多くの場合その解析的取り扱いは困難である.本書では,この集団同期現象の解析に有効な理論的アプローチとして知られる位相記述法を取り上げ,力学系の初歩から位相記述の導入,位相方程式による集団同期現象の解析までを解説している. 本書の特徴は物理学者と数学者の両名がそれぞれの専門的立場を活かした解説にある.序章では物理学者である郡氏が,生物リズムの具体例を多数紹介しながら,これらの現象を記述するための数理モデルの導入を行う.これを受け,次章では数学者である森田氏により数理モデルに関する力学理論入門が解説される.同様に,3章で位相記述法による同期現象の解析が説明された後,4章では位相記述法の数学的基礎付けが解説されている.学際的な研究分野において,このようなそれぞれの専門性を活かした教科書の共同執筆は興味深い試みであり,著者らも述べるように研究現場の雰囲気を感じる一助になるかと思う. また各章毎に補足の項目があり,より専門的な参考書の紹介と,関連研究や最近の動向に関する重要文献がまとめられている.これは興味を持った読者が,本書の内容を越えて学んでいくためのガイドラインとして非常に有効である.また,さらなる情報収集の仕方や計算機シミュレーション等に関しても触れられており,入門的教科書として有用であろう. 記述も図を活用しつつ丁寧に説明されている.ただ一部,位相記述について,ある変数が時間変数であるか,それとも位相変数であるか,説明が不十分と思われる点もあった.初学者として混乱しやすいところでもあり,一部の証明に関わる箇所もあるため,詳しい説明が加わるとさらに読みやすくなるかと思う. ともあれ近年,工学や生物分野など,物理学以外の分野においても位相記述を用いたリズム現象の解析は広く盛んになってきている.本書は,その位相記述に関する数学的基礎付けを,力学系の基本から学ぶ上で適した入門的教科書である. (2012年3月9日原稿受付)
BCS: 50 Years
原著者:L. N. Cooper and D. Feldman
World Scientific, Singapore, 2011, ix+575p, 25×17 cm, $135/£84[専門~学部向]
ISBN 978-981-4304-65-8
紹介者:青木秀夫(東大理)
超伝導は,物性物理学だけでなく,物理の多くの分野に関わる特段の面白さをもっているといえるが,1911年にKamerlingh Onnesによって超伝導が発見された百周年に当たる昨2011年にはこれを記念した様々な国際会議が行われた.一方,1957年にBardeen, Cooper, Schriefferにより提出された超伝導のBCS理論は基本中の基本だが,これも数年前に50周年記念を迎えた.本書はこれを記念した論文集で,23の章から成り,編集にはBCSの一人であるCooperとBrown大学での同僚Feldmanが当たっている.
BCSは,二つの点で興味深い.一つは,20世紀前半には超伝導を理論化しようと多くの物理の巨人(Heisenberg, Landauや実はEinsteinも)が挑戦したが,半導体を専門とするBardeen(Shockley, Brattainとともにトランジスターを発明)のグループが成功した.実際,Cooperは自らの章で,「自分が1955年にBardeenのpostdocになった時点では,超伝導の素人どころか,超伝導という概念すら知らなかった」といっている.もう一つは,半世紀の間に,BCSをはじめとする様々な概念が,ハドロン物理などへのスピンオフを見せた一方,MRIなどデバイスへの影響も与えた.そのため,本書も内容は非常に多岐に亘っている.
本書の構成は,先ず「歴史的概観」から始まる.Cooperの「超伝導の懐古」で彼はBCSの事始めを語り,先ずはエネルギー・ギャップを説明しようという方針をたて,当時最新のファインマン・ダイアグラムや繰りこみの手法を駆使しようとしたが,出発点のエネルギー・スケールに比べ,超伝導状態になったためのエネルギー利得が桁違いに小さい,という壁に先ず突き当った由(このあたりは,電子相関の関与する高温超伝導酸化物で,同じ問題が別の物理で生じたことを思い出させる).フォノン交換が電子間引力を生むことはFröhlichなどにより示唆されていたが,Cooperはこれがフェルミ面上の電子に働いたときの問題(Cooper不安定性)となることに気付いた(1956年).しかし,Cooperペアは重なりあっているので単純なボース・アインシュタイン凝縮(BEC)はしないのでは,というのがCooperの勘だった.ただ,現在の目で見れば,BCS-BEC間のクロスオーバーは冷却原子系で実現している.いずれにせよ,当時のアメリカ物理学会で,Feynman(超伝導理論をやろうとしていた)とOnsagerが居るところに,目に唯ならぬ光をたたえた(wild-eyed)Cooperがやってきて,「僕は超伝導を解いた」と説明したが,Feynmanは理解できずこの若者はおかしいのでは,と思ったのに対し,Onsagerはしばし黙考したのち,彼は正しいと思う,といった.しかし,Cooper不安定性から多体系全体の状態への道程は一筋縄ではなく,丁度1956年に半導体関連でノーベル賞を受けたBardeenがストックホルムに行くときに,Schriefferが絶望してテーマを変えたい,というとBardeenは「やり続けてごらん,何か(something)は出てくるかも」といった.そのsomethingがBCS波動関数形であった.マイスナー効果の計算ではゲージ不変性が気になったが,Bardeenは,ゲージ不変性は有るはずだから特定のゲージでやれ,といった.後に,Weinbergが,(本書の彼の章を含め)「超伝導とはゲージ対称性の自発的破れに他ならず,マイスナー効果等の物性はこれの帰結だから超伝導機構を探索する必要はない」と主張するが,Cooperはその見解には反対している.これはほんの粗筋の一部であるが,小説を読むように興奮させられるとともに,現代でも色々な意味で示唆的なことを考えさせられる.
Schriefferの「BCSへの道程」は,インタビュー形式(AIP websiteにも貼ってある)を活字にしたものである.日本の読者に特に興味深いのは,Schrieffer(BCS理論当時25歳の院生)がBCS波動関数の形を思いついたのは,元々,朝永振一郎が原子核の中のπ 中間子の問題において変分法の試行関数を作っていた(1947年)のに触発されたことである(これはAPS百周年記念のRev. Mod. Phys. 71(1999)の中でもSchriefferが述べている).
Bardeenの「超伝導概念の開発」では,彼は1991年に没した故,ここでは1962年にロンドンでの低温物理学国際会議でFritz London賞受賞記念に行った講演が収録されている.BCS状態を特徴付ける重要な性質は波動関数のコヒーレンスだが,一つ注目すべきは,Bardeenのイリノイでの同僚にHebelとSlichterがおり,現在では彼等の名を冠したNMRの現象を1957年に実験で見つけ,それがコヒーレンスと関係していることにBardeenはすぐ気付いた,ということである.後の「NMRとBCS理論」の章でSlichter自身も詳しく語っているが,彼が超伝導に興味をもったのは偶然ではなく,Bardeenが超伝導の講演で多体効果によりギャップが開く,といったので,NMRに影響しないはずはなかろう,と実験をした由である.また,BCS理論は発表当時は意外と強い批判もひきおこした.一つの批判はこの理論はゲージ不変性を破っているという点であり,理論を全てゲージ不変に定式化できるということは,この数年後(1960年)の南部やGor'kovの理論を待つ必要があった訳である.これは南部自身が「エネルギー・ギャップ,質量ギャップと対称性の自発的破れ」の章で述べている.
さて,この調子で紹介していては紙幅を大幅に超えてしまうので,あとの目次はhttp://www.worldscibooks.com/physics/7728.htmlで見ていただくことにして,特徴ある章に一言ずつコメントすると,Gor'kov(Landau学派)は,BCS理論をBogoliubovが場の理論で分かり易くしたので「西側と違って」ソ連ではBCSはすんなりと受け入れられた,と強調し,Andersonはゲージ不変性について南部理論を経て
Anderson-Higgs機構に至ることに触れている.また,超伝導の電子機構の提唱者の一人として,関連する3Heの超流動や有機超伝導体,最近の鉄系超伝導体にも触れている.第二部は「揺らぎ,トンネリング,不規則性」,第三部は「新超伝導体」,最後は「超伝導以外でのBCS」の部となる.
このように,多彩で錚々たる著者により広い範囲が論じられているのが本書の迫力である.銅酸化物高温超伝導をはじめ,ヘリウム(Leggett)や冷却原子系(KetterleらやBaym),ハドロン物理・QCD(BaymやWilczek)がカバーされる.関連書としては,Bardeenの伝記(V. Daitch: True Genius(Joseph Henry Press, 2002))や,いまだに価値を失わないJ. R. Schrieffer: Theory of Superconductivity(Benjamin, 1964; Perseus Booksから1999に再刊)がある.今はarXivの目まぐるしい時代ではあるが,それだからこそ,ものごとを50年,100年単位で見直すことはますます大事と思われる.というわけで,本書のような集成は,読者は歴史に浸るのも良し,実験的・理論的にブレークスルーを狙うスタートラインに使うのも良く,超伝導専門外の方も含め,研究者,学生ともに強く薦められる本である.
(2012年2月20日原稿受付)
カダノフ/ベイム 量子統計力学
原著者:L. P. カダノフ,G. ベイム著,樺沢宇紀訳
丸善プラネット,東京,2011,ix+202p,21×15 cm,本体4,800円[大学院向]
ISBN 978-4-86345-090-5
紹介者:北 孝 文(北大理)
グリーン関数法を用いた量子統計力学の古典的名著"カダノフ-ベイム"が,丁寧に訳出されて,英語の得意でない大学院生にとっても身近な存在となった.ハーバード大学の同じシュヴィンガー・スクールで独立に博士号を取った若きカダノフとベイムが,ポスドクとして再会したニールス・ボーア研究所で初めて共同研究をして講義をし,それをもとに1962年に書き上げたのが本書である.同時期の他の教科書と比べたその大きな特徴は,シュヴィンガー直伝の汎関数微分法を駆使して,非平衡系を扱っていることにある.具体的には,一粒子グリーン関数のシュヴィンガー-ダイソン方程式がボルツマン方程式の一般化になっていることを示し,それらの間の関係を明らかにした点に大きな業績がある.これにより,非平衡現象を,シュヴィンガー-ダイソン方程式と摂動論を用いて,微視的かつ系統的に扱う道が開かれた.シュヴィンガー-ダイソン方程式に勾配展開をほどこして得られた(9.30)式と(9.31)式は,しばしば"カダノフ-ベイム方程式"と呼ばれる.
議論は,二次摂動までの結果と物理的直観とに基づいて,本質を射抜いて簡潔にきびきびと進められていく.これについていければ良いのであるが,一般には,敷居が高いことを覚悟して読み始めるべきか.摂動展開の一般論や既約自己エネルギーの定義も出てこない.また,ここで扱われている摂動展開は,繰り込まれたグリーン関数を用いた自己無撞着摂動展開であって,単純な摂動論ではないのだが,その辺りに関する説明も不足している.さらに,早い時期に書かれたことから,後年における二つの大きな発展が取り込まれていない.その一つは,ケルディシュによる実時間非平衡グリーン関数法(1964年)である.本書は,平衡状態の虚時間松原形式を経由して実時間の動力学を議論しているが,このアプローチは現時点から見るとやや冗長で,その上,三次摂動以上に踏み込むのは困難である.一方,最初からケルディシュ・グリーン関数を用いれば,見通しよく高次まで議論を進めることが可能である.第二点は,ベイム自身によるΦ微分近似の開発(1962年)である.一般に,非平衡現象を扱うには,時間発展しても粒子数・運動量・エネルギーを保存するような枠組みを用いる必要があり,本書でもその点には十分な注意が払われている.しかし,Φ微分近似は,「保存則に従う」という非平衡系必須の要請に対して,より簡潔で見通しの良い条件を与え,また,本書で議論されている様々な近似も,採用するΦの違いとして明快に理解できる.
以上の難点を補ってあまりあるのは,随所に散りばめられた物理的な議論で,今読んでも大変有益で学ぶ所が多い.身近な書棚に置いて暇を見つけて繰り返し読んでいると,味わいが深まり,得る所の多いこと請け合いの名著である.
(2012年2月13日原稿受付)
大沢流 手づくり統計力学
原著者:大沢文夫
名古屋大学出版会,愛知,2011,vii+154p,21×15 cm,本体2,400円[大学院~一般向]
ISBN 978-4-8158-0674-3
紹介者:永 山 國 昭 (自然科学研究機構)
20年前になるが,つくば市の筑波コンソーシアムで私が主宰していたプロジェクトの面々と大沢流統計力学の講義を受けたことがある.「目からウロコ」とはこのことかと思うほどの衝撃を受けたのを思い出す.私一人に留まらず,受講者全員が同じ思いだったろう.たった2時間の講義で3つの普遍的真実を悟ったのである.①「手づくりの物理は身につく」,②「ボルツマン分布の本質」,③「統計法則の普遍性」.
①はこの本を読むときの心構えと関係している.読者は統計力学を体感するためサイコロとチップで問題を解かなければならない.この作業はゲーム性や意外性があり,楽しい.そして私達の統計事象に関する根源的先入観を矯正してくれる.粒子間のエネルギーの自由な交換は交換回数が多ければ多いほどエネルギーの偏在を招来する.その偏在の程度がエネルギー分布関数ボルツマン分布である(②).この物理の深遠な法則を2つのサイコロと30枚のチップを用いて1時間かからずに納得できる.そしてはたと気づくのだ.自由な市場経済において富が偏在(少数の金持ちと大多数の貧民)するのは逃れられない統計的普遍法則なのだと(③).
この機会均等にチップのやりとりをする消費税型のルールを変えると異なる分布が生まれる.各粒子のエネルギー量に比例して交換量を増減させると(所得税型ルール)低エネルギーに分布の山が出て極端な低エネルギー粒子は減る.しかし高エネルギー粒子はやはり少数.どんなことをしても統計法則の呪縛,結果不平等(チャンス平等だが)はなくならない.いやおかしい,物理の世界にそんな不平等のあるわけがないと思う人には次のゲームが用意されている.
1つの粒子に注目し,そのエネルギー量の変動を時系列で追うのである.長い時間をかけると1つの粒子は低エネルギー,中エネルギー,高エネルギーの間をめぐる.すなわち長時間かけて平均をとれば系の平均エネルギーと等しくなり,物理法則は中立を保証していると分かる.しかし粒子一個一個のエネルギー滞在時間を見るとほとんどの時間は低エネルギーでたまに高エネルギーとなる.それはボルツマン分布の時間表現でもある.このことは純粋な自由市場経済においてほとんどの場合人間一生の平均所得がその社会の平均所得に及ばないことを意味する.人生100年では富の時間平均化は実現せず,多くの人間は一度もお金持ちになれない.人類の歴史を見てもこれは充分納得がいく.しかしそれが人間の努力や英知を超えた自然法則だと達観すればかえってすがすがしい気持ちにもなれる.
私が20年前に悟れなかったさらに大事なメッセージがこの本の第二部を形成している.④「3個以上の要素よりなる系から統計力学は成立し,少数自由度よりなる生体系の分子機械の作動機構を説明し得る」.日常機械に比べ熱的揺動の中で動く蛋白質という分子機械が何故高効率の化学-力学エネルギー変換を成し得るのか(筋肉を構成する分子モータなど).その秘密を少数多体系においてさえ定義し得る局所温度の導入で説明している.これは多くの物理屋の先入観を裏返す革命的物理モデルではないだろうか.最先端の物理計測法で是非とも実証したいと願うのは私だけではないだろう.
この本を物理屋に読んでもらいたい.さらに政治家,経済学者そして一般社会人にもささげたい.ここには世の中の根源的不条理をすがすがしく説明し納得させる真実が詰まっているのだから.
(2012年1月10日原稿受付)
液晶の歴史
原著者:D.ダンマー,T.スラッキン著,鳥山和久訳
朝日新聞出版,東京,2011,535+49 p,19×13 cm,本体2,300円[一般向]
ISBN 978-4-02-259982-7
紹介者:福田 順一(産総研)
ほとんどの人が日頃テレビや携帯電話,パソコンのディスプレイで液晶の世話になっていると思うが,それらが開発されるまでの経緯を知る人はほとんどいないであろう.そもそも液晶がどのようにディスプレイに用いられているかを説明できる人も,決して多くはあるまい.本書はそれらの疑問にわかりやすく答えてくれる良書である.
本書の縦糸をなすのは,どんな研究者がどのように液晶の研究に関わってきたかに関する詳細な記述であり,「流れる結晶」に対する初期の激しい論争,あるいは液晶ディスプレイの開発にまつわる生々しいドラマは,非常に読みごたえがある.また,液晶の研究を生業にしている評者も知らないことが数多く書かれていて驚かされた(例えば,最初の液晶はニンジンの研究から発見されたこと,Max Bornが液晶相発現理由の理論的考察を試み失敗していたことなど).著者は研究者の遺族からのものを含め膨大な一次資料を調査しており,それが本書の記述に反映されている.液晶研究の歴史を記した書としては,決定版とも言えると思う.
そして本書の横糸をなすのは,「科学抜きの液晶の歴史を語ることは不可能だ」と著者が記すように,液晶科学の基礎に関する説明である.随所に挿入された「解説」は液晶の構造や物性,あるいはディスプレイの原理を理解するために必要な事項を簡潔に紹介しているし,巻頭にはカラフルな口絵もある.さらに第12章「液晶物質の新世界」では,前の章で触れられなかった種々の興味深い話題(強誘電性液晶など)を取り上げている.これらの記述や図は,液晶の何が物性科学として重要で面白いかを専門外の読者がざっと理解するには良い資料となる.また,ソフトマターに関する導入的な講義のための良い種本にもなるだろう.なお原著のタイトルは"Soap, Science and Flat-Screen TVs"であり,標準的な液晶の教科書ではあまり取り上げられない界面活性剤(石けん)や生物系についても1章が割かれている.液晶はディスプレイだけのものではないと伝えるのも著者の意図であり,それは十分に達成されている.
480ページもの大部を訳し切ったのみならず,邦訳のために1章を書き下ろした訳者の功績は大きい.この章では日本の液晶技術開発の歴史を活き活きと描写し(訳者は日立製作所で液晶研究に関わった),日本の液晶産業が華々しい成功を収めた理由について考察を加えている.ただ,専門用語の訳語の選択には,やや癖がある.液晶のtwist変形を「よじれ」としているが,「ねじれ」が一般的であろう(ただし,この選択についてはp. 503にコメントがある).巻末には丁寧な用語集があるので,専門用語の英語表記を一度参照することを,読者にはお勧めする.
(2012年1月6日原稿受付)
いきいき物理わくわく実験3
原著者:愛知・三重物理サークル編
日本評論社,東京,2011,iii+232 p,21×15 cm,本体2,200円[一般向]
ISBN 978-4-535-78431-4
紹介者:種村 雅子(大阪教育大)
本書は,愛知・三重県の中学校・高校・大学の教員を中心に集まった物理教育を研究するグループによって執筆されたものである.これは好評であった「いきいき物理わくわく実験1, 2」に引き続いて出版されたものである.創意工夫された手作りの実験がかなり豊富に紹介されていて,読み応えがある.
第1集は1988年に発行され,いきいきと物理を学び,わくわくと実験することを目指して編集された.これは「理科嫌い・物理離れ」といわれた時代の中で物理の楽しさを伝える著書として大きな反響を得た.1999年には第2集が発行され,2011年にこの第3集が発行される運びとなった.この著者たちは物理教育国際会議では"STRAY CATS(のらねこ)"という愛称で呼ばれている.
生徒たちの意欲を引き出す授業をしたいという教員の思いは世界共通であり,彼らのワークショップやポスターセッションは,物理教育の研究者や物理教員たちから高く評価され,注目を集めた.
本書で紹介されている実験は簡単に作れそうなものから大掛かりな装置まで様々であり,教室での演示実験用として大型でダイナミックなものが多いようである.例えば,大学の基礎課程でも取り扱われるメルデの実験の改良型も載っている.大学では電磁音叉を使っているが,本書では身のまわりにある電動のこぎりのジグソーを使用している.電磁音叉付きの実験装置が無くてもできるので,ぜひやってみたいとわくわくした.また,光の三原色の実験についても,赤・緑・青の色セロハンと光源を用いて,光の混合実験をして,シアン・マゼンタ・イエローの光を作り出している.赤と青からマゼンタができる過程がわかり,この実験を通して本質的な理解ができる.このテーマは教科書のカラーの図を見て,暗記していることが多く,理解しているわけではない生徒・学生も多いのではないか.他にも,ぜひやってみたいと思う実験が多々紹介されている.また,第1集,第2集からどんどん改良型もでてきていて,この研究グループの活動が継続的で活発なことが伺える.
本書は高校の物理教員や物理教育の研究者のみならず,学部の授業を担当する大学教員や高校教員を目指す学生たちにも有用である.最近の高校物理では実験をしない教員も多く,日本全体で見れば,この著者たちのような優れた演示実験を普段の授業に取り入れている高校教員は少ないのが現状のようである.やはり,基礎として学ぶ古典物理では物理現象を実験で見て,理論と一致していることを確認することで,意欲的に学び,本質的な理解に繋がるのではないかと思う.来年度から高校では新カリキュラムが始まり,教科「物理基礎」を必修とする高校も増えるようである.本書のように,いきいき,わくわくと物理を学んできてくれることを願っている.
(2012年1月10日原稿受付)
結晶欠陥の物理
原著者:前田康二,竹内 伸
裳華房,東京,2011, ix+216 p, 22×16 cm,本体3,500円[大学院・学部向]
ISBN 978-4-7853-2917-4
紹介者:白 井 光 雲〈阪大産研〉
書評というものは,書いた著者と同等かそれ以上の学識をもった人が書くのが普通で,その意味で評者ははじめからその資格がない.200ページあまりの本書にちりばめられている事項で評者の知らなかったことは多い.しかし教科書の目的は知らない人にわかってもらうことであるから,そういう読者の立場でみることが評者に求められていることと勝手に解釈して本書を読む.
まず,最初の印象であるが,格子欠陥の作る電子状態のミクロ理論と,転位論を中心としたマクロ理論を統合し全体を俯瞰するという著者の意図はよい着眼点である.前者は,半導体の価電子制御の中核として半導体研究者が知らなければならないものである.一方,後者の転位論に関しては,どちらかというと冶金学的な色が濃く,物理の教科書ではあまりない.しかし考えてみると,結晶成長に携わる人にとって,このような区別は意味がない.現実には点欠陥も転位も同時に起きているし,また点欠陥から転位まで成長することもあり,自分の都合通りの現象だけが現れるのではない.両方知らなければならない.ところが転位論というものは,日本語で読めるものはほとんど金属などの工学書で,そういうものをひも解くとき,やれ金属組織学だの冶金学的な知識とかが要され,物理屋からみるとそこに障壁がある.
著者たちが指摘する「格子欠陥を物理の立場から論じるものが少ない」というのはその通りと思う.評者の身の回りにあるものを探すと,キッテルの『固体物理学入門』では転位論に一章を割いている.ところがキッテルのものは理解し難い代表である.訳者には失礼ながら訳が悪い.特に欠陥に関する章は何を言いたいのかわからない,誤りでないかと思われる箇所もある.勇み足で他書を批判したが,もちろんそれが意図ではない.主張したいことは,物理の分野で学生が転位論を勉強しようとしたとき日本語で手ごろな本はキッテルくらいしかなく,そのような状況は非常にまずいということである.その意味で今回の企画は当を得たものといえ,まずはこのような状況の中で時代の要請に応えるものと喜びたい.
説明の仕方は,通り一遍のフラットな言い方ではなく,初心者だけでなく専門の人にも間違えそうなところをきちんと説明している.最初のところの,格子欠陥の形成エネルギーの定義など,よく「格子点にある原子を取り除き,結晶表面につける」というような表現を目にするが,そうすると表面状態がどうのこうのとあらぬ方向に議論が反れることを目にする.そのようなboundary sensitiveな定義に陥らないように説明している.ギャップ準位についても,今日の第一原理計算の達成点を良く反映して,単に「バンドの中にこのような準位ができます」というような説明に留まっていない.
扱っている物質は金属から半導体まで幅広い物質にわたっている.我々物質の研究者はえてして自分の研究対象物質に関して詳しいだけで,ちょっと違った物質でどうなっているか知らない.違っているとして,その違いが一般的なものなのか,たまたま違っているだけなのかよくわからない.こういうことがわかるためには物質全般に対する大変な研究経験が要され,それをハンドブック的列挙にならず有機的にコンパクトに収めることは,著者のようなごく少数の研究者のみが達成し得るものであろう.評者などこの本のレビューを書くことで一番利益を受けた一人である.
後半の転位論に関しては,評者は素人であるが,これまで他の本を読んでもあまり理解できないことが多かった分野である.他の本を読んで困ったことは,「らせん状転位の境界はすべり方向に平行である」など然も当たり前のように書いてあるのをみるが,素人にとって「境界」とはどのことをいうのか戸惑う.転位は動き得るので,変位といってもバーガーズベクトルのことをいっているのか,それとも転位の運動の変位なのか.写真なども現実のものを観察することは大事であるが,しかし前提としてきちんと説明されている必要がある.写真というものはしばしば主張したいこと以外のものも映っており,きちんとした説明なしでは初心者はゴミにも惑わされかねない.こうしたことは評者のよく経験することであるが,本書ではそのような曖昧さはほとんどなかった.
著者たちのような博識を持ってすると,はじめ思い描いた題材は多く,それを削りに削ってこのページ数に収めたことと想像する.日本の出版社は常に簡潔さを要求してくるからだ.簡潔という言葉は聞こえは良いが,言葉足らずということに陥りがちである.本書だけで自己完結的に理解しようとすると,私にはやはり転位のところは多少の論理の飛躍が感じられ,ついていけなかったところがある.これを丁寧に説明しようとすると,その代償としてページ数は増え定価は上がる.それを読者は受け入れるだろうか? そういう板挟みを背負いながら著者たちは書いているのだと想像するが,このあたり出版社にも薄いことを至上命令とするような姿勢を改めて欲しいものである.
(2011年10月25日原稿受付)
基礎からわかるナノデバイス
原著者:青柳克信,石橋幸治,髙柳英明,中ノ勇人,平山祥郎
コロナ社,東京,2011, vi+242 p, 21×15 cm,本体3,400円[大学院向]
ISBN 978-4-339-00823-4
紹介者:町 田 友 樹〈東大生産研〉
量子ビット,単電子トランジスタ,スピントロニクス,フォトニック結晶など,量子効果を利用したナノデバイスの研究は基礎・応用の両面で大きく発展し,関連する論文や研究者の数も飛躍的に増大している.一方,大学院生や学部生が新たに研究を開始するとき,最初にぶつかる壁は最先端の研究論文を理解するための基礎的知識の必要性であろう.本書はナノデバイス研究の基礎物理現象に関する初学者向け教科書であり,ナノ構造中の物理現象が量子力学の基礎から丁寧に解説されている.背景にはナノデバイスを用いた量子情報技術への挑戦があり,固体量子ビットの実現に不可欠な要素として電子・スピン・フォトン・クーパーペアを取り上げて,最先端研究の理解に必要な基礎事項の習得を目指している.
「電子」の章では,低次元電子系における電子波干渉効果やクーロンブロッケード効果などの物理現象が解説されている.ナノ構造中の電子輸送現象に関する基礎知識が習得でき,単電子素子や量子ビット素子への展開を理解していく.
「スピン」の章では,スピン演算子の基礎的な取り扱いに始まり,スピン磁気共鳴の説明を経て,電子スピン/核スピン量子ビットの議論に至る.磁気共鳴の回転座標系における記述を扱うなど,スピンの基礎から量子状態制御までが非常に丁寧に解説されており,この分野の若手研究者にとって有意義である.また,スピントロニクス応用やスピンホール効果についても簡単に触れられており,より具体的な論文や発展的な解説への足がかりにするとよい.
「フォトン」の章では,量子井戸における電子状態など,基礎的な量子力学・固体物理学を実践的に復習し,半導体低次元構造の発光特性やレーザ応用,急速に発展しつつあるフォトニック結晶の基礎までが理解できるように構成されている.
「クーパーペア」の章では,巨視的トンネル効果などの超伝導入門から始まり,超伝導量子ビット操作の実際と多量子ビットへの展開が記述されている.本分野の先駆者らが執筆しただけに,クーパー対の制御により実現された3種類の超伝導量子ビット(電荷/磁束/位相)の動作原理を理解する上で,格好の解説書となっている.
本書で特徴的なのは,最先端の研究内容を理解するために必要な基礎事項を,先駆的な研究を進めてきた著者らが自ら丁寧に講義しているかのような内容となっている点である.全編を通じて演習問題と解答が用意されており,重要な基礎法則や関係式の導出など,学習者が自ら手を動かして確認することで理解が深まるだろう.この点も新たに研究室に配属された大学院生/学部生が基礎事項を学ぶ上で親切な構成となっている.研究室で行う輪講のテキストとしても適切である.
(2011年9月3日原稿受付)
High Energy Astrophysics 3rd Edition
原著者:M. S. Longair
Cambridge Univ. Press, New York, 2011, xv+861 p, 25×20 cm, $85[専門・大学院向]
ISBN 978-052-175618-1
紹介者:郡 和 範(KEK)
十数年ほど前に,東京大学宇宙線研究所のガンマ線観測の大御所の方に,偶然,本書のファーストエディションの感想を伺ったことがある.その方の表現は鮮烈で,「著者1人でこれだけ広い内容をカバーできるものなのか?」であった.高エネルギー宇宙物理学に現れる素過程を網羅し,反応の観点からあらゆる高エネルギー天体現象を紹介する内容に,彼は素直にそう口にしたのであろう.今回のサードエディションでは,セカンドエディション以降に話題になった内容も豊富に取り込まれて改定されている.例えば,大きく発展してきたニュートリノ振動実験の結果を紹介する部分なども加わっており,たいへん頼もしい内容となっている.以前に古いエディションで勉強された方々も,新しい内容を網羅したハンドブックのような感覚で,本書を手元に置く価値もあるのではないだろうか.
通常の教科書で素粒子の散乱断面積や反応率の具体的な計算を解説する際,場の量子論などのフォーマルな手法を用いて,正確に求めることに主眼がおかれることが多い.かなりの技術的な修練が必要であり,初学者であればあるほど,その細かい技術に気を取られ,全体の物理的な理解が不十分なまま先に進んでしまう傾向があるように思う.実際に学部生や修士1年生の頃の評者はそうであった.
しかし,最前線の宇宙物理学の研究に徐々に触れるにつれて,宇宙物理学では,ユーザーの立場で教科書を利用する場合が圧倒的に多いと気付くようになる.それは素粒子論と宇宙物理学との間の業界の価値観の違いといってもよいかもしれない.Longairは,細かい計算技術にとらわれることなく,他によく知られている素過程とのアナロジーを使いながら,最初におおざっぱに導出する方法を紹介し,まず物理量の組み合わせが物理的にどのような意味があるかを簡単に紹介する.式を通して,背後で起こっている宇宙の現象が透けて見えるかのごとくにである.その後,「もっと正確な計算に基づくと,このような式になります」と,さらりと厳密な結果を書いて終わるのである.例えば,第5章のイオン化損失のそうした導出方法は美しく,驚くほど見事である.本書は高エネルギー宇宙物理研究の実践向けの教科書と呼ぶにふさわしいだろう.
評者が大学院に入りたての頃,丁度,2分冊にわたるセカンドエディションの2分冊目が発売された.上述のようにファーストエディションが1冊の評判の良い本であったため,2冊もあるセカンドエディションを持っている我々は,色々と揶揄されたものである.それが,サードエディションでは再び1冊にまとまるに至り,評判のよくない版で勉強してきた身として,いくぶん複雑な想いである.著者も書いているように,この"コンパクトで使いやすい"サードエディションで,最初から高エネルギー宇宙物理学の素過程をスマートに学べるとは,今の若手研究者はさぞかし幸せに違いない.
最後に,他の標準的な教科書と比較しておくのも重要であろう.George B. RybickiとAlan P. Lightmanの共著"Radiative Processes in Astrophysics"は,比較的電磁相互作用の紹介に重きを置いている.また,式の導出の方法も,厳密に求まる場合が多いせいか,天下り的に行う場合が多いように思う.幅広い相互作用を扱い,物理的な側面に焦点を当てている本書とは役割分担されているだろう.Lyman Spitzer Jr.による"Physical Processes in the Interstellar Medium"では,式の導出にはあまり説明が割かれておらず,行間を埋めながら勉強することを期待して書かれているように思われる.本書のねらいとは,むしろ正反対であると言っても過言ではないだろう.上述したとおり,高エネルギー宇宙物理学の専門家には,知識をコンパクトにまとめてくれているハンドブックとして,また,初学者には実践的な入門書として他に例を見ない良書であると推薦したい.
(2011年9月5日原稿受付)
プラズマ原子分子過程ハンドブック
原著者:浜口智志,村上 泉,加藤太治,プラズマ・核融合学会編
大阪大学出版会,大阪,2011,x+394 p,26×18 cm,本体5,200円[専門・大学院向]
ISBN 978-4-87259-362-4
紹介者:赤 塚 洋(東工大原子炉研)
「プラズマ」に関わる学問は非常に幅広く,日本物理学会の方々に馴染みの宇宙物理や核融合だけとは限らない.工学分野では,溶接など金属工学,蛍光灯やEUVなどの光源,LSI・絶縁膜・太陽電池生成などの電気電子工学や表面処理など材料工学でも応用され,これらはプロセスプラズマと総称されている.そのほとんどにおいて,プラズマ内部の原子分子過程が重要である.本書は基礎分野と応用分野の双方を扱うこの分野の待望の書籍である.
第1部基礎編では,プラズマ内部の原子分子過程を解説すべく,序論に始まり,原子構造とスペクトル,分子構造とスペクトル,衝突断面積と反応速度係数,電子・光と原子・イオン衝突,電子・光と分子衝突,イオン原子衝突,イオン分子衝突,化学反応速度論と衝突輻射モデル,輻射輸送と,各章毎に古くからの基礎理論から最近の成果まで網羅的に記述がなされている.それぞれの分野の第1人者による分担執筆が功を奏し,バランスの良い事が特筆すべき点である.
第2部応用編では,超高層大気,宇宙プラズマ,核融合プラズマ,レーザー生成プラズマ,プロセスプラズマ,環境プラズマと対象となるプラズマごとに1章を割き,特徴となる原子分子過程のリストアップ,断面積の解説から実験方法の簡単な紹介や,流体コードとのカップリングなど,それらを利用して解明された物理現象についても研究成果が多数紹介されている.最後に,各種のデータベース概論についても1章を割き,各種文献やオンラインの計算サイト,計算コードなどが紹介されている.本書は「データそのものは掲載しない」事を原則とし,データに対してはガイドブックとしての役割に徹していることにも敬服できる.
第1部は基礎を重視した教科書,第2部は応用を重視したハンドブックとしての色彩が強いが,あえて分冊とせず一つにまとめた所が,本書の大きい特徴で,かつ,我が国のプラズマ理工学分野の状況をも,端的に示している.日本物理学会領域2独自の事情であるが,2011年度の日本物理学会秋季大会では,領域2は初めて「物性」分野を離れ,プラズマ・核融合学会および応用物理学会プラズマエレクトロニクス分科会と合同で,11月に金沢市内で開催の「プラズマ・カンファレンス」を秋季大会に代えて行なった.我が国におけるプラズマ学際連携を推進し,プラズマ分野の基礎と応用の交流を促進するため,学術団体が相互協力している.団体だけでなく本書のように,基礎分野と応用分野の研究者の相互理解に基づき意識が統一され,多くの分野の研究者による共著の形で本書が上梓された事は,多数の研究者が基礎分野と応用分野の相互協力の必要性を強く認識している事を意味している.誠に慶ばしい事であり,今後のプラズマ界の益々の発展が期待されるところである.学際共同が具体的に実行されつつある今まさに,プラズマ物理学分野の研究者はもちろん,基礎現象に興味のあるプラズマ工学技術者にも,本書は強く推薦の1冊である.
(2011年8月31日原稿受付)
超重力理論;超弦理論における役割
原著者:谷井義彰
サイエンス社,東京,2011,vi+178 p,26×18 cm,本体2,381円(SGCライブラリ-82)[専門・大学院向]
ISSN 4910054700411
紹介者:今 村 洋 介(東工大院理工)
本書が解説する超重力理論とは,超対称性をもつ重力理論のことである.超対称性はボゾンとフェルミオンを結びつける対称性であり,素粒子論において,現在もっとも注目されている対称性と言ってもいいであろう.現在進行中のLHC実験においてもその検出が期待される.現象論的に重要なものであるというばかりでなく,解析的に扱い易く,数理的観点からも注目されている.特に,超弦理論の低エネルギー有効理論として超重力理論が現れるため,超弦理論を用いた解析には欠かすことができない.本書では,その副題が示す通り,後者の側面に主眼をおいた超重力理論の解説書である.
超弦理論においては,時空の次元などが異なる様々な超重力理論が登場するが,これまでそれらを初心者向けに解説する教科書は存在しなかった.超重力理論を含む最も標準的な教科書としてはWess-Baggerのものが挙げられるが,そこでは4次元の超重力理論しか触れられていなかった.本書はそれとは対極的に,様々な超重力理論について,その構成法などには触れずに結果だけを示し,それらの関係を概観するという方針を取っている.
本書の構成について簡単に述べておこう.まず第1章で超弦理論との関係と,超重力理論に現れる幾つかの種類の場について解説し,その後で,4次元の場合の超対称性の種類について解説している.その後は様々な次元の超重力理論に触れながら,非コンパクト対称性の存在や,次元還元を通した理論間の関係などが解説されている.
本書では,ラグランジアンを与える際には弦理論への応用であまり用いられることのないフェルミオンを含む項は多くの場合に省略されており,また,物質多重項を導入することによる拡張についても触れられていない.従って現象論への応用に興味のある読者や,非常に複雑なラグランジアンの完全形を見て悦びを感じる超重力ファンにはもの足らないかもしれないが,副題が示すような超弦理論への応用を念頭においた入門書としては大変読みやすくなっている.
本書の内容は超重力理論におけるアノマリー相殺について解説した第8章を除いて古典論であり,古典的な場の理論の基礎について学んだ修士課程の学生であれば難なく読み進むことができるであろう.弦理論を学ぶ際には,ぜひ平行して読んでおくことをお勧めしたい.
(2011年8月15日原稿受付)
素粒子・原子核物理学の基礎~実験から統一理論まで~
原著者:A. Das, T. Ferbel,末包文彦,白井淳平,湯田春雄訳
共立出版,東京,2011, xv+389 p, 22×16 cm, 本体5,000円[大学院・学部向]
ISBN 978-4-320-03467-9
紹介者:住吉 孝行(首都大理工)
本書は,ロチェスター大学の3, 4年生を対象とした素粒子物理学の講義を基に教科書として編集された,Introduction to Nuclear and Particle Physics, 2 nd editionを日本語に翻訳したものである.原著の初版は1989年に出版されており,2006年に出版された2版ではその後の新しい発見を取り入れることには留意せず,主に初版の記述内容への修正が行われている.T. Ferbelと聞いて多くの素粒子実験研究者は,Experimental Techniques in High Energy Physicsを思い出すであろう.この本はどこの素粒子実験研究室にも置いてあり,素粒子実験に使われる検出器に関するバイブル的書物となっている.CERN(欧州合同原子核研究機構)における夏の学校の開催に尽力するなど教育に熱心な研究者というイメージがある.本書はそのような研究者によって書かれた教科書であり,基礎的な事柄に重点を置いて,初学者にも出来るだけ判り易くという気持ちが貫かれているように感じる.簡単に本書の構成について以下に記す.
1章:ラザフォード散乱,微分断面積
2~5章:原子核の構造とモデル,核力,放射線,核分裂と核融合
6~8章:粒子と物質の相互作用,検出器と加速器
9~12章:素粒子の相互作用,対称性,K中間子の物理(CP対称性など)
13~15章:標準模型とその検証,標準模型を超える物理
最初に原子核・素粒子実験における基本ともいえるラザフォード散乱について詳しく説明がなされていることが嬉しい.過去100年にわたって素粒子・原子核実験はラザフォードの手法を踏襲し,それを繰り返しているといっても過言ではない.取り上げられている内容,原子核と素粒子のバランス,全体の構成など良く練られており,大学で「原子核・素粒子」というような概説的講義を行っている教員が学生に推薦するのにうってつけの参考書だと思う.要所に例題が取り入れられ,理解がより具体的になるように配慮されている.また,各章末には質の高い演習問題が載せられ,巻末には解くためのヒントが記されている.また,最近の研究動向などに関しては,簡単ではあるが訳者による脚注で説明されている.本来なら学生には英文の原著を読んで頂きたいのであるが,最近の学生には敷居が高いかもしれない.そのことを考えると今回日本語訳が発刊されたことは喜ぶべきことかもしれない.当然と言えば失礼になるが,本書だけで原子核から素粒子の統一理論までを専門レベルで理解することはできない.しかし,大きな道筋を教養レベル以上で理解したいという学生にはうってつけである.個人的には,標準模型の検証に非常に大きな役割を果たしたLEP実験に関することや,ニュートリノ振動の発見によるニュートリノ質量の存在確認などの話題にも紙数を割いて欲しかったという気がする.
(2011年7月25日原稿受付)
スピントロニクス―基礎編―
原著者:日本磁気学会編,井上順一郎,伊藤博介
共立出版,東京,2010, xi+278 p, 22×16 cm, 本体3,600円(現代講座・磁気工学3)[大学院向]
ISBN 978-4-320-08589-3
紹介者:白井 正文(東北大通研)
スピントロニクスという研究分野の名称が使われ始めてから10年程度が経過して,最近では多くの人に認知されたように思われる.この研究分野は,電子がもつ電荷だけでなくスピンの自由度を活用した新しいエレクトロニクスを創ることを目標に目覚ましい発展を遂げている.また同時に新しい物理現象・概念を次々と打ち出してきた.本書は,新しくこの研究分野に参入する者が,スピントロニクスの初歩を学習するのに適した教科書といえる.スピントロニクスの基礎知識が平易に記述されていることが,本書の特徴である.第1章ではスピントロニクスの発端となった巨大磁気抵抗の発見から最近のデバイス応用までが概観されており,初学者の動機づけとなる適切な導入となっている.第2章は磁性の基礎と局在スピン系の磁性理論の初歩が簡潔にまとめられており,続く第3章では磁性体の電子状態について具体的な物質を例に挙げながら丁寧に記述されている.第4章は電気伝導の理論について古典論から量子論まで広範な説明にあてられており,本書を特徴づける内容となっている.電気伝導の理論的取扱いには多くの方法論があり,初学者でなくとも混乱しやすい.本書ではドゥルーデ理論やボルツマン方程式から始まり,ランダウアー公式や久保公式に至るまで,限られた紙面で必要な事項が記述されており,次章の内容を理解するための助けとなっている.第5章が本論であり,スピントロニクスの理解には不可欠な各種のスピン依存伝導現象について詳しく述べられている.巨大磁気抵抗効果ならびにトンネル磁気抵抗効果に関する記述は,単なる一般的な説明にとどまらず,多彩な物質系に対する実験結果を数多く引用しながら,第3章で述べられた物質の電子状態と関連づけて詳述されている.また半導体スピントロニクス素子の典型例として,いくつかのスピントランジスタについても述べられている.さらに最近話題となっているトピックスとして,スピンホール効果などスピン軌道相互作用が重要な役割を果たす現象や,電流駆動磁化反転など磁化ダイナミクスと関連した現象について平易に説明されている.以上のように本書はスピントロニクス分野に新規に参入される者にとって格好の入門書といえる.続いて刊行が予定されているスピントロニクス応用編も今から楽しみである.
(2011年7月26日原稿受付)