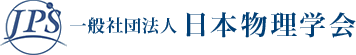会誌Vol.72(2017)「新著紹介」より
このページでは、物理学会誌「新著紹介」の欄より、一部を、紹介者のご了解の上で転載しています。ただし、転載にあたって多少の変更が加わっている場合もあります。また、価格等は掲載時のもので、変動があり得ます。
惑星形成の物理;太陽系と系外惑星系の形成論入門
井田 茂,中本泰史
共立出版,東京,2015,vii+130p,21×15 cm,本体2,000円(基本法則から読み解く物理学最前線6)[専門・大学院向]ISBN 978-4-320-03526-3
紹介者:佐々木 貴教(京大院理)
1995年10月,人類は初めて太陽以外の恒星の周りに惑星を発見する.「系外惑星」という新たな学問分野の幕開けである.それからわずか20年ほどで,発見された系外惑星の数は瞬く間に3,500個を超えた.驚くべきは,この膨大な「量」だけではない.20年の間に,「質」的なブレークスルーも次々と起きてきた.
1995年:巨大ガス惑星の発見
2002年:惑星大気成分の同定
2005年:赤外輻射観測による惑星温度の推定
2007年:スーパーアースの発見
2008年:巨大ガス惑星の直接撮像
2010年:地球型惑星の発見
2011年:周連星惑星の発見
2014年:ハビタブルゾーン内の地球型惑星の発見
これほどまでに急激な勢いで進歩し続けている学問分野が,他にあるだろうか.「系外惑星」は,いまや最もエキサイティングで,最もアクティビティの高い学問分野であるといえよう.
こうした異様な盛り上がりをうけ,近年では多分野からの新規参入も活発だ.物理学を専攻してきたものにとっては,系外惑星系の形成メカニズムや力学進化などが,魅力的な研究テーマとなっている.若い分野であるが故に,過去の蓄積が無くとも短期間に一気に世界の最先端研究の仲間入りができる点も,参入障壁が低い理由であろう.特に惑星形成理論の分野に関しては,まさに「群雄割拠」の時代がやってきている.多様な系外惑星が発見されたことにより,古式ゆかしき太陽系形成論の枠組みは大きく変更を迫られ,新たなシナリオやアイデアが次々と台頭してきているのだ.
そこで本書である.系外惑星の形成理論に興味を持たれた方には,まず何よりも最初に本書を手に取って一読していただきたい.本書の構成は以下のとおりである.
第1章では,系外惑星の観測と惑星形成理論の現状が簡単にまとめられている.第2章では,惑星形成理論に関する基礎的な物理が簡単に紹介されている.本書のメインパートである第3章では,現代の惑星形成理論の枠組みの中で重要なプロセスに関して,その背景にある物理を中心に丁寧に解説されている.そして最終章では,2000年代前半に著者(井田)らが考案した「惑星分布生成モデル」の概要を示し,最先端の研究への橋渡しを行っている.
基本的には学部レベルの物理学・物理数学の知識があれば読めるように書かれているので,気負うことなく読んでほしい.ただし本書は,あくまでも2010年代半ばにおける惑星形成理論の「到達点」を示したものであり,この分野の最終ゴールを示した「集大成」ではない点には注意が必要だ.そのため,惑星形成理論についての「知識」を得るために読むのではなく,「方法論」を学ぶことに重点をおいて読んでもらいたい.
本書を一通り読みきれば,最新の惑星形成理論の現状を学び,新しい研究に取りかかるための準備が整うはずだ.その後は,ぜひ系外惑星の大海に乗り出し,最先端の論文を読んで議論するなり,独自のモデルを構築して世界に打って出るなり,新たな研究生活を自由に楽しんでいただきたい.
(2016年4月25日原稿受付)
プラズマ物理の基礎
宮本健郎
朝倉書店,東京,2014,viii+322p,21×15 cm,本体5,600円[専門~学部向]
ISBN 978-4-254-13114-7
紹介者:上田良夫(阪大院工)
この教科書の歴史は,1976年に出版された『核融合のためのプラズマ物理』(第1版,岩波出版)までさかのぼる.私の手元には,この改訂版(1987年),英語版(Fundamentals of Plasma Physics and Controlled Fusion,1997年,岩波ブックサービスセンター),『プラズマ物理・核融合』(2004年,東京大学出版会),『核融合のためのプラズマ物理』(2009年,核融合科学研究所)があるが,これらは一連の出版物の一部に過ぎない.ちなみに,中国語版も見たことがある.初版本は,誤植が散見したため,改訂版を購入したときに廃棄した記憶があるが,この大事業の価値を鑑みるに手元に置いておくべきだったと後悔している.
この教科書は,この一連の宮本先生のライフワークの最新版である.内容は,大学生や大学院生を対象とした,磁場閉じ込め核融合を主に念頭に置いたプラズマ物理と,核融合プラズマ研究の歴史や最新の研究成果の紹介である.核融合プラズマの研究を志す者が知る必要のあるほぼすべての分野について説明があり,本書を一読することで,この分野で研究を行っていくための広範な基礎知識が得られる.宮本先生の一連の教科書は,改訂や再出版にあたり,読者によりわかりやすく有用な情報を伝えることと最新の情報を盛り込むこと,の2点を常に念頭に置いて書かれており,その集大成とも言える本書は,初学者だけではなく,研究者にも大変に参考になる教科書である.また,重要な数式については,省略せず丁寧に記述されていることで,数式の導出に多くの時間を取られずに物理の理解に集中できるような配慮もされている.
第1章と,第2章では,プラズマの基礎知識,プラズマの諸量,クーロン衝突,等について説明があり,一読することでプラズマの概念を理解できる.続いて,第3章では,一般的な電磁場の性質と,主にトーラス磁場中の荷電粒子の運動について詳細な説明があり,特に捕捉荷電粒子の運動について深く理解できる.第4章では,プラズマ物理学において最も基礎となる方程式である,速度分布関数に関するボルツマン方程式が説明される.
第5章から第9章は,プラズマを電磁流体と見なした場合の,磁場閉じ込め系における平衡,閉じ込め,安定性を説明しており,磁場閉じ込め方式の核融合システムを理解する上で,重要な内容が網羅されている.第5章では電磁流体の運動方程式,第6章ではプラズマを平衡状態に保つための平衡条件,第7章ではプラズマが平衡状態で安定な場合の拡散と閉じ込め,について説明がある.さらに,磁場閉じ込めでは平衡状態が安定であることが重要であり,第8章ではプラズマ抵抗が零の理想的な場合の代表的な不安定性,第9章ではプラズマが有限な抵抗を持つ場合の抵抗性不安定性について説明される.
第10章からは,プラズマ中の電磁波動に関する説明が詳しくなされる.第10章では電磁波動理解の基礎となる冷たいプラズマ中の波動が説明され,続いて有限な温度のプラズマを想定し,第11章でランダウ減衰とサイクロトロン減衰,続く第12章では波の伝搬に続いて,熱いプラズマの分散関係が説明されている.さらに,第12章の後半では,磁場閉じ込めプラズマの波動加熱や電流駆動を想定した具体的な説明がなされており,実際の研究にすぐに生かせる内容である.
第13章は,本教科書で新たにまとめられたものであり,乱流によるプラズマ輸送を扱っている.ここでは,従来の教科書でも取り上げられていた,揺動損失やボーム拡散等に加えて,最近の重要な研究課題である帯状流について詳しい説明がある.最新の研究内容を盛り込んで発展し続ける宮本先生の教科書の真骨頂とも言える部分である.
第14章以下は,核融合研究全般の歴史と,具体的な3種類の方式に対する詳しい説明がなされている.まず,磁場閉じ込め核融合の中心的な装置であるトカマク,続いて主に東京大学で教鞭を執っておられた時代に研究対象とされていた逆磁場ピンチプラズマ,及び慣性閉じ込めである.記述をこれらの方式のみに絞り,重要なポイントをわかりやすく説明している.
この教科書は,著者である宮本先生のプラズマ物理をわかりやすく伝えたいという長年の思いが強く感じられる名著であると思う.特に磁場閉じ込め核融合プラズマの研究を行う大学院学生には必携であり,またこの分野の研究者にとっても,知識の整理や新しい研究を始めるときの参考書として有用である.なお,宮本先生は,核融合研究の第一線を退かれてすでに10年以上が経ったが,今でも機会あるごとに新しい論文に目を通して,最新情報を得ておられると伺っており,頭が下がる思いである.
(2016年8月18日原稿受付)
初歩の統計力学を取り入れた熱力学
小野嘉之
朝倉書店,東京,2015,vi+206p,21×15 cm,本体2,900円(シリーズ〈これからの基礎物理学〉1)[専門~学部向]ISBN 978-4-254-13717-0
紹介者:香取眞理(中大理工)
標記のタイトルから本書の独創的な試みが想像できることだろう.著者のアイデアは次のようである.従来大学で,熱力学と統計力学をこの順番で積み重ね式に教育しているのは,おそらく歴史的経緯を反映した結果であろう.しかし,物質の原子的描像と量子力学という理論の存在が広く受け入れられている現代では,熱力学の最初から,統計力学的な解釈・説明を取り入れて教えるという方式があってもよいのではないか.そのために,確率・統計の考え方や,初歩の量子力学についても一緒に教えてしまう.そうすれば,非物理系の理工系学生たちにも現代物理学の面白さを伝えることができるし,物理系学生たちも,形式的な熱力学の体系の背後にあるミクロな構造を知ることで,理解が深まるはずである.(以上,「まえがき」前半の概要.)
確かに,熱力学の講義でファンデルワールスの状態方程式を導入するときは,気体分子運動論の立場に立ち,レナード=ジョーンズポテンシャルのグラフを書いて説明するのが分かりやすい.気体の混合エントロピーの計算でも,容器中に2種類の気体分子を色分けでもして描いた図があれば話は早いし,ギブスのパラドックスの説明もしやすい.統計力学を一緒に教えてもよいのなら,これに対する処方箋(分配関数をN!で割る工夫)も話せる.黒体輻射のスペクトルの話題は「温度と色」といういかにも熱力学的な話なので,もしも量子力学の計算も交えて講義できるなら,心置きなく説明できる.本書は,上述のような試みをすべて行った上に,相転移のランダウ理論を詳説する.臨界指数にまで話は及び,それらは系のミクロな情報をマクロなレベルで見せる指標であると説く.
これだけ広範かつ高度な内容を含みながら,本書では熱力学・統計力学の偉人たちの写真と共に史実も語られ,また,熱力学の公式暗記術「ラッキーセブンの公式」の図解もある.標記の通りコンパクトな1冊で,どうしてこれが可能なのか.
評者は次のように考えた.この本は,卒研や研究室セミナーで,熟達した先生がやる一連のお話をまとめたものなのである.したがって,話題の内容と順番は先生が話しやすい(つまり,学生たちに伝わりやすい)ように工夫されているが,決して簡単ではない.その順番こそがポイントであり,実はどこから話を始めてもよく,どこで(その回は)終わってもよいようにできている.
学部生や大学院生にはもちろん,研究室を立ち上げてまだ間もない若手の教員にも,本書の一読を薦める.学部教育では,内容を科目ごとに分割し集団的に教育するが,大学院教育では,各教員が自分のところの学生に一人ですべて教える.この伝統的なシステムの功罪についても考えさせられるからである.
(2016年8月29日原稿受付)
不安定核の物理;中性子ハロー・魔法数異常から中性子星まで
中村隆司
共立出版,東京,2016,viii+181p,21×15 cm,本体2,000円(基本法則から読み解く物理学最前線8)[専門~学部向]ISBN 978-4-320-03528-7
紹介者:宮武宇也(KEK)
物理のフロントラインを,研究者自らが最先端の成果をもとに解き明かす.原子核物理の基礎知識を網羅的に伝える教科書ではない.むしろ「不安定核物理」に限定して,現場で活躍する研究者の動機と目的を縦糸に,ブレークスルーとなる実験装置や方法の発明と発展を横糸に組まれた啓蒙書だ.学部生程度の基礎知識で不安定核研究とその研究者の魅力に触れられる.
第1章「はじめに」,第2章「原子核の限界」,第3章「不安定核を作る」という基本項目とトピックスを扱う第4章「中性子ハロー」,第5章「不安定核の殻進化」,第6章「中性子過剰核で探る中性子星」,展望をまとめた第7章「結び―不安定核物理の展望」という構成.適宜相互参照されているので飛ばし読み可能だが,研究の醍醐味を知るには冒頭から読むことを勧めたい.
1,2章では「原子核はどこまで存在しうるのか?」という素朴な疑問を引き金に,質量公式の対称エネルギー項から核力の中心力と非中心力までをストレートフォワードに,かつ丁寧に説明している.3章は不安定核生成のための実験技術,いわゆるIn-flight法とISOL(Isotope Separator On-Line)法の解説.核反応の運動学的特徴を生かした前者と化学・原子物理的知識を基礎とした後者を原理から説明する.
本書の圧巻は4,5,6章.4章では量子トンネル効果によるハロー現象の理解に始まり,ソフト双極子励起から見えてきた2中性子相関におけるテンソル力の重要性が実験データとともに語られる.殻模型の概念導入が,議論の途上で簡潔な説明とともに現れる.これは新鮮だ.殻模型は,安定な原子核の標準的な1粒子軌道エネルギー準位を与えるが,そこからの逸脱現象の理解こそが本書の中心テーマなのだ.5章では視野が広げられて,中性子ハローから原子核ドリップライン近傍に現れた異常現象へと誘われる.着目するのは,基底状態に2粒子2空孔状態のスピン・パリティが現れる「逆転の島」.殻進化と呼ばれる物理描像の発展と未解明要素が,今後の展望とともに語られる.6章では視点を変えて,ホットな研究課題である中性子星の物理と中性子過剰な不安定核研究との緊密な関係が解説され,本書で触れなかった研究項目とともに,分野の展望がキーワードの形で7章にまとめられる.
進路模索中の学部後期学生に是非とも読んでもらいたい本である.実際にその頃の私には,同一出版社の大槻義彦編『物理学最前線』(本シリーズの前身だと思うのだが)が面白くてタイムリーな出版物だった.一方,須藤彰三・岡真監修による本シリーズでは1テーマに1冊が割かれており,式を含めた丁寧な解説が可能となっている.その点では大学初年度の学生にも良き入門書であり,基礎物理を教える教員・研究者の方々にも概念の整理を行う上で適している.
(2016年8月30日原稿受付)
核の誘惑;戦前日本の科学文化と「原子力ユートピア」の出現
中尾麻伊香
勁草書房,東京,2015,vii+384+20p,22×16 cm,本体3,800円[一般向]ISBN 978-4-326-60280-3
紹介者:平田光司(総研大/KEK)
原爆の被害国であるにもかかわらず,日本は戦後の早い時期に原子力を(喜んで,とまでは言えないかもしれないが,大きな反対もなく)導入した.本書は,この点について納得のいく説明を提供してくれるものである.
本書によれば,日本人にとって核,原子力は原爆によって登場したのではなく,戦前から魅力あるものとして認識,受容され,日本人を「誘惑」し続けていた.日本人が抱いていたものが書名の一部となる「原子力ユートピア」,核・原子力の利用によって生まれる夢の世界という期待に満ちた神話であった.
本書は大きく2つの部分からなり,第1部「放射能の探求と放射能文化の創生」では戦前の「核」に関する「大衆」の関心がテーマとなる.「核」はまず,心霊現象や千里眼との関わりで興味を持たれた.放射線の医学利用が進むと,ガンを消し健康を促進する「良いもの」として放射線が認識されるようになる.優れた放射線源としてラジウムが注目された.高価なラジウムを人工的に製造できる装置として出現したのがサイクロトロンであった.さらに,温泉にラジウムから生じるラドンの成分が発見されることによって,温泉の効き目の原因物質としても認識されるようになった.良い温泉ほどラジウム・ラドンの存在量が多いという測定結果があった.放射線による障害も知られていたが,それも放射線の「威力」の現れであるとされ,ラジウムの魅力を損なうことはなかった.
第2部「原子核の破壊と原子力ユートピアの出現」では,核エネルギーの利用,原爆を期待する大衆のイメージと,それを利用して大型サイクロトロンの建設の必要性を訴える物理学者,決戦兵器の開発を宣伝して戦意高揚をはかる軍部,そして原爆投下後の様子が描かれる.広島,長崎の惨禍は,原子力・核エネルギーの素晴らしさの証明として,むしろ原子力ユートピアを強めるものであった.原子力ユートピアの形成は,物理学者,マスメディア,および政府,軍部の共同によって生まれたものであり,放射線障害や原爆の残酷さにもかかわらず戦後にもほぼ無傷で生き延びたものであるとしている.
本書の記述は丁寧であり,説得力がある.社会との相互作用の中で科学を記述するという「科学の社会史」の流れを継承する著作と言える.残念な点としては,本書の記述が日本における原子力利用の開始の前で終わっていることだ.原子力の推進は原子力ユートピアの幻想を利用しつつ,それを強化することで行われたと思われるが,それについてはまた別の作品が必要となるだろう.著者に期待したい.
(2016年9月27日原稿受付)
ワード-トンプソン&ウィットワース 星形成論;銀河進化における役割から惑星系の誕生まで
D. W.-Thompson,A. P. Whitworth著,古屋 玲 訳
丸善,東京,2016,xvi+404p,21×15 cm,本体15,000円[大学院・学部向]ISBN 978-4-621-08736-7
紹介者:井上剛志(名大理)
本書は英国カーディフ大学を最近退官された星形成が専門の理論天文学者ウィットワース教授と観測天文学者ワード-トンプソン教授の著書An Introduction to Star Formationを星形成観測が専門の古屋玲准教授(徳島大学)が邦訳した星形成論の入門書である.ワード-トンプソン教授と古屋准教授は共に,現在進行中のハワイ島マウナケア山頂にあるジェームズ・クラーク・マクスウェル望遠鏡を用いて行われる星形成領域の磁場観測プロジェクトであるBISTROの代表者であることから,両者のつながりは深く古屋准教授は訳者としてうってつけであったであろう.星形成に不慣れな読者はここまでの紹介を読んで「なぜ星形成と磁場が関係するの? なぜ望遠鏡で磁場が観測できるの?」と思ったかもしれないが,その疑問に対する答えも本書を読めば明らかになることは間違いない.
本書を読めば,本格的に最先端の星形成を学ぶ,もしくは研究を始めるための基礎知識が全て身につくようになっている.2人の著者はそれぞれ理論と観測の専門家であるので,観測結果の単なる羅列に終わったり,過度に数式に埋もれたりすることなく理論と観測それぞれから得られている基礎が比較的コンパクトにまとめられている.本書の最大の特徴は,分量にして本書の約3分の1を占める巻末の補遺である.補遺の他にも本書には訳者による40ページに及ぶ注釈が加えられており,初学者に極めて優しい仕上がりになっている.本書のような入門的専門書の中には学部で習う熱力学,統計力学,電磁気学等の基礎知識がよく身についていることが前提となっていて,読み進めるのに学部時代の教科書を常に傍らに置いておかなければならないものも多い.その点,詳しい補遺に恵まれた本書は比較的軽快に読み進めていくことができるようになっている.巻頭に訳者が書かれているように,独習や輪読に勧めたくなる本になっている.
日本語で書かれた本で専門的な知識を学ぶことの最大のデメリットは,オリジナルの専門用語まで日本語化されてしまっていて研究現場に出ると英語が出てこなくて困ることである.その点においても本書は非常に気が使われており,専門用語と思われる用語には全て英原文が併記されている.その点に関してここまで徹底的に気が使われている専門書を評者は他に知らない.総合すると,どうしても英国人が本物の英語で書いた本で星形成を学びたいというのでなければ,価格的には少し高くなってしまうが評者は本訳書をお勧めしたい.
(2016年11月4日原稿受付)
科学の発見
北川米喜
文藝春秋,東京,2016,428p,20×14 cm,本体1,950円[一般向]ISBN 978-4-16-390457-3
紹介者:秋本祐希(Higgs Tan)
本書「科学の発見(原題:To Explain the World: The Discovery of Modern Science)」は物理学に関わるものであれば知らぬものはいないであろう物理学者スティーブン・ワインバーグ氏が,テキサス大学の教養学部向けに行われた科学史の講義を元に執筆されたものである.わかりやすく科学史が説明されており,イオニアのタレスから始まり,古代ギリシアからニュートン,そして現代科学に至るまでの科学史の流れを把握するための読み物として役立ち,そして,面白いものである.
しかし,「はじめに」でワインバーグ氏は,「本書は不遜な歴史書」と記している.
何故か.
本書では現代の科学知識をもって,過去の科学の偉人を評価しているのである.特に,研究対象を純粋に方法論的自然主義に従って考察しているのか,あるいはそこに人間的・宗教的価値を持ち込む立場を取るのか,というところにその評価の軸を置いている.
現代科学においては,前者の態度をとることが当然であると考えられているが,アリストテレスやケプラー,近年ではアインシュタインでさえこのような態度を取り続けることができなかった.自分は本当にこのような科学的態度を取れているのか,現在の科学に携わるものとして改めて自省させられる.
解説で大栗博司氏も述べているが,現在の基準で過去を裁くというウィッグ史観は「勝ち残ったものが一方的な視点で見た歴史」であり,歴史学の分野では禁じ手である.ワインバーグ氏がウィッグ史観によって過去の偉人を評価するというこの態度は,歴史家などの批判を生み出し,多くの論争を巻き起こしたそうである.
だが,ここで我々が考慮すべきことは,ワインバーグ氏が評価しているのは科学に関する歴史であるということであろう.いわゆる勝者と敗者が存在するような歴史とは異なり,科学は自然の有り様を説明するために作られたものであり,それは進歩の歴史である.現在の科学は過去の科学より自然の有り様を上手く説明できる.このため,現在の視点から過去の科学の手法を批判的に見ることは,現在の科学の成り立ちを理解するのに役立つ.そして現在の科学が未だ完成されたものではなく,未来の科学による批判を受けるかもしれない,という警告ともなるのである.このように考えると,なぜ確信犯的にウィッグ史観を用いたのか,私には,ワインバーグ氏の科学観の一端が見えてくるように思えるのである.
本書はワインバーグ氏の持つ科学観に基づいた「不遜な歴史書」である.その評価はやはりわかれるものであろう.しかし,科学に携わるものとして,ぜひ一読して頂いた上でご自分なりの評価をして頂きたい本である.
(2016年9月5日原稿受付)
パーフェクトPython
ハイパフォーマンスPython
Pythonサポーターズ
M. Gorelick,I. Ozsvald著,相川愛三訳
技術評論社,東京,2013,463p,24×19 cm,本体3,200円[学部・一般向]ISBN 978-4-7741-5539-5
オライリージャパン,東京,2015,xxi+335p,24×19 cm,本体3,600円[学部・一般向]ISBN 978-4-87311-740-9
紹介者:川面洋平(オックスフォード大学)
PythonはWEBアプリ開発,機械学習など様々な分野で使われている汎用プログラミング言語であり,物理学においても実験データ解析や可視化に使われている.Pythonを使う利点は,他の言語と比較して同じ作業を簡潔なコードで書くことができることである.また豊富な統計解析・数値解析ライブラリが開発されており,それらはオープンソースであるため導入コストを気にする必要がない.メジャーなOSに対応しているため,ソースコードの共有も容易である.さらにユーザー数が多いため,必要なドキュメントやトラブルシューティングをオンライン上で容易に見つけることができる.このような理由から,今後物理学の分野においてPythonユーザーの数は増えていくことだろう.ここでは入門者向けの「パーフェクトPython」と上級者向けの「ハイパフォーマンスPython」を紹介する.
「パーフェクトPython」は言語仕様から代表的なライブラリの使い方まで網羅的に解説した入門書である.平易に書かれているので,何か別の言語での開発経験があれば一日で読み通すことができるであろう.新しく実験データ解析を始めた学部生や大学院生に是非読んでいただきたい.前半はPythonの言語仕様についてであり,ここを理解できればPythonを使った開発を始めることができる.また,整理された構成になっているので辞書代わりに使うこともできる.わからない文法に出会ったらまず本書に載っていないか調べてみれば良いだろう.後半は応用であり,実験データ解析に不可欠なNumPy, SciPy, matplotlibに関する簡潔な導入がある.より詳細な情報はオンライン上のドキュメントやトラブルシューティングを参考にすれば良い.本書の前半で得たPythonの基本知識があればオンラインドキュメントは問題なく読むことができる.本書で実験データ解析に必要な部分は第2~9章(言語仕様),第10章(ファイル入出力と文字列),第13章(テスト),第15章(NumPy, SciPy, matplotlib)である.
一般的に実行速度と開発速度はトレードオフの関係にあり,Pythonは開発が簡単になる一方で実行速度はC言語等に劣る.「パーフェクトPython」(及び必要に応じたオンラインドキュメント)を読めば, Pythonを用いて実験データ解析プログラムの開発ができるであろう.しかし,対象データが大規模である場合,適切なチューニングや並列化を行わなければ実用に耐えない.「ハイパフォーマンスPython」はそのような高速化技法を詳説した上級者向けの解説書である.Pythonが対象言語であるが,本書で語られる高速化の基本理念はPythonに留まらず他の言語を使う際にも大変参考になるものである.データ解析だけでなく,数値計算を利用する研究者にも是非読んでいただきたい.本書の構成は大きく三つに分けることができる.まず高速化の前提知識としてのハードウェア・アーキテクチャについて,次に単一プロセスにおけるチューニングについて,そして並列計算についてである.具体的には律速箇所の特定方法,リストとタプルの高速化における違い,CythonやPyPy等の処理系の長短所,multiprocessingモジュールの使い方など,高度な内容が実例を交えながらわかりやすく説明されている.筆者自身も本書を読んだ後に自分のコードを見直して改善すべき点に気づいた.また本書の終わりにはPython高速化の事例が紹介されている.
最後に筆者の経験から物理学においてPythonが推奨される点を幾つか挙げよう.筆者はここ数年Pythonを用いて高温プラズマの実験データ解析を行っている.多変数非線形フィッティングなど,解析の核となる部分はScipyで用意されているものを使っている.またScipyの最適化モジュールでは複数の最適化アルゴリズムが用意されており,引数一つでそれらを使い分けることができる.こういったアルゴリズムを一からCやFortranで書くのは骨の折れる作業であるが,Pythonで書けば簡素に書くことができる.またScipyと呼ばれる記号計算ライブラリを合わせれば,Mathematicaライクに使うこともできる.筆者もコストの低い数値計算は,CやFortranを使わずPythonで済ませている.また物理実験のように,共同研究者や後任者など複数の人が関わる場合,読みやすくメンテナンスしやすいコードを書く必要がある.この点においてもPythonは他言語に優る.
(2016年11月9日原稿受付)
重点解説 スピンと磁性;現代物理学のエッセンス
川村 光
サイエンス社,東京,2016,iv+156p,26×18 cm,本体2,130円(SGCライブラリ-125)[専門~学部向]ISSN 4910054700565
紹介者:宇田川将文(学習院大理)
タイムリーな本である.昨年のノーベル物理学賞はトポロジーの多体問題への応用に対して授与された.直接の受賞対象となった業績はKosterlitz-Thouless転移,トポロジカル電子状態,そしてHaldane gap問題の進展についてであるが,その全てについて,本書で言及があることは決して偶然ではない.スピンと磁性はその単純さのために,数々のミニマルな理論模型を産み出す母体となり,新しい物理概念を創出する舞台として長く機能してきたのであろう.本書の序文にあるように,磁性を学ぶのは過去一世紀の物理学を振り返ることに等しい.
本書の構成はまず,第1章から第10章までは基礎事項の概観に当てられる.第4章まではスピンの量子力学,第5章から第9章まではスピンと磁性に関する物性論的な基礎,第10章では磁性体の臨界現象について詳しく解説される.第11章から第14章まではここ20年程に発展してきた新しい話題から最先端のテーマまでが紹介される.第11章ではフラストレート磁性体と複合自由度の物理について,第12章と第13章はそれぞれスピングラスとスピン液体,そして最後の第14章では遍歴磁性体についての最近の進展が話題となる.
本書の前半で解説される基礎事項は他書でもカバーされていることが多いが,後半の進んだ内容を理解する上で,基礎事項が簡便に参照できるのは便利である.また,基礎から出発して全体像の有機的なつながりを記述するという著者のスタンスは,未解決の問題に取り組む際に模範となる姿勢でもあろう.例えば,第13章にあるように,スピン液体の起源として,最近は電荷自由度や軌道の効果など,微視的なモデル自体の構造や成立条件が問われることが多いようである.系を記述するモデルの成り立ちから出発して,結論に至るまでのプロセスを丁寧に吟味することにより,思わぬ突破口が開かれる,ということもあるのではないだろうか.
第10章までの基礎事項を消化した後はいよいよ,研究の最先端に筆が移る.後半部の内容を詳述した類書はなく,本書のハイライトと言えよう.
まず第11章ではスピン格子結合,異常ホール効果(トポロジカルホール効果),トポロジカル励起など,フラストレート磁性体に現れる種々の興味深い現象が解説される.フラストレート磁性体については,「フラストレーションが秩序を壊すので,代わりに非自明な状態が出現するだろう」という論調の,頼りない動機に基づいた研究も多い.しかしながら,この章ではカイラリティの概念を軸として,フラストレート系で何が本質的か,という点が積極的に描かれており,確かな動機をもって研究を開始するための大きな助けになるだろう.特に,本章で解説されるZ2 vortex転移や第12章におけるカイラルスピングラス転移は著者本人によってなされた金字塔的な発見であり,現象の本質を鋭く突いた発見者自身による解説が手に入ることは貴重である.続く第13章のスピン液体については研究現場の最前線におけるテーマであり,本章の内容は将来的にはあるいは変更を受けるかもしれない.しかしながら,実験,理論の現状について要を得たまとめが与えられており,今後の研究展開のための確かな足がかりを与えてくれるだろう.
本書にただひとつ注文を付けるとすれば,話が詳細に入りかけると,「紙数の都合で」と省略されてしまうことがやや多く目に付く点だろうか.特に最先端の話題については,まだまだ手の内は明かせない,という事情もあるかもしれない.しかし,長く本分野を牽引してきた著者のこと,数々の秘伝をつまびらかにする本書の続編についてもぜひ,楽しみに出版を待ちたいと思う.
(2016年11月1日原稿受付)
ストロガッツ 非線形ダイナミクスとカオス;数学的基礎から物理・生物・化学・工学への応用まで
S. H. Strogatz著,田中久陽,中尾裕也,千葉逸人訳
丸善,東京,2015,xvii+523p,21×15 cm,本体6,300円[大学院・学部向]ISBN 978-4-621-08580-6
紹介者:郡 宏(お茶大基幹研究院)
この世界は時間的にも空間的にも複雑で多様性に富んでいます.物理学がこれまでに明らかにしてきた簡潔な自然法則からどのようにそのような複雑性が生まれるのか,たいへん不思議に思います.その秘密を紐解く重要な概念として「非線形性」があります.非線形性とは,数学的には時間発展方程式に非線形項があることですが,平たく言えば,作用と反応の因果関係が線形の関係ではないこととも言えます.現実のほとんどのシステムがこの性質を有します.非線形性によって,システムの挙動は単純な構成要素の重ね合わせではなくなり,構成要素の性質からはにわかには予測できない複雑な構造が生まれます.
非線形システムの重要な特徴の1つは,分岐と呼ばれる転移現象を起こすことです.これは,物理学で馴染みの深い相転移の,決定論的な類似概念と言えます.例えば,化学反応系において何らかの化学物質の濃度を上げたとき,ある臨界値で平衡状態が不安定化するとしましょう.化学反応を線形の微分方程式で記述すると,不安定化に伴って解が発散してしまいます.しかし,現実には非線形性による押さえ込みがあり,これを適切に含んだ方程式では,単純な解の不安定化に伴って複雑性を増した新たな解が安定化します.このようにしてリミットサイクルと呼ばれる周期解が現れたり,さらには,不安定化のカスケードの果てにカオスと呼ばれる非周期解が現れます.非線形の偏微分方程式においても,空間的に一様な平衡状態の不安定化に伴い,複雑な時空パターンが生まれます.このような分岐は,化学反応系における振動やパターン形成,あるいは,熱対流系におけるベナール・セルの出現や乱流化など,現実の非平衡開放系に広く見られます.非線形ダイナミクスは,不安定化が複雑性の源であるという自然観を与えてくれます.
本書は,このような非線形ダイナミクスの入門書として世界的に評判の高い教科書の待望の日本語訳です.原著者はこの分野において卓越した研究実績を持つ数学者であるストロガッツで,原著は彼が行ってきた大学の講義にもとづいてまとめられています.数学者の著作と聞くと,定義,定理,証明が中心のかっちりした内容を思い浮かべるかもしれません.ところが本書は,様々な層の読者が抵抗なく読めるように工夫されており,まるでわかりやすい講義を聞いたような爽快感があります.それにもかかわらず,数学的な間違いがないように細心の注意が払われており,安心して読むことができます.内容は,微分方程式系における平衡状態の安定性や分岐といった非線形ダイナミクスの基礎から,振動現象やカオスといった複雑な現象,カオスとフラクタルの関連などの発展的話題までの内容が盛り込まれています.特に,基礎の部分はかなりのページ数を割いて丁寧に解説されており,初学者に親切です.また,機械振動,生物リズム,超伝導回路,生態系,化学反応系など,様々な例が豊富に盛り込まれており,数学的概念と解析手法だけでなく,その応用についても学習することができます.練習問題は基礎的なものから発展的なものまで多数掲載されており,学生の自習に適しています.
非線形ダイナミクスは今後ますます重要となるであろう基礎的な学問であるにも関わらず,初学者にすすめられるような丁寧な入門書は本書以外に未だほとんどありません.そのような状況でこの翻訳が出たことは,特に初学者にとってたいへんな意義があります.翻訳は,ストロガッツと同じ分野で活躍する数学者,物理学,工学者の3名がタッグを組み,正確に行われ,自然な日本語に仕上げており,原著の魅力はまったく損なわれていません.物理学を学ぶすべての学生に,非線形システムに関わる研究者に,さらには微分方程式によるモデリングや数学的解析手法を学びたい生命科学分野などの研究者に,心よりおすすめできる良書です.
(2016年4月16日原稿受付)
固体の磁性;はじめて学ぶ磁性物理
S. Blundell著,中村裕之訳
内田老鶴圃,東京,2015,xii+320p,21×15 cm,本体4,600 円[専門~学部向]ISBN 978‒4‒7536‒2091‒3
紹介者:小山知弘(東大院工)
本書は,"Oxford Master Series in Condensed Matter Physics" のうち"Magnetism in Condensed Matter"(Stephen Blundell 著)の日本語訳である.「はじめて学ぶ」とあるように,これから磁性を本格的に学ぼうという初学者にうってつけの一冊である.
原著は世界で最も支持されている磁性物理のテキストの一つであるが,その最大の特徴は著者ならではのオリジナルな展開であろう.磁性において最も基本的な要素であるミクロな磁気モーメントの記述から出発し,それが周囲の環境から受ける影響・複数個が集まり相互作用して秩序を形成する様子が流れるように展開されていき,相転移・磁区構造というマクロな系にたどり着く.相互作用する磁気モーメントの集団現象としての磁性を理解するうえで大変面白い話の進め方であり,初学者でもスムーズに読み進めることができるのではないかと思う.また後半には低次元性や有機物磁性体・スピントロニクスといった新しいトピックについても紹介されており,基礎的な物理と最先端の研究テーマの間にある溝を埋めるための工夫もなされている.電磁気や量子論の基本的な内容は付録の中できちんとおさらいされている.さらに各章の終わりには豊富な演習問題が与えられている.詳細な解説付きの解答が省略されることなく掲載されているため,読者は自分で理解度をチェックできるようになっている.これらは初学者には嬉しい配慮である.
もう一つ重要なことは,磁性物理を中心に議論する途中で,現象を観測するための測定技術に関する記述が適宜盛り込まれている点である.磁力計による古典的な磁化測定手法から中性子・X線を利用した新しい技術に至るまでカバーされている.実験に携わる研究者が実際に用いている手法について丁寧に説明がなされているため,本書は理論・実験のどちらかに偏っているということがなく,将来実験系を志す学生にとっても有益な一冊となることは間違いない.こうした視点は,磁性という分野は「アカデミックな興味」と「応用展開」の両面を意識して,同時並行で発展してきたという著者の考え方を強く反映しているように思われる.
初版の出版から10年,世界的に有名な原著の日本語訳が満を持して出版されたというのは,(執筆者のように)英語が不得手な読者にとっては喜ばしい限りである.ただ心配になるのは,邦訳に際し原著のオリジナリティーや哲学が損なわれてしまうのではないかということであるが,本書ではそんなことは一切ない.明快なストーリーはそのままに,随所に散りばめられた原著者の磁性に対する熱意までもが邦訳を読むことでしっかり伝わってくると感じた.このような素晴らしい日本語版を世に送り出してくださった訳者に対し,この場をお借りして感謝申し上げたい.
本書は初学者向けにコンパクトにまとめられているとはいえ重要事項は余すところなく網羅されており,一通り磁性を勉強し終えた研究者も読んでみると新しい発見があるかもしれない.物理学会員に自信をもってお薦めできる一冊である.
(2016年12月19日原稿受付)
Fundamental Fluid Mechanics and Magnetohydrodynamics
R. J. Hosking and R. L. Dewar
Springer,Heiderberg,2016,xiv+279p,24×16 cm,$99.00[大学院向]ISBN 978‒981‒287‒599‒0
紹介者:廣田 真(東北大流体科学研)
磁気流体力学(Magnetohydrodynamics,通称MHD)とは,電磁場と相互作用するような導電性流体の巨視的な運動を取り扱う学問であり,主にプラズマが研究の対象となる.本来プラズマはイオンと電子が別々に運動する電離した気体であり,個々の荷電粒子の微視的な運動は非常に複雑である.MHDでは,そうした微細なスケールはひとまず無視し,単一の流体の巨視的運動へと簡略化した方程式を扱う.このMHD方程式は,宇宙プラズマや磁場閉じ込め核融合プラズマなどの流動現象を理解する上で,重要な基礎方程式となる.また,磁場を恒等的にゼロとすれば通常の流体方程式に帰着するという意味で,数学的には流体力学を拡張した学問体系ともみなせる.
本書の最大の特色は,しばしば別々の講義で扱われる流体力学とMHDを,まとめて習得できることである.読者は大学院生レベルを想定しており,輪講などで読み進めるには程良い難易度と分量だろう.ベクトルやテンソルを用いた演算や公式などは,第1章にまとめられており,後の章で必要となる数学的な予備知識は本著の中で「自給自足」できるように工夫されている.第2章では,MHDよりもさらに拡張された二流体方程式が体系的に導出されており,著者等の専門知識も相まって,非常に洗練された内容となっている.第3,4章は流体力学,第5,6章はMHDに関する様々な話題に触れており,波動や平衡・安定性といった基礎的な概念の解説がほとんどを占める.ただし,著者等も冒頭で弁明しているように,乱流に関してはまったく触れられていない.トーラス型プラズマにおけるバルーニング不安定性や,降着円盤における磁気回転不安定性については,やや掘り下げた解説があるので,興味がある読者にはお勧めしたい.
取り上げられている話題は多岐にわたるが,それぞれについて数ページ程の核心をついた解説が与えられており,著者等が長年培ってきた学識の深さがかいまみれる.おそらく,彼等が本書によって伝えたいのは,流体力学やMHDにおいて共通する数学的手法の重要性ではないかと思われる.数式を用いることで,現象の本質を簡潔に述べることができ,それはプラズマを含む様々な「流体」に普遍的に当てはまるというわけだ.その点で本書はこれまでの教科書にはない趣があり,初学者が数学・流体力学・MHDを必要最小限の労力で一度に学べるように配慮した良著といえる.
数式を用いた抽象的な解説がほとんどであるため,読者によっては宇宙プラズマや磁場閉じ込めプラズマに対する具体的なイメージや関心をもった上で臨むと,後半は読み易いだろう.例えばインターネット上の解説や画像などで情報を補完するとよい.基礎的な知識を身につけるための最初に手にとる本として,学生や他分野の研究者などに本書はお勧めである.
(2017年1月4日原稿受付)
量子系のエンタングルメントと幾何学;ホログラフィー原理に基づく異分野横断の数理
松枝宏明
森北出版,東京,2016,xi+383p,22×16 cm,本体8,000円[専門・大学院向]ISBN 978-4-627-15571-8
紹介者:中村 真(中大理工)
近年,さまざまな分野横断的研究が注目を浴びているが,本書で取り扱う量子エンタングルメントをキーワードとする研究もその一つである.量子エンタングルメントはどちらかと言えば物性物理学の研究者になじみの深い用語であったと考えられるが,超弦理論の枠組みで発見されたAdS/CFT対応を通じて,重力理論(一般相対性理論)を用いた記述へと広がりを見せている.
本書では,このような広範な分野にわたる関連内容が一冊にまとめられており,一人の著者がよくこのように多岐にわたる内容を網羅したものだと感心させられる.各内容についても,読者が計算を追いやすいように,式を多用した丁寧な解説がなされている.
少し表現が飛躍するが,本書は「ロゼッタ・ストーン」のようにも映る.ロゼッタ・ストーンとは古代エジプトの石板であり,そこには同一内容の文章が2種類の古代文字と判読可能なギリシャ文字で併記されていた.このため,この石版は古代エジプト文字解読の端緒となった. 本書では,互いに関連があると思われる内容が,量子エンタングルメント等のキーワードのもと,テンソルネットワーク,可積分系,一般相対性理論,共計場理論などの異なる「内容」で併記されている.素粒子理論を本来の専門とする私にとって判読可能な「ギリシャ語」に相当するのは一般相対性理論(7章),共計場理論(8章)そしてAdS/CFT対応(9章)であり,これから解読したい古代文字に相当するのは,行列積状態(4章)やテンソル・ネットワーク(5章),あるいは前半部分に記述されているエントロピー(2章)や量子もつれ(3章)の解説ということになる.しかし,読者の専門によっては,この関係性は完全に逆転するのであろう.
本書は通読することで「その後の勉強の流れが自然と理解できるように」,そして「関連分野の全体を俯瞰して眺められるように」との意図で書かれている.この意味で本書の目的は達成されていると考えられる.一方で,かのロゼッタ・ストーンの解読がそうであったように,読者が専門としない内容の部分を深く理解するには,本書以外の解説書も併読するなどの努力も要求されるであろう.しかしこれは本書の目的や趣旨から考えれば避けられないことだと思われる.
一つコメントしておきたい点は,本書で取り上げられている項目の相互の関連性は,全てが完全に解明されているものではなく,まだ研究途上のものも含まれる点である.本書では随所に異なる項目の関連性や類似性がコメントされているが,例えば鈴木-Trotter変換とAdS/CFT対応の類似性など,現時点では類似性を超えた議論がまだ不明瞭なものもある.したがって本書を読み進めるうえでは,確立した解説と,現時点では類似性や推測の段階にとどまるコメントを区別しながら読み進める必要がある.なお,これらのコメントは今後の研究への良いヒントとなっており,本書を読むうえでの楽しみの一つでもある.
量子もつれ,エントロピー,重力といったキーワードに興味を持った読者は,本書を通じて「異分野の解読」に挑戦してみてはいかがだろうか.
(2017年1月10日原稿受付)
カミオカンデとニュートリノ
鈴木厚人監修
丸善,東京,2016,xii+163p,21×15 cm,本体1,400円[大学院~一般向]ISBN 978-4-621-30049-7
紹介者:森 俊則(東大素粒子物理国際研究セ)
カミオカンデとニュートリノといえば今や,日本人なら知らない人はほとんどいないのではないだろうか.ただ一般の人が興味を持っても,雑誌や新聞などで断片的な解説はあるが,その全体像がうまくまとめられた本はこれまでなかったように思う.本書は,スーパーカミオカンデ実験の開始から20年,ニュートリノ振動の発見によって梶田隆章氏らがノーベル賞を受賞した直後,という記念すべきタイミングで出版された一般向けの解説書である.その特徴は,実際にニュートリノ物理分野を開拓してきた第一人者たちが,研究現場の生の声を交えながらその歴史を語っているところにある.
前半はカミオカンデ実験について書かれており,カミオカンデ誕生の経緯とその研究の概要をまとめた後,陽子崩壊,太陽ニュートリノ,超新星爆発ニュートリノ,大気ニュートリノという研究テーマについてそれぞれ,その第一線で活躍した研究者が解説している.物理や研究の単なる解説に留まらず,バックグラウンドに頭を抱えたり,理論家の思わくが大きく外れたり,また如何に超新星爆発ニュートリノの発見に至ったかなど,当事者ならではの語り口に当時の興奮を少し感じることができるだろう.丁寧にわかりやすい言葉で説明しており,意欲ある一般読者なら興味を持ってかなり深い知識を得ることができるものと思う.
後半はいよいよスーパーカミオカンデ実験の登場となり,ニュートリノ研究の一つの大団円を迎える.続いて,加速器ニュートリノを使った実験と,原子炉ニュートリノを測る実験によって,ニュートリノ振動現象の全体像がさらに明確にされてきた状況が描かれている.最後に,現在進行中のニュートリノを伴わない二重ベータ崩壊の探索実験と,スーパーカミオカンデをさらに10倍大きくするハイパーカミオカンデ実験計画が簡単に紹介されて終わっている.この辺り後半の解説は簡潔に書かれ過ぎていて,はっきり言って一般読者には分かりにくいであろう.最後はややまとまりに欠けており,将来の研究の展望についてもっと突っ込んだ議論があるとよかったように思う.
陽子崩壊の探索から始まった研究が理論と実験が絡み合って次々に展開し,ニュートリノ物理学という新たな分野として拓けていった様子は,身近にその進展を追ってきた研究者にとっても改めて概観するととても興味深い.常に先手を打って研究を提案して進めていくことの重要性を再認識した.また例えば太陽ニュートリノの謎が解かれていく経緯など,素粒子物理の研究者でも知らないことは案外多いのではないだろうか.大気ニュートリノのデータの中にどうして太陽ニュートリノ欠損の原因となる振動が見えないのか,という疑問は大学院の講義で何回か宿題に出したことがあるが,正しく答えられた学生はこれまで一人もいなかった.
一般向けの書ではあるが学ぶものがあり,学生や若手研究者にも是非一読をお勧めしたい.
(2017年1月10日原稿受付)
Cosmic Rays and Particle Physics(2nd Edition)
北川米喜
Cambridge Univ. Press, New York, 2016, xiv+444p, 25×18 cm, £44.99[専門・大学院向]ISBN 978-0-521-01646-9
紹介者:浅野勝晃(東大宇宙線研)
1912年のV. F. Hessによる発見以来,宇宙から地球に降り注いでいる高エネルギー粒子,宇宙線の研究は物理学の一つの分野として発展してきた.特に1930-1940年代にかけては,陽電子,µ粒子,π中間子,Κ中間子などが,宇宙線から生成される二次粒子として次々と発見され,素粒子物理学の発展にも大きく寄与した.その後の一時期,加速器実験や電磁波による天文観測と比較すると,宇宙線物理は地味な印象を与えてきたかもしれない.しかし,近年はニュートリノや高エネルギーガンマ線など,電子や原子核以外の粒子の観測手段も確立し,電波・可視光・X線による天文観測と共に,多波長・多粒子観測に基づくマルチメッセンジャー天文学の重要な一翼を担っている.
比較的低エネルギー(およそ1015 eV以下)の宇宙線は超新星爆発後の残骸,つまり星間空間を伝播する衝撃波によって生成されると予想されてきたが,これは超新星残骸からの電子シンクロトロン放射や,加速陽子起源のπ0崩壊に伴うガンマ線放射の観測によって実際に確認された.しかし,宇宙線は1020 eVまで分布しており,そうした高エネルギー粒子の加速現場,加速機構,組成,星間・銀河間空間での伝播などは未だに解明されていない.加速された荷電粒子はガンマ線やニュートリノ,陽電子などを二次的に生成するので,これらの粒子を観測して加速現場を押さえるのがマルチメッセンジャー天文学の目標の一つである.
近年では,2008年にロシアのPAMELA衛星により,10 GeVを超える領域で陽電子宇宙線の過剰が報告され,2013年には国際宇宙ステーションに搭載された観測装置AMS-02がより高い精度でこれを確認した.この陽電子は暗黒物質の対消滅や崩壊を起源とする可能性があるとして,大量の論文がその後書かれることとなった.また,2013年には南極に設置されたニュートリノ望遠鏡IceCubeが,銀河系外を起源とする1015 eVにまで達する高エネルギーニュートリノを検出し,その起源天体について活発に議論がなされている.2014年には日本のTelescope Array実験が1019 eVを超える宇宙線の到来方向に異方性がある可能性を指摘し,その起源に迫る手掛かりを与えている.2015年には反陽子宇宙線が理論的予測よりも多いことをAMS-02が報告している.
このようにダイナミックに展開しているAstroparticle Physicsであるが,今までこの分野全体を俯瞰できる良い本が無かった.日本語のものとしては,1983年に出版された小田稔による「宇宙線物理学」があるが,さすがに古くなってしまった.ここで紹介する本は1991年にT. K. Gaisserが単著で書いた本の第二版である.この第一版は小早川惠三によって翻訳され,「素粒子と宇宙物理」として日本語でも出版されている.しかし1991年の出版以降,ニュートリノ振動の確立,最高エネルギー宇宙線観測の進展,ニュートリノや高エネルギーガンマ線観測技術の向上,活動銀河核などの高エネルギー天体観測による新しい知見,LHC実験による高エネルギー反応断面積の更新などが相次ぎ,第一版の内容はかなり古くなってしまった.この第二版では二人の共著者を新たに迎え,上で述べた近年の観測的成果や新しい知見を取り入れ,大幅に内容を刷新し,時代の要求を満たしている.
内容は網羅的で,①素粒子物理や高エネルギー反応,ニュートリノ振動などのレビュー部分,②銀河系内外の宇宙線の伝播や伝播途中の二次粒子生成,衝撃波による粒子加速などの物理的解説,③超新星残骸やガンマ線バーストなどの天体現象,④大気に突っ込んだ宇宙線が作る空気シャワーの観測から物理量を引き出す解析技法,⑤ニュートリノやガンマ線の最新観測成果などが丁寧に書かれている.宇宙の観測は多様な天体現象を探る楽しみを提供してきただけではなく,標準理論を超える物理の必要性を示唆してきた.本書はAstroparticle Physicsが次世代の物理・天文学に迫る最前線にあることを実感できる本となっている.かなり読み応えのある本であるが,一気に全体を学ぶことができるので,特にこれからこの分野に参入する大学院生や若手研究者に読むことを薦めたい.
(2017年1月7日原稿受付)
自然世界の高分子;物理現象から生命の起源まで
A.グロスバーグ,A.ホホロフ著,田中基彦,鴇田昌之監訳
吉岡書店,京都,2016,xvii+372p,21×15 cm,本体5,500円[大学院・学部向]ISBN 978-4-8427-0367-1
紹介者:山口哲生(九大工)
われわれの住む世界は,物質で構成されている.生体系もしかりで,DNAやタンパク質のような高分子や,リン脂質をはじめとする両親媒性物質など,いわゆるソフトマターからなる.生物の機能や生命の成り立ちを物理学の立場から理解しようとするとき,構成物質であるソフトマターの物性を考慮するのは極めて自然な試みであると考えられるが,実際にそのような例はどのくらいあるのだろうか? 最近,研究論文は増えてきているが,筆者が知る限り,教科書はほとんど見当たらない.これは,これから生物を遺伝子ではなく物性の視点から研究したいと考えている初学者にとって,大きな障害であると思われる.
本稿で紹介する「自然世界の高分子」は,まさに生命と物質とをつなぐことを試みた,極めてまれで,かつ先駆的な教科書である.もちろん,ソフトマター物理の教科書としても十分な内容を含んでいる.第1章から第4章において,他のソフトマターの教科書と同様に,ソフトマターの物理・化学に関する一般的な記述がなされる.第5章では,リン脂質からなる生体膜,タンパク質,DNA,RNAなど生体高分子の一次,二次,三次構造が,ソフトマターの自己組織化の観点から,まずは大雑把に議論される.その後,再びソフトマターの基礎に立ち戻り,エントロピー弾性,排除体積,コイル・グロビュール転移などが説明される.これは,第10章で紹介されるタンパク質のフォールディングのイントロダクションになっている.さらに,結び目,ゲル,DNAの電気泳動といった,生体物質の物理を語るうえで欠かせない内容が盛り込まれる.そして,最終の第15章では,塩基配列の統計学や,生命と熱力学,原始地球におけるアミノ酸の合成など,ソフトマターと生命の起源との関係が,著者の強い思いをもって語られる.
このように,本書は,ソフトマターの基礎から生体物質の機能に至るまで,幅広くかつやさしく記述されている.統計力学を学んだ学部4年生や大学院生が自習するのに適していると思われる.ただ,少しだけ難を言えば,数式に対する説明が不足しており,本書だけでフォローするのはそれほど容易ではない.また,とくに第15章に見られるように,生命と物理学との関係が議論されているものの,いささか独断的な印象を受ける.したがって,巻末に挙げられている専門書を適宜参考にしながら,数式の導出や書かれていることの意味を一つ一つ輪講などで確認しながら読み進めていくと,より効果的だと思われる.物質に即した生命現象の理解や,生体物質の機能への統計力学的なアプローチ,生体を題材にしたソフトマター分野に興味を持つ学生・研究者に,一読をお薦めする.
(2016年12月20日原稿受付)
Field Theories of Condensed Matter Physics 2nd Ed.
E. Fradkin
Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2013, xvi+838p, 25×18 cm, $109.99[専門・大学院向]ISBN 978-0-521-76444-5
紹介者:古川俊輔(東大院理)
物性物理学における場の理論的アプローチの教科書として長年親しまれてきたE. Fradkin氏の本が大幅増補されたのが本書である.内容量は以前の倍ほどにも及び,著者自身が語るように,実質的に新しい本とも呼べるものである.内容としては,1991年に出版された第一版ではHubbard模型の磁性から始まり,量子スピン鎖,量子スピン液体,エニオン超伝導,整数・分数量子Hall効果などの項目が並んでいた.これらは,共形場理論,格子ゲージ理論,トポロジカルな場の理論などの美しい体系のもとで理解される興味深い対象である.今回の第二版においては,これらの各項目が拡充されるとともに,繰り込み群やLuttinger流体などの基礎概念や,トポロジカル絶縁体・超伝導体,非可換量子ホール状態,量子エンタングルメントなどの発展的内容も加えられ,800頁を超える大著となった.
興味深い点は,90年代初頭に書かれた第一版の内容が今日色褪せるどころか,より豊かな分野として発展している点である.銅酸化物超伝導体の発見に触発されて発展した量子スピン液体の理論が,近年のフラストレート磁性体の研究の中で実験,数値計算と直接比較しながら発展している.私個人,同分野を研究し始めた2000年代に,量子スピン液体のゲージ理論が書かれた数少ない本の一つとして,第一版にお世話になった.第二版では,抽象的なゲージ理論と,トーリック・コード模型,量子ダイマー模型などの厳密に解けるトイ・モデルとの関連を詳しく議論した新たな章が加えられ,具体的な模型の中でスピン液体の理論を理解できるよう工夫がなされている.物性物理学の現在最もホットな分野の一つであるトポロジカル相の研究の源流は,80年代の量子Hall効果と量子スピン鎖の研究にあった.急速に発展する同分野を研究するにあたっても,古典となるこれらの研究を深く理解することは不可欠である.本書ではこれらの「古典」的例を通じて,Berry位相,バンド・トポロジー,トポロジカルな場の理論がいかに応用されてきたのかを詳細に学ぶことができる.特に,分数統計や非可換統計がトポロジカル項からどのように現れるか,それらが量子干渉計によりどう検出されるかにまで話題が及んでいるのは類書に例をみない.第二版でより最近の内容が加えられたことによって,基礎から近年の話題まで体系的に学べるようになった.
2016年のノーベル物理学賞は,物性物理学のトポロジカルな側面を開拓した3名の研究者に授与された.受賞の主な対象となったKT転移,TKNN公式,Haldane予想はいずれも本書でカバーされている.トポロジカル相の研究は弱相関系から強相関系への移行期にあり,本書の扱う場の理論の非摂動論的手法がますます重要になってくるであろう.また,本書の最終章でも紹介される通り,量子エンタングルメントが多体系の背後の場の理論の情報を抽出する道具として発展し,量子情報理論,素粒子物理学と融合した学際的研究が進んでいる.本書の扱う内容は多岐にわたるが,いずれも最先端の研究と通じており,異なったトピックはある程度独立に読むことができる.最初の数章で経路積分や繰り込み群について基礎から解説がされており,初学者にも一定の配慮がなされている.初学者が基礎から体系的に学ぶための本として,あるいは関連分野の研究者がより包括的な知識を得るための本として有用である.
(2017年1月20日原稿受付)
現代素粒子物理;実験的観点からみる標準理論
末包文彦,久世正弘,白井淳平,湯田春雄
森北出版,東京,2016,vi+247p,22×16 cm,本体3,800円[大学院・学部向]ISBN 978-4-627-15581-7
紹介者:陣内 修(東工大)
素粒子物理学では,Bメソン系のCP非保存やニュートリノ振動,そしてヒッグス粒子の発見に代表されるように,私が学生であった時代以降も,ノーベル物理学賞に直接つながるような新しい驚きが次々と登場した.時代の変遷とともに,素粒子物理で扱うトピックスも増え,理論的な背景はより抽象化・複雑化し,また実験技術はより高度なものへと発展して来ている.これらの新たな発展を最近の学生はどうやって学んでいるのであろうか.
素粒子の教科書には様々な良書があるが,多くは大学の学部後期の学生を対象としたいわゆる素粒子初学者向けのものである.本書は学部で素粒子の講義を受けた学生が修士の初年度に,素粒子物理の世界へもう一歩踏み出すことを,絶妙な力加減でサポートする,これまでに類をみなかったスタイルの教科書である.これは大学院の講義を担当する我々のような教員にとっても当てはまる.素粒子物理の発展項目は非常に幅広く存在しており,取捨選択に迫られる.自分の専門ばかりに偏らないよう満遍なく分野を横断しつつ,1つ1つの話題をある程度の深さで掘り下げるのは至難の技である.本書はそんな我々にとっても,良いガイドブックとなるのである.
幅広い素粒子実験の経験をもつ著者らがまとめた本書では,歴史的な発見や最新の結果,さらに将来計画まで,理論的な背景と実験とを対比させ,多くのイラストやプロットを配している.大学院生向けの構成であるので,数式も多く用いられてはいるが,その多くは直観的理解を補足するためのものであり,実験屋同士がホワイトボード上で議論する際にでも,即席で参考にできそうな実用レベルのものが多い.
本書は11章と3つの付録から構成されている.第1章で,学部で習った素粒子の基礎を一気に復習し,第2から4章では,電磁・弱・強相互作用のおさらいを説明しつつ,応用トピックスを散りばめている.例えば,第2章においては,電子・陽電子の束縛系であるポジトロニウムという原子様粒子を題材として取り上げ,メソン束縛系の理解につながる説明を行っていたり,またポジトロニウムをパリティ,荷電共役など抽象的な対称性の説明における具体例として用いたりすることで,斬新な切り口から基礎知識の理解を促している.学部向けの教科書であれば後半の発展項目に登場することの多いニュートリノ振動に関しても,本書では第2章で早くも登場する.素粒子の混合と振動という重要な基本概念を,早いうちに説明してしまおう,それならばいっそのこと自分たちの十八番であるニュートリノ振動を題材に使ってしまおうという妙案である.
実験例は,最新のものに限らず,歴史的な発見に関するものも数多く取り上げている.第4章ではπ粒子の諸性質を測定した実験手法をイラストもふんだんに交えながら特集している.π粒子の質量,スピン,パリティ,そして寿命などをどのように決定したのか等.大学院講義の現場において,演習課題として取り上げると良さそうな題材である.第5,6章を通して,量子色力学とハドロンの物理を程よい応用レベルで解説し,第7章では,チャーム,τ,ボトム,そしてトップ・クォークやW,Zと発見の歴史を一気に駆け上がる.第8,9章ではフレーバーの混合の理論的な基礎から実験での検証までを,丁寧に解説する.第10章では著者らが専門とするニュートリノについて,これまでの様々な取り組みや,発見の歴史,そして未解決問題への将来実験構想までをページ数を割いてじっくりと説明してある.国際会議などでいま正に取り上げられている話題にまで拡げて解説してあり,純粋にニュートリノ物理の全体像を知りたい人にとっても有用な章である.最終章となる第11章では,標準模型の根幹であるゲージ対称性の検証実験を丁寧に解説し,最後にはヒッグス粒子の発見の解説,そして,素粒子実験全般の将来構想について言及している.
このように本書は,そのままで大学院講義の教科書,副教材として用いることができる内容を有していながら,近年の発展を一望するためのまとめ本としても読み応えがある.また,各章には章末問題が複数用意してあり,講義中の理解度確認テストなどにも有効に活用できるであろう.自信をもってお薦めできる一冊である.
(2017年3月9日原稿受付)
スパース性に基づく機械学習
冨岡亮太
講談社,東京,2015,xi+179p,21×15 cm,本体2,800円(機械学習プロフェッショナルシリーズ)[専門・大学院向]ISBN 978-4-06-152910-6
紹介者:中西(大野)義典(阪大院工)
地球科学の反射法地震探査,生化学の核磁気共鳴分光法,天文学の電波干渉法,表面科学の走査トンネル顕微・分光法.広範にわたるこれらの物理計測の共通点は何だろうか.その一つが本書の表題にあるスパース性である.スパースとは「疎ら」を意味し,多くの変数のうちごく一部だけがゼロでない値をとることを指す.たとえば,分散関係があるということはスパースであるということである.というのも,エネルギーを指定すると許される運動量がごく一部だけになるからである.スパース性を活用すると,複雑な物理現象を記録した高次元データから有効な説明変数を選択できる.また,計測時間を削減できるようになり実験計画に有益な指針を与えられる.本書はスパース性に基づく機械学習について,機械学習の初歩から,基礎理論や最先端アルゴリズムに至るまでが僅か200頁足らずに収まっている.
本評の読者には機械学習に馴染みの深い方ばかりではないと思う.ここでは本書の導入になぞらえて,基本的なデータ解析手法である最小二乗法に機械学習の一端を垣間見てみよう.最小二乗法を使うとき,「このデータは何次関数を使うのが適切か」や「このスペクトルのピークは2個か3個か」といった疑問を抱くことはないだろうか.もしくは物理的直感の赴くままにフィッティングパラメータを増やしていくと,データが100個しかないのに100個のパラメータを用いていたということはないだろうか.機械学習はこういった点に問題意識を持っている.スパース性に基づく機械学習では,データを説明できるならなるべく少ない変数で,という観点に基づき,これを数理的に最適化問題として定式化する.スパース原理は物理的直感とも合致すると考えられ,一度定式化されれば,人の手に負えないような高次元データも計算機を用いて取り扱えるようになる.
ところで本書を紹介するのは,これを読みさえすれば物理学の諸問題がたちどころに解決するからというわけではない.むしろ物理学と機械学習の協力を促したいからである.本書の終章にもある通り,「どのような問題にスパース性は適しているのか」という問いかけは機械学習の中だけで閉じるものではない.たしかに本書では,最も基本的なベクトルや行列としてのスパース性だけでなく,グループ構造を有したスパース性やそれらを包括した「一般的なスパース性」に基づく機械学習の手法が説明されている.しかしながら,具体的な物理現象のどこにスパース性を見出し,どのように機械学習の問題としてモデリングするかについては課題として残されている.近年,スパース性に基づく機械学習が物理学をはじめとする自然科学との接点においてスパースモデリングと渾名されるのもモデリングの難しさ・重要性を反映してのものであると頷ける.
最後に,本書が機械学習プロフェッショナルシリーズの一巻として刊行されていることからも分かる通り,機械学習はスパース性に基づくものに限らず,物理的直感を記述できるだけのさまざまな観点を用意している.本評を通じて物理学と機械学習とが有機的に連携しそれぞれの地平を広げることになれば,評者にとって望外の喜びである.
(2017年3月8日原稿受付)
機械学習入門;ボルツマン機械学習から深層学習まで
大関真之
オーム社,東京,2016,vii+201p,21×15 cm,本体2,300円[学部・一般向]ISBN 978-4-274-21998-6
紹介者:安田宗樹(山形大理工)
最近の人工知能分野の驚異的な発展は専門家でなくとも肌身に感じざるを得ない状況であることは連日のニュース等で皆さんもよくご存知であろう.その発展の根底を支えているのが機械学習とよばれる理論とその技術であり,中でもとりわけ目立っているのが深層学習(ディープラーニング)である.そのせいか(いや,そのおかげか),ここ一年間で深層学習に関する専門書は多くなったように思う.しかしこれは,これから機械学習分野に入門しようと考えている方にとっては少々やっかいな状況を生む.多すぎるが故の「最初はどの本で勉強すればよいのだろうか?」という問題である.そのような方にこそ,まずは本書の一読をお薦めしたい.
本書は,白雪姫の世界観になぞられたお妃さまと鏡とのコミカルな会話でのやりとりが主軸となって話題が進行する.各所に挿入されたイラストも相まって,まるで絵本のような雰囲気である.その中で数式という数式はほぼ現れてこない.一見,「これって本当に専門書か?」と疑問をもつような見た目である.しかし,その見た目に騙されてはいけない.これは立派な「専門書」である.機械学習とは何か?という基礎中の基礎から始まって,最新の深層学習の話題はもちろんのこと,スパースモデリングの世界にまで話題は広がっている.またその内容は,この手の書籍にありがちな「単なる理論概念のみ」に留まらず,かなりの意味で個々の要素技術の本質に踏み込んだ内容であることが読み取れる.そして何より,個々の技術の間のつながりやそれぞれの立ち位置が手軽につかみやすいというのが本書の一番の売りだと思う.詳細な数式を用いて内容の深堀をしていない本書だからこそ伝わりやすいのだろう.
本書から教科書的な機械学習の知識を得ることはできない.しかし,最近話題の機械学習分野の俯瞰を手っ取り早くつかむための登竜門的入門書としては打って付けであろう.読み物として気軽に読める内容なので,機械学習についてまったく知識のない学生諸君にも無理なく読めるものになっていると思う.
最後に付け加えておくと,著者は物理学者である.これが,この場で本書を紹介する一番の理由である.機械学習の勉強をこれから始めようとしたときに,分野の違いから来る文化の障壁に遭遇するかもしれない.それで挫折してしまった人もきっと少なくないだろう.それとも,もしかしたら機械学習という方法そのものになんとなく抵抗感のある読者もいるかもしれない.物理学は自然との対話にあり,法則を見出す直感力は人に勝るものはない,そう考える向きもあるだろう.自然科学としての物理学の始まりは,実験データからの法則の抽出にあったはずだ.機械学習は,多様で一見複雑に見える現象を大規模で高次元なデータから出来るだけ客観的に把握しようとする試みであり,そう考えると,機械学習のやろうとしていることは実は自然科学としての当然の所作なのであり,自然科学の目標とかけ離れたものではないと言える.物理学者の視点で考えられた表現がなされている本書であれば,今までなんとなく感じていた障壁や抵抗感を乗り越えることが可能ではないだろうか.
先にも述べた通り,これから本格的に物理学を学ぶ学部生でも無理なく読める内容であり,また,これまで自然科学に従事してきた研究者にも新しい方法論を学ぶ一手として本書をお薦めしたい.
(2016年12月5日原稿受付)
格子QCDによるハドロン物理;クォークからの理解
青木慎也
共立出版,東京,2017,vii+130p,21×15 cm,本体2,000円(基本法則から読み解く物理学最前線13)[専門・大学院向]ISBN 978-4-320-03533-1
紹介者:保坂 淳(阪大核物理研究セ)
2012年に稼働し始めた神戸のスーパーコンピュータ「京」はマスコミでもしばしば取り上げられ,国民の多くに知られることとなった.本書で扱う話題は理論物理学の中でも,スーパーコンピュータを最大限に駆使した研究である.物理学は数学によって表現され理解されるが,従来の解析的な道具に加え,現代ではコンピューターが数の足し算や掛け算を超えた新たな解析手法をもたらしている.今では,最も難しいとされる非摂動QCDによるハドロンの研究にもスーパーコンピュータが用いられ,新たな可能性を切り開いているのである.物理学では原理の解明とともに現象の定量的な予言能力が問われる.QCDでは後者が特に難しいといわれるが,実際のところ両者は表裏一体なのである.
著者の青木慎也氏は格子場の理論を専門とする素粒子論の研究者である.その中で最近世界的にも注目を浴びているのが,本書の中心テーマである核力(一般的にハドロン間相互作用)の研究である.いわゆるHAL法の開発は強い相互作用の研究の歴史において,湯川博士がπ中間子を核力の起源として提案して以来の大きな進展であると言える.そのため2007年のNature誌年間ハイライトに選出され,また2012年には共同研究者である石井理修氏,初田哲男氏らと仁科記念賞を受賞されている.
前置きが長くなったが,本書はQCDから核力を導くための著者たちの奮闘の様子が伝わるものである.対象となる読者は大学生とされている.QCDをラグランジアンによって定義し,それにより諸性質をきちんと解説するのは難しいと思われる.しかしながら読み進めるにつれて,むしろ彼らに最先端の様子をありのままに提供し,好奇心を誘うには適しているように思えてくる.向学心旺盛な若者にとっては惹かれる箇所が非常に多いに違いない.
2章と3章では,ハドロン物理とQCDの基本的な内容が要約されている.4章からが本題である.まず格子QCDのエッセンスについて,繰り込み,相転移の考えを使って,連続場の理論をいかに定義するかという観点から簡潔に述べられている.標準的な教科書ではあまり記憶に残りにくいけれど重要な点が丁寧に述べられているのは印象深い.最後に観測量の計算法についても簡単な例と類似によって述べられている.5章で現実との比較が始まる.QCD真空が示すカラーの閉じ込め,カイラル対称性の自発的破れ,そしてハドロン質量の計算と進む.きっちりした理論家らしい展開である.そしていよいよ6章で核力の話題に移る.核力はもともと核子間のポテンシャルによって記述されてきたが,QCDという場の理論にはそれに対応するものがあらわに書かれていない.そこでいかにそれらを定義し,QCDによって導くかという問題を丁寧に議論している.これは古典論,量子論,場の理論を改めて見直すにも大いに役立つ.
以上見たように,最先端の理論研究の展開の様子が簡潔にまとめられた本である.内容は必ずしも容易でないが,現在と未来に何が行われるのかを著者の考えとともに知るのに良い.挑戦したいという大学生はもちろんのこと,この分野に携わる研究者にとっても有用な書物である.
(2017年1月30日原稿受付)
原子核物理学
北川米喜
共立出版,東京,2015,vii+307p,22×16 cm,本体4,200円(KEK物理学シリーズ2)[専門~学部向]ISBN 978-4-320-03485-3
紹介者:中野健一(東工大理)
本書にはごく一般的な表題が付いているが,その内実は言わば「ハドロン・原子核物理学」の教科書であり,強い相互作用によって束縛される量子多体系としてハドロン(核子を含む)と原子核を記述し,その構造と性質を解説するものである.従来の原子核物理学の教科書が前提としている「核子が核力で束縛された原子核」という描像に留まらず,量子色力学(QCD)に基づいてハドロンと原子核を体系的に記述している.学部4年生から大学院1年生を対象として書かれているが,ハドロンと原子核の構造を統一的に理解するという本書の視点に触れることは,若手研究者にも有意義であろう.
ハドロンや原子核の構造を理解する基礎として,本書は強い相互作用の性質自体も詳しく解説している.特殊Lorentz変換などの基本事項から段階的に説明してあり,式変形の過程や条件も丁寧に書かれているので,初学者にも理解しやすいはずである.2章のQCDの説明は,格子QCDの計算手法にまで言及する詳細なものであり,その後の5章でQCDを踏まえて核力が導入される.
3,4,6章ではハドロン(核子を含む)と原子核の内部構造を観測エネルギースケールに応じた理論で定式化する.すなわち,3章では有効QCD理論(クォーク模型)を用いて構成子クォークからハドロンを構築し,4章では摂動論的QCDを用いてパートンから核子を構築し(パートン模型),6章では核子とパートンそれぞれから原子核を構築する.ページ数制限により章ごとの項目は限られているものの,主要な項目がコンパクトにまとめられている.例えば3章ではMIT袋模型などのハドロン模型が網羅されており,日本語の参考資料として貴重である.しかし本書の特色は,ハドロンも原子核も究極的にQCDで統一的に記述できるという論理構成にある.QCDの低エネルギー有効相互作用として核力を理解・統一するという視点は,強い相互作用の研究においてその重要度を増していくだろう.
QCDによる核子と原子核のクォーク・グルーオン描像は多くの観測事実を説明できるが,理論的・実験的精度の向上によって未解決の現象も様々に発見されており,今も活発に研究されている.その幾つかが7章で紹介されており,現在の研究課題が日本語で解説されていることも本書の貴重さの一つである.例えば核子の3次元構造(4.9節)が実験的に明らかとなったのは2005年頃であり,学生がこれを勉強しようにも古い教科書では解説されていなかった.他の原子核物理学の教科書を読んでいる場合にも(むしろ読んだ上で比較しつつ),強い相互作用の研究に対する統一的な視点と現在の課題を学ぶために本書の通読をお薦めしたい.
(2017年4月30日原稿受付)
すごい!磁石
宝野和博,本丸 諒
日本実業出版社,東京,2015,318p,19×13 cm,本体1,800円[一般向]ISBN 978-4-534-05276-6
紹介者:岡林 潤(東大理)
本書は,磁石に関する基本事項から応用開発の現状まで,極めて分かりやすく紹介されている.磁石開発の歴史,磁石の基本,作り方,分析手法の最先端までが記述されている.特徴的なのは,難しいと言われる磁性の本質について式を用いずに平易な言葉で明確に説明されていることである.磁石研究の第一人者である著者(宝野氏)が,サイエンスライター(本丸氏)の質問に答える形で解説されているのがユニークなところである.
タイトルにある「すごい!磁石」のすごい部分は,近年の磁石応用の最先端であるハイブリッド自動車のモーター開発への応用に向けたネオジム磁石について,研究開発の最先端について熱く語られているところにある.元素戦略という言葉を聞くことが多くなっているが,磁石の開発において,稀少金属であるジスプロシウム(Dy)を用いないレアメタルフリーな「すごい磁石」,特にネオジム磁石の応用について,研究開発の経緯から述べられており,専門家であっても一読する価値がある.ちなみに,周期表の60番目の元素neodymium(Nd)は,ネオジウムではなくドイツ語のNeodymに由来してネオジムと呼ぶのが正しいそうだ.確かに,周期表でもネオジムとなっている.
近年の磁石の性能向上は,佐川眞人氏によるネオジム磁石の発見による.本書の帯には,ネオジム磁石の多くの謎が解き明かされつつある現状について,寄せ書きがある.原子を見る技術であるアトムプローブの研究者である著者が実際にこの技術を駆使して,「なぜネオジム磁石がすごいか」について丁寧に紹介されている.相分離が磁石の性質に及ぼす影響など,アトムプローブを用いた磁石研究の最先端が紹介されており,関連する研究者にも有益な本と言える.
磁石の用途は多岐にわたり,強力な磁石の開発の他にも,トランスやハードディスクに用いられる磁石開発についても原理の説明と現状の研究開発動向が示されている.ネオジム磁石の他にも,サマリウム磁石やフェライト磁石についても本書によって知識を得ることができる.基礎物理学から応用開発まで直結した磁石研究の面白さについて述べられている.自動車や電化製品には多くの磁石が用いられている.これらの小型化や高機能性が進んだ背景や今後の課題が見えてくる.時折あるコラム欄を読むと,著者のアトムプローブや磁石研究への思いにさらに引き寄せられる.
磁石の基本や作り方のみでなく,歴史や現状の開発動向,及び電子顕微鏡などの先端計測について興味のある人には,導入として極めて分かりやすい解説である.そして,将来の元素戦略に対するヒントが詰まっていることは間違いない.専門家もそうでない人も,本書によって「すごい!磁石」に魅了され,引きよせられることと思う.
(2017年3月20日原稿受付)
生体分子の統計力学入門;タンパク質の動きを理解するために
D. M. Zuckerman著,藤崎弘士,藤崎百合訳
共立出版,東京,2014,xiii+322p,26×18 cm,本体4,800円[専門~学部向]ISBN 978-4-320-03499-0
紹介者:北尾彰朗(東工大生命理工)
本書は統計力学を従来の体系で記述した教科書ではなく,代表的な生体分子であるタンパク質をターゲットにしており,第9章以降で取り扱われているタンパク質の折り畳み・アロステリー(機能部位から離れた部位への分子結合による機能制御)・構造変化・分子の結合解離等のダイナミクスを理解するために必要な統計力学にフォーカスして書かれている.またカバーしている範囲は統計力学を中心としているものの,熱力学や分子の解離・結合,構造変化に関する速度論についてもかなり紙面が割かれている.統計力学の教科書というより,むしろタンパク質ダイナミクスを理解するための化学物理・物理化学の教科書だと言った方がよいだろう.随所にブタンやタンパク質を具体例とした説明がなされているが,これは他の分子の立体構造変化や離合集散を理解するためにも役立つ一般性があるものである.一方で,多種類のアミノ酸や核酸などのヘテロな構成要素からなる生体高分子を理解する上で,大自由度性とそれに伴う物性は重要であるものの,この点にはほとんど触れられていない.本書は,分子シミュレーションで得られるタンパク質ダイナミクスの軌道のアンサンブルから,観測量である反応レートや拡散を得るまでをテーマにした第11章に,全体として収斂する形になっている.これが原著者の主要な研究テーマであり,この教科書を最も特徴づける一章となっている.
本書の大きな特徴として,原著者の講義に参加して,その名調子を直接楽しんでいるかの如く読者に感じさせる,独特の筆致が挙げられる.アメリカ人にはおそらく馴染みがあるキャンディーやテレビのクイズ番組を導入として親しみやすく説明した部分は,残念ながら日本人にはピンとこないだろうが,随所で極力単純化してあるが本質を取り込んだモデルを使って,式や現象の物理的な意味がわかりやすく解説されている.また,理解が難しいと思われる概念や誤解しやすいと思われる点が,紙面を割いて丁寧に説明されている.取り扱われている問題は分子シミュレーションによって具現化されることが想定されているので,実際のシミュレーション結果が図としてふんだんに用いられ,これによって個々の課題が理解しやすくなるよう工夫されている.それに対応して最終第12章には代表的な分子シミュレーション法・計算法とそれに対する原著者のスタンスが要領よくまとめられている.これらは本書の優れた点であろう.
評者の経験では,生物を物理学的に理解しようという生物物理学を志す若い人たちの中には,それまで物理学を系統的に学んできておらず,生物学・化学・情報学などを中心に勉強してきたという人たちも多い.彼らが物理学的な思考法を学んでいく際に,統計力学が最初の難関となることがある.本書は,大学1年レベルの力学・電磁気学・化学・微積分の知識を前提に書かれており,様々なバックグラウンドを持つ広い分野の人々にとってよい教科書となるかもしれない.しかし,本書はかなり高度で専門的な内容を含んでいることから,評者はむしろ物理学・タンパク質・分子シミュレーションすべてに既にある程度の知識を持っている人に一読をおすすめしたい.本書の道筋に沿ってタンパク質の物理学を見直すことで,理解をより深める好機となるのではないだろうか.
(2017年3月27日原稿受付)
量子力学で生命の謎を解く
ジム・アル=カリーリ,ジョンジョー・マクファデン著,水谷 淳訳
SBクリエイティブ,東京,2015,ix+396p,19×13 cm,本体2,400円[学部・一般向]ISBN 978-4-7973-8436-9
紹介者:南部伸孝(上智大理工)
本書は,日本語タイトル通り,生命の謎と量子力学のつながりを紹介しています.特に最新の成果を基に,様々な学術的視点・角度や歴史を通して正確に議論がなされています.そして,全体として原著タイトルの"Life on the Edge: The Coming of Age of Quantum Biology"と言いたいのだろうと感じます.つまり,個人的に意訳を試みますと,「生命科学の最前線:量子生物学の時代の到来」でしょうか.ただし,これでは頭が固すぎます.私の学術雑誌になってしまいます.そこで,もう少し想像すると「Life on the Edge」は,「無茶をやる」「危険な生き方をする」「ワクワクするような人生」などに使われる言葉であることから,生物の世界とは真逆に思われがちな「量子論」を議論するのかと,ある意味「無茶」を醸し出します.さらに,この本の結論と思われる「無秩序」から「秩序」へ進むこの「秩序」が,量子論により生み出されていることを主張します.この主張は,生命体をマクロからミクロへ観測すると,細胞からタンパク質そして機能分子へ辿り着き,その機能分子の位置する場所が,まさに「Life on the Edge」の場所だと表現したいようにも感じさせます.
具体的な内容の紹介をしましょう.量子効果を重要視する分子生物学者であるジョンジョー・マクファデンが,素粒子研究を主に行っている物理学者ジム・アル=カリーリの手を借り,量子力学が産声を上げた時代から現代に至るまでの量子生物学の変遷を,生体における様々な機能を通して紹介しています.
話の始まりは,渡り鳥であるヨーロッパコマドリの磁気感覚が磁気コンパスと同じ働きをすることを見出す1970年代の議論からです.実験により磁気コンパスと同じ働きをすることが,生物学者により見出されました.そして1976年に,クラウス・シュルテンにより量子論に基づき,その機能の説明が試みられます.それは,2013年度にノーベル化学賞を受賞したマーティン・カープラスとアリー・ウォーシャルが,視覚の初期過程に現れる網膜にあるレチナール分子の光異性化反応を,1972年に量子論と古典論で説明した時期とほぼ同じです.大型計算機の利用が比較的容易になりつつあった年代だと思われ,若き研究者が生物の世界へ挑戦した時代です.しかし,物理化学の教科書の著者として有名なピーター・アトキンスは,1976年の学術誌において動物の地磁気感知能力に関し疑念を示していました.学術の世界は様々な意見があり,まさに多様性を感じます.
さらに歴史を遡ると,1944年に,シュレーディンガー方程式の発見で有名なエルヴィン・シュレーディンガーが生命に関する本を出版しています.彼は,生体が「無秩序」の中にいて「秩序」=「機能」を生む過程での量子論の重要性を述べています.ごもっともな意見ですが,70年代以前まで生物学の世界では,量子論の意義を何も感じていなかったのでしょう.70年代に入り量子論の生物学への応用が真剣に取り上げられるようになり,さらに21世紀に入ると,その在り方が劇的に変わります.コンピュータの性能がPeta-Flopsへと飛躍的に進み,量子論による「秩序」が物理モデルによって計算可能になります.タイトルの「量子生物学の時代の到来」です.そして,生命の起源まで議論は進みます.
私は,ここまでを紹介します.本書は量子現象を分かり易く説明する工夫が多く見られ,生物学にも興味を持つ本学会員,学生諸氏に是非読んで頂きたい本であると思います.特に,話が章ごとにほぼ完結している感じもあり,気になった章を読むのもよいかもしれません.さらに,参考文献の引用もなされるなど,素晴らしい配慮が見られます.このように,理工の学部生にお勧めですが,私のようなものでも楽しく拝読することができました.
そして,読者の皆様は,もしかするとこの本に登場する人物たちが,まさに「無茶をやる」「危険な生き方をする」「ワクワクするような人生」な方々だとも感じるでしょう.それが,まさに新しい科学分野を創造してきた歴史なのかもしれません.
(2017年5月3日原稿受付)
リヴァイアサンと空気ポンプ;ホッブズ,ボイル,実験的生活
S. シェイピン,S. シャッファー著,吉本秀之監訳,柴田和宏,坂本邦暢訳
名古屋大学出版会,名古屋,2016,vii+337+106p,22×16 cm,本体5,800円[専門・大学院向]ISBN 978-4-8158-0839-6
紹介者:有賀暢迪(国立科学博物館)
奇妙な表題を持つこの本は,現代における科学史研究の古典の邦訳である.原書は1985年に英語で出版され,科学史という学問分野の性格に大きな影響を与えてきた.本書の概要とそれがもたらした影響を,物理学研究者向けにできるだけ簡潔に紹介することが,評者に与えられた課題である.
最初に断っておくと,本書は一般向け書籍ではなく,人文系特有の文章スタイルで著された大部の専門書である.内容面でも,十七世紀のイギリスにおける政治・宗教・哲学が詳しく議論されており,大部分の理工系読者にとっては難解(もしくは退屈!)に感じられることが予想される.
それにもかかわらず,本書は科学史上の有名な題材を扱っている.十七世紀のサイクロトロンとも呼ばれることのある当時最先端の装置,空気ポンプ(真空ポンプ)と,それを用いたロバート・ボイルの実験である.もっとも,著者らの関心は,ボイルがどのような科学的知見をどのような実験により得たかということには向けられていない.問題にされているのは,「実験事実」なるものが生み出される過程あるいはメカニズムであり,また,それが有している社会的な性格である.
著者らの主張によれば,ある実験結果が「事実」とされるには,その手法を妥当と見なす人々の同意が必要である.そしてそのためには,実験という手法を有意義だと認める人々の集団が存在しなくてはならない.逆に,実験というアプローチを有効と考えない人間はこの社会から排除され,そこに境界線が引かれることになる.本書の大部分は,ボイルを中心とする「実験哲学者」たちと,彼らの研究プログラムを批判したトマス・ホッブズ―政治思想の古典である『リヴァイアサン』の著者―の論争を分析することで,以上のような問題を考察している.
要するに,本書は科学史上の有名な実験について,社会学的観点から論じた研究である.それまでの科学史はどちらかと言えば学説や思想の変化を追うものだったが,90年代以降は,本書にも見られるように,科学的知識が実際にはどのようにして生み出されたのかという問題意識が強くなった.
このような観点からの科学史は,現代の物理学研究者にとってはむしろ有意義であるかもしれない.同意や境界をめぐる議論というのは,今日で言えば査読システムの問題である.また,第6章で扱われる空気ポンプの複製という話題は,最先端の高価な装置を用いた実験を追試する困難さや再現性の問題として読むことができる.
本書に興味を持たれた方には,最初に第2章を読み,次いで第6章を読むことを勧めたい(この二つの章は,科学的な内容が比較的多い).あるいは,著者の一人であるシェイピンの『「科学革命」とは何だったのか』(白水社,1998年)は,『リヴァイアサンと空気ポンプ』で示されたような視点から十七世紀の科学史全体を概観しており,本書への導入として役立つだろう.
(2017年5月16日原稿受付)