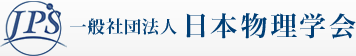40年のおもいで2
日本物理学会誌 第30巻 第3号(1975)pp.170-177.より 望月 誠一
- 編集、出版
- 1) 機関誌の出版 その1
- 機関誌の出版 その2
- 2) 論文選集の出版
- 3) プログレスとの関係
- 4) JJAPとの関係
- 5) Journalの長期対策
- 6) 日本の物理学界(会)の大合同の夢
- 学術的会合
- 1) 年会 その1
- 年会 その2
- 年会 その3
- 2) 分科会
- 3) 国際会議 その1
- 国際会議 その2
1) 機関誌の出版 その1
定款によれば会誌、欧字報告などの出版が第三条第二項に明記されている。設立の年(1946年)には結局会誌第1巻、欧字報告( Journal of the Physical Society of Japan ―以下 Journal という)Vol.1のそれぞれ1冊づつしか出せなかった。それも印刷の進行が遅れて実際日の目をみたのは翌年6月になってしまった。予算では2~3冊出す予定であったが資金不足、物不足、人手不足のせいもあるが先ず印刷所を探すことから始めねばならなかった。委員の方々の御苦労にもかかわらず適当なところが見当たらず困っていたとき日立製作所のご好意で当時同社が「日立評論」その他社内の諸印刷を自社でやっておられた川崎市矢向の同社の印刷所で引受けてもらうことになった。編集、出版の要員が別に居たわけではなく私がその事務を引受け、校正は勿論、原稿の持込みや校正のやりとりは郵便でなく、直接私が川崎の印刷所まで持参した。この印刷所では会誌第1巻のみ、Journal はVol.2 No.4 までを出した。印刷された雑誌は同社の常磐橋別館まで運んでもらい、そこから我々が学会まで運んで発送した。勿論事務員だけで出版ができる筈はなく、この頃委員でこの方面の仕事に熱心に努力された方は柿内賢信先生であった。
物理学会設立当初は編集委員会は直ちには設けられなかったが、翌年には発足し「日本物理学会出版物編集方針」と「会誌および欧字報告投稿規定」が 1947年7月にでき上った。これらの基本的な部分は古谷正雄先生によってつくられたものであったと記憶している。この編集委員会は Journal の編集だけでなく会誌の編集の責任をも負っていた。しかし、会誌編集のためには抄録委員会が編集委員会の下部機構として設けられた。
日立製作所の印刷所は遠くて不便であるし、活字の種類も多くなく体裁の良いものとはいえなかったので他の印刷所を物色した。岩波書店に発行を依頼する話も出たが実現するには至らなかった。そうこうしているうちに洋々社(後に学術図書出版社と改称)という出版社が面倒をみてくれることになり、会誌は明和印刷(神田神保町)で印刷し、Journal は、洋々社から独立したアカデメイア・プレス社のきも入りで国際出版印刷社(京橋新富町―現在の国際文献印刷社社長が勤務していたところ)で印刷することになった。
機関誌の出版 その2
この頃になって学会の事務も非常に忙しくなったので手が回らなくなり1947年秋から当時小谷研究室の大学院学生になられた土方克法先生がアルバイトとして担当されることになった。同氏は事務的才能も大いにあり、特に英語が堪能であられたので学会としての英文レターの作成などもついでにやっていただいた。その一例として当時米占領軍のGHQ に提出する書類、特に学会の定款、細則の英訳文をつくっていただいた。物理学会として公式に定款、細則の英訳文をつくったことは無かったので非公式ではあるが土方先生の訳が唯一のものとして今でも保存定款のファイルに綴じ込んで仕舞ってある筈である。
土方先生が3年程編集の仕事をやられたあと米国留学から戻ってこられた増田秀行先生が1年余続けられた。そのあと1952年に至ってはじめて本職の編集委員として松本くわさんが就職された。松本さんはその後約10年の間会誌及び Journal の編集、校正を一手に引き受けてこられたが脳腫瘍で1962年2月に亡くなられた。1955年からは会誌、Journal とも月刊となり編集、校正の仕事は多忙を極め、松本さんは心身ともに疲れて睡眠薬などを常用されていたらしいことが健康を害された遠因をなし死期を早めたことと推察され、もっと早く編集部の人手を増してあげるべきであったと悔やまれてならない。
松本さんの死を機会に編集部は会誌1人、Journal2人に、一般事務の方もついでに増員された。設立当初の2~3年は財政状態、原稿の集り具合、印刷所の都合などもあって合併号とせざるを得なかったが会誌、Journalとも第2巻から第9巻までは年6冊刊行を建前とした。第10巻(1955年)から両方とも月刊とすることになりこの年から会誌編集委員会が独立した委員会となった。久保亮五先生がその初代委員長となられ会誌の誌面の改善に力を尽された。会誌の印刷は学術図書出版社の手を離れて明和印刷から 1951 年に渋谷の眞興社に変り、会誌に広告をのせるために親しみある表紙にすることを考えたのが 1957 年で、例の赤紫の表紙にButuriと筆書体で白抜きにすることにした。このとき表紙の色刷りの具合を検討するために当時の出版委員会長小野周先生にお伴して眞興社の神田の印刷所に行ったことがある。その後、欧文誌の自由購読制採用に際しJournalの表紙の体裁が変わったのを機会に会誌も現在の表紙に再度変更された(1967年)。Journalの方は先のアカデメイア・プレス社が手を引いた(1947年)後も直接取引で続けたがJournalの印刷所での担当者であった笠井康頼氏が独立して国際文献印刷社を創立したのを機会に、直ちに後者に移すことをせず、芝の笠井印刷や、本郷春木町にあった横浜正金銀行の専属印刷社などで出版を続け、1952年に至って初めて国際文献印刷社に依頼することになりその後現在に至っている。国際文献印刷社の社業が確立するに至ったので会誌も1959年にここに移すこととした。
2) 論文選集の出版
終戦直後は国内の文献の出版が思うに任せなかったのは勿論であったが外国文献の入手はなおさら困難であった。そういうときにGHQにおられた物理学者Kelly 氏らの尽力によって物理学会に対し American Institute of Physics の出版物の寄贈などをしてもらったほか米国物理学会の好意によりReviews of Modern Physicsのリプリントを許可してもらうことができた(1947年)。本会としても大いに喜んで、東西出版社とアカデメイア・プレス社に依頼してそのVol.13 No.3,4,Vol.14 No.4,Vol.16 No.2,Vol.17 No.1を複製することとした。このリプリントが表紙の色まで本物そっくりに真似されたので米国物理学会から中止を要請された。それでその後は A.I.P.に依頼してA.I.P.出版物の中から主題別に選んだ論文選集として出版することにした。その企画、出版のために編集委員会とは別に出版委員が設けられた。リプリント出版に関しては企画面では山内恭彦先生、実務面では雨宮綾夫先生らがその中心的役割を果たされた。その後オリジナルの論文も A.I.P.出版物に限らず広く全世界の物理学会雑誌から採録するように拡張した。いずれも著者、発行所からの正式許可を得た上で出版する方式をとった。
論文選集は戦後の文献入手困難な状況において図に当たり、経済的にも十分成立つことができた。もっともそのための専任職員は全く置かず出版は望月、頒布は山里氏が片手間にやっていたからで専任職員などを雇っていたら勿論赤字を出していたことは確実である。
論文選集の会計は、本会計とは全く分離して委員会までの報告にとどめ、会員には1964年末に複式簿記を採用することに決ったとき初めて創始以来の会計内容が報告された。本会の会計は論文選集会計により実質的には大いに助かっていた。学術的会合関係の備品、要具はじめ書棚その他の備品、交換雑誌の製本代など殆どこの会計から支出されてきた。
論文選集の出版は、その後外国文献の入手が容易になってからも研究者にとっては非常に便利なものであり、需要が減ることもなく現在も続刊されている。
3) プログレスとの関係
物理学会設立後間もなく湯川秀樹先生から戦時中から蓄積された素粒子論関係の論文を出版したいが物理学会でこれを引受けてもらえないかとの打診があった。初代委員長清水武雄先生の時であったと記憶する。当時設立後間もない学会として財力もなく、また当時ものすごいインフレーションの進行しているさ中で Journal を出版するのに大変な苦心をしていた状態であったので委員会としても甚だ残念ながらこれを辞退せざるを得なかった。
そこで湯川先生を中心に京都で理論物理学関係の雑誌を出版する企画が進行し当初は秋田屋書店刊行という形で始められた。これが Progress of Theoretical Physics(以下Progressと略称する)である。
しかし、1949年に至って秋田屋書店が解散することになり、Progressの編集当事者は素粒子論懇談会にも諮って発行主体を日本物理学会として欲しい旨学会に申入れがあった。当時用紙が配給制であったための申請者として、また文部省の補助金を受けるための申請者として、さらには Progress が公的な出版物であることが望ましいという事情からこのような申入れとなったようである。物理学会の委員会でこの問題を検討した結果 1) 物理学会が名目上の発行者となる、2) 会計報告は年度末に特別会計として物理学会会計に繰り入れる、3) 編集、出版、頒布等の実務は旧当事者が行う、4) 会員中の希望者に有料配付する、ということになり Vol.4 No.1 から実施することにした。しかし、Vol.6 から湯川記念館が発行主体となり、文部省の補助金は物理学会が申請し、会員には半額で配付することに変った。その後、三転して1953年には「理論物理学刊行会」が発行主体となり、物理学会での会計報告をもしなくなった。これらの関係から Progress の表紙に (1) Published by the Yukawa Hall with the cooperation of the Physical Society of Japan とか (2) Published for Research Institute of Fundamental Physics and the Physical Society of Japan などと印刷されてきた。
さらに、1955年にいたり、その方面の会員の希望を容れてProgressを購読する会員はJournalの配付を辞退することができるように定款が変更され1956年から実施された。
4) JJAPとの関係
Journalのページ数が増大するにつれ1960年頃から物理学会内部にJournalを2分冊にし、その1冊は applied physics にしてはどうかという案が真剣に検討され始めていた。これとは独立に同じ頃応用物理学会では邦文の機関紙「応用物理」のほかに欧文の応用物理の雑誌を是非持ちたいという機運が生じていた。そこで両学会が協力し合って一つの応用物理学の欧文誌を出そうということになり1961年に両学会から同数の委員を出し合って「応用物理学欧文誌刊行会準備委員会」ができ、何回もの会合を重ねて協議した結果「応用物理学欧文誌刊行会」を両学会の外に設け両学会から半数づつ運営委員および編集委員を出し合って Japanese Journal of Applied Physics (以下 JJAP とよぶ)を刊行することになり、刊行会は1962年1月から発足し、JJAP はその年の7月に創刊号を出すことができた。財政的には、固定経費は両学会折半、比例経費は引取部数の比で、分担金という名義で負担し合うという方式をとった。 JJAP の実際の出版の事務は日本物理学会が引受け、事務所も日本物理学会内におかれた。事務は編集部にだけ1人専任職員をおいたほかはすべて日本物理学会職員の手で行われた。海外への頒布も Journal の販路に乗って順調に延びていった。当初 American Institute of Physics が米国内での実需が500部に満たない場合はその差額を負担してもらうということもあってだいぶ助かったがこの補助も3年ほどで実需が500部をこえることになったのでその必要がなくなった。
応用物理学欧文刊行会の定款および細則の立案に当たっては私もその素案をつくって大いに協力した。1964年末に物理学会が複式簿記を採用するに伴い刊行会もこれにならって複式簿記を採用した。複式簿記に切換えてみると未収入金と備品が財産として残ってしまう。それの持主は誰かという問題が起った。というのはそれまで刊行会は両学会から赤字補てんの形で分担金を出してもらっていたので財産は持てないことになっていた。そこで、ここに現れてきた財産は両学会の「出資金」ということにし、その持分の計算は、応用物理学会推薦の会計委員の強硬な提案により固定的な部分(例えば備品など)は折半にし、比例的な部分(その主なものは売掛金)は引取部数の比で両学会に分けることになった。これは普通の意味の出資金とはだいぶ性質の異なったもので未収入金の金額などは年度末当日現在の状況によるもので不定のものであるため両学会の実質負担とは無関係に、また毎年流動的なものとなってしまった。これが永い間 JJAP の会計はさっぱり判らないと言われた所以で、両学会の理事会、委員会等で会計理事が説明するのに非常に困難を感じておられたことであった。この方式の不合理であることが確認されて1973年からこの方式を清算し、規則も改めて刊行会自身が財産を持てることにし、不足の場合は両学会から普通の意味での出資を求めることに切換えられた。
刊行会は、日本物理学会自身の都合(事務所および倉庫が手狭になったこと、物理学会自身の事務が増えて職員が JJAP の事務を兼任できなくなった)もあり1971年11月に事務所を移転し、専任職員も雇って名実ともに独立することになった。
5) Journalの長期対策
会誌は、1951年頃から投稿論文を受入れず依頼原稿だけにしたので財政状態とにらみ合せて出版規模を調整することができたがJournalは投稿論文数の自然増により膨張する一方であった。論文の長さの制限などをしてもあまり有効ではなかった。
Journalの出版ページ数(論文のみのページ数で)は1946年33ページ(Vol.1 1冊だけ)、1947年214ページ、1952年 652ページ、1957年 1,426ページ、1962年1,906ページ、と増加していった。1962年にJJAPが発刊されて一時増勢はとまったがすぐに延び率は上昇した。1967年からは年間のページ数が大きくなり過ぎ(2,954ページ)、年1巻では製本も困難になりhandyでなくなったので年2巻に変えた。Journalのページ数はこのように爆発的に増加し、急カーブで上昇しはじめた。これに反し、1966年に欧文誌の自由購読制が実施(それまでは会員は3種の物理欧文誌のうち少なくとも1誌は購読しなければならなかったが、この年からこの制限を外して全くの自由購読制をとった。)されてから会員の購読数は逆に減少の一途をたどるようになった。そこでこのままにしておいたら数年後には学会の財政は破綻してしまうだろうという見透しが立てられ、何とかしなければいけない、ということで1967年にJournal長期対策委員会が設けられ、Journalの将来あるべき姿とその財政的な裏付策とが検討された。2年間に亘り何回もの会議を重ね1967年夏には鹿沢温泉で合宿までして議論した結果、漸く結論を得たので1968年12月の委員会に報告された。(その要約は会誌23(1968)391(5号)に掲載されている。)その結論を要約すれば (1)一般にオリジナルな論文を掲載する第一次情報誌はそのVolumeの大きさと価格の高騰並びに複写技術の進歩によって、個人会員は買えなくなり(買う必要もなくなり)、図書館、研究室等に備えつけるためのもの(これを Library Journal と呼んだ)として残る。(2)一般会員向けにはそれらのアブストラクトを集めた二次的情報誌を配付する。(3)会員は、二次的情報誌を見て自分に必要な論文を知り、それの別刷を学会に請求する。学会はこれに適当な価格をつけて販売する。この場合予め自己の希望する分野を登録しておき、その分野の論文別刷は自動的に配付されるようにする案も出された。(4)上記だけでは速報が得られ難いのでLetter Journalを別に発行することも考える、というものであった。なお、Library journalの出版そのものも場合によっては不要となり、著者が提出した論文原稿を学会が保管しておき、そのタイトル(またはアブストラクト)だけを配り、テキスト希望者にはそのコピー(マイクロフィッシュ方式などによる)を売るという案まで出された。
この長期対策委員会の報告は、例の第33回臨時総会のすぐあとの委員会に出されたというタイミングの悪さと、学園紛争の勃発による研究停滞が原因と思われる投稿論文数の横ばいが始まったことによりその後現在に至るまで無視されてきた観がある。Journal長期対策委員会の見解は時代を先取りし過ぎたのかもしれないが、いずれ近い将来はそのような方向に向かうものと思われる。事実、既に米国では American Institute of Physics によってこれとほぼ同じ構想の出版体制が1972年から開始されている。
6) 日本の物理学界(会)の大合同の夢
日本の物理学界には戦後、Journal, Progress, JJAP, 日本物理学会誌、応用物理と三つの欧文誌と二つの邦文誌が出版されている。その出版元は日本物理学会、理論物理学刊行会、応用物理学会、応用物理学欧文誌刊行会の4団体となっている。
これらはそれぞれの歴史的状況において独自の生い立ちをもち、発展してきたものである。それぞれの創始者、並びにその後の維持者達はそれらを各々我が子のようにいつくしみ育てて来られた。それぞれ深い愛着の念を生じておられることは当然のことと思われる。
自然科学の純粋学術誌の需要には自らその限度があり、そうむやみに出版部数をふやすことができず、その台所は非常に苦しい。また1主体が1種の雑誌を発行するのと3種の雑誌を発行するのとでは手間、ひまや資金が3種の場合は3倍かかるかというとそんなにかける必要はない。校正などは明らかに3倍必要かもしれないが管理的な面や会計などはせいぜい2倍程度で済む。物理学関係の上記諸団体が一致協力して1箇の事務所で(大合同して1箇の団体になることができればさらに有効であるが)事務処理をすれば相当無駄が省け、経営の困難さも相当緩和される筈である。
雑誌の内容にしてもProgressとJournalの間、JournalとJJAPの間のダブりをなくして交通整理をすれば各々の雑誌の個性を今よりもっと鮮明に打ちだすことができる。
上記のようなことは私の在職中いつも念頭を離れなかった夢の一つであった。会員の方々の間にも同じような構想をお持ちの方が相当居られるよう見受けられた。
しかし、言うは易く、行うは難し、でこの夢の実現はそれほど簡単ではない。一番の難点は創始者、維持者の方々の感情であるのかもしれない。理性的に考えれば最も望ましい姿であろうと思うのに。
Letter 誌、abstract 誌などの必要性が強調され始めている現在、日本の物理学界として、これらはそれぞれ1箇の雑誌であることが望ましいし、経済的にもそうでなければ成立たないと思われる。ここらあたりから突破口が開けるかもしれない。
1) 年会 その1
年会、分科会などの学術的会合の開催は、機関紙その他の出版と並んで物理学会の二大事業の一つである。
1946年4月28日の設立総会と同時に第1回年会が東京大学において開催された。そのときの講演数は222題、6会場4日間という規模であった。第 2回は東大で224題、4会場3日間、第3回は京大で329題、3日間、9会場であった。このときから初めて地方で年会が開催された。この年会の際私が初めて京都に出張した。当時学会の財政が豊かでなかったため普通の旅館に泊れず京大物理教室の玄関脇の宿直室に1人で泊り自炊することになった。そのために京大の先生方から寝具まで借り、生れて初めて羽根ぶとんをかけて寝かせてもらうことになった。準備を済ませて明日の開会を待つばかりにして寝たが、それまでの疲労が重なっていた上に生来の神経質と初めての経験のため不安がつのって全然眠れず心悸亢進してついにダウンしてしまい翌朝になっても起き上れず、当時編集を手伝って下さっていた土方克法先生が学会に来ておられたので受付係を代ってやっていただき私は京大物理の先生方の御好意で京大病院に入院し年会が終ってから数日後に退院して帰京した。このときの京大の先生方の御芳情は今も忘れがたい思い出として残っている。
その翌年までは東京大学と京都大学とで交互に年会を開催した。1951年には大阪でも開催するようになった。年会を東京で 3年目に 1回、他の場所で2回という習慣がついたのは戦災の復興がだいぶ進んだ1960年頃からのことであった。
幻灯機がまだ普及しなかった戦後の十数年間は、講演者は大きな模造紙に数式や図を沢山書いて持ってこられたので会場係はビラ掛けへのセット、講演の変わる毎のビラ掛けの交換などに追われた。この風景は米国の Physics Today に米国物理学会のセクレタリー Darrow 氏が写真入りで紹介され日本独自のものとして珍しがられた。このT字型ビラ掛けは物理学会としては嵯峨根遼吉先生が考案され、その型式を永い間踏襲した。物理学会にはこのビラ掛けが60本以上もあった。もっともこれは組立式ではなかったため東京以外の地方に運ぶことは国鉄のコンテナー輸送が始まるときまでは不可能であった。その後これが次第にスライドにとって代られた。それもはじめのうちは幻灯機や暗幕、映写幕の数が少なく特定の会場(総合講演や特別講演、シンポジウム会場など)に優先的に使われた。物理学会では他の学会に比べて割合早く全会場スライド映写可能というふれこみで講演募集の会告をすることができた。物理学会ではこのために前述のリプリント会計から暗幕、映写幕、映写機を大量に買入れ、特に暗幕は3m平方の大きさのものを100枚以上持っているので、どこの大学で年会を開催しても全会場を暗くすることができた。暗幕を使い暗室にしてスライド映写を継続的にやることは本当は好ましい形ではないので昼光幕が考案されたが甚だ不完全なもので現在に至るまで暗室方式にとって代わる程のものが現れていないのはまことに残念に思われる。
戦後の数年間の年会などの受付での主な仕事は会費滞納者から会費を徴収することであった。会費滞納者の氏名を受付の周囲の壁などにはりめぐらし、それらしい会員が来られたら積極的に集めることに心掛けた。これが会員の顔と名前を覚えるのに大いに役立った。しかし、この仕事も1952年頃から講演予稿集をつくって会場受付で売る仕事が始まってからはやっておられなくなり、さらに1965年からは参加費(最初は300円)をとるようになったこと、さらには論文選集の販売などで受付風景は全く変ってしまった。
年会 その2
年会の規模は年毎に大きくなっていった。1952 年には京都会場で 6日間かかった。年会に6日間かけることはその後も永いこと続いた。1970年の東京学芸大学の際は会場数が少なかったせいもあって7日間もかかった。他の学会では普通会場数を多くして、せいぜい3日間で済ませているところが多かった。会員の年会に出張する旅費がかさんできたので物理学会としてもこの期間を短縮しようという機運が生じてきた。1971年の北大での年会の際現地の事情として4日間しかとれないという物理的な理由も加わって、20会場4日間(原著発表1,409題)で済ませることになり、以後年会4日制が確立した。私が物理学会を退職する直前の1973年度(第23回)年会は九州大学で、4 日間、23会場で原著講演数1,311、特別講演29、シンポジウム11箇となっていた。
原著講演数の増加するにつれ参加者数も飛躍的に増していった。年会における原著講演数と全会員数の比、参加者数と全会員数の比のいずれをとっても物理学会はいつも全学会中の最高のレベルにあった。このため会場数も、最近のように年会の期間を4日間に縮めたこともあって、二十数会場を必要とし、それも 200人程度入れる会場が10室程度必要となり、年会を一校だけで引受けてもらえる大学はだんだん少なくなってきている。
また、シンポジウムや特別講演の際は格別に多数の参加者が殺到するので300人以上収容できる室3~4室を特別講演、シンポジウム用として特に設ける必要が生じてきた。
米軍資金問題や学園紛争で大学を借りることが困難になった一時期に市内のホールとか公会堂とかを借りて開催してはどうかという議論もかなりあったがそのためには十数箇所の会場を借りてバラバラに行わねばならず、費用も莫大なものとなるので物理学会のように年会の規模が大きく、かつ財政がそれ程豊かでない学会では実現性の乏しい案であり、 また、 大学を避けて、これら市内の施設を使うことによって軍機関関係者の講演の問題から逃避しようとすることに対する反対論も強かったため、とうとうこのようなことは一度も実現しなかった。
年会、分科会の際に物理学会の特別の行事として Informal Meeting (以下 I.M. と略称)というものがある。他の学会ではせいぜい参加者全体を対象とする懇親会が有るに過ぎないが物理学会はそれ以外に多くのI.M.が持たれる。I.M. は研究グループの事務連絡、研究討論、懇親やそれらの混合した目的を持った会合であるが正規の年会、分科会のプログラムの外でグループの世話人が適宜企画して行うもので本来は学会としては責任を持たなくてよいようなものであるが、会場を正規のプログラムで行われる大学等の構内とすることが多いため、使用室の鍵の開閉、湯茶の接待、火の用心等そこの施設の持主に対してはどうしても学会が中に立って責任を持たざるを得ない場合が多いので放っておくわけにはいかない。そのため開催を引受けられる側としては正規の会合のための手配以上にやっかいなものとなる。特にその会合の出席者の食事の面倒を見ることは大変手数がかかる。 I.M. なるものがあるため会場側の担当者(最近は実行委員会をつくって当たっているが)が結局、朝は会場の始まる 1時間前から、夜は I.M. が終了するまで当直していなければならず大変な負担になる。最近 1~2年来この手数をなるべく少なくするために I.M. の食事の世話は一切しないという方式に漸時変ってきている。
年会 その3
しかし、I.M. の世話は一切やらぬ、つまりその開催をボイコットするということは物理学会としてはできない相談である。というのは物理学会自身がこれらの会合を公式的に利用しているからである。分科の世話人の選定、年会・分科会の開催分針、総合講演候補・特別講演の選定、シンポジウムの企画、さらには論文選集の候補などを世話人だけで決めることなく、これらの I.M. などを利用してなるべく各分野の研究者の広い範囲の意見を聞いた上で学会に持込んでもらうよう学会から依頼しているからである。これは物理学会の特異な体質の一つの現れであり、変更することの困難なものと思われる。
年会や分科会を開催するに当っては事務局と開催現地の実行委員会との間にその準備について種々綿密な打合せが必要であるが戦後の約10年ぐらいの間は私がそれを手紙で詳細に亘って手書きで通信していた。そうしているうちに大体準備要領のformulaができ上ってきたので「年会分科会等開催準備要領」と「アルバイターの仕事の内容と心得」という2冊の小冊子にまとめてタイプ印刷したものをつくっておき開催校が決まって、そこでの中心となる会員が決まった段階でこれをお送りして、それに則って準備を進めてもらうことにした。もっともこれは特務委員会や委員会など学会の公的機関に諮ってでき上ったものではなかったので、いわば事務局の私的文書であった。それが永い間支障なく行われてきたが、1971年の年会の際現地実行委員会との間で食い違いが生じ、改訂すべきであるということになった。その根本的な改正点は、現地実行委員会に相当大幅な権限を委譲し、実行委員会の採量で準備と実施を行うというにあり、それまで細大もらさず本部から指示していたこと、特に支出項目の制限などが撤廃された。そして、理事会を通した公式文書ということになった。また、この改訂に当って実行委員会の運営の仕方にA方式とB方式という二つの方法を規定し、現地の実情に応じてこのうちの一方式を選んでもらうことにした。A方式というのは少数精鋭主義といった方が判り易いようなやり方で、運営に当るのは委員長と幹事ぐらいで他は大学院学生などを準備の当初から雇ってサブマネージャーとして幹事の手足となって働いてもらう方式である。B方式はこういう形態のとりにくい場合に多数の会員がいくつもの部所に割当てられて合議制で運営していくやり方である。
いずれの場合も学会の事務局は単なるお手伝いとして1~2名派遣するにとどめるというものである。この改定前は年会には学会事務局から5~6名は必ず現地に出張してきた。これは経済的には確かに失費になるが職員は多数の会員に接することができ、特に現地の状況などもよく知ることができて爾後の事務処理に大いにプラスとなったことは否めない事実である。
2) 分科会
分科会はもともと自然発生的なもので開催方針なども全く異なっていて差し支えない。事実物理学会発足の当初はそのとおりであった。しかし設立後数年経ってからは年会とそれ程ちがったものではなくなった。年会には総合講演と会員懇親会があるが分科会にはそれがない。年会は一大学または同地区の二、三の大学を会場とするが、分科会は会場を異なった二、三の地区で行っている。予稿集の原稿提出時期が年会は申込と同時であるが分科会は約一ヶ月おそい。講演時間の長さに多少のちがいがある。post dead line paper を認めることがある、などが相異点であるが会員にとっては年に2回研究発表の機会があるという点では殆ど変ったことはない。事務局にとっては年会よりも分科会の方が連絡する相手が多くなり、出張の度数も多くなって手間がよけいかかる。
分科会は、ある年は思い切ってシンポジウム形式だけとし、次の年は原著発表だけにするとかいったことはできないものであろうか?原著発表の機会は年に1回あれば十分だという意見と分野の性質によっては少なくとも2回は是非必要だという意見とがある。議論しているよりも果敢に実行してみては如何であろうか。また、年会にしろ分科会にしろ講演数は今後増大するばかりでそのうちに収容しきれなくなる。講演数を制限することは好ましくないとしたら分科会を細分してパラレルセッションを設け50~100人程度の室でも使えるような方法を論ずる必要も生じてくるであろう。
3) 国際会議 その1
日本で物理学関係の国際会議が最初に開催されたのは1953年の理論物理学国際会議であった。この国際会議は日本学術会議が主催したもので物理学会は共催団体であったが脇役しか果たさなかった。東大安田講堂での開会式の手伝い、歌舞伎座での観劇会の世話(平田森三先生と共に招待客の座席の割当てを行ったことを覚えている)などをやったほか物理学会主催でノーベル物理学賞受賞者の Mott, Slater, Wheeler 三博士の特別講演会を東大安田講堂で開催した。このときの講演謝礼に現金では失礼であるからというので役員の先生方が手分けして適当な土産物を探すのに苦労された。
1961年には国際宇宙線地球嵐会議と国際磁気学・結晶学会議が開催された。このときも学術会議が主催で、前者は物理学会、地球電磁気学会などが共催、後者は物理学会、結晶学会が共催した。この両国際会議は同じ年の9月上旬と下旬に行われたのでそのための募金は一本で行うことになり物理学会の中に募金委員会を設け茅誠司先生を委員長として募金計画と募金の実務を行った。集めた資金は両国際会議で折半することにした。
この募金を行うには先ず東京都の許可が必要であり、また募金がスムーズに行われるためには寄付する企業にとって寄付金が免税されることが重要であることから大蔵省に「指定寄付」の申請をする必要があり、そのために尨大な資料が必要であることを身をもって体験させられた。
この両国際会議では単に募金事務だけでなく、会場である京都市京都会館に出張して受付のお手伝いもした。 また、 これらの国際会議のプロシーディングズを物理学会が出版することになった。これが国際会議のプロシーディングズの出版を物理学会が引受ける最初の機会となった。それらは Journal の supplements として、Journal の販路にのって主として外国に頒布された。宇宙線・地球嵐の方は1,000部しか印刷しなかったためすぐ売切れとなってしまった。磁気・結晶の方は 2,000部刷ったが2年ぐらいして1,500部程度までは捌けたと思う。磁気と結晶の Joint Meeting の分冊は特に売れ行きがよかった。いずれにしても物理学会の財政にとってはプラスになった。もっとも出版を引受けるに当っては国際会議組織委員会側で固定経費を支弁してもらうことを当時の鳩山委員長が主張されそれが引受けの条件となった。この方針はその後も引継がれた。
この「宇宙線・地球嵐」、「磁気学・結晶学」両国際会議に協力したことによって物理学会に国際会議を主催する力が十分あることが確証され、その後格子欠陥国際会議 (1962年)、半導体国際会議 (1966年)と相次いで本会が単独で主催することができた。といっても、国際会議を開催することがいともたやすいというわけではなかった。特に資金面においては実行委員会、募金委員会にとっては非常な苦労が伴う。格子欠陥国際会議のときは本会にとって単独主催は初めての経験であり、委員会での不安の声もあったが組織委員長藤原武夫先生は委員会の席上で御自身の身体をはり、全財産をなげうってでも学会に損失はかけられないと明言されて物理学会単独主催を承認してもらった程であった。幸い、藤原先生御自身の東奔西走により所期の募金を達成され無事盛会のうちに会議を終えることができた。
国際会議 その2
半導体国際会議は物理学会単独主催の国際会議として第2回目であり、武藤俊之助先生を組織委員長とし、鳩山道夫先生を実行委員長として会議自体はその準備も進行も実に見事に進められ成功裡に終了した。プロシーディングズの出版も会議当日に著者校正してもらうほどに進められ、当年12月には出版されるという手際のよさであった。しかし、資金面では米軍資金導入という事件が起き、翌年9月9日に、会員544名の申入れにより第33回臨時総会が開催され、四つの決定案のうち第4決議案(関係者の処分問題)を除いて可決された。そのうちの決議3「日本物理学会は今後内外を問わず、一切の軍隊からの援助、その他一切の協力関係を持たない」により、その後この決議に従って物理学会を運営するための方針を決めるために長期間、巨大なエネルギーが費やされた。特務委員会および委員会は数年間この問題の検討で明け暮れた。特に臨時総会直後の伊藤順吉先生を委員長とする委員会、翌年の小林稔先生を委員長とする委員会の頃は委員会の審議が長びいて機械振興会館の裏門の門限午後11時を過ぎてしまったことも度々であり、特務委員会などは月1回の定例日だけでは足りず日曜日に開催したことも度々であった。それらの度重なる審議の結果物理学会のとるべき方針は学術的会合での軍機関関係者の問題を除いては一応まとまった。(「臨時総会の決議3を実施するための方針について(訂正)」-会誌24(1969)497参照) 学術的会合と軍機関関係者の問題は次の西川委員会においても結論を出し難かったので全会員にアンケートしたが、種々の意見があって一方的な結論を出すことができなかった。(アンケート「決議3と学術的会合のあり方に関する報告書」-会誌26(1971)161参照)
それで 現在に至るまで軍機関関係者から講演の申込みがあった場合はその都度委員会に諮ってその処置を決めてきた。これまでのところ講演申込者にお願いして講演を辞退してもらうという解決方法しかとれなかった。
事のよしあしは別問題としても私自身米軍資金導入に直接関与しなかったとはいえ、それを知っていて委員長に報告することを怠った点は職務怠慢のそしりを免れることはできず臨時総会直後の伊藤委員長にも進退伺いを出したが、ここに改めて皆様にお詫び申上げる次第である。
半導体国際会議以後も1973年までに物理学に関係ある国際会議は、核構造、レオロジー、統計力学、強誘電体、質量分析、低温物理、量子エレクトロニクス、フェライト、真空紫外、X線光学とマイクロアナリシス、液体金属、核モーメントと核構造、電子線およびガンマ線による核構造、結晶学、固体表面物理、真空等があった。それらの国際会議のそれぞれの事情により、物理学会の国際会議に対する方針ともかね合って物理学会が主催したり、共催したり、後援または協賛したり、また全く関与しなかったりと、さまざまであった。
プロシーディングズの出版にしても物理学関係のものは全部引受けることが望ましいと我々が思っても、「物理学会の方針」という壁があるのでそれも難しい状態にあるようである。また、プロシーディングズ出版の会計は、固定経費の組織委員会負担という方針を核構造国際会議のそれからはとりやめ、せいぜい組織委員会が買上げる分の代金(一般売価よりは相当に割引された直接原価に近い値段)を受取るという一般に行われている商習慣に従った方針に変更されたので、必ずもうかるというわけにはいかなくなった。(つづく)