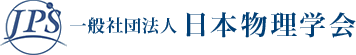言語 : English
第30回(2025年)論文賞授賞論文
本年度の日本物理学会第30回論文賞は論文賞選考委員会の推薦に基づき、本年1月18日に開催された第711回理事会において次の5編の論文に対して与えられました。
授賞理由及び選考経過報告
授賞理由及び選考経過報告の著作権は日本物理学会に帰属します。HP等にご転載をご希望の場合は、日本物理学会事務局・論文賞担当(ronbunsho-s@jps.or.jp)までお問い合わせください。
| 論文題目 | Exponential Speedup of Quantum Annealing by Inhomogeneous Driving of the Transverse Field |
|---|---|
| 掲載誌 | J. Phys. Soc. Jpn.87,023002(2018) |
| 著者氏名 | Yuki Susa, Yu Yamashiro, Masayuki Yamamoto, and Hidetoshi Nishimori |
| 授賞理由 | 量子アニーリングは、日本発の量子計算の新技術として、特に最適解の求解が困難とされる組合せ最適化問題の高速解法の観点から大きな注目を集めている。この方法は、著者のグループ等が提案した独創的な方法であり、すでに商業的にも実装され多くの問題に適用されている。この方法は、強い横磁場をかけた状態での自明な基底状態から、徐々に横磁場を減じて、最適解を断熱的に求めるものであるが、その過程においてレベルクロスがある場合この方法は適用できず、また1次相転移に相当する準位の擬交差がある場合には断熱変化が実際上困難になる。この問題は量子アニーリングの最重要問題であり、多くの研究が続けられてきた。本論文では、少し特異なモデルではあるが、量子アニーリングにおいて量子1次相転移を示す簡素で典型的かつ数理的解析が容易な模型として、多体相互作用する平均場Ising模型を取り上げ、その相図上で一次相転移の端点(臨界点)の迂回が制御外磁場の空間的に不均一性な操作で可能であることを発見し、実際に回避する具体的手法を示した。この成果は、この種の問題に関する重要なブレークスルーを与え、本論文の結果に基づき、実機の量子アニーリングにおいて多数のプロトコルの構築が試みられている。本論文の結果は量子アニーリングの分野を進展させる端緒となり、また当該分野に留まらず物理学諸分野からも高い関心が寄せられている。以上より、本論文は日本物理学会論文賞にふさわしい。 |
| 論文題目 | Orbital Magnetism of Bloch Electrons I. General Formula |
|---|---|
| 掲載誌 | J. Phys. Soc. Jpn.84,124708(2015) |
| 著者氏名 | Masao Ogata and Hidetoshi Fukuyama |
| 授賞理由 | 遍歴電子の外部磁場応答である軌道磁化率は、基本的かつ重要な物理量であり実際に測定可能であって、その研究の歴史は長い。本研究の基礎となるグリーン関数による簡潔で一般的な軌道磁化率に対する公式は、著者の一人によって1971年に発見されている。その一方で、特に結晶の周期場の効果を考慮した多バンド系のブロッホ状態に関する軌道磁化率は、近年新しい視点から多くの興味を集め、研究が進展している。本論文では上記の簡潔な公式をブロッホ波動関数で表現することで遍歴電子の軌道磁化率を詳細かつ見通しよく検討した。その結果、軌道磁化率には(1)ランダウ・パイエルス磁化率、(2)バンド間行列要素の寄与、(3)フェルミ面からの寄与、(4)占有状態からの寄与、以上の4種があることを明示的に示し、各項の物理的な意義を明らかとすることで新しい知見を得るとともに、他の研究との整合性についても議論し包括的な理解を与えた。本論文の結果は、遍歴電子系の軌道磁化率に関して、将来の理論研究の発展に見通しの良い基礎を与えるとともに、関連分野での理論、実験研究を活性化すると期待され、日本物理学会論文賞にふさわしいと考えられる。 |
| 論文題目 | Chiral Soliton Lattice Formation in Monoaxial Helimagnet Yb(Ni1-xCux)3Al9 |
|---|---|
| 掲載誌 | J. Phys. Soc. Jpn. 86, 124702 (2017) |
| 著者氏名 | Takeshi Matsumura, Yosuke Kita, Koya Kubo, Yugo Yoshikawa, Shinji Michimura, Toshiya Inami, Yusuke Kousaka, Katsuya Inoue, and Shigeo Ohara |
| 授賞理由 | 「カイラリティ」はケルビン卿が提案した古くから知られる概念であるが、近年様々な物質におけるカイラリティとそれに関連する現象が、物質科学において注目を集めている。カイラルな結晶では、ジャロシンスキー守谷相互作用の効果で非自明な磁気秩序構造が発現し、スキルミオンとカイラルソリトン格子がその代表例である。後者は遷移金属磁性体のCrNb3S6がその例として知られるが、f電子系がつくるカイラルソリトン格子は実証されていなかった。 本論文は、磁化測定からカイラルソリトン格子の存在が示唆されていた重い電子系物質Yb(Ni1-xCux)3Al9に対し共鳴X線散乱実験を行い、f電子系におけるカイラルソリトン格子の存在を初めて実証した研究の報告である。共鳴X線回折の磁気反射を用いるユニークな手法で、結晶の左右掌性の違いでらせん磁気構造の回転の向きが変わることや、磁気反射の高調波成分の増大を観測し、f電子系のカイラルソリトン格子の存在を実証しただけでなく、d電子系のそれとは異なる性質を有することも明らかにした。これらの研究成果は、結晶のカイラリティが生み出すカイラル磁気構造の系統的研究の端緒をなすものであり、物理学におけるカイラリティ研究への貢献が期待される。よって本論文は、日本物理学会論文賞に相応しいと認められる。 |
| 論文題目 | The mean square radius of the neutron distribution and the skin thickness derived from electron scattering |
|---|---|
| 掲載誌 | Prog. Theor. Exp. Phys. 2021, 013D02 |
| 著者氏名 | Haruki Kurasawa, Toshimi Suda, and Toshio Suzuki |
| 授賞理由 | 原子核内の陽子と中性子の密度分布を求めることは、原子核物理学分野のみならず、宇宙物理分野においても重要な課題である。 特に、中性子過剰原子核では、中性子分布半径と陽子分布半径の差から生じる「中性子スキン厚」は、中性子星の半径や最大質量を決める中性子物質の状態方程式を決定する鍵となっている。 原子核内の陽子密度分布に関しては、電磁相互作用による「電子散乱」を用いて高精度で決定することが可能となっている。一方、中性子密度分布に関しては、原子核反応による測定がなされてきたが、その密度分布を引き出すには、理論による模型依存性が強く信頼性が低かった。本論文では、中性子分布が電子散乱で得られる電荷密度分布の4次モーメントに敏感であることを指摘し、電子散乱による中性子分布半径を模型依存性の少ない手法で引き出すことを世界で初めて示したものである。模型依存性の少ないスキン厚の導出を切り拓いた画期的な論文であり、原子核物理分野のみならず、宇宙物理分野の研究の発展にも幅広く貢献するものとして日本物理学会論文賞に相応しい業績であると認められる。 |
| 論文題目 | Global inconsistency, 't Hooft anomaly, and level crossing in quantum mechanics |
|---|---|
| 掲載誌 | Prog. Theor. Exp. Phys. 2017, 113B05 |
| 著者氏名 | Yuta Kikuchi and Yuya Tanizaki |
| 授賞理由 | 場の量子論におけるアノマリーは古典論における対称性が量子化によって破れる現象として知られるが、より広義には、大域的な変換に対応する外場を導入した際の系の応答がエネルギースケールによらないという条件(トフーフトのアノマリー釣り合い)を通じて低エネルギー有効理論がもつべき条件を与え、理論のダイナミクスを調べる手掛かりとしても用いられる。本論文は、この考えをさらに進めた「大域的矛盾」に関するものである。量子色力学のθ角のような理論のパラメターを変換した際にアノマリーがある場合、低エネルギー、特に真空構造に関する制限に結びつく可能性がある。本論文は、これを具体的解析が可能な量子力学の模型を使って解き明かしたもので、新概念を切り開く先駆的な研究である。 |
選考経過報告
第30回論文賞選考委員会*
本選考委員会は2024年6月の理事会において構成された。日本物理学会論文賞規定に従って、関連委員会等に受賞論文候補の推薦を求め、10月末日の締め切りまでに16件15編の論文の推薦を受けた。15編のうち5編は昨年も候補として推薦された論文であった。推薦された15編の論文については、選考委員を含む計のべ30名に閲読を依頼し、すべての閲読結果の報告を選考委員会までに得た。
選考委員会は2024年12月17日に開催された。昨年に続きオンラインで開催され、12名の委員全員が参加し、受賞候補論文の選考を進めた。論文賞規定に留意しつつ、提出された閲読結果に基づき各論文の業績とその物理学におけるインパクトの大きさと広がりについて詳細に検討した。その結果、上記5編の論文が第30回日本物理学会論文賞にふさわしい受賞候補論文であるとの結論を得て理事会に推薦し、2025年1月の理事会で正式決定された。また、選考対象論文には最近出版され、今回の受賞には至らなかったが、今後さらに評価が高まることが期待されるものが見られたことを付記する。
第30回論文賞選考委員会*
委員会委員メンバーは表彰式後に公開