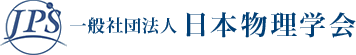第6回(2025年)米沢富美子記念賞の受賞者を以下の3名に決定しました。
第6回(2025年)米沢富美子記念賞の受賞者を以下の3名に決定しました。
授賞理由及び選考経過報告
授賞理由及び選考経過報告の著作権は日本物理学会に帰属します。HP等にご転載をご希望の場合は、日本物理学会事務局・米沢富美子記念賞担当(yonezawasho-s@jps.or.jp)までお問い合わせください。
※50音順/敬称略
| 氏 名 |  桂川 美穂(かつらがわ みほ) |
|---|---|
| 所属先 | 京都⼤学⼤学院理学研究科・助教 |
| 業績名 | 宇宙硬X線観測技術にもとづく分野横断的研究と加速器実験への展開 |
| 授賞理由 |
桂川美穂氏は、宇宙X線観測衛星のために開発された硬X線検出器を非破壊元素分析やがん治療など全く異なる分野に展開して、新たな境地を切り開いている。この検出器は、CdTe半導体を用いたイメージング素子であり、X線のエネルギーとその入射位置を正確に求めることができる。 負の電荷を持つミュオンを用いた非破壊元素分析では、負ミュオンのビームを対象物に打ち込み、原子核に捉えられたミュオンが出す特性X線を観測して元素を同定するが、今まで元素の位置はビームの大きさでしかわからなかった。桂川氏は広い面積に高い強度のビームを照射し、衛星用に開発された検出器技術を応用し、コリメータと組み合わせてX線の発生位置分布を撮像し、短時間で特定の元素の2次元の位置分布を約1mmの分解能で測定できるようにした。ミュオンのエネルギーによって深さも選べるため、3次元で特定の元素の位置分布がわかる。これは画期的な技術であり、すでにリチウムイオン電池の調査など産業面での応用も始まっている。 がん治療では、投与した薬剤から放射されるX線の発生位置分布を測定することにより、その薬剤がどの程度目標とする腫瘍に取り込まれているかを撮像できるようにした。マウスを使って実証した成果は医学部や薬学部の研究者、製薬会社にも注目され、すでに複数の共同研究が立ち上がっている。 このように、桂川氏は検出器開発の優れた能力と宇宙観測用の測定器を活かし、異なる分野の人と協力して今まで見えなかったものを可視化し、新たな世界を切り開いている。また今後、異分野融合研究のみならず、新たな分野や研究を創出することも期待できる。以上のことから、桂川美穂氏は米沢富美子記念賞の受賞に値する。 |
| 氏 名 |  冨田 夏希(とみだ なつき) |
|---|---|
| 所属先 | 京都大学 理学研究科 物理学・宇宙物理学専攻・助教 |
| 業績名 | 光ビームによるハドロンの質量起源の研究 および 大面積高時間分解能検出器の開発 |
| 授賞理由 |
冨田夏希氏は、η'中間子原子核の束縛状態の探索実験で顕著な業績を上げている。この実験は、原子核内でのη'中間子の質量変化を通してハドロンの質量生成機構の解明を目指したものである。冨田氏はSPring8-LEPS2において、光ビーム(ガンマ線)を炭素核に入射してη'中間子原子核の生成を試み、生成後に放出される陽子とη'中間子を同時測定するという手法を導入してバックグラウンドを劇的に低減させ、将来の高統計実験による探索の道を拓いた。 この実験で鍵となった実験装置の一つが、大面積かつ高時間分解能を達成したResistive Plate Chamber(RPC)である。冨田氏の第二の業績は、この高性能なRPCの開発である。大強度ハドロンビームや光子ビームの実験では、大立体角を覆い、同時に高い時間分解能を持つ検出器の開発が喫緊の課題で、RPCはその候補の一つであったが、大面積化と高分解能化の両立が難しいとされていた。冨田氏は大面積RPCの開発にゼロから取り組み、さまざまな課題を解決して、大面積RPCとしては世界最高時間分解能を持つ検出器の開発に成功した。同検出器は、η'中間子原子核探索実験での成功を受けて、J-PARC, LEPS2だけでなく海外の主要研究所での採用も決まり、その可能性が大きく広がることとなった。冨田氏は、さらに、次世代RPCの共同開発チームのリーダーを務めるなど、RPC検出器についての国際的な第一人者として認知されている。 以上のように、η'中間子原子核観測の可能性を大きく切り拓いたこと、および素粒子・原子核実験で標準検出器となるような高性能RPC検出器の開発を行い、さらに、今後も、その開発を国際的レベルで牽引していることから、冨田夏希氏は米沢富美子記念賞に値する。 |
| 氏 名 |  中村 祥子(なかむら さちこ) |
|---|---|
| 所属先 | 九州大学 理学研究院 物理学部門・准教授 |
| 業績名 | 非線形テラヘルツ分光による新奇な超伝導ダイナミクスの研究 |
| 授賞理由 |
中村祥子氏は、低温実験技術とテラヘルツ分光技術とを組み合わせることにより、超伝導ヒッグスモードの観測が可能であることを実証し、その観測手法の新たな境地を切り開いている。 超伝導ヒッグスモードとは対称性の破れに付随しておきる集団励起のことで、従来はテラヘルツ波との非線形光学応答を介して行っていたため実験的な制約が大きく、対象となる超伝導体が限られていた。中村氏は、超伝導電流注入下においてテラヘルツ波との線形結合を用いることで観測を可能とし、この技術により、より広範な超伝導体への展開が期待できる。 さらに中村氏はこの手法を応用することで、クーパー対の相関距離が平均自由行程よりも十分に長いような汚れた極限の超伝導体NbNにおいてテラヘルツ波の第2高調波が発生することを見出し、その起源が磁束量子の運動によるものであることを明らかにするとともに、その質量を決定する独自の手法を提案した。また、鉄セレン系超伝導体FeSe0.5Te0.5にこの手法を拡張することで、それまでの理論予測に反しクリーンな超伝導体においても磁束コアの質量は電子質量と同程度であることを明らかにしている。このことは、超伝導体における超高速ダイナミクス、とりわけ超伝導破壊メカニズムの解明に重要な役割を果たすと評価できる。 このように、中村氏は自身の低温物理学と光物性の両方の専門性を活かすことにより物性物理学の発展に貢献しており、米沢富美子記念賞の受賞に値する人物である。 |
第6回(2025年)日本物理学会 米沢富美子記念賞選考経過報告
日本物理学会第6回米沢富美子記念賞選考委員会 * 2024年5月の理事会で第6回米沢富美子記念賞の選考委員会委員10名が決定された。同年7月9日より領域・支部等に受賞候補者の推薦を求め、10月31日の締め切りまでに9名の推薦を受けた。昨年までの選考委員会から繰り越された3名を加えた12名の候補者の各々について10名の委員が推薦書、業績リスト、主要論文の閲読を行い、閲読結果を選考委員会内で共有した。2024年12月23日の選考委員会では10名の選考委員により受賞候補者の選考を進めた。各候補者について、研究業績の卓越性、インパクトの大きさや将来の展望、候補者の貢献度について詳細に検討を行った。加えて、物理学教育・アウトリーチ活動の状況や本会活動への貢献などについても検討した。慎重に議論を進めた結果、上記3名の候補者が第6回米沢富美子記念賞の授与にふさわしいとの結論を得て理事会に推薦し、2025年1月の理事会で正式決定された。2022年以降候補者は年々増えており、今後とも、多くの優れた女性研究者の推薦・応募を期待する。
*第6回米沢富美子記念賞選考委員会の構成員は表彰式後に公開予定