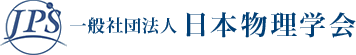2017年度 世田谷区中学生講座(新・才能の芽を育てる体験学習:サイエンス・ドリーム)
世田谷区教育委員会主催、日本物理学会協賛の「世田谷区中学生講座(才能の芽を育てる体験学習:サイエンス・ドリーム)」では、世田谷区立中学校の生徒を対象に、物理や科学に対する驚きや楽しさを体感してもらうことを目的として、普段の授業では体験できない実験や施設の見学などの連続講座を行っております。
昨年まで10月~12月に3回連続講座として開講していた「才能の芽を育てる体験学習 サイエンス・ドリーム」を、より参加しやすいように2回の独立講座とし、さらに開催時期を1学期終了直後にした「新・才能の芽を育てる体験学習 サイエンスドリーム」として開催しました。今回も大学1年生が実験授業で使用する設備をそのまま利用して、光に関係する以下の2テーマを取り上げました。
お問合せ先 : 世田谷区教育委員会事務局 生涯学習・地域・学校連携課
TEL : 03-5432-2739
新・才能の芽を育てる体験学習「サイエンス・ドリーム」(全2回)
| 会場 日時 |
国立大学法人 電気通信大学 第1回 7月25日(火)13:30-16:30 (参加者10名) 第2回 7月26日(水)13:30-16:30 (参加者10名) |
|---|
第1回 7月25日(火) 「光を分けてみよう!」
回折格子を用いて、水素のスペクトル線を観測し、その回折角から波長を求めました。ピント調節やスリット幅変更のネジ、多くの固定・解除用のネジの操作を駆使する分光器の扱いは、多くの参加生徒にとって初めてで、大変で、良い経験になったようです。回折角から波長を求めるためには、三角関数の値を知る必要がありますが、まだ学習していません。そこで、あらかじめサイン関数をプロットしたグラフを用意し、そこから読み取ることにしました。この作業も、多くの生徒が初めてだったようです。最後に、観測した紫・青・赤色の波長が、バルマー系列の式から計算できることも学びました。


----------------------------------------------------------------------------------
第2回 7月26日(水) 「光の速さを測ってみよう!」ものの速さを測るには、移動した距離をその移動にかかった時間で割る方法が、おそらく最もわかりやすい方法でしょう。しかし、光のように、1秒間で地球の周りを7周半も進んでしまうものの速さを、同じ方法で測れるでしょうか。この実験では、レーザー光を小さな塊(パルス)にして、数メートル先のプリズムで反射させて戻ってくるまでの時間を光検出器とオシロスコープを用いて計測します。光の進む距離はおよそ往復6メートル程度で、往復にかかる時間が20ナノ秒程度であることを、全員確認できました(2人1組の実験です)。光学系の調整やレーザー光を連続光からパルス光に変えるための変調電圧の調整など、分光器同様にアナログ的操作が大変だったようです。




両日とも休憩時間に、「電子顕微鏡の観察体験」(第1回)、「液体窒素に触れてみよう」(第2回)を企画しました。最近は一部のレストランで使用するほど身近になった液体窒素ですが、実際に手で触れる経験は新鮮だったようです。