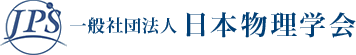会誌Vol.69(2014)「新著紹介」より
このページでは、物理学会誌「新著紹介」の欄より、一部を、紹介者のご了解の上で転載しています。ただし、転載にあたって多少の変更が加わっている場合もあります。また、価格等は掲載時のもので、変動があり得ます。
写真で読み解く 雷の科学
音羽電機工業株式会社編,横山 茂,石井 勝著
オーム社,東京,2011,111p,21×15 cm,本体1,800円[一般向]ISBN 978-4-274-50354-2
紹介者:新藤 孝敏(電中研)
昔から,「地震,雷,火事,親父」と言われるように,雷は怖いものの代表である.実際,雷が鳴ると雨戸やカーテンを閉め,家の中に閉じこもる人も多いであろう.その一方で,自然現象としての雷の壮大さや美しさに魅せられた隠れファン(?)も実は少なくない.
そのような雷に魅惑された人たちのために,音羽電機工業株式会社では数年前から雷の写真コンテストを開催しており,毎年,受賞した数件の作品はホームページなどで紹介されている.評者は,いつかそれらをまとめてもらえないかと思っていたが,本書は,まさに雷写真コンテストの集大成と言える待望の書である.さらに雷の写真のみならず,我が国を代表する雷の研究者で,世界的にも著名な横山,石井の両氏による解説が加えられており,学術的にも充実したものとなっている.
第1章では「雷写真コンテスト傑作選」として,上記の雷写真コンテストで入賞した作品のうち,特に傑出した写真が紹介されている.それぞれの写真には,「稲妻,都を走る」,「針立雷」,「50年目の落雷」など,写真にふさわしいタイトルとともに短い解説がつけられている.肉眼では「あ,雷が落ちた.」ということは分かるが,どこに落ちたかは良く分からない場合がほとんどであるが,写真はその一瞬の現象を切り取り,我々の眼前に生々しく示してくれるので実に有難い.まさに建物の避雷針に落ちている雷,同時に複数の場所に落ちている雷,大空を縦横無尽に駆け回る雷,夏の風物詩である花火と雷の共演など,ただ写真を見ているだけでも,千変万化する雷の姿に目を奪われ,思わずページをめくってしまう.また,大地への落雷のみならず,火山爆発に伴って起こる雷や,雷雲の上部から宇宙空間へ向かって伸びる雷など,普段はまず見ることのできない写真も数多く載せられており,興味は尽きない.
第2章では,「雷写真にみる学術的考察」として,雷写真コンテストの入賞作品をもとに,雷現象について解説がなされている.「学術的考察」と,ややいかめしいタイトルではあるが,その内容は,雷の写真から,その雷がプラスの極性の雷なのか,マイナスの極性の雷なのか,また,その写真に写された雷が生じるまでに,どのようなプロセスがあったのかなどを,最新の知見に基づき分かりやすく説明しているものである.もとになるのは静止写真であるから,雷のほんの一瞬を捕えたものにすぎない.しかし,その一枚の写真からその雷現象についていろいろな事実が明らかにされていく様子は,あたかも名探偵シャーロック・ホームズが現場に残されたわずかな手がかりから事件の謎解きをするのを聞いているようである.また,この章の解説には,専門の研究者にとっても,示唆に富む内容が多く含まれており,雷研究を志す者にとっては必読の書である.
雷や写真に興味のある人はもちろん,そうでない人も本書を手に取って,自然の造形美を楽しんで戴ければ幸いである.
(2014年7月20日原稿受付)
伏見康治コレクション1;紋様の科学
伏見康治コレクション2;ふりこの振動を追って
伏見康治著,江沢 洋解説
日本評論社,東京,2013,vi+366p,22×16 cm,本体5,400円[広い読者向]ISBN 978-4-535-60346-2
日本評論社,東京,2013,vi+304p,22×16 cm,本体4,500円[広い読者向]ISBN 978-4-535-60347-9
紹介者:並木 雅俊(高千穂大)
中学生の頃,『ガモフ全集』*1に夢中になったことがある.伏見先生は,この全集のうち4つの巻を訳された.第4巻『原子の国のトムキンス』の訳者あとがきに,「背伸びをしてようやく学者の仲間に入れてもらっている人びととちがって,完全に対象を自家薬籠中のものにしている大家であって,初めてできる芸当ですが,それにしてもだれにもわからせ,そして笑わせるガモフの手腕というものは,まったく真似のできない独自なものです」とある.伏見先生の本からは,ガモフにみられるアクロバティックさは感じられないが,これら2冊も,物理を自家薬籠中とした大家の書である.
『紋様の科学』は,『数学セミナー』に1967年5月号から1969年12月号のうち30回にわたって連載されたものを江沢洋先生が編集・解説をした書である(この期間,伏見先生は名古屋大学プラズマ研究所所長であった).本書も連載回数と同じ30の章からなる.
連載執筆の動機は「日本の伝統のなかから,紋様の科学の素材となるものをできるだけ拾い出すということにあった」.ここで科学の素材とは,群論を指している.その動機の通り,群論を用いて紋様を一般的・体系的に論じている.書名を「紋様」としてあるが,帯模様,彩色模様,すだれ模様,それに寄せ木細工などの和模様の多くを論じている.導入部に「紋とは点対称をもつ幾何学図形である」と定義し,n割り回転対称性,応用としてヘキサモンド(伏見先生はヘクサモンドとしている)や紋の対称性を述べ,素朴な疑問から発展させており,読者をうまく導いている.エッシャーや錯視も題材とし,ロゲルギストのような雰囲気もあり,十分に楽しめる.
『ふりこの振動を追って』は,『数学セミナー』に1974年5月号から1977年2月号まで連載されたものを江沢先生が編集し,解説をした書である(伏見先生は,1977年より1982年まで,日本学術会議会長であった).25の章(本文268頁)からなり,すべてふりこである.波動とのつながりである連続体の振動もない.「むだな道草をくったり,駄弁を弄したりという方ががらに合っている」とあるように,ゆっくりとふりこを語っている.
ふりこを表現するのによく使う「伸びない糸」という仮定はよい近似なのか,「ぶらんこ」の振幅を大きくしていくにはどうすればよいのか,「連成ふりこ」におけるエネルギーの授受,竿灯の安定化と「逆立ちふりこ」,「ふりこ時計」のエネルギー補給条件などをゆっくりと議論している.また,「料理され,抽象化されたものばかり教えられた人間は,非常に単純なものの考えしかできなくなる」など,伏見先生の人生論や教育論をも垣間見ることもできる.
これら2冊の本から,伏見先生の発想の豊かさ,思考の深さ,それに物理が好きであることが伝わってくる.多くの物理屋に薦めたい本である.
(2014年6月22日原稿受付)
*1 全13巻と別巻3からなり,邦訳は1950年に出版され,以後何度か改訂版がだされた.主人公トムキンスを光速度cが小さな世界やプランク定数hが大きな世界に旅させ,相対論的効果や量子論的効果を描写し,読者を魅了した.
放射線計測ハンドブック(第4版)
G. F. Knoll著,神野郁夫,木村逸郎,阪井英次訳
オーム社,東京,2013,x+868p,26×20 cm,本体28,000円[専門~学部向]ISBN 978-4-274-21449-3
紹介者:荻尾 彰一(大阪市大院理)
本書は,初版が1979年(訳書は1982年)に出版されて以来,放射線計測技術の向上に合わせてほぼ10年ごとに改訂が続けられ,2013年に改訂第4版の訳書が出版された.評者の研究室には第2版があり,勤務校の図書館には全ての版が収められているなど,これまでもしばしば手に取ってきた親しみのある参考書である.
放射線計測技術についての「ハンドブック」,というよりは「大事典」というおもむきの本書は,放射線検出の原理から広範囲の関連技術について網羅的に集録する大著である.しかしだからこそ,特定の検出方法とその応用についての完全な説明を本書に求めてはいけない.例えば,第9章「光電子増倍管と光ダイオード」では,光電子増倍管の動作原理,基本特性と応用上の注意についてとても多くの記述があるが,それでも,応答の光入射角依存性,温度等周辺環境の影響,諸特性の測定法,などについての記述は見当たらない.ある検出技術に精通した研究者や技術者がその知識を深めるために読むべき本ではない.むしろ,例えば,他の研究者による論文を読む際に検出器・実験技術の概要をつかむための参考文献とするのに適した本であろう.また,著者による初版序文に述べられているように,本書は放射線計測とその関連技術の教科書として用いられるべきであろう.
さらに特徴的な点は,特定の実在する(実在した)実験とそこで用いられた検出器といった応用例についての解説がほとんどない点である.これほど広範な主題について集めた教科書としての性格のため,実在の検出器を例示して詳しく解説することは意図的に避けられていると思われ,致し方ないのであろう.優れた実験家がその研究目的達成のために施した生々しい工夫を追体験することは,後学の徒にとっても大いなる楽しみで醍醐味であるが,これを味わうことは本書の意図ではないのだろう.同様の理由からと思われるが,大型加速器を使った素粒子実験や原子核実験,ニュートリノ検出用などの複合大型検出装置,またダークマター探索のための観測装置についても言及はほとんど全くない.この分野で和訳されたものといえば,例えばK.クラインクネヒトによる『粒子線検出器;放射線計測の基礎と応用』(培風館,1987)があるが,これとは章立ても内容も異なり,相補的な関係にあるといえるだろう.
ここまで,ややネガティブな批評になったが,教科書・参考書としてはたいへん優れている.第1章から第4章と第16章の一部を主とし,その他の章から受講者の分野と目的に合わせて題材を選択し,具体的な事例で味付けすれば,「放射線計測学」の講義ができそうだ.評者は,3.7節「時間間隔分布」や16.3節「同軸ケーブル」などを実験指導の参考資料として利用している.このような題材について簡潔に記述した参考書はなかなか見当たらない.
では,本書の改訂第4版では,その内容は旧版とどのように変わっているのであろうか.以下では第3版と定量的に比較してみた.
第4版は全868ページ,20の章と1つの付録,122節,358小節からなる.まず,全体の情報量を比較してみよう.今回の版から出版社がかわったことから,フォントやそのサイズなども変わったため,ページ数では情報量の比較はできない.そこで,「ページあたりの最大文字数×各章のページ数」を「章ごとの文字数」とし,これを情報量の目安とした.全20章合計での文字数は約145万字で,第3版から第4版では1.8%増加している.また,第6章「比例計数管」,第8章「シンチレーション検出器の原理」,第20章「バックグラウンドと検出器の遮蔽」では,10%以上文字数が増えている.逆に文字数が7%以上減った章はひとつも無かった.
第4版で新設された章はないが,節では6.6節「マイクロパターンガス入り計数管」が新設され,この部分だけで4小節,7ページ増えている.近年急速に研究開発の進んでいるMSGC,GEM,マイクロメガス,RPCといった検出器についての記述が大幅に書き加えられた結果である.このことが上述の第6章における文字数の大幅増加につながっている.
名称の変更された節は19.5節「極低温検出器」の1つである.追加された小節は26あり,名称の変更された小節も6あった.細かい部分では多くの加筆・修正がされていることがわかる.逆に,改訂で削除された章,節は無く,小節のレベルでは,統合されて名前が消えた分も含めて,消えたのは5つのみである.最新の技術を取り入れるだけでなく,古い技術の情報をしっかりと残す,という著者の姿勢が現れていると言えよう.
記述が新しくなったのは,追加された小節の部分だけではない.著者による第4版序文で言及されているように,第8章,第9章では,新しいシンチレーターやシンチレーション光検出器についてだけでなく,これまでも掲載されていたシンチレーターや検出器についてもさらに多くの情報が加えられている.また,第16~18章ではパルス処理における広範なデジタル技術の使用について取り上げられている.特に,第16章(パルスの処理)と第17章(パルスの整形,計数と時間測定)では,2つの章の間で項目(節,小節)の大幅な組み替え,入れ替えが行われており,さらにASICに関する新しい記述も加えられている.
第20章までに掲載されている総図数571のうち10%以上の67枚は最新版で追加または更新されたものである.特に,第6, 8, 10, 13, 17, 19章では5枚以上の図が追加または更新されている.図のように一見してわかるところ以外にも加筆・修正が細かくなされており,本文を読み進めると,第6章では追加された6.6節以外の部分でも12カ所,第9章では20カ所,第13章でも19カ所で,記述が追加されている.序文で「大幅加筆」と言及された8, 9, 16~18章以外でも,細かい多くの加筆が施されていることがわかる.また,章末に掲載されている参考文献数は,全体で実に28%も増えており,13の章で20%以上増えている.このことからも,多くの記載内容が見直され,最新のものに更新されていることがうかがえよう.
放射線計測はますますその重要性が増している.その中で,最新版となった本書は,この先も多くの関連する研究者・技術者にとって有用な教科書・参考書であり続けるであろう.高額かつ大型のハンドブックではあるが,放射線検出技術を利用する研究室にはぜひ手元に一冊置いておきたい優れた参考書である.
(2014年5月18日原稿受付)
Introduction to the Statistical Physics of Integrable Many-body Systems
L. Šamaj and Z. Bajnok
Cambridge Univ. Press,New York,2013,xix+504p,25×18 cm,$130.00[専門・大学院向]ISBN 978-1-107-03043-5
紹介者:松井 千尋(東大院情報理工)
本書は,「幅広い可解モデルを網羅しており,高次スピン鎖や熱力学的ベーテ仮設法など,比較的マニアックなものも取り扱われている.小難しい数学は必要なく,この本のみで理解できるように書かれている.」という前書きのスタンスに忠実に従って書かれた本と言える.数学的背景に関する説明は,物理的論理展開の妨げにならないよう端折られているが,詳細な導出と豊富な練習問題により可解モデルの取扱いに必要な計算の基礎を押さえられるよう配慮されている.
そもそも可積分系の定義は曖昧であり,様々な解法が存在する.あるモデルが「解ける」と言った場合にどの方法を使うかは,その時々で見つけ出さなければならない.本書は1次元系のみに焦点を当てた構成になっているが,数ある解法を系統的にまとめたという点で,有効的に可解系で記述できる物理系を取り扱う際に非常に役立つ.一方で,境界がある場合の取扱いや相関関数など,煩雑さを要するものは省かれているため,他の成書1-4)と並行して読むとより応用範囲が広がるのではないかと思う.
第一章から第四章は著者の一人であるL. Šamajの講義ノートに基づいている.また,第五章を担当したZ. Bajnokは量子場の理論の専門家であり,その緻密な論理展開に彼の人となりがよく表れている.
第一章では接触相互作用する1次元のボースおよびフェルミ気体の波動関数の導出について詳しく書かれている.また,熱力学の法則の定式化まで行われており,単なる方法論に留まらず,各々の式が導出された物理的背景までしっかり理解することができる.
第二章は量子逆散乱法に関する章である.ベーテ仮設法でよく使われるラックス演算子やモノドロミー行列といった抽象的なオブジェクトと,散乱行列との関係がわかりやすく解説されており,今まで代数的ベーテ仮設法にとっつきにくい印象を持っていた読者にとっても,その直感的なイメージが掴みやすいのではないかと思う.
第三章では様々な可解量子スピン鎖の解法が取り扱われている.数学的観点から書かれた文献1に対し,本書は可解モデルが解かれた歴史に沿って書かれている.また,数学的定式化の観点からは天下り的に与えられがちな変数変換等についても,その物理的解釈に触れられており,既に可積分系に馴染み深い読者にとっても新しい発見があることだろう.
第四章は強相関電子系について書かれている.特記すべき点は,近藤効果や離散BCS模型のような1次元以外の系に対しても,積極的にベーテ仮設法を活用していることである.一方で強相関電子系というと,共形場理論との関連にその面白みがあるように思うが,それに関しては他書に譲っている.しかしながら,ベーテ仮設法だけで励起状態や相転移等をここまで鮮やかに導いてしまうのは敬服に値する.
第五章は古典・量子サインゴルドン模型に関する章である.数学的な知識や共形場理論の基本事項を前提とせず読み進めることができるよう配慮されている.共形場理論の定義から出発して後に物理現象との関連を説明するスタイルを取っている文献2と比べても,物理的観点から読みやすい構成になっている.その一方で数学的な流れは多少犠牲になっており,共形場理論について詳しく書かれた本3)等と併用するとより深い理解が得られることと思う.
参考文献
1)V. E. Korepin, N. M. Bogoliubov and A. G. Izergin: Quantum Inverse Scattering Method and Correlation Functions (Cambridge Univ. Press)
2)川上則雄,梁 成吉:『共形場理論と1次元量子系』(岩波書店).
3)P. Di Francesco, P. Mathieu and D. Senechal: Conformal Field Theory (Springer).
4)M. Takahashi: Thermodynamics of One-Dimensional Solvable Models (Cambridge Univ. Press)
(2014年6月3日原稿受付)
量子光学の基礎;量子の粒子性と波動性を統合する
古澤 明
内田老鶴圃,東京,2013, vi+174p, 21×15 cm, 本体3,500円[専門~学部向]ISBN 978-4-7536-2030-2
紹介者:武岡 正裕(NICT)
本書は,量子光学及び光を用いた量子情報処理の実験研究の世界的な第一人者による,同分野の基礎的なテキストである.「量子光学」をタイトルに含む国内外の専門書では,必ずしも光の量子化だけでなく,物質は量子力学的に,光は電磁気学的に扱ういわゆる「半古典論」も扱っている場合があるが,本書では純粋に光の量子的な性質のみを対象としている.
電磁気学では波として扱われている光を量子化すると,波と粒子の二重性が顕著に現れる.本書では,副題にもある通り,光の粒子性と波動性を自在に行き来した解説により,その二重性を統一的に理解できるよう特に配慮されている.例えば,光子数状態などの粒子性を強く表す量子状態について,あえてその波の性質を表す位相振幅の分布を図示して特異性を論じるなど,多書にはない新しい観点がある.また,位相振幅や量子状態そのものを表すウィグナー関数などは,実際の実験データを多数掲載するなど,初学者や実験研究者の直感に訴えられるような説明が多い.
本書はおおよそ2部構成であり,前半(第1章)では光の量子状態の基本的な記述法と種類・性質が説明され,後半(第2,3章)はその応用編として,スクイーズド光,シュレーディンガーの猫状態(コヒーレント状態の量子重ね合わせ)など,光の量子化を経てはじめて説明できる非古典的な状態の具体的な生成方法,及び量子テレポーテーションや量子ゲート操作など,量子情報処理に関わる光の量子状態操作について,著者の研究室の最新の研究成果を中心に詳しく解説されている.量子光学という学問の体系的・網羅的な解説というよりは,むしろ後半の応用編をゴールとして,前半の基礎編では後半に必要な知識に内容を絞り,そこに一直線に向かって進んでいく印象である.分量も170ページ程度に収まり,直感的な図と説明を多用する一方,大事な部分の式の展開は非常に丁寧に記されているなど,量子力学を既習された方が新しく量子光学を学ぶ際におおいに助けになるテキストであると思う.
一方で,本書は内容が絞られており,この一冊で量子光学や光量子情報処理の全体像を把握することは難しいだろう(例えば量子化の詳細,ウィグナー関数以外の疑似確率分布や位相の話題,(量子化した)光と物質の相互作用,ベルの不等式や種々の量子測定などの量子光学が重要な役割を果たす量子力学基礎の話題等は,重要だが本書では扱われていない).もちろんそれらをより体系的に解説した名著は既に多く出版されており,本書の意図するところでもないと思うが,できれば巻末等で,そうした書物の紹介や本書との関連,読者の目的に応じて次にどのような書物へ進めばよいのか,などの補足情報があれば,勉強の大きな助けになるであろうと感じた.改訂版での充実を期待したい.いずれにせよ,量子光学に少しでも関わる学生・研究者の方々にとって,非常に有益な一冊である.
(2014年5月13日原稿受付)
Physical Mathematics
K. Cahill
Cambridge Univ. Press, New York, 2013, xvii+666p, 25×18 cm, $85.00[専門~学部向]ISBN 978-1-107-00521-1
紹介者:多田 司(理研)
本書は題名通り,物理数学と通常呼ばれる科目の教科書,参考書である.本書の特徴は,具体的な計算を徹底的に重視している点と,数学が実地に活用された例が豊富に紹介されている点にある.
本書で取り扱われているのはほぼ20世紀初頭までに成立した数学である.例えば比較的現代的なトピックである微分形式を導入していながらcohomology(例えばde Rahm cohomology)などへの言及はない.Robert Geroch著Mathematical Physics(The University of Chicago Press, 1985)が,圏論から現代的な位相幾何学,測度論まで扱っているのとは対極である.グラフも豊富に掲載されているが,キャプションには使われたパラメータが細かく書かれている.またクォークのCabibbo-小林-益川行列,ニュートリノにおけるシーソー機構,非線形光学の第3高調波,宇宙背景輻射と言った興味を惹くテーマが計算例として取り上げられており,学習意欲が刺激される.
自ら手を動かし結果が出せること,それを通じて物理学の研究に役立つ数学の技術を身につけることが本書の眼目である.このような本では,テーマ選びが難しく,また著者の経験がもっとも反映されるものであろう.著者と同じく素粒子論の研究者である評者には納得のいくテーマの選択,記述内容であると感じられた.テーマとして,確率・統計,モンテカルロ法,経路積分について取り上げられているのが特色と言える.
全体の構成を紹介すると,まずは線形代数の解説から始まっている.通常の数学的な記法の説明の後,ディラックのブラとケットが導入されている他,ラグランジュ未定乗数法や,密度演算子についても触れられている.フーリエ級数の説明,フーリエ変換とラプラス変換の章が続く.フーリエ級数の章ではギッブス現象なども明快な図解で示されており,かなり詳しい内容となっている.無限級数の説明の後,複素関数論が説明されている.カシミア効果の計算が例題となっている他,弦理論でのビラソロ代数の交換関係の導出も書かれている.続く微分方程式の章では具体的な解法が整理して簡潔に記述されており,実用的である.特殊関数等についてはルジャンドル関数と球面調和関数,ベッセル関数が取り上げられている.第10章からは群の解説が始まり,特に回転群,行列群,ローレンツ群とその表現が解説されている.確率と統計の章でも物理への応用の視点はゆるがず,ブラウン運動はもちろん,ポワソン分布の説明に際して,コヒーレント状態でn粒子状態を見いだす確率がポワソン分布になる例が挙げられている.モンテカルロ法,汎関数,経路積分,繰り込み群,弦理論についての基本的な説明の章がこれに続く.各章の終わりには簡単な練習問題が付されている.
600ページを超える大部の新著であるため,同じトピックが別々の章で導入される場合があるなど,全体の構成にまだこなれていないと感じられる部分もあった.誤記,誤植等も散見されるが,正誤表が著者のサイトhttp://theory.phys.unm.edu/cahill/で維持されており,新版には逐次反映されている.構成の整理や改善についても今後の改訂を待ちたい.英文の原書であることも考え合わせると,今の時点では初学者に勧められるというよりは,実際の研究上あるいは関連する講義を行う際の参考資料として非常に有用な本であると言える.
(2014年5月2日原稿受付)
ULTRACOLD ATOMS in OPTICAL LATTICES: Simulating Quantum Many-Body Systems
M. Lewenstein, A. Sanpera and V. Ahufinger
Oxford Univ. Press, New York, 2012, xiv+479p, 25×18 cm, £57.50[専門・大学院向]ISBN 978-0-19-957312-7
紹介者:渡辺信一(電通大情報理工)
本書は,近年,発展の目覚ましい光格子中の極低温原子の理論について網羅的に書かれた極めて野心的な本だ.物性理論において,古典計算機の力を超えた量子力学的問題を,光格子中の極低温原子を用いた実験によって擬似的に解いてはどうかと考える.そのため多くのページを,物性における格子系の量子多体問題との関連に割いている.極低温原子は本来,量子エレクトロニクス(量エレ)の対象であるが,光格子を理想的な周期場と考えると,極低温原子は光格子中をホップできるコヒーレントな物質波と捉えられる.固体の低温現象と類似の現象の発現はなるほどと頷ける.実際,光格子の高さを制御することで超流動相とモット絶縁体相の間の転移が観測されて12年ほど経過し,ボーズ・ハバード模型も量エレの分野に浸透した.レーザーでかなり複雑な結晶構造も構築できることから,最近ではフラストレーション,フラットバンド,ディラック錐など,量エレには耳慣れないテーマの論文も見かける.
このような事情の中で,本書は2010年ころまでに報告された量子シミュレーターの研究成果を集大成した最初の本と言ってよいだろう.量エレを背景とする読者には物性の多体問題への導入として,物性を背景とする読者には極低温原子物理への誘いとして書かれたようだ.約千件に及ぶ莫大な文献を備えているので,最近の研究の概要を知りたいとか,特定のテーマについての取っ掛かりにしたいと望むなら,豊富な情報を提供してくれる.半面,量エレと物性の両方に精通していることが読破の要件になるので,単独では教科書に向かないだろう.
本書は全15章からなる.前半の1章から6章までは網羅的な導入部だ.古典および量子相転移や周期系の基本概念などを踏まえて,量子シミュレーターで何ができるかを概説後,ボゾン系,フェルミオン系,混合系のハバード模型の物理と種々の計算手法の概略が述べられている.後半の7章から14章は光格子中の冷却原子を利用できる研究対象が紹介されている.例えば,スピン系,極低温双極子ガス系,無秩序系,スピングラス,フラストレートした系(反磁性)等々およびその理論的解析手法などである.また,"人工"ゲージ場を中心に量子ホール効果やディラック錐を持つ系の多体問題などを,量子情報的視点から取り上げて議論している.最後の章ではKITP conferenceなどで提供された話題を列挙する形で,今後発展的に継続されるべき課題や新しいトレンドが書かれている.
総じて,専門家にとっては座右の書として活用できるかもしれないが,記述の難易度が章によって教育的なものから難解なものまでかなりばらつきがあるため,冷却原子,量子情報,固体物性に習熟していない大学院生がじっくり読むべき教材としては重過ぎる.トピックを限定したうえで,原子物理の教科書,例えばC. Cohen-Tannoudji氏らによるAdvances in Atomic Physics(2011)や冷却原子理論の教科書,例えばM. Ueda氏によるFundamentals and New Frontiers of Bose-Einstein Condensation(2010)を適宜参照しながら読むことは可能だろう.
(2014年4月14日原稿受付)
デトネーションの熱流体力学1;基礎編
デトネーションの熱流体力学2;関連事項編
デトネーション研究会編
遠藤琢磨
理工図書,東京,2011,ix+291p,26×18 cm,本体3,500円[大学院・学部向]ISBN 978-4-8446-0784-7
理工図書,東京,2011,ix+411p,26×18 cm,本体3,500円[大学院・学部向]ISBN 978-4-8446-0785-4
紹介者:長友英夫(阪大レーザーエネルギー学研究セ)
デトネーション(Detonation)とは,衝撃波を伴った燃焼波のことであり,爆轟と訳されることもある.一見馴染みのない現象のようにも思えるが,通常の燃焼(Deflagration:デフラグレーション)がある条件下で遷移した場合に発生する現象である.爆轟という言葉からは大変危険な印象を受けるが,大きな化学エネルギーを瞬時に運動エネルギーに変換させることも可能であることを意味しており,現象を理解し制御できれば工学的な活用も期待できる.しかしながら,熱力学,流体力学,燃焼学,化学の複合分野の現象で,学生や初学者にとってはどこから手を付けたらいいのか分かりにくい.そのような状況を踏まえ,教育,研究の現場で使いやすいように上手くまとめた書である.
本書は2冊分冊で構成されている.1.「基礎編」はデトネーションを習得するための基礎知識をまとめた教科書,2.「関連事項編」はデトネーションに限らず熱流体を研究する際に必要な公式,数式導出をまとめたハンドブックのような書である.内容は独立しており,それぞれ単独でも活用できる.以下主に「基礎編」について紹介する.
第2, 3章で,「燃焼における化学反応」および「デトネーションの1次元解析」と題し,デトネーションに関連する基本的な化学と物理を説明している.ここでは,1次元解析に必要な流体力学も含まれているが簡潔な支配方程式の導出の後に,理想気体を仮定しないデトネーションの1次元解析から断熱曲線の導出に進むため少しステップが高いかもしれない.ただし,流体力学を履修したことがあれば,本書は式の導出は比較的丁寧に書かれているので,追随しやすいと思う.また,これらの前提となっている熱力学,音速,および流体の基礎方程式の導出,変形などは「関連事項編」に,化学反応を伴う場合も含め多様な観点から解説,補足されている.これらはデトネーション研究以外でも化学反応やプラズマ流関係の研究において数式を参照したいときにも活用できる充実した内容に展開している.
典型的なデトネーションの伝播例として,第5章「デトネーションのセル構造」の「5.1実験」で,デトネーションの3次元的な挙動を写真や図を多用しながら説明している.その特殊な条件を満たすときに,理想的な伝播例の一つ,シングルスピンデトネーションとなる.これは円管内をらせん状に燃焼波が伝播する場合で,その存在条件を第4章で導いている.ここは読み手によっては,章を入れ替えて読んだ方が理解しやすい.また「5.2数値シミュレーション」でも,セル構造が図解で詳しく示されており,セル構造の定性的な理解の助けとなる.
第6章「起爆」では,燃焼による圧力波形成から衝撃波を駆動して燃焼波になる条件(DDT: Deflagration to Detonation Transition),球状の爆風波を起動するのに必要な最小エネルギー,急拡大管におけるデトネーションの存在条件について,解析解や実験結果を詳しく紹介している.さらに続く章で,爆薬,火薬による燃焼,爆轟,実験計測技術,数値シミュレーション技術,パルスデトネーションエンジンの理論,デトネーション特性解析コードについて説明している.最新の手法,特性値や関係グラフを多用しているので実用面でも有用であろう.
全般に,式の導出も含め丁重な説明と多くの参考文献が随所に掲げられている.やや過保護のようにも思えるが複合的な分野を短期間で習得するためには最適な一冊である.また,研究会が主導して執筆したためか,バランスのとれた構成になっていることも読みやすさにつながっていると思う.
「関連事項編」は,「基礎編」の著者の一人が周囲の人に勧められて「基礎編」では詳細を記述できなかった公式,式の導出などをまとめた書だけあって,やや独特だが興味深い構成になっている.特に,本題からは脇道に逸れるが著者の思い入れのある関連する事項をまとめた部分は深く掘り下げた記述も見られ,関連分野を研究する人が読んでも大変参考になる.
(2013年9月7日原稿受付)
光物理学の基礎;物質中の光の振る舞い
江馬一弘
朝倉書店,東京,2010,ix+196p,21×15 cm,本体3,600円(光学ライブラリー2)[専門~学部向]ISBN 978-4-254-13732-3
紹介者:早瀬潤子(慶應大理工)
本書は,光物理学の最も基本的なことがらの一つである「物質中の光の振る舞い」を学ぶために書かれた初学者向けの教科書である.本書の特徴は,著者がまえがきで述べている通り,様々な光学現象を系統的に整理・解説することを目的としているのではなく,その現象が起こる物理的起源に焦点を当てて解説している点にある.
著者の意図が最も強く表れているのは,本書の導入部分である第1章であろう.第1章では,物質中の光の伝搬が,原子による散乱光(2次波)と,元の入射光との和によって物理的に理解できることを,わかりやすいイラストとともに丁寧に解説している.込み入った数式を取り扱う前に,光学現象の物理的イメージをつかむための導入部分があることは,初学者にとってありがたい配慮である.
第2章から第6章にかけては,光の伝搬方程式や物質の応答関数,反射と屈折の法則,誘電体ローレンツモデルや金属ドルーデモデルといった,「物質中の光の振る舞い」を理解する上で必要となる基本的なことがらを網羅した内容となっている.必要十分な数式や豊富な図表に加え,物理的概念に関する記述が随所にちりばめてあり,大変わかりやすい参考書となっている.他の教科書と比べて比較的平易な内容であり,当該分野を独学で学びたい初学者の参考書として,あるいは学部生向けの講義の教科書としてお勧めしたい.また,「ポラリトンの概念は必要か」や「超光速伝搬とは何か」といった興味深いトピックも含まれており,研究者にとっても楽しめる内容となっている.しかし一方,本書は入門書である面が強く,光物理学の深い専門知識を得たい研究者に対しては,より専門的な内容を取り扱う参考書が適しているかもしれないことを付記しておく.
本書で取り扱う光物理学は,物理学の基礎をなす研究分野の一つであるとともに,最先端光テクノロジーの発展に必要不可欠な分野である.本書のような良質な参考書により,一人でも多くの若者が光物理学に興味を抱いてくれることを期待したい.
(2014年3月23日原稿受付)
不確実性時代のエネルギー選択のポイント
J. Hermans著,村岡克紀訳
丸善,東京,2013,xv+244p,21×15 cm,本体2,300円[一般向]ISBN 978-4-621-08703-9
紹介者:岡野邦彦(慶應大院理工)
本書は,物理学者の視点でエネルギー問題を捉え,定量的に比較できる形で解説した一般書である.数式も図表も理解に必須の最小限度で構成されているので,ときには文字しかないページが続くが,具体例や絶妙なアナロジーを取り混ぜて,物理的本質をうまく説明する著者の解説に飽きることはない.また,適切な訳注も理解を助けている.
人が使うエネルギーから入るのではなく,階段を登るエネルギー,フライパンをかき混ぜるエネルギーなど,人の出せるエネルギーから説明していく導入も秀抜だ.章が進むにつれて,家庭で,移動で,国で,世界で使われるエネルギーへと展開する.化石燃料が中心となっている世界のエネルギー消費と,おそらくそれに起因する地球温暖化問題に触れたのち,個別のエネルギー源の解説に入る.各種再生可能エネルギーの解説に続き,原子力エネルギーにも多くのページを割いている.原子力の解説の約半分を核分裂に,1/4を核融合に,残りを放射線の理解に充てている.バイオマスを太陽光に含めているのも慧眼だ.運輸部門のエネルギーと関連する形でエネルギー貯蔵の重要性にも触れる.いずれの章でも利点と欠点がうまく整理され,本質がよく理解できる.ただ,著者が原理的に安全な原子炉(ペブルベッド型)を,「100%事故をなくせる原子炉」と呼ぶのには同意できなかった.その安全は原理を具現化する構造が破壊されないのが前提なのだから,100%は言い過ぎではないだろうか.
本書の構成でやや弱いと感じたのは社会経済的視点からの分析が不足な点である.経済発展と環境改善の関係は本書が標榜するエネルギー選択のポイントとして重要なはずだ.たとえば,ビョルン・ロンボルグ著,山形浩生訳『環境危機をあおってはいけない』(文藝春秋)を読むと,環境危機問題への多くの疑問が示されている.ロンボルグの批判のすべてには同意できないが,極端な温暖化対策が未来世代の収入を押し下げる負の側面も考えるべき,という考えは理解できる.日本は京都議定書での公約(1990年比で二酸化炭素排出量-6%)の達成を昨年発表したが,これがリーマンショック後の長期不況の産物だったことはよく知られている.著者がこの大不況を「祝福の神様かもしれない(p. 230)」と書いているのには抵抗がある.著者の心配する孫の世代のためにも,温暖化防止は経済発展を維持しつつ実現したい.
本書はエネルギー問題の一般向け入門書にとどまらず,物理の基礎が十分にある大多数の本学会会員にとっても,物理の本質を解きほぐす巧みな解説から得るものは大きいと思う.一方,本書をすでに読まれた方は,同じ問題を米国ジャーナリストの視点から見た本,ロバート・プライス著,古舘恒介訳『パワー・ハングリー』(英知出版)と本書を読み比べてみるのはいかがだろう.そこに巧みな物理解説はないが,取材と経験をもとに,何が起きていて,何ができるか,という現実主義に徹している点が特徴で,両書を読むことでこの問題への理解が一層深まるはずだ.
(2014年3月10日原稿受付)
ページの頭に戻る
時間とは何か,空間とは何か;数学者・物理学者・哲学者が語る
A.コンヌ,S.マジッド,R.ペンローズ,J.ポーキングホーン,A.テイラー著,伊藤雄二監訳
岩波書店,東京,2013,xviii+229p,21×15 cm,本体3,700円[一般向]ISBN 978-4-00-005468-3
紹介者:細谷暁夫(東工大)
この本は,2006年9月にケンブリッジ大学エマニュエルカレッジで行われた「空間と時間について」(ON SPACE AND TIME)というタイトルの公開討論会をまとめたものである.パネラーは天文学者,物理学者,数学者,哲学者と神学者である.
趣旨については,講演者であり編集者でもあるシャーン・マジッドが「はじめに」で明快に述べている.時間と空間についての深い科学的理解,すなわち,プランクスケールの量子時空の可能性について,ドグマや流行を排した知的な討論が目的である.量子重力について,現在われわれは何も知らないという「無知の知」を前提にした真の意味の自然哲学者たちの強靭な思考力が展開される.
構成は,宇宙の観測事実(A.テイラー),離散時空描像への入門 (S.マジッド),相対論の特異点問題からのアプローチ(R.ペンローズ),非可換幾何(A.コンヌ)と言う風に,具体から抽象の度合いを上げて,締めくくりは神学における時間の意味(J.ポーキングホーン)となっている.テイラーの宇宙論のまとめはこれだけ独立して読んでも有用である.マジッドのものはコンヌの非可換幾何の物理的な導入になっている.ペンローズのものは彼独自であり他とは相補的になっている.全体の基調はコンヌによる壮大な統一理論へのプログラムである.
これは純粋な意味で,現代のプラトニストたちの響宴である.功利主義と妥協せず真っ直ぐに真実を問うヨーロッパの知性の伝統を見る.その一方で,そのような文化的背景を持たないものが読むと,一抹の危うさも感じる.彼らの追い求める時間と空間は現実の時間と空間なのか,それとも頭の中にある想念に過ぎないのか,と.また,アインシュタインの相対性理論から100年経って,その間に人間社会は近代科学のお陰で大きく変貌し,その影響を受けて人々の思考形態と価値観も変化している.それと全く無関係にアインシュタインの統一理論のいわばリベンジを純粋思考で追求するのだろうか.それに対して,取りまとめ役のマジッドは,大胆にも,彼らの追求する非可換時空は実験的に検証できると言い切る.
この本の読者は超一級のパネリストに心酔するもよいだろう.論文には書かない踏み込んだ本音も書かれているようだ.また全く別の観点からの量子時空論を展開して,やや孤独を感じている人たちには勇気を与えるだろう.しかし,科学である以上,決着は実験でつくということについては,この本の編集者に同意して貰いたいと思う.私自身は,トリのポーキングホーンの指摘が気になる.確かに彼の言う通り.物理学における時間には「今」の概念が欠如している.
訳は専門家によるもので読み易く正確である.細かいことを言えば「標準ろうそく」よりは標準的な「標準光源」を使って欲しかった.
(2014年2月19日原稿受付)
これが物理学だ!;マサチューセッツ工科大学「感動」講義
ウォルター・ルーウィン著,東江一紀訳
文藝春秋,東京,2012,403p,20×14 cm,本体1,800円[専門~一般向]ISBN 978-4-163-75770-4
紹介者:堂谷忠靖(JAXA)
「物理を学ぶと世界が違って見えてくる.」これが,Walter Lewinが全身全霊で読者に伝えようとしていることである.
Walter LewinはMassachusetts工科大学(MIT)の名誉教授で,専門は宇宙物理学,なかでもX線による宇宙観測である.氏は,その型破りな物理学講義で名を馳せており,「教壇のスーパーヒーロー」をはじめとして様々な異名を取っている.講義の様子はMITの公開授業サイトやYouTubeで視るこ
とができる他,少し前にNHKの白熱教室で放送されていたので,観た人も多いだろう.本誌でも紹介されている(峰 真如,木村 元:日本物理学会誌68 (2013)483).本書は,この名物講義の内容をベ-スに,物理学の魅力を文章で読者に伝えようとしたものである.
本書は講義に基づいてはいるものの,単に講義そのものを文字にしたものではない.そもそも氏の講義の特長は学生の心をわしづかみにする派手な演出にあり,とても文字にできるものではないので,是非とも本書と併せてLewin氏の講義を見ることをお勧めしたい.代わりに本書では,読者はWalter Lewinの思考をたどることになる.突飛で時には執拗な考察により,虹とか水圧などの身近な現象の背後にある物理に肉薄していく.まるでWalter Lewinとともに日々の生活を営んでいるかのように,ポケットに偏光板を忍ばせ,夕立には虹を探し,みそ汁のベナール対流を楽しむことになるだろう.肌で感じることができる現象を存分に味わった後,本書の後半では,Walter Lewinが渦中の人であった,新たな分野--X線天文学--の開花を共に追体験することになる.壮大な宇宙の営みも,身近な現象と同じように物理に支配されていることが,その巧みな語り口によって解き明かされていく.
物理学の魅力を伝える本や講義は数多くあるが,なぜWalter Lewinの講義はこれほど多くの学生を魅了するのだろうか.物理学の本には相応しくないような最終章で,その理由の一端が明かされる.Walter Lewinは,私が物理学以上に好きなものは芸術だと書き,これまでに携わってきた芸術的創作について触れている.氏の言葉を借りれば,芸術もまた,世界の新しい見え方新しい目の向け方を示してくれる.つまるところ,物理学にしろ芸術にしろ,それを学ぶことで今まで(眼前にあるのに)見えなかった全く新しい世界が見えて来るようになる,ということだ.これは,第一章で「我々の世界の仕組みと優雅さ,美しさを照らし出す物理学の真髄に,あなたが開眼するきっかけとなるように―.」と書いていることと呼応する.世界を見る新しい目を手に入れるということは,新しい生き方を手に入れるに等しい.これを念頭におけば,Walter Lewinが電磁気学の講義(Lec. 22)でMaxwell方程式の真髄を説明し終えた際に,数百人の学生一人一人に水仙の花を手渡すという大仰なセレモニーも合点がいく.学生が得た新しい生への祝福なのだ.物理学の魅力を伝える講義や著作はあまたあるかもしれないが,物理学によって新たな人生をもたらそうとするのは,おそらくWalter Lewinが最初に違いない.
(2013年5月30日原稿受付)
Astrophysics at Very High Energies
F. Aharonian, L. Bergström, C. Dermer
Springer-Varlag, Heidelberg, 2013, vii+361p, 24×16 cm, 80.24€(Saas-Fee Advanced Course 40)[専門・大学院向]ISBN 978-3-642-36133-3
紹介者:戸谷友則(東大院理)
"Very High Energy"すなわち「超高エネルギー領域の宇宙物理学」と題した本書は,2010年3月にスイスの宇宙物理・天文学会が主催したthe 40th Saas-Fee Advanced Courseの講義録である.GeV領域のガンマ線天文学はフェルミ衛星の成功により,またTeV領域は地上チェレンコフガンマ線望遠鏡の著しい発展により,この10年の間に驚異的なスピードで様々な天体からのガンマ線検出が相次ぎ,数多くの新たな知見がもたらされた.本書は,この発展著しい分野の第一線で活躍する3人の理論家によるレクチャーをまとめている.理論家といっても,HESSやFermiといったプロジェクトの正式メンバーとして参加して,最新データを使ったサイエンスを展開している人たちであり,その意味では理論と観測をバランスよくレビューできる陣容と言えるだろう.
最初に登場するのはF. Aharonianで,主に銀河系内天体の地上ガンマ線観測による最新成果をまとめている.具体的には,超新星残骸,コンパクト連星,パルサー,銀河系中心などである.続いてL. Bergströmが,主に暗黒物質からの対消滅シグナルの検出について執筆している.といっても,ビッグバン宇宙論の基礎から始まり,宇宙論における素粒子反応や,様々な暗黒物質候補の解説など,幅広い.検出法としては対消滅ガンマ線だけでなくニュートリノにも焦点が当てられている.最後に,C. Dermerが主にフェルミ衛星の成果を中心に,特に活動銀河中心核(AGN)の最新の知見について詳しくまとめている.AGNだけでなく,ガンマ線バースト,スターバースト銀河,銀河や銀河団内の宇宙線によるガンマ線,宇宙ガンマ線背景放射や,可視赤外線宇宙背景放射との相互作用なども,Aharonianの担当部分とうまく棲み分ける形で書かれている印象である.
書かれてある内容のフレッシュさやレベルの高さについては,さすがに第一線の研究者の筆によるだけあって,充実の内容である.ただし単著での系統的な著書ではなく,3人の著者がそれぞれの得意分野を独立にレビューしたというものであり,これ一冊を読んで関連分野をバランスよくカバーできるという本ではない.(内容的にも,DermerをBergströmの前に持ってきた方が順序の収まりが良いと思えるが,アルファベット順?)また,書籍タイトルはガンマ線には限定されていないが,実質的にはガンマ線についての内容が主である.その意味では,たとえばAugerやTAで進展のあった超高エネルギー宇宙線はほとんどカバーされていない.(業界用語で,GeVやTeVはvery high energy,一方で1020 eVの宇宙線はultra high energyを使うという意味では正しいのかも知れないが,そういう慣例に慣れていない一般読者には誤解を生みやすいかも知れない.)しかしながら,本書の内容で"very high energy astrophysics"のかなりのトピックスをカバーしていることは間違いなく,若い大学院生が面白そうな研究テーマを探すために眺めてみるには格好の書と思われる.
(2013年10月29日原稿受付)
Fundamentals of Cosmic Particle Physics
M. Khlopov
Cambridge Int. Sci. Pub.,UK,2012,xi+431p,24×16 cm,129,95€[専門・大学院向]ISBN 978-1-907343-48-3
紹介者:郡 和範(KEK)
著者であるMaxim Khlopov氏のご専門は,素粒子論と宇宙論の境界領域で,日本語では素粒子的宇宙論とも呼ばれる分野の理論研究です.その分野が始まった1980年ごろから勢力的に研究を続けられ,この分野の発展に長く寄与してこられました.
特にこの分野を表す"Cosmoparticle Physics"という,オリジナルに作られた用語を頻繁に用いられており,1999年に発表された彼の前作の英文の著書は,このタイトルで出版されています.また,最近,彼がフランス・パリのAPC研究所の図書館のウェブサイトで進めている,virtual libraryと名付けられた,多くの研究者のトークのビデオファイルを閲覧できるというオンライン講義の宣伝の意味もあるそうです.この教科書により,そのオンライン講義で語られる現代の素粒子的宇宙論の理解に至るまでの,歴史的なギャップを埋めることができるそうです.
この教科書は,もともと彼がロシア工科大学で行った講義をもとに編纂されています.前作と同じく,過去のロシアで行われた仕事が世に知られていないことを憂いており,欧米諸国にその偉業を知らせることも,目的の一つにしているそうです.前作から貫かれたこの精神はゆらぐことはないようです.
扱っている内容は,インフレーション宇宙論,宇宙における対称性の破れ,ダークマターモデル,ビッグバン元素合成,原始ブラックホール,宇宙反陽子の起源,大規模構造の形成などです.特に宇宙初期の物質優勢期における原始ブラックホールの形成可能性の議論は,彼のオリジナル論文を噛み砕いて説明しており,一読の価値があります.
この教科書を読むためには素粒子論と宇宙物理学の深い知識が前提となるかもしれません.標準的な教科書ではなく,全体的にかなり上級な内容ですので,日本の修士の学生のような初学者にはすすめられません.また,プロの研究者にとっても「2,3冊目として持っておくと重宝する」という使われ方が適当ではなかろうかと思われます.
この本が著された動機を知った後,ふと日本も似たような状況にあることに気づかされます.現在の日本は素粒子的宇宙論研究のメッカの一つであることはよく知られています.現代的な素粒子的宇宙論の理解に至るまで,これまでもコミュニティーに対して多大な貢献をしてきました.しかし,欧米ではそうした日本で行われた初期の頃の優れた仕事は,あまり知られていないのが現状です.
Khlopov氏が前作から今回の教科書を著すまでの13年間,我々は日本で行われた研究を世界に知ってもらう努力をどれだけしてきたでしょうか.前作の評者である横山順一さん(東大理)の提案した,「我が国でもこうした成書があっても良いと思う.どなたかなさいませんか?」に重みが感じられます.
(2013年9月17日原稿受付)
ヒッグス粒子の見つけ方;質量の起源を追う
戸本 誠,花垣和則,山崎祐司
丸善出版,東京,2012,ix+136+4p,21×15 cm,本体1,900円[一般向]ISBN 978-4-621-08617-9
紹介者:大林 由尚(東大カブリ数物)
2012年,ヒッグス粒子の発見を遂げたLHC実験の最前線で戦う,3人の研究者による素粒子物理学の最新の解説書である.一般向けの解説書となってはいるが,物理学実験の専門家にもぜひ読んでいただきたい一冊.
最近,特に大型研究に携わる研究者には,一般の人々に研究について知っていただく「アウトリーチ活動」が義務づけられるようになってきている.しかし,日頃専門家集団の中で議論を続けている研究者が人々に分かるように伝えるというのは簡単な事ではない.本書の著者らも,ヒッグス粒子の発見に沸く中,多くのアウトリーチ活動を経験して研究を分かりやすく伝えようと,多大な苦労を払って伝え方を工夫してきたと思われる,その苦労の結果が随所に見られる.
全140ページ程の比較的薄い本だが,その前半を費やして素粒子と宇宙との関わりから標準模型,素粒子に質量を与えるヒッグス機構まで,ヒッグス粒子探索に関連する理論全てが非常にコンパクトに解説されている.多岐にわたる内容を本書の執筆方針に乗っ取って極力数式を使わずに分かりやすい解説に努めている一方,分かりやすさのためのごまかしはない.例えば,ヒッグス機構により素粒子が質量を得る仕組みを説明するのに,一般書で多用される,パーティーに現れた有名人の例えはあえて使わず,でこぼこ道の例えを使い,空間が障害を持つとして丁寧な説明が試みられている.その分,一般向けとしてはかなり高度な内容になってしまい,ついてゆけないと感じる人々も少なくないかも知れない.しかし,本会誌の読者の多くを占める物理学の専門家にとっては,コンパクトな説明により,自身の理解の再確認ができると思われる.また,それぞれの専門分野で,研究を分かりやすく伝えるのに苦労している方々の,「伝える」ための工夫の手助けにもなるものと思う.
中盤から,素粒子実験の概説と,本題「ヒッグス粒子の見つけ方」がはじまる.実験に話が移っても,コンパクトな解説は相変わらずで,「見つけ方」の第5章は僅か20ページである.著者陣の本職の部分だけにこの章は検出器の較正,バックグラウンドの見積り,系統誤差など書き始めたら止まらなくなってしまうであろう所を短く切り上げ,読者が興味を持てるように話を進めているのは見事.しかも章の後半は統計処理の話に集中し,「5σ で発見」というのが何を意味するのかが丁寧に説明されている.評者も,統計処理に悩んでいた修士課程の時分にこのような解説の本に出会っていれば,もっと簡単に理解できたのにと残念な気分である.
最終章では,ヒッグス粒子の発見によって標準模型が完成し,素粒子物理学はこの先やる事が無くなったのかというとそうではなく,階層性とファインチューニング問題,超対称性と宇宙の暗黒物質や,余剰次元に至る素粒子物理の発展が期待できると希望たっぷりに描いている.最終章に限らず,著者陣が最先端の科学の追求に,本当に楽しんで携わっているのだ,ということが随所に滲み出ている本書は,繰り返しになるが物理学の専門家にも十分読み応えがあり,研究とそのアウトリーチを進めるために大いに参考となるものと思う.一度読むだけではなく,事あるごとに部分部分読み返してみたくなりそうだ.
(2013年9月9日原稿受付)
Einstein Gravity in a Nutshell
A. Zee
Princeton Univ. Press,New Jersey,2013,xxii+866p,26×18 cm,$90.00[専門~学部向]ISBN 978-0-691-14558-7
紹介者:夏梅 誠(KEK)
著者のZeeは,"Quantum Field Theory in a Nutshell"の著者として名高い.この本は,テクニカルな詳細より,背後にある物理的アイディアに重点を置いた本で,時にはユーモアや逸話をまじえたカジュアルな語り口で,物性理論から素粒子論,超弦理論まで縦横無尽に行き来しつつ場の理論を紹介した本であり,初学者から研究者まで幅広い読者を獲得した.
その著者が,今度は一般相対論の教科書を執筆したと耳にしたので,出版前から宣伝文などに眼を通していた.だが,さすがのZee先生でも,二匹目のドジョウは無理なのでは,とタカをくくっていた.しかし,月並みな言い方であるが,現物を読んでこの想像がよい意味で裏切られたことを知った.
"QFT Nut"の特徴は,この本でも健在である.この本ならではの特徴を3つ挙げると,第一に基礎知識として仮定されているのは,基本的にはニュートン力学だけである.(このため,研究者にとっては説明が冗漫に感じられる部分もあるかもしれない.)
第二に,重力にまつわるおよそ思いつく限りの話題が網羅されている.特に,現在未完成である量子重力と関係しそうな話題は,十分な扱いとは言えないものの,ほぼ網羅されている.
第三に,作用原理と対称性に重きが置かれており,この立場は特殊相対論の説明にさえ,かなり早い段階で導入されている.これは,現代の物理学者にとって当然の立場ではあるが,初等的な一般相対論の教科書で,この立場を採用している本は驚くほど少ない.一つの理由としては,実際に作用原理からアインシュタイン方程式を導くのは,初学者にとってハードルが高いからである.したがって,この点どう処理するのかが気になったのだが,読んでみると技術的な詳細を避けて,対称性その他の考察からうまく導いていた(原著347ページ).と同時に,詳細が気になる読者のために,後できちんとした導出も与えている.このように,この本では初心者が負担にならないように気を配りつつ,しかし物理の根幹については王道を行く,という方針が貫かれている.
とは言え,900ページ近い量,しかも細かい活字の脚注や付録も満載であり,正直言って初学者向けとしては長い.初学者向けのガイドラインはついているが,ゼミで使う場合,あらかじめ教員が読むべき箇所を指定した方がいいだろう.この点で,この本は全ての初学者向けとは言いにくい面もある.
この本の利点は,むしろ将来重力も研究していく学生に対して,将来を見据えた方向づけがなされている点である.私が学生の頃に,こんな本があればどれだけ助かったかと思わずにはいられない.なかには,いくら何でもこんな話題まで扱わなくても,と感じる点はあるが,これも重力とは何なのか,特に量子重力理論の難しさを反映しているのだろう.博学な読者のなかには,この本に書かれた話題を全て承知しておられる方もいよう.しかし,それでも一般相対論をどう教えるべきか,物理教育の一つのあり方として,この本から学べることが必ずあるはずである.
重力に興味を持つ万人に,強くお勧めする.
(2013年9月12日原稿受付)
クラウジウス熱理論 論文集;エントロピーの起源としての力学的熱理論
ルドルフ・クラウジウス著,八木江里監訳,八木江里,林 春雄,依田 聖,岡本里夏共訳
東海大学出版会,神奈川,2013,xxviii+369p,22×16 cm,本体4,000円[専門向]ISBN 978-4-486-01946-6
紹介者:佐々 真一(京大院理)
「宇宙のエネルギーは一定である.宇宙のエントロピーは最大に向かう.」1865年に出版されたクラウジウスによる論文の結語がこの有名なフレーズである.この論文により,「エントロピー」という名前とその定義が与えられた.これらの事実は多くの文献で紹介されている.しかし,ずっと不思議に思っていたことがあった.現在の知識では,クラウジウス等式から熱に関係する状態変数を定義するのは直ちにできそうだが,歴史では11年かかっている.何故11年も必要だったのか.クラウジウス論文集の英訳を何度か眺めたことはあったのだが,全体像をつかめないままだった.いつか理解したいと思っていたときに日本語訳がついに出版された.背景や用語が分からないまま文脈を推測しながら読むときには,日本語で読める恩恵は極めて大きい.11年の謎を自分なりに理解して気持ちよくこの紹介記事を書いている.
このようなはっきりした動機があったとしても,一般的な物理学会会員が最初から読むのはやはりつらいだろう.最初にとりあげられる1850年の論文では,カルノーの法則が検討されるが,「自由な熱」「潜んでいる熱」「内的な仕事」「外的な仕事」などの概念に面喰って先にすすむのは困難である.何はともあれ,まずは,山場の1865年の論文から読むのが良いように思う.その論文の前半では,クラウジウス等式が意味する積分可能条件の数学的帰結が議論されており,記号を少し変更すれば現在でも馴染みの話である.その後で,クラウジウス等式からかなり唐突にエントロピーが定義される(フェルミなどの伝統的な熱力学本と同じである).これでは11年の謎が分からない.1854年の論文でクラウジウス等式に関連して完全微分の概念が述べられているし,積分可能条件を使ってクラペイロン=クラウジウスの式が導出されているので,11年かかったのは数学の問題ではないだろう.
エントロピー導入に時間が必要だった理由を解く鍵は,エントロピーが定義された後で議論される10ページ程の「物理的表示」の説明にある.実は,この表示は1862年の論文で示されている.その論文では,最初に1854年のクラウジウス等式およびクラウジウス不等式の復習をし,「これらは厳密な数学的な証明がなされているとはいっても,それはなお理解されにくい抽象的な形を持っている.そこで,この法則のもたらす真の物理的な原因の探求に進みたいと思う.」と論文の動機を述べている.ただし,1862年の論文でも,物体に含まれる「状態変数としての熱量」や「熱によってされる内的および外的な仕事」が使われるので,すらすら読めない.そして,「物体の分散度」という新しい量が導入される.これらの概念は現代には存在しないので,21世紀の読者には解釈が必要になる.まるでパズルを解くようである.しばらく格闘すると分かった.物体の分散度とは「構成要素の配置のエントロピー」に他ならない.そして,状態変数としての熱量は「構成要素の運動エネルギー」であり,熱の変換値と呼ばれているのは「運動量空間のエントロピー」である.つまり,1862年の論文でエントロピー概念が登場しているのである.1865年の論文で物体の分散度は「配列の変換値」と認定され,変換に相当するギリシア語を使ってエントロピーと名付けられたのだった.
それでは,1854年から1862年までの8年は何だったのか.この理由が1862年の論文の冒頭に記されている.「私の法則の残りの部分について(発表を)今まで遅らせてきた.なぜなら物体に含まれる熱について現在まで広く行われてきた考え方と,明らかに異なる結果をそれがもたらすからである.したがって,それについて再検討することが望ましいと思われた.しかしながら,年とともにますます次のように確信するようになった.すなわち科学的基礎にもとづくより,むしろ大部分が慣習に基づいている.このような考え方にあまり大きな価値をおくべきではないと―.」状態量としての熱の概念と測定量の関係についての混乱が残っていたのである.例えば,クラウジウスは比熱と真の比熱を区別しようとしている.
今から考えれば何を迷っているのか分かりにくいかもしれない.しかし,歴史に沿って振り返ると,それまであった慣習の一部を捨てるのが簡単でなかったことが分かる.この転回を抑えてから,冒頭の1850年の論文に戻れば,言葉の翻訳もある程度まで可能だし,当時の状況も分かるのではないだろうか.そして,抽象的な考察をしながらも,クラウジウスは,気液転移,蒸気機関,熱電効果などの具体例を念頭においていた.例えば,1856年の論文で蒸気機関において非補償変換(現在のエントロピー生成)を具体的に計算しているし,1853年の論文では熱電効果の考察をしている.輻射に関する1864年の論文の解説とともにこれらの論文も本書では紹介されている.
本書は,科学史の資料として,専門家および熱力学の愛好家が手に取るような本かもしれない.しかし,エントロピーが熱力学を超えて発展しようとしている21世紀に,その誕生ドラマに触れるのも楽しいと思う.この紹介記事で興味を持った方がいれば幸いである.
(2014年1月16日原稿受付)
ゼロから学ぶ統計力学
加藤岳生
講談社,東京,2013,222p,21×15 cm,本体2,500円(ゼロから学ぶシリーズ)[学部・一般向]ISBN 978-4-06-154676-9
紹介者:小林 晃人(名大院理)
本書は統計力学の基本をわかりやすく解説することに特に注意を払われたうえで,幅広い読者が興味をもって読み進められるようにさまざまな工夫のなされた入門書である.
本文は語り口調の生きた言葉の講義形式によって進められる.エルゴード仮説,N次元超球の体積,位相空間など初学者が躓く原因になりやすい言葉は出てこない.それでいて平易な例や挿絵を多用することにより,さりげなく必要な知識は導入され,最終的に統計力学の骨格に当たる部分はすべて説明される.すなわち著者の言葉を借りれば「初学者にとって難解な言葉の使用をできるかぎり避け,これだけわかっていれば統計力学は大丈夫という内容を厳選した」教科書となっているのである.また講義形式の本文の合間に「おもしろゼミナール」と題された会話形式のコーナーが織り込まれている.ここではエルゴード仮説など本文では避けられた言葉がわかりやすく説明され,統計力学におけるそれらの概念の位置付けが理解できるようになっている.またこのコーナーでは物理学者の生態が学生の視点から描かれ,物理学者に対する親しみや興味を引く内容となっている.
本書は前提知識をできるかぎり必要としないように工夫がなされている.必要となる知識は高校までの物理の知識と大学初学年程度の微積分の知識だけである.多くの教科書では熱力学を基礎として統計力学に進む.しかし本書の重要な特徴の一つは,すべての熱力学の関係式を統計力学の考え方のみから導く点にある.熱力学が不要だというのではないが,熱力学で培われた概念を背景としつつも熱力学の助けを借りず,統計力学の枠組みの中に埋め込まれた熱力学の関係式を掘り起こしてゆく.したがって読者は予備知識としての熱力学の前提知識を要求されないのである.やがて本書は気相から液相への相転移現象で締めくくられる.ここでも平易な例と挿絵が多用され,著者一流のくだけた語り口でわかりやすく解説がなされている.そして相転移現象は熱力学量に異常な振る舞いがでる場所であること,数学的に言えば熱力学関数が特異点を持っていることが示される.この特異点を生じさせるメカニズムが統計力学に備わっていることの説明を以て,「統計力学のみがこの特異性を生み出せる学問である」という本書の結論にたどり着く.
統計力学に関する名著は多く,優れた教科書が刊行されているが,その中で本書は統計力学を初めて学ぶ人,最短経路で統計力学の知識を習得したい人,高校生で高校の数学や物理に飽き足らなくなっている人など,多くの読者のニーズに応えられるよう工夫がされている.本書を読破したならば,さらに進んだ教科書を読みこなすこともできると思われる.物性を専門としない学生に対しての講義・指導にあたられている会員にもぜひ一度手に取っていただきたい良書である.
(2013年9月9日原稿受付)
Lectures on Quantum Mechanics
S. Weinberg
Cambridge Univ. Press,New York,2013,xix+358p,25×18 cm,$75.00[大学院・学部向]ISBN 978-1-107-02872-2
紹介者:藤川 和男(理研仁科セ)
Weinbergが書いた量子力学の教科書ということで,一体どのような教科書なのだろうか,一昔前のLandau-
Lifshitzの『古典力学』とか『場の古典論』のような全く斬新な見方から量子力学を再構成しているのだろうか,と考えながらページを開いた.最初目次を見て非常に手堅い教科書という印象を持ったが,読んでみると過去の教科書にないトピックスも多く含まれており所々に工夫が見られた.また類書には見られない量子力学の解釈(コペンハーゲン解釈)に対するかなり詳細な個人的見解が与えられており期待に反しない楽しい書物である.評者の個人的な経験になるが,Weinbergのカイラル対称性の自発的な破れに関する講義を1970年のBrandeis大学での夏の学校(大学院生から博士研究員向けのもの)で聞いたときに,驚く程手堅く一歩一歩計算をして,学生に分からせながら講義をしていたことを思い起こした.その意味では,この教科書はWeinbergらしい実際に計算して納得できることに重点をおいて親切に書かれた教科書と言える.いわゆるヒッグス機構を用いて,電磁相互作用と弱い相互作用の統一理論を提案するという大きな業績を上げた研究者ではあるが,そのスタイルはFeynmanとかLandauとは違っている.
著者も最初に書いているように,標準的な量子力学の教科書としてはDiracによるものとSchiffによるものがある.Diracの教科書は量子力学とは何かがわからなくなった時に読むと明快になり,Schiffの教科書はひたすら量子力学に地道に慣れるというスタイルである.Weinbergが本書で提案しているのは,過去の教科書の内容を整理して論理的に理解しやすい形に再構成し,同時に最近の量子力学の基礎に関係した発展およびこれまでに取り上げられなかったテーマ(例えば対称性の考察等)を加えて,現代的な視点から統一的に議論することである.レベルはアメリカの大学院での1年間の講義を想定している.日本で言えば,残念ながらこのレベルの講義はないが,学部の4年生レベル以上の学生が直接の対象と言える.(余談になるが,日本の大学院での基礎科目の講義は今後大いに工夫する必要がある.) 本書の記述は,理路整然としておりWeinbergらしく明快で見事である.断熱位相(Berry位相)とかエンタングルメント等も簡潔に説明されているが,Weinbergによるこれらのテーマの批判的な評価を含むより詳細な解説が将来期待されるところである.
シュレーディンガー方程式との類推でDirac方程式を議論するのは,その本質の理解には繋がらないという理由で,Dirac方程式を本書では一切議論していない.著者の言う通りであるが,他方Dirac方程式による水素原子の解とか最近物性物理で重要なスピン・軌道結合の自然な導出等は他の教科書を参照する必要がある.
本書は量子力学を勉強する学部高学年から大学院の学生に新鮮な構成の教科書を提供すると同時に,今後日本人の研究者が教科書(過去にも力作が見られたが)を書くときにも大いに参考になるのではないか.
(2013年9月3日原稿受付)
原子核物理学
滝川 昇
朝倉書店,東京,2013,vii+243p,21×15 cm,本体3,800円(現代物理学[基礎シリーズ]第8巻)[大学院・学部向]ISBN 978-4-254-13778-1
紹介者:松柳 研一(理研仁科セ)
著者は長年にわたり原子核論のフロンティアで活躍されてきた.大学・高校の物理教育にも熱心に取り組まれてきた.これらの経験が随所に活かされており,広い分野の研究者にも原子核物理学の基礎知識を更新するのに役立つだろう.前半で核力と原子核構造に関する基本的な知識を概観し,後半で非相対論的および相対論的平均場モデルを微視的に導出する道筋を丁寧に説明している.ここでは量子多体系における密度依存有効相互作用や原子核に超流動性をもたらす対相関についても書かれている.「平均場のシェル構造」と「原子核の形の変形」の関係についても平易な解説を与えている.近年,原子核と核物質に対する微視的平均場理論は密度汎関数法の観点から見直され著しい進展をみせている.このような進展を反映した入門的教科書の出版が望まれていた.本書はその期待に応えている.また,量子力学の半古典近似を用いて原子核現象への物理的理解を深めていることも本書の魅力となっている.半古典論の基礎的事項を要約した付録もついている.核反応論は系統的には取り扱われていないが,核構造論と関係する箇所で部分的に説明されている. 現代の原子核物理学はきわめて広範な現象を対象としているため,200ページ余りの教科書でその魅力を伝えるのは容易なことではない.学生にしっかりした基礎知識を身につけてもらうことを目的に,量子力学の初歩的な知識から出発し,議論の筋道を失わず徐々に高度な理論に進む道案内をして,その過程で現在の研究のフロンティアにも触れようと,著者はさまざまな工夫を凝らしている.豊富な演習・課題に加えて,随所に話題・余談をうまく織り込み,沢山の脚注で補足説明を与えている.更に,tea timeのコラムで核物質の相図,超重元素,超変形状態,元素合成といった現代的なトピックスにも触れている.このような立体的な構成が本書の特長となっており,著者の講義やゼミの雰囲気が伝わってくる.演習・課題にはかなり骨の折れるものも多いが,学生が数式を段階的に導けるように配慮されている.これらはゼミなどで取り組むとよい.学生は本書によって原子核の世界の基本的な現象だけでなく,量子力学や統計物理学などが原子核という有限量子多体系の記述や理解にいかに用いられているかを学べるだろう. 巨大共鳴,高スピン状態,ソフトモードなど集団現象のダイナミクスについて記述が少ないのは残念であるが,200ページ余りの教科書では割愛せざるを得なかったであろう.しかし,この教科書で学んだことはより進んだ核構造・核反応論に進むためのしっかりした土台となる.最近活発に研究されている中性子過剰不安定核とハイパー核については,[展開シリーズ]の一冊として(他の著者による)新しい教科書が準備されているようである. (2013年8月30日原稿受付)
計算科学3;計算と物質
押山 淳,天能精一郎,杉野 修,大野かおる,今田正俊,高田康民
岩波書店,東京,2012,vii+292p,22×16 cm,本体3,800円(岩波講座)[専門・大学院向]ISBN 978-4-00-011303-8
紹介者:有田亮太郎(東大院工)
今日,計算機を用いて物質内部の原子核や電子の振る舞いを記述するアプローチは「京」コンピュータに代表される計算機自身の能力の発達と,計算科学の発展に伴ってその重要性が急速に増している.前世紀においては到底実行不可能であった高度の近似を用いた精度の高い計算,多数の原子群からなる物質に対する計算,電子遷移から原子構造変化までの長時間シミュレーションなどが活発に行われ,精度,空間,時間の軸における目覚ましい進展によって,物質科学における新しい潮流が作りあげられている. 本書は,この計算機を活用した物質科学の最前線を解説した専門書である.方法論の背後にある基礎理論から,最近の研究例,次世代スパコンを活用する上での将来課題を幅広く取り扱っている. まず,第1章において本書の目的とその構成の概要がまとめられ,第2章において電子系,格子系のハミルトニアンやグリーン関数法や経路積分法といった理論手法など,第3章以下で共通に用いられる基礎事項がまとめられている.第3章では量子化学で用いられる様々な方法論の理論的背景,計算コストと精度についてコンパクトな解説が与えられている.第4章は密度汎関数理論,時間依存密度汎関数理論が解説されている.同じ岩波講座の現代物理学叢書『固体―構造と物性』金森順次郎ほか著に比べるとハイブリッド汎関数やフォノンを取り扱う密度汎関数摂動理論についてなど,より新しい内容が盛り込まれている.第5章は物質の動的性質を調べる計算手法が取り扱われている.カー・パリネロ法から核の量子効果,非ボルンオッペンハイマーダイナミクスなどの最近の研究成果までがわかりやすく解説されている.第6章では,物質のより正確な電子励起スペクトルを計算するためのアプローチとしてグリーン関数の方法とその応用が詳述されている.GW近似および関連する手法についての和書は珍しく,摂動論に基づく第一原理手法の現状を整理,理解するのに役立つと考えられる.第7章では,強相関電子系を取り扱う手法として,様々な波動関数法の解説が行われている.その後,密度汎関数理論の方法と波動関数法の一つの融合のあり方として,階層的強相関第一原理手法の考え方が議論されている.この分野については英文による優れたreviewが出版されているが,和書としてはおそらく最初のもので,大学院生の入門書としても適している.第8章では超伝導転移温度の第一原理計算が取り扱われている.3節で解説される超伝導密度汎関数理論は,和書のみならず洋書でも教科書がまだ出版されていないと思われるが,今後の超伝導研究にとって重要な役割を果たすと考える.この分野の研究人口を増やす上でも貴重な書籍になると期待される. 以上のように,本書では約300ページという限られた紙幅に,計算機を使った物質科学の最前線が数多く盛り込まれている.巻末には興味をもった読者がさらに詳しく勉強するための参考文献も適切な分量で選ばれており,大学院生から専門家まで,幅広い読者層に有益な専門書であると言える. (2013年8月26日原稿受付)
The Theoretical Minimum; What You Need to Know to Start Doing Physics
L. Susskind,G. Hrabovsky
Basic Books,New York,2013,xi+238p,22×15 cm,$26.99[学部・一般向]ISBN 978-0-465-02811-5
紹介者:米谷 民明(放送大学)
"Theoretical Minimum"はランダウスクールの教育方針として有名な標語だが,本書での意味は違う.Scientific American式解説のレベルではなく,数式も使って本当の物理を学びたいという一般人のためのミニマムだ.Susskind氏(1940年生,以下S氏と略)は弦理論,QCD,ブラックホールの量子物理における独創的業績で高名な理論物理学者である.彼はスタンフォード大学でContinuing Studies programの講義を担当して,前述のような希望を持つ社会人が多いことを認識し,本書のもとになるコースを企画した.共著者Hrabovsky氏は,それをインターネットを通じて知り本にすることを提案し実を結んだのが本書である. 評者は学生時代からS氏の仕事の独特なスタイルに惹かれてきた.序文冒頭の「説明のために一番よい方法を考えることが,自分にとって理解を深める最良の方法だ」は,いかにも彼らしい.15年ほど前,彼の研究室に1ヶ月ほど滞在したときも,彼から私への最初の問いかけは「弦理論から重力が出るのを式なしで説明するにはどうやればよいか」であったと記憶している. Lecture 1は,古典力学の決定論的構造や状態の考え方を離散時間と有限自由度の例で説明する.二つのInterludeとLecture 2までは,主にベクトル空間,微分積分等の数学的準備の説明に充てられる.Lecture 3から力学の本論に入り,さらに数学の準備を交えながら,最小作用の原理,対称性と保存則,ハミルトン形式,相空間,ポアソン括弧等,標準の力学コースの解析力学に相当する内容が,ウイットに富む前置き付きで,生き生きとした口調で語られる.最後は,電磁気力を扱い,ゲージ変換の重要性を強調した後,「ここまで付き合ってきた読者はTheoretical Minimumを知ったわけです.では,量子力学で会いましょう.」で結ばれる. 評者のような理論家にとっては,本書の内容・題材はごく自然で違和感は感じない.たまたま評者自身も東大定年後,放送大学で社会人学生に教える立場になり,2013年春に出版した力学テキストの解析力学に関する内容は,結果的に本書のミニマムとほぼ重なり,より凝縮してはあるが,もう少し肉付けを与え,現在執筆中の量子力学に向けてHamilton-Jacobiなど,二三のテーマを加えた恰好になっている.勿論,本書の「ミニマム」は,解析力学を深く会得するには足りないが,出発点としてはまことに適切であるとともに,S氏の個性がにじみ出た魅力的な本と言える.様々な環境で物理を教える読者諸氏に参考になるだろう.なお,本書を補う題材や問の答,等がwww.madscitech.org/tmで公開されている. (2013年8月4日原稿受付)
オープンサイエンス革命
マイケル・ニールセン著,高橋 洋訳
紀伊國屋書店,東京,2013,398p,20×14 cm,本体2,200円[専門~一般向]ISBN 978-4-314-01104-4
紹介者:北野 正雄(京大工)
マイケル・ニールセンは量子情報のバイブルともいうべき,Quantum Computation and Quantum Information(2000)の著者として,また同分野の研究者として有名である.最近はライターとしての活動に専念するようになり,ネットワーク時代における新たな科学の方法論を提唱,その啓発活動に力を注いでいる.本書はその集大成で,"Reinventing Discovery ― The New Era of Networked Science"と題されている.ニールセンは,インターネットによって可能となったネットワーク上の知的協働作業の潜在的可能性に注目している.実例として,フィールズ賞数学者が未解決問題をブログに公開し,一般読者との議論を通して解決に到達した「ポリマス・プロジェクト」,ネット上の素人集団がチェスの世界チャンピオンと互角に戦った「カスパロフ対ワールド」,ハッブル望遠鏡の銀河画像の公開分類プロジェクト「ギャラクシー・ズー」,パズルファンによるたんぱく質の立体構造解析「フォールド・イット」などの例が紹介されている.さらに分野を超えたものとして,リナックスOS,プレプリント・サーバarXiv,ウィキペディアなどが挙げられている.ニールセンはこれらの例を通して,インターネットによって可能となった「集合知」を活用した新たな科学の枠組みの構築を提案している.科学者らしく,単なる思いつきではなく,実例を失敗や問題点を含めて冷静に分析し,今後の方向性を探っている.科学のオープン化への障害要因として,1980年代以降の特許重視政策が,研究成果の公共財としての性格を弱めていること,論文数などによる研究者の評価が強化された結果,共有知への貢献のインセンティブが働かなくなっていることなどを挙げている.さらには,ネットワークツールやオープン化は科学の本質とは無関係という保守的な考え方も負の要因になっていると考察している.ニールセンは誰にでも始められるオープン化の小さな第一歩として,各自がプログラムやデータを整理してオンライン公開することを勧めている.ツールの整備は,科学の進歩にとって論文執筆と同等に重要であり,これらを評価する仕組が必要だと述べている.公開すべきプログラムなどを持たない人でも,学術雑誌に投稿した論文を,並行してプレプリントサーバや大学等のレポジトリ,あるいは個人のホームページで公開することで,オープン化に貢献できる.本書で指摘されているように,公的資金で補助された成果物について,一般の人々のアクセスを確保することは当然の義務だといえる.現在,大半の学会,出版社は著者に対し公開の権利を一定の条件下で認めており,著者の心がけでオープンアクセスが実現できるのである.将来を担う若い研究者はもちろん,科学政策に係わる人々にもぜひ読んでいただきたい一冊である. (2013年7月15日原稿受付)
現代の熱力学
白井光雲
共立出版,東京,2011,x+309p,26×18 cm,本体3,600円[学部向]ISBN 978-4-320-03466-2
紹介者:村山 能宏(東京農工大工)
物理は実学である.このことを改めて実感した一冊である. 大学における物理教育の現場では,学生は将来物理の専門家になるために物理を学ぶのではなく,あらゆる科学,技術,産業に通ずる基盤科目として物理を学ぶ場合が多い.そのような現場では,学問としての面白さを伝えるだけでは不十分であり,身の周りの現象や先端科学,技術との関係を伝えることにより,はじめて「物理の実力」が伝わるように思う.具体的な問題に対し,基本となる原理や数式からおおざっぱに数値を見積もることは,現象の本質を捉えようとする物理の醍醐味であり,物理の「面白さ」と「実力」を伝えることができる最良の機会である.本書に記載されている豊富な例題,問題,トピックスは,熱力学の「面白さ」と「実力」を伝える格好の材料であり,熱力学に関してこれだけの実例を取り上げている物理の教科書は見当たらないように思う.その上,基本原理の記述や数式,物理量の意味についても,安易にごまかすことなく丁寧に説明されており,著者のこだわりが伝わってくるとともに,熱力学の魅力を味わうこともできる. 本書は,著者が冒頭で述べているように,「熱力学は現実の問題を解決するために学ぶ」という立場で書かれている.教科書や参考書には著者と読者の相性があり,理解を深める最良の策は多くの書物(考え方)に触れることであろう.その一つとして,本書を一度講義で用いてみたくなり,そしてすでに熱力学を学んだ人ではなく,本書を通して初めて熱力学を学んだ学生たちに感想を聞いてみたくなった.(誤解を恐れずに言えば)専門家の卵に対してではなく,将来物理を専門としない人たちに物理の「面白さ」と「実力」を伝えることが,物理教育に携わる者たちの責務ではないだろうか.そんな思いを強くした一冊である. (2013年6月27日原稿受付)
だれが原子をみたか
江沢 洋
岩波書店,東京,2013,xv+385p,15×11 cm,本体1,420円(岩波現代文庫 / 学術281)[一般向]ISBN 978-4-00-600281-7
紹介者:長谷川 修司(東大理)
走査トンネル顕微鏡や電子顕微鏡をつかって研究してきた評者には,「だれが原子をみたか」というタイトルがとても魅力的にみえたので意気込んで読み始めたが,良い意味で期待は裏切られた.話はブラウン運動を軸にして,原子や分子の実在を人類が確信していく過程を丁寧におった"大河ドラマ"である.そこに,いくつかの歴史的実験を筆者らがみずから追試していく様子が挿入されており,単なる歴史書ではなく,実感をもって偉人たちの発見を追体験できるというユニークな色付けがされている.高校から大学初年程度の読者を想定した稀に見る良質の教養書といえよう.講義でつかう教科書でもなければ特定分野の専門書でもない,本書のような教養書が学びを豊かにしてくれることを実感できる.1976年の初版本が,昨年,文庫版で再刊されたのは嬉しい限りで,古典として読みつがれることを願う.空気の重さの議論など,大学の先生方にとっては試験問題のネタ探しにも活用できそうな一冊である. 古代ギリシャまでさかのぼる原子論が実験による実証科学の俎上に載るきっかけとなったのは,ブラウンによる水面に浮かべた花粉の動きの顕微鏡観察である.筆者らは,ブラウンの真似をして花粉や泥,アルミナ粉末などの顕微鏡観察を実際に行って,「ブラウン運動するのは多くの本がいうような花粉そのものではなく,花粉がパンクしてプッと吐きだす微粒子たち」であることを"発見"している.最後には,微粒子の平均二乗変位が経過時間の平方根に比例するというアインシュタインの理論とペランの実験によって,水分子による衝突がブラウン運動を引き起こしていることが明快に示される.そこにいたるまでに大気圧の発見,真空,気体分子運動論,ドルトンの原子量表,気体の化学反応など,19世紀から20世紀初頭にかけて発見された原子・分子を示唆する話題が盛り込まれている.圧巻は,トリチェリの水銀柱の実験を「水柱」で行ったパスカルの実験の再現である.数名の中学生らとともに,谷川にかかる橋の上から吊るした10 m程度の長さのビニール管に入れた「水柱」を作って大気圧を測定した.水柱から出てくる気泡(水の脱気が重要!)や水面の振動など,実験してみなければわからない"新発見"があったりして実験を楽しんでいる様子がいきいきと描かれている.統計力学の基礎としてサイコロを使った実験を行い,「デタラメ数の和の黄金率」なる"法則"をデモンストレーションしてアインシュタインのブラウン運動の理論につなげているところも極めて面白い. 原子の実在を確立するには長い時間と多数の科学者の寄与が必要だったが,それは,原子論反対派が強力だったからである.原子のような「目には見えないもの」で説明する科学など科学ではない,というマッハら反対派の気持ちもわからないわけではない.ここで頭をよぎったのが,19世紀末から20世紀初頭にかけて,真空での電磁波伝播の媒質として広く存在が信じられた「エーテル」なる「目には見えないもの」である.原子の場合と違ってエーテルは存在が否定されたが,そこから生み出された理論や実験は,その後の物理学の発展に大いに寄与した.20世紀から21世紀にかけてまた同じような「目には見えないもの」,ダークマターなるものが登場して物理学が構築され始めている.マッハ流にいえば,ダークマターなど「目には見えないもの」で説明する科学は科学でないということになるが,はたして100年後,原子のように肯定されるのか,それともエーテルのように歴史から消え去るのか.「だれがダークマターを見たか」なる本が書けるのはいつなのか. (2013年5月16日原稿受付)
ネオジム磁石のすべて;レアアースで地球(アース)を守ろう
佐川眞人監修
アグネ技術センター,東京,2011,vii+204p,21×15 cm,本体2,800円[専門~学部向]ISBN 978-4-901496-58-2
紹介者:溝畑 典宏(和歌山市)
本書は発見者佐川眞人監修,各分野の第一人者11名による著作である.佐川氏は2012年の日本国際賞受賞者であり,受賞講演は賞のWebのビデオのサイト(YouTube)で見られる.ネオジム磁石Nd2Fe14Bはハイブリッド車・携帯電話・MRIに使われている. 最初に勧めたいのは,1章ネオジム磁石はどのようにして生まれ,育ったのか(浜野),11章ネオジム磁石発明者の述懐(佐川)である.発見のきっかけは1978年の浜野氏の学会発表(希土類-Fe磁石に関する)にあるという.発表を聞いて佐川氏は,Fe-Fe距離をホウ素で伸ばせばキュリー温度を上げられると考え,実験開始後2-3カ月でNdFeB系を突き止めた.この発見から磁石に適した合金組織に仕上げるまで4年かかるわけだが,発見の早さは羨ましい. 発見当初の最大磁気エネルギー積は(BH)max=272 kJ/m3であり,その後も440 kJ/m3まで向上した.添加物もあろうが,Tcが1 Kも上がらない超伝導体MgB2と比べると面白い特性である.(評者の関心は超伝導である)KS鋼の1917年発見から2000年にかけて (BH)maxが上昇する推移(本書のp. 7)も超伝導とよく似ているので,超伝導研究者にも示唆に富む内容と思われる. よって,1章,11章からは,化合物を発見することと磁石化(製品化)の違い,磁石化の困難さ,そして発見の喜びが分かる. 2章ネオジム磁石はなぜ強いか,やさしい物理(小林)は,金森順次郎の解説を利用したもので,初学者に分かりやすい.Fe及びFe-Co合金,希土類 - 遷移金属の電子構造や強磁性の起源を,フント則,結合性準位,磁気モーメントなどの用語を交えてわかりやすく説明し,最後に元素Bの役割を述べている.役割は全く異なるが,Nd2Fe14BとMgB2とでBは大活躍である. FeとNdは,それぞれ鉄族遷移金属と希土類元素の中で,最も存在比が大きい元素であるから,この磁石は究極とも思えるが,まだキュリー温度が低い弱点も抱えていることから,9章ネオジム磁石を超える新磁石の研究(広沢)も興味深い.2節低希土類組成ハード磁性では,LaFeSiのキュリー温度を水素化により高めようとした徒労や,SmFeN等の窒化物や炭素化による研究が紹介される. 副題の"地球を守ろう"に関しては,6章ハイブリッド車用ネオジム磁石の進歩(近田)ではネオジム磁石を活用しモーターを小型化したカーメーカーの苦労が読み取れる. 最後,11章で佐川氏は吐露する.結局Fe-Fe間を伸ばすことは正しくなかった.しかし回りの反対を押切って粘ったことが良かったと.そういった彼の信条は自己顕示欲,自意識と表現される.本書からはこの信条の薫陶を受けられる. MRIの構造など詳細は同氏監修『永久磁石』(同社,2007)を参照するといいだろう. (2013年3月10日原稿受付)