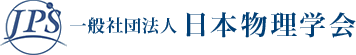会誌Vol.70(2015)「新著紹介」より
このページでは、物理学会誌「新著紹介」の欄より、一部を、紹介者のご了解の上で転載しています。ただし、転載にあたって多少の変更が加わっている場合もあります。また、価格等は掲載時のもので、変動があり得ます。
スピン流とトポロジカル絶縁体;量子物性とスピントロニクスの発展
齊藤英治,村上修一
共立出版,東京,2014,vii+160p,21×15 cm,本体2,000円(基本法則から読み解く物理学最前線1)[大学院・学部向]ISBN 978-4-320-03521-8
紹介者:佐藤 勝昭(JST)
本書は,スピン流を中心にスピントロニクスの基礎物理の最近の進展をまとめたものである.まえがきに「近年,スピン流の概念は物性物理やエレクトロニクスのいろいろな領域に登場するようになり,新しい現象を開拓する有用な指導原理の役割を果たしてきた」とあるように,「スピン流」の概念はごく最近になり注目を集めるようになった分野である.古典電磁気学では,電荷の流れとしての電流のみが取り扱われ,スピン流は無視されていた.この理由について,著者は次のように述べている.「スピン流はある程度の距離を流れると消えてしまう.この距離をスピン緩和長と呼び,通常の金属中では長くてもマイクロメートルスケールである.従って,せいぜいミリメートル以上の世界を主に扱ってきた古典物理学創設当時スピン流を考える必要がなかったのである」.
スピン流が観測され応用にまで結びつく道をひらいたのは,スピン流と電流を相互に変換するスピンホール効果および逆スピンホール効果の定式化と実験的検証が重要な役割を果たした.これには,村上修一氏(理論)と齊藤英治氏(実験)の貢献が非常に大きく,この2人をおいてスピン流を解説できる者はいないと評者は考える.
本書は第1章「はじめに」,第2章「スピン流」,第3章「スピン流の物性現象」,第4章「スピンホール効果と逆スピンホール効果」,第5章「ゲージ場とベリー曲率」,第6章「内因性スピンホール効果」,第7章「トポロジカル絶縁体」および付録「散乱理論」「スピン流回路理論」から構成される.
本書を読むための予備知識は,学部3年程度の基礎物理のみということになっており,実際,評者が試してみたところ,使われている式のほとんどをフォローすることができた.ただ時間を含むシュレーディンガー方程式を扱った経験が役立つので,大学院修士レベルの学識が必要であると感じた.
図も多く,随所に物理的意味をとらえやすいような説明が書かれている.例えば,スピンゼーベック効果の説明では,強磁性体の磁化が反時計回りに歳差運動することに本質があることが明快に書かれている.また,スピンホール効果の内因性機構には,ベリー曲率と呼ばれるバンドの微分幾何学的構造という抽象概念が本質的な役割をもつことが丁寧に説明されている.ベリー位相の空間にはモノポールが存在し,それが整数量子ホール効果をもたらし,さらには,トポロジカル絶縁体の概念にまで結びついている.最近話題のスピンに関連する物理現象が系統的に記述され,そのつながりと広がりに驚くとともに,感激さえおぼえた.
スピントロニクスに関わる研究者必読の好書である.
(2014年8月15日原稿受付)
伏見康治コレクション3;物理学者の描く世界像
伏見康治コレクション4;物理つみくさ集
伏見康治著,江沢 洋解説
日本評論社,東京,2013,vi+248p,22×16 cm,本体4,500円[広い読者向]ISBN 978-4-535-60348-6
日本評論社,東京,2013,v+284p,22×16 cm,本体4,500円[広い読者向]ISBN 978-4-535-60349-3
紹介者:並木 雅俊(高千穂大)
評者は,ロゲルギスト『物理の散歩道』のファンである.『物理の散歩道』は,1956年に結成された5~7人の物理屋からなる夕食を共にしながらの雑談記であるが,その内容は1本筋が通っているばかりかユニークであり,そのうえ自由を感じさせてくれる.この雑談記は『自然』*1に1959年2月より24年間にわたって連載された.伏見康治コレクション3巻と4巻の目次をみると,「すべての物質は透明か,不透明か」や「ラクダと針の穴」,「日のあたる学問,あたらない学問」,「なぜ右利きが多いのか」など,ロゲルギスト著の本を連想するタイトルが並んでいる.
『物理学者の描く世界像』は,15の章からなる「第I部 物理学者の描く世界像」と3つの章からなる「第II部 微分積分はやはり役に立った」から構成されている.第I部は,『科学朝日』*2に1964年1月号から1965年3月まで連載され,第II部は『数学セミナー』に1973年6月から8月まで連載されたものを江沢洋先生が編集・解説をした書である(この期間,伏見先生は名古屋大学プラズマ研究所所長,日本物理学会委員長(現在の会長)を歴任されている).
第I部は,「物の色」や「物の強さ」,「物と電磁気」,「物を熱するとき」,「物の電気磁気的性質」からなる.'一様な糸は強い力で引っ張っても切れない'というパラドキシカルな問いから始まっているなど,ロゲルギスト著との類似点はあるが,原子・分子レベルの考察が主で物理屋向きである.
第II部は,微積分が如何に役に立つのかを論じた文ではなく,*3中性子を物質に入射した際の速度分布関数の時間変化を論じたものである.アルキメデスの定理を用いて衝突後のエネルギー分布を導いているところ,線型操作をエネルギー量そのものではなく,その対数で行うことの解説にユニークさを感じた.
『物理つみくさ集』は,12の章からなる「第I部 物理つみくさ集」と6章からなる「第II部 M. C.エッシャーへの挑戦」から構成されている.いずれも『数学セミナー』に掲載された稿である.第I部は1966年6月号から1967年6月号までの12回連載された稿からなる.第II部は1966年4月号から1985年までに載った稿を江沢先生が編集したものである.
第I部は,いずれも基礎的で面白い.そのうえ,教科書では記述しきれない多くの題材があり,学習者がややもすると気づかない,あるいはそのため次の段階に進む際につまずきやすい箇所が扱われており,いたって教育的である.評者は,国際物理オリンピック(IPhO)の派遣に関わっているが,そこでの問題の解法に次元解析,相反定理,左右対称性を学んでいると楽に解法に近づく場合がある.IPhO候補者にも是非伝えたい技である.
0
1章の「ロケットをとばすには」は,第3巻第II部よりも,微分積分が如何に役に立つかを示すによい例であると感じた.第4巻は,ロゲルギスト著のように,読み手を誘い,それに考えさせる稿ばかりである.
全巻を通じて,物理の醍醐味を学ぶことができ,物理屋でよかったと感じることができる元気の出る本である.また,江沢先生の解説がとても読み手に優しい.
(2014年8月15日原稿受付)
- *1 『自然』は,1946年4月に創刊され,湯川秀樹「観測の理論」,伏見康治「原子物理学シリーズ」,朝永振一郎「スピンはめぐる」など読者を物理の世界に誘う多くの連載記事があったが,1984年5月号で休刊となった.
- *2 『科学朝日』は,1941年に創刊され,1996年に『サイアス』と改名され,読者獲得への努力はしたが2000年に休刊となった.
- *3 伏見先生は,「連続的に変化する量の,小さな変化を考えた」と述べている.
国際誌エディターが教えるアクセプトされる論文の書きかた
上出洋介
丸善,東京,2014,vii+223p,21×15 cm,本体2,000円[専門~学部向]ISBN 978-4-621-08690-2
紹介者:﨏 隆志(名大太陽地球環境研)
著者の専門は地球科学で,物理学会誌の読者とは比較的研究分野が近いほうだろう.論文作成に共通のマナーを学ぶと同時に,異分野で文化の違いは問題にならないのか,読書前のひとつの楽しみにしてみた.
本書は「書きかた」という指南書的なタイトルをもつが,はじめの2章は論文執筆を中心とした研究のありかたについて述べられている.論文数の推移や,論文の評価方法等が豊富な統計データとともに示される.自分の業績リストにあげた論文はどう扱われるのだろう,と気になる人は読んでみるといい.統計は自然科学の広い範囲にわたって分野別に示されている.インパクトファクターや評価指数の求め方が詳しく示されている点も興味深い.指数の利用にあたっては研究分野による特性を忘れてはならないことが強調されていて,先の心配(楽しみと書いたが)を打ち砕いてくれた.
4-6章が「指南書」にあたるが,その前の3章で論文投稿の基礎知識が述べられる.レフェリー,エディター,サブミット,アクセプト??? 初めての論文投稿時に戸惑う用語を丁寧に解説してくれる.「指南書」の内容とあわせて,本来これらは指導教員が教授すべきことかもしれない.とはいえ,すべての指導教員が英語も含めた系統的な論文作成指導をできるわけではない.若い研究者は本書で一般的なルールを学び,指導者は本書で自分の経験を補完しながら指導することで,著者の目的「アクセプトされる論文を書く」ことができるだろう.
エディターの視点で書かれた本書で興味深いのは,レフェリーの役割が多く述べられていることだろう.折しも,物理学会誌で最近「閲読のすすめ」が話題になっている.本書を「国際誌エディターが教えるレフェリーの心得」として読むことで,中堅研究者にも一層読み応えのある一冊になると思う.
著者が様々な論文スタイルを吟味するなかで,「共同論文」が議論される.個人の独創性を発揮するのが論文の重要な役割だとする著者にとって,多数の著者で執筆する論文に対する危機感が感じられる.物理学会誌読者の中には,このような研究に参加されている方が多いと思う.多人数著者の論文がどのような努力のもとで執筆されるか,どのように個々人の業績を評価するのか,どなたかが解説(反論?)していただけると面白いのではないかと勝手に期待する.
本書のタイトルを見て「自分には不要だ」と判断される方も多いと思う.しかし,1, 2章の統計や,エディターとレフェリーの役割に関する記述は中堅研究者にこそ有用な情報であり,また,自分の体験と照らして楽しめる内容だと思う.本書を読むと,単に著者の経験だけをもとに記した書ではなく,「論文執筆」というテーマについて著者が周到に調査をしたことが読み取れる.
論文を書く側ではなく,指導する側での紹介が主になってしまった.著者の意図からはずれるかもしれないが,研究室に一冊置き,論文執筆と論文執筆「指導」に役立つ書と言えるだろう.
(2014年9月1日原稿受付)
クォーク・グルーオン・プラズマの物理;実験室で再現する宇宙の始まり
秋葉康之
共立出版,東京,2014,vii+184p,21×15 cm,本体2,000円(基本法則から読み解く物理学最前線3)[専門~学部向]ISBN 978-4-320-03523-2
紹介者:平野 哲文(上智大理工)
「クォーク・グルーオン・プラズマ(以下QGP)」という用語はそろそろ市民権を得ただろうか? QGPは,初期宇宙を満たしていた原始物質,地球上で創られる最も熱い物質,と魅力的な言葉で紹介される一方,その物理を理解するためには多くのハードルが待ち構えている.私が学生の時以来,日本語で書かれた入門書は『クォーク・グルーオン・プラズマ』(神吉健著,丸善)しかなかった.初版から20年以上も経ち,RHICやLHCといった大型加速器の稼働によるQGPの発見,第一原理に基づく精密数値計算の発展など,QGPの物理をめぐる状況は探索の時代から,物性研究を展開する時代へと様変わりした.このような背景から,QGPの物理をちょっとかじってみようという他分野の研究者もおられるであろう.私自身教育をする立場になり,学生から何か日本語の入門書は?と訊かれても(英語の良い本やレビューは数あれど)なかなか答えに窮していたところであった.
本書は2011年に仁科記念賞を受賞した著者による日本語で書かれた待望の入門書である.国際共同実験で中心的な役割を果たしてきた著者だけあって,基本的な事項から最先端の実験成果までコンパクトに易しくまとめられている.
第1章ではQGP研究の目的や動機,著者なりのQGPの魅力が語られている.第2章から第4章では,クォークとグルーオンとそれらの性質,相対論的運動学,量子色力学が簡単にまとめられている.第5章から本格的なQGPの話題に移る.まず,クォークの閉じ込め,カイラル対称性という側面から,簡単な模型や様々な例を使って「QGPとは何か」が分かりやすく解説されている.最新の第一原理計算の結果もここで簡単に紹介されている.第6章ではQGP生成手段としての高エネルギー原子核衝突の物理が解説されている.合わせて紹介されている加速器や検出器の話は理論の研究者にも役に立つ.第7章でQGP発見の柱となった現象「ジェットクエンチング」と「楕円フロー」,及び,「QGPの温度測定」の結果がよくまとまっている.第8章では,まさに執筆時点に発表されたであろう最新の実験結果を踏まえ,今後の展望が述べられている.
この本自体は学部生向けに物理の最前線を紹介するシリーズの1冊として出版された.私の研究室の大学院生にも一通り読んでもらったが,入門書として概ね好評であった.ただし,天下り的に数式が導入される部分もある.学部生向けに場の理論を限られた紙面で解説するのは入門書の性格上無理であろう.この分野に参入し理論を深く理解しようとするならば,やはり,本格的な教科書やレビュー論文にあたる必要がある.
ともあれ本書は,QGP分野にこれから入っていく学生がまずはその物理の面白さと最新の現場の雰囲気を感じ取る,また,興味を持った他分野の研究者がここ10年近くの動向を手短に把握するという目的で読むのに良い入門書であると言える.
発展の早いこのQGP分野で10年後,20年後に本書を読み直したときにどのように感じるであろうか.今後も多くの進展があり,本書が良い意味で古臭くなるのも面白いと思う.そうなれば,著者には是非第2版の出版も期待したい.
(2014年9月5日原稿受付)
基礎からの量子力学
上村 洸,山本貴博
裳華房,東京,2013,xi+374p,21×15 cm,本体3,800円[学部向]ISBN 978-4-7853-2242-7
紹介者:中村 泰信(東大先端研)
2013年がボーアの原子模型提案100周年に当たり,多くの記念行事が開催されたことは記憶に新しい.ちょうど一世紀前に量子力学はその黎明期を迎えていた.その後20年弱の短い期間に,まさに奇跡のように量子力学の基礎理論体系が確立されることになる.そして100年後の現在,本書の第1章で「躍動する量子力学」と呼ばれているように,我々が日常生活で接する科学技術の中で,その発展においておよそ量子力学の助けを借りなかったものはないと言っても過言ではない.これからは物理を専攻としない学生にとっても「量子力学リテラシー」が必要であるというのが本書の著者の主張である.
本書は,量子力学を初めて学ぶ学生に向けた平易な教科書として書かれている.最近は量子力学の教え方にもいろいろなスタイルが取り入れられつつあるが,本書ではある意味王道に従って,量子力学の発展史を順に追うかたちで基礎概念の導入を行っている.ところどころにちりばめられた,著者の体験も交えたコラムも興味深く,スムーズに章を追っていくことができるように構成されている.
本書の特徴を挙げるとすると,物質科学における量子力学の役割が特に強調されている点であろう.7章・8章における原子・分子の量子力学的記述から,9章・10章へと連続的に自然なかたちで固体物理の基礎概念である周期ポテンシャル中のバンド理論が導入される.半導体や金属といった物質の特性の違いが固体中の電子の量子力学的振る舞いによって発現することが説明され,固体物理学への簡明な導入となっている.その反動として,11章(摂動論),12章(電子と光子の相互作用)の位置づけが,流れの中で少々わかりにくくなっているのはやむを得ないのかもしれない.
13章「配位子場の量子論」は遷移金属錯体や化合物の物性の理解に量子力学を適用する大変興味深いテーマであり,著者の思い入れが伝わってくる.ただし初学者には少々専門的かもしれない.それであっても,物性科学の幅広く奥深い分野への入り口として,ルビーがなぜ赤いのかを学ぶだけでも学生の興味を発展させることに役立つのではないだろうか.他の固体物理学の教科書や,著者の一人(上村)らによる,より高度な教科書『配位子場理論とその応用』(裳華房,東京,1969)へのイントロダクションと思えばよいであろう.
誕生後100年近く経っても,量子力学の世界は初学者にとって日常感覚と相容れない不思議にあふれた魅力的なものであることは変わらない.さらに近年のナノテクノロジー・物質科学の展開や量子情報科学の発展を例にとるまでもなく,量子力学の科学技術における役割はますます大きくなるばかりである.本書をきっかけに量子力学に関心を持ち,より深く学びたいと考える学生が増えることを期待したい.
(2014年7月6日原稿受付)
世界の見方の転換1;天文学の復興と天地学の提唱
世界の見方の転換2;地動説の提唱と宇宙論の相克
世界の見方の転換3;世界の一元化と天文学の改革
山本義隆
みすず書房,東京,2014,xxxi+356+41p,20×14 cm,本体3,400円[学部・一般向]ISBN 978-4-622-07804-3
みすず書房,東京,2014,v+342+38p,20×14 cm,本体3,400円[学部・一般向]ISBN 978-4-622-07805-0
みすず書房,東京,2014,vii+429+111+XXVIIIp,20×14 cm,本体3,800円[学部・一般向]ISBN 978-4-622-07806-7
紹介者:横山 雅彦
著者は近年ルネッサンス時代の科学技術文化についての研究を深め,『磁力と重力の発見』3巻(2003)と『16世紀文化革命』2巻(2007)という2冊の大著を相次いで発表し,広範囲な読者層から注目を浴びた.そしてシリーズ第三作目の本書も期待に違わぬ力作となっている.
本書の「あとがき」によれば,本書は以前の2著とともに三部作をなすものという.しかし三部作といっても,あらかじめ三部作の構想を着想し,その構想にしたがって次々と執筆していったものではない.第一作の執筆過程で,第二作の構想が生まれ,また第二作に対する鋭い書評が第三作を生み出す契機になったことは,氏自身率直に認めている.そのため,この三部作にはかなりの重複部分が存在し,時にそれが互いに整合的ではない場合も見受けられる.しかしそれはこの三部作の欠点などではなく,むしろ著者の長年にわたる思索と執筆の過程で生じた発展的不整合性となっている.
前口上は以上で止め,内容紹介に移りたいが,1,000頁を超える著作を3,500字程度(これが評者に与えられた文字数である)で,どのようにしたらよいか大いに悩ましい問題である.本書は,煮詰めて言えば,15世紀中葉のポイルバッハとレギオモンタヌスによるプトレマイオスの天動説的な数理天文学の復活から,コペルニクスによる太陽中心説(地動説)の提唱とティコ・ブラーエによる観測天文学の発展を経て,ケプラーによる惑星運動の三法則の確立までの歴史である.
本書には大きな特色が三つある.まず第一に,題名がコイレの大著のように『天文学革命』,あるいはそれに類したものではなく,『世界の見方の転換』という,一見聞き慣れない題名になっているが,そこには著者なりの自負がこめられているのである.この時代は同時に地理上の大発見の時代であり,これによって近代的な地理学が形成されるわけであるが,地理学は当時天文学と不離の関係にあり,しかも古代ギリシャの数理地理学を集大成したのも,同じプトレマイオスであってみれば,そのインパクトをも視野の中に収めなければ,「天文学革命」を充分に記述することはできないというのが著者独自の見解である.したがって「世界の見方」という言葉には,天文学的世界の見方と地理学的世界の見方という意味が同時にこめられているわけである.シリーズ第2作と重複する部分があるにもかかわらず,本書において,地理学的な諸問題が再述ないし発展させられているのは,そのような理由による.そしてこれは大きな成功を収めているように思われる.評者は特にゲンマ・フリジウスの仕事についての分析から学ぶところが多かった.オランダは16世紀後半から17世紀初頭にかけて,メルカトール,ステヴィン,ベークマンのような近代科学の先兵ともいうべき第一級の人物たちを生み出し,それがデカルトやパスカルの仕事へと継承されるのであるが,その発端となったのがゲンマ・フリジウスであることを著者から初めて学んだのである.
本書の第二の特色は,ルネッサンス時代の天文学的,地理学的思想の発展を,社会文化的なコンテキストと相即的に述べていることである.再びコイレの場合を例に挙げれば,コペルニクスもケプラーもいわばイデアの世界の人物として,極端に言えば思考機械として登場するにすぎないが─付言すれば,それはそれなりに充分興味深いのだが─,本書の登場人物は当時の社会文化的環境の中で生き生きと描かれていることである.その描写がもっとも成功していると思われるのは,レギオモンタヌスとメランヒトンについてである.レギオモンタヌスは,ヨーロッパ人でギリシャ語をきちんと学んだほとんど第一世代の科学者に属するが,彼はギリシャ生まれの大学者でヨーロッパに亡命し,カソリックの枢機卿にまで出世したベッサリオンの誘いに従い,その随行員になってイタリアに赴き,きわめて恵まれた環境でギリシャ語を習得できたのであった.レギオモンタヌスの主著は師のポイルバッハとの共著である『アルマゲスト綱要』であるが,それが画期的な著作となったのは,著者らの才能もさることながら─特にレギオモンタヌスは神童の誉れが高かった─,レギオモンタヌスが直接ギリシャ語の原典『数学集成(アルマゲスト)』を充分に読みこなしえたからであった.後に,イタリアから祖国ドイツに戻った彼は,当時ドイツで発明されたばかりの活版印刷術の大いなる可能性に注目し─彼より少し若いレオナルド・ダ・ヴィンチが活版印刷術にほとんど無関心だったのに比べると,大きな違いである─,南北ヨーロッパの交流の要衝の地でもあり,また精密品産業の一大中心地でもあったニュールンベルグに居住地を定め,天文観測に勤しむとともに天文学関連の出版活動に専念した.これによって彼は,ドイツにおける天文学研究の礎を築いたのである.その後,16世紀前半に天文学研究の重要性を大学制度としても確立したのが,宗教改革者ルッターの右腕として活躍し,「ゲルマニアの教師」とまでたたえられたメランヒトンである.この二人の活動によって,16世紀における天文学研究はいわばドイツの独擅場となったのである.著者によるこのあたりの記述は,社会文化史的にもユニークであり,繰り返し読むに値する.
第三の特色は,天文学研究における占星術の果たした役割の強調である.天文学史ではリップ・サービスとして占星術の意義について触れるのが慣例となっているが,著者はプトレマイオスの『テトラビブロス』やケプラーによる占星術改革をもその貪欲な胃袋でこなしたうえで,議論を展開している.評者は占星術については具体的にはほとんど何も知らないが,興味深く読むことができた.
以上のように評者は本書を高く評価する者であるが,賞賛だけでこの書評を終えるわけにはいかない.本書を幾度か読み返し,時には原著で著者の引用をチェックした評者としては,疑問に感じたいくつかの点を率直に指摘しておくこともその義務の一部と考えるのである.そこで,紙数の関係もあるので,ここでは細部に関する二つの事柄を批判的に見てみることにしよう.
(1)著者は第一章の註13(I. p. 41)において,「等化点」(エカント)に関して「equantまたはaequantはラテン語の動詞aequareから16世紀に造られた言葉であり......」と記しているが,実は13世紀のサクロボスコがすでにその『天球論』においてこの言葉を使用しており,さらに15世紀のポイルバッハもその『惑星の新理論』において使用している.著者自身これらの著作をラテン語で直接読んでいるはずであるが,それを見落としているのは,不可解である.おそらくこの言葉は翻訳の時代の12世紀にアラビア語からラテン語に移入されたものなのではないだろうか.
(2)つぎにコペルニクスの太陽中心説において重要な役割を果たしていることが近年ますます強調されるようになったsymmetriaの概念について.著者はこの言葉をときには「均衡」(たとえばII, p. 369)と訳し,またときには「対称性」(III, p. 872)と訳している.だが著者はこの概念がルネッサンス時代にどのような意味内容を有していたのかについてはまったく触れていない.しかし美術史においてはよく知られているように,この概念は美の本質を指す概念であり,全体と部分,部分と部分の間の「適正な比例ないし関係」を表現する概念だったのである.当時の社会的,学問的常識に真っ向から対立する太陽中心説は,最高の職人(=芸術家)たる神によって創造された世界は美的に優れたものであり,驚嘆すべきsymmetriaが存在すべきであるというコペルニクスの予断的な信念に支えられて初めて形成されえた理論だったのではないだろうか.
以上,細部に関する批判点を二つ挙げたが,これらは本書の力作たる所以をほとんど損なうものではない.この半世紀ほどの間に16-17世紀の天文学革命を主題とする大作が国外でも3冊出版された.一つはA.コイレ『天文学革命』(フランス語原版,1961)であり,もう一つはH.ブルーメンベルク『コペルニクス的宇宙の生成』(ドイツ語原版,1975;邦訳,I, II, III, 2002-2011)であり,3冊目はR. Westman: The Copernican Question(2011)である.いずれも特色のある(あるいは癖の強い)力作であるが,本書はこれらの3冊と較べてもけっしてひけを取らない著作であると言えよう.
(2014年9月15日原稿受付)
計算で身につくトポロジー
阿原一志
共立出版,東京,2013,ix+213p,21×15 cm,本体2,800円[専門~学部向]ISBN 978-4-320-11039-7
紹介者:鈴木 淳史(静岡大)
本書は,非専門家を念頭に予備知識をほぼ必要とせず,ホモロジー群の解説を行っている.記述は非常に具体的であり,まさに計算で身につくというタイトルにふさわしいものになっている.
近年,物理の諸分野において,ホモロジーや圏論などといった従来の物理数学の枠組みで教えられてこなかった種々の概念に出くわす機会が非常に増え,分野によっては必須というような状況になりつつある.学校で習わなかったことは,理解できても使いこなすのは大変難しいといった意味の文章を,あるところで読んだことがあるが,確かにその通りである.このギャップを埋めるためには,経験を積むしか無いのだが,抽象的な内容になればなるほど,なかなか具体的な例を取り扱うのは難しいし,自分で適切な例を設定すること自体が大変である.コホモロジーは,微分形式等に基づいているので手を動かしやすいが,ホモロジーは図形に根ざしているために大変である.一時,物理学科の学生の間でよく読まれた『物理学者のためのトポロジーと幾何学』(C.ナッシュ・S.セン著,マグロウヒル)などでもあまり丁寧な例をあげて説明してあるとはいいかねるように思う.その点,この本はまず適切な例を具体的に計算させて納得させた上で次に進む,という体裁をとっており,独学者にとって大変ありがたいものとなっている.また計算の詳細も丁寧に記されており,こちらの計算間違いで疑心暗鬼に陥ることが無いように配慮されている.ホモロジー代数の解説書として,従来,『ホモロジー代数』(河田敬義著,岩波基礎数学)が名高い.そこでの蛇の補題の証明も2ページ半ほどあり,数学書としては比較的詳細に記述されたものであるが,本書ではホモロジー群をH0とH1に限定しているにもかかわらず,6ページも使った大変に丁寧なものとなっている.他の記述の丁寧さも推して知るべし,であろう.
本書は二部構成となっており,第一部ではグラフの(すなわちH2以上を考えない)ホモロジー群について,第二部では曲面の(すなわちH2まで考える)ホモロジー群について閉曲面の分類定理まで解説を行っている.初学者にとっては(数学書にありがちな)いきなりHnまで議論する,となっていないところがウレシイ.
本書でこれらの基礎知識を身にしみこませた上で,さらに進んだ教科書,例えば前述の『ホモロジー代数』など読み進めると理解が深まるのではないか.また,この本の調子でもう少し進んだ話題まで丁寧に説明してほしい,とお考えの方は本著者が共著者のひとりになっている『パズルゲームで楽しむ写像類群入門』(阿原一志・逆井卓也著,日本評論社)など手にとられてはいかがか.
(2014年9月26日原稿受付)
クォーク・ハドロン物理学入門;真空の南部理論を基礎として
国広悌二
サイエンス社,東京,2013,v+155p,26×18cm,本体2,238円(SGCライブラリ-100)[専門~学部向] ISSN 4910054700831
保坂 淳 (阪大核物理研セ)
クォークとハドロンという言葉が1960年代に登場し半世紀が過ぎた現在,いずれも高等学校の教科書にも載るほどに市民権を得たものになった.この間,数多くの原著論文が生まれ,海外では単行本が出されてきた中,本書は日本語による,基礎から最近の話題までを系統的に扱う待望の書である.
クォーク・ハドロンという主題からは,ハドロンの構造や反応を連想するが,副題に目を移すと多体問題としての観点を重視していることが予想される.ハドロンの性質を語るときに,それが存在する真空を抜きにしては語れない.著者の国広氏の視点は「...物質と真空は相互規定的であり...何が物質かということは真空を決めることと等価である.(はじめに)」に如実に表れている.金属や固体物性との類推によって,温度や圧力などの環境変化に伴うハドロンの性質変化を追跡する研究において,国広氏は先駆的な研究を行ってきた.最近になり実験的な検証が進められている最先端の分野である.
2008年の南部陽一郎氏のノーベル賞授賞,2012年のHiggs粒子の発見と翌年のHiggs氏のノーベル賞授賞を機に,自発的対称性の破れに関心が持たれている.その考え方は多体問題の様々な局面で登場し,物質世界の多様性を説明する基盤を与える.クォークとハドロンの場合には,現在宇宙に見える物質質量の99%以上の起源を説明してくれる.さらに湯川のパイ中間子を説明し,原子核,従って原子の根幹となる部分をも説明する.
本書において国広氏は,場の理論の手法を基盤に上述の事象に潜む機構の本質を説明してくれる.1章で全体を概観した後に,2章で場の理論の基礎を導入する.場の理論に不慣れな読者は,標準的な教科書を別途手元に置いておくことを勧める.3章から本題に入り,カイラル対称性とQCDについての解説が始まる.以降はこの本の記述で十分追える構成になっている.4章ではカイラル対称性を持ったハドロンの低エネルギー有効理論として,線形シグマ模型を考察する.そして5章でハドロンをクォークの複合粒子として記述するQCDの有効理論として,南部ヨナラシニオ(NJL)模型を導入する.カイラル対称性の動的性質とそれに支配されるハドロンの性質を導き,最後に量子軸性異常を解説する.スカラー粒子の素性や,Hダイバリオンなど最近の話題にも触れている点が興味深い.5章以降は国広氏と共同研究者達が切り開いてきた分野であり,他の解説書などでは得がたいオリジナルな内容である.6章では有限温度の物質系を扱い,中性子星やQGP相転移の問題に触れ,系のソフトモードについて議論する.そして最後の7章で物質の性質として,クォーク数の感受率と密度揺らぎを紹介する.
本書は冒頭で述べたとおり,クォークとハドロンを題材にしながらも,一貫して場の理論としての真空を決め,その励起を探るという視点を貫いている.紹介されている様々な事象が,共通の原理に基づいて発現していることが理解できると思う.この点において,様々な研究者にとって有用な書物となるであろう.
(2014年10月4日原稿受付)
Magnetism and Magnetic Materials
J. M. D. Coey
Cambridge Univ. Press,New York,2010,xiii+617p,25×19cm,$95.00[専門・大学院向] ISBN 978-0-521-81614-4
合田 義弘 (東工大院総合理工)
磁性のカバーする領域は近年益々広がりを見せ,永久磁石材料など物理と材料科学との分野融合的な研究領域が形成されてきている.また,磁性の書物は内外に数々の名著が既にあるが,磁性発現の舞台である磁性材料に関しても詳細に記述している本はさほど多くないと思われる.
本書は磁性と磁性材料に関して体系的・網羅的にまとめられた教科書である.大書であるが,金森先生や近藤先生も含めた数々の磁性研究者の写真もしくは肖像画が関連する内容の頁に掲載されており,楽しみながら読み進めることができる.イントロダクションは古代文明における磁鉄鉱の記述から始まっており,最終の第15章では磁性流体・磁気電気化学・磁気浮上・生命科学での応用・ダイナモなどの地球惑星科学や天文物理学における磁性にも触れられている.物質科学を中心としつつも,磁性と磁性材料に関するあらゆる事項をカバーしようとする著者の意気込みが伝わってくる.記述は全体的に丁寧かつ要を得ており,全編にわたりSI単位系が用いられていることも好ましい.
第2章から第4章までは古典的な静磁気学と基礎的な磁性の電子論に関する記述となっており,学部レベルの電磁気学・量子力学の知識とその後の専門的な部分との橋渡しとなっている.また,強磁性・反強磁性などの磁気秩序(第5,6章)やドメインとヒステリシス(第7章)といった標準的なトピックに加えて,ナノスケールでの磁性(第8章)・磁気共鳴(第9章)・様々な実験手法(第10章)・磁性材料(第11章)・磁石材料の応用(第12,13章)・スピントロニクス(第14章)がカバーされている.特に,第11章で個々の磁性材料の具体的な結晶構造と性質が65頁にわたり記述されていることは本書の特徴の一つと言えよう.著者は実験家であるが,放射光等の最近の実験手法の発展のみならず密度汎関数理論による第一原理電子状態計算にも触れられており,磁気状態の説明等に効果的に用いられている.内容の広範さを考えると617という頁数はむしろコンパクトに良くまとまった結果とも言えるかもしれない.これから磁性・磁性材料の研究を始める大学院生は勿論のこと,専門家の参考書としても推薦したい.他分野の研究者にも手引書として手に取って頂きたい本である.
(2014年10月6日原稿受付)
数物系のためのミラー対称性入門;古典的ミラー対称性の幾何学的理解に向けて
秦泉寺雅夫
サイエンス社,東京,2014,v+207p,26×18 cm,本体2,500円(SGCライブラリ-109)[専門・大学院向] ISSN 4910054700749
立 川 裕 二 (東大院理)
場の量子論は,点粒子が時空を動いているのを量子的に扱う理論です.その拡張として,空間に一次元的に広がった弦を量子的に考察するのが超弦理論で,時空の次元が10次元にはなりますが,重力を量子的に無矛盾に扱えるという特徴があります.しかし,現実の時空は4次元ですから,残りの6次元をどうにかしないといけません.もっと積極的に捉えると,4次元の場の量子論には粒子の種類,相互作用の入れ方に選択肢があります.一方で,超弦理論は10次元の理論としてはほとんど選択肢がありません.ですから,4次元での粒子の種類等の選択肢が,残りの6次元空間がどういう形をしているか,という選択肢に対応する,というのが超弦理論の枠内では自然な考え方です.
このような考察で現実の素粒子物理もしくはその自然な拡張が記述できるかどうかは未解決ですが,その研究の過程で,新たな数学的現象が沢山発見されてきました.その典型例がミラー対称性です.内部空間として6次元空間Aを使うことと,全く別の6次元空間Bを使うことを考えましょう.内部空間が異なるのですから,残った4次元に出てくる物理は古典的には全く異なりますし,場の量子論を用いて調べても全く異なった結果が得られます.しかし,超弦理論の場合は,Aに対してBをうまく選ぶと,残った4次元に出てくる物理が等価になってしまう,ということが起きます.この際,AとBは互いにミラーである,と呼ばれます.
これは,80年代後半から90年代前半に発見され,その後,理論物理学者および数学者によって深く研究されており,物理への影響は兎も角,数学への影響はかなりのものであったと言えます.研究がはじまって四半世紀が経とうとしていますから,英語および日本語での成書は既に沢山あります.
しかしながら,数学者にとってこそ衝撃であったためか,それらの本は大抵数学者によって数学者向けに書かれたものでした.物理屋が大幅に関与して執筆された教科書1)もありますが,これは900頁にも及ぶ大著で,取り付くには相当の覚悟が要ります.ですから,ミラー対称性は,理論物理側で発見されたものであるにもかかわらず,理論物理側から勉強をはじめるために,適切な本が無かった,という逆説的な状況にあったわけです.
このギャップを閉じてくれる有り難い本が,日本での理論物理側のミラー対称性研究の第一人者によって書かれた,本書です.この本の特色はこれまで述べたことに加えてまだあります.それは,具体的に詳細にミラー対称性の両側での計算が述べられていて,雰囲気を理解するに留まらず,ミラー対称性を自分で確認することができるようになっていることです.さて,ミラー対称性の両側の確認は,多様体A内の二次元球面S2の数が,別の多様体Bに付随する微分方程式の解の挙動で決定される,という形をとります.微分方程式の解の挙動は,伝統的に理論物理屋の育つ過程で学ばされるものですから,このB側の解析の理論物理側での解説は,記事がいくつか見つからなくはありません.しかし,A側での数え上げの問題は,英語記事ですら,物理屋向けに書かれたものは,この本以前に私は見たことがありませんでした.ですから,これまでは,ミラー対称性の計算の物理屋向けの紹介,というと,B側だけ計算法を説明して,A側は数学者によるとこうである,と書いてあっただけなのですが,本書を読めば,A側もB側も自分で確認できる,というわけです.(実際に,私もこれまではB側のみの計算しか経験がなく,この本を得てはじめて,A側の計算をきちんと追ってみようとしているところだということを告白しておきます.)
おしまいに,本書はサイエンス社のSGCライブラリの一冊ですが,このシリーズではほぼ毎月,質の優れた日本語のモノグラフが出版されています.この内容を,日本語を解する読者で独占しておくのは,人類全体での知識の共有という観点からは,全く勿体無い話です.日本物理学会及び関連学会の援助もしくは斡旋で,全巻を系統だって英訳するわけにはいかないものでしょうか.
参考文献
1)Hori, et al.: Mirror symmetry (Clay Mathematical Monographs 1,アメリカ数学会,2003).
(2014年11月14日原稿受付)
非線形科学;同期する世界
蔵本由紀
集英社,東京,2014,247p,18×11 cm,本体760円(集英社新書)[広い読者向] ISBN 978-4-08-720737-8
竹 内 一 将 (東工大院理工)
振り子時計,ホタルの発光,歩行者の足並み....世の中には,自ら一定のリズムを刻んで何らかの時間変化を繰り返す「振動子」を多く見出すことができる.こうした振動子は,しばしば相互作用を介して同期する.振動子の同期と聞くと,何か古典物理の練習問題のようなものを想像される方もおられるかもしれないが,そうした印象は本書を一読すれば払拭されるだろう.
本書で扱う振動子とは,自ら周期的運動を生み出して振動する本質的に非線形・非平衡の現象であり,その多体効果である同期には数多くの非自明な物理学が潜んでいる.1)そして驚くべきは,心拍などの生理現象や,繁殖期の動物が見せる求愛行動など,様々な生命活動が同期という物理現象を巧みに利用しているという事実である.これはとりもなおさず,同期が医学や工学などにおいて様々に応用できることも意味している.
本書は,同期の数理的研究の第一人者である蔵本由紀氏により書かれた,一般向けの入門書である.同氏には,同じく集英社新書として出版され,書名も似た著書2)があるが,前著では様々な非線形非平衡現象を数式も交えつつ解説しているのに対し,今回の新著では対象を振動子とその同期現象に限定し,数式抜きで,それでいて明快さを損なうことなく本質を描き出している点で,随分と趣が異なる.話題が絞られたことで,むしろ同期というキーワードで結ばれる現象の多彩さが一層目を引く形となった.紹介される題材は,先に述べた例のほか,体内時計から電力供給ネットワーク,ロボット制御まで多岐にわたる.いずれも安易な比較ではなく,個々の分野で得られている知見や実データなどが丁寧に紹介されるため,非専門家はもちろん,非線形科学の研究者にとっても得るところが大きい.加えて,一般の読者向けには,複雑な現象を単純かつ抽象的なモデルで説明することの意義なども説明されており,まさに幅広い読者の知識欲に応える一冊であると思われる.
また本書では,科学的な解説に終始せず,話題によっては歴史や映画のシーンなども絡めて話が進んでいく.その語り口もどこか和やかであり,本書の読書感は,まるで物知りで親切な親戚の叔父さんに色々と面白い話を聞かせてもらっているかのようで,大変心地よい.研究者から学生,家族や友人まで,多くの方々が手に取れる一冊として,ぜひ推薦したい良書である.
参考文献
1)同期に関する専門書としては,例えばA. Pikovsky, M. Rosenblum and J. Kurths: Synchronization; A universal concept in nonlinear sciences(Cambridge Univ. Press, 2001)がよく知られている.
2)蔵本由紀:『非線形科学』(集英社,2007)
(2014年12月9日原稿受付)
Gauge/String Duality, Hot QCD and Heavy Ion Collisions
J. Casalderrey-Solana, H. Liu, D. Mateos, K. Rajagopal and U. A. Wiedemann
Cambridge Univ. Press,New York,2014,vi+460p,25×18 cm,$90.00[専門・大学院向] ISBN 978‒1‒107‒02246‒1
菅 本 晶 夫 (お茶大理)
2011年にプレプリントサーバーで見つけたこの本の原稿を,私は無謀にもテキストとして,2011年4月から7月まで,修士課程の院生相手に講義を行った.実は前年度に素粒子論研究室の学部学生4名の「RHIC とQGP」をテーマとする卒研指導を行った.RHICとはBNLにあるRelativistic Heavy Ion Collisionを行う加速器の名であり,QGPとはQuark Gluon Plasmaである.4名の学生はとても良くできたのでこの課題を見事にこなした.その内2名はお茶大大学院に進み,2名は他大学の大学院へ進学したが,2名が他大学から入学したので,計4名の修士1年生を相手に講義を行ったのである.
目標は素人向けの前半,即ち第1章~ 第5章(heavy ion phenomenology,finite temperature QCD,gauge/string duality)であり,専門家向けの後半第6章~第9章は講義しないという方針にした.本となった現在でも前半は同じ第1章~第5章であるが,後半は第6章~第10章となり,第7章が加わった.
この本は,RHICおよびLHC(LargeHadron Collider)における金あるいは鉛の原子核衝突実験で明らかになったQGPの発生とその性質を説明することから始まる.発生したQGPはほぼ完全流体であるが,原子核が正面衝突からずれて衝突する場合には独特の流れ(elliptic flow)が発生することから「ずり粘性」(shear viscosity)の値を測定したこと,QGP中を走るquark がエネルギーを失うこと(jet quenching)及びクォーコニウム(quarkと反quarkの複合粒子)の発生がQGPによって抑制されること等が解説される.流体力学を相対論的に記述するためにLandau-Lifshizの教科書『流体力学』(東京図書)の内容を,jet quenching を理解するためにEikonal近似,Glauber模型,Landau-Pomeranchuk-Migdal理論等を,文献を頼りに補足説明した.
最近の物理は狭くなって,これらの知識を知らなくても済ませる人も多いが,この本はそれを許さない.従って,講義をしてとても勉強になった.
次に強結合にあるゲージ理論が古典的重力理論で記述できるという「ゲージ/重力双対性」が素人にも分かるように解説される.
2011年の6月末にKEKの夏梅誠さんが「超弦理論の応用̶物理諸分野でのAdS/CFT双対性の使い方」(サイエンス社SGCとして出版)という集中講義をしてくれたので,学生さんにはそれを聞くように伝えて講義ではゲージ/重力双対性は割愛した.
加筆された第7章では,流体のエネルギー運動量テンソルを重力理論から見るとどうなるかを議論している.平衡状態から大きく外れた場合にも適応できるとするなど,今後の物理に新しい風が吹く予感がある.
この本は決して易しい本ではなく骨があるが,様々な物理がQGPを理解するために寄与していることを明確に示している.そのどれもが重要な物理である.自分の得意な分野から入って,他の分野の最近の発展を理解したいとする人には最適の本である.
研究につながる様々なアイデアをこの本から得ることができるだろう.
(2014年12月28日原稿受付)
重力とエントロピー;重力の熱力学的性質を理解するために
福間将文,酒谷雄峰
サイエンス社,東京,2014,vi+211p,26×18 cm,本体2,546 円(SGCライブラリ-112)[専 門・大学院向] ISSN 4910054701043
磯 暁 (KEK・総研大)
2015年はアインシュタインが一般相対性理論を提案して100年の節目にあたる.この長い歳月を経て,一般相対性理論は天体物理学や宇宙物理学で精密に検証されてきただけでなく,GPSなど私たちの生活をも陰で支えている.重力波も近いうちに観測されるだろう.
このように確立された基本理論でありながら,一般相対性理論で記述される重力理論にはまだ大きな謎が残されている.それがホーキングにより指摘された,重力理論,特にブラックホールが存在する時空のもつ不思議な熱力学的性質である.ホーキングは一般相対性理論の幾何学的な性質から,ブラックホールが温度やエントロピーという熱力学的量をもち,熱力学第一法則(エネルギー保存則)や第二法則(エントロピー増大則)が成り立つことを示した.さらにこの時空上での場の量子論を考えることで,ブラックホールが,幾何学的考察から導入された温度と同じ温度の輻射(ホーキング輻射)を放出することも明らかにした.一様な加速度運動をする観測者は有限温度に励起されること(ウンルー効果)も知られている.
これらの事実は,一般相対性理論が記述するマクロな時空の背後に,何らかの微視的な(すなわち統計力学的な)自由度が存在することを示唆する.実際,超弦理論を使ったブラックホールエントロピーの導出はこの考え方を支持しており,超弦理論が実在する証拠と考える研究者もいる.また,一般相対性理論から熱力学を導出するという論理を逆転させ,熱力学から一般相対性理論を導出しようという提案(ヤコブソン)もなされている.これらの成功にもかかわらず,重力がもつ熱力学的性質の真の意味はまだ謎に包まれている.
重力理論の熱力学的性質を理解するためには,測地線や超曲面の幾何学,重力の正準形式などの理解が欠かせない.しかしこれらの話題は少々高度であり,通常の一般相対性理論の教科書ではあまり扱われていない.本書では,これらの基本的な手法を丁寧に説明しながら,時空の熱力学の一般論までを解説している.1章で測地線束の満たすRaychaudhuri方程式やブラックホール時空の数学的性質を扱い,4章で重力の正準形式を解説している.エネルギーや角運動量といった重力理論の熱力学的量は,局所的な一般座標不変性に付随する保存量(ネーター電荷)である.このため,電磁理論の保存量である電荷がそれを囲む境界領域での電場の表面積分(ガウスの定理)で書けるように,重力の保存量も境界面での積分で表される.そこで重力理論の理解には境界項の扱いが本質的である.4章では,重力理論の境界項をラグランジュ形式(Gibbons-Hawking項)とハミルトン形式(Regge-Teitelboim電荷)の2通りの見方で扱い,後者の例として3次元漸近的AdS空間での無限次元対称性にまで言及している.また,ユークリッド化の手法による時空の熱力学を,小正準統計集団の立場から基礎付けたYork らの仕事の解説もあり面白い.5章では,1章と4章をベースにしてブラックホール熱力学の一般論が展開される.特に,ネーター電荷としてブラックホールエントロピーを解釈するWaldの方法が丁寧に解説されている.これは重力を熱力学的に解釈する上で要でありながら,日本語で書かれた解説は少なく貴重である.
これ以外の章は,上記の流れを補完する章となっておりそれぞれ独立に読める.逆にこのことに気付かないと,2章,3章で躓き,基本的な流れを見失う読者もいるかもしれない.2章では相対論的流体力学の観点からみたエントロピー,3章は曲がった時空の場の量子論における熱力学的性質(ウンルー効果)を扱っている.6章では,超弦理論,Dブレインの解説とそれを用いたブラックホールエントロピーの導出が明快に示されている.
このように本書は,重力がもつ熱力学的な性質を理解するための基本的な手法と概念が網羅されたツールブックである.同様なツールブックには,E.Poisson: A Relativist's Toolkit; The Mathematics of Black-Hole Mechanics(Cambridge Univ. Press, 2007)が隠れた"あんちょこ"として知られているが,本書はPoisson の本よりも高度で深みがあり幅広いトピックスを扱っている.記述も緻密で,腰を落ち着けて読めば必要な手法概念を理解できるだろう.
(2015年1月18日原稿受付)