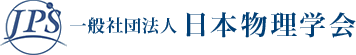会誌Vol.71(2016)「新著紹介」より
このページでは、物理学会誌「新著紹介」の欄より、一部を、紹介者のご了解の上で転載しています。ただし、転載にあたって多少の変更が加わっている場合もあります。また、価格等は掲載時のもので、変動があり得ます。
フラーレン・ナノチューブ・グラフェンの科学;ナノカーボンの世界
齋藤理一郎
共立出版,東京,2015,xi+163p,21×15 cm,本体2,160円(基本法則から読み解く物理学最前線5)[大学院~一般向] ISBN 978-4-320-03525-6
紹介者:小鍋 哲(東京理科大)
0次元物質のフラーレン,1次元物質のカーボンナノチューブ,そして2次元物質のグラフェン,これらのナノスケール炭素物質を総称してナノカーボンと呼ぶ.これらはその特異な構造に起因し,多くの興味深い特性を持つことから,基礎から応用にわたる幅広い分野において精力的に研究が行われている.一方で,分野があまりにも広がってしまったため,その全体像を掴むのが困難なのも事実である.そのような中,本書の目的は,物理学・化学・工学・材料科学・生物学へと拡大し続けている「ナノカーボンの世界を案内する旅のガイドブック(本書,まえがき)」である.啓蒙書と専門書の性格を兼ね備えながら,160ページ程度の限られたスペースにバランス良くまとめられており,著者の目標は十分に達成されている.
本書はどの章も単独で成り立っているので,読者の興味に応じ好きな箇所から読み進めることができる.前半部ではナノカーボンの世界について,高校生や一般の読者でもわかるように手際良くまとめられている.まず1章でナノカーボンについて概観した後,続く2章から5章までで,フラーレン,カーボンナノチューブ,グラフェンそれぞれの発見物語,結晶構造,合成方法,技術応用について順次述べられている.6章からの後半部は,ナノカーボンの電子物性について説明されている.6章ではナノカーボンの電子状態の特徴がその導出方法とともに非常にわかりやすく説明されている.7章ではカーボンナノチューブやグラフェンの低エネルギー有効理論であるディラック電子についての説明である.軌道反磁性,クライントンネリング,後方散乱の消失,バレースピンなどディラック電子に起因した特異な物性が簡潔にまとめられている.8章では,ラマン分光について,そのメカニズムの定性的説明と利用の仕方までが述べられている.後半部はいずれの章も内容は高度であるが,最小限の数式と著者ならではの噛み砕いた表現により,物理的ピクチャーをしっかりと身につけることができる.最後の9章では,ナノカーボンを利用したオールカーボン集積回路や太陽電池など最先端研究についていくつか紹介され,ナノカーボン研究の今後の展望や期待が述べられている.著者によるこれまでの著書(量子物理学,基礎固体物性)同様,充実した脚注も本書の特色の一つである(本文より分量が多いかもしれない).本文中の説明の足りない箇所を十分過ぎるほど補強するだけでなく,ユーモアあふれるコメントも有り,脚注だけでも楽しく読める.
本書をガイドに,「ナノカーボンの世界の入り口から少し入ったところまで(本書,ティータイム13)」を散策すれば,大学院生・若手研究者もナノカーボン研究分野に飛び込む準備はできるであろう.また,これまでナノカーボン分野で研究を続けてきた研究者にとっては,適度な分量に幅広い分野の内容がコンパクトにまとまっているので重宝する.そして何より,随所に科学者を目指す若者への著者からの熱いメッセージと親切なアドバイスが盛り込まれており,若い読者に対する著者のエールが聞こえてくる.次世代を担う中学生や高校生にも是非一読を薦めたい.
(2015年6月6日原稿受付)
ホログラフィー原理と量子エンタングルメント
高柳 匡
サイエンス社,東京,2014,v+176 p,26×18 cm,本体2,407円(SGCライブラリ-106)[専門・大学院向] ISSN 4910054700442
紹介者:奥西巧一(新潟大理)
ホログラフィーの原理やAdS/CFT対応は,著者のホームグラウンドである弦理論のキーワードである.一方,量子エンタングルメントはもともと量子情報分野より発生した概念である.現在,両者は融合し,素粒子論,量子情報,物性理論などの広範な領域の研究動向に大きな影響を与えるようになっている.自ら首を突っ込まないまでも,潜在的に興味を持っている方々も多いのではないだろうか.それゆえ,物性理論の研究者が本書の紹介をするということにも意味があるかと思う.しかし,広い分野すべての事情に通じているわけではないので,あくまで少し偏った見方であるとご理解いただきたい.雑誌『数理科学』に江口先生の書評1)もあるので,そちらも参考にしてくださるとよいと思う.
さて,本書は独創的な研究でこの分野をリードしている高柳氏自らが,ホログラフィーの原理と量子多体系のエンタングルメントに焦点を絞って解説したものであり,弦理論の専門的な知識はほとんど前提としない形で話が展開される.中心的な役割を果たすのが,重力における極小曲面の面積とエンタングルメントエントロピーを結びつける笠-高柳の公式だが,ホログラフィー一辺倒ではなく,共形場理論による説明と,ホログラフィーの原理にもとづく重力による説明が交互に現れる.技術的な詳細を必要最小限にとどめつつ,むしろ理論の要所や数式,そして結果の物理的な意味や位置づけにテンポの良い解説が割り振られており,導入から高度な内容,そして最前線まで一気に駆け抜けている印象を受ける.典型的な模型や現象を挙げながら解説しているので,抽象的な一般論にならずにイメージも掴みやすい.古典重力の知識をかじっていれば非専門家でも十分に楽しめるであろう.また,専門的に深く学びたい読者が巻末の文献に当たる際にも,本書の要所を押さえた解説は大いに理解の助けになると思う.
物性の立場からは,エンタングルメントの性質がブラックホールなどの概念と結びつくのは楽しいのだが,一方でなんでも重力で理解できるのか? と,少々不思議な感覚にとらわれるのも正直なところである.一因は,自分に弦理論も含めた背後の専門的な知識の蓄積が足りないことにある.しかし,もう一つ基本的な要因に,物性では時空を単なる物理系の入れ物とみなすことが多いのに対し,本書が逆方向の論理,すなわち,エンタングルメントの埋め込み方がむしろ時空の計量も決めるという,物理の新しい方向性に挑戦しようとしていることがあると思う.個人的な見方かもしれない.しかし,タイトルがAdS/CFT対応やゲージ重力対応ではなく,ホログラフィーの原理となっているところに,著者の意気込みと期待が表れているように感ずる.本書はゴールではなく,今後の展開への序章であると解釈するのがよいだろう.
参考文献
1)江口 徹:数理科学(サイエンス社)620(2015)60.
(2015年6月25日原稿受付)
Turbulent Transport in Magnetized Plasmas
W. Horton
World Scientific,Singapore,2012,xvi+501p,26×18 cm,$150.00[専門・大学院向]ISBN 978-981-4383-53-0
紹介者:渡邉智彦(名大理)
周知のように,核融合研究は,半世紀以上におよぶ努力のもとに営々と進められ,核燃焼プラズマの実現を目指したITER実験が(建設が順調に進めば)2020年代に開始される予定である.この間,プラズマの密度や温度に代表される閉じ込め性能の向上を阻んできた最大の要因が,本書の主題となるプラズマ中の異常輸送,すなわち,乱流輸送である.
非定常・非線形現象の代表例である乱流は,プラズマ中では電磁場揺動と結合し,非平衡な系の輸送を駆動する.さらに核融合や宇宙の無衝突プラズマでは,流体近似も成立せず,分布関数にもとづいた運動論的記述が不可欠となる.そのため,この問題に対する理論的に有効なアプローチは極めて限られる.
本書には,この困難な問題に対する著者の半世紀近くにわたる格闘の歴史が刻まれている.W. Horton先生は,テキサス大学においてプラズマ乱流輸送の理論研究に長年携わってきた,この分野の第一人者である.40有余年のキャリアにおいて,ドリフト波と呼ばれる磁場中でのプラズマ波動とその不安定性理論において数多くの業績を挙げられた.また80年代以降は,非線形理論や計算機シミュレーションにも取り組まれ,プラズマ乱流研究全般にわたって多彩な業績を残されている.本書は,これらの研究業績を縦糸に,また,旧ソ連,欧州,日本の研究者との交流を横糸にして織りなされた,プラズマ乱流輸送の専門書である.
構成としては,第1章で核融合研究の歴史を振り返り,引き続く数章で実験計測の紹介を交えながらドリフト波の基礎理論について説明している.トーラス・プラズマを対象とした乱流輸送のより専門的な話題は後半で扱われ,第9章の不純物輸送,第13章のイオン温度勾配不安定性,第14章の電子温度勾配駆動乱流,第15章の磁気リコネクション等が取り上げられている.
本書の特徴は,欧米の大規模な核融合プラズマだけでなく,基礎的な実験室プラズマや,我が国のトカマクおよびヘリカル型プラズマ等を含む多彩な実験に言及しつつ,なお著者自身の研究や着想を軸として,乱流輸送の幅広いテーマをカバーしている点にある.この力技は,Horton先生ならではである.また,磁気流体理論の限界と二流体理論や運動論の必要性についても,やや詳しく論じられている.一方,最近話題のゾーナル流や運動量輸送には,あまり紙面が割かれていない.
本書はプラズマ波動理論の基礎知識を仮定しており,この分野の初学者よりも専門家向けの構成となっている.また,著者の所属は核融合理論分野における日米科学技術協力の中心機関であり,Horton先生には,日本のプラズマ理論研究者の多くが知遇を得た.この国際協力の成果は,本書の重要な構成要素をなしている.表紙絵は,我が国の共同研究者(評者を含む)による乱流シミュレーション結果をデザインしたものであり(これも長年にわたる友好の証と感謝している),第12章および第13章で議論される.最後に,敢えて本書の難点を挙げるとすれば,共通した内容(イオン温度勾配不安定性等)を含む節が別々に繰り返し現れるため,全体的な構成が把握しにくいことである.ただ,これも著者の語り口を彷彿とさせ,また印象深い.
(2015年7月24日原稿受付)
ボーア革命;原子模型から量子力学へ
L. ローゼンフェルト著,江沢 洋著訳
日本評論社,東京,2015,v+197p,20×14 cm,本体2,200円[学部・一般向]ISBN 978-4-535-78766-7
紹介者:西尾成子(元日大理工)
2013年にボーアの原子構造の量子論100年を迎え,国内外で大小さまざまな記念行事が行われた.本書の著訳者・江沢は,仁科記念財団(仁科記念講演)と学習院大学とで,「ボーアの原子模型,革命から百年」と題する講演を行った.それらの講演をまとめたものが,2編からなる本書の第II編である.第I編は,ボーアの共同研究者であったローゼンフェルトが1963年に書いた,ボーア原子構造論の成立についての歴史的論考で,ボーア理論50年を迎えて出版されたボーアの3部作「原子と分子の構造について」の複製版に付けられた「解説」である.江沢によるこの「解説」の翻訳も,この複製が出されて間もなく,いまは発行されていない雑誌『自然』(1958年,4~6月号)に「ボーア原子模型の成立」と題して掲載された.本書では,当時付けられていた懇切丁寧な訳注がさらに加筆され,ボーアが第2部に加えるつもりで書いた磁性についての下書きも訳出されている.
第I編は,当時のローゼンフェルトならでは得られない資料(ボーアの手稿類,ボーアが師と仰ぐラザフォードをはじめ弟・ハラルや友人たちとの手紙など)を駆使して,ボーアの理論がいかにしてできあがったかに光を当てる.それらの資料は今ではボーア研究所のアーカイブやボーア全集に収められ,入手可能ではあるが,日本語で読めるのはありがたい.第II編では,ボーアの原子模型がなぜ革命といわれるのか,高校生でも大学初年生でも理解できるように,1913年前後の原子に関係する研究の状況を背景に,来るべき量子力学も視野に入れて説明され,第I編をよく補うものになっている.
50年前とはいえ,ローゼンフェルトの「解説」は今でも新鮮である.例えば,ボーアが1912年,学位取得後の留学を終えてマンチェスタ-を去るときにラザフォードに残した原子構造に関するメモ(ラザフォードメモといわれる)がある.それを見ておや?と思われる方が多いに違いない.そのメモでボーアが扱っているのは,原子内,分子内の電子配置であって,スペクトルについてはまったく触れられていないからである.教科書などに,古典論ではスペクトル公式が説明できないという困難を,ボーアは量子的な二つの基本仮定(いわゆる定常状態の角運動量の量子条件と振動数条件)を立てることによって解決した,とあり,はじめからスペクトル問題に取り組んでいた,と思われがちである.しかし実際には彼が水素スペクトルのバルマー公式を友人から知らされるのは1913年に入ってからであったという.さらに興味深いことは,バルマー公式を知ってから水素と水素型原子を論じた第1部を書き上げたのが,ボーアにしては異例に早いということである.ボーアは論文を書くにあたって,推敲に多大の時間をかけた.それが,1カ月足らずのうちに第1部を書き上げ,ラザフォードに送っているという.
いうまでもなく,ローゼンフェルトは「解説」をボーアの3部作が手元にあることを前提に書いている.要所要所は訳注に引用されているが,この機会に革命的なボーアの論文を読まれたらいかがであろうか.
(2015年7月27日原稿受付)
トポロジカル絶縁体入門
安藤陽一
講談社,東京,2014,ix+174p,21×15 cm,本体3,600円[専門~学部向]ISBN 978-4-06-153288-5
紹介者:佐藤昌利(京大基研)
物質は,多数の電子や原子によって作られており,そのため個々の電子や原子そのものとは異なる新しい性質を示す.物質が固体として示す多様な結晶構造や磁性,超伝導・超流動現象などは,そのような協調現象の典型例である.物質の示すこのような構造―相構造―は,物性物理の研究における中心課題の一つである.さらに,超伝導現象のアナロジーを素粒子論に求めた南部理論が,ヒッグス理論へと拡張され,最終的に素粒子論の標準模型(ワインバーグ・サラム理論)へと発展したように,相構造の理解は物性物理にとどまらず,広く他の領域の研究にも大きな影響を与えてきている.
相構造の理解に関する最近の著しい進歩は,波動関数のトポロジーによって区別される相が広く普遍的に存在することが明らかになったことであろう.1980年代初頭のサウレス・甲元・ナイチンゲール・デンナイスらの研究によって,整数量子ホール状態および分数量子ホール状態が波動関数のトポロジーによって特徴づけされることが知られていたが,量子ホール状態が強磁場下の2次元電子系という特殊な状況で実現されることもあり,長い間このような状態は特別な系でのみ可能であると考えられてきた.ところが,近年,磁場が印加されていない系や3次元物質においても,類似の相が可能であることが理論的に明らかになり,2007年に実際に実験でその存在が検証されるに至った.これを契機に,トポロジカル絶縁体・超伝導体と呼ばれるトポロジーで特徴づけ可能な物質群が存在すると広く認知されるようになった.本書は,この分野の実験的研究の第一人者である安藤陽一氏によるトポロジカル絶縁体・超伝導体の入門書である.
本書の特徴は,入門書と呼ぶにふさわしく,多くの事柄が基礎的なところからきちんと準備立てて説明がされていることである.まず,トポロジカル絶縁体の歴史が紹介され,初期の量子ホール効果のアイデアがどのように磁場のない系に拡張され,トポロジカル絶縁体の発見につながったか,が説明される.続いて,トポロジカル絶縁体を理解する上で必要なクラマース縮退やスピン軌道相互作用,ディラック方程式,固体中の電子の振る舞いに関するブロッホの定理などトポロジカル絶縁体を理解する上での基本事項が要領よく整理される.また,トポロジカル絶縁体の実験を理解する上で必要不可欠な手法である角度分解光電子分光および量子振動の概念がコンパクトに解説される.これらの準備の後,トポロジカル絶縁体で中心的役割を果たすトポロジカル数の説明へと進んでいく.
著者は実験家であるが,多くの式が省略なしできちんと導出が与えられているため,初学者であっても内容を把握できるようになっており,ゼミなどで輪講する本としても推奨できる.一方,後半部分には,トポロジカル絶縁体に関する主な実験成果も包括的に紹介されており,手っ取り早く,トポロジカル絶縁体に関する成果を知りたいという人にとっても,有益な本となっている.本全般に,著者の生き生きとした物理観が織り込まれており,専門外の読者にとっても面白く読めると思う.
本書は,日本語で書かれた数少ない本格的なトポロジカル絶縁体・超伝導体の教科書であり,この分野に新たに参入したいと考えている研究者はもちろんのこと,この分野の勉強をしたいと考えているすべての学生や他分野の研究者にもおすすめできる良書である.
(2015年7月26日原稿受付)
宇宙の物質はどのようにできたのか;素粒子から生命へ
日本物理学会編
日本評論社,東京,2015,vi+195p,21×15 cm,本体2,400円[学部・一般向]ISBN 978-4-535-78743-8
紹介者:吉田直紀(東大理)
起源の問題ほど人間の興味をそそるものはない.地球上で生命はどのように誕生したのか.元素はいつ,どこで生成されたのか.そして宇宙そのものはどのように誕生したのか.最も素朴な疑問とも言える起源の問題について,物理学,生物学,宇宙論の研究として取り組む研究者らが宇宙の進化と重ねあわせて語っていく.
本書は「物質」をテーマとして,初期宇宙の進化や元素合成,惑星の形成,さらには生体物質の探索に至るまでについて分かりやすく解説している.最近の大規模実験や宇宙観測,スーパーコンピューターシミュレーションの成果も含まれており,専門的な内容に興味がある読者も満足するだろう.
およそ138億年前のビッグバンによって宇宙は生まれ,やがて物質のもととなる素粒子が生成された(1, 2章).現代の巨大実験物理学はそのような初期宇宙の出来事を部分的に再現しつつある(3, 4章).宇宙では,分子を含む星間ガスから星が生まれ,星の中で生成された元素がまた宇宙空間へとばらまかれていく(5, 6章).このようなサイクルを繰り返すうちにやがて惑星系をもつ星が誕生し(7章),生命を育む環境が整っていく.有機物やアミノ酸のような生体分子がどのように生成されたかは大きな謎であり,生命の起源は「宇宙」と「生命」をつなぐ重要な鍵として捉えられるようになった(8章).
章ごとのテーマについては,歴史的な経緯だけではなく現在進行中の研究が臨場感をもって描かれており,各章の最後には未解明の謎も提示されるなど,さらなる研究への興味がわく構成になっている.
生命の誕生や宇宙創生など,根源的な謎に物理学の手法によって迫ることができるとは感動的でさえあり,また,そのための各種実験や観測の規模の大きさにはひたすら圧倒される.本書の後半では中性子星や宇宙のダークマターについての研究が紹介されており,そこでは,宇宙観測から地下実験まで,実に様々なアイデアに基づいた 研究が世界中で行われていることに読者は驚くだろう.
科学に興味ある一般の人はもちろん,高校生大学生には是非読んでもらいたい.具体的な研究テーマに関心のある大学生らにとっては,宇宙,物質,生命に関する研究のホットトピックを知る機会になるだろう.本書に触発されてさらに勉強を深める読者も多いのではないだろうか.各章末には参考文献もリストされており,そのような読者の欲求にもある程度応えるが,やや残念なことに,参考文献の多くが専門誌に掲載された原著論文になっている.それらは私のような専門の研究者でさえ敷居が高く,興味のままに手にとるのは難しい.しかし全般に,複雑な物理過程も平易な言葉で解説されており,補足や比喩を脚注に盛り込むなど,知的読み物として十分に楽しめる.興味のある章から読み進めてもよいし,宇宙進化の歴史とあわせて1章から順に読むのも楽しいだろう.
(2015年8月24日原稿受付)
場と時間空間の物理―電気,磁気,重力と相対性理論
米谷民明,岸根順一郎
放送大学教育振興会,東京,2014,290p,25×15 cm,本体3,200円[専門~学部向] ISBN 978-4-595-31511-4
紹介者:川合 光(京大院理)
電磁気学から特殊相対論,一般相対論にいたるまでの道筋をバランスよく明快に示した名著である.前半は,高校で学ぶ電磁気学からはじめて,マクスウェル方程式が自然に理解できるように議論が展開されている.実際,最初に電磁場の定義とベクトル解析を簡潔にまとめた後,マクスウェル方程式の積分形から微分形を導き,静電場,静磁場,時間変化とエネルギー・運動量の保存則,電磁波と順を追ってきわめてオーソドックスに議論を展開している.その後,物質中のマクスウェル方程式をミクロな視点から導出し,物質中の電磁場について議論している.ここまでの議論は,いわば電磁気学の現象論ともいうべき部分であり,マクスウェル方程式をいったん認めたうえで,その帰結について詳しく議論するというスタンスで展開されている.高校物理の知識を前提としたうえで,読者を電磁気学の高度な内容に導いており,大学初年級の学生にとっても親切な内容となっている.
後半は,いわば電磁気学の本質論とでもいうべき部分であり,マクスウェル方程式がどのような原理で導かれるかを示している.実際,特殊相対性理論について詳しく解説した後,粒子の運動方程式とマクスウェル方程式をローレンツ不変な形に書き直し,それらが最小作用の原理から自然に導かれることを示している.また,電磁気学の締めくくりとして,運動する荷電粒子のつくる電磁場を求め,古典電磁気学の限界について議論している.ローレンツ不変性の起源は,特殊相対論に関して自然に生じる疑問であるが,本書の最後の部分はそれに対する答えである,一般相対論の展開にあてられている.等価原理を導入した後,リーマン幾何学について議論し,重力の作用を書き,それからアインシュタイン方程式が導かれる道筋をわかりやすく示している.また,一般相対論の帰結に関しても,少ないページ数ながら,重力波からブラックホールにいたるまで,豊富な内容が盛り込まれている.
私見になるが,学生,研究者を問わず,特殊相対論にいたる論理が大変自然だったのに対して,一般相対論にいたる議論のあいまいさに当惑している人が多いのではないだろうか.本書では,最小作用の原理にもとづいた議論が,電磁場と重力場の場合に統一的に明快に展開されており,一般相対論の知識を整頓したいと感じている人にもぜひお勧めしたい.
本書は300ページに満たない教科書であるが,論理展開が明確であり,内容も大変豊富であり,随所に,より高度な視点からの展望が書かれている.また,例題,問題も豊富に配置されており,講義に使う教科書として以外にも,自習のための便宜も図られている.初学者のみならず,専門家にとっても知識の確認に役立つ信頼できる名著である.
(2015年9月7日原稿受付)
磁石の発明特許物語―六人の先覚者
鈴木雄一
アグネ技術センター,東京,2015,iii+118p,21×15 cm,本体2,000円[一般向]ISBN 978-4-901496-80-3
紹介者:小林研介(阪大院理)
本書は,日本における磁石開発の歴史を六話構成で紹介するものである.第一話から第五話にかけて,日本の磁石の先覚者たちとその発明,すなわち,本多光太郎のKS磁石鋼,三島徳七のMK磁石鋼,増本量らのNKS磁石鋼,渡辺三郎のFW磁石鋼,加藤与五郎と武井武のフェライト磁石が紹介される.彼らの活躍は第二次大戦前の話であるが,その当時,日本が磁石研究の最前線にあったことが強く印象づけられる.そして第六話に,戦後,世界から遅れをとった日本の栄光を回復した先覚者として,ネオジム磁石を開発した佐川眞人が取り上げられる.
発明発見の物語,というと,通常は,研究者の心情や周囲の人間関係に焦点が当てられ,数々の失敗の後の華々しい成功,などがドラマティックに記述されるものが多い.それはそれで面白いのだが,本書のスタイルは,それとは違っている.題名にもあるように,本書の記述は「特許」が中心である.特許の文言を,時には数ページにわたって引用することにより,発明した本人の言葉で,発明の要点が語られる.その結果,彼らが何を考え,何に気づいてその発明に至ったのか,あたかも本人が語るかのように浮かびあがってくるのである.
例えば,第五話では,加藤与五郎と武井武の磁性フェライトの特許が引用される.味わい深いので,ここでも,一部分を引用させていただく.「本発明の特長の例を次に説明せん.金属製磁石は其の製作容易ならず.特に金属製強力磁石に至っては,其の製作すこぶる困難にして,それが製作に当っては不良品を生ずること多く,換言すれば歩止りいちじるしく低し.これ金属製磁石の欠点の一なり.(中略)然るに本発明の磁石は金属の代わりに金属酸化物の粉末を固めて作られるを以て,其の製作の容易なるは明らかなり」(p. 82)このような抑えた筆致で記述された特許の文言から,加藤と武井の誇りが力強く伝わってくる.
しかも,本書は,取得された特許の「その後」にも注目する.この点でも本書はユニークである.日本そして世界で特許がどのように取得され,どのように展開され,どのように製品開発につながっていったのか.その過程がきちんと書かれている.本書の「はじめに」には「磁石開発の歴史は一方で特許の歴史であった」とある.確かに本書を読むと,特許の重要性を具体的に学ぶことができる.また,それ以上に,ここに取り上げられた人々が,磁石の開発だけでなく,特許においても先覚者であったことがわかるのである.
本書は磁石材料とその特許についての技術的な内容が中心ではあるが,当時の時代背景や人間関係にも,きちんと触れている.「(本多光太郎は)長岡半太郎の指導で,強磁性体の磁気ひずみの研究をはじめた」(p. 2)という記述にであうと,日本における物性物理学の源流がここにあるのだと感じさせられる.また,評者は,本多の有名なKS鋼の「KS」が「住友吉左衛門」に由来することを初めて知った.本書には随所にそのような事実がちりばめられており,評者は,歴史の妙を感じながら楽しく読み進めた.
本書の文体は,無駄のない明快なもので,読みやすい.発明者本人の特許や講演記録などの一次資料をもとに,日本における磁石の発明と特許の歴史を丹念に紐解いた労作である.関連する磁石についての特許一覧も付されており,本書自体が第一級の資料的価値を持っている.磁性材料に関わる研究者はもちろんのこと,種々の材料開発に携わっている方々,特許戦略に関心のある方々におすすめしたい.
(2015年11月4日原稿受付)
元素生活(文庫版)
寄藤文平
化学同人,京都,2015,211p,15×11 cm,本体700円[一般向] ISBN 978-4-7598-1595-5
紹介者:安藤康伸(東大院工)
本書は,タイトルが表す通り,「元素」と「生活」がどう繋がっているかを非常に見やすく,楽しく教えてくれる名著の文庫版である.本書は1.リビングと元素,2.スーパー元素周期律表,3.元素キャラクター,4.元素の食べ方,5.元素危機,の全5章から成る.特に2・3章が全体の4分の3程度を占めているのだが,専門家の目では,何がスーパーなのか,キャラクターとは何かなど,タイトルが何を意味しているのか全くわからない.この点こそがまさに本書の醍醐味であり,デザイナーである著者から見た「元素」の姿である.
彼は118種の元素を「118人の人物像」として擬人化することで,周期律表が表現している元素の多様性及び周期性を視覚的に明確にしようと本書で試みている.彼は原子番号を人の体重に,元素の族を髪形に,主な使用用途を被服に,また放射性などを背景で表現している.想像していただきたいのだが,H, He, Li, Be ... とアルファベットが羅列しているだけでは,知識を有さない人の目には,その豊かさや意味が全く想像できないだろう.私たち専門家が暗黙知としていた元素の多様性と周期性が,このような「擬人化」によって誰の目にもありありと映るように工夫されているのだ.そのため,彼は118人が並ぶ表を「スーパー元素周期律表」と呼んでいる.
この表を見ると,誰もが人の個性に興味を抱くのと同じような感覚で,気になる元素のことを知りたくなるから不思議なものである.まるで新しい友人に出会ったときのように,君はなんでこんな髪型をしているの?と聞きたくなりさえする.私の自宅に貼ってあるものも「元素周期律表」ではなく「スーパー元素周期律表」である.
以上のような事柄から,本書は科学コミュニケーションという切り口で捉えることができる.帯コメントにもあるように,日常「元素なんてどうだっていいじゃん」と感じている層をターゲットとして,元素の面白さや身近さをうまく伝えてくれる.監修に複数の専門家が入っていることからも,本書の科学的に誠実であろうとする姿勢がよく分かる.元素よりさらに説明が難しい,抽象概念を扱う物理学の諸分野においてもこういった切り口による表現手法は十分参考となるだろう.科学コミュニケーターを志すならば必読・必分析である.
同時に,専門家がこの書を一冊手元に置いておくことも強く勧めたい.専門家は元素について科学的に十分な知識を有しているが,一方で「生活」という切り口で元素を語れる人材はどの程度いるだろうか? 元素発見の歴史や主な用途,産地などの事柄は,普段,我々が目にする論文や専門書では多く語られていない.しかし講義などにおいて,学生の注意を引きつける非常に魅力的な知識である.本書は,研究室の外側から見た元素を専門家に伝えてくれる.この点も強調しておきたい.
最後に,「元素を知りたいという気持ちにあんまり理屈はない気がします」と本書冒頭で著者が述べていることを紹介しよう.専門家もそうでない人に対しても,この気持ちを,本書が抱かせてくれることは間違いない.
(2015年10月16日原稿受付)
Physics of Graphene
H. Aoki,M. S. Dresselhous, Eds.
Springer Int. Pub. Switzerland,Cham,2014,xii+350p,24×16 cm,129.99€(NanoScience and Technology)[専門・大学院向] ISBN 978-3-319-02632-9
紹介者:長田俊人
最初の原子層物質(2次元結晶)であると同時に固体中で初めて実現した質量ゼロのDirac電子系であるグラフェンは,2010年のNobel物理学賞の対象となるなど大きな関心を集めている.グラフェンの電子物性については,既にM. I. Katsnelsonの教科書(Graphene, Cambridge Univ. Press, 2012)が存在するが,本書は最新の話題までを含む,より専門性の高い教科書になっている.
本書は,以下の実験5編,理論5編の独立なレビューから構成されており,グラフェン物理の主要な問題をバランス良くカバーしている.
まずChapter 1で,本分野を先導してきたP. Kimらが,Dirac電子系を特徴づけるBerry位相あるいは擬スピン(副格子)自由度について解説し,それがLandau量子化やKleinトンネリングを通じて,磁気抵抗の量子振動や電子波のFabry-Perot干渉にどのように現れるかを紹介している.
Chapter 2ではEva Y. Andreiらが,電子正孔パドル,Landau準位,エッジ状態,歪効果,捩れ二層系などのグラフェン系の各種エネルギー構造について,走査型トンネル分光法(STS)のデータを用いて解説している.
Chapter 3では,カーボン系の大御所で編者であるMildred S. Dresselhausらが,グラフェンの輸送特性を,グラファイト,層間化合物(GIC),ナノチューブなどと比較した歴史的観点から概説している.
Chapter 4では,M. Potemskiらによりグラフェンのバンド間・Landau準位間遷移による強磁場磁気光学に関する実験がまとめられている.
Chapter 5では,K. Ensslinらのグループにより,狭窄構造により形成されたグラフェン面内量子ドット系における帯電効果に関連した話題が解説されている.
Chapter 6では越野と安藤が,グラフェン系の電子状態と基礎物性について,有効質量近似に基づくDirac型方程式を用いて理論的にレビューしている.
Chapter 7では初貝と編者の青木が,蜂の巣格子のカイラル対称性と,その帰結であるゼロモードのエッジ状態やLandau準位構造について,トポロジー的観点から解説している.
Chapter 8では,T. Chakrabortyらがグラフェンの特異な分数量子Hall効果について,Haldane流の擬ポテンシャルを用いた議論を行っている.
Chapter 9では,野村とAllan H. MacDonaldらが,Zeeman効果と相互作用による縮退したn=0 Landau準位の自発的な対称性の破れと,発現する秩序状態について議論している.
Chapter 10では,E. McCannとV. I. Fal'koが,非弾性散乱とバレー間およびスピン軌道散乱の大小関係により,弱局在と反局在がどのように起こるかを理論的に議論している.
以上のように,各レビューとも本分野の第一線で活躍する実験・理論の専門家が,十分な紙数を用いて基礎から最新の研究までを詳細かつ丁寧に解説した内容になっている.グラフェン物理のadvancedな教科書として,研究の概要を知りたい読者,個々の問題の理解を深めたい読者にとってお薦めしたい一冊である.
(2015年1月29日原稿受付)
今度こそわかるくりこみ理論
園田英徳
講談社,東京,2014,x+197p,21×15 cm,本体2,800円(今度こそわかるシリーズ)[専門・大学院向]ISBN 978-4-06-156603-3
紹介者:鈴木 博(九大院理)
Kenneth G. Wilsonにより創始された,いわゆるWilson流くりこみ群に関する日本語の解説書である.素粒子理論の現代的な話題,例えば,カットオフを持つ低エネルギー有効理論,格子ゲージ理論によるゲージ理論の非摂動論的構成,非自明な赤外固定点を持つ場の理論,ラグランジアンの存在を仮定しない共形場理論などの文脈では,固定点,臨界指数,有意(relevant),無意(irrelevant),「境界線上」(marginal)な演算子,臨界部分空間,普遍性などといったWilson流くりこみ群の概念が既知のものとして頻繁に用いられる.Wilson流くりこみ群にはWilsonとKogutによる有名な講義録があるが,これは初学者には分かりやすいものではないと思う(評者も修士の時に挫折した覚えがある).これは一つには,朝永以来の摂動論的なくりこみ理論が理論的に完成している(このために素粒子標準模型では不定性のない予言が可能である)一方,このWilson流くりこみ理論は,(評者の印象では)素粒子理論の基礎をなすゲージ理論に対して万人の満足のいく形では完成していないことにも理由があるように思われる.このことから,通常の場の理論の教科書ではWilson流くりこみ理論は表面的にのみ取り扱われることが多い.しかしながら,上記のようにWilson流くりこみ群の概念が"常識的"なものとなるに伴い,Wilson流くりこみ群の現代的でわかりやすい解説書は誰もが待ち望んでいたものと思う.
本書は,Wilson流くりこみ群研究の第一人者の手によるものである.ここでは,スカラー場理論を題材として,Wilsonのくりこみ群変換に基づいて如何に場の理論の連続極限が実現されるかというステップが,途中の数式の変形も含めて非常に丁寧に提示されている.誤植も少ない.大部ではないが労作であり,「読者があまり苦労せずにWilsonのくりこみ群を理解できるよう」という著者の狙いは成功していると思う.Wilson流くりこみ理論のエッセンスが要領よくまとめられており,繰り返し味わって読むべき良書と感じた.ただし読者は,「今度こそわかる」というタイトルを鵜呑みにしてこの一冊の本だけでくりこみが学べると考えてはいけない.まず,標準的な場の理論の教科書で通常の摂動論的なくりこみ理論とくりこみ群に親しんでから,この本に取り組むべきであろう.相対論的場の理論の摂動論的なくりこみにすでに親しんでおり,これとWilson流くりこみの関係に特に興味がある読者は,各章を1→2→7→3→4→5→6→8→9→10という順序で読むのも論理がとらえやすいのではないかと感じた.この時「この本で言うt→∞での連続極限とは,運動量カットオフΛをμetとした通常のくりこみに他ならない」ということを常に念頭に置きながら読み進めるとよい.最後に,第8章の終わりのところで,Gauss不動点のまわりの連続極限のさらに連続極限としてWilson-Fisher不動点まわりの連続極限を得る,という話が出てくるが,これはちょっと難しい印象を受けたので,もう少し詳しい説明があってもよかった.
(2015年12月22日原稿受付)
1秒って誰が決めるの?;日時計から光格子時計まで
安田正美
筑摩書房,東京,2014,167p,17×11 cm,本体780円(ちくまプリマー新書215)[一般向]ISBN 978-4-480-68918-4
紹介者:熊倉光孝(福井大院工)
日本発の原子時計である光格子時計が世界的に注目を集めている.これまでの原子時計に比べて精度が飛躍的に高いことから,従来困難であった超精密実験の進展や「秒」の定義の見直しに繋がることが期待されている.本書は,計測標準の管理・研究を行っている産業技術総合研究所において,この光格子時計の研究開発に直接携わっている著者が,一般の読者向けに,時計の歴史から光格子時計の仕組みまでを平易に解説した啓蒙書である.
第1章の始めでは,各時代が求める性能と技術の進歩が織りなす時計の歴史が,本書の三分の一程度の頁にわたり,簡明に解説されている.時計の精度向上が世界史にどのような変化を引き起こしたのか,古代から大航海時代,宇宙開発時代に至るまで,様々な話題が取り上げられ,技術分野以外ではあまり意識されない精度向上の意味や社会への影響が大変わかりやすい文章で説明されている.また,この章の最後には,国際標準の管理に携わる著者ならではの視点から,標準制定の歴史や意義・重要性についても解説されている.近年,大学などでは一般向けの講座が開催される機会が多くなっているが,「時間」は一般聴衆の興味を引くテーマの一つで,本書にはこのような場面でも役立つ興味深い情報が多数ちりばめられている.
第2章からは,全体の半分程度の頁で原子時計と光格子時計が解説されている.光と原子の共鳴現象を説明したのち,ドップラー効果などの共鳴周波数をシフトさせる要因について紹介し,原子本来の共鳴周波数を測定することの困難さとそれが如何に克服されてきたかが平易に解説され,光格子時計に至る道程と,マジック波長を用いた原子トラップなどの光格子時計の新規性が説明される.また,従来のマイクロ波よりも高い周波数を持つ可視光を原子時計に用いる利点についても解説し,第3章では更に周波数の高い紫外線やX線を用いた時計の開発やその応用についても紹介している.ここでは原理の説明に多くの喩えが用いられ,一般の読者にもイメージが掴みやすいよう様々な工夫がなされているほか,日常目にする時計からかけ離れた実際の装置のイメージや,多くの研究者が加わる実験の雰囲気も伝わるように配慮されており,異分野の研究者が読んでも楽しめ,参考になる内容であろう.
巻末にあるように,本書は一般読者にわかりやすく伝えることを重視しているため,専門的すぎると判断された内容は巧妙に回避されている.そのため,読み手によっては誤解を招きやすい点もあるように思われるが,時間標準に関する技術が大きな進展を遂げつつある今,この分野に若手や異分野の研究者を誘うこのような書籍の出版は,時宜を得た,意義深いものであろう.
(2016年1月19日原稿受付)
電子・物性系のための量子力学;デバイスの本質を理解する
小野行徳
森北出版,東京,2015,vi+303p,22×16 cm,本体4,200円[大学院・学部向]ISBN 978-4-627-77521-3
紹介者:相馬聡文(摂南大理工)
「デバイスの本質を理解する」という副題に込められた趣旨が反映された,量子力学の初学者はもちろん,電子デバイスの立場から量子力学や統計力学全体を再度勉強したいという人にも最適な教科書である.
物理工学,応用物理,電気電子工学などの応用系学科において,電子物性や電子デバイスの動作原理を理解することは重要な課題であるが,そのためには量子力学,統計力学,固体物性等の知識を総動員する必要があり,これは初学者にとって高いハードルである.初学者が目的意識を見失わないようにするためには,デバイスという「出口」を見据えた上で,上で挙げたような物理学の各項目を系統的に,相互の関係性を意識しながら理解することが不可欠であるが,本書はまさにそのような配慮を持って書かれている.一冊の中で量子力学の導入からデバイスまでが一貫して解説されており,初学者にとって大変学習しやすい,また講義でも使いやすい構成となっている.
本書の構成において特徴な点がいくつかある.第三章までの,量子力学の導入から水素原子モデルまでの部分は通常の教科書でも論じられている内容であるが,本書では,波動の一般的性質や角運動量など,初学者がつまずきがちな部分を詳しく解説している点が特徴的である.それに続く章では,原子から分子,分子から結晶,そして結晶から電子デバイスという流れで,通常の量子力学の理解から順を追って自然にデバイスの理解に至るよう読者を誘っている.続いて統計力学に独立した一章が充てられ詳しく解説されているが,これは本書の前書きにもあるように「最終的にデバイスの性能を支配するであろう「熱」の理解には統計力学の考え方を身に付けることが重要である」という点が反映されたものであり,この前書きの一文とともに,デバイスに興味のある読者が統計力学を学ぶ上での良い動機付けになると思われる.ここでの理解が,次に述べるように,本書の出口である最終章「電子デバイスの極限」に向けての特に大事な伏線になっている.
近年,ムーアの法則に沿ったトランジスタ等の微細化による性能向上が限界を迎えつつある中,更なる性能向上を図る上で,デバイスの性能を本質的に決定する物理が何であるかという問いに答えること,中でもデバイス動作に係る「熱」の理解や制御の重要性に対する認識が高まっている.最終章「電子デバイスの極限」では,そのような「デバイスの本質に係る物理の理解」が命題に掲げられており,トランジスタのスイッチングに係る消費電力や,情報処理におけるエネルギー消費の原理的下限を示すランダウアーの原理という,「熱」が本質的にデバイスの動作の限界を支配する例が詳しく解説されている.それとともにトンネルトランジスタ,単電子トランジスタ,量子コンピュータが詳しく解説され,読者がデバイスの未来に興味を持つきっかけを与えている.
以上のように,本書は,電子デバイスの本質の理解をゴールに設定した上で量子力学,統計力学がバランス良く解説された,この分野の初学者に最適であるとともに,電子デバイスの性能を支配する熱の重要性や電子デバイスの未来に関心のある広い分野の研究者,技術者にとっても有益な一冊である.
(2016年1月26日原稿受付)
20世紀物理学史;理論・実験・社会(上)
20世紀物理学史;理論・実験・社会(下)
H. カーオ著,岡本拓司監訳
名古屋大学出版会,名古屋,2015,v+299p,22×15 cm,本体3,600円[専門~学部向]ISBN 978-4-8158-0809-9
名古屋大学出版会,名古屋,2015,iv+330p,22×15 cm,本体3,600円[専門~学部向]ISBN 978-4-8158-0810-5
紹介者:廣政直彦(元東海大)
本書は,デンマークの科学史家ヘリガ・カーオの1999年の著書Quantum Generation: A History of Physics in the Twenties Centuryの全訳である.ただし,今回の日本語への翻訳に当たって,原著者により多くの訂正追加がなされており,「訳者あとがき」にもあるように,改訂第2版といえるものである.
20世紀は物理学にとって大きな変革期であった.しかしそれは,相対性理論や量子力学の形成といった物理学の理論の変革だけでなく,社会における物理学や物理学者の役割の変革期でもあった.また,物理学が専門分化し,多様化してゆく時代でもあった.そのような,複雑化し多様化してゆく20世紀の物理学の様相が,4部29章にわたって記述されている.
第I部では,19世紀末から第一次大戦終結までの,量子論や相対論に代表される物理学の発展や,物理学が産業と結びつき,また戦争をきっかけとして,間接的ではあるが,政治と関わりをもつ状況について述べられている.第II部では,第一次世界大戦終結後から第二次世界大戦の終結までの,ドイツの物理学研究の状況,量子力学や原子核物理学の発展,また量子力学の哲学的問題や原子爆弾の開発といった,思想,政治,社会との関係など,多岐にわたる記述がなされている.特に,第一次大戦後のドイツの物理学の状況や,原子爆弾開発など,物理学が社会や政治と深く結びついてゆく過程についての記述が興味深い.第III部では,第二次大戦後から20世紀末までの,素粒子物理学,場の理論,固体物理学等の発展,さらに軍事科学やビッグ・サイエンス等について記述されている.この第III部の後半は,歴史的研究があまりされていない分野や,歴史的評価が定まっていない領域もあり,原著者の記述に関して異論があるかもしれない.第IV部では,以上をふまえて,20世紀の物理学の概括がされる.そこでは,第二次大戦後に起こった変化として,物理学が「道具主義的・実用主義的な思考様式」へと転換し,物理学の中に哲学の居場所がなくなったことや,20世紀の物理学からすると,民主主義の自由な精神が科学の発展にとって必要不可欠であるとは必ずしも言えないことなど,興味深い指摘がなされている.これらの指摘は,今後の物理学史のテーマになるかもしれない.
ところで,一般に,物理学は古い理論の限界が明らかになり,それに代わって新しい理論が現れ,より優れた「正しい」理論へと直線的に進むと思われがちである.しかし,物理学の歴史はそのように単純なものではない.ときには,出口のない袋小路に入り込んだり,かつて行き詰まった理論が新たな装いで復活することもある.それは,物理学の研究が物理学者という人間によって営まれているからである.物理学の歴史は,他の歴史と同じく人間の営みの物語であり,個人の思想や哲学,社会や時代の状況などが絡み合い,複雑な様相を呈する.本書は,そのような複雑な20世紀の物理学の歴史を,29章で叙述しているが,この29章を第1章から順番に読む必要はあるまい.興味のもてる章から読み始めるのもよい.物理学史の面白さを実感できるであろう.また,巻末の参考文献以外に,原著者による文献案内や訳者による注も記載されており,より詳しく調べることができる.本書を読み,物理学史に興味をもつ人が増え,できれば物理学史の研究者が現れることを期待したい.
ところで,本書の内容とは関係ないが,カバーのイラストについて一言述べておきたい.カンディンスキーの「円の周り」が使われており,物理学史の本とは思えないしゃれたカバーになっている.これにより,書店で本書を手に取りやすくなるかもしれない.訳文は読みやすく,一般の読者にも読んでいただきたい本である.書店で本書を手に取り,物理学史の面白さを知る人が少しでも増えることを願っている.
(2016年1月19日原稿受付)
アト秒科学;1京分の1秒スケールの超高速現象を光で観測・制御する
大森賢治編
化学同人,京都,2015,xi+178p,22×16 cm,本体3,800円[専門・大学院向]ISBN 978-4-7598-1805-5
紹介者:芦原 聡(東大生産技術研)
本書を開くと,アト秒パルス発生装置とその中で鮮やかに光るアルゴンプラズマの写真が目に飛び込んでくる.おおもとにあるレーザー装置はさておき,高次高調波発生そのものはシンプルな系で起こっているようである.これらの写真に続く,理論と実験データを表すカラー画像は,フェムト秒科学でお馴染みのポンプ・プローブデータとは趣を異にし,質的にも新しい光科学の様相が窺える.
本書はアト秒科学の入門書として編纂されている.アト秒科学は,短時間性の究極を追い求め,高速現象の観測・制御を目指す科学のフロンティアと位置づけられよう.1990年以降のフェムト秒レーザーの進展,特にその高強度化によってもたらされた強光子場科学を足場にして,アト秒領域へ踏み込むものである.フェムト秒科学が原子核の運動の観測・制御を可能にしたのに対して,アト秒科学は原子核の周りに存在する電子の運動の観測・制御を可能にすると期待される.
本書の全5章のうち,2つの章が理論,3つの章が実験の解説となっており,いずれも各分野の専門家によって執筆されている.第1章「アト秒光パルス発生の理論」では,アト秒光パルスの発生や応用を理解するうえで基礎となる概念とその理論的側面が説明されている.第2章「アト秒領域のダイナミクス―トンネルイオン化の数理」では,原子や分子のトンネルイオン化に焦点を絞り,その数理が詳しく解説されている.第3章「アト秒光パルスの発生の実験」では,超短パルス高出力レーザーの進歩,高次高調波によるアト秒光パルス発生・測定についてまとめられている.第4章「アト秒光パルスの応用研究」では,アト秒光パルスの計測手法およびアト秒科学における分光手法が紹介されている.第5章「アト秒精度の極限コヒーレント制御」では,2つのレーザーパルスを用いて物質中の波動関数の干渉,ひいては物質の量子状態を美しいまでに制御する実験が紹介されている.
アト秒科学には,従来の非線形光学の教科書には書かれていない概念が数多く登場する.本書では,その概念と理論的側面が丁寧に解説されているうえ,付録に用語集がまとめられており,入門者に親切な構成となっている.実験の章でも重要なトピックがわかりやすく紹介されているが,アト秒科学に特徴的な現象や手法がいくつも登場し,興味深い.例えば,高次高調波発生はアト秒パルスを発生するための手法として活用されているが,その物理を巧みに利用すると原子・分子の構造とダイナミクスを計測できるのである.
本書のまえがきによると,アト秒科学とは,孤立原子・分子から固体にまで至る幅広い物質を対象とし,電子波束の観測・制御を通して,物性の量子力学的な本質の理解や新たな量子機能性の発現を目指す研究領域,ということである.すると,アト秒科学は,今後,その対象を気相原子・分子から界面や固体へと広げ,多面的な発展をするだろう.本書は,その根幹をなす理論と実験技術をまとめており,当該分野を学ぶ科学者・技術者にとって有益な一書になるであろう.
(2016年2月17日原稿受付)
ニュートリノで探る宇宙と素粒子
梶田隆章
平凡社,東京,2015,240+vii p,19×13 cm,本体1,800円[学部・一般向]ISBN 978-4-582-50305-0
紹介者:固武 慶(福岡大理)
本書は初版が2015年11月20日となっており,著者のノーベル物理学賞受賞を待ち構えていたかのようなグッドタイミングで出版された.日本中がそのニュースに沸き返っている中,新聞の投稿欄に「快挙でありうれしいが,受賞理由に登場する"ニュートリノ振動"が一体どのような現象か,なぜ起きるのかがピンと来ないのが歯がゆい」といった内容の読者の声が寄せられていた.本書はそのような一般読者にとっても,またニュートリノ物理には馴染みの少ない研究者にとっても「いちばんよく分かるニュートリノの本」(本書の帯より)であると断言して間違いないだろう.と言っても内容的には啓蒙書を遥かに超えた骨太なものになっており,また論文や国際会議で用いられた図を多用し,丁寧に解説することで第一線の研究現場のライブ感を伝えることにも成功している.
内容に関して,まず1章では量子論の世界に読者を誘い,2章からは素粒子の世代に関する話題に移っていく.原子核のβ崩壊の実験からはじまり,ライネス・コーワンによる実験,加速器実験など,実に様々な実験テーマが時系列に沿って視覚的に分かりやすく説明されている.本書の大きな特徴であるこの図解によって,読者はストーリー性をもって,ニュートリノに反粒子が存在すること,さらにニュートリノもクオークと同様に「世代」を持つことが,スムーズに理解できるであろう.3章で小柴先生が提案されたカミオカンデ,その誕生の歴史と意味が述べられた後,4章以降ではニュートリノ天文学が打ち立てた金字塔的発見・科学的業績(太陽ニュートリノ,超新星ニュートリノ等)の解説に進んでいく.6章「ニュートリノ質量の発見」ではいよいよニュートリノ振動の説明に踏み込んでいく.教科書的には,ニュートリノの質量に関する固有状態とフレーバーに関する固有状態が異なることからニュートリノ振動が生じるわけだが,これを一般の読者にどうしたら分かりやすく説明できるであろうか? 本書は最も明解な答えを与えてくれる.ここまで読み進めば,今回の受賞につながった大気ニュートリノ問題の解決(本書の裏表紙の図)のインパクトが明瞭に理解でき,読者は大きな知的満足を得ることができよう.
最終章は,若い読者に対する熱いエールで締めくくられている.これは本書で述べられている様々な重要未解決問題の解明に挑戦し(たとえばニュートリノ質量の起源など),またハイパーカミオカンデをはじめとする次世代観測を担う若い研究者を育成していくことが,ニュートリノ研究(実験・理論とも)において世界を引き続きリードしていくために必要不可欠であるからであろう.著者のエールに賛同し今後ニュートリノ研究を志す(おそらく非常に多数の)大学生,大学院生が次に読み進むべき「実験に重心を置いた」教科書,それも本書のように分かりやすく最新の成果を含むものは果たしてどれくらい見つけることができるであろうか? 一読者,一研究者としても著者による次の一冊を心待ちにしたい.
(2016年2月29日原稿受付)
がんと闘った科学者の記録
戸塚洋二著,立花 隆編
文藝春秋,東京,2011,450p,16×11 cm,本体790円[一般向]ISBN 978-4-16-780135-9
紹介者:石田 卓(KEK)
梶田隆章氏受賞の一報に快哉を叫ぶと共に,戸塚洋二先生の事を思った.先生はスーパーカミオカンデ(SK)の光電管が大量に破損した事故の直後,夜半の神岡研究棟所長室で一人ボトルを傾けておられた.「君ならどうやってほとんどの玉が吹き飛んだSKを復旧するか?」当時熾烈な国際競争をしていたK2K実験の完遂のため,一年以内にSKを再建する決意に圧倒された.現地スタッフや共同研究者らと共に必死で携わった再建には,先生の発意により全国から集った学生ボランティアも任に当たった.復旧を見届けKEK機構長に就任されてからは,T2K実験を基幹の一つとするJ-PARCの建設を,抗がん剤治療を延期してまで推し進められた.
本書の出典であるブログは抗がん剤治療が難しさを増し,自身の死と向き合わねばならぬ状況となった時から,身内や親しい友人への近況報告として始まっている.治療経過の壮絶な記録,科学政策,エネルギー政策,人生,宗教,若者に向けた科学入門,植物への尽きぬ観察と興味など,回を追う毎に内容を加え,3カ月毎にタイトルを更新して続けられたが,4回目が最後の更新となった.本編では逝去直前に対談を行った立花隆氏が,闘病記録・人生・宗教など,万人共通のトピックのみを纏めている.研究遂行のため先生が払った代償の大きさに慄然としたと同時に,逝去一週間前まで綴られた内容の豊かさ深さに魅了された.就中感銘を受けたのは,治療の万策がつきようとする時,自宅の庭に咲き誇る花々の生命の中に,宇宙の誕生と死にも通ずる何かを見いだされたのではと思える数節である.自らの身体を松明として燃焼しつつ,ニュートリノ研究の行くべき道を示された先生の最期がやさしい花々に囲まれてあったことに一抹の安堵を覚えた.
(2016年5月20日原稿受付)
分子性物質の物理;物性物理の新潮流
鹿野田一司,宇野進也
朝倉書店,東京,2015,vi+206p,21×15 cm,本体3,500円[専門~学部向]ISBN 978-4-254-13119-2
紹介者:妹尾仁嗣(理研)
新著紹介では,目次をそのまま原稿の一部にするのは推奨されないそうだが,あえて章立てを紹介する.まず「分子性物質とは」という導入章からはじまり「電子相関と金属―絶縁体転移」「スピン液体」「磁場誘起超伝導」「電界誘起相転移」「質量のないディラック電子」「電子型誘電体」「光誘起相転移と高速光応答」がそれぞれ独立した章として構成されている.
本書は,分子が構成要素となった固体である分子性物質,とくに電気伝導性を示す分子性導体が示す物性現象を,包括的に解説した専門書である.実験研究者(と若干の理論研究者)によってそれぞれの章が執筆され,物性物理の基礎を習いたての読者にも配慮しつつ,最先端の研究結果も十分に盛り込まれている.
分子性物質が,物性を担う原子軌道から「(p)π電子系」として,「d電子系」「f電子系」などと並んで固体電子物性の標準的な研究対象として認識されてから久しい.その基礎にあるのは,化学式による暗号のような物質名やしばしば100個を超える原子が単位胞に存在する結晶構造の複雑さとは裏腹に,出発点となる電子構造が簡単な強束縛モデルで表され単純ということである.さらに電子格子相互作用や電子間相互作用の効果も合わせ様々な物性を創り出す.
そのような流れの中で分子性物質の研究は編著者のいう"新しい潮流"に現在なっている.より横断的に物性物理学を捉え,普遍的なテーマの中で分子性物質が最適なモデルケースとしての役割を果たす,ということが増えてきた.その現代的トピックスがまさに目次に並んだ章なのである.どのテーマも分子性物質に特有ではないが,分子性物質がその研究において理想的な環境を整えている.上記の出発点としての素性の良さに加え,分子自由度を生かした物質設計や外部パラメータ(圧力,磁場,電場)制御のし易さもその理由である.
分子性導体の合成は日本で最初の芽が出たということで歴史的にも意義深い.そして現在も世界的トップランナーを輩出しており,それらの研究者がそれぞれ各章を担当していてさすがに迫力がある.かなり豊富な内容となっており,各章の文献を見て理解を深めれば最先端の研究位置に立つことができよう.そういう意味で大学院生には最適な専門書となっており,研究者にとっても急激に拡がる分野の全貌をつかむには重要な良書といえる.物性物理のなかでも様々な小分野の境界領域を結ぶテーマも多いため聞きなれない言葉も頻出するが,ネット検索などで補いながら読み進められると思う(私はそうした).
じつは,本書で取り上げている主役を担う分子は10種にも満たない.それでこれだけ豊かな現象が発見され続けているという事実に改めて驚かされつつ,今後の発展を大いに期待させる内容となっている.
(2016年3月17日原稿受付)
量子ウォーク
今野紀雄
森北出版,東京,2014,v+242p,22×16 cm,本体4,860円[専門~学部向]ISBN 978-4-627-06161-3
紹介者:鹿野 豊(分子科学研)
本書は,離散時間量子ウォークの数理的な側面を著者自身の近年の結果を中心にまとめた,これから量子ウォークの分野を研究してみたいという学部生から研究者までを対象とした教科書である.そのため,本書を読破することができれば,量子ウォーク分野で新しい研究テーマを見つけ出すことは容易に可能であろう.
さて,そもそも量子ウォークとはランダムウォークの量子力学でのアナロジーとして定義されたものであり,数学的なモデルを研究することになる.本書にも垣間見られる側面であるが,考えることのできる量子ウォークのモデルが極めて多いため,どのようなモデルを解析するかというのは個々の研究者に依る.しかし,様々なモデルを徹底的に調べていくと確率過程はもちろんのこと,物理学に出てくる諸概念との対応関係に気づくことができる魅力がある.本書は,量子ウォークと直交多項式系の関係を調べる手立てとして導入されたCGMV法を紹介した日本語での初めての教科書であり,量子ウォークの研究を専門としていない人にも役に立つことは多いであろう.また,上述したように近年の著者自身の結果を日本語で丁寧に解説しているものであるが,本書だけを読めば理解することができるよう,前提知識がほぼない状態でも読めるように工夫されているのが本書の最大の特徴である.また原論文ではおそらく触れることができなかったであろう著者の思いや息吹を,時折登場するコラムや本文を通じて感じることができる.この恩恵を受けられるのは,母国語を駆使することの利点であると感じている.一方で,著者の研究以外の部分に関しては文章中の紹介にとどめているだけであり,更に近年盛んに研究されているトポロジカル相との対応や連続極限での物理ダイナミクスとの対応,量子情報分野で注目されている量子アルゴリズムの研究内容について触れられていないのは残念である.ただ,具体的な計算のイメージが沸きにくい数理的な道具を量子ウォークという具体例を通じて勉強できる教科書として至適なものであると思う.
(2016年1月10日原稿受付)
Plasma Scattering of Electromagnetic Radiation, 2nd Edition; Theory and Measurement Techniques
D. H. Froula, S. H. Glenzer, N. C. Luhmann, Jr. and J. Sheffield
Elsevier,USA,2011,xiv+497p,24×16 cm,$170.00[大学院・学部向]ISBN 978-0-12-374877-5
紹介者:久保 伸(核融合科学研)
本書は,同名のタイトルで1975年にAcademic PressからJohn Sheffieldの単名で出版され,関係分野の学生・研究者の間では,必読の古典的教科書として読み継がれてきた名著に,3名の著者によるレーザー核融合プラズマ,工業プラズマ,磁場核融合での最近の結果を加えて大幅改訂し,第2版として出版されたものである.
第1章はプラズマによる電磁波の散乱現象を扱うための基礎として,プラズマの特徴とその中での電磁波とプラズマとの相互作用を記述した導入部となっており,電磁波の散乱を扱わない一般読者にとってもプラズマ物理のコンパクトな入門編となっていて,簡潔にエッセンスを解き下している.第2-7章では,散乱現象の一般論として入射電磁波によって加速される電子の再放射としての散乱を扱い,プラズマ理論と散乱スペクトルの関係を議論した後,自由電子による散乱(いわゆるトムソン散乱)やイオンと協同運動する電子による散乱(協同散乱)を有効に数式を用いて丁寧に記述している.さらに,散乱計測の限界や光学システムまで記述されており,旧版を増補した内容となっている.第8章の計測技術,第9章の工業応用で用いられる低温プラズマ,核融合プラズマ中の高エネルギーイオンのための散乱計測,第11章のX線トムソン散乱は,新たに書き加えられた章である.特に,第9章での国際熱核融合炉ITERにおけるトムソン散乱計測と協同トムソン散乱計測,及び慣性核融合装置National Ignition Facility(NIF)におけるトムソン散乱計測は最新の成果がうまくまとめてある.第10章の磁化プラズマからの散乱の一般論や第12章の不安定プラズマによる散乱は旧版とほぼ同様の内容である.旧版同様,各章末には非常に教育的な演習問題が多数設けてあり,その奇数番には解答までつける徹底ぶりである.また,旧版同様,Appendix Aに本書で頻繁に用いられる複素解析,フーリエ解析,ラプラス変換,これらの応用としてのプラズマ波動の安定性,B, Cではプラズマの運動論的な扱い,熱いプラズマの分散関係,Eではプラズマからの散乱実験の歴史的レビュー,Fは物理定数やよく用いられる定式,表式が要領よくまとめられている.Dには,散乱のForm Factorを計算するためのMATLABコードリストが新たに加えられており,総じて「痒いところに手が届く」教科書となっている.本書の対象を学部から大学院生向けとしたが,専門家にも役立つお勧めできる名著である.
なお,長年米国の核融合研究において指導的役割を果たしてきた主著者John Sheffieldによって著された自伝的核融合の入門・歴史書とも言うべき"Fun in Fusion Research" (Elsevier, 2013)を合わせて読まれることをお勧めしたい.
(2016年4月25日原稿受付)
量子ドットの基礎と応用
舛本泰章
裳華房,東京,2015,viii+312p,21×15 cm,本体5,300円[専門・大学院向]ISBN 978-4-7853-2921-1
紹介者:太田泰友(東大ナノ量子機構)
量子ドットとは,平たく言えばナノサイズの電子の箱である.箱の材料・形状・サイズ等により3次元量子閉じ込め効果を制御し,捕捉電子の量子状態を自在に操ることができる.この効果の一端として,バルク材料にはない優れた光学特性を発現する.半導体量子ドットは,レーザー,バイオマーカー,量子情報デバイス,太陽電池,ディスプレイなど,多方面にわたって利用されており,その応用範囲は今後さらに広がっていくものと思われる.
本書は,これらの応用を念頭に置きつつ,半導体量子ドットの多彩な光物性を解説したものである.内容は,量子ドット分野の基礎を中心に応用もカバーし,これから量子ドット研究に携わる人々に向けたものとなっている.著者の長年にわたる幅広い研究活動を反映して,多くのトピックにおいて著者自身の研究成果を題材としつつ,力の入った議論が進む.
第1章から第4章までは,量子ドットレーザー等の応用に触れつつも,量子ドットの形成法や閉じ込め励起子における輻射緩和過程等,主に基礎的な内容を議論の対象としている.ここでは,ヘテロエピタキシーと化学合成による2種類の重要な量子ドットをある意味同等に,比較しつつ扱っている.これは,他書には見られない点である.以降,より発展的な内容に関する議論が進む.第5章でコロイド量子ドットの生体イメージ応用について手短に紹介があった後,第6章では永続的ホールバーニングによる光多重メモリが扱われる.スペクトルホール形成機構に対して多様な観点から議論がなされ,著者の本現象に関する深い見識が窺い知れる.第7章ではインパクトイオン化による多励起子生成,第8章ではフォトンエコーやラビ振動などの励起子コヒーレント操作が扱われる.これは量子光学では馴染みのトピックであるが,量子ドット系独自の進展が紹介されている.量子ドット分光で多くの業績を有する著者の,力のこもった解説が興味深い.第9章では量子ドットスピン物性が電子・核スピン両面から議論されており,スピンコヒーレンスに関する議論が手厚い.第10章では量子情報応用,第11章では主に量子ドット増感太陽電池が紹介されている.どの話題も,量子ドット研究において重要なものであり,その他の分野においても普遍的な内容を含んでいると言える.
本書の特色の一つは,物理現象の解説の大半が,応用にひも付けされている点である.これは,応用を意識する多くの研究者にとって有益である.また,材料系の異なる量子ドットを,随所で比較している点も特徴的である.これは,初学者だけでなく,量子ドット研究者にとっても改めて良い勉強となる.一方,トピックごとに,議論の深さがばらついているように見受けられた.ただ,これは非常に多彩な内容を単行本に詰めたがゆえの,ある程度避けられない帰結と思われる.いずれにせよ本書は,量子ドットの光物性に関連する非常に多様なテーマが扱われており,その応用の広さを実感できる一冊となっている.
(2016年5月15日原稿受付)
不規則系の物理;コヒーレント・ポテンシャル近似とその周辺
米沢富美子
岩波書店,東京,2015,ix+256p,22×16 cm,本体4,600円[専門・大学院向]ISBN 978-4-00-005969-5
紹介者:加藤岳生(東大物性研)
固体物理学の分野において,不規則系の研究は重要な位置を占めている.不規則系はバンド理論などの通常の結晶に対する理論では記述できず,新しい理論が必要となるが,タイトルにもある「コヒーレント・ポテンシャル(CPA)近似」はその代表的な近似理論体系である.CPA近似は原子組成の不規則性の影響を1サイト近似の範囲内で自己完結的に取り扱う近似であり,現実の合金系の性質を初めて定量的に記述することに成功した.今でも現実的なバンド計算手法であるKKR法に組み込まれて利用されるなど,固体物理学のさまざまな問題に活用されている.本教科書はこのCPA近似理論を軸として,合金・アンダーソン局在・金属液体などの不規則系を丁寧に解説した教科書である.数ある固体物理の教科書でも,不規則系のみに特化した教科書は珍しい.特にCPA近似の詳しい説明がある日本語の教科書は,私の知る限り他にないので,その意味で貴重だと思う.
本教科書では,不規則系を理解することの重要性から説明が始まり,「CPA近似」の詳しい導出法や有効媒質近似との関係とともに,関連項目(ハバード近似との関係や液体金属の取り扱いなど)の紹介を行っている.第1章で不規則系の定義および多くの実例が丁寧に述べられたあと,第2章では結晶に関する基本事項(バンド理論など)が簡潔にまとめられている.第3章では以降で扱われる考え方(エネルギー・ギャップの概念や有効ハミルトニアンなど)が要領よく解説され,第4章ではさまざまな種類の近似理論が紹介される.そして,第5章と第6章で満を持して「CPA近似」が導入される.本書は,通常の導入の仕方である「有効媒質近似」の考え方ではなく,ダイアグラムの地道な数え上げに基づく「かっちりした」導出法が採用されている.このようなやり方は初めて知ったが,数式はやや多く出てくるものの,やっていることが明快で感銘を受けた.また第4章での近似との関係が,ダイアグラムを用いて明快に説明され,とても教育的であると感じた.第7章では,「CPA近似」の通常の出発点である有効媒質近似の式が導出され,電子相関模型でのハバード近似との関係が論じられる.第8章ではアンダーソン局在が取り扱われる.ここでは通常の説明で用いられるスケーリング理論だけでなく,アンダーソンの最初の論文内容に沿った説明も含まれており,一読の価値がある.第9章は液体金属の議論に当てられている.あまり見たことがない議論であったが,大筋は理解することができた.
すでに述べたように,不規則系に焦点を当てた教科書は珍しく,初学者への配慮が十分に行われている教科書はこれまでなかったのではないだろうか.一つだけ難を言えば,第2章は駆け足すぎており,固体物理の基礎を一通り学んだ後に本書に挑戦するのがよいと思う.CPA近似は現在も普遍的なツールであり続けているため,大学院生が自習できる教科書が出版されたことは喜ばしい.随所にCPA近似に対する著者の思い入れが感じられ,個性的な教科書にも仕上がっている.不規則系の理論についてまとめて学びたい大学院生・研究者にお薦めしたい.
(2016年5月1日原稿受付)
共形場理論
江口 徹,菅原祐二
岩波書店,東京,2015,xii+321p,22×16 cm,本体5,700円[専門・大学院向]ISBN 978-4-00-005249-8
紹介者:山口 哲(阪大院理)
本書は,少し進んだ話題も含む2次元の「共形場理論」の教科書である.
2次元の共形場理論は,理論物理学,数理物理学の中で揺るぎない重要な位置を占める理論である.その歴史は長いが,最近になっても応用範囲は広がり続け,重要性は増すばかりである.最も古くからある重要な応用の一つは弦理論であろう.また,統計力学における臨界現象は,共形場理論の鮮やかで美しい応用例である.最近では,これら伝統的な応用に加えて,4次元や6次元の超対称場の理論と2次元の共形場理論の関係が盛んに研究されている.4次元の物理量が2次元の共形場理論の物理量で表されることが発見されたり,4次元や6次元の超共形場理論の広い意味での対称性として2次元の共形場理論の代数が現れるということが発見されたりしている.
本書は,この共形場理論を学ぶための教科書である.最初は比較的標準的な道筋に沿って共形対称性を導入しミニマル模型までを説明する.その後,様々な共形場理論の親玉とも言えるウェス・ズミノ・ウィッテン模型とコセット模型を導入する.そして共形場理論の中で非常に有用な概念であるモジュラー不変性について詳しく説明したあと,有理共形場理論の一般論を取り扱う.その後,本書の主眼とも言える超共形場理論に進んでいく.
他の共形場理論の教科書と比較して,本書の特徴は「超共形場理論」について詳しく説明があることである.超弦理論へ共形場理論を応用する際,世界面の超対称性を含む超共形場理論について詳しく知る必要がある.特に拡大された超対称性をもつ超共形場理論は弦理論の時空の超対称性を保ったコンパクト化を研究する際に重要な役割を果たし,これまでにたくさんの興味深い結果が発見されてきた.これまでは,超共形場理論を学ぶには,結局原著論文に当たるしかなかった.しかし,本書では,カイラル・プライマリー状態やスペクトラル・フローなど超共形場理論で重要な役割を果たす概念が丁寧に説明してあり,本書を読むだけでかなりの知識を得ることができる.さらに詳細な情報が必要になれば原著論文に当たる必要があるが,その際にも本書で得た知識があれば,スムーズに理解が進むであろう.
また,本書の終わりの方では,モック・モジュラー形式とモジュラー完備化やムーンシャイン現象など,著者らが大きな寄与をした最新の研究成果の概略と今後の展望が述べられる.この部分も興味をかきたてられる内容となっており,共形場理論自体が,今後もまだまだ発展していくと感じさせる.興味をもった読者はさらに詳しいレビューや原著論文を読めば,詳細を知ることができるであろう.
本書を読んでいると端々にこだわりを感じる.例えば共形変換の導入の部分で,座標変換と微分同相写像を明確に区別し,共形変換は(座標変換ではなく)微分同相写像で角度を保つもの,としている.普通の場の理論の教科書を含め,多くの教科書ではこの区別が曖昧で,しばしば誤解の原因になっている.私は本書のように明確に区別している方が好ましいと思うが,読者諸氏,特に初学者がどう感じるか興味あるところである.
数理物理学や弦理論に興味があり,本格的に勉強を始める大学院生が読む共形場理論の教科書として,本書は有力な選択肢の一つであろう.また,共形場理論を研究で使うことになった研究者が,原著論文に当たる前に大まかな知識を得るのにもおすすめできる.また,普段から共形場理論を研究している研究者の座右の書としても有用である.
(2016年6月14日原稿受付)
Theoretical Femtosecond Physics; Atomos and Molecules in Strong Laser Fields Second Edition
F. Grossmann
Springer,Switzerland,2013,xv+254p,24×16 cm,49.99€ (Graduate Texts in Physics)[専門・大学院向]ISBN 978-3-319-00605-5
紹介者:片山郁文(横国大工)
近年,振動周期を数サイクルしか持たない,きわめて短い時間幅のレーザー光源が各種手に入るようになってきている.このような光源ではほんの一瞬のみにエネルギーが集中しており,その瞬間の電場強度は非常に高くなるため,物質と相互作用すると極端に非線形で,かつ興味深い現象が起こる場合が多い.例えば,気体原子にパルスレーザーを照射することによる,X線領域にも及ぶ高次高調波・アト秒パルス発生や,破壊,相転移現象などがそれにあたる.一方でこれらの現象は非常に非線型で非摂動論的なものであるため,それらを理論的に記述する際には,光電場と物質との相互作用を周波数領域ではなく時間領域で取り扱う方が見通しが良い場合もある.しかしながら,物質と光との相互作用を取り扱う教科書のほとんどは周波数領域の記述を中心に据えており(R. Boyd: Nonlinear Optics, Y. R. Shen: The Principles of Nonlinear Opticsなど),時間領域の記述をベースとしているものには,良書ではあっても難解になる傾向がある(S. Mukamel: Principles of Nonlinear Optical Spectroscopyなど).
このような中で本書は原子気体からの高次高調波・アト秒パルス発生というトピックに的を絞り,それを理論的にうまく取り扱うためにはどうすれば良いのか,という観点でまとめられた教科書である.著者の大学院での講義をベースとしているだけあって,種々の興味深い問題が数多く掲載されており,第二版になって,それらの解答も充実したものとなった.1章では導入として,これらの実験で用いられる光源や概念の基礎が簡潔に記述され,その後,2章において時間領域の摂動理論について述べられている.特に,極端に非線形な現象を取り扱う際に有効な,プロパゲータを用いた手法なども具体例とともに紹介されている.また,本書は自ら計算を行うことができるよう,各種の数値計算手法などまでも含めて紹介されていることも興味深い.さらに3章では,二準位系を例にとって物質と光との相互作用を記述する手法を概説し,厳密解があるモデルなども紹介している.そして,4章は原子,5章は分子への応用計算事例が,特にイオン化や反応制御を念頭に記述されている.後半部分は計算結果の解説が多くやや難しい印象があったが,随所に関連するモデルや計算手法,実験手法のトピック的な記述があり,読者を飽きさせないよう工夫されている.
アト秒領域の物理学は近年発展しつつある分野であり,それを扱う教科書はまだ少ないので,本書のようにトピックを絞ってそのエッセンスを学ぶことができる書籍は貴重であると言えよう.また,時間領域の計算手法は高次高調波・アト秒パルス発生のみならず,高次の効果が重要となる他の極端に非線形な現象の記述にも有用である.本書は理論の教科書であり,時間領域の現象を取り扱いたいと考えている理論研究者にはもちろん薦められる書籍である.一方で,多くの論文において実験結果と理論計算結果との比較が重要となっている現状を考えると,実験家にとっても理論計算のハードルを下げ,その内容を理解するための知識が得られるという点で大変有益だと考えられる.本書を読んだうえで時間領域の記述をより詳細に学べる教科書に進めば,必要に応じて時間領域と周波数領域を使い分ける必要がある超高速分光法の基礎を身につけることができるのではないかと思う.
(2016年6月30日原稿受付)