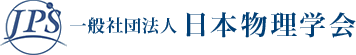会誌Vol.73(2018)「新著紹介」より
このページでは、物理学会誌「新著紹介」の欄より、一部を、紹介者のご了解の上で転載しています。ただし、転載にあたって多少の変更が加わっている場合もあります。また、価格等は掲載時のもので、変動があり得ます。
「軍事研究」の戦後史;科学者はどう向き合ってきたか
杉山滋郎
ミネルヴァ書房,京都,2017,xii+298+8p,20×14 cm,本体3,000円[広い読者向]ISBN 978-4-623-07862-2
紹介者:高岩義信(KEK)
20世紀の二つの世界大戦を通じて,科学技術の優劣が戦力に直結することを知った.本書は,その後に続く「戦後」から現代にいたるまでの軍事と科学者および科学研究との関係の歴史的叙述を行っている.
著者はさきに中谷宇吉郎の評伝1)を書いており,その執筆時にもった疑問が本書を著すきっかけであったと「あとがき」に書いている.その疑問とは1954年に中谷が米軍から委託された研究を北海道大学で行おうとした時に巻き起こった論争に関連して「軍事研究かどうかを研究資金の出所だけで判断することが適切だったのだろうか.基礎研究なら軍事研究でないといえるのだろうか.また「軍事研究反対」は大学での研究だけを対象にするものなのだろうか.」というものであった.この「論争」とその顛末は本書にゆだねることにするが,その疑問から出発して書かれた本書はこの三つの主題の変奏曲のようなものである.
なお「軍事研究」という語について,なにが「軍事研究」か自体が重要な争点であるから,それをあらかじめ明確に定義できない.誰かが「軍事研究ではないか」というものはすべてその範疇に含めて多様な論争をカバーできるようにすると著者は言っている.
本書の構成は,主として日本の研究状況を取り上げ,以下のようになっている.
はじめに第1章(「軍事研究」前史―ダイナマイトから七三一部隊まで―)で19世紀末から世界大戦終結までの状況を簡潔に述べたあと,第2章から第5章では年代を追って特徴的な事例が取り上げられる.第2章(冷戦が進む中―大学が聖域になったとき―)は1945年から1960年ころまでをカバーし,戦時の研究体制への反省から軍事目的の研究をしないという姿勢をとった時代である.学術会議は1950年に「声明」を出したがその後繰り返して表明することは容易ではなかった.第3章(ベトナム戦争の時代―「平和の目的に限り」の定着―)は1960年前後から1970年代前半のことである.米国に有力な科学者を擁して国防を含む政策に助言する委員会が目立った時代である.米国の軍事機関に由来する研究資金が日本にも流れてきて,それが批判的に取り上げられる.学術会議における「声明」の再確認および物理学会の「決議」もそのコンテクストでなされる.その一方で,高度経済成長期にあって軍事に転用可能な技術でも「平和目的」に限るという条件で承認される.第4章(新冷戦の時代―「平和の目的に限り」の裏で―)の1970年代から1990年代は大学を中心とするアカデミズム以外の科学技術の開発が進む時代である.国際的には米ソ対立にとどまらない紛争に拡大しつつ緊張が増す新冷戦の時代となり,日本も潜在的に軍事に結びつく技術の研究開発が隠然たる事実として推進されたのではないかと指摘する.つづく第5章(冷戦終結後―進みゆく「デューアルユース」―)は現在の状況を語っているものとみてよいだろう.基礎研究は研究内容で軍事研究か民生研究かをいうことは難しい.研究の資金に様々な形と名分で産官学の組織に軍・防衛機関由来のリソースが配分される現実が示される.そして最後の第6章(軍事研究の是非を問う―何をどこまで認めるか―)では,提示された課題を整理し著者の考えと姿勢を述べて結ばれる.
日本学術会議は1950年と1967年の「戦争・軍事研究」を行わないという声明の見直しにかかわって,2017年の3月に「軍事的安全保障研究に関する声明」2)を出した.以前の声明は継承するとしたものの「各研究機関,各分野の学協会,そして科学者コミュニティが社会と共に」議論を続けて行かなければならないとしている.本書で述べられているような状況を既往の事実として認めるとしても,さらに規制を緩和していくのか批判的に検討し直すのか,コミュニティとして今後の態度を決めなければならない.そのための議論をし検討を重ねる前提となる事実と経緯を知るのに本書は格好のものであると思われる.
参考文献
1)杉山滋郎,『中谷宇吉郎:人の役に立つ研究をせよ』(ミネルヴァ書房, 2015年).
2)日本学術会議,声明「軍事的安全保障研究に関する声明」2017年3月24日.
(2017年5月15日原稿受付)
ミュオンスピン回転法;謎の粒子ミュオンが拓く物質科学
門野良典
共立出版,東京,2016,vi+174p,21×15 cm,本体2,000円(基本法則から読み解く物理学最前線10)[専門~学部向]ISBN 978-4-320-03530-0
紹介者:小池洋二(東北大院工)
ミュオンスピン回転法(μSR)は,最近では,物性物理学における磁性の実験的研究手段として,中性子散乱,核磁気共鳴法(NMR)と相補的で,かつ重要な役割を担っている.μSR実験には,単結晶でなく多結晶試料を用意すれば十分であり,回折ピークやNMR信号の検出に苦労することもない.実験すれば必ず時間スペクトルが得られるので,実験に熟練は不要である.そして,得られた時間スペクトルを見れば,試料が常磁性であるか,磁気相関が発達しているか,磁気秩序が発達しているか,一目で分かる.したがって,新物質を合成した場合,その物質の磁性をチェックするのに最も簡便な方法である.簡便と言っても,試料に撃ち込む大強度のミュオンビームを生成する大型施設が必要である.そのような大型施設は世界に4箇所しかないが,幸いなことに,その一つが茨城県の東海村のJ-PARCにあり,全国共同利用に供されている.
評者は磁性の専門家ではなく,μSRに関して全く無知であったが,研究していた銅酸化物高温超伝導体に磁性が絡むことが分かり,急遽μSR実験を始めた.多結晶試料を準備して大型施設に持って行きさえすれば,施設の方が時間スペクトルの取り方を教えてくださり,さらに,得られたスペクトルの物理的解釈までしてくださった.そして,施設の方とのディスカッションによって,あっという間に論文が完成した.有難いことであった.しかし,μSRの実験方法は分かっても,何故そのようにすれば実験できるのか,ほとんど理解していなかった.時折施設の方に聞いてはいたが,それにも限度があった.そんな評者であるが,本書を読み,「なるほど,だからそのようにしていたのか.」と納得するところが多々あった.そして,1970年代に素粒子・原子核物理学の研究対象であったミュオンを物性研究に利用できると考えた先人の知恵に敬服した.
本書では,まず第2章において,素粒子物理の基本法則である「標準理論」に基づいて,ミュオンという素粒子の性質を概観している.パイ中間子の自然崩壊によって生成されるミュオンが何故物性研究に利用できるのかを学ぶ.第3章以降はμSR実験の時系列に従って述べてあり,第3章では,大量のミュオンを発生させ,ミュオンビームとして物質中に注入し,ミュオンが物質中で静止するまでの過程を概観している.ここでは,特殊相対論に基づく運動学と物質とイオンビームとの相互作用について学ぶ.第4章では,物質中に静止した直後のミュオンの状態について学ぶ.金属,半導体,分子性結晶等,物質による違いが明確に記されている.第5章では,物質中に静止した瞬間から内部磁場(核スピンと電子スピンの磁気モーメントによる双極子磁場)を感じて歳差運動をするミュオンスピンが生み出す時間スペクトルから物質の磁性をどのように読み取るか,詳述されている.横磁場(ミュオンスピンの偏極方向に垂直な外部磁場)の印加によって観測されるミュオン・ナイトシフトや第2種超伝導体における磁束格子の研究,さらに,正電荷を持ったミュオンが電子を1個束縛したミュオニウム(水素原子の同位体と見なせる)と呼ばれる状態の時間スペクトルについても述べられている.第6章では,μSRを使った最前線の研究として,鉄系超伝導体に関する著者らの研究が紹介されている.磁性と超伝導の関係をミクロに明らかにしたμSRの威力を感じることができる.最後の第7章では,素粒子物理学と物性物理学の繋がりが大局的に展開され,物質科学の意義が述べられている.学生時代に原子核物理学を専攻しようとしていた著者ならではの記述であり,著者の物理学に対する造詣の深さを感じる.
本書は,共立出版から刊行されている「基本法則から読み解く物理学最前線」シリーズの1冊であり,物理的背景(仮定)が明確に述べられており,学部2・3年で習う量子力学に基づいて展開されているので,量子力学を修得した学部4年生以上の学生には大変理解しやすい内容になっている.時間スペクトルの解析に使う数式の導出も丁寧である.評者は,μSR測定を始める大学院生には,まずは,一般人をも対象とした啓蒙書『ミュオンの科学』1)を勧めているが,それに続く書として本書を勧めたい.また,μSR実験の経験のない磁性研究者,物質中における水素の挙動を研究している人,さらには,大学院で素粒子物理学を専攻すべきか,物性物理学を専攻すべきか,迷っている学部学生にも一読を勧めたい.
参考文献
1)永嶺謙忠,『ミュオンの科学;21世紀をになう粒子』(FRONTIER SCIENCE SERIES,丸善,1988).
(2017年5月15日原稿受付)
光誘起構造相転移;光が拓く新たな物質科学
多電子系の超高速光誘起相転移;光で見る・操る・強相関電子系の世界
腰原伸也,T. M. Luty
岩井伸一郎
共立出版,東京,2016,vii+107p,21×15 cm,本体2,000円(基本法則から読み解く物理学最前線11)[専門~学部向]ISBN 978-4-320-03531-7
共立出版,東京,2016,x+130p,21×15 cm,本体2,000円(基本法則から読み解く物理学最前線12)[専門~学部向]ISBN 978-4-320-03532-4
紹介者:石原純夫(東北大院理)
腰原伸也氏とTadeusz Luty氏による『光誘起構造相転移』(以下著書『構造相転移』)と岩井伸一郎氏による『多電子系の超高速光誘起相転移』(以下著書『多電子相転移』)が,共立出版の「基本法則から読み解く物理学最前線」シリーズとしてほぼ同時に出版された.シリーズ監修者による刊行の言葉には,基本法則から最前線の研究に至るまでを「飛び石のように」紹介することがシリーズの趣旨であると記されている.「光誘起相転移」というややマニアックなテーマでこの趣旨に沿って2冊も同時に出版して大丈夫?というのが,生協の本棚に2冊並んでいるのを見たときの正直な感想であった.本書評を最後まで読む暇のない読者のために結論を先に申し上げると,評者の第一印象は杞憂であり2冊セットで買って読み比べるのがオススメである.
通常は温度や圧力,磁場などにより生じる固体の相転移を,強い光照射により誘起する現象は光誘起相転移と呼ばれる.サブピコ秒程度の時間幅をもつレーザー光を照射することで電子系や格子系に強い摂動が加わり,これが相互作用を通じて固体中のマクロな領域に広がる.強い非平衡状態の過渡現象であることから数学的に厳密な"相"や"相転移"とみなせるかは議論があるが,著書『構造相転移』にあるように相転移の前駆現象などの広範囲の概念にこの言葉が広く用いられている.初期のミクロな励起が相互作用を通してどのようにマクロな状態変化に移り変わるかが肝心な点であり,その視点から二つの著書をやや強引に色分けすると,著書『構造相転移』は「電子格子相互作用」に,著書『多電子相転移』は「電子間相互作用」に重きを置いたものと分類できる.
著書『構造相転移』の二人の著者は,光誘起相転移研究の黎明期からこの分野を支えてきた実験・理論研究者であり,記述の至るところに研究の歴史が垣間見られて楽しめる.7章からなる本書は大きく3部に分けられる.最初の2章は,光誘起構造相転移の概観からはじまり理論面からみた4つの挑戦的課題まで触れられ,これからこの分野に参入する若い方が俯瞰するのに良い記述となっている.続く2章では,光によるパイ電子系ポリマーの相転移と電荷移動錯体の中性・イオン性転移が大きく取扱われている.特に前者は著者らにより30年前に光誘起構造相転移が"発見"され,その後の研究の発展につながった記念碑的な研究である.当時の研究者たちの活気が直接感じられて興味深い.最後の2章は,この10年間で急速に発展した構造相転移を直接観測できる時分解X線回折・散乱や時分解電子線回折などの過渡時分解プローブを用いた研究例である.大型放射光施設などを巻き込んで,今後この分野が大きく進展するであろうことを伺わせる.読後に再び目次を見直すと,この現象が比較的単純な系で発見され,より複雑な系へと発展していることが見て取れる.高温超伝導研究において,最初に発見された超伝導体が最もシンプル(簡単ではない)な銅酸化物超伝導体であったことが想起され,テーマの詳細に依らず物質科学研究の普遍的な傾向かもしれない.
著書『多電子相転移』の表紙を開くと,まず時分解実験データのきれいなカラーの図が目に留まった.この研究分野の醍醐味の一つであるが,あたかもストロボ写真で撮ったかのように電子や格子が時々刻々と動くさまがわかる.こちらの著書も大きく3部に分けられている.第1章の導入部を経て,第2章から第4章では相転移や強相関電子系に関する基礎的な記述が続く.大学2,3年生が学ぶ統計力学,量子力学,固体物理学の知識で十分理解することが可能であり,まさに「飛び石のように」最先端の研究と直接結びついた記述となっている.講義で習ったことが物理学最前線の研究に必要不可欠であることを学ぶことで,学部学生が基礎物理学を勉強する上で大きなモティベーションになるであろう.続く2章では,超高速分光法を駆使して明らかにされた最近の研究の紹介が本格的に展開される.代表的な二つの強相関絶縁体である電荷秩序絶縁体とモット絶縁体の研究例が,具体的な実験データに基づいて紹介されている.強相関絶縁体は相互作用に起因した協力現象であり,光により生じた局所的な金属状態が雪崩的,ドミノ倒し的に広がることで絶縁体・金属転移が生じる様子がよくわかる.最後の2章は最新の話題である.数フェムト秒を切ろうとする超短パルス光により光励起の初期過程にいかに迫るか,数百MV/cmの瞬時強電場で電子をいかに操作するか,という著者の熱い意気込みが文面にも見て取れる.
2冊を通して読むと,当初心配したような両者で重複する内容や,研究の詳細に固執したマニアックな印象はほとんど感じず,互いに相補的な著書であることがわかる.初学者にもこの分野の歴史,基礎から最先端研究成果を経て現在の課題まで,この研究分野を概観する形で知ることができるであろう.敢えて注文を付けるならば,2冊とも国外の関係する研究動向にもう少し紙面を割いてよかったのではないかと思えるが,これは我が国の研究が国際的に最先端であることの裏返しか.
通読して改めて感じるのは,この分野がレーザー光源や各種時分解測定技術,大型放射光施設などの最先端実験技術の進歩に大きく支えられていることである.確かに,パルス幅が一ケタ短くなったら,プローブの感度が一ケタ向上したら,電場強度が一ケタ上昇したら,自然の違う側面が顔を出すであろうことは容易に想像される.そのような意味において,この分野の研究の奥行きがまだまだあることを実感させる2冊である.
(2017年5月23日原稿受付)
物性量子化学
山口 兆
朝倉書店,東京,2016,xi+367p,22×15 cm,本体7,600円(朝倉化学大系1)[大学院・学部向]ISBN 978-4-254-14631-8
紹介者:山下将嗣(理研光量子)
量子化学は量子力学の諸原理によって分子構造や物性あるいは反応性を理論的に説明づける学問分野である.1980年代以降の計算機処理速度の向上と計算機科学の発展により,簡単な分子については経験的パラメータを用いず第一原理的に精密な解を求めること(ab initio法)が可能となっている.その適用対象は,強相関電子系を含む有機化合物,錯体化学物,高分子・生体関連物質,固体表面での界面化学の解析など多種多様の分野に及んでおり,理論・実験・計算科学の協奏による物質科学の一層の進展が期待されている.一方で,一般的な量子化学の教科書は,量子力学の説明に始まり水素分子モデルを用いた化学結合などの基本的な説明や,量子化学ソフトの使用方法の説明にとどまっており,実際の物質へ適用した研究事例を紹介する教科書は少ないように思う.近年,対象とする物質に応じて計算時間及び精度を向上する様々な手法が開発されており,当該分野の研究をこれから始めようとする研究者にとってハードルが高くなっているように思われる.
このような中で本書は3d遷移金属錯体系へ適用した研究を中心にまとめられており,物性物理学の研究者にも大変興味深い内容となっている.本書は三部から構成されている.第I部では,物性量子化学基礎理論の紹介として,Hartree-Fock法から始まり,密度汎関数法(DFT)及び一般化スピン軌道を用いるハイブリッドDFT,配置間相互作用法及び関連する高精度波動関数法や密度行列繰り込み群法について,その基本概念と背景となる考え方を概観したのち,具体的なモデルを用いて歴史的な発展の経緯を踏まえながら簡潔に説明されている.したがって,各手法の詳細についてより深く理解したい場合は,それぞれの専門書を参照することが望まれる.第II部では,スピンをもつ分子のポリマー化,自己集積化,あるいは格子への閉じ込めによるスピンクラスターの形成及び1-3次元集積体の形成による磁性,磁性伝導性,非BCS機構超伝導性,近年注目を集めている強相関電子系を持つ分子集積体の分子システム設計を取り上げている.第III部では遷移金属酵素系を"強相関電子系の蛋白場による制御に基づく機能発現"という視点で統一的に取り扱っており,太陽光を利用した光合成水分解サイトに存在するCaMn4O5クラスターに関する研究を紹介している.2013年のノーベル化学賞は量子力学(QM),分子力学(MM)及び分子動力学(MD)法の融合による複雑系の理論的取り扱いが受賞対象になったが,QM/MM/MD法の今後の展開の第一の対象系に挙げられているのが光合成系であったのは記憶に新しい.
最近では,量子化学でおなじみのGaussian基底を用いるab initio法が分子固体にも展開され,さらに,強相関電子系の物性・機能発現の学理解明には,量子化学分野で開発されてきた高精度計算手法が不可欠になってきた.すでに,ab initio法と量子モンテカルロ法などの確率論的手法の連結,密度行列繰り込み群法との連結,あるいは動的平均場理論との連結など物性物理と量子化学は融合しつつある.最新の量子・計算化学の進歩の具体例を提示してくれる本書は,強相関電子系の物性と量子化学を結び付け,新規物質系の分子設計に研究を展開するための基礎を与える良い入門書となるのではないかと思う.
(2017年4月19日原稿受付)
量子コンピュータが人工知能を加速する
西森秀稔,大関真之
日経BP社,東京,2016,187p,21×15 cm,本体1,500円[大学院~一般向]ISBN 978-4-8222-5189-5
紹介者:田中 宗(早大高等研)
いま注目されているキーワードがタイトルにある本書は,書店でひときわ目につく.実際,産業界で活躍する私の友人たちから,本書を入手したと聞いた.ある人は,学生時代に聞いたことのある「量子」というキーワードに惹かれ,また別の人は「人工知能」の最新の話題を知りたいという動機から購入したそうだ.物理学を学んだことのない人にとっては,最先端科学の発展のスピード感を味わえるし,また,学部生程度の物理学の基礎知識があれば,本書で紹介されている詳細な内容に関しても十分に理解できるよう,随所に工夫が凝らされていると感じた.
著者の一人(西森)は門脇正史博士とともに,組合せ最適化問題を高速かつ高精度に解くと期待される方法,量子アニーリングを提案した.もう一人の著者(大関)は,学生及び研究員として西森研究室でスピングラス理論や量子アニーリング理論の研究を行っており,現在はそれらに加え,機械学習にまで研究分野を広げている.本書は,量子アニーリングの基礎理論や機械学習の研究に取り組む著者が筆を執ったからこそ完成した書籍である.
量子アニーリングがひときわ注目を集めたきっかけは,2015年末に発表された「量子アニーリング専用機は古典コンピュータに比べて1億倍速い計算を達成した」というニュースだ.この「1億倍」という数字が独り歩きし,科学的に不正確な記事を目にすることがある.本書ではこのニュースのきっかけとなった研究について,科学的に正確に,かつ平易に紹介している.量子アニーリングの仕組みについても明快に述べられている.量子アニーリングとは何か? 何ができるのか? を知りたい方にとって,絶好の書籍だ.
また,2016年6月にアメリカで開催された量子アニーリングの国際会議についての最新リポートもあり,会場の熱気が伝わってくる.更に,量子アニーリング研究の初期から現在に至るまでの注目度の変遷や,海外での爆発的な研究のスピード感,国内動向に対する著者の思いが詰まった記述に溢れている.最先端研究ドキュメンタリーとしても,気楽に読める書籍である.
評者は本書が対象とする研究分野の応用展開の研究を進めている.本書を読み,ハード・ソフト・アプリの三方向から協調的な研究開発を進めることの重要性,それを実現させるため,様々な垣根を乗り越える挑戦が必要であることを再認識した.
本書は,量子アニーリングに特化している点が特徴である.本書を読んだ後で,量子コンピュータ全般についての進展を追いかけたくなるかもしれない.量子の生み出す不思議を追求したくなるかもしれない.本書をきっかけに,読者の視野が更に広がる.それこそが著者の真の狙いなのだと感じる.
(2017年3月8日原稿受付)
量子散乱理論への招待;フェムトの世界を見る物理
緒方一介
共立出版,東京,2017,ix+285p,21×15 cm,本体4,800円[専門~学部向]ISBN 978-4-320-03600-0
紹介者:萩野浩一(東北大院理)
量子散乱理論は,学部学生が量子力学の講義の後半で学習する内容であるが,苦手意識を持つ学生が少なくない.散乱の量子力学には特殊関数がたくさん出てきてそれだけで嫌になる,という学生の声も聞こえてくる.散乱は,あらゆる物質や粒子の性質を知るうえで必須の手段であるが,このままではどうにももったいない.
本書は,散乱問題が初学者に与えかねないこのような苦手意識をうまく取り去るとともに,散乱問題を学ぶ魅力を十二分に伝えてくれる良書である.そこでは,原子核反応(したがって表題にあるフェムト・スケールの散乱)を主な題材にして,現実の世界で起こっている散乱現象と量子力学がうまく結び付けられている.原子核反応から題材がとられているが,むろん,書かれている内容は多分に量子力学の応用問題であり,原子衝突や分子衝突など,量子散乱問題が必要となる他の分野の現象でも有用である.
「恥を忍んで告白すると,著者は昔から量子力学が苦手であった.」と著者自身も前書きで述べているように(ただし,「苦手」という言葉にはかなりの謙遜が含まれていると捉えるべきである),本書には初学者が得てして躓いてしまいがちなところが丁寧に説明されており,まさに「かゆいところに手が届く」教科書になっている.難しい概念や,通常だと数式ばかりになって初学者が本質をつかむのが大変なところも,簡潔で分かり易い説明があり,量子散乱問題を楽しむことができるようになっている.これはアイコナール近似を主な手段として用いることにより可能となったことであり,量子力学の教科書によく出てくる部分波展開も教科書の後半になって初めて顔を出す.
本書は全10章から構成されており,1~9章は量子散乱理論の良い入門書になっている.一方,最終章はそれまでの章とは趣が多少違っており,著者自身の研究内容のレビュー的な章となっている.当該分野の大学院生や研究者にとっては著者の研究内容を知るうえで有用であるが,それ以外の読者は読み飛ばしてよいであろう.
本書のもう1つの特徴は,教科書の中の結果を得るために用いられた計算プログラムが,著者のホームページ上で公開されていることである.実際に計算プログラムを走らせてみて数値計算を行うと(そして,できればプログラム自体を読んでみると),教科書の内容がぐっと深く理解できるであろう.これは初学者にとって量子散乱理論をより身近に感じることができる近道である.
量子散乱理論に苦手意識を持っている学部学生はもちろん,散乱の量子論をこれから学ぶ学部学生,量子散乱理論を実際に必要としている大学院生や研究者に広く本書をお薦めしたい.教育的な良書であり,学部3年生~4年生の少人数ゼミの輪講用テキストとしても適当な教科書となっている.むろん,散乱の形式論や共鳴散乱理論など,本書でカバーされていない内容も多々あるが,本書を足がかりとしてよりアドバンストな教科書に読み進めれば,著者が意図した本書の目的の主な部分は達成されたと言えよう.
(2017年7月26日原稿受付)
トポロジカル絶縁体・超伝導体
野村健太郎
丸善出版,東京,2016,xii+371p,22×16 cm,本体5,500円(現代理論物理学シリーズ6)[大学院向]ISBN 78-4-621-30103-6
紹介者:古崎 昭(理研)
物性物理学においてこの10年間に最も大きな研究の進展があったテーマの一つがトポロジカル絶縁体であることは言を俟たない.2005年~2007年に量子スピンホール絶縁体と(その3次元版である)トポロジカル絶縁体の存在が理論的に指摘され,それらが一年も経たないうちにHgTeやBiSb合金などの物質で実験的に検証されて以来,トポロジカル絶縁体となる物質が数多く発見され,実験と理論の両面で活発に研究が展開している.また,超伝導体にも3Heの超流動相のように準粒子励起が非自明なトポロジカル構造をもっている相があることが再認識され,超伝導体の端や渦に束縛されたマヨラナ状態が注目されている.2016年のノーベル物理学賞は「トポロジカル相転移と物質のトポロジカル相の理論的発見」の業績によりThouless, Haldane, Kosterlitzが受賞したが,ThoulessとHaldaneのトポロジカル相に関するいくつかの先駆的研究が種となって近年のトポロジカル絶縁体研究につながっており,2016年のノーベル賞は時宜を得たものであった.
本書は,トポロジカル絶縁体とトポロジカル超伝導体について,基礎的な理論を詳しく説明している教科書である.著者はこの分野の最先端で活躍してきた理論研究者であり,本書は著者が大学院で行った集中講義のノートをベースとしている.トポロジカル物質群の紹介や実験に関する説明は最小限にとどめて,理論的な側面について基礎から最近の話題まで広くカバーしている点が本書の特徴である.途中の式変形をあまり省かずに詳しく理論が説明されているので,自分で計算を追って学ぶことができる点で教科書として有用だろう.
本書はBerry位相の説明(第2章)から始まり,第3章で整数量子ホール系のエッジ状態やTKNN数が説明されている.第4章と第5章では,トポロジカル絶縁体の標準的な模型と時間反転対称性やトポロジカル不変量について詳しく議論されている.第6章と第7章では,BCS理論の導入後,トポロジカル超伝導体とその境界に束縛されたマヨラナ状態について説明される.第8章では対称性に基づいたトポロジカル絶縁体・超伝導体の分類の一般論が解説される.ここまでは量子力学を一通りマスターしていれば,読み進めることができる.第9章~第13章では発展的な話題として,場の理論を用いた電磁応答と熱応答の有効理論,乱れの効果,ワイル半金属とカイラル・アノマリーが取り上げられている.これらの章には著者自身の研究が反映されている.
本書は,トポロジカル絶縁体・超伝導体に関する理論を基礎からじっくり学ぶのに好適な教科書である.一方,トポロジカル物質群や実験について知識を補うためには,実験家らがトポロジカル絶縁体について書いた他書1-3)を参照する必要がある.
参考文献
1)安藤陽一,『トポロジカル絶縁体入門』(講談社,2014年).*1
2)齊藤英治,村上修一,『スピン流とトポロジカル絶縁体;量子物性とスピントロニクスの発展―(基本法則から読み解く物理学最前線1)』(共立出版,2014年).*2
3)高橋 隆,佐藤宇史,『ARPESで探る固体の電子構造;高温超伝導体からトポロジカル絶縁体(基本法則から読み解く物理学最前線16)』(共立出版,2017年).
(2017年8月10日原稿受付)
*1 編集部注:当学会誌第71巻第3号新著紹介欄に書評記事あり.
*2 編集部注:当学会誌第70巻第1号新著紹介欄に書評記事あり.
超新星
山田章一
日本評論社,東京,2016,vi+279p,22×16 cm,本体3,400円(新天文学ライブラリー第4巻)[専門~学部向]ISBN 978-4-535-60743-9
紹介者:諏訪雄大(京大基研)
本書は,「物理学の総合商社といわれる重力崩壊型超新星」(本書より抜粋)について系統的にまとめられた教科書である.超新星は,既知の4つの相互作用(重力,電磁気力,弱い力,強い力)のすべてが重要な働きを持つ極めて希有な現象である.そのため,その理解は困難を極める.実際に,1,000年以上におよぶ観測例があるものの,いまだに爆発機構は明らかにされていない.超新星の爆発機構は宇宙物理学における大問題のひとつとして長年議論が続いており,いまなお活発な研究現場である.
著者は超新星爆発機構の研究に長年携わっており,その幅広い知識を網羅的にまとめたのが本書である.これまで宇宙物理について書かれた教科書は数多くあるが,超新星に特化したものはなかった.本書では,大質量星の末期の瞬間に起こる重力崩壊,中性子星形成にともなう衝撃波形成,そして衝撃波の失速および復活といった近代的な超新星ダイナミクスのエッセンスをあますことなく丁寧に解説している.特筆すべき点として,近年注目されている新たな流体不安定性である定在降着衝撃波不安定性(Standing Accretion Shock Instability; SASI)の解説があることが挙げられる.この不安定性はまだ発見から歴史が浅く,きちんとした解説をした教科書は洋書にも(解説者の知る限り)存在しない.したがって,周辺分野の方で研究会等では聞いたことがあるもののその実体が理解できない,という不満をお持ちの方には一読をお勧めしたい.難解であるためこの本だけで完全な理解に至ることは難しいものの,さらに深く調べる際のとっかかりとなる情報が提供されている.
本書の後半では,近い将来に我々の銀河系で超新星爆発が起こった際に観測されるであろうニュートリノおよび重力波についても述べられている.超新星1987Aからのニュートリノ観測によって「中性子星形成が超新星爆発を引き起こす」という基本的な描像が観測的に実証され,次に同様のイベンが起こればニュートリノ観測によって爆発機構に迫ることが可能となる.それに加えて,ブラックホールをはじめとするコンパクト連星系からの重力波が検出されたいま,超新星からの重力波を観測することが次に新たな驚きや発見をもたらすことが予見される.銀河系内超新星はいつ起こるか予想できず,明日にでも観測されるかもしれない.こうした状況の中で,現在の理解や今後の発展に欠かすことのできない知識を得るのに本書はうってつけだと言えるだろう.本書を入り口に,わくわくする超新星爆発業界に新規参入する研究者が現れることを切に願う.
(2017年8月30日原稿受付)
科学の曲がり角;―ニールス・ボーア研究所ロックフェラー財団核物理学の誕生
フィン・オーセルー著,矢崎裕二訳
みすず書房,東京,2016,xiii+210+115p,22×16 cm,本体8,200円[一般向]ISBN 978-4-622-07987-3
紹介者:今野宏之†
ニールス・ボーアを扱った研究といえば,原子の量子論や「コペンハーゲン精神」に象徴される若手研究者を惹きつけるカリスマ性などが殆どだった.これに対して本書では,これまであまり注目されなかった研究所の運営・資金調達に見せたボーアの強かな経営手腕に焦点を当てている.そのためボーア研究所が核物理学へ大きく方向転換する時期,つまりビッグサイエンスの始まりの時期に着目して,研究所の研究内容の変化という内的原因と国際的資金援助という外的原因の両面から分析する.扱われる期間は,研究所が設立された1921年から40年にナチスに占領されるまでである.
研究所設立の趣意書では,物理学における理論と実験の一体化が強調されていた.ここでの理論はスペクトル線の量子論,実験は分光装置だった.資金集めではビール醸造会社の「カールスベリ財団」に援助を求めている.外国からの財政支援では,ロックフェラー財団の国際教育委員会(IEB)が主要な支援元となる.IEBの援助政策には,優秀な若手科学者を研究所で一定期間研鑽させるという趣旨が含まれていた.これはボーア自身の研究スタイルにも合致していた.ところが30年代半ばになるとIEBの出資目的が変化する.ヒトラーが政権を握りユダヤ人科学者たちが追放されたからだ.出資要件は,亡命者の研究を支援すること,しかし従来のような若手でなく業績を積んだ中堅科学者が対象となった.さらにIEBは物理学と化学を生物学に用いる新たな実験生物学の研究を資金援助の対象にした.ところがボーアは,相補性関係を生命現象に敷衍する哲学的問題の方にしか興味がなかった.そのため,IEBからの何度かの働きかけにも34年4月までは具体的な提案を出すことをしなかった.ところが半年後にはボーアの態度が一変して,財団の要望にピッタリ合った計画書を提出したのだ.何がボーアにそう仕向けさせたのか,というのが本書の論点である.
ボーアは,当時研究所に亡命していたG.ヘヴェシーに白羽の矢を立て,彼の開発した放射性トレーサー法を生物学の問題に応用するという計画を立案したのだ.実はこれにはもう一つの目論見があった.この時ボーアの研究所は最先端の核物理学へ舵取りをしようとしていたのだ.そこでボーアは加速器の導入を計画した.まずカールスベリ財団からコッククロフト−ウォルトン型高電圧装置の資金援助を取り付ける.一方IEB側にはこのことをほのめかしながらサイクロトロン建設を申請した.名目上は実験生物学の計画に沿う申請だったが,用いられる装置はそのまま核物理学研究に利用することができた.これ以降ボーアの研究方法も一変する.それまで原子核の実験成果は量子論の一般的な理解を深めるための手段ぐらいにしか考えていなかったのが,36年の「複合核モデル」が示すように,特定の実験結果を説明するために理論を考えるというスタイルに変わったのだ.こうして核物理学研究への転向は,理論と実験の新たな一体化へ進むことになる.
物理学と科学史で学位を持つ著者オーセルーは,公刊・非公刊資料を駆使して,資金集めのタフネゴシエーターとしてのボーアの姿を余すところなく描き出している.こんにちのような基礎科学の研究にもお金がかかる時代にこそ,一読をお薦めする本である.
(2017年9月1日原稿受付)
† 別府大学名誉教授
物性物理100問集
大阪大学インタラクティブ物質科学・カデットプログラム物性物理100問集出版プロジェクト編,木村 剛,小林研介,田島節子監修
大阪大学出版会,大阪,2016,xiv+139p,30×21 cm,本体2,400円[大学院・学部向]ISBN 978-4-87259-571-0
紹介者:越野和樹(東京医科歯科大教養)
人文・自然を問わず,科学の一分野を初めて学ぶときにまず欠かすことのできないのは,優れた教科書に従って系統的に知識を身につけることであろう.それに並行して,特に自然科学の場合には,数多くの演習問題をこなして理解を定着させ応用力を養うことも重要である.固体物理学では,前者の教科書に関しては,キッテルのような古典的名著をはじめとして,より現代的な視点から工夫を凝らした良書が国内外の著者により数多く出版されており選択の幅が広い.一方,後者の演習に関しては著作が少なく,大概は教科書の「章末問題」などに頼らざるを得ないが,問題量が少なかったり,解説が不十分であったりといった難点を抱えていることが多い.
本書は,物性物理学(主に固体物理学)に焦点を絞った演習書である.元々は物性物理を専攻する大学院生に対して使われてきた問題集であったものに,履修学生自身が毎年度改訂を重ねて完成した,いわば出題者と解答者とのコラボレーションで生まれた演習書である.特に解答者側の視点が強く反映されているのが本書の特長であり,問題・解説ともに読みやすく書かれていると評者には感じられた.とはいえ演習書という性格上,個々のテーマを深く掘り下げている訳ではないので,詳しく書かれた教科書で知識を補いつつ,本書の問題を解き進めるのが良さそうである.
標題通り,本書は100問からなる物性物理の演習書であるが,その内訳は次の通りである.第1章で現代物理学の基礎である量子力学・統計力学に関する11問を,第2・3章で結晶構造とX線回折に関する16問を扱ったのち,第4章から12章で,固体物理学の主要テーマ(格子振動,自由電子モデル,エネルギーバンド,半導体,光学応答,相転移,磁性,超伝導)に関して,バランス良く67問が割り振られている.本書に特徴的なのが実験に関する話題を扱う第13章である.この章は6問と分量は少ないながらも,様々な物性実験の測定原理や長短所が簡潔にまとめられており,物性実験の基礎知識を効率良く得ることができる貴重な一章である.問題のタイプは,紙と鉛筆を使った本格的な計算を求めるもの,定性的説明を求めるもの,基礎知識を端的に問うもの,と多様である.それぞれの問題に対して,およそ2倍のスペースを割いて解答例が記されており,結果の解釈や含意にまで言及している箇所も多く教育的である.
これから物性物理を学ぼうとしている学生には,是非じっくりと取り組んで欲しい良書である.また,本書をきっかけとして,他の分野でも同様の演習書が出版されることを期待したいと思う.
(2017年9月11日原稿受付)
半導体量子輸送物性
勝本信吾
培風館,東京,2015,v+268p,22×15 cm,本体3,600円(新物理学シリーズ43)[大学院・学部向]ISBN 978-4-563-02445-7
紹介者:阪野 塁(東大物性研)
物性物理学の究極の目標の一つは,物性を発現する機構を理解し,そしてその知見を活かし物性を自在に制御することである.半導体物理の研究においても,不純物ドーピングに始まり,ナノスケールでの構造の微細加工により様々な物性を創り出す技術が研究されてきた.今日では基板上で個々の電子の量子性を制御し,実験できるまでになっている.また,制御性と作り込みが可能なことを活かし,単純な半導体の物性の研究を超えて,量子力学や統計物理学,多体効果など基礎的な性質を調べる舞台としても,注目を集めている.
本書は,半導体物性の基礎から始まり,半導体基板上に作り込まれた量子デバイスの量子輸送までの,最近の話題を解説している.具体的には,量子ドット,量子細線,量子井戸などの低次元系と,それを組み込んだ干渉計などの量子回路,超伝導接合系,スピントロニクスの基礎となる半導体物性が挙げられる.特にここ10年で発展してきた話題を中心に,実験・理論の両面から丁寧に解説されている.
私は同じ著者の『メゾスコピック系(朝倉物性物理シリーズ)』(朝倉書店,2003年)を修士課程時代から愛用してきた.背景にある理論の丁寧な解説に加え,精巧な実験結果の説明が多く示されているため,読者の興味を強く惹き,飽きさせない構成になっているからだ.また,当時の最先端かつ,重要な話題に内容が絞られていたため,内容は今でも色褪せない.本書でもそのスタイルは変わっていない.さらに培風館の新物理学シリーズの特徴を反映し,説明は一層丁寧になっている.半導体物性のテキストでは,理論,実験どちらか一方に重点を置いたものは多くあるが,ここまでバランス良く展開しているテキストは少ない.本書がターゲットとしているように学部4年生程度の基礎知識があれば,十分に理解できるように構成されている.それを超えるものも,詳しい導入と付録などで,この一冊内で理解できるようになっている.前著『メゾスコピック系』と比較すると,この10年で大きく発展した,量子ビットとしての量子ドットや,スピン輸送,トポロジカル絶縁体,スピンホール効果などの半導体スピントロニクスの最近の話題が中心へと変わっている.また,量子回路や,超伝導接合系,整数・分数量子ホール効果などの解説も,近年の発展を受けて大幅に更新されている.ただし,本書は高度に専門化された最新の理論についてのテキストではない.最新の実験がたどり着いたところまでの物理が,懇切丁寧に解説されている.
半導体物性の研究者や学生ばかりではなく,量子論や熱・統計力学の基礎を現実に試す舞台を探している研究者にとっても有益な一冊であるはずだ.また,丁寧な解説により,分野外の読者にも,半導体基板上で展開する量子力学や多体効果などの興味深い物理とその現状について,楽しめる内容になっていると思う.
(2017年10月3日原稿受付)
相転移・臨界現象とくりこみ群
高橋和孝,西森秀稔
丸善,東京,2017,x+385p,21×15 cm,本体5,200円[専門~学部向]ISBN 978-4-621-30156-2
紹介者:竹内一将(東工大理)
統計物理学において,臨界現象は,素朴な問題設定から極めて非自明で,普遍的で,美しい物理が出現する代表例として,今なお多くの人を惹き付けている.その魅力を最も強く感じるのが,Wilsonのくりこみ群による臨界現象の記述を目の当たりにしたときではないだろうか.固定点にパラメータが吸い込まれていく図を見て,あるいは単にくりこみ群という名前の響きから,漠然と興味を持つ方も多いだろう.しかし,いざ中身を勉強しようと思うと,意外と教科書選びに苦労する.定評ある本は大体洋書で,また計算の詳細に踏み込まないものも多いからである.
本稿で紹介する書籍,高橋和孝氏・西森秀稔氏による『相転移・臨界現象とくりこみ群』は,そのような方にとって標準的な選択肢の1つになることだろう.本書は,相転移や臨界現象の基礎的な解説から始まり,平均場理論や可解模型などの要所を抑えながら,くりこみ群の概念的導入,具体的手法へと入っていく.前半は後半の枕に終始せず,それ自体が臨界現象の優れた解説となっている.気液臨界現象とIsing転移の繋がりも示唆され,普遍性への布石が打たれる.後半は,スケーリング理論やくりこみ群の考え方が説明されたうえで,実空間くりこみ群,運動量空間くりこみ群,演算子積展開など具体的方法が詳述される.連続対称性をもつ系も扱われる.また,Wilson流くりこみ群のほか,場の量子論で発展したくりこみ群の方法も簡潔に触れられ,橋渡しにフラクタルの例を挟むなど,工夫がされている.最後は,2016年ノーベル賞でも話題になったKosterlitz-Thouless転移や,量子相転移についてもエッセンスが語られ,本書の結びとなる.くりこみ群の解説後半はやや難度が上がるものの,全体的に飛躍の少ない丁寧な説明がなされており,読者が実際に計算できるようになるための配慮も感じられる.
実は本書は,著者の一人である高橋氏が,東京工業大学の大学院生向け講義で配布していた講義ノートがベースとなっており,当時から学生には重宝されていたようだ.それが書籍化にあたり,西森氏が著者に加わったこともあって,大幅に加筆修正されたものが本書である.そのためだろうか,本書には痒いところに手が届くような注釈が多く,学生が抱きやすい疑問点に講義で対応してきた経験が随所に感じられる.また,原著論文も数多く引用されているほか,巻末には著者のコメント付きの関連書籍リストがあり,学習を一層深めるのに役立つ.高橋氏による特設サイトhttp://www.stat.phys.titech.ac.jp/˜ktaka/rg/ もあり,Q&Aや,書籍化にあたり割愛された章が公開されている点もユニークだ.なお,西森氏には『相転移・臨界現象の統計物理学』(培風館)という著書がある.扱う内容からして必然的に重複する部分はあるものの,今回の書籍は高橋氏のスタイルが色濃く,別書と言って良いだろう.こうした書籍が日本語で手に入るようになったことを喜びたい.
(2017年10月6日原稿受付)
ブラックホール天文学
嶺重 慎
日本評論社,東京,2016,vii+292p,22×16 cm,本体3,300円(新天文学ライブラリー第3巻)[専門・大学院向]ISBN 978-4-535-60742-2
紹介者:吉田直紀〈東大理〉
ブラックホールに関する書籍は相対論から宇宙物理学,そして量子情報理論などの専門書,さらには一般向け解説書と数多くあるが,意外にも天文学の重要トピックとしてブラックホールを取り上げ,関連する物理過程や最近の多波長にわたる観測結果を1冊で解説したものはほとんどなかった.一方でブラックホールに関する興味は研究者の間でも高まっている.最近では米国のLIGOによる重力波検出のニュース(とノーベル物理学賞受賞)も記憶に新しい.また,長基線長の電波干渉計により「ブラックホールシャドウ」を直接観測する計画が順調にすすんでいるとも聞く.
本書はタイトル通り,ブラックホールを天文学の主役の一つとして取り上げ,宇宙に存在する大小様々なブラックホールについてその理論予言から発見の歴史,さらには最近の研究の進展まで解説している.ブラックホールは天文学を研究するうえで欠かせない要素であると思われるが,著者は昔からそう受け止められていた訳ではないと述べる.今では考えられないが,キワモノ的な扱いをうけた時期も長かったらしい.
本書第1章は,ブラックホール天体発見の歴史的経緯や論争などを描いたイントロダクションからはじまる.はじめは教科書というよりは読み物的で気軽に読むことができるが,中盤以降は数式も使い,回転ブラックホールのカー解やエディントン光度などもこの章で紹介される.第2章はブラックホールの「光り方」について,標準的な理論モデルを用いて解説する.ブラックホールは光さえ飲み込んでしまうのでその名の通り暗黒の存在である.しかし,周辺のガスや星が飲み込まれる際に円盤(降着円盤)が形成され,様々な物理過程を通して電磁波を放出することでブラックホールは光輝く天体となる.ちなみにカバー裏表紙に載せられた回転ブラックホールの画像は,ぱっと見ただけでも興味をそそられるが,この章の最後にその現象が紹介されている.第3章と第4章は標準円盤理論モデルから円盤不安定性や超臨界降着流などの高度の内容を含んでおり,これから高エネルギー天体の研究をはじめる大学院生に薦めたい.私が夢中になって読んだのは,第4章にある円盤不安定性の議論であり,降着円盤と星の構造の比較のおかげで随分と理解がすすんだ.これらの章の内容は著者の専門分野に近いもので,その分熱意あるいは気迫が伝わってくる部分も多い.第5章では星の進化理論とともに恒星質量ブラックホールの形成を解説したのち,超巨大ブラックホールの謎に迫る.この中で,フリードマン宇宙モデルや密度ゆらぎの成長など宇宙論の基礎を挿入し,読者の理解を助けている.本文中での宇宙論の解説は少し寄り道に感じられるかもしれないが,銀河とブラックホールの共進化に関しては宇宙論的な文脈での考察が必要であるから適切な配分だと思う.最後に第6章では,研究の最前線と題して,現在アクティブに研究されている課題を紹介する.若手研究者にとっては良い研究テーマ探しの一助になるだろう.
こうして1冊読み終えると,宇宙に存在する大小様々なブラックホールの形成や進化についての知識を万遍なく習得できる.天文学と宇宙物理学の教科書として,この新天文学ライブラリーシリーズの趣旨に沿っていると言えるだろう.唯一惜しまれるのは,最近の重力波検出や連星大質量ブラックホールに関する記述がないことであるが,本書が出版されたのはLIGOによる重力波検出報告の前なので,非常に残念だがやむを得ない.質量が太陽の30倍以上にもなるブラックホールが存在し,連星系をなしていたことは天文学上全く新たな発見であり,現在ホットな研究トピックにもなっているので,できるだけ早くに本書の改訂の機会があり,内容がさらに充実することが望まれる.また,重力波については同シリーズで刊行が予定されているので,待ち遠しく思われる.
(2017年10月12日原稿受付)
基礎から学ぶ強相関電子系;量子力学から固体物理,場の量子論まで
勝藤拓郎
内田老鶴圃,東京,2017,x+248p,21×15 cm,本体4,000円(物質・材料テキストシリーズ)[学部向]ISBN 978-4-7536-2310-5
紹介者:沖本洋一(東工大理学院)
私が学生時代に(というともう20年以上も昔か...),よくこんな言葉を聞いた.「最近の本や教科書は,薄くて文字がスカスカになってしまったが,これも時代の流れですかね...」確かに私の世代より前の本は活字が小さくびっしり文章が書きこまれており,再版するときに活字を大きいものに改める,といった改訂作業もよくなされていた.しかし慣れというのは恐ろしいもので,我々はいまやこの「軽薄な」レイアウトにすっかり慣れてしまっている.いわんや21世紀生まれの学生なら薄くて活字の大きな教科書を読みたがるであろうし,出版社も分厚い本の出版には二の足を踏む時代だ....そんなことを考えていたら本書が現れた.
本書の特長は,何といっても字数の密度の高さだろう.ページをめくってみれば,サイズの小さい活字がびっしり埋まっており,まさに昭和にタイムスリップしたようだ.では,この時代に逆行(?)する教科書の出版において,出版社と著者たちはどのような戦略を用意したのだろうか? 本書はいわゆる「強相関電子系」と呼ばれる研究分野のための教科書で,前半は基礎となる固体物理学の重要点がまとめられている.量子力学の基礎からはじまり,1個の井戸から2個の井戸,そして無限個の井戸のポテンシャル中を動く電子の運動を説明していく.通常の固体物理の教科書では簡単にすまされてしまうところを,たくさんの図とページ数を割いて熱く読者に語りかける.これにより読者は,よく言われるところの「固体とは電子の導波路である」ことを容易に会得することができるだろう.ここで説明された一電子系の知見は,後半部において直ちに多体系に拡張され,波動場の量子化に基づく第二量子化の考え方が説明される.世の教科書では,第二量子化とは実は二回目の量子化ではないよといって冷めた書き方をするものが多いが,そんな中で本書ほど第二量子化を熱く丁寧に説明した教科書は他に類を見ないと言ってよいだろう.大学の学部の講義で量子力学の講義が途中で終わってしまった実験系の学生にとってもよい入門書になっている.後半部では,主に遷移金属酸化物を中心にd電子が織りなす伝導と磁性,およびその複合物性が解説されており,強相関電子材料の面目が語られる.といっても単なるレビューではなく,前章までに(これでもかと)書かれた電子の量子力学の知識(と対称性の議論)をうまく使った骨太の記述となっており,これからこの分野に進む若手の研究者ばかりでなく,マルチフェロイクスやトポロジカル絶縁体などの分野を志す大学院生や学部生にとっても基礎的知識を与えてくれるだろう.興味深いのは,最終章に固体の光学的性質についての章が置かれていることで,そこでは固体の誘電関数がマクロとミクロな観点からどう記述できるかがコンパクトに説明されている.
総ずるに,本書には強相関電子系を熟知した著者による,若き学徒への熱くそして温かい語りかけがある.これこそが,この密度の濃い教科書を新しいタイプの入門書として白眉たらしめているのであり,そしてそれは強相関材料研究の道を一歩一歩堅実に歩んできた著者だからこそ可能になったものと言ってよいだろう.本書を強相関電子材料研究に従事する若手研究者や大学生はもちろん,広く固体物理学に携わる人々に推薦したい.
(2017年11月20日原稿受付)
中間子原子の物理;強い力の支配する世界
比連崎 悟
共立出版,東京,2017,vi+171p,21×15 cm,本体2,000円(基本法則から読み解く物理学最前線15)[大学院・学部向]ISBN 978-4-320-03535-5
紹介者:大西宏明(東北大電子光理学研究セ)
物質を構成する最も身近な存在と言える陽子は,素粒子クォーク3つからなる複合粒子であることはよく知られている.さて,この陽子の質量のうち,構成要素たるクォークの質量(ヒッグス粒子により与えられる質量)の占める割合は高々3%である.では残りの97%はどのように獲得されるのか? それは,2008年に南部陽一郎博士のノーベル賞受賞で有名となった我々の真空が持つ「カイラル対称性の自発的破れ」により獲得される,と考えられている.実は,このハドロン質量獲得機構ともいうべき,「カイラル対称性の自発的な破れ」をどのように実験的に検証すれば良いのか?という問いは,今尚ハドロン物理において注目を集める大問題である.その有効な方法の一つが本書のメインテーマと言える「中間子原子核束縛状態」の研究である.
著者は,この分野を牽引する非常にアクティブで,また本書でも触れられている「深く束縛されたπ中間子原子」研究の創成記から第一線で活躍してきた理論研究者である.したがって,本書の内容は,歴史的な背景を熟知している著者らしい,実に興味深い内容となっている.評者はこれまで中間子原子核,特にK中間子やベクトル中間子に関する実験的な研究に携わってきたが,本書4章で詳細,丁寧に説明されている散乱断面積の導出部分などを読み改めて,「あ,こういうことだったのか!」と気付かされる場面が多くあった.これまでの不勉強を恥じるとともに,良い書籍に出会えたという感慨は深い.
さて,本書は1章,2章で基本的な事項を一通り示したのち,3章で中間子原子核研究について,またその背後にあるハドロン物理の面白さについての見解を示されている.例えば,「クォーク階層とハドロン階層の間をつなぐ研究は,真空の構造変化の研究であると言うことである.」と言う指摘は,ハドロン物理の本質的な課題をまさに言い当てている.その後,第4章として中間子原子核探索に関する理論的な枠組みを,実験結果などを踏まえ,わかりやすく解説し,最後の5章で最新実験結果や現在進行中の理論的,実験研究に関する紹介,またその解釈に関する議論を展開している.全体を通じて,「わかりにくいかな?」と思うところには参考文献が引用されているなど,細かな配慮がされているのであまりこの分野に馴染みのない読者にも読みやすいものとなっている.
本書は,多くの読者にハドロン物理の面白さを垣間見させてくれる良書であると同時に,ハドロン物理を志す大学院生にとっては,良い入門書となるであろうと確信している.より多くの学生,院生に一読を薦めたい書籍である.
(2017年10月31日原稿受付)
Trapped Charged Particles; A Graduate Textbook with Problems and Solutions
M. Knoop, N. Madsen, R. C Thompson, Eds
World Scientific,UK,2016,x+434p,23×15 cm,US$78.00(Advanced Textbooks in Physics)[専門・大学院向]ISBN 978-1-78634-012-2
紹介者:岡田邦宏(上智大理工)
近年,イオントラップを利用した研究が再び活況を呈している.従来から行われてきた精密分光や精密質量測定への応用に加えて,反物質科学など基礎物理学の検証実験,極低温化学,さらにはエレクトロニクス分野を巻き込んだ量子計算・量子情報処理技術への応用が注目されるようになったことがその大きな要因と思われる.本書は,上記のようなイオントラップを用いた先端的な研究を行いたいと考えている大学院生や若手研究者に向けて書かれた参考書である.原案はフランスで開催された若手研究者向けのウィンタースクール(Second Winter School on Physics with Trapped Charged Particles at Les Houches in January 2015)での講義であり,そのときの講師陣や各分野の最前線で活躍している研究者が本書を執筆している.本書の特徴は,イオントラップとそれを取り巻く様々な研究に関する理論と実験の基礎知識に加え,装置開発や実験のノウハウについても解説していることである.章末にはより深く学ぶために必要な文献がリストされ,内容の理解を深めるための演習問題(とその解答またはヒント)まで与えられている.イオントラップを用いた研究のための参考書としては,初学者への配慮がみられるこれまでに無いタイプのものと言えるだろう.
本書は全18章,434頁からなり,電子版も作成されている.イオントラップ研究に関連した基礎的な理論と実験技術の解説に1-13, 16章が充てられ,残りの章では具体的な研究トピックス(14, 15, 17, 18章)が紹介されている.詳細をみてみよう.1,2章ではイオントラップの原理,6,7章ではイオン冷却法の要点がコンパクトに解説されている.3, 4章,及び9-13章では磁場中の荷電粒子の一般論やプラズマの基礎理論,さらには非中性プラズマの特性とその測定法が解説されている.一方5章と8章では,原著論文では滅多にお目にかかることのない実用的な知識が披露されている.例えば5章では,実験に必要な超高真空を得るための"コツ"が事細かに説明されており,実験家としてとても印象に残る内容であった.8章では,イオントラップ中のイオン運動をシミュレートするための数値計算法とその周辺技術が概説されている.計算に必要なコンピュータの処理能力とディスク容量,並列CPUとGPU計算機による計算時間の比較,さらには並列計算コードのライブラリに触れるなど,初学者が必要とする情報の要点が記述されている.研究トピックスでは,反水素物理学(14章),イオンのクーロン結晶を用いた応用研究ガイド(15章),基礎物理学の精密検証(17章),光周波数標準の研究と応用(18章)が紹介されている.原著論文には書かれてはいないが,第一線で活躍する研究者だからこそ書ける研究のノウハウがあちこちに散りばめられているので,興味深く読むことができる.なお,これらの研究トピックスの章末にも演習問題が準備されており,本書のコンセプト"A raduate Textbook with Problems and Solutions"が貫かれている.敢えて足りない点をあげるならば,イオントラップを用いた量子計算,量子情報処理に関する話題が殆ど取り上げられていない点であるが,これらの内容については続編の刊行に期待したい.イオントラップを用いて行われてきた膨大な研究の全容を本書だけで網羅することは不可能であるが,章末には適切な文献が与えられているので,本書を手がかりにして必要な知識に寄り道することなく辿り着ける.イオントラップを自分の研究分野で生かしてみたい,あるいはイオントラップを用いた研究の概要を知りたいという大学院生や若手研究者にはうってつけの参考書となりそうである.
(2017年12月25日原稿受付)
ナノ構造物質の光学応答
張 紀久夫
丸善,東京,2012,xi+233p,22×15 cm,本体6,000円[専門・大学院向]ISBN 978-4-621-06474-0
紹介者:横山知大(阪大院基礎工)
本書はマクスウェル方程式で記述される古典電磁気学と量子電磁力学(QED)の中間領域,ナノスケールにおける物質と電磁場,特に可視光との相互作用を理論体系付ける目的で書かれた「教科書」である.著者の英文書の著者自身による訳本と位置付けられているが,著者本人が翻訳よりも原著意図の伝達に重きを置いており,補足も多くされていることから独立した新著として紹介したい.
先に教科書と述べたが,率直に言って教科書とするには少々難読である.著者は若い読者も対象としているが,内容としては大学院生以上向けの専門書で,むしろ光物性に馴染みのある研究室では1冊は置いておきたい,という類の辞書的文献である.本全体のストーリーは1章で本書のメインテーマである「微視的非局所光学応答」に至るまでの背景を簡単に触れた後,2章・3章で本書の半分を使って理論構築と一般論を解説している.後半の4章・5章は各論として著者の研究を基にした具体的な応用例の解説に当てている.「辞書的」と言ったように前半ではナノスケール物質と輻射場の相互作用を厳密・詳細に記述している.序盤のハイライトである電流密度とベクトルポテンシャルを自己無撞着に決定する連立方程式の定式化は非常に簡潔で理論として美しいので,是非一読してもらいたい.また,後半では各論を個別につまみ食いで読める点も「辞書的」である.その意味で,後半は深く通読するよりも必要に応じて読み返すのが良いように思われる.個人的には,4.3節で走査型近接場光学顕微鏡(SNOM)の説明が簡潔で今後何度も読み返すと思う.
本書の主題であるナノ物質の重要性はここで改めて述べる必要もないと思うが,量子サイズ効果によって同じ組成でもバルクとは異なる物性を示すことを考えれば,電磁気学・光学応答を見直すというのはむしろ当然の課題である.しかし,QEDにまで進むと物性としては扱いづらいため,電磁場は準古典的に扱い,ナノ物質中の電子や励起子に量子性を考慮している.この電子や励起子の波動関数がコヒーレントにナノ物質全体に広がっていれば,そのナノスケールの範囲で入射光に対する応答が非局所になり得る,という着想もごく自然なものである.ナノ科学が進歩することで可視光の数百ナノメートルの波長と物質のコヒーレント長を同程度にできるようになった訳だが,そこに現れる非線形・非局所応答を明瞭な理論体系としてまとめたいと思わずにはいられない.
物質と光の相互作用は様々な成分が含まれる.例えば,物質中の誘起電流,その電流による輻射場,誘起電荷間のクーロン相互作用などである.これらは互いに関連しており,慎重に二重カウントを避けなければならない.そのために場の発散がゼロ(∇・E=0)となる横場とそうでない縦場成分の結合,分離について繰り返し言及しており,ナノ物質での統一的な理解・概念構築に腐心していることが分かる.メゾスコピック系の電気伝導論では,技術の発展にともなって量子ホール効果やトポロジカル物性,超伝導量子回路などの多様な広がりを見せた.本書は光物性における「ナノの世代」を構築しようという著者の熱意が伝わる内容である.しかし,未完成な枠組みであるためか表記などが複雑であり,それが内容の難しさの理由の1つだろう.発展途上の分野だが,理論体系をまとめようとする専門書が日本語で書かれていることは日本の学術にとって意義深い. 人は古代から暗闇で火を灯し,星空を見て方角を知り,色で食べ物や鉱物を判断してきた.光による観測は文明の歴史とほぼイコールである.ナノ物質の精密な作製と発光測定によって産声を上げた新しい光科学を楽しみたい.
(2018年1月4日原稿受付)
場の量子論;不変性と自由場を中心にして
坂本眞人
裳華房,東京,2014,xiv+437p,22×16 cm,本体5,300円(量子力学選書)[専門~学部向]ISBN 978-4-7853-2511-4
紹介者:土手昭伸(KEK理論セ)
場の量子論は素粒子,物性は言うに及ばず,宇宙や原子核など様々な分野で用いられ,物理学者にとって必修のものとなってきている.本書はそのような場の量子論のテキストである.私は場の量子論の専門家ではないが,是非とも紹介したいと思い書評を書かせて頂いた.
本書では場の正準量子化までが懇切丁寧にそして独特の語り口で説明されている.著者の軽妙な語り口のためか,理論のテキストでありながら推理小説のようにすら感じられる.さて内容であるが,テンソルなど計算に関する諸準備,物理的背景に始まり,クライン・ゴルドン方程式,マクスウェル方程式,ディラック方程式,各々の説明が続く.ラグラジアン形式そして有限自由度での量子化を経て,スカラー,ディラック,マクスウェル,各々の場の量子化へと進む.正準量子化による場の量子化の説明としては標準的な流れであろう.しかしディラック方程式のローレンツ不変性や離散的不変性の詳細な説明(5, 6章),各場でのネーターの定理を軸にした不変性の説明(9章以降),そして最終章でのポアンカレ代数と1粒子状態の分類など,サブタイトルの通り,不変性や対称性にウエイトをおいた内容となっている.また初学者への配慮も本書の特徴である.初学者が抱くナイーブな疑問,躓きかねない計算には,必ず【注】という項目で補足説明がなされている.また量子力学から場の量子論への橋渡しとして,一つの章が割かれているのも有り難い(8章).そして最大の特徴は,徹底的な計算方法の説明である.正準量子化までの内容で,丸々一冊約400ページを費やしていることからも,如何に丁寧に説明されているか想像できるであろう.例えば,ディラック方程式に関する説明では,何が行列で何が単なる係数なのか,この添え字はスピノルの足,この添え字はローレンツの足といったことまで説明がなされている.更にはダミーインデックスの使い方にまで注意するなど,ここまで説明するかというほどである.また随所にある演習問題"check"にはウェブ上で回答が与えられているが,本文以上に丁寧な説明である.有益な計算方法や追加説明が示されており必見である.
計算に関する多くの記述にも関わらず,その計算自体の意味を忘れないように配慮されている.丁寧な計算の説明の後,必ずその物理的意味の説明に話を戻す.またその計算に関連し,実際の研究での諸問題に随所で言及している.例えば場のエネルギーの計算で正規順序積を導入するところでは,発散するゼロ点エネルギー(真空のエネルギー)を除くためということで話は終わらない.発散のオリジンにまで踏み込み,重力方程式の宇宙項や超対称性との関連を述べている.また場の量子化に進む前に一度立ちどまり,ゲージ原理と3つの力(強い力,弱い力,電磁気力)について,そこまでの話を踏まえた説明がなされている(7章).このように,今学んでいるものが単なる計算ではなく,現実世界を記述する物理であることを強く意識させられる.今日至る所で顔を出す「自発的対称性の破れ」「繰り込み」については,説明は省かれている.この点は残念であるが,さすがに本書一冊にそこまで含めるのは難しかったのであろう.自発的対称性の破れは,続巻にて詳細に説明されるようである.本書によってモチベーションを高められた読者であれば,既存のテキストで頑張って勉強する気になるかも知れない.しかしやはり著者独特の軽妙な語り口による説明が大変楽しみである.続刊の早期発刊が望まれる.(2018年1月現在,未発刊)
最後に.本書前書きを読んだ際,私は次の文章に強い衝撃を受けた:「初学者が場の量子論を難しいと感じる理由の1つは,式の導出に労力の大半が使われてしまい,式の物理的意味を考える余裕がない(式の導出で満足してしまう!?)からである」.私は過去幾度か場の量子論の習得を試みたが,その度に挫折した.延々と数式のフォローをするものの,その意味が理解できないことが度々あった.結果,時間の無駄にしか思えず,場の量子論には極力関わらないでおこうと逃げてしまった.まさに著者の言う通りである.本書では「数式の見方」まで教えてくれているように思う.学生はもちろん,私のように幾度も場の量子論に挫折をした方たちに是非とも読んで頂きたい.
(2018年1月29日原稿受付)
観測に基づく量子計算
小柴健史,藤井啓祐,森前智行
コロナ社,東京,2017,vi+186p,21×15 cm,本体2,800円[専門・大学院向]ISBN 978-4-339-02870-6
紹介者:佐々木寿彦(東大工)
ここ数年,一般のニュースにすら量子コンピュータという単語が現れるようになってきた.ただ実際に量子コンピュータを学ぼうとした場合,通常のコースとしてはまず量子情報理論の基礎を学んだ後で,回路型量子計算の基礎を学び,Shorの素因数分解アルゴリズムといった量子アルゴリズムがどのようになっているのかを学び,回路型での基本的な誤り訂正符号によってエラーが動的に対処できるということを学んだくらいでやっとそれなりに量子コンピュータについてわかってくるようになる.最近の話題についていくにはこれに加えて本書で扱うような測定型量子計算やその他の数々の進展を学ぶ必要がある.
こう書いてしまうと大抵の読者に見切りをつけられてしまいそうであるがちょっと待って欲しい.測定型量子計算は量子計算の実装方法のひとつであるが,特に量子多体系や統計力学と深い繋がりがあるのである.なぜなら,測定型量子計算はまずちょうどよい量子相関をもつ量子多体系の状態を用意し,その後局所的な測定を繰り返すことで計算を進めていくという構造になっており,最初に用意する量子多体系の状態の性質が量子計算の能力という形で捉えなおされるからである.そのため本書が有益となる読者としては,量子情報を学んでいて測定型量子計算をこれから学ぼうとする人のみならず,量子多体系や統計力学をやっている際に量子情報という単語がチラついて気になるものの量子情報を最初からやるほどの時間はないという人が考えられる.実際,著者らは非専門家向けに講演することも多いし,本書もその経験が大いに生きたものになっていると感じられる.
この本の構成としては,1, 2章で背景知識と測定型量子計算に必要な量子情報の基礎を量子ビットの導入という初歩から始めて最短経路でまとめたあと,各章で測定型量子計算の基盤となる種々の考え方の説明とそれに関連する最近の結果について述べられている.特に,物性物理との関連,量子光学・光物質系との関連,誤り耐性量子計算との関連,古典統計物理との関連,暗号との関連,計算量理論との関連について重点的に書かれている.計算量理論との関連のところで量子超越性の最近の話についてまとめられているのも人によっては有益だろう.
この本の長所としては,測定型量子計算の最新の結果に基づいて書かれている点や,各章が比較的独立していて必要な話題について個別に読み進めやすいという点,個々の結果に対する参考文献がしっかりしている点がある.一方で短所としては,教育的配慮が行き届いたタイプの本ではなく未定義の言葉が多少出てきても目をつむって読み進めることが必要な点や,実際の証明は参考文献まかせの結果も多々あるという点がある.このような特徴のため,本書は量子計算を基礎から学びたい人には適していないが,測定型量子計算やその関連分野との関係の概観を日本語で手早く吸収できるものになっており,それが必要な人にはかゆいところに手が届く一冊となっている.本書を通して量子計算の前線の研究に是非触れてもらいたい.
(2018年2月5日原稿受付)
相転移と臨界現象の数理
田崎晴明,原 隆
共立出版,東京,2015,xvi+403p,22×16 cm,本体3,800円(共立叢書 現代数学の潮流)[専門・大学院向]ISBN 978-4-320-11108-0
紹介者:森 貴司(東大院理)
本書は大自由度系に見られる相転移・臨界現象の数理を,イジング模型という最も単純な理論モデルに焦点を絞って解説したきわめてユニークな著作である.特定の模型の詳細な解析が主題でありながら,本書は決してマニアックな書ではなく,大自由度系の物理と数理に関心のある学生,研究者に広く推薦できる一冊に仕上がっている.
本書で強調されているように,イジング模型は「着目する普遍的な物理現象の本質を集中的に研究することを可能にするような最小モデル」であり,その意味で「よいモデル」なのである.イジング模型という限定的な対象を徹底的に研究することによって普遍的な相転移・臨界現象の本質を解き明かすことができる.本書はイジング模型を数理物理学の対象として研究することの重要性と面白さを伝えることに成功していると思う.
もちろん,この成功の理由は題材のよさだけによるものではない.丁寧な解説は細かいところまで行き届いており,予備知識がなくても読めるように周到な目配りがなされている.数理物理の教科書の中には,物理学者にとって高度な数学が前提知識として仮定されており,解説も不親切で「読めない」ものが少なくないが,本書にはそういうことはない.高度に技術的な内容は付録にまとめられており,それらを消化せずとも本筋の内容の理解に支障がないように書かれているところにも,なるべく広い層の読者にとって読みやすい本にしたいという著者の配慮が感じられる.
構成もよく練られている.第1章から第3章までは相転移・臨界現象の標準的な解説であるが,評者にとって,第3章5節の記述が印象に残った.この節では臨界現象についての「よく知られている」ふるまいについて紹介されているが,「一般的な証明はない」,「...と信じられている」,「d=2のみで証明されている」のようなコメントが散見される.こんなことすらわかっていないのか,と数理物理の方法の無力さを感じる読者もいるかもしれないし,むしろ一筋縄ではいかない相転移・臨界現象の物理と数理の世界に魅力を感じる読者もいるかもしれない.第4章でイジング模型を数理的に解析する道具を整え,第5章で無限体積極限の議論をした後,第6章と第7章でそれぞれ高温相,低温相の重要な厳密な結果が示される.第9章で転移点の一意性を示すことによって高温相と低温相をつなげ,第8,10章で臨界現象についての厳密な結果が提示される.無限系の平衡状態の特徴づけを扱う第11章と,イジング模型に関連した問題について解説する第12章は幾分気楽に読めるおまけ的な章である.付録の内容は高度に技術的であるが,数理物理に興味のある読者にはきわめて有益だろう.特にクラスター展開の解説は秀逸である.
本書の持つ魅力を堪能するためには,焦らず,じっくりと読み進めることが肝要である.本書は重厚な本であり,相転移の気楽に読める入門書ではない.また,数理物理学を専門としない読者にとって,本書で学んだ知識がすぐに何かの役に立つことはないだろうし,自身の研究を進める際に手元に置いておくと便利な本というわけでもない.その意味で,本書は実践的な専門書でもない.相転移・臨界現象の数理物理学の世界を純粋に楽しむための一冊である.
(2018年2月13日原稿受付)
量子計算理論;量子コンピュータの原理
森前智行
森北出版,東京,2017,v+183p,22×16 cm,本体3,600円[専門向]ISBN 978-4-627-85401-7
紹介者:後藤隼人(東芝研究開発セ)
最近「量子コンピュータ」というワードが新聞等のニュースでよく見かけられるようになり,一般の人にも広く知られるようになってきた.本書はその名が示す通り,この量子コンピュータの理論に関するタイムリーな本である.
量子コンピュータに関する重要な理論テーマとして,量子アルゴリズム・量子誤り訂正・量子計算量理論の3つが挙げられる.第1章で著者自身が述べているように,本書ではこのうちはじめの2つのテーマは扱わない.その代わり,3つ目の量子計算量理論に関しては最適な入門書となっている.量子計算量理論は,古典計算で確立された計算量理論に立脚して量子計算の速さを定量的に評価する理論であるが,そのわかりやすい教科書は和洋問わずこれまでなかった.本書はそれを基礎から最新の話題までコンパクトにまとめている.
本書は2部構成となっている.前半は量子コンピュータの基礎理論が説明されており,後半を理解するために必要な前提知識を提供している.ここで注目すべき点は,量子計算(量子力学)を確率論の拡張として導入している点である.特に,確率概念を(複素数にではなく)負の数に拡張したことが量子計算において本質的に重要だと強調されている.このような導入方法は,量子計算の入門的な講義はもちろんのこと,量子力学の講義においても有用ではないか,と評者は感じた.
後半は量子計算量理論への本格的な入門となっている.後半は第7章「状態の検証」から始まる.状態の検証と量子計算量理論は一見何の関係もないように見えるが,実は後のほうで必要となる.最近の量子計算量理論では,第8章で解説される「量子対話型証明系」が重要な役割をする.対話型証明系では証明者と検証者のやり取りが行われるが,ここで検証者による状態の検証がキーになるのである.
本書の最後の第10章「非ユニバーサル量子計算」は,量子コンピュータ分野で最もホットなテーマの1つであり,2011年にJohn Preskillが提案した「quantum supremacy(量子超越性)」(J. Preskill, arXiv:1203.5813)をキーワードに盛り上がりを見せている.量子超越性とは,古典計算にとって困難なタスクを量子計算で効率的に実行し,量子計算の古典計算に対する優位性を実証することを意味する.ポイントは,そのタスクを実行するのに必ずしもユニバーサル量子コンピュータは必要ないため,実験的に実現しやすい,という点である.非ユニバーサル量子計算でありながら古典計算にとって困難なものとして,2010年頃ほぼ同時に提案されたIQPとBosonSamplingという2つのタスクが有名であり,上記の文献で紹介されている.これらは,NP≠Pの拡張とも言える多項式階層に関する計算量理論の強力な仮説の下,その古典計算困難性が証明されている.その証明に,第9章で解説されている「超量子計算」(量子計算をも超越する架空の計算)が利用される点は大変興味深い.IQPは本書で詳しく解説されている.上記の文献ではもう1つ,DQC1という非ユニバーサル量子計算も量子超越性を示す候補として挙げられている.DQC1が非ユニバーサルであるにもかかわらず,古典計算では効率的な方法が知られていないJones多項式の近似計算などを解けることがその理由だが,上記の2つとは異なり,当時はその古典計算困難性の計算量論的な証明はなかった.それを証明したのは本書の著者らである(T. Morimae et al., Phys. Rev. Lett. 112, 130502 (2014)).このように,著者は本研究分野で重要な仕事を数多く行っており,本書ではそれらがわかりやすく紹介されている.
本書の第1章に述べられているように,量子計算量理論は「計算」という観点から量子と古典の境界を探る学問領域と言える.こういったことに興味を持つ読者,また,この分野の研究を始めたいと考える学生や若手研究者に本書を薦めたい.
(2018年2月21日原稿受付)
深化する一般相対論;ブラックホール・重力波・宇宙論
田中貴浩
丸善出版,東京,2017,ix+194p,21×15 cm,本体2,000円[専門・大学院向]ISBN 978-4-621-30231-6
紹介者:横山順一(東大院理ビッグバン宇宙国際研究セ)
ビッグバン宇宙国際研究センターに重力波データ解析部門を作る運動をしていた頃,その活動の一環として,一般相対性と重力に関する国際会議を開催した.そこに,LIGO検出器による重力波直接検出により,このほどノーベル物理学賞に輝いたキップ・ソーン教授も招こう,ということになって連絡を取ったところ,「いやもう私は物理の研究は引退して,ハリウッドで映画を作っているところだから行けません」という返事だった.
「それでは映画ができあがったら,試写会と一緒にKAGRAのプロモーションのための講演会をしましょう」と返事したところ,「ああそれは良いアイディアだね」と賛成していただけたのだが,その後私は忙しさにかまけて米国の映画界の動向に注意を払っていなかったので,映画が本当にできあがったことに気づいたのは「インターステラー」が公開されてからのことだった.
それで映画館にでかけて早速見ると,科学顧問としてではなく,製作総指揮としてソーン博士の名前がクレジットされていた.なるほど本当にハリウッドに入り浸って映画を作っていたのだなぁ,と感心した反面,ブラックホールの近くにあり,1時間が地球時間の7年に相当するという水の惑星が出てきて,完全に科学的にはできなかったから科学顧問というクレジットにはならなかったのか,とも思った.
本書の著者も同じ疑問を持ったらしい.しかし,ソーン先生,手抜かりはなかった.特殊なブラックホールを使うことによって,このような不思議な状況を実際に作り出すことができるというのである.その種明かしには本書を読まれたらよい.
本書は特殊相対論から始め,一般相対論を導入した後,インフレーション宇宙論,ブラックホール時空,重力波,と重力理論のトピックスを網羅しながら進んでいく.その意味では,やや応用に重きを置いた教科書,という体裁ではあるが,物理の雑誌『パリティ』に連載された原稿がもとになっているので,これを教科書として一般相対性理論を系統的に学ぼう,というのは筋違いである.
むしろ,さすが斯界最高の頭脳の書いた本だけあって,一般相対性理論に関する著者の深い理解と重力現象に関するすぐれた洞察が覗われるところが随所に見られるため,これらを味わいながら読む,というのが本書への正しい取り組み方であろう.
したがって,相対性理論をひととおり学んだことのない人は,信頼のおける教科書―たとえば,小玉英雄『相対性理論』(培風館,1997年)―を座右において並行しながら読み進めるのが良いだろう.
(2018年3月17日原稿受付)
チョコレートはなぜ美味しいのか
上野 聡
集英社,東京,2016,206p,18×11 cm,本体720円[一般向]ISBN 978-4-08-720860-3
紹介者:塩見雄毅(東大工)
昨年11月に小さいながらも研究室を主宰する立場となり,あらためて自分のやりたい研究について考える機会を得た.これまで極低温・強磁場・高真空といった極限環境を利用して実験研究を行ってきた私だが,極限環境を実現するには金がかかる.どうしたものだろうか.色々と思い巡らせていたとき,自分は何故こんなに極限環境にこだわってきたのかとふと疑問に思った.考えてみれば,自分の周りのものは全て物理学の法則に従っているはずである.もっと身近なものを題材にして物理の研究ができるのではないだろうか.
そんな折,本書を書店で目にした.なかなかキャッチーな題名である.本の帯には「食品物理学」とある.なにやらチョコレートが美味しい理由を物理学の観点から説明しようという内容のようである.私もチョコレートは大好きだし,興味が湧いた.何より,身近な題材に私が専門としてきた固体物理学を展開できるのではないかという期待感を持たせてくれる本だ.私はすぐに本書を手に取った.集英社新書から出版されている本書は,会誌記事1)のいわば完全版であり,専門的な内容を含むもののなるべく一般の方に理解しやすくするための配慮が施され,チョコレートの歴史などもふんだんに盛り込まれて読みやすい内容となっている.
食品の「美味しさ」というのは個人差や食文化,体調や心理状態にも依存する難しい問題だが,食品のもつ特性を科学的に調べることは可能である.食品の味(味覚)や風味(嗅覚)に関係する成分を分析するのは化学的な探求である.一方,煎餅やポテトチップスのパリパリとした食感(テクスチャー)も食べ物の美味しさを左右する要素であり,物質の硬さ,粘り気,水分含有量などと関係したテクスチャーを研究するためには物理学が必要となるという.このような食品を対象とする物性物理学を著者は食品物理学と呼んでいる.
チョコレートの口溶け(食感)には,原料となるココアバターの結晶構造が関係している.チョコレートは食べる前(室温)はしっかりとした固体であり,口の中(体温36°C)では溶け始める.このココアバターの融解によって砂糖などの風味が舌の上に放出されるためチョコレートは美味しく感じるのである.ココアバターは結晶多形であり,I型からVI型までの結晶タイプがあるが,美味しいチョコレートに適した融点を有するのは準安定状態であるV型結晶だけである.いかにこの準安定状態にチョコレートをとどめておけるかが美味しいチョコレート作りの肝となる.実は,ヨーロッパのチョコレート職人たちは経験的にこの事実に気づいており,遅くとも1930年代ごろから「テンパリング」と呼ばれる技術でV型のココアバターが結晶化されたチョコレートづくりを行っていた.経験に裏打ちされた伝統的なチョコレートづくりの製法が,近年ようやく結晶学的な知識によって科学的に説明されたのである.
食品物理学の対象はチョコレートだけに留まらず,本書ではマヨネーズやマーガリンの例が挙げられている.世の中が便利となり,冷凍食品の普及や健康意識の高まりによって,加工食品はその成分や保管法を変化させてきた.そのような食生活の変化を裏から科学的に支えているのが食品物理学である.まさに身近にある先端物理学と言ってよいだろう.しかしその一方で,従来の固体物理学と調和しづらい要素もある.それは「汚い」系であるということである.ココアバターにおいても,産地によってその成分が微妙に異なる.普段3Nや4Nといった高純度原料を用いて試料を作製し研究を行っている我々からは,このアバウトさは感覚的に受け入れづらい側面もある.しかし,科学の進歩が著しい現代においては,複雑系である食品を研究対象として受容できる研究者も少なくないのではないだろうか.
参考文献
1)上野 聡,本同宏成,山田悟史,日本物理学会誌71, 767(2016)―チョコレートのおいしい物理学.
(2018年3月19日原稿受付)
酸化物薄膜・接合・超格子;界面物性と電子デバイス応用
澤 彰仁
内田老鶴圃,東京,2017,viii+324p,21×15 cm,本体4,600円(物質・材料テキストシリーズ)[専門~学部向]ISBN 978-4-7536-2309-9
紹介者:中野匡規(東大院工)
薄膜研究は主に半導体のエレクトロニクス応用を目的として発展してきたが,銅酸化物高温超伝導体の発見を契機に,物性研究の手段として薄膜を用いるケースが急増した.21世紀に入ってからは,エピタキシー技術や微細加工技術の発達に伴ってその流れがさらに加速し,酸化物へテロ界面における2次元超伝導や,単層FeSeにおける高温超伝導,あるいは磁性トポロジカル絶縁体における量子異常ホール効果やアクシオン絶縁体の実現など,驚くべき物性が薄膜やそのヘテロ界面を舞台に次々と発見されており,薄膜研究の重要性が年々高まっている.
本書は,酸化物を対象とする薄膜研究のうち特に電子物性に焦点を絞り,薄膜成長の基礎からデバイス化,物性測定に至るまでを,体系的かつ網羅的にカバーした教科書である.第1章では酸化物薄膜の作製・評価・微細加工技術一般が解説されている.特に作製した薄膜の結晶品質を評価する上で最も基本的かつ重要な手法である反射高速電子線回折および薄膜X線回折についての説明は,詳しくかつ実践的であり,薄膜研究を始めたばかりの読者にとってすぐに役立つであろう.第2章では酸化物の薄膜成長が解説されている.なかでも薄膜特有の自由度であるエピタキシャル歪みを積極的に利用した物性研究の例が多数紹介されており,薄膜研究の意義の一端を垣間見ることができる.第3章,第4章では酸化物薄膜を用いた接合デバイスが紹介されている.とりわけジョセフソン接合に代表される超伝導トンネル接合は,酸化物薄膜研究の火付け役となった重要なデバイスであるが,その動作原理や銅酸化物高温超伝導体を用いた例が詳しく解説されている.続く第5章,第6章では,酸化物2次元電子系の伝導特性や電界効果デバイスが紹介されている.特にLaAlO3/SrTiO3ヘテロ構造は2次元超伝導や界面強磁性を示す特異な物質系であり,現在進行形で活発に研究されているが,その歴史的な経緯から最近の進展までが整理されている.また,電界効果デバイスとしては,応用上重要なアモルファス酸化物半導体IGZOを用いた電界効果トランジスタや,電子相関を利用した新原理トランジスタであるモットトランジスタなどが紹介されている.最後の第7章では,酸化物接合デバイスのうち既に不揮発性メモリとして実用化されている強誘電体メモリと抵抗変化メモリが紹介されており,酸化物薄膜研究の出口イメージの一端を掴むことができる.
薄膜研究は薄膜を作るところから研究が始まるが,特に酸化物の薄膜研究の場合,薄膜作製から最先端の物性・デバイス研究までをカバーした教科書は非常に少ない.本書を通読することで,薄膜成長の基礎から,接合や超格子,デバイスなど薄膜研究の最前線までを概観することが可能であり,本書は研究室に入ったばかりの学生や,これから新たに酸化物薄膜の研究を始めようという研究者にとって,よき指南書となるであろう.
(2018年3月26日原稿受付)
物質中の電場と磁場;物性をより深く理解するために
村上修一
共立出版,東京,2016,vi+181p,21×15 cm,本体2,000円(フロー式物理演習シリーズ【13】巻)[大学院・学部向]ISBN 978-4-320-03512-6
紹介者:佐藤正寛(茨城大理)
本書はタイトルの通り,物質中の電磁場についてのテキストである.著者は,スピンホール効果をはじめとするトポロジカル物性現象を中心に,まさに物質中の電磁場に関わる多彩な新現象を精力的に研究している理論家である.本書は計181ページ・全13章の比較的薄めのテキストで,各章が解説と演習問題で構成されており演習書に近い書籍といえる.問題解答も付いており,古典力学と古典電磁気学を学習した者であればおおむね独学で理解できるよう工夫されている.
物性物理学(特に固体物理学)の半分以上の分野は物質中の電磁気学の範疇にあるといっても過言ではあるまい.真空中やそれに近い系における電磁場の振舞いは,マクスウェル方程式や量子電磁力学の枠組みで精度よく予言できるが,物質中の電磁場に関係する物理学には現在でも未解決・未開拓の領域が多数存在し,それ故多くの物性研究者の存在が許される.このような状況から,本来,物質中の電磁気学の基礎的内容を頭で整理しておくことは非常に大事なはずだが,大学のカリキュラムの問題や日常的な研究教育活動の忙しさなどの理由により,物質中の電磁気学の学習は疎かにされ易い.本書は,量的・時間的な意味でエコノミカルに物質中の電磁場の基礎を復習・学習する為に適した書籍と言える.
1-2章は古典電磁気学の標準的テキストでも取り上げる電磁波と導体の性質に当てられている.3章の表皮効果は多くの大学の物理学科では触れない話題ではなかろうか.4-11章では電磁場と強く相互作用する典型的な系である誘電体と磁性体の基礎物性について議論しており,これが本書の中心部といえる.コンデンサや電磁場の境界値問題などの標準的な話題にも当然触れているが,幾つかの点で本書の個性が現れている.特に,誘電率などの応答関数の虚部を導入し,それが物質による電磁場やエネルギーの吸収に関係することを意識させている点,また古典物理学の範囲で誘電体や磁性体の微視的で単純化された模型を導入し,静電磁場だけでなくAC電磁場への応答の解説に注力している点,は本書の大きな特徴である.物質の電磁場応答を最短距離で学習する方法は量子論的な線形応答理論を学ぶことであり,特に理論系学生の多くはこの路線に従う.しかし,この方針ではしばしば物理現象のイメージが疎かにされてしまう.本書で登場する誘電体や磁性体の簡単な古典模型は(光物性など一部の分野では常識的であろうが)微視的な理論と実際の物理現象の間の架け橋の役目を果たしてくれる.本書を読んで,古典物理学の底力に改めて感心する物性研究者も少なくないだろう.さらに,物性研究者は自らの研究がどれだけマニアックであるかを再確認することもできる.12,13章は各々超伝導体,物質中の電磁波と磁気光学について解説しており,ここから研究への興味や研究テーマへ繋がることも期待できる.
標準的な固体物理学のテキストでは,はじめにブラベ格子や複雑なフェルミ面などの物質の多様性が強調される傾向がある.しかし,物理系の学生は物理学の普遍性や統一感に魅力を感じていることが多く,その意味で多様性を強調しすぎる構成はこれから固体物理学を学習する学生を失望させる性質を含んでいる.本書は,古典物理学を限界まで使いこなして物質中の多彩な電磁気現象の解説を試みており,学生の失望感を軽減させる1つの方法を提供していると言えるかもしれない.また,この内容の特性から,量子力学を十分理解していない学生に物性物理学の面白さを理解してもらう為に本書を利用することもできるだろう(実際,私は卒研生の輪講テキストとしてこの書籍を使わせていただいた).
薄い書籍であることは短時間で読みこなせるという長所にもなるが,説明が不十分になるという欠点にもつながる.本書の性格上難しいであろうが,解説や補足を充実させると研究者にはより有難い内容になる.特に,本書の内容とより微視的な理論との関係について補足説明があると,学生の学習意欲にもつながると思われる.分厚い電磁気学,固体物理学,統計力学のテキストを傍らに置きながら本書を利用すると,効率的により深い理解に到達することにつながるだろう.
(2018年4月2日原稿受付)
経路積分と量子解析;量子古典対応から量子現象に迫る
鈴木増雄
サイエンス社,東京,2017,iii+224p,26×18 cm,本体2,222円(SGCライブラリ-137)[専門~学部向]ISSN 4910054701173
紹介者:松枝宏明(仙台高専)
著者は高名な統計物理学者であり,例えば私の世代であれば,学生時代に量子モンテカルロ法を勉強して,所謂鈴木・トロッター公式でそのお名前を知った方は多いと思われる.現在80歳を超えてもお元気で,近年はご自身の業績が最新の複合融合課題と深い関わりを持つことに素直な喜びを示されているのが印象的である.
本書はタイトルにもあるように,経路積分法と量子解析を具体的な武器として,量子古典対応の視点から量子現象に迫ることが一応の目的となっている.経路積分を用いた量子古典対応の2つの立場として,(1)経路積分による量子化,(2)量子古典対応の表現ツールとしての経路積分,がある.前者は作用に対する変分原理を満たす古典解周りの軌道の寄与も取り込むという視点での量子化であり,後者は鈴木・トロッター公式を中心とする指数積公式を援用した量子古典変換技術である.また量子解析における量子古典対応の視点とは,非可換演算子を取り扱う量子統計力学の問題で,古典的な微分法との対応が明確な非可換微分法を定義すると,この方法論が広く活用できるということである.
しかしながら,著者の近年の研究トレンドを考えると,実際にはこれらの数学的技法を縦横に駆使して,ライフワークである非平衡系・散逸系の量子統計力学の構築に特別の関心が寄せられているように見える(著者の師は久保亮五先生).特に第2章と第7章以降でその傾向が強い.従って量子古典対応という言葉を額面通りに受け取ってしまうと,多少タイトルから逸脱していると思われる内容も見られなくもないし,所謂ゲージ重力対応などの流行のトピックとはだいぶ異なる視点である.それらの点は特に初学者の方は注意をされたい.上記(1)に関しては,量子力学も含めて物理の基礎法則が経路積分・変分原理で与えられるという事実を出発点として,これまで未解決だった非平衡系の取り扱いも変分的に定式化できることを理解し,変分原理の豊かな表現力を感じるということが大事である.また(2)の核である指数積公式,量子解析,あるいは熱場ダイナミクスの定式化に関しては,これらの技法が第7章以降の非平衡統計力学を取り扱う上で自然に現れてくるという意味で汎用性の高い技法であることを学ぶことが重要である.第7章から第10章の応用編では,非平衡系・不可逆過程のエントロピー生成や秩序形成におけるエントロピー変化の問題が詳細に議論され,第11章以降では,リー・ヤンの円定理やトポロジー変化法を基に,物理系の変換・対応・等価性に関するより発展的な話題が議論されている.
本書で取り扱われているトピックの一部に関しては,著者の代表的な著書「統計力学」「経路積分の方法」(岩波書店)や近年の著作である「変分原理と物理学」(丸善出版)に重複する部分がある.各論はそれらの既刊著書にもあたると良い.本書はどちらかというとタイトルの詳細に拘らず,著者の過去から現在までの研究を俯瞰し,ご興味の幅の広さを示されたものという認識で通読されると良いと思われる.所々に挿入されている逸話の語り口はいつもの鈴木先生である.
(2018年4月7日原稿受付)
結晶学と構造物性;入門から応用,実践まで
野田幸男
内田老鶴圃,東京,2017,viii+306p,21×15 cm,本体4,800円(物質・材料テキストシリーズ)[専門~学部向]ISBN 978-4-7536-2307-5
紹介者:有馬孝尚(東大新領域)
本書は結晶学,および,構造物性の専門家としての著者の教育や研究の成果を一冊にまとめたかのような力作です.副題に「入門から応用,実践まで」とあるように幅広い層の読者を想定し,結晶学と構造物性に関するさまざまな事項がこの一冊で理解できるようにという思いが伝わってきました.1章の「はじめに」から,結晶学の歴史,すなわち,化学反応の研究,鉱物学(形態結晶学),群論により,すでに結晶学がある程度確立していて,その後,レントゲンによるX線の発見を経て,ラウエやブラッグによる現代結晶学の確立に至ったことなどが紹介されており,巨視的な物性と結晶学の関連を強く意識していることがうかがえます.
その後,2章から5章までで結晶学の基礎となる事項がかなり丁寧に記載されています.6章から8章でX線回折と中性子散乱の方法論を述べた後,9章で構造相転移に関しての解説があります.最後の10章では,実例として,著者自身による代表的な研究成果が紹介されています.
結晶学は長い歴史を持ち,ブラッグ親子によるX線結晶構造解析から考えても100年以上の歳月があります.その一方で,最近においても,準結晶を結晶の一種に含めるなど,結晶の定義自体が変化しています.結晶構造解析技術も著しく発展しています.そのように長い歴史を持ち完全に確立した部分と,近年においても進化している部分について,バランスを意識した構成となっています.
量子力学,電磁気学,熱力学・統計力学といった固体物理の基礎科目と比べると,結晶学の理解に不可欠な数学や物理の知識はそれほど多くありません.その意味で,結晶学はとっつきやすい学問だと言えます.一方で,結晶学には,本質的な理解とは別に,記号や用語に関する決まりごとがたくさんあります.それらを覚えるのはかなり面倒です.結晶学の教科書の多くは,この決まりごとの部分をどのように説明するかに苦心しています.本書では,格子点の対称性(2章),シンモルフィックな空間群(3章),結晶点群と物性の関連(4章)と進めてから,らせん対称性や映進対称性を5章で扱うという工夫がされています.らせんや映進の説明を後回しにしたことで,日本物理学会の多くの会員にとってはもちろん,より広く理科系の学部生にとって,2章から4章までは比較的容易に理解できることでしょう.特に,今日の大学生にとって,圧電効果や応力歪み応答を講義で習う機会はほとんどないと思われます.その観点からも,4章は教育的な内容になっています.
5章で初めて,らせん対称性と映進対称性が登場しますが,それらが本質的となるノンシンモルフィックな空間群については,高度すぎることもあり,本書では軽く触れる程度となっています.さらには,時間反転操作に基づく磁気空間群や,構造相転移と部分群の関係などにも触れており,結晶学の専門家にも啓蒙的な内容となっています.
5章までで結晶学の基礎を理論的に説明してきたということで,6章から8章では,一転して,実用的な内容が展開されます.結晶構造解析に関わる実験家が直面しがちな細かな事項が,かなり新しい情報を含めて解説されています.ここでは,SPring-8,改造三号炉(JRR-3M),J-PARC MLFという日本を代表する3つの施設で結晶構造解析用の装置の設計と立ち上げに中心的な役割を果たしてきた経験,さらには,回折強度データに基づいた結晶・磁気構造解析を多くの後進に指導してきた著者の経験が存分に発揮されています.粉末法における誤差の過小評価の問題,最大エントロピー法における系統誤差の処理の問題,二次元検出器を用いた場合のローレンツ因子など,いずれも構造解析の豊富な体験に基づいているものであり,示唆に富んでいます.結晶構造データを自分の論文に載せたことのある研究者でも,上記の事項をきちんと意識している人は,多くはないと思われます.また,飛行時間法における各チョッパーの意義についても言及してあり,日本の中性子実験の多くがパルス中性子源に移行した現状を踏まえたタイムリーな内容になっています.
9章では,構造相転移の基礎に始まり,散漫散乱やフォノンのソフト化について紹介しています.この章の後半の記載はかなり専門的な内容となっており,構造相転移を初めて学ぶ読者にとっては少し難解かと思われます.しかし,構造相転移を調べる手段としてのX線・中性子散乱実験の有用性がよくわかり,実用的な内容となっています.
以上のように,本書は,結晶学と構造物性の幅広い範囲を網羅した贅沢な内容となっています.まえがきでは本書は千葉大学や東北大学の学部生向けの講義に基づいていると書かれていますが,大学院生はもちろん,固体物性研究の最先端にいる研究者にとっても,新しい知識が得られるような内容となっています.どの部分が役に立つのかは読者によって変わってきますが,全体として,結晶を対象とする物性研究者にはぜひ一読することを勧めたい一冊です.
(2018年1月22日原稿受付)
Nonequilibrium Many-Body Theory of Quantum Systems;A Modern Introduction
G. Stefanucci and R. van Leeuwen
Cambridge Univ. Press, UK, 2013, xvii+600p, 25×18 cm, $108.00 [専門・大学院向]ISBN 978-0-521-76617-3
紹介者:松尾 衛(中国科学院大カブリ理論科学研)
<p本書は量子多体系の非平衡現象をグリーン関数法によって扱うために必要な手法を基礎から丁寧に説き起こした教科書である.基本的な量子力学と複素解析を学んだ者を対象に,量子力学の基本から出発して,主に非平衡グリーン関数法の物理的内容について,特にその時間発展に焦点を当てながら,分子,ナノ構造,金属,絶縁体と多様な系に適用しながら詳述される.600頁の大部であるが,その頁数は,行間のギャップを極力減らし,読者の負担を軽減するために費やされており,初学者に配慮された構成となっている.
非平衡グリーン関数法(いわゆるKeldysh形式)では,量子非平衡系の確率分布のダイナミクスを,どんな励起が可能かを記述するスペクトル関数と,その励起の統計的分布を記述する分布関数について閉じた量子輸送方程式を用いて解析する.これはKadanoff-Baym方程式と呼ばれ,非平衡グリーン関数の従うDyson方程式のWigner表示から導かれる.とくにΦ微分近似とよばれる,保存則を自動的に満たす近似法と併せ,この方程式を粗視化することによって,非平衡系のダイナミクスを現象論的に記述する代表格であるBoltzmann方程式や拡散方程式が導かれることからも,この理論形式は非平衡現象の微視的機構を理解するための強力な手法の一つとなっている.
私自身は,ゼロ温度のグリーン関数法,有限温度のグリーン関数法(松原形式)と順を追って学んでしばらくしたあとに,A. M.ザゴスキン(樺沢宇紀訳)「多体系の量子論」(新装版は丸善,2012)や,北孝文さんの集中講義でKeldyshグリーン関数を学んだ(北孝文「量子輸送方程式と非平衡エントロピー―場の量子論による非平衡統計力学―」物性研究90(1), 1-95, 2008).その際に感じたのは,このKeldysh形式をもっと早い段階で学びたかったということだ.特に,複素時間に拡張された経路上のグリーン関数法「contour formalism」の一般論とその直観的説明を早い段階で学び,その経路や条件を様々に制限し,ゼロ温度のグリーン関数法や松原形式を再現する,という順番で学べる教材があるといいのにと他力本願に頼ったまま,そういった趣旨の教科書の登場を待ち望んでいた.実は,本書がまさにそれを体現した教科書となっている.
実際に第5章で,多体のグリーン関数から1体のグリーン関数までのMartin-Schwinger階層の一般論を展開したあとに,経路を制限して,各種形式が導かれる様子が書かれている.そうした一般論を受けた6章では,光電子分光におけるphotocurrentのlesser関数を用いた表式が与えられる.これは非平衡グリーン関数の直観的な理解にとても良いと感じた.最終章で解説されている,有限系のKadanoff-Baym方程式の数値的解析法も興味深い.
私が普段取り組んでいるスピントロニクスの理論解析では非平衡グリーン関数法が欠かせない.特にバルク金属や,非磁性金属/磁性体接合系における様々なスピン流生成の微視的機構を調べるのにKadanoff-Baym方程式や非平衡グリーン関数による摂動展開を使う.そうした研究に新規参入する学生,研究者にとって本書はとてもよい教科書である.また,非平衡多体系のグリーン関数に関する一般論が「too formal」にならないように配慮されている点からも,上記分野に限らず広い読者層に有用であると考える.
(2018年5月10日原稿受付)
プラズマ物理科学
石原 修
電気書院,東京,2015,337p,21×15 cm,本体3,800円[専門~学部向]ISBN 978-4-485-30075-6
紹介者:吉村信次(核融合研)
本書は,テネシー大学,サスカチェワン大学,テキサス工科大学,横浜国立大学における著者の講義をもとにしてまとめられた,プラズマ物理を学ぼうとする理工系学生や研究者を対象とした教科書である.物質の第4状態とも呼ばれるプラズマの研究は,核融合発電の実現を目指した大型計画や産業デバイス加工への応用を推進力として発展してきたが,本書にはそれらのベースとなるプラズマの複雑な振舞いの物理的理解の仕方がまとめられている.
本書の特色は,副題の「フェムトからハッブルまでのプラズマ宇宙」で示されている通り,それぞれのプラズマ現象に特徴的な空間スケールによって章立てが行われている点にある.著者は,サスカチェワン大学の研究員時代に国際会議でHannes Alfvén(ノーベル物理学賞,1970年)の講演を聴き,Cosmic Triple Jump1)という考え方に刺激を受けたという.そこでは,10-1 [m]スケールの実験室プラズマから109ごとのステップで3回ジャンプを繰り返すことで,108の磁気圏プラズマ,1017の星間プラズマ,1026のハッブル半径へと理解が広がることが述べられている.本書では,更に2段階小さなスケールを含めて10-19から1026までの5段飛びクインタプル・ジャンプ(Quintuple Jump)でプラズマの世界を眺めることになる.
第1章(10-19のプラズマ宇宙)では,クォーク・グルーオンプラズマ(QGP)が取り上げられる.QGPは狭義のプラズマには含まれないが,プラズマ物理の学習者への話題提供として簡単にまとめられている.この章は,教科書というより教養書といった趣である.第2章(10-10)では,プラズマを構成する個々の荷電粒子の運動について,電磁場中の運動方程式に基づく様々なドリフトの導出からクーロン衝突の効果までが示される.第3章(10-1)では,分布関数を用いた統計力学的アプローチからプラズマの集団運動である波動現象が解説される.プラズマの複素誘電率を数学的に正しく取り扱うことで,ランダウ減衰や種々の不安定性を導出する.理解のために必要な複素積分については,付録Dで解説されている.なお,非線形波動現象に対する準線形理論までを取り扱うこの章だけで,式番号で375(!)を数える数式が含まれている.一つ一つの式を確認していくことにはかなりの労力が必要だが,プラズマ研究を志す学生諸氏には是非挑戦してほしいと思う.第4章(108)では,地上の実験室を飛び出し,磁気圏などで起こる大規模なプラズマのダイナミクスを記述できる電磁流体力学(MHD)の基礎を学ぶ.磁気流体波であるAlfvén波や巨視的不安定性についても,この章で取り扱われる.数式は第3章より少なくなるが,それでも式番号は120を数える.第5章(1017)では,宇宙線で観測されるような高エネルギー粒子の加速現象にかかわるプラズマ衝撃波理論が議論される.最終章である第6章(1026)では,加速膨張する宇宙の簡単なモデルが紹介されるとともに,宇宙と実験室を結びつける宇宙の塵(ダスト)に着目して,著者の専門でもある"コンプレックスプラズマ"の基礎物理が議論される(コンプレックスプラズマは,原子サイズと比べると非常に大きな微粒子群の系がプラズマという系と相互作用している複合系として定義される).
第1章を除く各章には学生の理解を助けるための問題が配置されているが,それらの問題には学んだ内容をより具体的な状況に適用しようとするものが多く,楽しく取り組むことができそうである.なお,付録Eとして全ての問題に対する詳しい解答が与えられている.
以上,第1章から第6章まで全て合わせた数式の数が941にも達するこの教科書はもちろん万人向けではないが(そもそも万人向けの教科書なんてない?),やる気のある学生や一度プラズマ物理を勉強した研究者には,その世界の広がりを見渡すことができる格好の書であるといえる.数式が多いとは言え,標準的な教科書のような無機的な語り口ではなく,各所に著者の基礎プラズマ物理への情熱が感じられる一冊である.
参考文献
1)H. Alfvén, Phys. Scr. T2/1, 10(1982).
(2018年5月14日原稿受付)
多粒子系の量子論
藪 博之
裳華房,東京,2016,xvii+428p,22×16 cm,本体5,200円(量子力学選書)[大学院・学部向]ISBN 978-4-7853-2514-5
紹介者:大井万紀人(専修大)
大学院の修士課程に上がって1年が経ち,大学院の講義や研究室の輪講などを通じて基礎的な事柄を一通り修了したにもかかわらず,これからどんな研究をしていけばよいのか明確な方向性が打ち出せず,春の微風に散る花びらを見つめながら,心の迷いを払拭できない学生は少なからずいるはずである.
原子核や物性の理論研究室に配属された院生ならば,その要因として思い浮かぶのは,初年度の輪講で読まされた多体問題の分厚い洋書(Fetter-Waleckaか,Negele-Orlandといったところであろう)の内容が,消化不良のまま理解できずにいるからではないだろうか.まず英語の読解で足をすくわれ,次いでグリーン関数の物理的な意味が納得できず,さらには波動関数が教科書のどこかへ雲隠れしたことへの不信感といったところであろうか.さらに気分が落ち込むのは,友人たちはこの本を苦もなく理解しているように見える点だ(そうでもないだろうが).
輪講が始まってすぐの頃,一人だけ置いていかれたような感じがして,図書館に駆け込み「量子多体系」という題のついた教科書を徹底的に探してみる....Thouless, Ring-Schuck, Pethick-Smithなどの本を山積みにして貸出係に運んだとき心に芽生えた新鮮な期待と希望は,自分の部屋でページをめくり始めるとみるみる腐り始め,返却日に近づくと結局どれも役立たずに見えて,心は再び五里霧中である.
そんなとき,新刊コーナーに薮博之著『多粒子系の量子論』を見つけることができたならば,この学生は感激に咽び泣いたことであろう.日本人の物理学者による日本語の本である.馴染みのある波動関数を用いた多体状態の構成から始まり,第二量子化そして両者の関係へと少しずつ議論が進んでいく.グリーン関数も分配関数も出てこない.その理由は緒言において,「無限個数の粒子からなる無限自由度の物理系」ではなく,有限個数の粒子を焦点においた「多粒子問題」の教科書を目指したとある.つまり統計力学で扱うようなアボガドロ数の粒子がうごめくような多体系は議論の中心には置かないというのだ.にもかかわらず,この本は最後の章で多粒子論と場の理論との関連性を述べて結ばれている.「無限と有限の橋渡しか.なるほど,これで将来の発展性も見込める」と感じた学生は,輝く朝日が水平線から昇ってくるのを見つめるような面持ちで,貸出コーナーへと歩を進めたことであろう.翌年の桜の色は違って見えたかもしれない.
上述の内容が多少大袈裟なのはお許しいただき,この本を読んだ多くの標準的な大学院生は肯定的に感じると思う.本書の最大の特徴は,多体系の励起状態の記述としてRPA理論を紹介している点(RPA理論がどうして「乱雑位相」なのか説明してくれるのは,筆者の知る限りこの本だけである)と,ボーズ-アインシュタイン凝縮を多粒子系の立場から解説している点である.特に後者は,多体理論の研究者の多くが興味を持っている分野であり,研究テーマの発展を狙う若い研究者には刺激的な内容ではないかと思う.
しかし,この本によって多体理論を専攻とする全ての院生に直ちに福音がもたらされるとは言えない.例えば,群論とフーリエ級数理論については,事前に別の教科書で(あるいは副読本として読みながら)勉強しておく必要があろう.群論はボゾンやフェルミオンの多体状態の構成の理解に必要となる.クォーク理論についても少し言及があるので,Georgiなどで予習しておくとよいだろう.フーリエ級数理論は,量子気体模型で登場する平面波の取扱いなどで必要になる.生成消滅演算子の導入には調和振動子を用いている.散乱理論やリップマン-シュインガー方程式についての説明も少ないので,J. J. Sakuraiなどを副読本にして本書を読むとよいだろう.また,本書の前半に見られる,母関数を導入しての議論には薮氏の独自性が垣間見られるが,標準的な手法とは思わない人も多いかもしれない.最初に読むときは流し読みし,研究で使う段階になって深読みすれば効率的な学習ができると思う.超伝導の理論も割愛されている.
また,この本を初学者が一人で読むのはお奨めしない.残念ながら誤植が散見され,変なところでつまずいてしまう恐れがある(初学者が間違えて記憶しないよう,ここで一つだけ指摘したいのは,付録A3にある「ベーガー,キャンベル,ハウスドルフ公式」である.本文295ページでは正しく「ベーカー,キャンベル,ハウスドルフ公式」と書かれている).よく言われることだが,多体問題をすでに一通り習得した先輩や指導教官と一緒に読み,誤植を見つけながら読み進めば実力向上が期待できるだろう.
(2018年2月23日原稿受付)
新SI単位と電磁気学
佐藤文隆,北野正雄
岩波書店,東京,2018,xvi+200p,21×15 cm,本体2,300円[広い読者向]ISBN 978-4-000-61261-6
紹介者:安田正美(産総研)
本年は,130年ぶりとなるキログラムの定義改定も含めたSI単位大改定(質量,温度,電気量,物質量)の年であり,本書の出版は極めて時期を得たものといえる.なぜなら,本改定の原動力として,質量標準側からの要求は当然としても,電気標準側からの要求も大きかったといわれているからである.また,定義改定とは別のもう一つの本書の主題として,長年にわたる電磁気学における単位系の混乱について概観している.その後,単位系同士の関係を明らかにする形でそれらを解きほぐし,最終的には電磁気学に留まらない単位系一般についての考察へと昇華させているという点に本書の新味があると思う.
本書は,全8章と,参考文献,あとがき,索引の200ページから成る.第1章「物理学と単位系」では,本書の全般的なイントロとして,物理量の数量的記述とその物差しとしての単位について説明した後に,社会制度としてのSI単位,単位を定義する現象,SI単位の歴史と進化について述べている.第2章「国際単位系SI」では,SI単位の概要が簡潔に説明されている.第3章「単位系を定義する現象」では,特に新SIと関連が深い,基礎物理定数とつながる物理現象について述べられている.第4章「電磁気の単位とマクスウェル方程式」では,電磁気学における単位系の混乱とその正しい理解を念頭に,広範にわたる議論が展開されている.特に,真空のインピーダンスZ0について,「物理学汎論」にも通ずる,幅広い分野にまたがる形で,その有用性を説明している.第5章「電磁気の単位系の進化と単位系間の変換」では,esu系,emu系,ガウス単位系,MKSA単位系などのそれぞれの単位がどのように生まれて進化していったのかが,相互の関係も含めて,系統樹などを用いて詳細に説明されている.この章は後に続く,第7章の伏線となっていると思われる.第6章「単位系余話」では,単位系や精密測定の専門家ではない著者たちが,本書執筆の過程で気づかされた話題が提供されている.この手の蘊蓄ともいえる話題は,ともすれば羅列的で無味乾燥なものとなりがちな単位や計測・標準に関する講義などで,学生諸君に興味を持ってもらうためにも有効だと考えられる.この章の前半では,光周波数コムや光格子時計などの最新技術や,基礎物理定数の恒常性検証といった最新トピックにも触れられており,単位に関することが今もなお進化を続ける分野であることを印象づけている.一方,この章の後半では,単位に関することが歴史的・人文社会的にも語られており,興味深い.さて,本書で特筆すべきは,第7章「単位系の数理構造」であると思う.異なる単位系同士の関係や変換方法などが,圏論を用いたメタな視点から示されている.最後の第8章「諸定数表」はこの手の本の終わりには欠かせない要素である.
以上のように,これまで単位に興味や関心の薄かった物理学者のみならず,単位や精密計測を専門とする人たち,さらには,科学と社会の接点である単位という観点から,いわゆる文系の方々のためにも好適の書である.
なお,定義改定は現在進行形の事象なので,読者におかれては本書だけに頼らず計量標準総合センター(NMIJ)や科学技術データ委員会(CODATA)のホームページに掲載された最新情報も参照すべきであろう.
(2018年8月9日原稿受付)
新しい1キログラムの測り方;科学が進めば単位が変わる
臼田 孝
講談社,東京,2018,246p,17×11 cm,本体1,000円(ブルーバックスB-2056)[一般向]ISBN 978-4-06-502056-2
紹介者:久我隆弘(東大院総合文化)
高校時代(1973~76),良い意味で騙され続けてきたブルーバックスを久しぶりに手にとった.帯には「キログラム原器」がなくなる!? とある.思い起こせば小学校時代(1964~70),長さ(1 m)はメートル原器で,重さ(質量,1 kg)はキログラム原器で定義されている,と教わった.ただ,確か長さの定義は1960年にクリプトン(Kr)の発光波長に変更されていたはずだ.そう,当時はすでにメートル原器はなくなっていた.いや正確にはその役割を終えていたはずなのに,なぜ先生はメートル原器をもち出したのだろうか.あるいはその後に補足の説明をしたのだが,小学生の私には難しすぎて理解できず,すっかりと忘れ去ってしまったのかもしれない.
あれから50年,ついにキログラム原器もその役割を終える時が来た.本書は,このような単位の定義が変更される背景やその経緯について,物理を専門としない読者にも理解できるように書かれている.また物理を専門とする者にとっても,単位や単位系にまつわるよく知らなかった物理学的な内容や挿話もあり,改めて物理を考えさせられるきっかけにもなるのと同時に実話読み物としても面白い.ここで詳しい中身を書くことはできないが,新しいSIの基本的な考えは「自然界の基本定数」を確定値とするところにある.
実は1983年に,長さ(1 m)の定義はKrの発光波長から真空中の光速度c0に変更されている.「長さ:m」を規定するはずなのに,別の次元である「速度:m s-1」を使って定義することになった.これは,時間測定の相対不確かさがKrの発光波長による長さ測定の相対不確かさよりも小さくなったため,普遍的定数(自然界の基本定数)
今回のSIの改定は「長さ:m」に加えて,「質量:kg」,「電流:A」,「熱力学温度:K」,「物質量:mol」を自然界の基本定数であるプランク定数h,素電荷e,ボルツマン定数k,アボガドロ定数NAを確定値とすることで定義する.この改定により物質量以外のSI基本単位は「時間:s」で測ることになる.
このような改定を行うことの利点は,本書にもいろいろ書かれているが,やはり「すべての時代に,すべての人々に」というフランスのメートル法成立時の標語に行き着くのだろう.不変かつ普遍と思われる自然界の基本定数を確定値とすることで,宇宙人とも共有できると考えられる尺度を定めた意義は大きい.これ以外にも,新旧の定義を滑らかにつなぐために行われてきた研究開発は物理学の基礎研究に大きな恩恵をもたらしたし,今後さらに高度化していく社会活動をより円滑に進めることにも今回の改定は貢献することだろう.
難点としては,本書にもあるが,やはり定義が一般人にとっては難しく直観的には理解できないという点だろう.メートル原器やキログラム原器であれば小学生でもすぐに納得できる.実際私がそうであったように.また,本書では触れていないが,個人的には「基本定数の測定」という概念がなくなってしまうところに一抹の不安が残る.基本定数を確定値としてしまうことは,自然界が不変・普遍であることを人間風情が決めてしまうという意味にもとれる.本当に基本定数は不変かつ普遍なのだろうか.確かに,キログラム原器のもつ"相対不確かさ"よりもプランク定数測定の相対不確かさの方が小さいので,プランク定数を"とりあえず"確定値とした方がより不変・普遍的な質量の標準となる.ただだからといって本当に確定値としてしまっていいのだろうか.おそらく何か画期的な測定法でも考案して,今回確定値として採用された自然界の基本定数間にある(かもしれない)矛盾を探るのが,今後の一つの研究課題となるのだろう.
いずれにしても久しぶりに縦書きの本を通読し,あれこれと新鮮な刺激を受けた.皆さんも日々の研究に疲れて私のように妄想を膨らませたいときに一読してみてはいかがだろうか.
(2018年8月20日原稿受付)
量子測定と量子制御
沙川貴大,上田正仁
サイエンス社,東京,2016,vii+210p,26×18 cm,本体2,407円(SGCライブラリ-123)[専門・大学院向]ISSN 4910054700367
紹介者:森 貴司(東大院理)
近年の量子論の進展は,その基礎的理解に留まらず,測定結果に基づいた量子状態の推定や制御を通して,量子系をいかに手なずけ,使いこなすかという方向に展開している.その背景には,目覚ましい実験技術の進歩と,量子情報理論の進展がある.我々は量子系を受動的に記述するだけではなく,能動的に操作・制御するという段階に来たのであり,その先にはエキサイティングな世界が広がっているにちがいない.
残念なことに,これまで,このような新しい進展を基礎から体系的に学べる和書がなかった.それどころか,(少なくともマルコフ近似に限れば)古くから確立している量子開放系のダイナミクスの基礎理論の解説すら,日本語の教科書にはほとんど見当たらない.このような状況の中,量子測定・量子開放系のダイナミクスの基礎から量子状態推定や量子状態制御といった進んだ話題まで解説した本書が出版されたことは喜ばしいことである.
本書の特長は,驚くほど多くの話題がコンパクトにまとめられていることである(付録では古典確率過程と古典制御理論までが詳しく解説されている!).しかも,それぞれのトピックが単なる表面的な紹介で済まされるのではなく,基礎から手際よく解説されているため,読者はしっかりとした知識を得ることができる.もちろん,その分非常に密度の濃い議論が展開されているのであり,決して易しい本ではないが,論理は明快であり,読みにくさを感じることはなかった.量子測定や量子制御の理論を既に学んだことのある読者にとっても,知識を整理するのに本書は役立つだろう.この分野に関心のある学部生,大学院生にとって必携の書である.
当然ながら,本書で触れられていない重要事項に関連して,本書の記述にも補うべき箇所はあるだろう.例えば,4章でシステムと環境を合わせた全系のミクロなダイナミクスから量子マスター方程式が導出されているが,その導出は本書のメインターゲットである量子光学系では妥当であるものの,より一般的な状況では必ずしも正しくない(本書の導出ではシステムの運動に比べて散逸の方がずっと遅いことが仮定されているが,例えばCaldeiraとLeggettにより考察された量子ブラウン運動では,これらは同程度の速さである).しかし,本書を読み切れば,最先端の論文や他の参考文献を読みこなし,必要な知識を補うために必要となる基礎的な土台はしっかり作られる.まえがきに述べられている,「量子測定と制御の理解に必要な最低限の知識を系統的に解説」しようという本書の目的は十分に達成されている.
まとめると,本書は量子測定・開放系のダイナミクスが基礎から系統的に解説されている待望の書である.ほぼ最短経路で最先端の研究に到達できる点でこの分野に関心のある初学者が勉強を始めるのに最適であり,またその簡潔かつ明快な解説は研究者にも大いに参考になるだろう.
(2018年6月10日原稿受付)
格子場の理論入門
大川正典,石川健一
サイエンス社,東京,2018,v+215p,26×18 cm,本体2,407円(SGCライブラリ-140)[専門・大学院向]ISBN 4910054700480
紹介者:西村 淳(KEK理論セ)
場の量子論は,素粒子理論を記述する基本的な枠組みであるが,無限自由度の量子系のため,摂動論を超えた扱いが難しい.格子場の理論は,場の量子論をいったん有限自由度の量子系に落としてから「連続極限」をとることによって,これを非摂動的に定式化するものである.特に,数値計算アルゴリズムや計算機の目覚しい発展もあって,格子場の理論を使って場の量子論をスーパーコンピュータで研究する分野は,素粒子論において重要な地位を占めている.
本書は,この分野への入門書として書かれたものである.通して読んでみてまず感じたことは,前半(第8章まで)と後半(第9章以降)とで,専門性の度合いががらっと変わることである.前半では,1次元の結晶モデルの素励起としてフォノンが現れることなどから始まり,連続極限,経路積分,くりこみ,ゲージ対称性,漸近自由性など,場の量子論に関する最も基礎的な内容が要領よくまとめられており,これと並行する形で格子場の理論の説明が進んでいく.この部分は,既に場の量子論の基礎を学んだことのある人が,その理解をさらに深める目的で読むのにも適している.
一方後半は,これから格子場の理論を研究の道具として使う人のための「手引き書」に近い印象であり,研究を始めるのに必要となる内容がほとんど網羅されている.特に第9章のアルゴリズムの解説は,石川氏の本領発揮といったところなのだろうが,類書にはない丁寧さと深さが随所に表れており,実に読みごたえがある.その後,ハドロン質量などの物理量の計算法やデータ解析の方法について,極めて具体的な説明が続く.実際に数値計算を始める人には,すぐに役立つ内容だと思うが,ちょっと覗いてみたいというくらいの読者には,少々忍耐力が要求されるかもしれない.
また,最後の2章は,ゲージ対称性がSU(N)群である場合に,N→∞の極限をとることに関連した話題となっている.このような極限は,1974年にトホーフトが最初に考えたものであるが,最近では「AdS/CFT対応」の文脈で,さかんに議論されているので,ご存じの方も多いだろう.本書では特に,このラージNゲージ理論において,時空を一点に潰してしまった理論が,無限に広がった時空上の理論と等価になるという驚くべき可能性に関して書かれている.これはもともと1982年に江口・川合が指摘したことであるが,その後,大川氏が共同研究者のゴンザレス-アロヨとともに,大きな貢献をしたテーマである.本書では,お二人の提案したことに従い,有限の箱に入れたゲージ理論の境界条件を一般化(ツイスト)することにより,4次元の場合にも「江口・川合等価性」が成り立つことを,数値的に示している.これらの2章は,QCD以外の問題に対する応用例として,興味深く読むことができるだろう.
なお,ツイスト境界条件を課したゲージ理論は,2000年頃「非可換幾何」上のゲージ理論の文脈でも再発見され,弦理論との関連でさかんに議論された.また,時空を一点に潰してしまったラージNゲージ理論は,1997年に石橋・川合・北澤・土屋が提唱した超弦理論の非摂動的定式化という形で,素粒子理論の歴史に再び登場することになる.これらの話については,本書と同じシリーズの土屋麻人氏の著書に詳しい解説があるので,そちらと合わせて読めば,より一層興味を掻き立てられることだろう.
(2018年8月2日原稿受付)