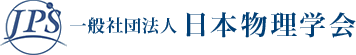会誌Vol.76(2021)「新著紹介」より
このページでは、物理学会誌「新著紹介」の欄より、一部を、紹介者のご了解の上で転載しています。ただし、転載にあたって多少の変更が加わっている場合もあります。また、価格等は掲載時のもので、変動があり得ます。
ハドロン物理学入門
永江知文
裳華房,東京,2020,x+256p,22×16 cm,本体4,200円[専門・大学院向]ISBN 978-4-7853-2924-2
紹介者:堀 正樹(マックスプランク量子光学研)
ハドロン物理学は,原子核物理学と素粒子物理学の境界に生まれた分野である.強い相互作用を記述する場の量子論である量子色力学QCDは,たった一つのゲージ結合定数g3を含む一見単純な構造を持つ.しかし,低エネルギー領域ではg3が1より大きい非摂動論的な値をとるために,クォークが集まって構成される多体系「バリオン」や「中間子」,それらの粒子が結合した「原子核」や「ハイパー核」,また初期宇宙における高温高密度状態や中性子星中の低温高密度状態において生成する特異な「核物質」等,多様な物質形態を発現させる.こうした強相関系を統一的に扱える手法がまだ存在しないために,現状では,各スケールで個別の有効理論を用いて理解せざるを得ない.有効理論は新しい量子数領域や密度領域でおこる諸現象を十分な確度で予言できないために,実際に実験を行ってみると従来の常識や枠組みを超えるような新現象が驚きをもって発見されることがある.近年,日本のスーパーKEKB電子陽電子コライダーや欧州のLHC加速器等で発見される,バリオンや中間子等に分類できない分子のような性質をもった「エキゾチック・ハドロン」はその好例であろう.
本書は原子核物理学の立場から多体系の構成粒子としてのハドロンの側面を概説した入門書である.大学の学部4年生にも理解できるように,諸現象を場の量子論を用いずに散乱断面積等の公式や波動関数を用いて解説している.まず第1章では,素粒子・原子核物理学で使用される単位や基本概念を解説している.第2・3章にかけては,クォーク模型が提唱され,電子ビームを用いた陽子標的中の深部非弾性散乱実験等において,クォークが発見されるに至った歴史的過程が,パートン模型や核子の構造関数の説明とともに解説されている.次に第4章では,ゲルマンやネーマンらによって提唱されたクォークモデルが詳述されている.アップ,ダウン,ストレンジの3種類のクォークは,質量が比較的小さいためにフレーバーSU(3)f 対称性がよい近似で成立する.この対称性を理解する上で必要なリー群の性質や,ヤング図形を用いた既約表現の推定,及びSU(3)f の昇降演算子を2個或いは3個のスピン1/2の粒子系に適用することにより近似的に説明されるバリオンや中間子の分類が丁寧にまとめられている.更に,チャームやボトムクォークを含む中間子やバリオンの分類を概説した後に,簡単なクォーク模型に基づいてハドロンのフレーバー波動関数や電荷,磁気モーメントや質量を導出している.また,ハドロンの形状因子や断面積の特徴,その存在が有効理論では予言されていながら実験的には確認されていないバリオンの「みつからない共鳴状態」等が説明されている.このように本書前半は,最近の欧米の素粒子物理学の教科書や素粒子データブック等に記述されている内容を踏襲しつつ,分かり易くまとめられている.最後にハドロン物理学のフロンティアであるテトラ・クォーク,ペンタ・クォーク,グルーボール等のエキゾチック・ハドロンがそれぞれ概説されている.
第5章はハドロンそのものから一旦離れて,伝統的な原子核物理学の解説に移行し,原子核の構造を理解する上で重要なフェルミガス模型,殻模型,中間子交換模型による核力等が説明されている.本書最大の特徴と言える第6章では,ストレンジクォークを含むバリオンの仲間である「ハイペロン」が原子核中で束縛されて生成されるハイパー核について詳述している.日本では,KEK旧陽子シンクロトロンや世界最大強度の陽子シンクロトロンJ-PARC MRにおいて,ラムダ,シグマ,グザイ等のハイペロンを含む新種ハイパー核の生成と詳細な分光実験等が行われており,本書の著者はこの分野における第一人者である.こうした実験を通じて,ハイパー核中でハイペロンが陽子や中性子とどのような有効相互作用を持つかを精緻に研究できる点が歴史的にも意義深い.更に,ラムダ1405等のストレンジクォークを含む共鳴状態及び中間子を含む特異な原子について,簡潔に述べられている.第6章後半では,宇宙論や星の進化の観点からビッグバンや星の中の元素の合成過程が,主に軽い元素を中心に概説されている.この章に関連する分野では,J-PARCや理化学研究所RIBF等における実験成果が知られている.第7章前半では米国RHIC加速器や前述LHCにおける高エネルギー重イオン衝突実験で観測された,クォークとグルーオンがハドロン中における閉じ込めから解放されて熱平衡に近い状態で長距離を伝搬するクォーク・グルーオン・プラズマ相について解説されている.ここではQCDを用いずに大学の学部課程で学習する熱力学の公式等を用いて平易に解説している.第7章後半では,中性子星中の高密度核物質や,その存在が議論されている中性子星のハイペロン化現象及びクォーク物質の可能性が解説されている.
「ハドロン物理学の課題と展望」と題した第8章では,QCDにおける未解決な大難問であるクォークがハドロン中に閉じ込められる現象の第一原理からの説明について概説されている.また,ハドロンが実験で測定されるような大きな質量を持つのは,本来理論が有するはずのカイラル対称性がQCD真空即ち場の基底状態では自発的に破れているためだと理解されている.しかし,本章で述べられているようにその詳細については理論的に未解明なことが多い.最後の第9章では,国内外の加速器実験施設J-PARCやRHIC,LHC,JLabが紹介されている.
本書は,日本の原子核物理分野において特にハイパー核や重イオン衝突研究を志そうとしている学部学生諸君にとって,格好の入門書であると思われる.同時に,素粒子物理分野側からのハドロン物理へのアプローチを詳述した教科書と併読すれば,更にハドロンの世界が一望できるであろう.
(2020年10月21日原稿受付)
共振器量子電磁力学;量子コンピュータのハードウェア理論
越野和樹
サイエンス社,東京,2020,vii+183p,26×18 cm,本体2,400円(SGCライブラリ-162)[専門~学部向]
ISBN 978-4-7819-1487-9
紹介者:金本理奈(明治大理工)
本書は,共振器量子電磁力学(cQED)の基礎物理としての学問の深みと,量子コンピュータを中心とした応用性の拡がりをシームレスにつなぎ,最先端量子技術に於けるcQED研究の位置付けを顕にする類稀な一冊である.
「共振器量子電磁力学」は,パーセルやクレップナー等による共振器(cavity)内の原子の自然放出レートに関する研究に端を発する,特殊な空間での原子と電磁場の量子電磁力学(QED)的相互作用の理解を目指す量子光学の一分野であった.今では共振器の種類の多様化と質的向上に伴い,cQED系に於ける究極の量子操作実現が視野に入ってきたため,cQED系はスケーラブルな量子コンピュータのハードウェア有力候補としても研究が進められている.また,元々の"天然の原子"と"光ドメインの光子"が主役のQEDから,近年は超伝導回路に於ける"人工原子"と"マイクロ波光子"が主役の回路QEDや,原子の内部状態の代わりに物質の"フォノン"が共振器光と相互作用する様を研究する共振器オプトメカニクス,また共振器光子が作る動的な光格子中の多原子ダイナミクスの研究も生まれるなど,共振器を用いた量子科学は多分野横断的な性質を帯びている.
それにつれて,「cQEDというものをちょっと勉強してみようかな」と考える学生や研究者が昔と比べて増えているはずであるが,この話題は,大抵量子光学のテキストの後ろの方に"advanced topicsです"と言わんばかりに,控え目に一章程度のページしか割かれていない.そのため,初学者がcQEDを学ぼうとすると,分厚いテキストの前の方から,光と原子の相互作用の量子力学的な扱い方や,開放量子系の扱い方など,必要な章を選びながら(時には他の書籍も引っ張り出しながら)読み進めていかなければならなかった.しかもこれらの基礎が網羅されている書籍は殆ど洋書であるため,学部生にとっては敷居が高く,advanced topicsに辿り着く前に時間切れになるか,興味を失ってしまうことが多々あった.
さらに量子光学のテキストに登場するcQEDの章は,「共振器光子の減衰レートが大きいとき/小さいとき何が起こるのか?」「共振器内の原子の自然放出レートはどう変化するか?」「原子と共振器光が強く結合すると何が嬉しいのか?」といった,共振器"内部"だけの世界で話が閉じていることが多い.しかしながら,スケーラブルな量子コンピュータを実装するためには,単独ではなく多数のcQED系を連結し,ある共振器で生成された光子を取り出して,それを今度は別の共振器に入力してゲート操作を行うといったプロセスを多数回繰り返すため,実際には「連結cQED系全体の実効的な散逸はどれほどか?」「共振器から取り出して再利用するモードと,その他の散逸モードをどのように切り分けて扱うか?」といったことが本質的な問題となる.これらの問題は今でも研究段階であるという理由もあるが,問題意識が明確に書かれたテキストを目にすることはこれまであまり無く,原著論文やレビュー論文を紐解く他なかった.このような理由から,私は長年,学問としてのcQEDと,これが量子コンピュータのハードウェアとして活用されるまでの間には何か目に見えないガラスの壁があるように感じていた.
本書は,このような高い敷居やガラスの壁を,次のような内容構成によって見事に打ち破ってくれる.第1~6章では,cQEDを理解する上で必要となる厳選された基礎理論が,学部生でも独学できるように無駄なくまとめられている.ここに超伝導回路QED系で実現される超強結合,深強結合領域の解説が組み込まれている点は量子光学のテキストとしても目新しい.第7章以降では,cQED系がいよいよ"外の世界"と本格的につながっていく.第8項のcQED系で実現する様々な量子ゲートの解説では,この研究を第一線で推し進める著者独自の理論も反映されている.第9章では近年目覚ましい進展を遂げている導波路QEDの最先端の理論がまとめられ,第10章では各種の量子技術応用が紹介されている.このように本書は基礎から最先端の話題までバランスよく網羅しつつ,著者の研究のオリジナリティが豊富に反映された構成となっている.
そもそもcQEDって何?何の役に立つの?と考えている初学者や異分野の研究者,量子光学の基礎を効率的に学びたい学生,或いは量子コンピュータの研究に関わる研究者,あらゆる層に本書は有用であろう.何より私自身,研究室に入ってきた「共振器○○○の研究をしてみたい」という学生に,付箋を貼りつけた何冊もの分厚い洋書やレビュー論文を積み上げて,初っ端から怯えさせることはもう無くなり,今後は迷うことなく「まずはこれ1冊」を差し出せばよくなったことを大変嬉しく感じている.
(2020年12月4日原稿受付)
Fundamentals of Magnonics
Sergio M. Rezende
Springer, Switzerland, 2020, xvii+358p, 24×16 cm, $89.99(Lecture Notes in Physics)[大学院向]ISBN 978-3-030-41316-3
紹介者:巻内崇彦(東大院工)
マグノンは強磁性体や反強磁性体に現れる代表的な素励起である.室温で制御可能であることと,豊富な非線形性を有することから,マグノン論理ゲートやレザバーコンピューティングへの応用が近年盛んに研究されている.
本書は,実験家でも理論家でもあり,ブラジルの科学技術大臣も務めた大家であるRezende氏が執筆した大学院生向けのマグノンの教科書である.理論と実験の記述がバランス良く織り交ぜられており,この分野の教科書として最初に読むのに適した内容になっている.図はカラーで明瞭であり,使用している単位系がSIかCGSかを明示しているため,初学者が混乱することは少ないと思う.全体を通して近年のマグノン研究を反映した話題をここかしこに盛り込んでいるので,分野の動向を整理するためにも役立つだろう.
第1章から第3章までは,半古典論と量子力学に基づいて磁化の運動方程式をコンパクトに導入し,マグノンをとりまく現象を紹介している.実験については,マイクロ波共振器を使った電子スピン共鳴と,Brillouin光散乱について詳しく記述されている.第3章で量子光学から始まったコヒーレント状態をマグノンの場合にも導入し,これがいろいろな章に登場してくるのが本書の特徴である.第4章と第5章では強磁性体と反強磁性体中のマグノンの分散関係を説明する.
第6章から第8章のトピックには著者の哲学が盛り込まれている.第6章ではマグノンの線形励起と非線形励起をまとめている.線形励起では,励起振動磁場による相互作用ハミルトニアンから出発するとマグノンのコヒーレント状態が生み出されることを導出する.マイクロ波共振器中の強磁性体と超伝導量子ビットの結合を利用した少数マグノン励起の最新の実験を取り上げており,著者が日頃から新しい研究に目を光らせていることが窺える.非線形励起としては,平行パラメトリック励起されたマグノンがマグノン同士の非線形相互作用とフォノン浴との相互作用を通じてコヒーレント状態に落ち着くことを説明している.最後に少々古いテーマとして自励振動とカオスを取り扱っている.第7章は室温で実現されるマグノンBose-Einstein凝縮(BEC)について,実験を紹介した後に理論を展開している.室温のマグノンBECは15年ほど前に報告されてから注目されているトピックの一つである.他のBEC・超流動系(液体ヘリウム,冷却原子気体,励起子ポラリトンなど)との凝縮の違いが簡単に述べられている.マグノン超流動が実現しているかどうかなどの未解明の問題は,これから他分野を巻き込んで議論されていくだろう.第8章は近年飛躍的な発展を遂げたスピントロニクスにおけるマグノンを概観している.内容の豊富さは他のスピントロニクスの教科書・専門書に及ばないが,ここにも著者のマグノンの捉え方が色濃く反映されている.
本書を読めば,著者がこれまでマグノンを研究する中で新たな視点を導入してきた先駆者のひとりだということがわかる.本書の流れに沿ってその先駆者の視線を追っていけば,マグノンをめぐる諸現象の理解と応用のこれからの発展を想像して胸が高まるだろう.
(2020年12月5日原稿受付)
ジー先生の場の量子論 基礎編
A. Zee著,原田恒司,筒井 泉訳
丸善,東京,2020,xviii+380p,21×15 cm,4,950円[大学院向]ISBN 978-4-621-30493-8
紹介者:曺 基哲(お茶大理)
本書はAnthony ZeeによるQuantum Field Theory in a Nutshell(第2版)という,場の量子論の教科書の和訳である.原書初版は2003年,第2版は2010年に出版されている.タイトルに含まれる"in a nutshell"というフレーズと,場の量子論の教科書としては比較的ページ数が少ないことからして,初心者向けの「お手頃の」教科書という印象をもたれるかもしれない(場の量子論の標準的な教科書として長く親しまれているPeskinとShroederによる著書1)が850ページを超えるのに対して本書の原書は約580ページ).しかし,実際に本書を読んでみるとそのような印象は一掃され,初学者にとって必要な場の量子論の知識と計算技術が身につけられる,優れた教科書であることがわかる.
本書はまず量子力学における経路積分の導入について解説したのち,スカラー場の量子化へと進み,正準量子化との比較を行う(第一章).ディラック場についてはスカラー場のときとは逆に,まず正準量子化を紹介し,それと整合するようにグラスマン数を用いた経路積分の導入へと進む(第二章).このように,経路積分量子化と正準量子化を行ったり来たりしているが,その意図と目的が適宜示されているので,読者は戸惑うことなく読み進められるだろう.次にスカラー場の模型を例にした繰り込みの説明,量子電気力学(QED)におけるゲージ不変性およびファデーフとポポフによるゲージ固定の議論へと進み,QEDの繰り込みについて解説が与えられる(第三章).そして有効ポテンシャル,自発的対称性の破れを経てカイラル量子異常までを議論している(第四章).
著者は序文で本書について「計算技法よりも概念の説明」に重きを置いていると述べているが,そんなことはなく,必要な計算手法の説明が(全てとは言わないが)かなり丁寧に与えられており,読者が手を動かして計算を確かめながら読み進められるよう配慮されている.独習用もしくは輪講用の教材として適切だと思う.本書の原書は気取らない,くだけた文体による明快な解説に多くの読者からの支持が集まっていると聞いているが,その雰囲気は日本語訳である本書でも引き継がれており,ユーモラスで臨場感あふれる説明にぐいぐいと引き込まれてしまう.訳者の力量が発揮されているところである.
ちなみに本書は第四章で終わっているが原書は第八章(と第N章というオマケ)まである.第三章で登場し,繰り込みの説明の際に「利口な実験家」にからかわれていた大学院生コンフュージオ君は,第四章ではテニュアを取ったばかりの新任准教授として再び登場する.しかし,(初心者が犯しやすい計算間違いの例として)カイラル量子異常の計算を誤ったまま論文を発表してしまうのだが,その後彼は無事だったのだろうか.第五章以降,コンフュージオ君が再び姿を見せてくれるのか,大変気になる.
参考文献
1)M. E. Peskin and D. V. Shroeder, An Introduction To Quantum Field Theory(CRC Press, 1995).
(2020年9月28日原稿受付)
プラズマプロセス技術;ナノ材料作製・加工のためのアトムテクノロジー
プラズマ・核融合学会編
森北出版,東京,2017,vii+273p,22×16 cm,6,160円[専門・大学院向]ISBN 978-4-627-77561-9
紹介者:田中 学(九大院工)
本稿で紹介する『プラズマプロセス技術 ナノ材料作製・加工のためのアトムテクノロジー』は,プラズマプロセスの関連研究を行っている学部・大学院生や,企業研究者・技術者,または他分野の研究者が,プロセス用プラズマの基礎・応用・計測について学ぶために有用な本である.また,プラズマの研究者ではないが,ナノ・アトムテクノロジーに関わる研究者・技術者にとっても,研究開発手段の一つとしてプラズマ応用を検討する際にも大いに有用な書である.
プラズマと一言で言っても,自然界のプラズマや人工的なプラズマがあり,1億度を超えるような核融合プラズマから,極めて低温のプラズマなど多種多様である.本書で主に取り上げているのは,通称プロセス(用)プラズマと呼ばれ,(i)軽い電子は高温であるが,重いイオン・中性粒子は室温近傍という,非平衡低温プラズマ,及び(ii)電子とイオン・中性粒子が同程度の温度となり約5千~数万度となる熱プラズマに大別される.特に,非平衡低温プラズマに関連する内容を中心として,基礎から最先端応用までを網羅している.
本書は,総勢18名のプラズマ技術の専門家により執筆されており,4つのパートに大別できる7章立てとなっている.第1章から第3章はプラズマプロセスの基礎として,プラズマプロセスにおける物理・化学過程について詳細に解説している.第4章では,特に重要なプロセスである集積回路製造におけるドライエッチング技術に関する基礎から最前線までを詳しく説明している.第5章と第6章では,ナノ材料の合成に関して,基板表面での成長と気相中でのナノ粒子・微粒子合成についてそれぞれまとめている.最後の第7章は,ナノ材料プロセスのためのプラズマ用プロセスの計測・解析法について,その場計測を中心に種々の方法を説明している.つまり,入門書としての基礎的な部分から,最先端の応用研究までを一冊で網羅している.さらに,単に紹介するという内容ではなく,読者自身が後に定量的に解析するに足る丁寧な説明,すなわち定量的なデータに基づく説明が心掛けられている印象を強く受ける.
冒頭で述べた通りであるが,関連研究を行う学部・大学院生,企業研究者・技術者に加え,他分野の研究者にお薦めしたい.例えば研究室の輪講でのテキストとして採用することで,研究室の基礎力・ベースアップにつながると想像できる.また,関連研究に従事されている企業研究者・技術者にとっては,本書で示されている内容を読み解くことで,自身の研究で対象とするプロセスを定量的に解析し,技術的指針を得ることにつながる.最後に,特に評者としては,他分野の研究者にも強く本書をお勧めしたい.充実した参考文献に加え,所々に散りばめられた有用なデータ表も活用しやすい.本書がなければ自身で論文・データブック等を検索・整理して調べる必要のある多岐にわたる内容を,一冊で網羅することができるため,効率的な調査が可能となる.つまり,例えば材料分野の研究者が,プロセス用プラズマを手法の一つとして用いる際にも極めて本書が有用だと言える.
以上を一言でまとめると,本書はプラズマプロセス技術の入門書であり,プラズマプロセスにおける重要な物理過程・化学過程を定量的に説明している実践的教科書でもある.プラズマプロセスに関わる研究者の一人である評者としては,ぜひ多くの方々に本書を手に取っていただき,広い分野の方々にプラズマプロセスの面白さ・重要性を知っていただきたいと願う.
(2021年1月14日原稿受付)
X線の非線形光学;SPring-8とSACLAで拓く未踏領域
玉作賢治
共立出版,東京,2017,xi+171p,21×15 cm,2,200円(基本法則から読み解く物理学最前線14)[専門~学部向]ISBN 978-4-320-03534-
紹介者:松田 巌(東大物性研)
外部刺激による系の変化は線形現象とした方が一般的に取り扱いやすい.現在,物質評価のスタンダードとなっているX線回折やX線分光といった手法は,実験室光源や放射光を使用すれば物質に対する刺激が弱いため解析は線形応答の範囲で実施することができる.しかしながら自然現象とは本来非線形であり,X線による刺激も大きくなれば光学現象も線形応答の理想から外れていく.21世紀に入ってから超短パルスかつ超高強度のX線自由電子レーザーの建設が世界中で行われ,我が国でも2011年にSACLAでX線レーザーの発振が実現された.そして多種多様な非線形X線光学現象が発見されるとともに,現在では新たな分光法の開発も進められている.本書はこのX線の非線形光学の解説書である.
本書ではまずは基本的な電磁気学と量子力学を復習しながらX線に対する物質の線形応答を丁寧に説明している.そして非線形X線光学の理論と実験の基礎を線形現象の場合と比較しながら取り扱い,最後にごく最近の先端研究の成果を分かりやすく解説している.内容は大学の学部生の知識で理解できるよう構成されているため,3,4年生や大学院生の参考書として利用できる.実際,私自身の光物性の講義においても取り上げさせていただいている.非線形X線光学はごく最近開拓された分野であるが,本書は専門家の間でも「これまでの専門知識を復習しながら分かりやすく学ぶことができる」,ということで評判が高い.
筆者である玉作賢治氏は驚くべきことにX線自由電子レーザー完成の10年以上前から非線形X線光学の学理探求を行っており,光源利用が始まると様々なX線非線形光学現象を発見してきた.まさに非線形X線光学のパイオニアであり,理論及び実験も自身で作り上げてこられた.そのため本書では数式が丁寧に導かれ,複雑な現象を理解するのに便利な視点などが組み込まれている.当事者ならではの工夫と熱い思いが感じられる.
さて本書の具体的な内容であるが,第1章では本分野の歴史的経緯が語られ,その後に筆者からその面白さが述べられている.可視光で発達した非線形光学が,X線領域において単に短波長化しただけでは「学術的に面白くない」とし,X線の特性から導かれる様々な課題を研究する意義を述べている.第2-4章ではX線の非線形光学を理解する上で必要なX線に関する基礎をまとめている.第2章ではX線と物質の相互作用の基礎として線形応答を扱っている.特筆すべきは従来のX線の教科書と比べて本書では数式が丁寧に導出されており,非線形光学を理解する上で線形光学そのものも正しく深く理解することの重要性が伝わってくる.第3章ではX線散乱の基礎が述べられており,X線回折理論を2つの流儀で解説するなど,長年X線研究に従事した玉作氏ならではの視点で分かりやすく説明がされている.そして第4章ではX線光学系の基本が扱われている.放射光やX線自由電子レーザーといった光源の基礎から,光学系,検出器,そしてX線光学用の非線形結晶まで紹介されている.第5章からは非線形な散乱過程がまとめられている.散乱過程に関わる光が3つともX線である場合について,2次の非線形分極率を第2章の数式を元に導かれている.そしてその研究例として第2高調波発生とX線パラメトリック下方変換が実験結果とともに紹介されている.X線パラメトリック下方変換の実験はX線レーザーなしでも実施されてきており,このような興味深い歴史的事実も本書で学ぶことができる.第6,7章ではさらに非線形分光研究例として玉作氏ご自身のものを中心に詳しく述べられている.第6章では長波長領域へのX線パラメトリック下方変換が説明されている.X線非線形光学を用いた新たな物質情報抽出法として,回折限界を超えた局所光学応答の観測を理論的に示すとともに,ダイヤモンド結晶で実証した成果が紹介されている.第7章では非線形なX線吸収過程が取り扱われ,逐次的な2光子吸収過程として「クリプトンガスのK殻2重イオン化実験」と直接多光子吸収過程として「ゲルマニウム結晶の2光子吸収実験」が解説してある.第8章では今後のX線非線形光学の展望がまとめられている.X線自由電子レーザーの強度化は今後も進み,その結果,量子光学分野における非線形光学の研究が大きく発展することが期待される.
本書はX線非線形光学を理解するために,線形的な光学応答からX線実験技術そして量子光学の内容を取り扱っており,「シュウィンガー限界」など専門用語を多く含んでいる.玉作氏はこれらに対して分かりやすい説明を入れており,読者は新しい用語を知るだけでなく,昔学んだものに対しても著者の視点からその理解をさらに深めることができる.いずれのキーワードも索引に挙げられているので,読者は本書を非線形X線光学に関係するキーワードの辞書代わりに使用しても良いであろう.
高強度X線と物質の相互作用は紛れもなく人類の未踏領域であり,今後のX線非線形光学は学理の探求だけでなく応用研究でも役立つことは間違いない.多くの方に本書を読んでいただきX線非線形光学の理解とともに,科学技術における新分野開拓の興奮も味わってもらいたい.
(2021年1月19日原稿受付)
なぞとき 宇宙と元素の歴史
和南城伸也
講談社,東京,2019,255p,19×13 cm,1,980円[大学院向]ISBN 978-4-06-518094-5
紹介者:﨏 隆志(東大宇宙線研)
「はじめに」によると,本書は著者が文系大学生向けに行った講義をベースに最新の成果を加えたものだという.数式はE=mc2しか使っていないと聞き,きれいな装丁を見ると,本誌読者は「なんだ一般向けか」と背を向けてしまうかもしれない.そんなあなた,損してます.確かに一章の波動性と粒子性の話や電磁波に関する説明はいかにも一般向けで,どうやって説明するのかな?くらいの興味で読むことになる.しかし,2章以降は次第に「最新の成果」が現れ,内容に引き込まれていく.講義を受講した文系学生を心配しながら読み進めることになる.
本書の内容を要点だけ言えば「天体の進化と元素合成」という天体物理学の古典的な内容である.タイトルの通り,我々の身の回りの物質がどのようにできたのか,という疑問になぞときのように答えていく.ビッグバンでリチウムまで,天体内部の核融合でニッケル(鉄族)まで,超新星爆発で鉄より重い元素が合成される,という本書のあらすじは多くの物理屋がご存知だと思う.一方,天文学を専門としていなければ,それぞれの上限の理由や質量ごとに場合分けした星進化の詳細は覚えていない方も多いと思う.そんな本誌読者(失礼)が,物理原理を理解した上で,宇宙の元素合成を復習するのに最適な本書である.E=mc2が核融合と核分裂の実現可否を司る最重要な物理原理であり,この式だけは譲らなかった著者の判断はもっともである.元素合成のややこしい場合分けは,それぞれの環境の物質密度で決まる核反応速度と,核反応を阻害する膨張・放射性崩壊・光子反応のタイムスケールの競合,という絶妙なバランスによっている.このバランスの支配者を明らかにしながら多様な天体現象を説明していく筆致が,本書を物語のようにスラスラと読み進められながら教科書のような説得力を持たせてくれる理由だと感じた.地球物理,太陽系外惑星,暗黒物質・暗黒エネルギーなど,ほどよく本題から脱線した話題も魅力である.
ところで,なぜ今(さら)元素合成を取り上げるのだろう? 2017年8月に連星中性子星合体からの重力波とそれに伴ったショートガンマ線バーストと多波長残光が発見され,rプロセス元素合成の証拠が発見されたことで,この分野が盛り上がっているからである.つまり,ブームに乗った本である.と思って読み始めた.しかし,重力波観測の話が出てくるのは7章で,連星中性子星が合体するのは本文242ページ中224ページ目である.なんだか予想と違う.答えは「おわりに」に書かれていた.著者のこれまでの研究とrプロセス元素合成の研究に関する物語が生き生きと描かれている.そして,実は本書のほとんどの原稿は2017年3月に書き終えていたと知り,私の浅はかな予想を恥じた.連星中性子星合体によるrプロセス元素合成を早くから予想し,困難を乗り越えて理論を築き上げてきた著者に敬意を表したい.そして,観測が予想を証明したことを祝福したい.宇宙の元素合成の物語と同じくらい,一人の,いや二人の研究者の物語に心を打たれた.
(2021年2月3日原稿受付)
相対論とゲージ場の古典論を噛み砕く;ゲージ場の量子論を学ぶ準備として
松尾 衛
現代数学社,京都,2019,viii+164p,21×15 cm,2,200円[大学院・学部向]ISBN 978-4-7687-0508-7
紹介者:佐藤正寛(茨城大理)
本書は「大学物理学科の学習」と「素粒子・原子核理論の研究者に必須の相対性理論およびゲージ場の理論の学習」の行間を埋めることを目指した書籍といえる.著者の松尾氏は原子核理論を専攻し博士号を取得し,その後研究分野を大きく転向し,現在は主に物性理論―特にスピントロニクス―に注力している異色の研究者である.
はしがきにも書かれているように,本書で取り上げる各項目の本格的解説は他の専門書にゆだねられており,著者は読者に「各項目の要点や目標などを読み取り,本格的テキストに突入する前の準備運動をしてもらう」ことを目指している.本格的または教育的な参考書の情報が各所に掲載されており,取り上げる各テーマの良質な参考書を見つけるために本書を利用することもできる.全体で164ページと薄く,時間をかけて解読する本格テキストとは対照的に,読みやすさを重視している.
2章以降の各章タイトルは「「ちゃんとした」理論とローレンツ群」「時空概念の変革」「質点運動のレシピ」「質点運動から場の運動へ」「多重線型写像と添え字の上げ下げ」「「ギョッとする」記法―微小要素と線形写像の二面性―」「ミンコフスキー時空上の微分形式」「特殊から一般へ」「スピノル場の方程式」「局所ゲージ対称性と非可換ゲージ場」「動き回る物質の中の電子スピンたち」「ゲージ場の量子論へのはるかなる道のり」である.各章では著者が読者へ伝えたい重要項目のツボが,主に解析力学や古典電磁気学を介して,解説されている.本書のはしがきには「古典力学や電磁気学や量子力学,線形代数やベクトル解析を聞きかじったことのある読者を対象に」と書かれているが,より絞り込むと「上記の各章のタイトルに関連する内容を多少かじってみたが挫折した者」が最適な読者ではなかろうか.大学物理学科の基本的学習内容を理解した学部3~4年生でも,上記のタイトルに全く馴染みがない者には本書の内容は(特に中盤以降)やや敷居が高いだろう.背伸びをしたい意欲的な学部生,場の理論に憧れている学部生,素粒子理論を学び始めた大学院生,素粒子理論を専門としない理論物理学大学院生や研究者は,「なるほど」と思える解説を多数見つけられるだろう.本格的な相対性理論やゲージ場の理論を学習してしまった素粒子論の専門家は,非専門家がどこで落ちこぼれるのかを理解するのに役立つだろう.解析力学に焦点を当てている部分,特に質点の力学から場の理論への乗り移りを解説している第5章は,学部1~2年生に場の理論に興味をもってもらううえで非常に有益といえる.
以下では,評者が感じ取った本書の特徴的な面について短く評論する.中盤までに登場するキーワードとして「回転対称性を典型例とする連続対称性」「ローレンツ変換を含む座標変換」「テンソル」「微分形式」が挙げられる.これらは特に解析力学や特殊相対論との関連が深い項目である.物理学科の教育では,多彩な物理現象の面白さやその背後の普遍的側面を理解してもらうことがしばしば目標となる.そのために必要な数学が多数あり,一定の学生は面白い物理に到達する前に数学で挫折してしまう.微分積分や線形代数の基礎的内容は乗り越えられても,上記4項目を理解するにはより抽象的な数学に触れる必要がある.カリキュラムや教員数や学生の基礎体力の問題から,上記4項目についての学部教育が充実していない大学が多い.しかし,本書のタイトルにある相対性理論やゲージ場の理論ではこれらが必須な訳である.したがって,本書はこれらの高等物理数学のユニークな入門書,または,その気持ちを伝える簡潔な解説とみなすこともできるだろう.特に「テンソル」と「微分形式」を学部で習う物理と関連させながらあっさりと解説している和書は少なく,これらの解説は本書のユニークな点である.たとえゲージ場の理論の理解を目標に設定せずとも,解析力学や古典電磁気学を例にとってテンソルや微分形式の有用性が示されており,これらを学ぶことでテンソルや微分形式への敷居は著しく低下し,より本格的にテンソルや微分形式を必要とする物理学を学ぶ際の準備にもなる.また個人的に,解析力学の変分原理で現れるリー微分の簡潔な解説,解析力学の運動方程式が任意の座標系において同じ「形」になること,ベクトル解析の勾配・発散・回転の表現が座標系に大きく依存する一方で外微分が座標系に依らないこと,など学部教育で見逃しがちな側面を強調した解説は多くの学生や研究者に有益ではないかと感じた.
本書後半では,特殊相対論と古典電磁気学を参考にしながら,一般相対論やスピノル場(電子の場)およびゲージ場の理論について簡潔に解説している.非専門家の評者にとってはこれらの解説は簡潔過ぎるようにも感じるが,それで著者の狙いは達成されているのかもしれない.第12章「動き回る物質の中の電子スピンたち」では,ゲージ場の理論の立場から物性物理の低エネルギースケールの電子の運動を見直すことで見えてくる量子論的コリオリ力が解説されており,これは著者たちのスピントロニクスに関わる成果と深く関連している.相対論的場の理論におけるゲージ対称性の指導原理から低エネルギーの電子スピンの運動の特徴が予言されており,ゲージ場の理論の考え方の面白い応用例と言えよう.
本格的テキストを傍らに置きながら本書を読む,まずは気軽に本書を読んで相対論やゲージ場の理論の雰囲気を味わう,などなど,読者に応じて色々な利用法があるだろう.相対論やゲージ理論―そこに辿り着くまでに出会う物理や数学―の理解を助ける新しいタイプの和書が1つ登場したことを歓迎したい.
(2021年2月28日原稿受付)
Physics and Mathematics of Quantum Many-Body Systems
Hal Tasaki
Springer, Switzerland, 2020, 525p, 24×16 cm, €93.59[専門・大学院向]ISBN 978-3-030-41264-7
紹介者:藤 陽平(東大院工)
本書は量子多体系の物理を扱う教科書であるが,自由粒子からの摂動論や平均場近似で始まる伝統的なスタイルの教科書では全くない.本書ではいくつかの理想的な模型における数学的に厳密な結果を通じて,量子多体系における普遍的な性質がどのように現れ,どのように物理的に理解されるかを明らかにしていく.「数学的に厳密な結果」と聞くと,評者のように数学が得意でない者は身構えてしまうが,学部レベルの量子力学および線形代数などの基本的な数学の知識だけで十分読み進めていくことができる.なお,著者の他の教科書の読者にはお馴染みであろう大量の脚注は(脱線の度合いは控えめながら)本書でも健在である.
本書の内容は,量子スピン系における対称性や基底状態などの一般的性質が述べられた後で,3つの話題に分かれる.各話題は独立しており,前後の章に表れる式や定義の参照はきめ細かくなされるため,「つまみ食い」的な読み方をしやすい構成といえる.いずれの話題もその発展において中心的役割を果たしてきた著者ならではの深い洞察がうかがえる.特に第1部は量子スピン系における長距離秩序と対称性の自発的破れという標準的な話題を扱いながら,数学的に厳密な結果から出発することで初めて見えてくる(つまり平均場近似では得られない)ユニークな視座を提供する.例えば,有限系で対称なはずの基底状態が,どのようにして無限系で対称性の自発的破れを導くかという,重要だが(ある有名な理論物理学者がPhysics Stack Exchangeに同様の質問をする程度には)明確に述べられない問題に一定の解答を与える.また,量子反強磁性は強磁性よりも「量子的」であるというよく聞かれる標語に興味深い反例を示す.確かに量子Heisenberg強磁性体の基底状態が厳密に得られる一方で反強磁性体の基底状態はreflection positivityという(本書で丹念に解説される)数理物理の道具を用いてやっと長距離秩序が示されるほどには非自明だが,対称性の破れた基底状態は強磁性体よりも古典的なベクトルとして振る舞うという意外な性質が議論される.このような結果は通り一遍の対称性の自発的破れの知識で満足してきた評者にとっては驚きであった.
以降はやや発展的な内容で,第2部ではスピン1の1次元反強磁性体におけるHaldaneの議論から始まり,それに触発されて提案されたAffleck-Kennedy-Lieb-Tasaki(AKLT)模型に対する厳密な結果が示される.AKLT模型自体は極めて人工的な模型でありながら,それが生み出した物理は当初想像しえないほどに豊富であり,行列積状態,クラスター状態,対称性に守られたトポロジカル秩序,作用素代数を用いた1次元量子系に対する厳密な結果など関連する話題について入門的な解説がなされる.第3部では,遍歴電子から生じる強磁性という身近にありふれた現象を相互作用する電子の基本的な模型であるHubbard模型からいかに引き出すかという数理物理の難解なパズルに対して,いくつかの厳密な結果が示され,現実的な強磁性に近づけるための地道な拡張が議論される.第2部がさらなる発展への楽観的な展望を示すのと対照的に,第3部は現状の方法の限界と困難が提示され,金属強磁性の普遍性の理解がまだ道半ばであることが述べられて終わる.しかし,いずれの内容も読者を各話題の最先端に導くものであり,本書はこれから研究を始める学部生・大学院生にとっては関連分野の入門書に,研究者にとっては分野の進展を整理し新たなアイデアを得るきっかけになると期待される.
(2021年3月16日原稿受付)
物理学者,機械学習を使う;機械学習・深層学習の物理学への応用
橋本幸士編
朝倉書店,東京,2019,viii+196p,22×16 cm,3,850円[専門・大学院向]ISBN 978-4-254-13129-1
紹介者:吉岡信行(東大院工)
機械学習,とりわけ深層学習が,社会を大きく変える力をもつことが明らかになってきた.そのポテンシャルは,基礎研究から産業応用に至るまで,想像だにしなかった領域を巻き込みつつある.物理学への応用も,むろんその一つだろう.
本稿で紹介する「物理学者,機械学習を使う」では,機械学習の活用によって物理学がどう進化しうるか,という疑問に対する議論が,縦横無尽に追求されている.融合分野が急速に発展する中で,本書のような網羅的なトピックを解説する和書は他に類を見ない.以下では,誌面の許す限りで,本書の概要と読みどころを紹介してみたい.
a)本書の概要
機械学習×物理学の境界をテーマにする本書の内容は,大きく分けて4つの分野に分割されている.その4つとは,(1)物性(2)統計(3)量子情報(4)素粒子・宇宙である.物理の研究者であれば,いかに広範な分野に跨っているかが一目瞭然だろう.それに加え,融合のアプローチも様々である.教師あり学習を活用してラベル推定を行うスタンダードなものから,ニューラルネットワーク自体を量子多体系や時空と同一視するものや,機械学習の動作原理に量子力学を導入するものまで,多種多様である.それぞれのトピックでは,計算事例が多数紹介されているが,計算環境や実行時間などを具体的に示すなど,従来の専門書には見られないような読者への配慮がうかがえる.
b)本書の読みどころ
著者によっても言及されているように,機械学習と物理学を関係づける切り口は様々である.本書の最大の読みどころは,様々な物理分野の研究を進展させる可能性を,多角的に提示している点である.読者は,本書を通読した暁には,物理と機械学習を結びつけるためのメタ的な視座を獲得することができる.その一方で,個別のトピックに興味のある読者は,それぞれのテーマを独立して学ぶこともできるため,非常に有機的な内容となっている.機械学習と物理の融合分野の最新事例をチェックしたい,という読者には,読めば読むほどに得るものが増えていくのも,本書の魅力の一つである.
本書の主なターゲットは,物理研究への応用事例を吸収したい,という意欲をもつ読者である.本書を読む中で実際に手を動かしてみたいと感じた方のために,著者たちが利用した機械学習ライブラリを紹介している.それぞれのウェブサイトで公開されているチュートリアルを参照しながら,ぜひ理解を深めてほしい.また,機械学習の基礎的な概念から学んで理解を深めたいという方には,それぞれの目的に応じた専門書を併用するとよいだろう.
機械学習と物理学の境界は,現在もなお急速に発展する分野である.この分野に携わる気鋭の研究者たちが集結した研究会「Deep Learning and Physics」を発端に生まれた本書は,読み応えたっぷりの贅沢な内容であり,迷いなくお勧めできる一冊である.
(2021年3月20日原稿受付)
フラックス結晶育成法入門
橘 信
コロナ社,東京,2020,vii+161p,21×15 cm,2,750円[大学院向]ISBN 978-4-339-06651-7
紹介者:村川 寛(阪大院理)
物性研究において単結晶の高品質化は物質本来の性質を評価するためには不可欠であるし,大きなサイズの単結晶では測定可能となる物理量の幅が広がることから,純良で大型の単結晶の合成技術を習得することはとても重要な意味をもつ.特に本書で扱われているフラックス法は特殊な装置を必要とせず,組み合わせられる元素の種類が豊富であるとともに組成比の調整も可能な大変有用な合成方法である.フラックス法と聞くと,これまでに結晶合成の経験がない方にとってはどことなく難しく敷居が高いものに感じられるかもしれないが,本書では熟練した合成技術をもつ著者の豊富な経験に基づいて,初心者であっても作業の全工程をしっかりとイメージして実行するために必要な具体的な情報と説明に加えて,合成を成功させるために押さえておくべき要点についてとてもわかりやすくまとめられている.合成をする際に使用する装置や道具についても写真とともに具体的かつ詳細に記述されており,安全に作業するための注意点や,経過を観察することではじめて気づくこと,さらには得られた結晶の管理方法に至るまで,現場で学んだときに実験ノートにまとめておきたくなる実用的な内容がしっかりと盛り込まれている.また,結晶が成長する過程についての記述や合成条件の違いによる結晶形状の特徴についての解説に加えて相図を用いたわかりやすい説明もあるので,得られた結晶の様子から状況の良し悪しを判断して最適な合成条件を絞るための手掛かりとすることができる.フラックス法については私もあまり経験がある方ではないが,本書の流れに沿って実際にやってみることで基本となる作業内容については思いの外手軽であることに気づく.そして,得られた結晶を観察して合成条件と照らし合わせることでよりよい結晶を作るための勘が自然とはたらくようになってくる.つまり,まずは手を動かして結晶を作ってみることが大切であるわけで,本書の内容はこれから結晶合成をはじめてみたいと思っている方が最初の一歩を踏み出すときの大きな助けとなるものである.さらに,様々なフラックスの種類ごとの特徴や性質,用途についての専門家ならではの貴重な情報や高度な合成技術の数々をまとめた章に加えていくつかの代表的な物質についての合成条件の一覧もあり,すでにかなりの合成経験を重ねられた方や,さらに技術を磨きたい方にとっても大いに参考になる情報が満載の書籍である.また,著者自身が合成された美しい結晶の写真も多数掲載されており,単結晶が放つ神秘的な魅力が伝わってくるとともに,著者の卓越した合成技術の一端を目の当たりにすることで「こんな結晶が得られるのか!」と刺激を受けてますます合成の意欲が掻き立てられるはずである.
(2021年3月30日原稿受付)
磁性物理の基礎概念;強相関電子系の磁性
上田和夫
内田老鶴圃,東京,2020,vi+207p,21×15 cm,本体4,000円(物質・材料テキストシリーズ)[専門~学部向]ISBN 978-4-7536-2316-7
紹介者:速水 賢(東大院工)
著者は,重い電子系やフラストレーションの強いスピン系といった強相関電子系分野における磁性と超伝導の研究を専門とする理論研究者である.その中でも本書では,磁性現象に焦点を当て,局在スピン系の磁性から遍歴電子系の磁性までの統一的な記述を試みている.我が国の磁性に関する教科書といえば,金森順次郎『磁性』(培風館),芳田奎『磁性』(朝倉書店),近藤淳『金属電子論』(裳華房),守谷亨『磁性物理学』(朝倉書店)などの数多くの良書が存在するが,しばしば行間を埋める必要があることから,研究室におけるゼミ本として使用されることもあるかと思う.一方で本書は,長年にわたって磁性理論を発展させてきた著者ならではの視点により,膨大な磁性現象の重要なポイントがコンパクト(わずか200ページ強)にまとめられているため,研究室に入ってきた学部生や大学院生が独学する最初の入門的な磁性の教科書として適していると感じる.また磁性に関する他の入門書とは異なり,強相関電子系特有の近藤効果や重い電子系などのより専門的なトピックスや,スピンアイスなどの比較的新しい話題にも触れるなど,単なる入門書に留まっていないのが本書の特徴である.
本書は7つの章から構成されている.5章までは,局在スピン系から遍歴電子系までの磁性現象の基礎的な事柄について触れられており,磁性の入門書の内容としてはスタンダードな部類に属する.普段の議論で当たり前のように用いるキュリーの法則,結晶場,超交換相互作用,ジャロシンスキー・守谷相互作用,分子場近似,スピン波,フラストレーション,ハートリー・フォック近似といった基本的な用語を,コンパクトながらも丁寧に説明しているため,初学者はまずここまでを読んでその内容を理解することをおすすめする.とりわけ局在スピン系と遍歴電子系における磁化や帯磁率の振る舞いの類似点と相違点がよくまとめられており,実験結果を解釈するうえでも有用になるだろう.さらには,スタンダードな強磁性体や反強磁性体の解説に留まらず,1/5欠損の入った正方格子系やシャストリー・サザランドモデルの直交ダイマー系における量子相転移,あるいはスピンアイス系における非共面的な磁気構造に関するトピックスも取り上げるなど,磁性現象の幅広さを感じさせてくれる内容になっている.
後半の6,7章では,近藤効果や重い電子系といった専門的な事柄がまとめられている.これらの現象では局在スピンと遍歴電子という相異なる個性をもつ電子自由度間の相関効果が重要であるため,しばしば煩雑な計算が必要になるが,各現象の導出過程や物理的な意味付けが丁寧に行われている.特に,7.3節「1次元近藤格子モデルの相図」は,著者が第一人者として開拓してきた分野であることから当時の研究の進展が感じられる力強い説明がなされており,磁性研究を行っている評者にとっては本書のハイライトになっている.
最後に本書を,10年前に同じ著者により執筆された書籍『磁性入門』(裳華房,2011)と比較してみる.前半の5章までの構成は類似しているが,各トピックの内容を掘り下げるレベルには差異が見られる.前著の『磁性入門』では各トピックについて必要最小限の事柄のみ紹介しており,正に学部学生や大学院生の入門書としてふさわしい.一方で,本書においては前著では詳しく触れられていなかったジャロシンスキー・守谷相互作用の導出やRVB状態の簡単な解説,次元性によるリントハルト関数の振る舞いの違い,グッツビラーの変分理論やブリンクマン・ライスの理論,SCR理論の詳細の解説を行うなど,より高度な内容を取り扱っている.さらには,近藤効果や重い電子系の詳細な解説は前著にはなかったものであり,より広いトピックスを系統的に学ぶことができる.したがって,入門書として適したものになっているのはもちろんのこと,磁性分野の研究を新しく始めようと考えている研究者に対してもおすすめしたい.
(2021年3月31日原稿受付)
高分子ゲルの物理学;構造・物性からその応用まで
酒井崇匡編
東京大学出版会,東京,2017,vii+198p,21×15 cm,3,740円[大学院・学部向]ISBN 978-4-13-062843-3
紹介者:山口哲生(東大院農学生命)
高分子ゲルは,3次元的な網目状構造をもつ高分子に多量の水(溶媒)を含んだ,やわらかい物質である.我々の体の一部を構成し,食品や医薬品にも使われる身近な物質である.にもかかわらず,適切な分子設計により,高分子重量の1,000倍もの溶媒を保持しうる膨潤能,電場,pHや温度などの多彩な刺激入力に対する巨大変形性,タンパク質などの巨大分子をも貯蔵・放出できる物質透過性など,極めてユニークな性質を発現させることができる.そのため,高分子化学,医薬学,生体工学,ロボット工学などの様々な分野において,スマート材料としての応用を目指した材料開発が精力的に進められている.
一方,FloryやEdwards,de Gennes,田中をはじめとする多くの研究者により,高分子ゲルの物理学に関する基礎研究も行われてきた(全くの余談だが,1981年ノーベル化学賞の福井にもゲル化に関する論文がある).そこでは,超巨大分子としての高分子ゲルが,階層的構造のもとでどのように振る舞うのかについて,ときには抽象化したモデル化がなされ,またあるときには実験結果から現象論が提案され,その理解に活用された.しかしながら,高分子ゲルの理解には大きな障害があった.それは,構造の特徴づけに対する困難である.一般的な高分子ゲルでは,合成の際に網目状構造の不均一性を回避できず,可視化における空間解像度の問題から構造を明確に決めることもできない.必然的に,構造と物性との相関を議論することは難しかった.
ところが,その困難の壁は崩れつつある.Tetra-PEGゲルと呼ばれる,これまでにはない均一性をもつ新規高分子ゲルが開発されたことが最大の理由である.分子量やトポロジーがよく制御された均一な網目状構造を合成できるだけでなく,意図的に不均一性を導入することもできる.それを用いた実験により,理論模型との比較や,均一系から不均一系へのクロスオーバーに関する定量的な議論が可能となっている.
本稿で紹介する「高分子ゲルの物理学」は,Tetra-PEGゲルを開発し,それを用いた精密な物性研究を展開している著者が,中性子散乱を中心とする先端的な構造解析結果とともに新たな視点をもって書いた,高分子ゲル物理のリバイバル版ともいえる教科書である.第1章,第2章においては,本論の準備段階として,高分子一本鎖や高分子溶液といった高分子の基本的性質が説明される.その後,第3章以降では,高分子ゲルの弾性,膨潤と収縮,巨大変形特性,高分子ゲル内部の物質拡散といった,本書の核となる内容が,著者ら自身による数多くの検証結果とともにいきいきと記述される.正直なところ,"ゲル研究者第3世代?"の評者がこの本を読む前には「何十年も前に確立されたことをいまさら蒸し返して何の意味があるのか」と思っていた.だが,いざ読んでみると,高分子ゲルのもつ不均一性に関する考察(ファントムネットワークモデル,不均一性と力学特性に関する実験)など,とても新鮮に感じられる記述が随所に見られた.
このように,本書は,高分子ゲルの基本から最新の成果まで,幅広い内容が現代的視点をもって記述されている.加えて,著者(いずれも気鋭の若手研究者)がこれまでの研究を精査し,自分の言葉で理解していった形跡が窺え,数式の背景や導出に対する説明も丁寧である.評者は,本書だけで容易に数式や議論をフォローすることができた.
本書は,統計力学やソフトマター物理を学んだ学部4年生や大学院生が自習するのに適していると思われる.また,高分子化学や物質科学分野の実験研究を行う学生が,本書によって理論的な側面を強化するのに適していると思われる.さらに,高分子ゲルに興味をもった研究者が,分野を概観するのにも活用できると思われる.
高分子ゲルの基礎物性やその理論的な取り扱い,新規機能の開発や高分子ゲルの応用などに興味をもつ学生・研究者に,一読をお薦めしたい.
(2021年4月3日原稿受付)
ブット・グラフ・カペル界面の物理と化学
H.-J. Butt, K. Graf, M. Kappl著,鈴木祥仁,深尾浩次訳
丸善,東京,2016,xii+422p,21×15 cm,8,580円[大学院・学部向]ISBN 978-4-621-30079-4
紹介者:菱田真史(筑波大数物)
本書はソフトマターやコロイドといった,物理学だけでなく,化学や生物学といった幅広い学問領域にわたる問題について,熱力学という観点から捉えることを目的とした教科書である.なかでも,表面張力や吸着といったソフトマターやコロイドの表面・界面に関わる現象を中心に解説されている.これらのサイエンスは上述のようないわゆる境界領域に属すものであるため,(応用)物理学科における伝統的カリキュラムからは除外されがちである.物理学科だけでなく,化学科においてもやはり,カリキュラムの中心からは外れることが多いように思われる.
一方で,この20~30年ほどのソフトマター物理学やコロイド界面化学の発展により,この領域のサイエンスはかなり体系化されてきている.また,ソフトマターやコロイドが関与する物性科学,材料科学は非常に多岐にわたっており,たとえば,高分子や界面活性剤,微粒子分散系などを扱う基礎研究,材料応用研究を行うにあたって,本教科書で扱われる「表面・界面の物理」を理解することが日に日に重要になってきている.また近年では,生物学の世界でも現象の理解に物理的な解釈を取り入れることが頻繁に行われるようになってきており,今後ますますこの領域の物理の普及が重要になると考えられている.
そういった背景のなか,本書は,上述した表面張力や吸着だけでなく,水中での静電的な相互作用の作用機構や濡れ,摩擦などの物理,および界面活性剤の自己組織化構造などの化学,これらを観測するうえで重要なX線回折の基礎などについて,数式を丁寧にフォローしながら体系的に解説している.本分野に関してはこれまでにもいくつかの教科書が出版されているが,それらと比較しても,数式が導出から丁寧に解説されていることが特徴である.できるだけ式変形を略せずに記されているため,理論の適用可能範囲などもわかってよい.このように初修者向けの教科書でありつつも,現象を表面的に知るだけではなく,物理的な原理から深く理解できるように工夫されている.熱力学の基礎から理解が深まるよう記述されているため,当該分野の学部~大学院生だけでなく,研究の中で当分野に関わるようになった周辺分野の研究者にもおすすめの書籍である.評者は現在,化学科に所属しており,化学の学生を指導しているが,彼らからも本書は理解しやすいとの声が上がっている.これは,訳書である本書の出版にあたって,日本語としても自然で読みやすくなるように翻訳が工夫されていることも理由の一つであると思われる.
このように,本書は,ソフトマター物理学やコロイド科学に関わる学部生や大学院生だけでなく,当該分野の現象について物理的な原理をきちんと理解したいと考える周辺分野の研究者にも是非勧めたい書籍といえる.
(2021年4月15日原稿受付)
数学のための英語教本;読むことから始めよう
原田なをみ,D. Croydon監修,服部久美子著
共立出版,東京,2020,xi+202p,21×15 cm,2,970円[広い読者向]ISBN 978-4-320-11430-2
紹介者:妹尾仁嗣(理研)
日本語を母語とする数学者である著者が,学部生向け「数学英語」の講義の経験を踏まえて書き下ろした,数学のための英語の教本である.高校~大学初級程度の実際の数学教科書の英語を読み解いていくスタイルをとっている.こう書くとターゲットは狭いと思われるかもしれないが,より広く科学全般における英文読解のみならず,論文執筆にも非常に役立つ本として勧めたい.
言わずもがなだが,英語は科学を学ぶ・研究する者にとっては必須である.その頂点ともいえる論文執筆はハードルが高く苦手に思う方も多いのではないだろうか.実際その執筆「術」に関して多くの書籍がある.私が大学院生のころの定番は日本物理学会編『科学英語論文のすべて』であり,その詳細な内容は現在も色あせない.一方で昨今ではインターネットの力によって,多くの英語知識をネット検索によってその時々で手軽に得ることができる.「すべて」が詰め込まれた書は今では助長かもしれない(何より通読が大変である).一方で実践向けの薄い本だけでは,すでに英文を書くことに十分精通していないかぎり,表層的となる危険性がある.
やや脱線するが,一般に日本の国語教育では論理的な文章を書く訓練を受ける機会が少ない印象を持っている.さらに研究に関連して英文を書くようになっても,伝えたいことをいかに簡潔に書くか,苦労されている方も多いかと思う.
そこで本書であるが,講義1回にちょうどよさそうなテーマが10章分,コンパクトにまとまっている.それぞれの章で,まず簡単な英文法のまとめからはじまり,その後,英文テキストに続きその詳しい解説とともに全和訳が載っている.また数学に関する語句とその中で注意すべきアクセントや,便利な表現,科学英語に特有(著者は数学特有と書いているが物理でも共通な点がほとんど)な表現,間違えやすい点,と例文を挙げて丁寧な説明がちりばめられている.
数学の内容は,関数,積分,行列,から集合論にいたる物理でも基本となる事項だが,完全に追わなくても読める.良文を読むのは大事なことだと思うが,世で一番論理に忠実である数学の文章はその目的において最適であることを実感した.日本では自国語で多くの教科書・専門書を読める恩恵を受けているが,自分が(昔々)習った内容を英文で改めて読むのも新鮮で楽しかった.そして,すでに20年以上科学英文を読み書きしてきたにもかかわらず,多くの気づきがありうなずきの連続であった.最近おっくうとなり英文執筆の際もほとんどネット検索ですませてしまうところ,漠然とそれでは何か足りないと感じていたのだが,まさにその痒いところに手が届くような読後感を持った.監修に,言語学者と,英語を母語とし日本で研究する数学者が名を連ねているからなのかもしれない.漠然とでは伝わりにくいかと思うので実例をいくつか挙げると,「名前が付いた定理・公式の冠詞」「valueとnumberの使い分け」「量の表し方」「thatかwhichか」と日々悩むポイントがどんどん,"you name it"と出てくる.
バックボーンとしての科学英語知識を身に着けたい学部生・大学院生には最適な本だと思う.テキストとしては数学英語に限定されているが,その中核は専門によらない.親切にも演習問題とのその解答が付いているので,そこまで手を動かせばかなり力がつくであろう.これに続けてレゲットの有名
なコラム"Notes on the Writing of Scientific English for Japanese Physicists"(上述『科学英語論文のすべて』に和訳が載っているが,インターネットで入手可能な英語版も勧めたい)を読めば,科学英語執筆に必要な知識の骨格は十分に得られると思う.
現役の研究者でも,英文執筆が苦手な方はもちろん,何か足りないと(私のように)日々悩んでいる方も一度手に取ってみてはいかがだろうか.なお出版社のホームページに補足コメントおよび正誤表が載っている.語句検索によって格段に便利となる電子出版も希望したい.
(2021年4月26日原稿受付)
動かして理解する第一原理電子状態計算;DFTパッケージによるチュートリアル
前園 涼,市場友宏
森北出版,東京,2020,viii+192p,22×16 cm,3,740円[大学院向]ISBN 978-4-627-17031-5
紹介者:永井佑紀(日本原子力研究開発機構)
ここ10年ほどで,「第一原理計算」という言葉は物性物理分野において理論家実験家問わず深く浸透していると考えられる.それは,計算機の能力が進歩しスーパーコンピュータを使わなくても手元の計算機で十分な精度の計算ができるようになったという要因も非常に大きいが,もう一つの要因として「第一原理計算」が非常に手軽に実行できる環境が整ってきたことが大きいだろう.最近では,Google Colaboratory*などを用いることで,手元に計算機がなくても第一原理計算が実行できるようになってきた.そのため,第一原理計算が専門でない理論家や,普段数値計算を行わない実験家が自分の物質について第一原理計算を行う,というシーンも増えてきたと思う.一方,「第一原理計算」という名前にもかかわらず,設定すべきパラメータはそれなりに多く,どのようなパラメータを設定すればよいのかなど,全くの初心者にとっては相変わらず難しいのが現状である.
本書は,全くの初心者が第一原理電子状態計算を道具として使えるようになるための第一歩を踏み出すことをサポートする本である.特に,無料パッケージQuantum Espressoを用いて,環境整備からインストール,そして実行までを懇切丁寧に記述することにより,可能な限り第一原理計算利用の障壁を取り払おうとしている.本書の特徴としては,「まず使ってみる」という方針がある.計算の実行を前半,理論的背景の説明を後半に持ってくることによって,「第一原理計算とは何か」ではなく「第一原理計算は何を計算しているのか」をはっきりさせようとしている.つまり,初学者が,自分で計算の妥当性まで把握するための処方箋を与えている.例えば,擬ポテンシャルや交換相関ポテンシャルの選択をどうすべきか(どう決めるべきか)等である.また,第一原理計算を「カーネル計算」と「その他」の二つに分け,パン作りに喩えながら,学習のモチベーションの喪失の防止を試みている.確かに,自分が何を計算しているかを見失い,自分がしたい計算ができるかわからなくなることはよくあることである.
動作確認したOSやソフトのバージョンが一切書かれていないことは注意すべきである.例えば,Mac OS用の説明でbrewを使っているが,2021年5月現在,本書で書かれた関連ソフトウェアのインストール方法「brew cask install emacs」は失敗するため,出鼻が挫かれる.現在は「brew install --cask emacs」でなければならない.また,Quantum Espressoのmakeはgfortran 10以降だと本書通りでは失敗するため「./configure FFLAGS='-I/usr/local/include/ -fallow-argument-mismatch' CPP='gcc -E'」とすべきである.
いくつかのコードがそのまま動かないという点が問題であるが,誤植表とWeb検索によりなんとか自力で解決することができる.その点を除けば,本書は,実験研究者や初学者が手を動かしながら学ぶ最初の本として有用である.
(2021年5月20日原稿受付)
* https://colab.research.google.com
わかりやすい放射線物理学(改訂3版)
多田順一郎,中島 宏,早野龍五,小林 仁,浅野芳裕
オーム社,東京,2018,x+295p,21×15 cm,4,180円[学部・一般向]ISBN 978-4-274-22193-4
紹介者:石井邦和(奈良女子大理)
本書は"高校の物理と放射線物理学をつなぐ"というコンセプトで書かれた放射線物理学の入門書であり,定性的な説明を主体として平易な解説を旨として書かれています.また,改訂3版となり,これまでの改訂2版の内容に加えて,序章に宇宙・元素・放射線という内容が書かれており,大学に入ったばかりの学生であっても,放射線物理学の自然界における立ち位置を俯瞰することができます.加えて,福島第一原子力発電所事故を機に,放射線防護に関すること,核分裂に関する物理や原子炉における工学的なことについても書き加えられています.
序章および第1章では,ビッグバンから始まり,星の中の元素合成や天然の放射性同位元素,宇宙線,放射線の説明があり,放射線物理学とは何かを論じています.第2章および第3章では,特殊相対性理論入門と量子論入門が論じられており,高校物理までしか学んでいない初学者への大学物理への橋渡しを簡潔に述べています.
第4章,第5章,第6章,第7章は,原子の構造,X線,原子核の構造,放射能がそれぞれの章で論じられており,放射線物理学を理解する上で必要となる知識が概観されています.基本的に原子から放出される光をX線と呼び,原子核から放出される光をガンマ線と呼びますが,初学者が放射線物理学を学ぶ際に,原子および原子核に関する知識が必要となるので,本書のように1冊にまとめて論じてあると大学教育においても使いやすいと思いました.
第8章,第9章,第10章においては,荷電粒子線,X線およびガンマ線,中性子と物質の相互作用が論じられています.物質との相互作用を理解する上でとてもよく整理されて論じられています.加えて10章では原子炉の原理,商業用原子炉,核燃料サイクル,放射性廃棄物の処理まで盛り込まれており,最後に福島の原子力発電所事故の概要と今後の対応についても書かれており,現代社会における原発問題を理解する一助にもなると思います.第11章は加速器として,電子銃から静電型加速器,高周波型加速器が紹介され,ビームモニタや加速器の制御および運転まで書かれています.また,第12章には放射線量として放射線物理学関係の様々な物理量が紹介されています.
これまで紹介してきたように,本書は"高校の物理と放射線物理学をつなぐ"というコンセプトの通りに書かれている教科書であり,放射線物理学という分野を理解する上で非常に読みやすい教科書です.また,関連する各論的科目を分野横断的に論じてあるため,放射線物理学に興味がある学生にはまず読むことを勧めたい内容となっております.また,本書はポスト原発事故が話題となる近年の社会情勢に関連する知識にも触れられること,放射線物理学を体系的に基礎から説明してあることから,放射線物理学の初学者だけでなく一般の放射線に興味を持つ読者や放射線取扱主任者等の国家資格に挑戦する人にとってもお勧めできる一冊と言えます.
(2021年5月19日原稿受付)
素粒子の探求で宇宙がみえてくる;波場センセイのとっておき50話
波場直之
丸善,東京,2020,vii+210p,19×13 cm,1,980円[学部・一般向]ISBN 978-4-621-30515-7
紹介者:小林良彦(大分大教育)
今回紹介する本は,物理学に興味のある非専門家,特に,中高生に紹介したい一冊である.
本書は山陰中央新報に連載されたコラム「素粒子から宇宙へ 島根大・波場センセイの教室」を基に単行本化されたものだ.著者である「波場センセイ」こと波場直之氏は素粒子論の研究者である.扱われている内容は,原子や素粒子の基礎知識,量子力学,相対性理論,さらには,大統一理論や超ひも理論といった素粒子論の最先端トピックに及ぶ.文章は平易でかつ柔らかい.本書は,専門家によって書かれた,非専門家向けの素粒子論的宇宙論の啓発書と言えよう.以下では,本書の魅力を三つの点から紹介したい.
まず一つ目は,先述の内容が数ページごとのトピックに分けられている点である.これは新聞の連載コラムであったことに強く関係しているのだろう.内容が細切れにされていることにより,目次の一覧性が際立ち,気になる話題から気軽に読み進めることができる.
次に,表紙にもある,親しみやすいタッチのイラストが随所に描かれていることである.イラストには「波場センセイ」も多く登場する.これらのイラストがあることで,内容の理解が促されるだけでなく,本書全体にわたって親しみがもてるようになっている.
三つ目に挙げられるのは,波場氏の考えや思い,経験談が散りばめられている点である.これらがあることで,読者は素粒子や宇宙について知ることに留まらず,波場直之という素粒子論研究者について知ることができる.特に,物理学者との出会いが波場氏を突き動かしている様子がいくつかのエピソードから読み取れ,波場氏の人間味や研究者としての魅力にも触れることができる.
とりわけ,三つ目の点は本書のオリジナリティを担う重要な要素でもあり,非専門家向けの発信には欠かせないものだと思う.
さて,本誌の読者は本書の内容を一度は聞いたことがある可能性が高い.しかしながら,素粒子論の最先端トピックについては,素粒子論研究者以外の他分野の物理学者にも目新しいと思われる.例えば,大統一理論と陽子崩壊の話や重力と余剰次元の話といった未解決問題について,波場氏の感情と共に活き活きと説明されていて,秀逸だと感じた.そのような書きぶりは,専門家だからこそできるものである.
また,本誌の読者,特に大学などの教育関係者には,出前授業などの際に,物理学,特に素粒子や宇宙に興味を抱いている中高生に本書を紹介してほしいと思う.波場氏は本書の冒頭で「たとえ,よい先生に出会えなくても,本には出合えます」と書いている.波場氏が本書を書いた動機がこの文に詰まっていると,本書を読み終えた後に改めて感じた.
物理学に出合うきっかけ,さらには,物理学者に出会うきっかけとして,本書はうってつけだと思う.
(2021年4月30日原稿受付)
フェルミオロジー;量子振動と角度依存磁気抵抗振動
宇治進也
筑波大学出版会,茨城,2020,xii+206p,21×15 cm,4,950円[専門・大学院向]ISBN 978-4-904074-58-9
紹介者:伏屋雄紀(電通大基盤理工)
フェルミ面はときに芸術的ともいえる,美しくも複雑な形状をとる.その形状を明らかにすることは,すなわちその金属の性質を明らかにすることに直結する."フェルミオロジー"とは,金属の物性解明に必要不可欠な,フェルミ面の構造を明らかにする研究を指す.
フェルミオロジーにおいて,古くから知られる重要な実験手法が,量子振動と磁気抵抗である.それぞれの基本原理はどの固体物理学の教科書でも紹介されている.しかし,それで実験を解析するのに十分な知識が得られるかといえばそうではない.研究の現場ではもう一段上の知識が求められるため,モノグラフ的教科書が必要となる.量子振動についてはフェルミオロジーの創始者ともいうべきShoenberg自身の手による大著"Magnetic oscillations in metals"がある.1)磁気抵抗のモノグラフはいくつかあるが,有名なものではPippardの"Magnetoresistance in Metals"を挙げることができる.2)どちらも大変良書で,指導教員としては読みこなしてほしいところであるが,研究室に入ってきたばかりの学生にとっては,この二冊は少々敷居が高いようである.本書はこうした関連研究室でよく見かける問題点を解消してくれる.
第1章で結晶中の電子状態とフェルミ面の構造に関する基本的な説明が与えられ,第2章で磁場によるランダウ量子化とその帰結である量子振動の原理が紹介される.どちらも一般の固体物理学の教科書で解説されている対象だが,少しアドバンスドな内容も与えられており,その後の話題の伏線ともなる.第3章の量子振動,第4章の角度依存磁気抵抗振動(AMRO)が,この本の真骨頂である.著者が長年研究の第一線に立つ有機導体分野に少々偏ってはいるが,非常に数多くの実験データがタイミングよく示されているのはありがたい.これにより,無味乾燥な知識としてではなく,血の通った実践的な知識を習得できる.
実験データだけでなく,説明のためのイラストが豊富なことも本書の大きな特徴である.試しに数えてみると,全198ページ中,図の数はちょうど100であった!(表中図も含め)見開きに1つは図が載っている計算で,これは物理系の専門書としては間違いなくトップクラスであろう.
実験を解析することに重点を置くと,理論部分は単なる公式として天下り的になりがちである.しかし本書では,必要な公式の導出が丁寧に示されており,初学者でも自身で式を追うことができる.中には文献にあっさり導出を委ねているものもあるが,導出の有無の線引きが明瞭で,おそらくは「実験系の学生であっても,ここまでの計算はできるように」という著者のメッセージが込められているのだろう.特にAMROの説明が詳しくて丁寧である.実はつい先日も,新たにAMROを勉強する学生と一緒にいくつか類書を比べてみた.結果,本書が最も丁寧であったため,本書で勉強することを勧めた.
一つ懸念があるとすれば,フェルミオロジーというやや耳慣れない用語のため,本書を手に取るべき学生が見落としてしまうのではないかという点である.近年の固体物理学では,トポロジカル物質に関する研究が猛烈なスピードで進められている.新物質も続々と登場し,そのフェルミオロジーは極めて重要である.しかし,猛烈なスピードについていくため,ついつい理論や公式の導出を省略して,新しい結果を出すことに専心しがちである.本書であれば,スピード感を維持しつつ,理論や公式の勘所を抑えることができるであろう.
参考文献
1)D. Shoenberg, Magnetic oscillations in metals(Cambridge Univ. Press, 1984).
2)A. B. Pippard, Magnetoresistance in Metals(Cambridge Univ. Press, 1989).
(2021年6月19日原稿受付)