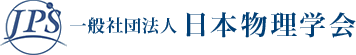会誌Vol.77(2022)「新著紹介」より
このページでは、物理学会誌「新著紹介」の欄より、一部を、紹介者のご了解の上で転載しています。ただし、転載にあたって多少の変更が加わっている場合もあります。また、価格等は掲載時のもので、変動があり得ます。
X線・光・中性子散乱の原理と応用
橋本竹治
講談社,東京,2017,x+402+iiip,21×15 cm,7,700円[専門向]ISBN 978-4-06-154397-3
紹介者:根本文也(防衛大)
本書は高分子,液晶,コロイドなどソフトマター凝集系を構造という観点から切り出した教科書である.規則性を有する結晶のX線・中性子構造解析については多くの良書があり,馴染みがある読者も多いであろう.他方で,ソフトマターのような乱れた系に対する構造解析手法については,決定的な教科書は存在しないように思われる.本書では,数式を丁寧にフォローしながら解説することで,門外漢であっても当該手法に関する理解が深まるよう記述されている.
本書が対象の1つとする両親媒性を有する高分子ブロック共重合体の溶融体では,水・界面活性剤系と類似したサブミクロンスケールのミクロ相分離構造が観測される.その発現メカニズムは,1980年代から太田・川崎を始めとする理論物理学者によってかなりの部分が明らかにされてきた.著者の橋本氏は,多くの実験手法を駆使してその構造を明らかにしてきた第一人者である.はしがきにも書かれているように,近年の放射光・中性子施設や機械学習を始めとした手法の発展は目覚ましく,一昔前であれば不可能であったサイズの試料で複雑な構造解析が可能となりつつある.ただ,いかに手法が発展しようとも,その根幹をなすのはボルン近似とフーリエ変換をベースとした電磁波・物質波の散乱理論であることに変わりはない.本書ではそれらの理論を基に,散乱曲線の計算手法が解説される.
第1章から第8章にかけては,物質との相互作用から始まり,散乱理論が電磁波の偏光も含めて丁寧に説明されている.電磁波・物質波の散乱が統一的に記述できることが明確に示されており,物理専攻の学部カリキュラムではなかなか到達できない事項についても補足されている.総じて式の導出や意味の記述は丁寧であり,前提知識の少ない他専攻の学生も十分フォローできる内容となっている.ただ,評者の好みかもしれないが,curlやD,Hを中心とした記法は時代がかっており,慣れる必要があるだろう.また,中性子散乱については必要最小限の記述となっており,飽き足らない読者は他書をあたるのが良い.
第9章から第14章にかけては,構造体からの散乱がどのような物理法則に従うかについて記述されている.具体的には多種の形状をとる孤立粒子,干渉が無視できる粒子分散系,粒子間干渉が起こる粒子分散系,粒子の結晶,フラクタル構造についてそれぞれ議論されている.さまざまな散乱曲線がフーリエ変換により導出されることが示されており,実際の解析に非常に役立つ内容となっている.これらは,小角散乱を取り扱う際に必須の基礎知識である.この内容がまとめられていることが本書の最大の特長であり,大学院に入学したばかりの学生やこの分野に興味を持った研究者にとっても有益であろう.
第15章から第20章にかけては,高分子の薄膜・微結晶・結晶からの光散乱について著者の研究内容をベースとして記述されている.屈折率やその異方性の空間揺らぎに関して,現象の解釈や測定装置も含めて,これまでの理論的背景をもとに解説されている.ただ,全編を通して共通であるが,入射波のエネルギー変化(=屈折率の時間揺らぎ)を測定する手法である準弾性散乱(動的光散乱)については記述が省かれている.
以上のように本書では,小角散乱による構造解析に関する基礎知識とその応用について,実験研究者の観点から丁寧に記述されている.高分子を始めとするソフトマターだけでなく,鉄鋼などの多成分系固体材料においてもメゾ領域の構造が重視され,(電子)顕微鏡による観察結果が報告されている.顕微鏡による直接観察は極めて強力な手法であり,その重要性は疑う余地がない.一方で周知のとおり,物性には物質の平均的構造が寄与し,外場応答は波数空間で議論することで見通しがよくなることも多い.散乱実験はそれら2つをダイレクトに捉えることができる有力なツールであり,本書はその良きマニュアルとなることが期待される.
(2021年8月10日原稿受付)
統計力学から理解する超伝導理論[第2版]
北 孝文
サイエンス社,東京,2021,vi+246p,26×18 cm,2,915円(SGCライブラリ-167)[専門・大学院向]ISBN 978-4-7819-1510-4
紹介者:堤 康雅(関西学院大理)
本書は超伝導の平均場理論の教科書である.超伝導に関する多くの教科書との違いは構成にはっきりと表れているので,いきなりではあるが概観しておきたい.まず1章から5章で,熱・統計力学の復習と本書の理解に必要な多体系の量子論の道具を準備する.6章で引力ポテンシャル下でのクーパー対形成と状態密度の関連を示し,7章でクーパー対凝縮の基底状態を実空間で表現したBCS波動関数を導入して,基底状態からの準粒子励起を記述するボゴリュボフ-ドジェンヌ(Bogoliubov-de Gennes,BdG)方程式を導いている.その後の8章で,一様なs波超伝導にBdG方程式を適用することでBCS理論の結果が説明されている.電荷の超流動性やマイスナー効果(9章),外部摂動への応答など(10,11章)もBdG方程式に基づいて示される.13章では,超伝導平均場理論をグリーン関数を用いて記述したゴルコフ方程式と,ゴルコフ方程式を準古典近似することで得られるアイレンバーガー方程式の導出を行い,磁束量子渦への適用なども14章,15章で紹介される.
上記の構成から明らかなように,本書の大きな特徴は,場の演算子で記述した実空間のBCS波動関数と,超伝導平均場理論の基礎方程式となるBdG方程式を基にして,超伝導の特性について一貫した議論を行っていることである.基礎方程式から導かれる一粒子密度行列から,超伝導電流やマイスナー効果が自然に得られている.また,多くの超伝導の教科書で現象論として導入されているギンツブルグ-ランダウ方程式もアイレンバーガー方程式を小さなペア・ポテンシャル(超伝導ギャップ関数)に対して展開することで微視的に導出している.
本書の理解に必要な多体系の量子論の手法は,熱・統計力学の復習と合わせて,本書の1/ 3程度の分量を使ってしっかりと導入されている.式変形についても丁寧に解説されているので,演算子の交換など煩雑な計算を確認する根気は必要となるが,十分に追うことができるだろう.また,線形応答理論や松原グリーン関数を使うところでは,これらが簡潔に紹介されており,他の教科書を参照せずとも最後まで読み通すことができる.
評者の研究手法とも関連するので特筆しておきたいのは,ゴルコフ方程式を準古典近似したアイレンバーガー方程式について詳細な解説がされていることである.準古典近似はアンドレーエフ近似と同等の近似である.アンドレーエフ近似が超伝導体と正常金属の接合を理解するのに便利なように,準古典近似は超伝導体中の磁束量子渦を研究する際に非常に有用である.しかしながら,準古典近似を扱っている日本語の教科書はこれまでほとんどなかった.さらに,アイレンバーガー方程式は数値計算を行ううえでも特殊な手法が必要であり,独学で数値計算を身につけるのは敷居が高かったと思う(評者は学生時の所属研究室で使用されていたので学修することができた).本書では,s波超伝導体中の孤立した量子渦を例として,アイレンバーガー方程式を数値計算として実装するための式変形や,数値計算上のテクニカルな点についても解説されている.本書のレシピに従えば,独学でも数値計算を行えるようになるだろう.
本書は初めて超伝導を勉強する(物性分野に限らない)理論系の学生や,他の教科書で超伝導を勉強したが現象論による説明に満足していない読者にお勧めである.また,準古典近似を用いて超伝導の理論研究の幅を広げたいという研究者にも有益だろう.
(2021年8月20日原稿受付)
量子コンピュータによる量子化学計算入門
杉﨑研司
講談社,東京,2020,viii+151p,21×15 cm,4,180円[専門・大学院向]ISBN 978-4-06-521827-3
紹介者:吉岡信行(東大院工)
近年の量子技術の発展は著しく,特に回路型量子計算に関しては,ランダム量子回路サンプリングによる量子超越性を実現するまでに成熟してきた.十分に成熟した量子コンピュータの活用先として提案されている分野は,機械学習・金融・物理シミュレーションなど様々であるが,最も注目されているものの一つが,量子化学計算である.本書「量子コンピュータによる量子化学計算入門」は,量子化学分野において,量子コンピュータが達成すると期待されるブレイクスルーを,丹念に紐解くことを目的に執筆されたものである.筆者自身も「まえがき」にて触れているように,大学の講義で習う初歩的な量子化学(もしくは量子力学)の知識さえあれば,十分に読み進めていくことができる内容になっている.アルゴリズムを理解する王道はそれを実装することであるから,意欲のある読者は本書を座右に置き,Cirq・Qiskit・Qulacsなどの量子回路シミュレータにて,実装を進めていくことをお勧めしたい.
本書では,量子化学計算と回路型量子計算の基礎がコンパクトかつ濃密に記述されたのち,近未来および誤り耐性量子コンピュータによる計算アルゴリズムが紹介される.誤り耐性量子コンピュータによる量子位相推定アルゴリズムを扱う第4章は,アルゴリズム全体を見通し良く記述しているだけでなく,著者自身による期待と熱意が端緒から感じとれ,読み応えたっぷりである.量子回路の構築法まで含めて丁寧に記述されているため,具体的な実装までイメージが膨らむことは間違いないだろう.
第5章では,量子誤り耐性を持たないデバイスによる量子変分計算,つまりVariational Quantum Eigensolver(VQE)法が議論されている.VQE法を用いた量子化学計算は,今まさに日進月歩で進展している研究分野であるにもかかわらず,本書では,非常に俯瞰的な視座から,現状と今後の問題意識が述べられている.特に第6,7章では,擬縮退(強相関)系やHartree-Fock波動関数が求まらないケースを始めとして,量子コンピュータによる量子化学計算が抱える課題が明文化されているため,最前線の臨場感が感じられると同時に,新規参入を目指す者にとって一つの大きな指針となるだろう.
本書の特色の一つとして,発展的な話題をも,丁寧にかつ端的にまとめ上げている点が挙げられる.誤り抑制(誤り低減)や勾配消失問題(もしくはBarren Plateau問題),さらには量子ビット削減や対称性の活用などといった,実応用に必須のテクニックを余すところなく,それでいて議論の大筋を外れないように述べており,読者にとって,ありがたいことこの上ない構成になっている.この観点で,本書は,これから関連分野の研究を始めようとする大学院生・研究者にとっては必読の一冊になるとともに,(現時点では非常に少数の)専門家にとっても,分野を整理し新たなアイデアを得るきっかけとなるだろう.
(2021年8月22日原稿受付)
ニュートリノ物理学
白井淳平,末包文彦
朝倉書店,東京,2021,v+186p,21×15 cm,3,740円(現代物理学[展開シリーズ]1)[専門・大学院向]ISBN 978-4-254-13781-1
紹介者:横山将志(東大院理)
物質の最も基礎的な構成要素である素粒子の一種に,ニュートリノと呼ばれる粒子がある.電子の仲間であるが電荷を持たないため非常に反応しにくく,質量が非常に微小であるなど特徴的な性質を持つ.小柴昌俊先生と梶田隆章先生がニュートリノの研究でノーベル物理学賞を受賞されていることもあり,素粒子の中では知られている粒子だろう.とはいえ名前以外はよく知らず,もっと詳しいことを理解したいと思う方も多いのではないか.本稿で紹介する「ニュートリノ物理学」は,そのような人に最適の教科書かもしれない.
著者のお二人はニュートリノ実験の第一線で長年活躍してきた研究者であり,これまでにも素粒子物理に関する複数の著書・訳書がある.研究にも執筆にも経験豊富なお二人が,いよいよ専門のニュートリノ物理を日本語で解説したのが本書である.歴史的経緯から今後の展望まで多くのトピックが難解な記述を避けて手ごろな分量でまとめられており,この分野に興味を持つ学部生から大学院の初年度,あるいは他の分野を専門とする方々が概要をつかむのによいテキストと言えよう.
ニュートリノの研究は現代の素粒子物理学の主要なテーマのひとつとなっているほか,天文学や地球物理学など幅広い分野に関連を持つ.著者自身のまえがきにもある通り,そのすべてをカバーするのは実質不可能であり,また本書の想定する読者層には適当でない分量になるだろう.そこで本書では最初にニュートリノ研究の歴史を簡単に述べた後,主に著者の専門に近いテーマのいくつかについて説明する構成となっている.パウリによるニュートリノの存在の提案から標準模型の確立に至るまでの経緯をまとめた第1章は「ニュートリノ研究の歴史」と題されているが,ほぼ20世紀の素粒子物理の歴史そのものであり,その中でニュートリノが大きな役割を果たしてきたことが理解でき,この部分をじっくり読むだけでも得られるものが多いだろう.続く章ではニュートリノ振動,地球ニュートリノ測定による地球内部の熱源の解明,ニュートリノのマヨラナ性の検証など,現在の研究の最先端のトピックがそれぞれ取り上げられている.
特に,現代の素粒子物理の主要な研究テーマのひとつとなっているニュートリノ振動については最も多くのページが割かれている.ニュートリノには3種類あることが知られている.元々ある種類のニュートリノだったものが飛行中に別の種類に変わってしまう現象がニュートリノ振動である.ニュートリノ振動はニュートリノ質量の起源や宇宙の物質・反物質の非対称性の原因の解明にもつながると考えられており,その研究には日本で行われた実験が大きな役割を果たし続けている.その中のカムランド実験で中核的な役割を担い,ニュートリノ振動現象の確立に大きな貢献をした著者たちによる記述は読み応えがある内容となっている.
本文では数式は最小限に抑えられており,興味のある読者のために理論的な記述や定式化が第7章に付録としてまとめられている.ただし,この本だけで理論的な内容を理解することはおそらく難しく,他の教科書を参考にする必要があるだろう.また,平易な記述が心がけられているとはいえ,何の解説もなくラグランジアン密度が突如として現れたり,パリティとは何かの説明がずっと後になって出てきたりする.いずれも素粒子研究者にとっては自明のことであるが,本書で想定される読者は引っかかるところかもしれない.
と,あえて書評にあたり粗探しをしてみたものの,本書では全体を通じてそれぞれの研究の動機を歴史的な経緯から説明し,研究者の横顔や実験装置の解説も挟んで研究のイメージをつかみやすくする工夫がされている.また関連する研究の話題をも各所で巧みに取り入れ,幅広いテーマをコンパクトに提供しつつも読みやすいという難しい構成を見事に実現している.日本が世界の最先端をリードしている分野であるニュートリノの研究に関して,最先端の現状までをカバーした新しい教科書が現れたことを歓迎したい.
(2021年8月30日原稿受付)
単一光子と量子もつれ光子;量子光学と量子光技術の基礎
枝松圭一
共立出版,東京,2018,vii+155p,21×15 cm,本体2,000円(基本法則から読み解く物理学最前線19)[大学院向]ISBN 978-4-320-03539-3
紹介者:山本 俊(阪大院基礎工/阪大QIQB)
本書は「基本法則から読み解く物理学最前線」の19巻として執筆されており,主な読者として学部生や大学院生のような初学者を想定している.量子力学を学習したことがあれば,スムーズに理解することができ,専門外の研究者の入門書としても利用できる.本書の引用文献を見るだけでも,これに類する和書が少ないことが読者にもわかってもらえると思う.著者が最前線で研究を進めてきた単一光子や量子もつれ光子などの量子情報技術を理解できるように,より現代的な視点からエッセンスを抽出し,短い紙面で量子光学の基礎から最先端への入門を手助けする内容となっている.
第2章では電磁気学における電磁波,第3章では調和振動子の量子力学の復習があり,本書の理解のために,その他の書籍を見直す必要がないように工夫されている.特に,本シリーズが目指す「大学初年度で学ぶ程度の物理で理解できる」を実現するためにコンパクトにまとめられている.第4章では,量子化された電磁場の様々な状態を紹介しながら,単一モードだけではなく,多モードの状態の取り扱いや純粋状態だけでなく密度演算子を用いた混合状態の表記に関しても紹介しており,量子もつれ光子対の性質やその評価法を理解するための基本事項の導入となっている.その後の章は,現実の量子光学実験に対応させて説明が行われている.第5章では,量子光学に必須の干渉系が登場する.古典論と量子論の違いは干渉系によって顕著に見ることができる.また,量子情報技術では干渉系は状態操作や測定手段として用いられる.それらの基本事項がまとめられている.第6章では,単一光子の発生法からその確認法,単一光子を利用して観測できる特徴的な現象である「遅延選択実験」,「量子消去」,「量子非破壊測定」,「弱測定」等々が紹介されている.第7章と第8章では,光子対発生法と量子もつれ光子対発生法およびそれらの測定・評価方法,さらには量子もつれ光子対を利用した量子テレポーテーション等が説明されている.短い紙面で,量子もつれ(エンタングルメント)の定量化など,量子情報理論を必要とするところまで触れるなど,挑戦的な試みがなされている.これらに興味のある読者は引用文献などを参考にさらに理解を深められることをお勧めする.
光の量子論として始まった量子光学はいつの間にか量子力学を実証する代表的なプラットフォームとなり,多くの典型的な実験アイデアを生み出し続けている.そのアイデアはすべての振動子に適用可能であり,すべての物理学に波及する.一方で,大学の理学部や工学部に量子光学や量子情報を専門とする講座が設置されていることは稀である.数十年後を担う現代の若者に,本書がその穴埋めとなることを期待する.
(2021年9月10日原稿受付)
トポロジカル物質とは何か 最新・物質科学入門
長谷川修司
講談社,東京,2021,302p,18×11 cm,1,210円(ブルーバックス-B2162)[一般向]ISBN 978-4-06-522267-6
紹介者:有賀哲也(京大院理)
大学でアウトリーチ活動のお世話をしていると,多種多様な分野の方々から専門の研究のお話を伺う機会が多い.どの分野の方も,門外漢にもついていけるように,比喩や研究上の逸話も交えながら上手に話される.全くの私見だが,そんな折に物理の方からは「ブルーバックス的な説明ですが」という言葉を聞くことが少なくない気がする.謙遜されるニュアンスで使われているようで,それは,物理学においてはとりわけ用語の選択や表現の厳密さが大切にされることの現れだろうと思っている.
さて,そのブルーバックスの新刊の紹介である.主題は,本誌でも近年何度も取り上げられているトポロジカル物質.理科オタクの中高生を引きつけるには格好のパワーワードであるが,その意味するところを,「ブルーバックス的」な言葉だけを使ってどのように伝えるのか.この難題にチャレンジした著者は東大理物の教授.専門は表面物理学.
2005年,強いスピン軌道相互作用のために結晶内部は絶縁体となる一方で,表面には純スピン流が流れるという,それまで誰も知らなかった奇妙な性質をもつ物質の存在がチャールズ・ケインらにより予想され,トポロジカル絶縁体と名付けられた.この予想はわずか2年後に実証されることになる.
本書において,著者はまず物質科学分野のノーベル賞受賞者の業績を辿りつつ,原子,電子の実在から,金属,半導体,さらに超伝導,量子ホール効果を経てトポロジカル絶縁体に至るまで,物質科学とりわけ固体物理の歴史とその成果を軽妙に語る.続いて,運動量空間の概念を紹介し,それに基づいて絶縁体,半導体,金属の違いを語り,さらに,量子ホール効果を説明する.ここまでが第一部で,総頁数のほぼ半分を使っている.
思い切った単純化はされているものの,比喩だけでごまかそうとしない姿勢は一貫している.物理とユーモアが同居する文体の効用もあって,このあたりまでは中高生でも読めるであろうし,それにより得るものも多いと思う.グラフェンのπ電子の特異性を説明するために,自動車の飛ばし過ぎがいかに燃費を悪くするかを滔々と語って脱線して見せるなど,読者の息抜きの工夫にも富んでいる.
後半に入ると,トポロジカル物質へ向かう準備として,まずスピン軌道相互作用を説明する.空間反転対称性と時間反転対称性を説明し,これらの対称性が破れることで結晶中の電子状態にどのような影響が生じるかを考えさせる.仮想磁場の概念からスピン軌道相互作用を導き,ビチュコフ=ラシュバ効果,ドレッセルハウス効果を解説するくだりは,ここまで挫折せずに来られた高校生には充分に得るものがあるのではないか.
最終盤,道具立てがすべて整ったところで,いよいよトポロジカル物質の登場である.紙数も残り少なくなり,著者の物理ギアは二段くらい上がる.ここは高校生にはかなり難しいと思う.物理系の学部生にぜひ読んでもらいたいところである.
本書の主題はトポロジカル物質であるが,それと並んで,固体物理の発展を辿る前半部も丁寧に書かれている.全体を通して著者の朗らかな声が聞こえてくるような好著.所属機関のアウトリーチ活動に駆り出される会員諸氏も少なくないと思うが,そういう皆さんにも参考になる一冊だと思う.
(2021年9月10日原稿受付)
物理学を志す人の量子力学
河辺哲次
裳華房,東京,2020,xi+312p,21×15 cm,3,520円[学部・大学院向]ISBN 978-4-7853-2271-7
紹介者:星野正光(上智大理工)
本書は,理工系大学の学部生を対象とした量子力学の入門書である.大変な名著から今日では漫画に至るまで量子力学に関する多くの書籍が出版される中,ユニークな構成で読みやすかったので紹介してみたい.
大学で最初に学ぶ力学や電磁気学と比べ,初学者にとって「わかった!」という実感が持ちにくく,どこかモヤモヤした気持ちや不可解さがつきまとう量子力学.本書はそれをどのように学び,そこから何を学ぶのかを,量子力学の世界像から理解することに主眼を置く.豊富な例題と章末問題,丁寧な解答・解説もまた理解をさらに深める助けとなる.所々に盛り込まれたNoteやTalkingには,行間を読むための補足や雑学的な知識も含まれ,初学者が理解しやすいよう工夫されている.
特に,第1章は他書と比べて少し特徴的である.まず,本書の主題となる量子力学の世界像を,いくつかの例を挙げ古典論との対応,量子力学的な視点や考え方をリテラシーとして解説している.ミクロな世界をいかにして理解するかが量子力学の魅力の一つであり,それを冒頭で伝えることは読者にとって本書の意図する全体像を俯瞰するうえで重要であり,興味深い始まり方である.
第2章から第10章は,いわゆる一般的な教科書と類似した構成である.前半では,お馴染みの光量子仮説から始まり,物質波への拡張,波動方程式の導出,波動関数の確率概念へと続く.後半は,1次元井戸型ポテンシャルの問題から3次元の水素原子内の束縛電子へと順を追って波動方程式の解法とその物理的意味を,実際に問題を解いて理解する,「使う」ことに特化した章立てである.特筆すべきは,第5章「量子力学の前提」で,コペンハーゲン解釈に基づいた前提条件と観測問題の概念から波動関数の性質を説明し,第6章「量子力学と古典力学との関係」では,エーレンフェストの定理から古典力学との対応,そしてハイゼンベルグの不確定性関係まで,一般に初学者には唐突ですぐには理解しづらい内容を,数学的な証明もうまく交えて,量子力学的な世界像の観点からイメージしやすく解説している.
第11章以降のブラケット記法,スピン,摂動論もまた他書で見かけるが,初学者だけでなく,すでに勉強した学生にとっても取っ付きづらく多少難解であることをよく耳にする.しかし,読み進めると最低限必要な知識と要点が自然と身に付くよう構成が工夫されているのも本書の特徴の一つである.
最終章では,量子もつれ状態や量子情報といった最近の話題が取り上げられている.一見すると入門書として詰め込みすぎと思われる点も否めないが,最後まで読み進めると,量子特有のこの現象を比較的平易な言葉で解説しつつ,タイトルにある「物理学を志す人」が上級コースへ進む「きっかけ」としてのメッセージが読み取れ,その必要性が理解できる.
以上,本書は大学でこれから量子力学を学ぶ理工学系学部生を対象とし,リテラシーから最近の話題まで,量子力学の世界像の一貫した立場から幅広い範囲を網羅した大変読みやすい入門書である.初学者に限らず,すでに学んだ学生,これから量子力学を講義する,あるいはすでに教えている教員,スタッフにとっても改めて読んでみて楽しめる一冊であると思う.
(2021年8月31日原稿受付)
探究する精神;職業としての基礎科学
大栗博司
幻冬舎,東京,2021,320p,18×11 cm,1,056円(幻冬舎新書-612)[大学院~一般向]ISBN 978-4-344-98614-5
紹介者:渡邉悠樹(東大院工)
本書は,著者である大栗博司氏の幼少期の生い立ちや,理論物理学者を志した経緯,そして研究者としての若手時代から現在に至るまでのキャリアを振り返る自伝的エッセイです.
大栗氏は場の量子論や弦理論の研究の第一線で活躍中のバリバリ現役の研究者であり,このような回顧録を書くにはまだ早いと辞退してきたそうですが,今回執筆に至った理由と本書に込められた思いが「はじめに」に述べられており,日ごろ読書をする習慣がない私も引きずり込まれてしまいました.
ご存知のように大栗氏は日米で様々な重要な地位に就かれて活躍されており,アメリカではカリフォルニア工科大学の冠教授やアスペン物理学センターの理事長,そして日本では東京大学カブリ数物連携宇宙研究機構(IPMU)の2代目機構長をされています.研究も世界的に高く評価されており,紫綬褒章やフンボルト賞といった数々の学術賞を受賞されています.このような輝かしい経歴をもつ先生は一体どのような幼少期を過ごされたのか,あわよくば自分の子育てに取り入れられるようなヒントはないか,などと期待しながら読み進めました.
本書第一部は小学校五年生の大栗氏が高層ビルから見える地平線までの距離から地球の半径を概算したという驚くべきエピソードから始まります.そしてこの話がサイモンズ財団のサイモンズさんとの面会でも役に立ったと言うところにスケールの違いを感じます.また,大栗氏の知識や考える力を育んだのが読書であったことが語られ,様々な本からの引用が本書の随所に登場します.また,大学学部までや大学院以降の各段階でどのような能力を意図して身につけるべきであるかについて考えがまとめられています.
第二部の若手研究者時代に関して特に印象に残ったのは,これほどの華々しい経歴をもつ先生ですら,必ずしも平坦な一本道を歩まれてきたわけではないという点です.場の量子論の発展に「遅れてきた」という引け目を感じたという話や,米国留学をしようか東大の助手になろうかという選択に悩んだ話,シカゴ大学助手へ転職したものの研究以外の業務量を前にすぐに京大数理研に移ったという失敗談や,どう転ぶかわからないが面白そうなテーマを前に機会を逃すまいと思い切って問題に飛び込んだという話が紹介されています.これらのエピソードは,日々不安を感じながらも前に進んでいる若手研究者の励みになると感じました.
第三部は大学や研究所の運営や資金調達を任される立場になって以降のお話です.カリフォルニア工科大学は現在世界的にも有数の物性及び量子情報グループを擁していますが,その背景に大栗氏の尽力があったというのは驚きでした.また,米国の大学の運営に長年携わりその内情を知っているものとしてIPMUの設立に関わったという経緯も印象的でした.第四部には,職業としての研究者の歴史を踏まえながら社会にとっての基礎科学の重要性が詳しく述べられています.これは研究者にとって至る場面で説明を求められる永遠のテーマですので,一度考えてみるきっかけになるかもしれません.
本書全体を通じて,哲学や歴史に関する機知に富む解説が随所にあり,物理学に留まらない大栗氏の知識の深さに驚かされます.また,業界の様々な有名人のエピソードが多数登場します.まさか「自分に自信がなく,常に他人と比べて不安になります」「誰もが私より賢く見えて,私は神経衰弱に陥ってしまいました」なんていうことをあの南部陽一郎先生が思っていたとは!
一般向けに書かれた本でありながら,研究者を志す学部生や大学院生が将来像を思い描いたり,私のような若手が研究者としての今後の生き方について広い視点から考え直すきっかけとしてもお薦めできる一冊です.(しかし,巨大実験施設での実験成果による小柴さんのノーベル賞受賞の報道に対し「国が豊かになるとはこういうことか」と感動されたという件は,国が単調に貧しくなっていく場面しか経験していない世代とはギャップが大きく感じられました.)
(2021年10月12日原稿受付)
図説表面分析ハンドブック
日本表面真空学会編
朝倉書店,東京,2021,558p,27×19 cm,19,800円[専門向]ISBN 978-4-254-20170-3
紹介者:水野清義*
表面科学の研究には様々な分析手法が駆使されており,その進化は目覚ましい.1994年に『表面分析図鑑』が出版されてから30年近くが経過し,表面分析を簡潔に網羅した新しい書籍の出版が渇望されていたと思う.本書はその待望の一冊である.『表面分析図鑑』で取り上げられた分析法が69項目であったのに対して,本書ではその2倍近くの121項目の手法が取り上げられている.また,『表面分析図鑑』は各項目を原則見開き2ページとしてコンパクトに要点を伝えることを特徴としていた.これに対して,本書では各項目6ページ程度となり,総ページ数が157ページから550ページへと大幅に増加した.このため,本が分厚くなり価格も高くなったというデメリットはあるが,柔軟な分量としたことにより,必要な事柄をわかりやすく記載しやすくなったのではないかと思う.原理が図入りで簡潔に説明されているとともに,複数の適用例が付属していて,各分析手法の特徴を理解しやすいように工夫されており,研究室における輪読など,教科書的な利用も有効であり,研究室に一冊は常備したい.
本書は「日本表面科学会」と「日本真空学会」が合併してできた「日本表面真空学会」による編集である.『表面分析図鑑』と比較して,執筆者の分野が広がったため,より幅広い読者に興味を持ってもらえるハンドブックになっている.なかでも,電子顕微鏡関連の記載が充実したとともに,大気中・準大気中・液中でその場観察できる手法の紹介が大幅に増加した.また,高い時間分解能やエネルギー分解能を持つ手法,原子・分子1個の状態を明らかにできる手法,動作中の状態を調べることができる手法など,最先端の研究例が数多く記載されており感銘を受けた.さらに,解析法を追加したことも特筆すべき特徴である.
『表面分析図鑑』では構造・形態・組成・電子状態に分類して分析法を紹介していた.この分類は,原理に基づいたよい方法であるが,複数の分類に該当する分析法が多いため,分類が困難であるとともに,どの分類の中に目的の分析法が含まれているか探しにくいという欠点があった.これに対して,本書ではプローブにより電子・粒子・光・探針・その他に分類している.これにより,目的の分析法を見つけやすくなったとともに,類似の手法が近くのページにあるため,併せて興味を深めることにつながると期待できる.とはいえ,この分類法も万能ではない.原理が類似している手法はまとまっていた方がよいが,EDS関係は1.2節,3.2節,4.4節に分散している.関係する項目を相互に参照するよう配慮してあるが,不完全なので,さらに徹底するとよいと思った.一方,電子回折や磁気計測はまとめてあってわかりやすい.陽電子回折は1.5節の電子回折にまとめた方がわかりやすかったのではないかという印象を持った.逆に,例えば26.7節のXMCDは磁気計測にまとめていてわかりやすいと思う一方で,3章の光の章に入っていないのでプローブによる分類としては探しにくいという欠点もある.他にも,ペニングイオン化電子分光法は励起ヘリウム原子がプローブなので,粒子に分類した方がよかったのではないか,など,若干の違和感が生じる分類もある.いずれにしても,分類が目的ではなく,本書の構成は理にかなっている.
本書は,それぞれの項目を単独で読んでもわかるように工夫されているが,基本原理からの説明が必要な項目と応用的な項目が混在しており,内容の整理が難しかったであろうことが容易に想像できる.この点,12.1節の「非線形分光法」は12.2から12.5節までの序章としての役割も果たしており,12章全体がわかりやすくまとめてある.一方,23章の原子間力顕微鏡は,23.1節における基本的な測定モードの説明などが不十分と感じた.発展が著しい原子間力顕微鏡の基本的な説明と適用例を合わせて6ページでまとめるのは無理があったのではないかと思う.23.1節は例外として,23章の基礎的な説明をする部分を増やしてもよかったのではないか.例えば,23.11節は,原子間力顕微鏡の基本原理が他の項目に記載されていることを前提に書かれている.このあたりの調整は改訂版に期待したい.個人的には,SPA-LEED,逆光電子分光,二光子光電子分光の項目がないことを寂しく感じた.特に,二光子光電子分光については16.6節において,他の項目に載っているという記述があるが,ほとんど記載がない.時代と共にそれぞれの分析法の主たる研究者が変化していくので,どの研究手法を取り上げるか,編集者や執筆者のご判断に委ねたい.
表面分析においては,必要とする表面深さの分解能(表面最上層,数原子層,1 nm程度,1 μm程度など),測定雰囲気(超高真空,高真空,大気圧,液中,界面など),試料の状態(単結晶である必要性,表面が原子レベルで清浄である必要性,ドメインのサイズなど),非破壊である必要性(その場合,分解能は原子レベルか1 nm程度かなど)を理解して装置を使用する必要がある.本書ではこれらの点に留意した記載をしている項目が多いが,さらに徹底するとよいと思った.また,表面分析に詳しくない研究者や学生のために,引用文献とは別に,原理などの詳細が載っている書籍(できれば日本語)を明示するとよいのではないか.多くの項目では末尾の引用文献に載せているが,原著論文的な引用文献の記載をしている項目もあり,初心者には若干不親切な印象を受けた.数十年前は,表面分析を応用研究の評価に利用しようとすると,両者の間に大きな溝(例えば,表面分析では単結晶試料が必要なのに対して,実際の触媒は微粒子であるなど)があり,適用できないケースが多かった.しかし,最近はその溝が埋まってきており,表面分析がさまざまな分野の応用研究にも適用できるようになってきた.本書は,どの表面分析が適用可能か判断する材料として切望された優れた内容となっている.このハンドブックを起点として,必要に応じて専門家に測定可能かどうかなどの詳細を相談できるようになることを願う.
最後に,このハンドブックの刊行により,表面分析がさらに普及・発展していくことを期待している.30年前と比較すると,インターネットの普及により冊子体よりもネットでの検索が増えている.しかし,本書のように,専門家が丁寧に書いた冊子体に圧倒的な価値があることは明らかである.特に,専門的な内容に関してはネットの検索は役に立たないことが多い.今後も可能な限り頻繁に改訂作業を行って,中身が古くなってしまわないようにして欲しい.編集にあたった先生方のご苦労を想うとともに,見識の高さに敬意を表する.
(2021年11月7日原稿受付)
*九州大学名誉教授
素粒子論の始まり;湯川・朝永・坂田を中心に
亀淵 迪
日本評論社,東京,2018,viii+296p,20×14 cm,2,750円[専門・大学院向]ISBN 978-4-535-78833-6
紹介者:久野純治(名大理KMI)
著者の亀淵迪氏は1950年に名古屋大学理学部を卒業後,同大学院理学研究科に進学,坂田昌一氏のE研(素粒子論研究室)に所属し,場の量子論の研究を行った.朝永振一郎氏のいわゆる「朝永ゼミ」にも顔を出しており,当時重要課題の一つであった場の量子論のくりこみについて取り組んだ.また,名古屋大で学士取得したのち,量子力学を産んだコペンハーゲン大学ニールスボーア研究所で研究を行っている.日本の素粒子論研究,量子力学の誕生の現場で,見て聞いて話した一研究者の自伝的エッセイである.
本著は二部構成になっており,第一部は「くりこみ理論誕生のころ」と題し,日本の素粒子論研究の始まりについてである.哲学をする湯川秀樹のマルの理論,現実主義の坂田のC中間子理論に刺激され,苦悩の中で進化していった朝永,この三名の誰が欠けても日本でくりこみ理論は誕生しなかった.また,戦後1946年に湯川によって刊行が始まったProgress of Theoretical Physics(現Progress of Theoretical and Experimental Physics(PTEP))をなくして,Tomonagaの業績は世界に認知されることはなかった.そして,終戦から1950年代にかけて,新しい学問である素粒子論は日本で黄金時代が出現した.研究者は皆若く,自由と平等と連帯の精神を持つコミュニティ(素粒子論グループ)が作られていった.湯川・朝永・坂田の三巨人を間近に見ながら,彼らとともに直接くりこみ理論の問題に取り組んでいた著者が,素粒子理論研究最前線で彼らが何に悩み,誰とどう議論し,いかに物理の真理に迫っていったかを,生々しくもノスタルジックに証言している.
第二部は「量子物理学の創始者たち」である.仁科芳雄氏によって日本にもたらされ,素粒子論グループの精神にもなったコペンハーゲン精神(著者曰く「研究者は皆対等である,研究は他の何者よりも優先する,研究上最も大切なことは他人との徹底的な討論である,研究は自分に適した方法でやればよい,よく学びよく遊べ」)は,人間ボーアから来ており,シュレーディンガーがニールスボーア研究所に来たときのボーアとハイゼンベルグとの大激論ではその精神が見て取れる.また,湯川,朝永,坂田の三名の研究者としてのスタイルを考察している.第二部も秀逸である.
私は著者が学生時代に所属した名古屋大学E研に席を置くが,不勉強で日本の素粒子論研究の歴史をあまり知らなかった.今年,同研究室で学生時代を送った益川敏英氏が亡くなった.2008年の小林・益川・南部3名のノーベル賞物理学賞受賞へと繋がる日本の素粒子論研究の始まりをこの本で生き生きと知ることができたことに感謝している.素粒子論研究者にはもちろん,多くの物理を研究する人に勧めたい一冊である.
(2021年11月8日原稿受付)
現代量子力学入門
井田大輔
朝倉書店,東京,2021,v+206p,21×15 cm,3,630円[学部向]ISBN 978-4-254-13140-6
紹介者:高橋和孝(東工大)
まえがきに,「シュレーディンガー方程式を解かない話で,誰もが疑問に思うけれど,答えるのが難しそうなものをいくつか選びました.量子力学のルール説明と,その周辺のことが中心になっています」とあります.本書はまさにそのような教科書で,量子力学の理論構造をいくつかの話題を扱いながら捉えていくものです.選択される話題は系統的ではないですが,それぞれの記述はしっかりとしており,通常の理解を深めることができるものとなっています.
入門とありますが,量子力学の知識をある程度持っていることが想定されているようです.ただし,前半の章に量子力学の基本原理がきちんと提示されています.序章に,「ただのゲームの説明だと思っておくとよいです.ゲームの主な目的は,自然現象を理解するための方法を見つけることにあります」とあります.量子力学は確かにそのような理解がしやすい体系です.初学者がこの本を読んで量子力学を身につけたらどうなるでしょう,とも思うのですが,基本的には通常の記述に満足できない読者を対象としているように思います.先入観を排したところで理解を積み重ねられるように構成されている点が本書の最大の特徴です.基本原理から最短の経路でさまざまな性質を正しく理解できるようになっています.全貌を把握しながら理解するというよりも,局所的な理解を積み重ねていくことでいつしか知らない風景が見えるようになっている,というタイプの教科書です.内容は数学的な記述が多く,応用例も決して豊富ではないので,難しく感じる読者も多いと思いますが,上述したようなことに気をつければ流れを理解することは難しくありません.
内容をおおまかに紹介すると,量子力学の基本原理について,量子状態の性質について(量子トモグラフィー,エンタングルメント等),対称性に関する話題(スピン,超選択則等),量子力学の原理に関わる話題(隠れた変数理論,多世界解釈等)という構成です.それぞれの話題は基本的に独立ですので,好みに応じて取捨選択することができます.第3章以外は状態空間次元が有限の場合の問題をとりあげています.最後の章は量子コンピューターですが,ショーアのアルゴリズムの紹介にとどめられています.上述したように,全体的なテーマの選択は系統的ではないです.それぞれの話題を純粋に楽しむのが正しい読み方だと思います.個人的には,無限次元空間のやっかいさを丁寧に説明した第3章や,複素ユークリッド・ベクトル空間の構造からボルン則を与えるグリーソンの定理(第9章)はとても面白く思いました.事実として知っていることでも,なるほどそうやって一般的に証明できるのか,と思うことが多々ありました.
量子力学と名のつく教科書は世の中に多々ありますが,本書はその中でもきわめてユニークなものです.他と比較するようなものではないでしょう.
(2021年11月22日原稿受付)
ARPESで探る固体の電子構造;高温超伝導体からトポロジカル絶縁体
高橋 隆,佐藤宇史
共立出版,東京,2017,vii+101p,21×15 cm,2,200円(基本法則から読み解く物理学最前線16)[専門・大学院向]ISBN 978-4-320-03536-2
紹介者:芝田悟朗(原子力機構)
光電子分光は,物質に一定以上のエネルギーの光を照射した際に電子が放出される光電効果を利用した実験手法である.照射した光(光子)のエネルギーと放出された電子の運動エネルギーの差から,物質中における電子のエネルギー準位を求めることができる.さらに,光電子の運動エネルギーだけでなく放出角度も測定することで,固体中の電子の運動量を推定することも可能である.これにより,固体中の電子のエネルギーと運動量の間の関係,すなわちバンド分散が直接観測できることになる.この手法が本書のテーマである角度分解光電子分光(ARPES)である.バンド分散は固体の物性を左右する最も基本的な情報であり,これを直接観測できるARPESは物性研究における極めて有力な実験手段の一つとして広く用いられてきた.
本書は,このARPESを用いた最近の物性研究の動向を広く紹介するものである.本書は6つの章から成り,第1章が概観,第2章が光電子分光の原理および実験装置の解説,第3章以降がARPESを用いた研究トピックの紹介,という形をとっている.3章以降の各章は興味のあるテーマを拾いながら読むことも可能である.第2章の実験原理は一般的な内容であるが,近年発展のめざましいスピン分解光電子分光についても説明されている.第3章と第4章は,それぞれ1986年,2008年に発見された銅酸化物高温超伝導体,鉄系高温超伝導体に関するものである.ARPESにより超伝導ギャップや擬ギャップを直接観測できることが明快な図とともに示されており,また,超伝導ギャップの対称性と超伝導発現機構がどのように関係しているのか,未解決問題である擬ギャップの起源についてどのような説が提唱されているか,といった議論までが詳細に説明されている.第5章はグラフェン,第6章はトポロジカル絶縁体をはじめとする各種のトポロジカル物質がテーマである.いずれの系も,ディラックコーンに代表される特徴的な形状のバンド分散を持ち,ARPESがそれを捉える重要な実験手法として利用されてきたことが伺えるようになっている.例えばグラフェンに関しては,自立した(基板と化学結合していない)単層グラフェンが作製された証拠がARPESによって見出されたことが紹介されており,またトポロジカル絶縁体に関しては,元素置換や界面の制御によってディラックコーンの形状(ギャップの大きさやフェルミ準位の位置など)がどのように制御されるかを系統的に明らかにした結果が述べられている.また,第2章で紹介されたスピン分解光電子分光の手法がこの6章につながっており,ディラックコーンが理論から予測されるヘリカルスピン構造を持つことが明瞭なデータとともに示されている.
著者の一人である髙橋隆氏の前著『光電子固体物性』(朝倉書店,2011)と比較すると,前著ではバンド理論や光電子分光の原理・実験装置の説明に重きが置かれていたのに対し,本書では光電子分光が実際の物性研究にどのように役立てられているかを紹介することが主眼となっている.2章の一部を除いて全体的に数式の利用はほとんどなく,その意味では学生にとっても読みやすい本であると言える.実際,本シリーズは「大学初年度で学ぶ程度の物理の知識をもとに,基本法則から始めて,物理概念の発展を追いながら最新の研究成果を読み解」くことを目的としており(本書刊行の言葉より),この目的は十二分に達成されていると感じる.かと言って,決して物理的内容が浅いわけではなく,実験結果の解釈や理論との関連性に関してはかなり踏み込んで書かれている.その意味で,研究者の方が新たな研究テーマを始める際に手早くこれまでの研究の全体像を掴むことにも役立つと思われる.副題にもある通り,本書では近年の物性物理の中心的テーマである高温超伝導体・トポロジカル物質といった分野を広く網羅しており,光電子分光を専門とする研究室においてはもちろんのこと,物性物理の多種多様な分野の研究者・学生にとっても非常に有益な一冊になると信じている.
(2021年11月20日原稿受付)
細胞の理論生物学;ダイナミクスの視点から
金子邦彦,澤井 哲,高木拓明,古澤 力
東京大学出版会,東京,2020,x+344p,21×15 cm,4,180円[学部向]ISBN 978-4-13-062621-7
紹介者:平岩徹也(シンガポール国立大)
物理学と生物学の垣根はますます低くなってきている.本稿で紹介する「細胞の理論生物学」はその現状において,物理の観点から生物を理解するのに有用な理論を解説する書である.主題には広く「理論」生物学とあるが,本書では主に力学系と揺らぎの統計力学の理論が展開されている.それが副題の「ダイナミクスの視点から」の意味であろう.例えば状態空間,アトラクター,リミットサイクルとカオス,反応ネットワーク,反応拡散系,ブラウン運動理論と確率微分方程式,情報理論など多岐にわたる概念や理論が説明され,生命現象のモデル化におけるその適用例が示されている.学部生には馴染みのない内容も多いかもしれないが,解説は平易で,大学教養レベルの数理を身につけていれば理解できると思われる.
全体的に(評者にとっては)ワクワクしながら読み進められたが,中でも第1章と第9章は格別のものを感じた.第1章「生物学のための力学系入門」は力学系の入門的内容を直感的に解説している.わずか40頁に上手くまとめられている上で,文章の端々や例示において,生き物の系にどのように適用されるかが述べられている.また1.3節,1.13節,1.14節はそれぞれ「状態の選択とモデル化にあたって」「細胞生物実験で力学系描像を調べる」「アトラクターの生物学的意義」と題して力学系の考えが細胞の話とどう繋がるかを議論している.評者も読んで理解が深まると同時に著者らの考え方を感じられた気がした.第9章「生命の起源と複製系の数理」は生命の起源(として可能性のあるもの)は何か,という広く興味を抱かれる問いへの理論研究例を解説している.この章は第2章以降の他の章と少し趣が異なる.まず大きな問いが与えられ,それについて詳しく掘り下げられ,次に,歴史的に重要な実験(9.3節「Spiegelmanの進化実験」)が説明される.その背景に基づき,生命の起源という問いに対する一つの数理(9.4節「自己複製系の数理モデル化」)が説明される.そしてその後の節で,その数理モデルの発展や相補的な理論などの発展的内容が展開される.この流れは見事で,学術的な好奇心に揺り動かされ読み進むのが止まらないほどであった.
ポジティブな面以外も評することも許していただきたい.序文で「本書と相補的な教科書としては『細胞の分子生物学』『細胞の物理生物学』(評者の知る限りそれぞれ細胞・分子生物学と生物物理を勉強する際に使われる標準的かつ網羅的な教科書)がある....」と書かれているので,本書はそれらに比するものを目指しているのだと思う.ただ,その2冊は内容が膨大で網羅的に広範な分野をカバーする教科書である.対して本書は,頁数の限りのためだろうか,数理の技術に関しては上述の教科書に書かれていない内容が広くカバーされている一方,生き物や細胞に関わる内容は網羅されていないように思う.例えば,細胞や組織の力学の話はほとんど書かれていないが,そこにもダイナミクスに関わる話は少なくない.本書を読んだ学生が,これが理論生物学の全貌なのだと思ってしまう(ダイナミクスの視点から,だけだとしても)のは惜しい.
ポジティブな面もそうでない面も評したが,学生への紹介の仕方に気をつければ,総じて良著だと思う.序論で著者らが述べる,「生物に興味をもち,その論理を理解したい」と目指す方々への書になれば,という目的は達成されていると思う.また,本書で扱われている内容を1冊でカバーする他の和書は思い当たらない.学生でもシニアな研究者でも,物理・数理の基礎を身につけながら生き物に興味をもち始めた方々には一読の価値のある書ではなかろうか.多くの方々にとって本書が理論生物学への興味を深めるきっかけになることを期待する.
(2022年1月5日原稿受付)
銀河団
北山 哲
日本評論社,東京,2020,iv+248p,22×16 cm,本体3,200円(新天文学ライブラリー第7巻)[大学院・学部向]ISBN 978-4-535-60746-0
紹介者:秋山正幸(東北大理)
銀河の集団でありダークマターや高温プラズマの塊でもある銀河団は,宇宙の中で最大の大きさをもつ「天体」である.著者がその重要性を「宇宙論と天体物理学の交差点」と表現している通り,銀河団は宇宙全体の枠組みを反映した性質と内部にもつ銀河や超大質量ブラックホールの影響を反映した性質をあわせもち,ユニークな物理の実験場となっている.
宇宙最大の天体である銀河団が形成された歴史は,宇宙の大規模構造の形成の歴史そのものである.冷たいダークマターモデルに基づけば,銀河団の統計は宇宙の中の構造形成がどれだけ成熟しているかのよい指標と位置づけられる.構造形成の成熟度はダークマターの存在量やダークエネルギーによる宇宙膨張の加速の影響を反映する.宇宙のはじまりから現在にいたる銀河団の統計は,構造形成の成熟度を宇宙のはじまりからの時間の関数として与えるユニークな測定量であり,ダークマターやダークエネルギーの性質にせまる重要なプローブである.幸い,銀河団の形成過程は銀河と比べるとバリオンの物理過程の影響は小さく,物理の基礎原理に基づいた扱いでよく記述される.本書の第2章に簡潔に説明されている.
銀河団の統計を行うには電磁波による測定が必要である.また銀河団の天球面上での個数密度が低いことから,広領域の観測が要求される.広領域の天球の探査は近年の検出器の多素子化により急激に進展を遂げており,近い将来にも新しい広視野探査装置の導入でさらに発展が見込まれる.すばる望遠鏡の超広視野観測装置をはじめとする,これからの観測的な進展への期待は本書の最後の節にまとめられているのでぜひ参照してもらいたい.
銀河団の統計を行う際の基礎となる放射過程は第3章に丁寧にまとめられている.電磁気の放射やプラズマ物理で現れた様々な物理過程が銀河団の放射において実際にどのように見られるかがわかる.また直接の放射だけでなく,宇宙最大の高温プラズマの塊は,逆コンプトン散乱によって我々が測定する宇宙背景放射のスペクトルの形にも影響を与える.このスニヤエフ-ゼルドビッチ効果と呼ばれる効果が見られる領域を電波波長域で探査することでも銀河団の統計が可能である.
最大の質量をもつ天体である銀河団では背景の天体に対する重力レンズ効果も重要となり,本書の第4章に詳しく説明されている.すばる望遠鏡の超広視野カメラによる測定は,弱い重力レンズ効果を活用して,個別の銀河団の内部の質量分布や銀河団の統計において世界をリードする成果を生み出してきた.
実は銀河団の形成過程を理解することの難しさが見えてくるのはこれからかもしれない.上ではその形成過程はモデル化しやすいと書いたが,これまでのところ実際にはその複雑な構造や形成過程が十分に見えていなかっただけかもしれない.XMMニュートン衛星やチャンドラ衛星によるX線観測では,銀河団が衝突する際にダークマターから取り残される高温ガスの様子や,中心の銀河の超大質量ブラックホールから噴き出すジェットにより高温ガス中にさざ波が立ち加熱される様子も捉えられている.このように見えてきた内部構造や形成過程の複雑さを定量的に理解する上で欠けている測定量は,高温ガスの運動の様子である.高温ガス内部の乱流としての運動や塊としての運動は形成過程や高い温度が維持される過程を理解する上で重要である.高エネルギー分解能のX線観測によって高温ガスの運動の様子をはじめて明らかにすると期待されたひとみ衛星は,本格観測の前に停止してしまったが,ペルセウス座銀河団の試験観測の結果では予想よりも小さい乱流速度が得られている.2022年に打ち上げが予定されているXRISM衛星によって,ついに高温ガスの運動の様子が系統的に解きあかされると期待される.
このように銀河団の研究は今後10年を見ても様々なホットな研究課題にあふれている.本書では銀河団に関わる物理過程が大学学部レベルの物理と数学で丁寧に記述されており,これから銀河団の研究に取り組もうとする大学生や宇宙論や銀河の研究において銀河団の基礎物理を押さえておきたい大学院生のよい教科書となる.私の知る限りでは,銀河団だけに焦点を当てた教科書はこれまでになく,本書はこれから出てくる銀河団の様々な観測成果を理解する上でよい道しるべとなるだろう.
(2021年10月18日原稿受付)
超伝導接合の物理
田仲由喜夫
名古屋大学出版会,名古屋,2021,ix+344p,22×16 cm,6,380円[専門・大学院向]ISBN 978-4-8158-1028-3
紹介者:正木祐輔(東北大院工)
本書は超伝導状態の物理の中でも接合系に現れる豊かな現象を解説する教科書である.接合系と聞くとマニアックな印象を与えかねないが,例えば超伝導の代表的な特徴であるジョセフソン効果の舞台が超伝導-絶縁体薄膜-超伝導からなる接合系であり,固体物理の教科書にも載っている基本的なテーマである.また近年よく耳にするトポロジカル超伝導体のトポロジカルな端状態も超伝導体と真空との接合の間にできる束縛状態のことである.本書では異方的超伝導のジョセフソン効果や他の異なる接合系の設定で現れる超伝導状態の特徴の違いを微視的理論に基づいて解説している.接合系の物理を理解するうえで重要なキーワードはアンドレーエフ反射やアンドレーエフ束縛状態(ABS)である.アンドレーエフ反射は常伝導体から超伝導体に粒子を入射させると,その界面でホールとなって反射される現象であり,超伝導の教科書に載っていることもあるがその記述は多くの場合従来型のs波超伝導にとどまるように思う.著者は,この現象を様々な異方的超伝導体やトポロジカル超伝導体に適用することで,その超伝導特性を明らかにする提案を行ってきた.個別の超伝導対称性について膨大な研究報告が蓄積されているが,本書は様々な超伝導接合がよく整理されており,分野を俯瞰したり,要点を抑えるうえで適している.またこれらの研究の根幹にあるアンドレーエフ反射やABSの奥深さを堪能できる内容となっている.結論からいうと,他書にはないトピックと書き味を持った超伝導の教科書であり,特に下記の点で本書を薦めたいが,テクニカルな箇所もいくつかあるため,読み通すには根気がいるかもしれない.また,超伝導の基礎は別の本で学習してあることが望ましい,と思われる.
具体的に本書の特色を記していく.本書は大きく3つのパートからなる.パートⅠでは他書にもあるような超伝導の平均場理論,異方的超伝導のクーパー対について一通り説明がある.この辺りはこれ以降を読むための基礎のおさらいという程度に簡潔にまとまっており,メインに入る前に息切れしなくて良いと感じられた.パートⅠの最後では,従来型のs波超伝導でアンドレーエフ反射やABSについて説明がなされている.この部分は他の超伝導の教科書で出くわさなかった読者も必要な式を十分フォローし,パートⅡ以降を読むための基礎項目の理解は十分にできると考えられる.パートⅡでは,超伝導対称性に起因した豊かな接合系の物理が説明されており,本書の独自性が強く出ている部分である.具体的にはまず異方的超伝導の運動量に依存したペアポテンシャル由来の内的位相により,表面アンドレーエフ束縛状態(SABS)が存在可能となり新奇なジョセフソン効果やトンネル効果を導くことが説明される.特に,SABSは異常グリーン関数(ペア関数)の奇周波数成分の存在に対応しており,非一様系で一際その威力を発揮する準古典グリーン関数の説明と,それに基づいたトンネル効果のゼロバイアスピークと奇周波数成分の関連が議論されている.日本語で準古典理論を説明した教科書は少ない現状で,本書では平均自由行程の短い(ダーティ)極限で妥当なウサデル方程式とその適用まで説明がなされている点でも評者は本書を薦めたい.パートⅢでは,近年盛んに研究が行われているトポロジカル超伝導の話題を取り扱っている.SABSの形成はトポロジカル超伝導の特徴の一つであり,パートⅡまででみてきたSABSにトポロジカルな特徴付けができることが示されている.従来のトポロジカル系の教科書と異なり,絶縁体についてそれほど説明がなされていない代わりに著者が研究で扱ってきた超伝導体の模型を中心に,トポロジカルな端状態としての様々なSABSとその指数付けが丁寧に例証されているので,初学者でも十分理解できる内容であると思われる.また,本書には60ページを超える付録がついており,この付録も本書を読み進めるうえで効果的であったことを付記したい.本書の特色の一つとして,数式が多用されているが,特に最初の方を付録と併せて丁寧に数式をフォローして,その計算過程を手に馴染ませておくことで,後半の理解度が飛躍的に上がると思われる.
最後に,気になる点をあげるとしたら,一点は初学者に難しい箇所がいくつかあった.特に12.4-12.5はダーティ極限での常伝導体への近接効果の定式化を扱っており,本書の目玉箇所と思われるが,テクニカルな式展開を理解して読み進めるのは,かなり難しいと思われる.一方でダーティ極限での異常近接効果における奇周波数s波超伝導の重要性は,続く12.6でかなり明快に説明されているので,物理として理解可能ではある.また最終章のパラフェルミオンの記述は前提知識が多く必要で,本書の該当箇所だけでは非常に難解に感じられた.もう一点は,実験データについてはほとんど見当たらず,これについては引用している参考文献を適宜チェックする必要がある.
結論として,本書は誤植等も少ないことに加え,数多くある超伝導の教科書にありふれた記述にはページを割かず,本書特有の内容が充実している点で,本書でしか学べないことが多いと思われる.数式の多さからも本書は主に超伝導の理論家向けではあると思われるが,関連する実験グループの研究室に置いてあっても適宜項目の要点をさらうことが可能と期待されるし,根気があれば理論部分を読み解き学習できる書き味である.
(2022年1月20日原稿受付)
高密度プラズマの物理;金属水素から中性子星・ブラックホールへ
一丸節夫 著,古田 治 訳
日本評論社,東京,2020,vi+211p,21×15 cm,5,280円[大学院向] ISBN 978-4-535-78911-1
紹介者:岩田夏弥〈阪大高等共創研〉
本書は,高密度プラズマの物理について,理論的な基礎事項と関連する天体・天文現象を紹介した入門書である.高密度プラズマの例として天体の内部構造の紹介から始まり,高密度プラズマの理論的取り扱いが解説されている.後半では,木星や白色矮星,中性子星などで見られる具体的な高密度プラズマ現象が取り上げられている.本書の特徴として,多体系における密度ゆらぎの記述法など高密度プラズマ物理の基礎を学べる点が挙げられる.理論式のポイントごとに物理描像がわかりやすく記述されており,難解なゆらぎの物理のイメージがつかみやすい.理論と実験・観測がバランスよく解説された入門書となっている.
第1章は,天体の進化過程や惑星の内部状態の網羅的な紹介から始まっている.また,プラズマ物理で重要な荷電粒子の集団的取り扱いについて記述されている.第2章では,高密度プラズマを扱うための基礎が紹介されている.多体系の密度ゆらぎの記述からシミュレーション手法まで丁寧に記述されている.統計物理学とフーリエ変換など学部の基礎知識だけでも大部分を読み進められると思われる.
第3章では,プラズマによる電磁波の散乱について,基礎事項に加えて実験・計測についても言及されている.第4章では,金属中の電子プラズマの特性やプラズマの結晶化,グラス転移といった現象と,それらの計測手法の基礎が述べられている.第5章では,金属中の電子を量子電子液体とみなした場合の熱力学的取り扱いについて,論文を参照しながら述べられている.第6章では,星内部など高密度状態において水素が示す金属化,結晶化,磁化などの相転移について紹介されている.
後半は,論文等を参考文献としてこの分野の研究の発展が紹介されている.第7章では超高圧実験データの解釈の仕方が述べられ,第8章では木星と磁気白色矮星について相転移に関わる現象が紹介されている.第9章は,高密度プラズマにおける核反応に関する章である.高密度の電子に遮蔽された核クーロンエネルギーや,電子遮蔽効果を考慮した冷核反応について述べられ,超新星などでみられる高密度プラズマ中での核反応増倍について紹介されている.第10章では,高密度プラズマにおける水素の金属化に似た物理現象として,通常物質からクォーク-グルーオンプラズマへの相転移について簡単に述べられている.
最後に,高密度プラズマに関連する天体現象が紹介されている.第11章では,高密度天体であるパルサーについて,電子-陽電子プラズマ生成や放射発生のモデルが紹介されている.またブラックホール降着円盤からの輻射についても述べられている.第12章で,2017年ノーベル物理学賞授賞対象となったLIGOによる重力波観測が重力波天文学のあけぼのとして紹介され,本書は完結している.
本書は,プラズマ物理とゆらぎの理論の基礎から,高密度プラズマ状態における相転移や核反応といった発展まで学習できる構成となっており,加えて高圧実験や天文観測データとともに高密度プラズマに関連する現象が豊富に紹介されている.高密度プラズマの物理に興味のある大学院生や研究者に勧めたい一冊である.
(2022年1月24日原稿受付)
物理数学;量子力学のためのフーリエ解析・特殊関数
柴田尚和,是常 隆
共立出版,東京,2021,viii+166p,21×15 cm,2,530円[大学院・学部向]ISBN 978-4-320-03616-1
紹介者:高柳和雄〈上智大理工〉
本書は,物理(特に量子力学)で出会う微分方程式の解法と解の説明に特化した(入門的)教科書である.その内容は,まず級数展開とフーリエ・ラプラス変換を説明した後に,それらの応用として具体的に物理で必要になる微分方程式(強制振動,熱伝導,ベッセル,ルジャンドル,エルミート等)の解を詳しく解説するという構成になっている.これに線形代数の知識を加えれば,本書の前書きにあるように「物理学の標準的な教科書を読みこなす」には十分だと思われる.四十数年前に私が量子力学の勉強を始めたときは,物理志向の学生向けにこれだけの内容を1冊にまとめた入門的な教科書は無く,何冊もの難しい専門書を読む必要があったことを思い出した.
本書の説明スタイルは,フーリエ変換とラプラス変換の部分を除いては,ほぼ全て「級数展開」の視点を表に出しており一貫性がある.また,各所にふんだんに図が示してあり,理解の助けになるべく配慮されていると感じた.それに加え,本文でも問題解答でも式変形の計算は実に丁寧に(時にはくどいと思えるくらいに)書かれており,初学者でも苦労なく追えるはずである.
本書のレベルは,「複素関数の基礎知識を前提」としているものの,学部1,2年生の読者を想定している.そのためか,なるべく複素関数を表に出さないで説明しようという努力が各所で見られるが,それでも複素関数の知識が全くない1年生には少々難しいところがあるかもしれない.また,厳密さが求められる専門書とは違っていて当然なのだが,定理や概念の説明にはやや物足りなさを感じる.しかし,本書は物理で必要な数学を実際に扱うことを目的とした初学者向けの本であり,具体的な計算過程を理解させることを優先させた,と考えるとそのような説明も納得できる.
本書の後半では,特殊関数がその級数展開を使って詳しく説明されている.普通に量子力学を学び始めると,まず出会うのはエルミート多項式で,その次にルジャンドル関数が一般的だと思うが,本書では最初にベッセル関数が初学者でも無理なく追える丁寧さで解説された後に,ルジャンドル関数,エルミート多項式の順で説明される.これは,「まず確定特異点を一般的に説明し,次にその周りの級数展開を使って微分方程式を解く」という立場からは自然なのだが,量子力学を学び始めたばかりの初学者にとっては少々戸惑うところかもしれない.
結論として,本書は詳しい問題解答も含めて160ページ程度の本ながら,「複素関数の基礎知識を前提」とした上で,物理に必要な微分方程式の解法と解の性質を独学でも身につけることができるように書かれている.前提の複素関数に関しては,冪級数,解析関数あたりまでの知識はあった方が良い.さらにコーシーの積分定理あたりまで知っていれば無理なく全体を読み通せる.もし四十数年前にこの本があれば,「犬井鉄郞,寺沢寛一といった人たちのがっちりとした本で勉強する前に,まずはこの本を読んでみれば」と当時の私に言ってあげたいと思う.
(2022年2月25日原稿受付)
Berry Phases in Electronic Structure Theory; Electric Polarization, Orbital Magnetization and Topological Insulators
D. Vanderbilt
Cambridge Univ. Press, New York, 2018, x+384p, 25×18 cm, $79.99[専門・大学院向]ISBN 978-1-107-15765-1
紹介者:速水 賢〈北大院理〉
著者は,第一原理計算手法を軸とした物性研究を行う理論研究者であり,世界的にも著名な人物である.本書では,著者自身が先陣を切って開拓してきた電子がもつ量子力学的位相であるベリー位相とそれがもたらす種々の物性現象に関する詳細な解説が記されている.本書の主なターゲットである電気分極や軌道磁化は,学部生が古典電磁気学において習う基本的な事柄のひとつであるが,こうした量は空間座標に依存していることから,周期的な固体中で計算を行う際にはしばしば困難を伴う.また古典的な世界で学んだ電気分極の概念が,量子的な世界で登場するベリー位相とどのような関係性で結びついているかに戸惑う方も多いだろう.こうした古典的な描像と量子的な描像の間のギャップを埋めるためにはトポロジーに関する知識が必要不可欠である.本書では,こうした電子物性に対するトポロジカルな考え方について初歩的な立場から丁寧に解説している.紹介者は2020年度の研究室内のゼミで,この本をテキストとして取り扱ったので,以下にその所感を述べたい.
本書は6つの章から構成されている.前半の3つの章は基礎的な内容であり,後半の3つの章は応用的な内容になっている.1章では,結晶中において電気分極や軌道磁化がどのように定義されるべきかについて紹介している.また,電荷ポンプや異常ホール効果の導入とともに,電気分極と軌道磁化の相違点が述べられている.これらについてのより詳細な解説は後の章に含まれているため,つまずきそうな場合は,とりあえず後の章に進んでみると見通しが良くなると思われる.2章では,周期系ハミルトニアンおよび強束縛模型の基礎的な事柄について触れられている.後者では,ベンゼンやポリアセチレン,グラフェンといった,比較的単純な模型に対する適用例が示されており,理解の一助を担っている.また,本章では数値計算に馴染みのない学習者を対象として,著書が開発したソフトウェア(PythTB)に関する記述がなされている.これは本書の最大の特徴のひとつであり,後のベリー位相の計算なども含め,実際に手を動かしながら内容を学べるため,より理解が深まることが期待できる.3章ではベリー位相が導入され,分子系や周期系への適用例が示されている.またワニエ関数との関係性についても詳しく紹介されている.特に,高次元系や多バンド系におけるベリー位相の計算やワニエ関数の選び方についての留意点など,実用的な立場からも重要な事柄がいくつも指摘されている.
後半の4-6章では,電気分極,トポロジカル絶縁体,軌道磁化といったより応用的な内容についてまとめられている.特に,4章の電気分極に関する章は,歴史的な背景から,定式化,現実物質への適用例,現状での未解明点など,盛りだくさんの内容が記されているが,著者自身が開拓者の一人であることから,非常に読みやすく書かれている.一方,5,6章はさらに発展的な内容であり,より最先端の専門用語(Z2トポロジカル絶縁体,ワイル半金属,カイラル異常,アクシオン絶縁体)が多く出てくるため,専門分野が異なる初学者には少し敷居が高いように思う.したがって,トポロジーが電子物性に与える影響を知りたい初学者には,まず,4章と前述の3章の内容をよく読んで理解することをおすすめする.5,6章においても,基本的には3章までの内容が軸になっているため,そこまでの内容をよく理解しておくことで,より深い理解が得られるだろう.また,著者のホームページ*には本文中の訂正箇所が記されているため,適宜参照すると良い.
本書のもうひとつの大きな特徴としては,各節の最後に演習問題が記されている点である.どの演習問題も基礎的な要素のみならず,実際に自分で計算を行う際に役立つような応用的な要素も含まれているため,ゼミでの議論を行う際や独習していく上で大きく役に立つ.以上から,本書はトポロジカルな考え方に基づいて物性を理解するための丁寧な入門書になっており,古典的な描像と量子的な描像の間のギャップを埋めたい学習者に対しておすすめしたい良書である.
最後に,本稿を執筆するにあたって,貴重なご意見を頂いた研究室メンバー(八城愛美氏,松本拓哉氏,山家椋太氏,沖上和希氏)に感謝いたします.
(2022年3月9日原稿受付)
* http://www.physics.rutgers.edu/~dhv/
統計力学の形成
稲葉 肇
名古屋大学出版会,名古屋,2021,vii+368p,21×15 cm,6,930円[広い読者向] ISBN 978-4-8158-1036-8
紹介者:白石直人〈東大総合文化〉
「いかにしてミクロな分子集団からマクロな物性が現れるのか」という疑問に答えてくれるが答えてくれないのが統計力学である.アンサンブルを利用すれば系の自由エネルギーは確かに求まる一方,ミクロな動力学に従うはずのマクロ系は統計的手法で計算されており,その結びつきは通常の基礎法則と比べても異質である.学部で習ったときに感じたであろう「腑に落ちなさ」は,過去の偉大な物理学者たちが通ってきた道でもある.本書はその歴史を解明してくれる貴重な和書である.
本書はマクスウェルとボルツマンから始まる.分布やアンサンブルの手法は,もともと希薄気体の運動論において,分子衝突の繁雑な計算と同等の結果を得るために導入された.この時点では,平衡状態よりも輸送や第二法則などの非平衡過程への関心が強かった.
統計力学の背後には,気体運動論の系譜だけでなく,「力学的アナロジー」というやや意外な系譜も存在する.これは,循環座標で記述可能な古典力学系の満たす関係式と,熱力学の関係式との間の形式的類似性を指摘するものである.ヘルムホルツに端を発するこのアナロジーは,ボルツマンやギブスにおいては,アンサンブルを用いて計算された量と熱力学の量とを「アナロジー的に」結びつける議論へとつながっている.
アンサンブル理論はギブスによって整備されるが,その受容過程は興味深い.イギリスやドイツなどでは第二法則の微視的導出といった基礎的な問題に関心が寄せられていたが,そうした地域ではギブスの理論は「第二法則や不可逆過程の導出の議論として不完全」とする批判的言及が多かった.これに対しオランダでは,(気体に限らない)多様な物質の物性値の計算という応用的な課題に関心が強かった.そのためギブスによる「アナロジー」という留保を飛び越え,一般の系においてアンサンブルで計算された量を熱力学の量と同一視するという道を進み,混合気体の圧力,毛管現象,電気抵抗などがアンサンブルを用いて計算された.こうした応用上の魅力は様々な研究者を惹きつけ,最終的には「分配関数さえ求めれば,あとは熱力学で計算できる」という現在の標準的理解に至る.
希薄気体の運動論から一般の物体へと飛躍するにあたり,統計力学の基礎付けの方法も揺れ動く.ミクロな力学に根を下ろす気体運動論からはエルゴード性が自然に見出された.一方,ボルツマンやギブスは多様な論拠に訴える折衷的方法を用い,さらに一般の系の静的性質に拡張されるに従い,典型性やマクロ系のゆらぎの小ささに訴える基礎付けが増していった.そしてひとたび確立した計算手続きへとのぼりきったならば,そのための梯子は投げ棄てられる.
概念的な論争からマニュアル化された実用的計算手続きへ,という歴史は,例えば「何が力か」の論争からラグランジュ形式に至る古典力学などにも見られるものである.しかし,完成されたマニュアルが,出発点にはミクロな動力学を認めつつ,計算過程では動力学を一切捨て去る,という宙ぶらりんな形式を採用する点で,統計力学は特異である.先人たちが積み上げた知見は「その問題は忘れて計算に徹すればよい」と教えてくれる.確かに論文を書くためにはそれでよいのだが,しかしそこには忘れ去りがたき不思議が残されているのである.
(2022年3月9日原稿受付)
グリフィス 電磁気学I
グリフィス 電磁気学II
D. J. Griffiths 著,満田節生,坂田英明,二国徹郎,徳永英司 訳
丸善出版,東京,2019,xviii+422,21×15 cm,4,180円[学部向] ISBN 978-4-621-30422-8
丸善出版,東京,2020,v+269p,21×15 cm,4,620円[学部向] ISBN 978-4-621-30423-5
紹介者:宮島顕祐〈東京理科大〉
本書はDavid J. GriffithsによるIntroduction to Electrodynamics Fourth Editionの邦訳である.原著は1巻であるが,訳書はI巻422ページ,II巻269ページの分冊となっている.電磁気学は物理の中でも基礎となる学問の1つであり,ほとんどの物理系の学科では1・2年次から学修するであろう.そのため,学部下級生向けの初等教育用のテキストが数多くあり,覚えるべきポイントや数式を簡潔にまとめているものも多い.一方,学部上級生や大学院生が学ぶためのテキストでは,初等教育においては難解な内容のものとなってしまう.本書はそれらの間の中級レベルの教科書である.第I巻では静電場・静磁場から時間変化する電磁場までを学ぶ「電磁気学」の内容であり,第II巻では電磁波や輻射,相対論などの発展的な内容を取り上げる.幅広い内容を取り扱いつつ,電磁気学の体系的な理解を促すために深く掘り下げた説明がされている.現在,学部2年生の電磁気学の授業を担当している評者にとっては,非常に参考となる本であった.
評者が特に感銘を受けたことは,電磁気学を学び始めた学生には少々難しい事柄でも,端折ることなく丁寧な解説を試みている点である.多くの分かりやすい図と軽妙な語り口の文体が,読者の理解を後押ししてくれる.また,例題とその解法が,筆者の考え方を理解するために巧妙に設定されている.単に問題を解く方法を提示したり,要点をまとめるというものではなく,物理学を基本から身に付けるための論理と知識を説明することに重心が置かれている.さらに本文中には脚注が多く,それぞれで参考書が細かく指定されている.より理解を深める方向へ読者を導く心配りが感じられる.
内容を具体的に見てみよう.ベクトル解析(第一章)から本書は始まるが,まずここに多くの紙面を割いており,微分,積分や各種公式の導出とその意味を詳しく説明している.初等教育向けのテキストではここまでの説明はないであろう.早く物理の話にならないかともどかしく思う読者がいるかもしれないが,第2章以降での説明に必要とされる数式の意味について詳細に説明されており,その恩恵は後で受けることになる.続いて第2~4章にて静電場に関連する内容の説明がある.静電気学では,クーロンの法則とガウスの法則の2つが電荷保存則とともに等価であることを詳細に導いている.分かりやすい図が多いが,数式はやや複雑かもしれない.また,ラプラス方程式の重要性が強調され,電荷密度から静電ポテンシャルを求めることを多くの例題を用いて説明している.単に問題を簡潔に解くことではなく,思考過程を示すことで物理的な理解を深めることを目的としていることが分かる.ちなみに,一般的な教科書での電束密度が電気変位と訳されている点が評者にとって新鮮であった.続いて,第5・6章にて静磁場に関連する内容の説明がある.ここではビオ・ザバールの法則,アンペールの法則に続いてベクトルポテンシャルを説明し,回転と勾配から成るベクトル場のあるべき形を詳しく説明している.物質中の磁場については,常磁性・反磁性・強磁性についての記述が豊富な図とともに説明される.また,反磁性については,磁場下での電子軌道の変化から定性的な考察がされており,読者に納得感を与えるだろう.そして,第7章において,ファラデーの電磁誘導や変位電流の説明がされ,マクスウェルの法則を完成させる.また,ポインティングの定理が導入されている.通常,ここまでが多くの「電磁気学」のテキストで取り扱う範囲であるが,第II巻の内容を見据えて深く掘り下げた記述が含まれている.
第II巻では,電磁気学の発展的内容が説明される.第8章では,電荷保存・エネルギー保存・運動量保存についての定式化を行っているが,特に通常の電磁気学のテキストでは触れられない電磁気的な応力についての詳細な説明がされている.第9章は電磁波を取り上げているが,波動の説明から始まり,物質中での電磁波(誘電率や屈折率分散),反射の法則や導波路など,主に光学の教科書で扱われる範囲まで手を伸ばしている.第10章では,電磁ポテンシャルの定式化から始まりゲージ変換と遅延ポテンシャルについて記述がされている.特にマクスウェル方程式の解について丁寧な説明がされており,続く第11章での電気双極子放射などの輻射のメカニズムの定式化に繋がっている.第12章では,相対論についての説明がされ,特殊相対論の導入から相対論的力学,相対論的電磁気学へと続く.電磁気学の教科書で,これほど相対論の説明に力を入れたテキストは珍しいのではないだろうか.第II巻全体として広範囲の発展的内容を取り扱いつつ,それぞれの基本事項については詳細な説明がされており,とても読み応えのある内容となっている.
例えば本書を講義のテキストとして用いる場合,その内容を全て行うには1つの講義では足りないであろう.翻訳は,本書を講義で使用している大学教授陣によって行われているが,授業を1セメスター(15回)単位で行うとして3セメスター必要であろうと書かれている.評者の感想として,初等教育を一通り終えてこれから専門分野を学ぼうとする学部上級生が,今一度物理の理解をじっくり熟成させるために適しているのではないだろうか.また,これから電磁気学の教育にあたる大学教員には手に取る価値のある良著であると考える.
(2022年3月22日原稿受付)
入門講義 量子コンピュータ
渡邊靖志
講談社,東京,2021,xvi+239p,21×15 cm,3,300円[学部向]ISBN 978-4-06-526311-2
寺師弘二〈東大素粒子物理国際研セ〉
量子コンピュータは量子力学の原理を直接使って計算を行う計算機で,これまでのコンピュータ(古典計算機)とは全く異なる仕組みで動作する.本書は,「量子コンピュータはどのように働くのか」「何の役に立つのか」に重点を置いて説明した入門書である.量子力学の原理に深く立ち入ることなく,量子の振る舞いをイメージできるように配慮された良書と言える.
第1章と第2章で量子の基本概念や古典計算との違いが語られるが,第2章が本書を最も特徴付けていると言えるだろう.「量子テーマパーク」で量子を使ったアトラクションを読者が楽しむというユニークな設定で,量子の不思議な振る舞いを解き明かしている.波の干渉や波束の収縮,量子状態の重ね合わせ,量子の非局所性(EPR相関)など,量子力学の本質を分かりやすい例で示すだけでなく,その検証を行った物理実験にも言及することで,読者の理解を助ける工夫がなされている.
第3章から第6章では,量子アルゴリズムから様々な量子ビットの開発状況,量子ゲート方式と量子アニーリング方式のコンピュータなど,広範なトピックがまとめられている.グローバーやショアのアルゴリズムを実例をもとに平易な言葉で説明しているが,より正確な理解を助けるために,最低限の数式を用いた説明を付録として提供しているのがありがたい.著者の関心のためか暗号に比重が置かれている印象があり,耐量子計算機暗号や量子暗号以外の量子アルゴリズムについては若干物足りなさを感じる方もおられるかもしれない.量子コンピュータの心臓部に当たるのが量子ビットだが,現在の量子コンピュータは超伝導回路や捕捉イオン,光子やシリコン量子ドットなど,多様な量子ビットの開発が進んでいる.量子ビットは原理や構造はもちろん,情報の操作や読み出しの方法も大きく異なるため,一般向け書物では断片的な説明になりがちである.本書は量子ビットの違いに焦点を当て,説明が不足していると思われる部分を問題・解答の形式にして提供することにより,この難しさに対応している.量子ビットに関しては紙面の都合上掲載されている図は小さいものが多く,注釈や参考文献の引用も限定的であるため,仕組みをよりよく理解するには他の文献も併用するとよいだろう.量子アニーリングについては,アニーリング法の基本的な考え方から量子・準量子・古典でのアニーラまで,最近の開発状況も踏まえた説明がなされている.量子アニーリングの入門的な教科書は数が少なく,この分野に興味のある学生や研究者にはとても有用だと言える.
量子コンピュータの開発は日進月歩で進んでおり,数年前の技術がすでに古くなっている分野も多い.最終章では,企業や研究機関での投資・開発の現状,ノイズを持つ中規模量子コンピュータ(いわゆるNISQ)から誤り耐性量子コンピュータへの道程がまとめられており,現状を俯瞰するのに大いに役立つだろう.古典計算を上回る量子加速をいかに実現するか,そのためには量子コンピュータに何が必要かなど課題も多いが,今後の量子コンピュータの進展に期待を抱かせる内容になっている.
(2022年3月25日原稿受付)
カシミール物理への招待;次世代マイクロ・ナノデバイスの実現に向けて
岡田勘三
日本評論社,東京,2020,v+160p,21×15 cm,4,620円[専門・大学院向]ISBN 978-4-535-78912-8
巻内崇彦〈東大院工〉
本書はカシミール効果の入門書である.カシミール効果は,ナノメートルスケールに近づけた2枚の金属板が引き合う静的カシミール効果と,その金属板を振動させると光子が生じる動的カシミール効果として知られている.背景を理解するにはゆらぎの物理を丁寧に扱う必要があるが,重厚な専門書に手を付ける前の日本語の教科書として本書は適している.学部・修士の物理の知識で読み進めることができ,より詳しく学ぶための参考文献も充実している.
本書の構成を見ていこう.第1-3章では,ランダムな動きから生じるゆらぎと緩和を結びつける揺動散逸定理を中心に,ゆらぎの捉え方を学ぶ.金属中の電子のブラウン運動における電流ゆらぎのパワースペクトルやジョンソン-ナイキストの関係式を見た後,量子力学のゼロ点振動を考慮したキャレン-ウェルトンの揺動散逸定理を与え,その性質をプランクの放射と対応付けて概観する.第4章では原子・分子の電荷ゆらぎによって生じるファンデルワールス力と,真空の電磁場ゆらぎによる静的カシミール効果の性質を学ぶ.通常の意味でのファンデルワールス力は遅延効果と力の非加算性を含まないため,電荷ゆらぎが作る電磁場の波長以上の距離には適用できない.カシミール効果では遅延効果と力の非加算性が本質的に重要であり,第5章から7章は,これらを考慮した一般理論であるリフシッツ理論を導入する.電磁ゆらぎの相関関数は光子のグリーン関数であり,外力と共役な物理量(電流密度とベクトルポテンシャル)の平均場とゆらぎを遅延グリーン関数で表すことを学ぶ.遅延グリーン関数が満足する方程式(アンペール-マクスウェル則)から物体に流れ込む電磁応力が計算でき,具体的な幾何学的構造に対するカシミール-リフシッツ力を計算する準備が整う.しかし正負を激しく振動する力の周波数スペクトルを積分する際に膨大な計算時間がかかる問題があるため,これを回避するテクニックが紹介される.
最後に第8章でカシミール効果の測定と応用可能性についてまとめられる.2000年代に行われたカシミール-リフシッツ力の測定では,カンチレバーと平板の間に誘電性流体を挿入し,これら3体の誘電率の大小を変えることで,カシミール-リフシッツ力を斥力にも引力にもすることができた.これにより2固体間の引力・斥力をエンジニアリングすることが可能となり,高感度なナノコンパス,ハードディスクドライブの読み出しヘッドの浮上安定化,高感度NEMS距離センサーへの応用が期待できる.
本書の性質上,導出は他書に任せて結果の性質を述べる場合があるが,上記の内容がコンパクトにまとまっている.ニューロンの自発的なゆらぎ,動的カシミール効果とホーキング放射の類似性,宇宙背景放射に含まれる量子ゆらぎといったゆらぎの普遍性がわかる記事も興味深い.2011年に超伝導マイクロ波回路において動的カシミール効果が実証されたことを皮切りに,今後も様々な量子系で注目されるであろうカシミール効果に興味をお持ちなら,本書を開いてカシミール物理の入り口に招待してもらうことをお勧めする.
(2022年4月11日原稿受付))
電磁気学とベクトル解析
吉田善章
共立出版,東京,2019,316p,21×15 cm,3,960円(数学と物理の交差点2)[専門・大学院向]ISBN 978-4-320-11402-9
小菅佑輔〈九大応研〉
電磁気学は物理や工学などの分野で広く学ばれている.その中で,都合2種類の講義を聞くことが多いかと思う.1つはガウスの法則やアンペールの法則などの実験事実から出発し,最終的に4組のMaxwell方程式を導き電磁波の伝搬を予測するまで.もう一つはMaxwell方程式から出発し,電磁気の現象を統一的な視点から学び,相対論的な運動や荷電粒子による電磁波の放射などの計算を進めるまで.これらに加え,今回紹介する『電磁気学とベクトル解析』は電磁気学を考えるまた別の視点を与えてくれる.
電磁気学に関する様々な良書がある中で本書の特徴を挙げると,数学と物理の交差点というシリーズ名の通り,電磁気学を記述するための数学をより深く理解するための視座を提供している点にあるだろう.通常電磁気学の背後にある数学といえば,本のタイトル通りベクトル解析であり,勾配や回転,発散といった微分演算やストークスの定理などの積分定理を思い浮かべられるかもしれない.これらの通常のベクトル解析にとどまらず,本書では微分幾何や関数解析といったより高度な(電磁気学の通常の講義ではあまり触れられることが少ない)数学的トピックスを扱っている.特に電磁気学と幾何学との関わりを取り扱う2章は圧巻であり,多様体という概念を通してベクトル演算に関する種々の恒等式や積分定理がより少ない公式に統一され,幾何学の言葉を用いてMaxwell方程式が表現される.3章では方程式を解くことに主眼が置かれ,解析学の視点が導入される.電磁場を含む一般のベクトル場をポテンシャルにより表現する際の注意点が,空間のもつトポロジー(穴のない球や穴の空いたトーラス)との関連に着目して説明される.また,磁場のポテンシャルによる表現を用いれば,磁力線の方程式がハミルトン系の形に帰着されることが示される.これらの例が示すように,電磁場と荷電粒子の結合した体系であるプラズマ,特に核融合を念頭に置いた環状プラズマからの例が豊富に取り扱われている点も本書の特徴であろう.
個人的な思い出で恐縮だが,評者は学生時代に和達三樹氏による「微分・位相幾何」という本を手にし,座標系で表現を変えるベクトル演算に対し微分形式を用いると座標によらない表現ができるのか,と感動した覚えがある.高度な数学との付き合いはそれ以降疎遠になっていたが,本書はこの時の感動を呼び起こしてくれた.その一方で,プラズマの理論モデリングを生業とし,豊富なプラズマ実験データとの睨み合いを続けてきた経験からか,体系は美しいけれどもどうやって具体的な問題に適用したものか,という思いを抱いたのも事実である.しかしながらこれは評者の理解不足によるところがあるだろうし,数学書という本書の立場を考えれば,電磁気学の背後にある美しい数学的な体系をまとめ上げるという本来の使命は十分果たされている.具体的な研究への応用などは読者に委ねられた宿題だと評者は思っている.意欲的な学部生や大学院生,電磁気学をまた違った視点から眺めてみたい研究者にもおすすめできる一冊だと思う.
(2022年5月11日原稿受付)
スピントロニクスの基礎と応用;理論,モデル,デバイス
T. Blachowicz,A. Ehrmann 著,塩見雄毅 訳
講談社,東京,2021,ix+325p,21×15 cm,5,500円[専門・大学院向]ISBN 978-4-06-524092-2
能崎幸雄〈慶大理工〉
本書は,磁気と電気の交差現象を取り扱うスピントロニクスの入門書だが,磁気や電気伝導に関する量子論の丁寧な記述から始まるこれまでの教科書とは切り口が異なっている.スピントロニクスを扱う研究室や企業に飛び込んだ初学者向けの書でもあるが,既に当該分野を専門としている研究者にも効率よく幅広い知識を身につける一冊としてお勧めできる.スピントロニクス現象の理解に必要な基礎知識に割くスペースを最低限にとどめ,スピン輸送現象や磁化ダイナミクスを応用した様々なスピントロニクスデバイスを幅広くコンパクトに網羅している.また,それぞれのトピックスの発見に至る歴史的経緯や最新の研究動向を調べる上で役立つであろう1,000を超える参考文献リストが整理されている点が本書の最大の特長であり,これまでになかったスピントロニクスの百科事典として位置づけられる.
数式によるスピントロニクス現象の原理の説明は,かなり大胆に絞られており,順を追って発現機構の物理を丁寧に理解したい読者は参考文献や他の教科書を併読する必要がある.例えば,スピントロニクス分野で最も重要な概念であるスピン流やスピン蓄積,スピントランスファートルクなどは,第6章において数式なしに簡単に紹介されているのみである.これらの項目を基礎から学びたい読者は,『スピントロニクスの物理』(多々良源著,内田老鶴圃)やSpin Current(Ed. by S. Maekawa, S. O. Valenzuela, E. Saitoh, and T. Kimura, Oxford Science Publications)などを参照されることをお勧めする.著者による序文でも,「これまで量子論を用いた定式化に嫌気がさしていた学生,企業の研究者,およびこの分野に関心のある科学者」を読者として想定していると書かれており,スピントロニクス分野の魅力を初学者に伝えることに全集中した教科書である. 一方,小さなスピントロニクスデバイスの磁化ダイナミクスに関するトピックスは,著者自身のマクロマグネティクス研究の成果などを具体例としてふんだんに取り入れながら第2章から第4章まで丁寧に説明されている.また,磁気ヘッドや磁気トランジスタ,磁気論理ゲート,MRAM,そしてニューロモルフィックコンピューティングに至るまで,スピントロニクスのデバイス応用に関する多くのトピックスを紹介している第7章も本書の特長といえる.それぞれのデバイスの動作原理を説明しながら,その開発の経緯と実用上の課題解決に向けた研究に関する文献が紹介されており,それぞれのデバイスについて調査しなければならない企業研究者にはよい道標となるのではないだろうか.
さて,翻訳を担当された塩見氏は,スピントロニクス分野で数多くの先駆的研究を手掛けてきた当該分野における気鋭の若手研究者である.膨大なトピックスを扱う百科事典的な本書を適切な日本語表現に翻訳するには,すべての内容に精通していなければならず,スピントロニクス研究で活躍されている塩見氏の尽力あっての一冊である.
(2022年6月7日原稿受付)