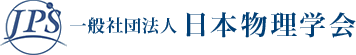会誌Vol.79(2024)「新著紹介」より
このページでは、物理学会誌「新著紹介」の欄より、一部を、紹介者のご了解の上で転載しています。ただし、転載にあたって多少の変更が加わっている場合もあります。また、価格等は掲載時のもので、変動があり得ます。
工学系のためのレーザー物理入門
三沢和彦,芦原 聡
講談社,東京,2020,viii+245p,21 cm×15 cm,3,960円[専門~学部向]ISBN 978-4-06-153281-6
紹介者:渡邉紳一〈慶應大理工〉
本書は「工学系のための」という枕言葉がついたレーザー物理入門の教科書である.たしかに第1章の「レーザー光の応用」では,工学的に重要な技術(レーザー顕微鏡,光ファイバー通信,光記録,レーザー加工など)を概説している.しかしながら,第2章以降では本格的なレーザー物理学の基礎を展開しており,工学系だけではなく,理学系の学生や研究者にとっても有用な一冊である.
本書の特長は,「はじめに」で触れられているように,コヒーレンス(可干渉性)を基軸として多くの光学現象を説明していることである.第2章の「レーザー光の性質」の部分は特に優れている.ここでは,時間,空間,周波数のコヒーレンスがすべて揃った理想的な条件下で,レーザー光の指向性,集束性(これらは光の空間波面形成に関連),および高速性(超短パルス光の時間波形に関連)について,光電場の空間,時間,周波数分布を数学的に表現しながら詳しく説明している.特に印象的だったのは,レーザー光を使用する際に実用的に重要なガウスビームの空間波面形成について,遠くに飛ばした時,凸レンズで絞った時,共振器に閉じ込めた時など,様々な状況に対応して丁寧に数式を導出している点である.ガウスビームの空間波面形成については,ヤリーヴ・イェーの教科書『光エレクトロニクス』の記述が有名だが,それと比べても,本書はより実用的に重要な部分に焦点を当て,簡潔だが詳細な説明をしていると感じた.
第3章の「レーザーの原理」では,はじめに正帰還の概念を簡単に紹介した後に,レーザー発振の原理についてレート方程式を用いて説明する.その上で,レート方程式を二準位原子と光の相互作用の視点から量子論へと拡張することを試みる.通常,この部分は密度行列を用いた光学的ブロッホ方程式を用いて説明することが一般的だが,本書では密度行列の概念を導入せず,反転分布と分極の要素を抜き出して,基礎方程式を丁寧に記述する方法を採用している.これは初学者にとって理解しやすい形式だろう.一方で,本書は入門書であることから,レーザー発振の量子論をより深く学びたい読者にとっては,他の参考書で補足する必要があるとも感じた.さらに,この章の最後には,様々なモード同期パルスレーザーの歴史,原理,特徴が説明されている.これは最新のパルスレーザー技術を学びたい読者にとって有用なガイドとなるだろう.
第4章の「媒質中の光の伝搬と非線形光学効果」では,物質内の非線形光学現象が幅広く説明されている.振動子ポテンシャルの非調和性や位相整合など,基本的事項の説明を組み込みつつ,様々な非線形光学現象が説明されている.疑似位相整合,白色光生成による自己位相変調効果,非線形ラマン散乱など,現役の研究者にも有用な内容が豊富に含まれていて参考になる.内容は多岐にわたり,限られたページ数の中で,これほど多くの内容が含まれていることに感銘を受けた.また,代表的な二次非線形光学材料の特性が表形式でまとめられている点も,実用的に価値が高いと考える.
なお本書は,「読者を意識すること」を念頭に様々な配慮がなされている.例えば,面倒な式変形も途中の式変形をほぼ省かずに記載してあり,読者が道に迷うことは少ない.また,光電場について正弦波表示で書いているのか複素表示で書いているのかを混乱することもない.さらに,変数の添え字も整理されており,非線形光学現象の教科書に特有な煩雑な添え字に伴う圧迫感を感じない.総じて読みやすく,初学者が入門書として読むことに限らず,ベテランの研究者がレーザー物理の基礎を素早く復習するときにも役立つだろう.
(2023年5月29日原稿受付)
超伝導;直観的に理解する基礎から物質まで
小池洋二
内田老鶴圃,東京,2022,xi+364p,21 cm×15 cm,5,500円(物質・材料テキストシリーズ)[専門~学部向]ISBN 978-4-67536-2319-8
紹介者:吉澤俊介〈物材機構〉
超伝導体を研究する実験系の研究室にいた学生のころ,初めて参加した物理学会で,超伝導関係のセッションを聴講したものの,知らない単語がつぎつぎに登場してあまり理解できなかった思い出がある.不勉強を白状するようだが,超伝導物質の種類も,超伝導体で起こる現象も,それらを研究する手段も多種多様なので,自分の研究の周辺だけ勉強しても予備知識として全く足りないことを痛感した.しかしその予備知識を得ようにも,入門的な教科書で扱われる内容と研究の最前線で飛び交う話題との間には大きなギャップがある.そのギャップを埋めるには個別の論文や解説記事で学んだら良いが,実験系の学生には難しい内容のものも多い.もし当時,超伝導の基礎事項から始めて分野全体を見通しよく学べる教科書があったら,どんなに助かっただろうか.
本書は,超伝導の実験系の研究室に配属された学部4年生や修士の学生が,超伝導の考え方と(物性物理学分野で行われるような)超伝導研究の全体像がつかめることを意図して書かれた教科書である.『新著紹介』欄でも何度か取り上げられている内田老鶴圃の物質・材料テキストシリーズの一つとして出版されている.学部レベルの量子力学,熱・統計力学,初歩的な固体物理の知識は前提とされているが,随所で補足があるので,多少うろ覚えでも思い出しながら読み進められるだろう.
本書は全7章から構成される.第1章で対凝縮状態としての超伝導の短い導入があり,第2章で完全導電性,完全反磁性,磁束の量子化という超伝導を特徴付ける3つの現象が示される.第3章では比熱,準粒子トンネル現象,ジョセフソン効果など,超伝導体の一般的な性質が紹介される.第4章では現象論を扱っており,ロンドン理論やギンツブルグ・ランダウ理論が導入される.第5章は微視的理論の章である.その前半はBCS理論の解説になるが,第二量子化法を用いた計算はほぼ省かれている.第5章後半からは本書の特色が強くなる.強結合超伝導とBCS-BECクロスオーバーの説明があり,さらに異方的電子対とその形成機構としてのスピンゆらぎと軌道ゆらぎが紹介される.第6章は,160ページにもわたる各種超伝導物質のレビューになっている.取り上げられている超伝導物質は,元素単体から始まり,合金,2元化合物,2次元超伝導体(遷移金属ダイカルコゲナイドやボロカーバイド,MgB2など),1次元超伝導体,有機超伝導体,磁性超伝導体,重い電子系(空間反転対称性のない化合物を含む),酸化物,銅酸化物,C60インターカレーション化合物,鉄系超伝導体,BiS2系超伝導体,超高圧下の水素化物に及び,バルク物質に関しては網羅的に近い.銅酸化物超伝導体と鉄系超伝導体については,当然ながら,他より多くのページを使って解説されている.なお,トポロジカル超伝導体や表面・界面の2次元超伝導については,省略されているか,軽く触れられている程度である.最後の第7章では,常圧・室温超伝導を実現する方策に想像を巡らせて締めくくられる.
本書の特徴は大きく3つ挙げられる.第1に,タイトルに「直観的」とあるように,超伝導体の性質を理解するための考え方を平易な言葉で説明することに重点が置かれている点である.実験データの当てはめにも使うような基本的な関係式は導出されるが,進んだ内容についてはアイデアの定性的な説明が主となる.数式に目を回す心配はあまりないが,理論系の人が読むと物足りなく感じられるかもしれない.第2に,脚注の多さである.ほとんどすべてのページに脚注が付いており,ページによっては面積の半分以上が脚注で占められている.ここでは,本文に入りきらない議論の補足,超伝導の話題に登場しがちな周辺知識,超伝導体が発見されるに至った経緯などが,やや小さめのフォントでびっしり紹介されている.第3に,超伝導の初歩から,各種超伝導物質で対形成機構がどう理解されているかまで,連続して学べる構成になっていることである.これらの特徴により,本書は1冊の教科書としては相当多くの話題が噛み砕いた説明とともに盛り込まれている.読み通せば最新の研究で頻出する物質や概念と(おそらく最速で)一通り顔見知りになれるだろう.一方,厳密な説明を省いている部分も多いので,もっと正確に理解したい時には,巻末に紹介されている発展的な教科書などを必要に応じて参照すると良いかもしれない.
以上をまとめると,超伝導の(とくに実験系の)研究を始める学生や若手研究者にとって,本書は基本事項から最近の研究までカバーする心強いガイドブックになるだろう.通読するのも良いし,すぐ手に取れる所に置いておくのもおすすめである.ちなみに某ECサイトのレビューには文字が小さくて辛いという指摘があるが,想定読者は若手なのであまり支障はないと思われる.
(2023年6月5日原稿受付)
放射線物理学
C. Rangacharyulu 著,遠藤 暁・和田義親 訳
森北出版,東京,2022,ix+262p,22 cm×16 cm,4,400円[大学院・学部向]ISBN 978-4-627-15751-4
紹介者:間嶋拓也〈京大院工〉
放射線物理学の教科書を探すと,医療技術者向けの国家試験に対応したものが多く見つかる.また,原発事故による社会的な関心の高まりにより,一般向けの関連書籍も増えた.その一方で,放射線や量子ビームの関連分野は上記以外にも幅広く多岐にわたるが,これらの研究者・技術者に適した学術的な入門書は少ない.
初等的な入門書の多くは,「放射線とは何か?」から始まり,ボーアモデルに続く原子構造や原子核の基本など,放射線物理の前提となる基礎知識の説明に多くのページが割かれる.これに対し,本書も非専門家向けではあるが,「必要とされるのは学部1年生での数学と物理の知識」とあって,原子の説明から始まることはない.準備の章は1章のみで,書籍の前半で放射線の発生や物質との相互作用の説明がなされる.後半では線量測定や発生装置,検出器などの技術的な解説がなされ,最後に放射線技術の応用例が物理過程と関連付けて紹介されている. 放射線と一言でいっても荷電粒子,電磁波,中性子で相互作用の仕方が異なるため押さえるべき範囲はそれなりに広い.これらの物理を本当に理解するには,高度な電磁気学や量子力学の知識が必要であり,非専門家向けの"放射線物理学"の範囲を超える.本書は,各項目の導入部と結論の説明に重点を置くことにより,全体をコンパクトに収めている.
原著には「Concepts, Techniques and Applications」の副題がある.物理学者である著者が,物理的なコンセプトに気を配りつつ説明が進むのが本書の特徴である.例えば,1章では最初に保存則の要点が語られており,物理志向の読者は共感を覚えるだろう.3章では「原子核には,崩壊するものと崩壊しないものがあるのはなぜだろうか」という問いかけが始めにあり,ひとまず「最も単純な答えはエネルギー収支である」というコンセプトが示される.5章の序文でも「物質と光子の相互作用では,エネルギー損失ではなく,光子ビームの強度の減弱について考える」と述べられ,荷電粒子の場合とのコンセプトの違いに気付かせてくれる.
本書のもう一つの大きな特徴は,例題や演習問題がふんだんに織り込まれている点である.具体的な計算によって理解を深める仕掛けとなっており,教育現場でも活用が期待できる.また,基礎データを調べるための実用的なウェブサイトも紹介されており,現場の研究者・技術者を意識して書かれていることが伺える.
重荷電粒子と物質の相互作用の章では,細部で気になる点があったので,僭越ながら言及してみたい.ベーテの式に出てくる「平均励起エネルギー」あるいは「平均励起ポテンシャル」と一般に呼ばれる量が「イオン化ポテンシャル」とされているのには違和感があった.また,物質中でのイオン価数が入射時の価数で制御できるように読めてしまうところも少し引っかかった.α粒子が空気中を透過する際の,単位長さあたりのエネルギー損失を示すグラフ(いわゆるブラッグ曲線)も値や形状が不自然で,何か取り違いがあったのではと想像する.前述のとおり放射線物理学の扱う範囲は広く,単独で全てをまとめるのは非常に困難な仕事である.紹介者も馴染みのある箇所以外の詳細はわからない.いずれにしても,深掘りしたい項目のある読者は,本書を入口にさらに専門的な文献に当たってその理解を深めることになるのだろう.
本書は,全体を俯瞰しながら放射線物理の物理的な要点を学べる貴重な本となっている.読者に語りかけるような筆致で,翻訳も読みやすい.これから放射線物理を専門にしようとする学部生の入門書としてはもちろんのこと,放射線や量子ビームに携わる多様な分野の研究者,技術者,大学院生らが,その物理過程をしっかり理解したいと思ったときの手引きとしても,有用な一冊である.
(2023年6月12日原稿受付)
思考実験 科学が生まれるとき
榛葉 豊 著
講談社,東京,2022,246p,18 cm×11 cm,1,100円(ブルーバックス-B2193)[一般向]ISBN 978-4-06-527068-4
紹介者:村山 功〈静岡大院教育〉
ガリレオ・ガリレイの『新科学対話』では,重い物の方が軽い物より早く落ちるというアリストテレスの主張を支持するシムプリチオと,以下の対話が行われる.
サルヴィヤチ「ではもし自然速度の異なる二つの物体をとって,二つを結び合わせた場合,速い方の物体は遅い方の物体のために幾分かその速さを緩められ,遅い方は速い方のため幾分か速められるということがあるわけですね.こういう考えでは私と一致するでしょうか.」
シムプリチオ「全く仰せの通りです.」
サルヴィヤチ「しかし,もしこれが本当だとし,そしてもし大きな石が例えば8の速さ,一方小さな方の石が4の速さで動くとすればその二つが結び合わさったものは8より小なる速さで動くでしょう.ですが二つの石が結合されれば,その大きさは,以前8の速さで動いていた石よりも大となりますから,重い物体が軽い物体よりも速度が小であるという,貴方の仮説と全く相反する結果になります.これで貴方の仮定,即ち重い物体が軽い物体より速度が大きいということから理を推して行けば,重い方が軽い方より一層速度が小さくなる,と言えることがお分かりでしょう.」
(今野武雄・日田節次訳『新科学対話(上)』岩波書店pp. 97-98,筆者により表記を変更)
この話を初めて知ったとき,私はその鮮やかさに感動した.今これを書いていても,その気持ちは変わらない.同じ思いの読者も多いのではないだろうか.
本書は「思考実験」について論じた書籍である.「第1章 思考実験を始める前に」で仮説の生成について論じた後,次の「第2章 実験とはなんだろうか」において,まず思考がとれた「実験」から考察を始めている.実験とは仮説から演繹される結論と実験結果から演繹される結論とを闘わせるものであり,思考実験はこの実験を実際に行わずに頭の中の操作から演繹するものというのが著者の主張である.この,仮説,演繹,結論の組み合わせを思考実験のセオリーと呼んでいる.そのあとで実験しない実験として自然実験や計算機実験などを取り上げ,思考実験との違いを論じている.こうして,思考実験を原理や法則を求めるために行われるものとして位置づけ,次章からその説明に入っていく.ただし,原理や法則を求めるといっても,それを生み出す手段というよりはふるいにかける手段として扱われている.
「第3章 思考実験の進め方」では,アインシュタインの自由落下するエレベーターとマックスウェルの悪魔を例に取り上げ,それを第2章で示した思考実験のセオリーで説明していく.思考実験の例を示し,そこで検討される仮説を明示し,仮説から演繹的に導かれる結論と思考実験から操作的に導かれる結論を対比することで,その思考実験の仕組みが示されていく.この記述方法は,これ以降の章でも一貫して用いられている.これに続いて,テセウスの船を例にして物理学以外での思考実験について議論を展開している.これは著者が思考実験を科学の方法としてだけではなく,人がものを考え意思決定していく方法だと捉えているからである.
「第4章 思考実験の分類」では,ポパーの挙げた「批判のための思考実験」,「発見のための思考実験」,「弁護のための思考実験」の3タイプに加え,「問題提起のための思考実験」,「判断や解釈のための思考実験」,「教育的な思考実験」の合計6タイプを提唱している.第5章以降は,このうち5つのタイプの思考実験について順に解説していくが,残念ながら発見のための思考実験は取り上げられていない.発見のための思考実験は,思いつきを理論化するために,それがうまくいくかどうかを確認するためのものであり,第3章で触れたアインシュタインの自由落下するエレベーターがその典型例だとしている.これを詳述しない理由は,「ほかのタイプの思考実験の前段階であり,やや趣が異なりますので」としか書かれておらず,期待も大きいだけに少々納得し難い.
「第5章 批判と弁護のための思考実験」「第6章 問題提起のための思考実験」では,不確定性原理に関する思考実験や,シュレーディンガーの猫,アインシュタイン=ポドルスキー=ローゼンのパラドックスなど,量子力学に関連した有名な思考実験を紹介しながら話を進めていく.しかし,「第7章 判断や解釈のための思考実験」になると,一転してマイケル・サンデルのトロッコ問題やチューリング・テストなど科学から離れた思考実験を題材とし,原理や法則が成り立つかどうかではなく複数の考え方を比較検討するような思考実験について論じている.
「第8章 教育的な思考実験」では,ある理論を学習してもどうにも腑に落ちないとき,「最低限の本質を頭の中で自分の思うままに動かしてみて,そうなることを確信するために役立つのが思考実験」だと解説されている.そして,最後の「第9章 意思決定と思考実験」で意思決定理論と思考実験を結びつけて,人生において思考実験が持つ意義にまで話を広げて終わっている.
1986年に同じブルーバックスから刊行された金子務著『思考実験とはなにか』は,自然科学の思考実験だけを扱ったエピソード重視の内容であった.これに対し本書は,科学以外の思考実験も幅広く扱いながら,思考実験の仕組みや役割について迫ろうとしている.これは,金子氏が科学思想史を専門にしているのに対し,本書の著者が科学哲学者であることからくる違いだと思われる.両書を読み比べると本書の持つ面白さがさらに際立つのではないだろうか.
(2023年1月25日原稿受付)
入門 現代の宇宙論;インフレーションから暗黒エネルギーまで
辻川信二 著
講談社,東京,2022,ix+253p,21 cm×15 cm,3,520円[大学院・学部向]ISBN 978-4-06-526631-1
紹介者:樽家篤史〈京大基研〉
題名が示す通り,本書は現代宇宙論,英語でいうphysical cosmologyの内容をまとめた専門書である.宇宙の成り立ちとその進化を探る宇宙論は,観測の進展に伴い,飛躍的な発展を遂げてきた.特にこの20数年の間に,遠方のIa型超新星サーベイ,探査機WMAPやPlanckに代表される宇宙マイクロ波背景放射の精密観測,それにスローン・デジタル・スカイサーベイなどの大規模銀河サーベイから続々と観測結果が報告され,宇宙の膨張と構造の進化を統一的に記述する「標準モデル」が確立したことは,大きな成果である.その華々しさは,2000年代に3度のノーベル物理学賞,6名もの受賞者を輩出したことからも窺える.なお「標準モデル」の確立には,日本人研究者の多大な貢献があったことも忘れてはならない. そのような現代宇宙論に関心を寄せる人は,数多くいることだろう.最近では,宇宙に関するニュース・話題はネットなどでも頻繁に見かけるようになっており,分野を問わず,年齢を問わず,幅広い層からの関心があるかもしれない.
言うまでもなく,現代宇宙論は,物理学をベースにした学問分野である.扱う対象は,宇宙そのものと,そこに存在する銀河・銀河団などから成る巨大な構造(大規模構造と呼ばれる)の時間進化である.ミクロからマクロまで,様々なスケールで現れる物理現象を記述するため,素粒子物理,量子力学から熱・統計力学,電磁気学,流体力学など,様々な物理学が総動員される.中でも,一般相対性理論は,宇宙の進化に圧倒的な影響をおよぼす重力場を記述する理論として,最も本質的である.そのため,宇宙論をしっかりと学ぶには,物理基礎教科を一通り学び,さらに一般相対性理論の知識を踏まえてからが望まれる.つまり,物理学科の学生でも学部4年生か,大学院生以上からの習得が適当である.
本書は,習得までに時間のかかる一般相対性理論の前提知識なしに,現代宇宙論が学べるようにと,意欲ある学生へ向けた「入門」書である.ソフトカバーA5版で本文235ページと,コンパクトなサイズでまとめられた本書ではあるが,全9章,理論から最近の観測結果までかなり「がっつり」と書かれている.おおまかには,宇宙膨張と物質進化の歴史についての記述と(第1~5章),物質・輻射のゆらぎ(空間非一様性)についての説明にわかれ(第6~8章),最終章9章は暗黒エネルギーの解説に割かれている.なお,本書の著者はインフレーションや暗黒エネルギーの専門家でもあり,その意味でも第9章は本書の特色といえそうだ.全体を通して随所に一般相対性理論が必要になる内容ばかりだが,第2章では,ニュートン力学における一様球の運動のアナロジーをベースに,熱力学の法則とも絡めながら,膨張宇宙モデルの基礎方程式であるフリードマン方程式を「導出」している.その他の章でも一般相対性理論の重要性をちらつかせながらも,複雑さを避けて物理的本質に焦点をあてた解説が試みられている.ただし,宇宙マイクロ波背景放射の記述がある第7.3章では,摂動がある宇宙での測地線方程式を用いて,光の伝搬過程を通じて現れる相対論的効果を説明するくだりがあり,さすがに一般相対性理論の知識が必要になる.とはいえ,結果の物理的意味は明確なので,細部に拘りさえしなければ読み進めていけそうだ.その意味で,一般相対性理論の知識を前提としないという,本書の目標は概ね達成されたといえるかもしれない.
とはいえ,本書は,物理基礎教科の知識を大前提としている点を,十分,心にとどめて読み進めるべきである.ある程度自己完結的な記述が試みられてはいるが,少なくとも解析力学,熱・統計力学,量子力学,それに流体力学あたりの基礎を習熟していないと,それらを総動員して得られる新しい知見や概念の理解には追いつかないだろう(本書に限った話ではない).また,やはり一般相対性理論の知識なしに正確な理解は得られないし,誤解が生じうる.著者自らも勧めているように,本書の付録や他の宇宙論の教科書を参照しつつ,理解を深めるべきである.加えて本書は,最新の観測成果を紹介しながら,現代宇宙論の成り立ちを説明しているため,その情報量は圧倒的である.全くの初学者が,溢れる情報を整理しつつ,宇宙論の概念などをおさえるにはかなり手強そうにも思える.そういう意味では,本書は入門書というより,現代宇宙論を俯瞰するための情報をコンパクトな1冊にまとめたハンドブックともみなせそうだ.学生向きというより,大学院生・専門家にむしろ有用かもしれない.
最後に,観測に関する説明について気になる点が散見されたので,気づいたものを挙げておく.1つは,宇宙論における距離の説明である.宇宙論的な距離が宇宙モデルにどう依存するかが後半まで読み進めないとわからないし,与えられた関係式は,平坦な宇宙に限られ,閉じた・開いた宇宙では適用できないため,注意を要する.2つめは,第8.5章のバリオン音響振動を用いた宇宙論的な距離の測定方法に関する説明が不正確な点である.特に,(8.91)式あたりの記述は正しくない.また(8.92)式は,1次元相関関数ではなく1次元相関関数から求まるシフトパラメータの誤りである.その他,第7.8章の宇宙マイクロ波背景放射の偏光に関する記述や,第9.2章のIa型超新星観測から距離を決める方法についても,記述が端折られていて誤解や間違った印象を与えそうに思えた.これらの間違い・誤植等は,第2版に訂正・改善されていれば幸いである.
(2023年7月17日原稿受付)
グラフェンの物理学;ディラック電子とトポロジカル物性の基礎
越野幹人 著
内田老鶴圃,東京,2023,x+232p,21 cm×15 cm,4,400円(物質・材料テキストシリーズ)[専門・大学院向]ISBN 978-4-7536-2321-1
紹介者:磯部大樹〈理研創発物性科学研セ〉
グラフェンは炭素原子が蜂の巣格子を組むことにより構成される原子1つ分の厚さをもつ物質である.炭素原子が共有結合することによりできるこの物質は,それ自体が興味深い機械的・熱的性質を示すと同時に,原子単層の厚さの理想的な2次元電子系である.1947年にWallaceにより低エネルギー有効模型が相対論的なDirac電子系となることが示されていたが,その後2004年にGeimやNovoselovらにより粘着テープを用いた剥離でグラファイトから単層グラフェンを作成できることが報告されたことを契機に,実験と理論の両面において研究が大きく進展した.近年では2018年にCaoやJarillo-Herreroらにより単層グラフェン2層をわずかにずらして積層させたねじれ2層グラフェンにおいて,電子相関効果により絶縁体や超伝導体に転移することが実験的に示され話題となっている.本書の表紙イラストにもなっているねじれ2層グラフェンは,最近の物性研究のハイライトのひとつといえる.
本書はグラフェンに関する多くの論文を記した著者による,最新の研究の進展を含むグラフェンおよびその他の2次元物質に関連する事項を網羅する教科書である.2次元電子系としてのグラフェンは物性研究のあらゆるトピックと関連する興味深い物質であるが,それは同時に研究を行うにあたり広範な知識を必要とすることを示唆する.本書ではDirac電子系やトポロジカルな性質を中心に,最近のねじれ2層グラフェンを含む最前線の研究を理解するために必要な事項が理論研究者の観点から簡潔にまとめられている.グラフェンに関する研究の動向のフォローを目的とする研究者や,これからグラフェンや2次元物質に関する研究を始めようとする大学院生を対象として,この分野を俯瞰し,より基礎的な教科書と最近の論文との間をつなぐ橋渡しとなる教科書である.
目次から分かるように本書の網羅する内容は多岐にわたり,なによりグラフェンに関する物理の広がりを物語る.まずグラフェンの発見と関連する2次元物質の解説(第1章)から本書は始まる.続いて固体物理の基礎を振り返りつつグラフェンを特徴付ける性質のひとつであるDirac電子系としての性質を強束縛模型から導出し,乱れの効果などを踏まえて電気伝導や光学応答に関する説明がなされる(第2,3章).グラフェンの持つ別の側面としてDirac電子系に端を発するトポロジカルな性質があるが,強磁場下におけるLandau準位と量子Hall効果の説明を経てBerry位相が導入される(第4,5章).波数空間で記述され抽象的にも見えるBerry接続やBerry曲率であるが,本書で示されるようにWannier軌道や異常速度を通してその一端を理解できる.トポロジカルな性質の発現についてはグラフェンナノリボンにおけるエッジ状態を用いて例示される.関連するトポロジカル格子模型(第6章),すなわち種々の質量のあるDirac模型(第7章)についても紹介されている.グラフェンはグラファイトを剥離して作成できることから分かるように,層間結合は弱いvan der Waals結合によるものである.これがグラフェンの物質設計における自由度を高めている主因であり,多層グラフェンにおける積層パターンの効果についてトポロジカルな性質との関連を踏まえて解説される(第8章).
第9章のモアレ2次元物質に関する記述は本書の到着点といえよう.モアレ2次元物質は,2次元物質を積層させて作るvan der Waals物質のうち,単層グラフェン2枚や,グラフェンと六方晶窒化ホウ素の組み合わせなど,各層の格子定数が同じかごく近い場合に全体の格子構造に長周期のモアレ模様が現れる物質系である.近年の物性研究の一大テーマであり,シンプルにも見える物質系だが背景や発現する物性には物性物理学のさまざまな事柄が関連しており,8章までの内容はモアレ2次元物質のための準備を整えたとみることもできる.グラフェンについてすでに詳しく,モアレ2次元物質の基礎について知りたい読者はこの章をまず読むことも可能であろう.単層グラフェンは非常に速いFermi速度(~106 m/s)を示すが,2011年にBistritzerとMacDonaldによりねじれ2層グラフェンでは長周期モアレ構造に伴い,2層の相対角度に応じて非常に平坦なエネルギーバンドが形成されることが理論的に示された.この平坦なバンド構造が実験でも確認された電子相関効果の増大と関連するが,実際にはモアレ構造に伴う格子緩和が電子状態にも多大な影響を与えるなど注意が必要である.著者はモアレ2次元物質のエネルギーバンド計算にも多大な貢献があり,本書を通じてその要点・機微を直接学ぶことができる.
このように本書ではグラフェンにまつわるさまざまなトピックが理論研究者の観点からまとめられており,簡潔ながらも詳細まで配慮した記述が見られる.一方で,物質の合成や実験,また応用などについても随所で触れてあり,グラフェンの物理学について気負うことなく知識を深めることができる.さらに数式の記述についても工夫が成されており,自ら導出を行うことでより理解を深めることができるだろう.
(2023年7月24日原稿受付)
微生物流体力学;生き物の動き・形・流れを探る
石本健太 著
サイエンス社,東京,2022,iv+201p,21 cm×15 cm,2,970円(ライブラリ数理科学のための数学とその展開-AP1)[大学院向]ISBN 978-4-7819-1559-3
紹介者:内田就也〈東北大院理〉
バクテリアやゾウリムシなどの微生物の遊泳は,生物の運動の中では数理的な解析が最も進んでいる問題の一つである.この分野は,1951年のG. I. Taylorの仕事を嚆矢として長い伝統を持つが,近年,アクティブマターと総称される非平衡系の研究の進展に伴い,新たな脚光を浴びている.本書は,微生物の流体力学をその基本から最近の研究成果に至るまでまとめた,邦書としては他に例を見ない教科書である.
第1章では,遊泳する微生物の分類や,鞭毛や繊毛とよばれる運動器官の概要が紹介された後,微生物の世界の特徴的なスケールが示される.第2章では,流体力学の基礎方程式であるナビエ-ストークス方程式に続いて,その慣性項を無視した近似であるストークス方程式の基本的性質が述べられる.第3章では,剛体の流体抵抗が定式化された後,体を変形させて遊泳する物体の理論が展開される.特に重要な結果は,ストークス方程式の時間反転対称性に起因するパーセルの帆立貝定理である.これは,帆立貝の貝殻の開閉のような,形状空間において同じ経路を往復する運動では,正味の移動が生じないことを示した定理である.したがって,微生物が遊泳するためには単純な往復運動ではなく,回転的な運動を用いる必要があることが分かる.第4章では,遊泳する物体の周りの流れ場の構造が議論される.流れ場は多重極展開で表され,その基本的なパターンは,力の二重極(双極子)の構造によって分類される.また,数値計算に必要となる理論的枠組みもこの章で解説されている.第5章は,個体と流れの相互作用,および個体間の流れを介した相互作用の解説にあてられている.実際の例としては,精子が流れに逆らって泳ぐ性質,境界壁に近づく性質,他の精子と協調して泳ぐ性質などが挙げられている.第6章では,微生物の集団の性質に焦点が当てられる.章の前半では拡散やレオロジーについて述べられた後,後半ではアクティブ乱流や生物対流など,巨視的スケールで生じる集団運動が紹介されている.アクティブ乱流は微生物に限らず自己駆動性を持つ粒子の集団で普遍的に見られる現象である.一方,生物対流は,微生物が重力や光を検知して移動する性質に起因する.第7章では,より複雑な問題として,微生物の体の曲げ弾性や表面張力による変形が関わる現象や,流体の慣性の効果が取り上げられる.最後に,遊泳効率の最適化の問題が,生物の行動・生態・進化のメカニズムの力学的理解という未解明の問題の一つとして掲げられている.
本書は,定理,命題,証明といった数学書の体裁を取りつつも,多くの図が挿入されていることでイメージが湧きやすく,実際の微生物への応用が豊富な例によって解説されているため,物理を専攻とする学生にも楽しく読み進められる教科書となっている.また,より専門的な理解へのガイドとしては,本文中に挿入された注や,多数の参考文献への誘導が役に立つ.内容的にも年代的にも広範にわたる生物流体力学の諸結果が,見通しよく整理され,日本語で学べるようになったことの意義は大きい.生物物理やアクティブマター,および応用力学一般に関心を持つ多くの方に一読をお勧めしたい.
(2023年9月4日原稿受付)
科学と仮説
科学と仮説
アンリ・ポアンカレ 著,南條郁子 訳
アンリ・ポアンカレ 著,伊藤邦武 訳
筑摩書房,東京,2022,336p,15 cm×11 cm,1,210円(ちくま学芸文庫)[一般向]ISBN 978-4-480-51091-4
岩波書店,東京,2021,494p,15 cm×11 cm,1,320円(岩波文庫 青902-1)[一般向]ISBN 978-4-00-339029-0
紹介者:高橋 浩〈群馬大理工〉
原著は1902年出版であり「新著紹介」に相応しくないが,最近,新訳が2つ相次いで出版されたので紹介したい. 「仮説」の役割を中心にしてポアンカレ自身の科学思想を一般読者向けに語った原著は,本国フランスでベストセラーになり,直ちに,英語やドイツ語に翻訳され多くの読者を獲得した.日本語訳も林鶴一によって『科学と臆説』の題名で1909年にはもう出版されている.アインシュタインも1904年に出版されたドイツ語訳をその年に熟読したらしい.南條訳の解説(南條訳p. 304)でも指摘されているように「相異なる舞台で起こる二つの事象の同時性について直接的直観さえ持っていない」(南條訳(第6章p. 121))や,「この特異な運動(注:ブラウン運動)はカルノーの原理に従っていない」(伊藤訳(第10章p. 305))などといった記述は,大いに彼を刺激したであろう.
2つの新訳を比較しての全体的な印象は次の通りである.これまでも多くの数学啓蒙書の翻訳を手掛けてきた南條氏の訳の方が,日本語としてこなれていて読みやすい.伊藤氏のものは,ポアンカレの考えを誤解なく読者に伝えることを大切にしていることが,ひしひしと伝わってくる訳文である.そのために全体的に文章が長く,ややくどい感じになっている.エネルギー保存則に関連して登場する文を例に比較してみる.南條訳は,「もし世界が法則によって支配されているならば,一定に保たれる量が存在することは明らかだ」(南條訳(第8章p. 162))であり,一方,伊藤訳では,「世界がもろもろの法則によって支配されているのであれば,定数にとどまるようないくつかの量が存在するであろうことは明白である」(伊藤訳(第8章p. 228))となっている.伊藤氏の単数,複数の差を明確にする姿勢は,高く評価したい.
新訳登場以前親しまれていた岩波文庫の河野伊三郎訳(1938年初版,1959年改訂)と比較すると,河野訳で,「ケプレル」「エネルギー恒存の原理」(索引参照)と表記されているものは,新訳はどちらも「ケプラー」「エネルギー保存(の)原理」(索引参照)と現代的な用語になっている.原著の"la philosophie naturelle"を,河野訳では「自然科学」(改訂版p. 157)としているが,2つの新訳はともに,そこは敢えて「自然哲学」(南條訳p. 164,伊藤訳p. 230)としているのは興味深い.第10章に登場する小見出"La physique et le mécanisme"は,河野訳では,「物理学と力学観」(改訂版p. 196),伊藤訳では,「物理学と力学的世界観」(p. 287),南條訳では,「物理学と力学理論」(p. 206)と3者で異なっている.訳者の個性,考え方が反映した部分であろう.
伊藤氏の訳に関して1点だけ,紹介者が戸惑った部分があった.それは,確率計算に関係して登場する"instinct"という言葉に対しての訳し分けである.ポアンカレは,全体の要約を序文として掲載している.序文でも確率計算の議論の部分に"instinct"という言葉が登場する.南條訳は,序文,本文第11章の両方で「直感」(p. 13, p. 227)という言葉で統一している.因みに,旧訳の河野氏のものでも,序文では「感じ」(p. 18),本文では「直感」(p. 216)としていて,ほぼ同じ訳語になっている.一方,伊藤訳は,序文では「本能」(p. 11)とし,本文では「直感」(p. 315)としている.「本能」と「直感」ではだいぶ印象が違う.哲学者である伊藤氏には,何か深い意図があるのかもしれないが,紹介者にその訳し分けの意図がくみ取れなかった. 巻末解説と原著にはない索引の存在は,両新訳書の価値を高めている.巻末解説のスタンスは,両者で大きく異なっている.伊藤氏の解説は,『科学と価値』などのポアンカレの他の著作にも言及しながら,彼の科学哲学思想を要約し,その一貫性とある種の保守性を指摘している.一方,南條氏は,『科学と仮説』を解釈する際,前提となるカント哲学について解説している.紹介者のように哲学に疎い読者にとっては大変にありがたい.索引に関しては,両者ともにやや不満がある.伊藤訳書の索引には,「一様性」「時間」「矛盾律」という項目はあるが,南條訳書には登場しない.逆に,南條訳書の索引には,「帰納」「科学」「変位電流」は登場するが,伊藤訳書にはない.人名解説が伊藤訳書にあるが,その人物への言及が何ページでなされているかの索引はない.一方,南條訳書には,人名による索引が完備されている.
科学哲学,科学史の専門家は原文を読むであろうが,一般の物理学徒や物理学者にとって,この古典の現代日本語訳が2つも同時に登場したことは大変に喜ばしいことである.是非2冊とも入手し,読み比べることをお勧めする.
新訳2種類が,ほぼ同時に出たのは偶然であろうか.もしかすると,科学における探究だけでなく現代社会一般においても,「仮説」の役割が今注目されているためかもしれない.従来の「総合的な学習の時間」に代わって,2022年度から高校必履修科目として登場した「総合的な探究の時間」について『高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説』*1では,社会や地域の問題に対して「その解決に向けて仮説を立てたり,調査して得た情報を基に分析」(第7章p. 84,傍点:紹介者)することを各校の設定目標の例として挙げている.『解説』は学習指導要領の改訂の度に発行され,現場に強い影響力を持っている.
*1 https://www.mext.go.jp/content/1407196_21_1_1_2.pdf
(2023年11月7日原稿受付)
テンソルネットワーク入門
西野友年 著
講談社,東京,2023,192p,21cm×15cm,3,630円[大学院・学部向]ISBN 978-4-06-531653-5
紹介者:森田悟史〈慶應大理工〉
ここ最近,「テンソルネットワーク」という言葉を目にする機会が増えていると思う.テンソルネットワークとは端的に言うと,テンソルの縮約に基づいた表現方法である.縮約を取る共通の添字を持ったテンソル同士が繋がっているとみなすことで,ネットワーク構造が現れる.分配関数や波動関数などを多数のテンソルの縮約として表現し,その形式の元で数値計算や数理解析を行う手法がテンソルネットワーク法と呼ばれる.統計力学の転送行列や量子多体問題の密度行列くりこみ群など,その萌芽となるアイデアは昔から存在していたが,21世紀に入り「テンソルネットワーク」という用語が開発され,分野を横断した統一的な観点から急速に発展が進んでいる.特に,テンソルネットワークの表現能力に関する量子情報理論からの洞察が重要な貢献を果たしている.その高い汎用性から,当初の枠組みを超えて,量子重力,量子計算,機械学習,金融工学など様々な領域で応用が広がっている.テンソルネットワークに関する書籍はまだ少なく,本書は日本語で書かれた待望の入門書である.
本書には,テンソルネットワークを理解するために必要な概念が,200ページ弱のコンパクトな分量でまとめられている.まず始めに全体の準備として,テンソル間の縮約を視覚的に表すダイアグラム表記が導入される.数式よりも図を眺めたほうが,テンソルネットワークの計算内容を直感的に把握することができる.第3章から第7章までは古典統計力学を題材にテンソルネットワークの基本的な考え方が紹介される.畳の敷き詰め方の数え上げ問題という身近な題材を用いて,自然な形でテンソルネットワークが導入される.第5章では,テンソルネットワークによる数値計算で重要となる特異値分解が導入され,低ランク近似による情報圧縮とエンタングルメントの関係が説明される.第8,9章では,手書き文字認識の教師あり学習と制限ボルツマンマシンを題材に,機械学習とテンソルネットワークの関連が紹介される.第10,11章は,実空間くりこみ群に基づく計算手法が紹介される.テンソルくりこみ群法は,重要でない自由度を削ぎ落とすことで粗視化をし,巨大なテンソルネットワークを近似的に縮約することができる.また,エンタングルメントをほどく操作もここで導入される.第12,13章は量子力学系を題材に,基底状態の計算手法や時間発展シミュレーション,量子計算との関係が説明される.第14章では,歴史を振り返りながら,テンソルネットワークの今後に関して著者の考えを垣間見ることができる.
本書は幅広い読者を対象としており,統計力学や量子力学の予備知識を極力必要としないように構成が練られている.第10章までは,なるべく量子力学を避けながら解説を進めているが,流石にエンタングルメントの知識があったほうが読みやすいと思われる.また,読者の理解を助けるために,本書には様々な工夫が凝らされている.テンソルネットワークを数式で記述すると多数の添字が現れて混乱が生じるが,本書の数式ではダイアグラムの形と同じ対応する場所に添字が置かれている.初見ではぎょっとしてしまう形だが,慣れると分かりやすい.参考文献には,インターネット環境さえあれば誰もが最先端の研究へアクセスできるよう,プレプリント番号で参照先が記載されているのも本書の特徴であろう.
本書の著者は,テンソルネットワークという用語が生まれる前から,この分野に携わっていた第一人者である.先駆者ならではの視点やエピソードが,著者独特の軽妙な語り口で散りばめられており,読者を飽きさせない.小さなコラムが多数挿入されており,ここだけを拾い読みしても十分に面白い.これからテンソルネットワークを学習したい学生や非専門家の入門書として,ぜひ,手にとって読んでいただきたい一冊である.
(2023年9月25日原稿受付)
プラズマ乱流輸送の基礎
伊藤早苗,伊藤公孝 著
岩波書店,東京,2023,ix+195p,22cm×16cm,4,620円[専門・大学院向]ISBN 978-4-00-006344-9
紹介者:前山伸也〈核融合研〉
プラズマ乱流は,実験室プラズマから宇宙・天体プラズマにおける輸送過程と密接に関係した物理現象であり,プラズマを構成する荷電粒子と電磁場の長距離相互作用に起因して,種々の波動や渦の励起,大域的構造形成などの多様なダイナミクスを生み出す.本書は磁場閉じ込め核融合プラズマ研究を中心としてプラズマ乱流理論を開拓してきた伊藤早苗博士,伊藤公孝博士による和書である.両氏の初期の代表的な仕事として1988年のPhysical Review Letters誌論文があるが,1980年代当時の核融合分野は,外部加熱を増やしてもプラズマの温度が上昇しない異常輸送の問題や,急峻な空間構造の変化を伴ってプラズマ閉じ込めが改善するHモードの発見など,従来の定説では解釈できない「新しい見方」が必要とされた時期であった.そうした中で,乱流揺動による酔歩的拡散過程の描像を超え,大域的径電場の分岐による構造遷移という新たな理論を提案したのが上述の論文であり,その後の関連する理論の発展や実験解析へと花開いた.本書は,両氏の「解ける問題ではなく,解くべき問題にチャレンジする」という基本理念と自身の経験に基づいて,近年の磁場閉じ込めプラズマ実験,理論,シミュレーションにより得られてきた新しい知見から,今後解くべき問題の所在を示そうとする意気込みが感じられる一冊となっている.
本書のタイトルにある「基礎」は標準的な基礎知識の意味ではなく,考え方の本質(英題ではEssentialsの語が充てられている)の意味である.序文でも述べられているように,「新しい見方を生み出していくために,理論の考え方の本質を理解してもらうこと」を主眼に置いており,標準的・演繹的な説明は既刊の教科書や論文に譲っている.そのため想定読者としては,プラズマ物理の基礎的な勉強が済み,いざプラズマ乱流研究を始めようとする大学院生,理論研究の結果をその仮定や理論的な適用範囲まで踏まえて(細かい計算過程は抜きにして)理解したい実験家,理論技法の考え方や両氏の指摘する解くべき問題を学んで自分の研究に応用したい理論家に勧められる.
内容については,第2章で磁化プラズマ中の微視的揺らぎの典型例であるドリフト波の線形理論,および,局所・拡散型・単一スケール・準線形的混合長見積もりによる輸送過程が述べられる.第3章では帯状流についての線形理論が説明される.この辺りまでが議論の下地であり,以降が本書の主題である.第4章では微視的乱流と帯状流やストリーマといったメゾスケール構造との相互作用を準粒子モデル(あるいはwave kinetic equation)に基づいて解析し,構造の励起や乱流捕捉について説明している.第5章では,プラズマ中の輸送過程を局所拡散,長波長揺動による大域的輸送,素過程は局所拡散であるが大域的な弾道的伝搬に分類して議論している.第6章では電場による構造相転移,第7章では加熱による輸送の動的応答についての研究成果がまとめられ,最後の第8章では多輸送チャンネルの競合,位相空間乱流,突発現象などの話題が触れられる.演繹的な説明は省くということだけあって,第2・3章の線形解析辺りまでは基礎方程式から導出を追えるが,適宜導入される運動論効果や,各種モデル方程式の詳細な導出などは大幅に省略されている.その代わりに,乱雑位相近似(p. 30)や,ミクロ揺動をパケットとして巨視的スケールと分離する準粒子モデル(p. 57),TSDIA(twoscale direct interaction approximation, p. 93)などの理論の着想についても,簡潔ながらツボを押さえた説明と詳細な文献への引用が同時に示されており,これらの理論のプラズマ乱流への応用研究を見渡すためのガイドブックとしても機能する.
著者らのプラズマ乱流輸送研究に対する多大の業績のために致し方ないが,著者らの国内共同研究が2010年以降の参考文献の多数を占めている点には注意しておきたい.例えば,国内外のジャイロ運動論に基づく研究,プラズマ乱流スペクトルの冪則や臨界バランスの問題,高エネルギー粒子との相互作用などのいくつかの研究トピックは本書では扱われていない.しかしこれは,上に挙げたような個別事象を網羅的に取り上げるのではなく,本書の「考え方の本質を考える」という立場から具体例となるトピックを取捨選択した結果であろう.著者らが,それまでの局所・拡散型・単一スケール・準線形的混合長見積もりによる輸送理論を超えて,異なるスケールを内包した乱流輸送と構造形成という問題を開拓するにあたって,どのような実験事実や考え方を理論を進めるための足掛かりとして仮定し,どのように推論を推し進めてきたかを読者が追体験し,今後の解くべき問題にチャレンジしていく姿勢を学べれば,本書の目論見は成功したといえるだろう.
(2023年11月2日原稿受付)
格子振動と構造相転移
石橋善弘 著
森北出版,東京,2023,viii+316p,22 cm×16 cm,8,250円[専門・大学院向]ISBN 978-4-627-17061-9
紹介者:塩見雄毅〈東大総合文化〉
格子振動と構造相転移が関連していることを意識している人はそれほど多くないかもしれない.格子振動は物性物理学の講義で最初の頃に習う一方,構造相転移の物理は大学院に入ってから自分で勉強する人も多いであろう.その意味で両者の関係を有機的に理解する機会は,構造相転移を専門とする人以外は多くないのが現状だと思われる.私も何を隠そう,この歳まで両者の関係を強く意識したことがなかった人間であり,「格子振動と構造相転移」という本書の題名には興味をそそられた.
著者の石橋氏は同じ出版社から『強誘電体入門』という本を2020年に上梓しており,その本でも格子振動と強誘電相転移の関係について触れられているが,本書ではより深く掘り下げられ,構造相転移の基礎が網羅的に説明されている.前半の第1部(1-6章)では,格子振動のいわゆるバネのモデルから始まり,基礎知識の説明を経て,強弾性相転移や強誘電相転移との関係が論じられている.続く第2部(7-9章)では,群論の知識に基づき構造相転移の議論がなされている.最終章である9章で扱われる不整合相転移についてはこれまで他の書籍で取り上げられているのを見たことはなく新鮮に映る.
第2部で基礎から説明されているように,構造相転移の結果生じる低対称相は群論に基づいて整理される.本書の特徴の一つは,点群や空間群,既約表現などの基礎知識の説明から詳しく書かれている(7章)ばかりでなく,実際の適用例としてチタン酸ストロンチウム(SrTiO3)といった具体的な物質に対する構造相転移の現象論が丁寧に説明されていることである(8章).著者まえがきにあるとおりこれは著者が狙ったものであり,多くの例題をこなすことによって一般論を理解しやすい構成となっている.
一方で,構造相転移は格子振動の特定のモードのソフト化によって誘起されるものだという見方もできる.格子振動と強弾性・強誘電性の関係を議論するのが第1部である.格子振動の音響モードは結晶の弾性的性質ひいては強弾性相転移と密接に関係しており(4章,5章),光学モードは誘電分散を通じて強誘電相転移と関係する(6章).このあたりの現象論も具体的な物質に即して丁寧に説明がなされている.
第1部の前半(1-3章)では,バネのモデルに基づき様々な対称性の1次元格子や2次元格子の格子振動の分散関係が導出されている.その議論で強調されているのは,分散の交差(縮退)と対称性の関係である.結晶構造という共通の舞台の上で生じる格子振動や構造相転移は,共に構造の対称性の影響を強く受け,深く絡み合っている.簡単な格子振動のモデルからでも構造相転移について皆が思っているよりも多くの知見が得られるというのが著者が本書を記した動機の一つであると思われ,実際9章においては格子振動からみたリフシッツ条件の意味が述べられている.
いささか専門的で難解な印象がある構造相転移であるが,具体的な物質例に触れながら手を動かすことで理解が深まるように設計されている.部分読みでは著者の意図を完全にくみ取ることは難しいであろうから通読の必要があろう.その意味で少し精神的なハードルは高いかもしれないが,構造相転移を網羅的に理解したいという強い意欲がある人にとっては恰好の入門書であると思う.
(2023年12月1日原稿受付)
分子動力学法と原子間ポテンシャル
渡邉孝信 著
森北出版,東京,2023,vi+226p,22 cm×16 cm,4,400円[大学院・学部向]ISBN 978-4-627-92251-8
紹介者:國貞雄治〈北大院工〉
分子動力学法は,各原子に働く力に基づいて各原子の運動を計算する手法である.各原子の運動を直接観察することができるため,結晶成長,材料の劣化プロセス,ナノスケールでの材料加工,生体内化学反応など,様々な分野で利用されている.本書で取り扱われている分子動力学法は,量子力学に基づいて原子間の相互作用を逐次計算するかわりに,あらかじめ原子間の相互作用を適当に関数で近似した原子間ポテンシャルから計算する古典分子動力学法とも呼ばれるものである.そのため,密度汎関数理論に基づく第一原理計算よりも計算コストが小さく,手元の計算機でも比較的大規模な系を取り扱うことができるという利点がある.また,本書でも紹介されているLAMMPSなどの無料で利用できるソフトウェアもあり,シミュレーションの実行自体はそれほど難しくない.
一方,分子動力学法で妥当な結果を得るためには,原子間ポテンシャルの特徴と適用可能範囲を理解し,適切な原子間ポテンシャルの選択が必要不可欠である.しかし,原子間ポテンシャルは選択肢も多く,全くの初学者にとってその選択は簡単ではないことも多い.近年は第一原理計算の結果を用いた機械学習ポテンシャルのデータベースも少しずつ整備されており,実験系の研究者が分子動力学法を解析のために使用することも増えている.
本書は分子動力学法に初めて取り組む読者を対象としており,分子動力学法に関する基本的な説明に加え,書名の通り原子間ポテンシャルの記述が充実していることが特徴である.Chapter 1では物質・材料シミュレーションにおける分子動力学法の位置づけや歴史,数値解法について簡単に述べられている.読者はこの段階で分子動力学法のサンプルプログラムの実行と原子運動アニメーションの可視化に取り組むこととなる.C言語のプログラムを実行できる環境が必要ではあるが,分子動力学法の初歩的な理解には非常に良い題材となっている.実際にアルゴンの液滴が激しく運動するアニメーションを目にできれば,分子動力学法に取り組んでいる実感が湧くだろう.なお,本書に登場するサンプルコードは出版社のウェブサイトからダウンロードできる.これらのサンプルコードはいずれも数十秒程度でシミュレーションが完了するため,待ち時間のストレスも感じなかった.
Chapter 2では分子動力学法の方法論として,周期境界条件,圧力と温度の制御法,長距離力の計算法などが取り上げられている.各項目の記述はそれほど多くないが,図や数式を使いながら初学者にもそのエッセンスが感じられるように工夫されており,分子動力学法で用いられるパラメータの意味を理解する助けになるだろう.
Chapter 3からChapter 5,すなわち約200ページの本文のうち約110ページが原子間ポテンシャルの説明に充てられている.Chapter 3では様々な原子間ポテンシャルの特徴と適用可能範囲が網羅的に解説されており,原子間ポテンシャルを選択する際の判断材料となる知識を得ることができる.Chapter 4とChapter 5では化学反応を取り扱うことができるReaxFFと機械学習ポテンシャルの一つであるガウス近似ポテンシャル(GAP)をそれぞれ取り上げている.これらのポテンシャルやChapter 3で取り上げられているニューラルネットワークポテンシャルは近年注目を集めているものの,多くのエネルギー項の取り扱いや,ガウス過程回帰モデルなどを用いた機械学習の知識が必要であり,他の原子間ポテンシャルよりも理解が難しい.これらのポテンシャルについても初学者がそのイメージが捉えられるように丁寧に記述されている.また,LAMMPSを用いて,実際に手を動かしてこれらの原子間ポテンシャルを体験できるようにも配慮されている.
強いて気になる点を挙げるとすれば,表面や界面,アモルファスなどの初学者が躓きそうな構造モデルの作製に関する記述があれば読者にとって有益であったと感じた.また,重箱の隅をつつくようではあるが,巻末の日本語索引部分に人名を冠した用語の英字綴りが併記されていれば,初学者が参考文献を検索する際に少し楽になるだろう.なお,誤植が多少見受けられたが,正誤表が出版社のウェブサイトにて公開されている.
本書はこれから分子動力学法に取り組む読者に向けて,そのエッセンスが理解できるように丁寧にかみ砕いて説明された良書である.初学者が先行研究を真似てブラックボックス的に分子動力学法を使用するところから一歩踏み出すための大きな助けとなるだろう.特に,機械学習ポテンシャルなどの原子間ポテンシャルの発展にともない,分子動力学法に取り組む研究者が増えている今非常に価値がある書籍だと考えられる.
(2024年1月17日原稿受付)
Ultrashort Pulse Lasers and Ultrafast Phenomena
T. Kobayashi
CRC Press, Boca Raton, 2023, xxiv+682p, 25 cm×18 cm, $186.98[専門・大学院向]ISBN 978-042-91-9657-7
紹介者:小西邦昭〈東大院理〉
レーザーの発明とその進歩は,1秒の1兆分の1に相当するフェムト秒以下のパルス幅のレーザー光の発生を可能にした.このような超短パルス光によって,物質の電子遷移や分子ダイナミクスなどの極めて短い時間スケールで生じる現象を実験的に観測することができるようになり,現在においてこのような超高速レーザー分光技術は,物質の超高速応答を理解,制御する上で不可欠なものとなっている.
本書は,我が国における超高速レーザー分光の研究分野を長年牽引され,現在においても第一線で研究を進められている小林孝嘉氏が,これまでの約30年間に発表されたご自身の研究論文の内容をテーマごとにまとめられた著作である.現在もっとも広く利用されている超短パルスレーザーの一つであり,本書で用いられている超短パルスレーザー技術の中核を成しているチタンサファイアレーザーのモード同期は1980年代前半に初めて報告された.そのため,本書で紹介されている数々の研究の発表された時期は,まさにチタンサファイアモード同期レーザーの出現によって超高速レーザー分光技術が飛躍的な進歩を遂げた時代と一致しており,本書には,その研究の歴史が活き活きと刻まれている.
本書には,著者の極めて広範な分野を対象とした長年にわたる研究活動を反映し,超短パルスレーザー技術と超高速レーザー分光に関するほぼあらゆる分野の研究が含まれている.本書の前半では,チタンサファイアレーザーを用いた超広帯域光の発生と,そこから生み出されるパルス幅が数フェムト秒の極短パルス光を駆使した,深紫外から中赤外,テラヘルツ波領域にまで至る様々な波長・周波数領域の超短パルス光発生技術が紹介される.さらに,パルス幅が数フェムト秒のオーダーになる際にはその包絡線内での光の振動電場の位相(キャリヤーエンベロープ位相)の制御も重要な課題となり,それらの安定化に関する研究が説明されている.そして,このような超短パルス光の発生の基礎となる四光波混合に代表される非線形光学過程そのものについての研究や,レーザーに欠かせない非線形光学結晶そのものに関する研究が紹介される.
後半では,このような著者の開発した最先端の超短パルスレーザーを用いた,超高速レーザー分光の研究の数々が紹介されている.本書で紹介されている研究の対象となる物質は量子ドット,カーボンナノチューブ,有機物質,強相関物質,超伝導体,トポロジカル絶縁体,二次元材料など極めて多岐にわたり,現代の光物性物理学における重要な研究対象が網羅されていると言ってよい.さらにその対象は,生体分子や光化学反応など,物理の枠を超えて化学や生物学の範囲にまで及んでいる.いずれの材料を対象とした場合でも,そこで生じるフェムト秒,ピコ秒,ナノ秒という時間オーダーの超高速現象のダイナミクスを実験的に観測するためには,超短パルスレーザーは不可欠であり,その実際の研究を網羅的に学ぶことができる.これらの広範な材料を対象とした研究が,一人の研究者によって統一的にまとめられているという点において,本書は貴重な著作であるといえる.
本書の内容を理解するためには,レーザーや光物性に関する専門的な知識が必要とされるため,レーザー分光を専門とする研究者や,博士課程の大学院生が読者の対象として適当であると考えられる.全体を通して読めば,超高速レーザー分光に関する研究の全容を理解することができる.一方で,それぞれの研究者が興味を持っている研究対象に関連するトピックについて個別に学びたい場合にも重宝する書籍である.
近年,超短パルスレーザーのパルス幅はフェムトを超えてアト秒の領域に達しており,一方でチタンサファイアレーザー以外のイッテルビウム系やエルビウム系の固体レーザーやファイバーレーザー等も広く用いられるようになるなど,超高速レーザー分光技術の発展のスピードはとどまることを知らない.そのような状況においても,本書で紹介されているような超高速分光の素晴らしい研究の数々に立ち戻って学び,考えを深めることが,レーザー分光の更なる発展の礎となると思われる.
(2024年2月2日原稿受付)
物性化学;分子性物質の理解のために
菅原 正 著
裳華房,東京,2023,xiv+259p,21 cm×15 cm,3,520円(化学の指針シリーズ)[学部向]ISBN 9978-4-7853-3229-7
紹介者:榎 敏明〈東工大〉
本の帯に,この本を"電子の動きを追いながら,光物性,導電性,磁性といった物性発現の基礎と応用,将来の展望をていねいに解説した画期的参考書"と表現している通り,本書はオーソドックスな物性物理学や物性化学の教科書と違い,化学や材料科学の立場から,分子をスタートとして,分子性物質の理解に重きを置き,電子の振る舞いを軸として展開する物性科学の分かりやすい入門書である.本書の構成は,まず"まえがき"として"物性化学とは"で始まり,物性をもたらす電子構造の特徴,新物質開拓への指針提供について触れ,物質理解における物性化学の重要性を述べている.本論は9章からなる.第1章は"日常的に出会う物性現象"と題し,光合成を中心に物質と光の相互作用,導電現象として,金属,半導体,絶縁体,超伝導体等,また,高分子や有機物質の導電現象,さらに,磁性については,磁性の起源とスピン,磁化現象等について紹介している.第2章"物性を導く電子構造-ヒュッケル分子軌道法による理解"ではエチレン等の小分子を対象にヒュッケルの分子軌道について議論し,それに基づき,ナノ粒子から無限のサイズを持つ物質における金属,半導体の電子構造について議論を展開している.その後,d電子を持つ遷移金属の電子構造について触れ,d電子スピンによる磁性現象の発現を議論している.第3章"π電子系のトポロジーと物性"では分子の形と電子構造の関係,光学的性質,導電性,磁性について議論をしている.第4章"光と分子の相互作用"では光と分子との相互作用について議論をしている.第5章"光誘起の物性現象"では,第4章を踏まえ,エキシトン,光誘起電子移動等,光誘起の物性現象を論じている.第6章"導電性を示す物質"では,電気を流す仕組みと導電性,半導体と金属の違い,さらに,遷移金属錯体の導電性,分子性結晶の導電性,有機合成金属等の導電メカニズムについて議論をしている.第7章"導電性の展開と応用"では,第6章での議論を踏まえ,バンド理論,金属・半導体の違い,超伝導について議論を展開している.さらに,議論は電子デバイスにも及びトランジスタについても説明をしている.第8章"磁性の基礎"は磁性の起源を議論した後,常磁性,強磁性,反強磁性,フェリ磁性について述べている.第9章"磁性の展開と応用"では,第8章で学んだ磁性の知識を基礎に,強磁性,反強磁性転移,有機分子からなる磁性体,低次元磁性体,単分子磁石等について議論をし,さらにスピントロニクスへも議論は展開されている.
以上,分子とその電子の振る舞いを出発点として,本書は光学,伝導性,磁性等の基本的な物性現象を議論するユニークな教科書であり,初学者にも抵抗なく理解できる物性化学の入門書である.
(2023年12月27日原稿受付)
入門 ソフトマター物理学
松山明彦 著
森北出版,東京,2022,v+212p,22 cm×16 cm,3,740円[大学院・学部向]ISBN 978-4-627-17051-3
紹介者:伊藤弘明〈千葉大院理〉
ソフトマターとは,コロイド,高分子,液晶,界面活性剤の自己集合構造,生体物質,などに代表されるやわらかな物質の総称である.元々はこれらの対象を扱う研究を包括して生まれた凝縮系物理学の一分野であったが,近年は食品・化粧品・医療・バイオテクノロジーなどの広範な応用分野・産業分野を支える基礎的な学問分野ともなりつつあり,この知見のもつ重みは増す一方とも言える.本書は,ソフトマター物理学分野における伝統的な研究対象(相分離現象,コロイド分散系,高分子,液晶,自己集合構造)について,基礎的な内容を初学者に向け入門的に紹介した教科書である.
Chapter 1とChapter 2では,ソフトマター系一般の解説とともに,その物理学的な取り扱いの肝となる分子間相互作用および自由エネルギーの一般論が展開される.著者はソフトマターを「エントロピーの大きな物質」と表現し,状態数の多さがやわらかさに対応する,と導入する.そして,ソフトマター系を構成する大分子や分子集団に働く種々の相互作用を紹介した後,理想気体の状態方程式やファンデルワールスの状態方程式を例に挙げながら分配関数と自由エネルギーの概念を説明する.Chapter 3では格子模型による正則溶液の混合自由エネルギーや化学ポテンシャルを用いて相分離現象が説明され,相分離ダイナミクス,濃度ゆらぎの散乱関数,界面の張力や厚みが議論される.Chapter 4ではコロイド分散系が扱われ,ランジュバン方程式や拡散方程式の枠組みで輸送現象が説明された後,ファンデルワールス相互作用や枯渇相互作用などの粒子間相互作用が簡潔に紹介される.Chapter 5からChapter 7では高分子鎖,高分子溶液,高分子ネットワーク(ゲル)についての記述が展開される.高分子鎖の統計則,セグメント相関やそのフーリエ変換としての散乱関数,高分子溶液の相分離を記述するフローリー-ハギンス理論,統計から現れるマクロなゲルの力学的性質,などの高分子物理学の伝統的なトピックが丁寧な導出で押さえられている.Chapter 8とChapter 9は液晶系についての解説である.等方的な液体相と格子を組む結晶相の間の性質をもつ熱力学的な安定状態を液晶相と呼ぶ.前半で様々な対称性の液晶相やそれを特徴づける秩序パラメータとフランク弾性の理論が導入され,後半ではフレデリクス転移,オンサガー理論(斥力モデル),マイヤー-ザウぺ理論(引力モデル),ランダウ-ドゥ・ジェンヌ理論などによる相転移現象の解説が続く.Chapter 10では両親媒性分子の熱平衡状態で実現する自己会合構造が説明される.
内容について特筆すべき点として,各系の相転移・相分離現象に関する記述が多いことが挙げられる.とりわけ著者の専門分野と思われる高分子と液晶に関する解説は充実しており,内容のおよそ半分がこれらのトピックに割かれていることは本書の特徴である.各章末にはいくつかの演習問題が付されている.解答例はついていないが,物理量の定量的な値を算出する,本文の数式の補助的な導出を行う,といった章の内容を確認する目的のものが多い.本文の丁寧な説明と併せ,読者にソフトマター物理学を実感し理解してもらいたい,という著者の親切心が表れているように感じた.それぞれの章の内容は,詳細な途中計算や直感的な描像も随所に記述され,丁寧な論理展開とともに説明されるため,基本的には数式を追いながら容易に読み進めることができる.とはいえ,おそらくは説明の本筋を見失わせない著者の工夫であると思われるが,天下り的に与えられる表式も多少は見受けられ,本分野の理解を深めるためには本書で概観を掴んだ後に他書を当たることも必須に思える.評者は,学部生・大学院生の頃に本書とは異なる「行間の広い」教科書に悪戦苦闘しながらソフトマター物理学を学んだ記憶がある.本書は分野の基礎的な内容を概説する貴重な「行間の広すぎない」和書であり,学部生など初学者には特に読みやすい入門書と言える.初等的な物理数学(テイラー展開・フーリエ変換・ベクトル解析)と熱・統計力学を学んだ読者であれば,独学でソフトマター物理学の基礎を身につけられるだろう.本書の導入に当たるChapter 1末の演習問題が「みなさんが物理学者になったつもりで,この続きを考えてください.」と締め括られているように,本書が手引きとなり,ソフトマター物理学分野に入門する研究者が更に増えていくのではないかと期待している.
(2024年3月5日原稿受付)
入門 現代の電磁気学;特殊相対論を原点として
駒宮幸男 著
講談社,東京,2023,xi+210p,22 cm×16 cm,2,970円[大学院・学部向]ISBN 978-4-06-532245-1
紹介者:角野秀一〈都立大院理〉
大学で電磁気学を教えている.電磁気学を教えていていつも思うことは,電磁気学自身は本質的には美しいのに,歴史的な積み上げによって定式化されたものは美しくなく,もう少しすっきりとした形で教えられないかということである.磁束密度を磁場と呼びたい気持ちを抑えつつ,日々授業を行っている.本書の著者も恐らくそのように感じており,執筆されたのが本書であるように思う.電磁気学があまり美しく見えないのは,まだ特殊相対論が知られていない時代に,電気や磁気の現象が定式化されていったからであり,また通常の電磁気学の教え方としても,その電磁気学の歴史と同じ流れで,電気や磁気の現象をまず教え,それらを定式化して教える方法が一般的である.電磁気学が本質的に美しいことは,電磁気学が特殊相対論を基盤として成り立っていることを理解して初めて分かる.そのため本書では,まず1章で特殊相対論を解説している.分量としては1つの章でありながら,ローレンツ変換,特殊相対論により現れる時間の遅れやローレンツ収縮などの現象,および特殊相対論で用いる数学的記法について,簡潔にまとめられている.2章では,相対論的運動学について述べられている.この章は,電磁気学を学ぶ上では,必ずしも必要ではないと感じるが,とくに素粒子の実験的研究などを志す学生にとっては,実験データを解析する上で必要となる事項が書かれている.これまで,相対論的運動学を学ぶための教科書はあまりなく,1960年代に書かれたR. Hagedorn著の英文の本が現代でもよく使われていると思う.本書は,電磁気学だけでなく,新しい相対論的運動学の教科書として,1章と2章を読むだけでも十分価値があると感じる.3章以降では,いよいよ電磁気学について述べられている.3章では電場について述べられているが,通常の教科書と異なるのは,ローレンツ変換の元で電場がどのように振る舞うのか議論されている点である.3章の終わりでは,電場のローレンツ変換から磁場が自然に現れることが示されている.4章では磁場について述べられているが,ここでも通常の教科書と異なっている.通常は,現象を定式化したビオ・サバールの法則を示し,そこから磁束密度の回転や発散,ベクトル・ポテンシャルなどに展開していくのが一般的であるが,本書では,逆の順番で,より原理に近い磁束密度の回転や発散,ベクトル・ポテンシャルについてまず説明し,現象を表すビオ・サバールの法則を導いている点も印象的である.4章の最後では,電磁場のローレンツ変換についてまとめられ,5章では,変動する電磁場とマクスウェルの方程式について述べられている.6章と7章は,実験技術の基礎となる実用的な内容になっている.6章では,複素インピーダンスを用いた交流回路について述べられている.交流回路に関する様々な例も取り上げられており,インピーダンスマッチングなど,実験における信号処理などで必要となる知識がまとめられている.7章では,荷電粒子の電磁場中での運動について述べられている.ガスを用いた放射線検出器での荷電粒子の運動を念頭に書かれていると思われる.最後の8章では,再び電磁気学と特殊相対論の理論的な内容に戻り,マクスウェル方程式に対応する電磁ポテンシャルの方程式や,相対論の記法を用いたマクスウェル方程式について述べられている.これらを通して,一見すると統一性がなさそうに見えるマクスウェルの方程式が,本来は統一性があり,すっきりとした形で記述できることが,本書の最後で示されている.
電磁気学に限らず一般的に物理学を最初に学ぶ時は,歴史に沿って現象を定式化していく方向で学ぶことが多いと思うが,全体像が掴めずなぜそのように定式化されるのか理解できないことが多い.ある程度知識が身についた後に,当初学んだ方向とは逆の方向で,原理に近い方から学んでいくと,全体像が見えて理解が深まることがある.本書は,そのように一度電磁気学を学んだ後で,もう一度学び直し理解を深めるための教科書として適している.また,本書の2章,6章,および7章辺りは,素粒子,原子核,および宇宙線などの実験的研究で役立つ内容が書かれており,これらの研究を志す学生にとって,持っておくと良いお薦めの本と言える.
(2024年3月24日原稿受付)
分光イメージング走査型トンネル顕微鏡
花栗哲郎,幸坂祐生 著
共立出版,東京,2023,viii+143p,21 cm×15 cm,2,420円(基本法則から読み解く物理学最前線32)[専門~学部向]ISBN 978-4-320-03552-2
紹介者:長谷川幸雄〈東大物性研〉
走査トンネル顕微鏡(scanning tunneling microscope, STM)は,表面原子を視覚化し,かつ電子状態に関しても局所的にプローブできる顕微鏡として,特に表面科学の分野において広く活用されてきた.そうした中,(表面科学ではない)物質科学を対象とし,しかも電子状態分布の視覚化(分光イメージング)に特化したSTM本が出版された.著者は,強相関物質等のSTM研究の第一人者である理研の花栗氏と,最近,花栗グループから独立して京都大学に異動した幸坂氏である.STMを用いた電子状態のエネルギー分散関係を探る手法として知られる準粒子干渉の詳細な説明や,分光イメージングによる銅酸化物や鉄系の非従来型超伝導体やトポロジカル物質の研究がコンパクトにまとめられた良本である.
内容を見ると,1章でのSTMの原理およびトンネル分光による電子状態測定の説明ののち,2章・3章では,高精度な分光イメージングを実現させるための装置開発やトンネル分光データの解析方法などが丁寧に解説されている.ピエゾ素子の共振周波数やトンネル分光におけるエネルギー分解能・セットポイント効果などSTM研究者にとっては重要項目が満載ではあるが,そうでない読者には読み飛ばして構わない章であろう.
4章の準粒子干渉に関する内容は,この本のハイライトの一つと言える.STMによる分光イメージングでは,欠陥等での電子散乱由来の定在波が実空間観察され,この定在波の解析から,元の電子状態の波数やエネルギー分散関係さらには電子散乱そのものの性質が導き出される.これまでの研究では,多くの場合,解析が容易な結合電子状態モデルが用いられるが,この章では,定在波の定式化からこのモデルが厳密には正しくないことが説明され,さらに実際の定在波(あるいはそのフーリエ変換パターン)には結合電子状態モデルでは説明できない点があることが明快に示されている.磁性散乱やスピン軌道相互作用による散乱についても言及し,著者らによる実験結果を元にしてその影響が実際に現れることを例示している.
5章から7章にかけては,それぞれ銅酸化物超伝導体・鉄系超伝導体・トポロジカル物質の分光イメージングによる著者らの研究が具体的に紹介されている.これらの章で何よりも秀逸なのは,各章の始めにそれぞれの物質に関するわかりやすい解説があり,読んだだけでそれらの物質研究の現状や課題について何となくわかった気にさせてくれる点である.例えば,5章の銅酸化物超伝導体の部分では,銅イオンの電子状態から始まり,モット絶縁体へのドープによる電子相図・電子秩序・超伝導ギャップの対称性・擬ギャップなどの簡潔な説明があり,続けて,実際の分光イメージングデータのオクテッドモデルによる解釈,さらにはコヒーレンス因子解析による超伝導ギャップの波数空間における位相情報の決定に至るまで,難しい内容ではあるが噛み砕くように丁寧に説明されている.6章の鉄系超伝導体における種々のクーパー対生成機構による超伝導ギャップ対称性や電子ネマティックの解説,7章のトポロジカル物質では,ディラックコーンで観察される特異なランダウ準位の形成や,個々の準位の分光イメージングでのスピン軌道相互作用の役割などの説明は,読み応えのある部分である.
STMに関する成書は,これまで表面科学研究者によるものが多いが,本書は物質科学の視点から書かれている.超伝導体・トポロジカル物質など具体例を交えて説明がなされていることから,こうした分野に関心を持つ研究者にも興味を持って読み進めることができるであろう.一方,STM研究者にとっても,高精度な測定を実現するための装置上の指針や,得られた分光データの精緻な解析手法が丁寧に記載されており,必読と言える.さらに,文献も整えられていることから,最近のSTM研究のトレンドでもある非従来型超伝導体や電子ネマティック・トポロジカル物質の学習用としても,極めて有用であろう.
(2024年3月25日原稿受付)
位相的データ解析から構造発見へ;パーシステントホモロジーを中心に
池 祐一,E. G.エスカラ,大林一平,鍛冶静雄 著
サイエンス社,東京,2023,x+257p,21 cm×15 cm,2,970円(AI/データサイエンスライブラリ"基礎から応用へ"4)[専門・大学院向]ISBN 978-4-7819-1580-7
紹介者:本武陽一〈一橋大〉
位相的データ解析は,ガラスや高分子材料,遺伝子ネットワークといった複雑現象の幾何的な理解において威力を発揮するデータ解析の枠組みで,近年ますます多様な分野で有効性が確認され注目が高まり続けている.位相的データ解析は,位相幾何学を用いたデータ解析手法の総称で,その代表的手法が,あるパラメータに応じて変化する穴の構造変化を定量化する幾何学的構造であるパーシステントホモロジーを用いた手法である.パーシステントホモロジーを用いることで,穴の数のようなトポロジカルな特徴だけでなく,穴のスケールや等高線情報などを含む特徴を抽出することを実現する.一方で,「古典的な特徴量とは様々な面で異なるパーシステントホモロジーは特に,ブラックボックス的に利用すると本来の性能が発揮できなかったり,バイアスを含むなど誤った結論に陥ったりする危険性をはらんでいる.(本書5.3節より抜粋)」という点に注意しなければならない.
本書は,位相的データ解析について,パーシステントホモロジーの理論的背景や実際のデータ解析手順,応用事例などを幅広く扱う書籍である.著者らは(応用)数学者であるが,材料科学をはじめとする多様な分野での応用研究にも携わっているため,本書は応用時に必要となる知識やデータ解析上の注意点を網羅しつつ,理論的側面も疎かにしない書籍となっており,これから位相的データ解析を試してみたい読者や,とりあえず試してみたがこれをどのように研究として精緻化させようか悩んでいる読者にも適している.
私自身は位相的データ解析を応用する研究に従事しているため,ここでは特に応用者(ユーザ)としての視点から,この書籍の概要を述べたい.この書籍は位相的データ解析を初めて使う時点から,最終的に得られた結果を研究として論文化するまでの一連の過程で必要となる知識が体系的かつ網羅的に含まれている.その内容は,私自身が初めて位相的データ解析を用いて研究を実施した際の次のような体験と合致する.まず位相的データ解析の概要を理解し(1章),ライブラリを用いて目的とする現象のデータに適用してみる(5章).その上で,機械学習や逆解析などを用いつつ現象についての情報抽出と物理的解釈を試みる(4章),その過程で,パーシステントホモロジーがあらゆるケースで一意に定まるのかといったパーシステントホモロジーの数理的な性質に対する疑問が発生するので,それを理解するために位相的データ解析の数理的背景(2章)を理解する.そしてさらに欲が出て,パターンとそのダイナミクスの両方を同時にパーシステントホモロジーに基づいて特徴量化できないかといった,発展的な内容に興味が出るので,それらの応用数学研究について調べる(3章).このように,本書籍はこれから位相的データ解析を用いた応用研究に挑戦する研究者にとってのマニュアルのような内容となっており,そのような研究者にとって必携書であると言える.
著者らもまえがきで部分的に述べているが,位相的データ解析の応用研究者(ユーザ)には,上述の流れ(1章→5章→4章→2章→3章)で本書を読みながら,実際のデータ解析を行うことをお勧めする.その際,5章はシリカ・金属ガラスや医用画像,ウィルスの遺伝的系統分析といった多様な対象・データ構造に対する応用例が豊富に含まれるため,自分の研究対象に位相的データ解析を適用する際の参考となるだろう.ただし,5章にはそれまでの章で出てくる用語や知識が用いられるため,5章にある引用にしたがって,適宜前の章を簡単に読み定理の概要などを理解しながら読み進めることをお勧めする.また,こちらも著者らがまえがきで述べているが,本書は位相的データ解析の数学を学びたい者もターゲットとして書かれてあるため,2章や3章の数理的な説明は,記述形式が数学的であるなど,非数学者が短期間で理解するには困難な内容である.そのため,これらの章(特に3章)をきちんと理解するには,それなりの時間と労力を使う前提で本書を読み進める必要があると思われる.その際には,類似書籍と比較して豊富に与えられた本書の具体例が理解を深める手がかりとなってくれるだろう.また,実際に手を動かす前に,機械学習を用いた一連の位相的データ解析の分析手順を知りたいという場合には,著者らが1章で提案している1章→4章→5章という読み方も有効であると考えられる.
本書籍は,(応用)数学者が書いた書籍であるにもかかわらず,パーシステントホモロジーをブラックボックスとして用いることの危険性など,応用者として重要な視点が多数含まれている.また,前述のようにこの本は位相的データ解析の応用研究をする際のマニュアルとも言える内容となっているため,この書籍によって参入障壁がより一層小さくなったと考えられる.さらに,位相的データ解析に関する最新の数学研究を理解するための基盤となり,応用研究者と数学研究者の知識・問題共有の円滑化が期待される.この書籍によって位相的データ解析の研究がますます活発化し,この複雑な世界の理解が深化されることを期待する.
(2024年4月11日原稿受付)
Pythonによる計算物理
大槻純也 著
森北出版,東京,2023,vi+215p,22 cm×16 cm,2,970円[専門~学部向]ISBN 978-4-627-17081-0
紹介者:苅宿俊風〈物材機構〉
世間ではプログラミングの重要性が叫ばれ今では小学校の学習指導要領にも含まれている.物理業界では今さら言うまでもなく,計算機の発展の歴史とともにデータ処理や数値計算,また近年では機械学習など幅広くプログラミングは重宝されてきた.学校教育の現場では「論理的思考力」といった側面から語られることが多く,特定のプログラミング言語が推奨されるようなことはないそうであるが,研究の現場では具体的に結果を出すことが要求され,かつプログラムを共有したり配布したりする必要に迫られることもあるので使うプログラミング言語はランダムというわけにはいかない.
表題の書籍はタイトルの通りプログラミング言語Pythonを用いた計算物理の入門書である.Pythonは近年機械学習・AIの分野で使われることが多いため人気も高く,ゆえに関連情報はインターネット上で比較的容易に入手できる.また数値計算ライブラリも充実しておりその点からも物理学徒・研究者が選択するメリットのある言語である.ただしPythonはスクリプト言語に分類され端折って言えば最速動作を指向するものではない.
本書では第1章でその点に言及した上で,Pythonを用いた計算を効率的に行うにはライブラリを上手く使うなどコツがいると説く.本書のテーマはまさにそのコツを伝授することであり,実際第1章の後半は主要ライブラリの利用方法が解説されている.
第2章では古典力学をテーマに常微分方程式の解法を学ぶ.ルンゲクッタ法・刻み幅制御などアルゴリズムの簡単な解説のあとロジスティック方程式,ニュートン方程式,LLG方程式がPythonプログラムを用いて解かれる.第3章では振動・波動をテーマに偏微分方程式の初期値問題・境界値問題が扱われる.手法としては差分法と行列表示,それによって導かれた連立方程式を解くための直接法・反復法が紹介され,それを適用してKdV方程式,時間依存シュレディンガー方程式,ポアソン方程式を解く方法が解説される.第4章は量子力学をテーマに固有値問題が扱われる.全体角化法や疎行列に対する反復法の基本が解説された後,量子非調和振動子や少数サイトのハイゼンベルグ模型・ハバード模型のエネルギー固有値の計算方法・計算結果が提示される.第5章では量子統計力学をテーマに数値積分としてガウス求積,非線形方程式の解法としてニュートン法,乱数を用いた手法としてモンテカルロ法などを学び,イジング模型の相転移の問題に応用する.
全体を通しサンプルコードが提示されながら解説が進むため,気軽に手元で試しながら物理で頻出の計算手法の多くを学ぶことができるようになっている(サンプルコードは著者のホームページからダウンロードすることもできる.「はじめに」を参照のこと.またPythonそのものに不慣れな読者向けに「付録」も用意されている).サンプルコード中心の構成とはいえ,アルゴリズムの解説も最小限ながらあるのでプログラムが実際何をしているのかも理解できるようになっている.また計算の不安定性など数値計算にありがちな失敗に対するケアも適宜はさまっているのも親切である.
本書の主な用法としては,初学者が計算機の傍に置き実際にプログラムを実行しながら計算物理の基礎をマスターしていくというものであろう.また計算物理の入門講義や演習コースの教科書としても利用できる.ただし前述の通りアルゴリズムの解説は最小限といったところなので専門家として羽ばたくにはもう一歩ということも言えるかもしれない.とはいえ数値計算には「習うより慣れよ」という面もあるので実践的な本書が役に立つことは間違いないであろう.
(2024年4月25日原稿受付)
カピッツァの手紙
斯波弘行 編・訳
ふくろう出版,岡山,2023,ix+288p,21 cm×15 cm,3,300円[一般向]ISBN 978-4-86186-883-2
紹介者:伏屋雄紀〈電通大基盤理工†〉
ソビエトがランダウをはじめとする傑出した物理学者を次々に生み,華々しい科学的成果を上げたことはよく知られたところである.独裁的な共産党政権が国の威信をかけて科学を振興したことに違いはないが,それが科学を推進するための恵まれた環境であったかといえば,それはおそらく否であろう.液体ヘリウムの超流動を発見したことでノーベル物理学賞を受賞したカピッツァも,政権から国際的幽閉の扱いを受け,設備も人材もままならず,研究上の艱難を強いられた中でその偉大な発見を遂げた.
本書はカピッツァ自身が書いた114通の手紙から構成される.第三者に読まれることを意識していない手紙は,評伝や自伝よりもはるかに書き手の肉声を伝える.1)本書を読み進めれば,不断の努力や不屈の精神といった言葉ではとても言い尽くせない,カピッツァの悲痛なまでの心の叫びが迫ってくる.
単に手紙を時系列に並べただけでは話題が散漫になり,全体像が見えにくい.しかし本書では,およそ時系列順に並びながらも適切に編纂されているため,全体像や流れが掴みやすい.ケンブリッジ時代(第2章),ソ連からの出国禁止を受けた時代(第3~5章),ドイツとの戦争の時期(第6章),公職剥奪の時期(第7章),公職復帰からノーベル賞受賞まで(第8章).そのときどきによって手紙の宛先は家族や研究者仲間(ラザフォードやボーア,ディラックなど)から,政治家や科学アカデミーの指導者宛へと移り変わる.それに伴い,書かれる内容も日々の研究に関するものから,研究所の運営,大学の教育改革,国家と科学行政のあり方へと推移する.それはあたかも,研究者人生で直面する様々な課題が例題として示されているかのようである.カピッツァの手紙からは,そうした課題について本人から直接教えを受けているような息遣いが感じ取れ,大いに学ばされる.少々長くなるがいくつかを抜粋してみる:
「経験によれば,実験研究者と理論研究者の共同研究は,理論が実験との関係を失わず,同時に,実験データに然るべき理論的な総括を与え,すべての研究者に広い科学的展望を与えるための最良の方法です」(モロトフ*1宛)
「偉大な人間の第一の特徴は,自分や他人の間違いを気にしないということです.一方,取るに足らない人間は,専ら,人々の間違いについて考えたり,語ったりします」(妻宛)
さらに本書で印象的なのは,70年ほど前の独裁的な政権の指導者に宛てた手紙にもかかわらず,2)現在の日本にもそのまま通用するメッセージが多く見られることである:
「真の科学は,どんなにそこへ引き込む力があろうとも,あらゆる政治的激情との戦いの外側にいなければならないと私は信じています」(モロトフ宛)
「今は我が国の研究者への配慮が著しく少なくなり,非常にしばしば,官僚的悪平等が広まっています」(アンドロポフ*2宛)
また,科学の振興のためには"学会の世論"に耳を貸すべきであるという考えを,時の最高指導者に対して再三訴えている:
「学会の世論なしでは先進的科学を創造することができないにもかかわらず,最近我が国の科学会の世論が放置され,科学の発展のために活用されていない」
「もし科学が研究者たちの世論に立脚しているならば,そのときに初めて,科学の計画的な発展のみならず,先進的で大胆な科学が我が国で存在できます」(共にフルシチョフ宛)
カピッツァのいう"世論"とは,いわゆる国民の声ではなく,科学者コミュニティの声を指す.物理学の場合,それはまさに本誌読者の声に相当し,学会誌こそが"学会の世論"を醸成する場たり得るのではないかと考えさせられた.
カピッツァからの手紙が,著者の丁寧な手作業を経て,時間を遠く隔てた現代日本の私たちに届けられた.3)それを受け取った私たちはカピッツァにどう返信を出すのか.それが問われているように思えてならない.科学研究・行政のあり方について見直しが求められている今だからこそ,カピッツァの声にじっくり耳を傾けたい.
注
1)第三者の読み手を想定していないため,当人どうしでしか伝わらない情報や表現を含んでいることが書簡集の欠点であろう.本書では,そうした部分には著者によって適切な脚注が添えられており,読みづらさを感じることはない.
2)独裁的な共産党政権下にあって自由な発言のできない時代に,スターリンやフルシチョフなど,ソビエトの最高指導者たちに鋭い意見を送りつけていることには驚かされる.しかし,(その代償として)9年に及ぶ公職追放を受け,研究者として極めて厳しい状況に置かれることにもなる.
3)カピッツァの書簡はこれまでロシア語でしか読むことができなかった.今回,著者が労を惜しまず原語から翻訳されたことで,初めて一般読者が読めることとなった.著者の献身的な作業に敬意と謝意を表したい.
(2024年4月30日原稿受付)
† 現所属:神戸大院理
*1 人民委員会議議長(首相)などを歴任,スターリンの片腕.
*2 プレジネフの後の最高指導者.
流体力学超入門
E.ラウガ 著,石本健太 訳
岩波書店,東京,2023,v+155p,18 cm×13 cm,1,870円(岩波科学ライブラリー323)[学部・一般向]ISBN 978-4-00-029723-3
紹介者:中垣俊之〈北大電子科研〉
本書は,Eric Lauga氏の著した洋書Fluid Mechanics: A Very Short Introduction(2022年出版)を石本健太氏が和訳した本である.Lauga氏は,現在,ケンブリッジ大学の応用数学の教授であり,トリニティカレッジのフェローである.2020年にはThe Fluid Dynamics of Cell Motility(Cambridge Univ. Press)という専門書も出版しており,間違いなくこの分野を先導するお一人である.
今回紹介する原本のタイトル「A Very Short Introduction」とは,Oxford University Pressのシリーズタイトルで,理系文系を問わずあらゆる学問領域をカバーせんと,これまでに700あまりのタイトルが出版されており,53カ国語に翻訳されて販売部数累計1,000万部超とのことである.まさに,世界的な知の泉のようなシリーズであろう.そこでの流体力学である.
今回紹介する本は,8つの章からなる.1)「流体」とはなんだろうか?,2)流れがあると「粘性」が見えてくる,3)世界に溢れる「管内流れ」,4)「次元」で現象の本質をつかむ,5)流体力学の歴史を変えた「境界層」,6)「渦」を見る,「渦」を使う,7)パターンを生み出す「不安定性」,8)「流体力学」の未来.どれも20ページほどでコンパクトに述べられている.
1章では,分子から連続体記述へと話がはじまり,圧力と静力学の話に移って浮力の仕組みを説明したのちに,分子の観点から表面エネルギーを説明して濡れの話で閉じる.2章では,いよいよ流体が動く話になる.それを表すのに流速場が必然的に現れて,変形の話になる.変形は,基本的な3つの運動,すなわち並進,回転,伸長の足しあわせで表されると説明したのちに,圧縮性の話に移る.流体が圧縮されたり膨張したりする場合には,上記3つの基本的な運動の他に湧き出しと吸い込みを加えて扱う必要があるという.しかし,圧縮性は流体の運動が十分早く起こる場合のみ実効的であって,日常的な多くの流れでは空気でさえも非圧縮性として扱える.その時,流速場には,発散がゼロという強い条件が課せられる.最後に流体が動く時に作用する独特の力,つまり粘性応力の特徴を述べてナビエストークスの方程式を書いて終わる.この式を解くとか,解析するとかは,後の章で一切出てこないが,基礎的な方程式を愛でるために記されている.次に3章である...という具合に全章の流れを説明したいのだが,誌面が足りないので興味のある方は読んでいただければと思う.
その後の章で取り上げられる,次元解析や不安定性,境界層,渦,管内流れの考え方は,流体力学の真骨頂であり,非線形問題やパターン形成問題へもつながる面白どころである.これらを,必要最小限の簡単な関係式だけを用いて,上手な表現で説得している.流体力学の諸現象は,一方で式による正確な記述が整備され続けており,かつ解析技術もまだまだ日進月歩である.「基礎方程式ができたので終わり」なのではなくて,実は世の中には未解明の興味深い流体現象が沢山あるので,「基礎方程式ができたからこそいよいよ始まった」と言うべき現況である.
この本の希有な点は,数式の解析を深々と理解した大家が,数式の表すコアの部分を改めて日常言語で巧みに語り得ていることだと思う.日常言語で説明しようとすると往々にして式の説明になりがちなところを,そう感じさせない語りになっていて,読み物として面白い.うっかりするとさらっと読み通せてしまうが,ちょっとした説明のひっかかりに拘ると,著書の表現の意味するところを考えざるを得なくなってしまって,やむなく何度も読み直してしまう.
ここで,訳者の石本氏についても一言触れておきたい.石本氏は,現在,京都大学数理解析研究所の准教授であり,専門は応用数学,流体力学,数理生物学である.生物の遊泳に関する流体力学において,有名な「帆立貝定理」に関する数理解析で世界的に名を馳せている方である.近年,『微生物流体力学;生き物の動き・形・流れを探る』(サイエンス社)という専門書も著している.
ちなみに,この原本のオーディオブックも発売されており,流暢な英語での朗読が聞ける.英語の耳慣らしに聞いてみると,この本がより身近に感じられて,流体力学へのさらなる興味が鼓舞される思いがした.私は,原生生物の行動を30年以上研究しており,遊泳や這行の物理モデルを考える時に,流体力学のお世話になる.流体力学は私にとって十分に難しく,色々な本を読みかじりながら,計算力と直感イメージを養っている途上である.この本は,私のこれまでの知識を相互に関連づけて整理し直してくれた実にありがたい本である.私にとって,ラウガ氏は面識はないものの憧れの研究者のお一人であり,また石本氏は最も信頼する研究者のお一人であると同時に今後どんな研究を展開していかれるのかとても気になる研究者でもある.お二方から受けたこの本の恩恵に感謝したい.
(2024年6月11日原稿受付)
システム生物学入門
畠山哲央,姫岡優介 著
講談社,東京,2023,vii+279p,26 cm×18 cm,4,950円[大学院・学部向]ISBN 978-4-06-533434-8
紹介者:前多裕介〈京大院工〉
システム生物学は1997年ごろに登場し,ウェット(実験)とドライ(計算)の融合を掲げた新しい生命科学分野である.1990年代後半~2000年代前半は生命科学の変革期で,ヒトゲノム解読後のポストゲノム時代にあった.振り返れば,ゲノム情報解析など計算生命科学への注目が高まり,生命システムを分子の詳細ではなくダイナミクスの普遍性で捉える動きが強まったと言える.そして現在も生命科学と物理学の関わりが深化しており,これからシステム生物学を学ぶための邦書入門書が待ち望まれていたところである.
本書序説(第1章)と第I部(第2章・第3章)は数理的手法と統計力学基礎論を約80ページでまとめている.時間変化する生命システムに焦点を置き.システムの時間発展を表現するための力学系理論の入門(第2章)に続き,統計力学・熱力学の入門(第3章)まで,後の章を読み進めるために必要な基礎論が示されている.「生命システムの理解に資するものを」という著者の理念は,酵素反応のミカエリス=メンテン式や化学修飾の統計力学モデルの導入に表れている.タンパク質や核酸分子が複数部位でリン酸基やアセチル基を付加される生化学反応(修飾反応)は重要な制御メカニズムであり,この化学修飾を例に,化学修飾状態の確率分布を求め,速度論と統計力学の結果が一致することを示している.具体的な生化学反応を出発点とする統計力学の導入は構成として優れている点であり,生命現象の物理的モデリングを学ぶ上で必読の章である.
第II部「細胞のシステム生物学」は,細胞内における酵素の化学反応とその制御機構に関するもので,生体分子間の協働性(第4章),その非自明な反応制御機構(第5章)をまとめ,第6章以降ではシステム生物学で活発に研究がなされてきた走化性やリズム現象に展開される.第6章で扱う走化性とは,化学物質の濃度勾配に応答して移動する性質のことを指し,特に大腸菌のシステムが有名である.本章では化学誘引物質の濃度検知から濃度変化への適応が関わることが概説され,朝倉=本多モデルから適応ダイナミクスの本質を捉えたのち,フィードバック機構・フィードフォワード機構を定義し,その安定性解析へと進む.第7章でも概日時計システムを取り上げ,分子実体が不明な時代における慧眼的な数理モデル,2000年代に発展した合成生物学,そしてシアノバクテリアで発見された「時計タンパク質の概日リズム再構成」までが一望できる.遺伝子発現のフィードバック制御という現象の一側面から先に進み,時計タンパク質の化学修飾反応の協働性および活性化状態の律速反応の共存が概日時計の三つの生理的機能(リミットサイクル振動,外界との同期現象,温度補償性・栄養補償性)の発現に本質的であることを鮮やかにまとめている.日本の研究者がシステム生物学の発展に確かな貢献を与えてきたことがわかる点も一読の価値がある.
第III部の「代謝のシステム生物学」では,大腸菌の中心代謝経路を題材として,多数の化学物質と複数の化学反応から構成される反応系のモデリングが紹介されている.化学反応が進むことで生成・消費される分子数の増減を数値化し,代謝経路のネットワーク構造を化学量論行列と定める代謝反応モデリングの出発点(第9章)である.この量論行列には反応回路の構造情報が含まれており,各フラックスの上限・下限の制約のもとで,可能な定常状態のうち実現されるのは増殖因子の生成速度が最大化された状態であるとするのがフラックスバランス解析(第10章・第11章)である.また,具体的な反応系を扱う動力学的アプローチ(第12章)においては,フラックスバランス解析では定常状態が前提にあったものの動力学的にはその成立が自明でない点が強調される.その例が低栄養条件下では生育できるにもかかわらず豊富すぎる栄養条件では増殖停止してしまう「栄養加速死」であり,高栄養条件下では増殖因子の前駆体の反応フラックスに歯止めが効かずエネルギー分子が枯渇してしまうということが起こり得る.紹介者の所属である化学工学分野においても化学量論は重要であるため,他分野の読者にも勧めたい内容である.
第IV部は「進化・生態系のシステム生物学」である.ここでも同様に力学系理論が有効であり,個体数増大と種間競争のレプリケーターモデル(第13章)や生命進化の確率モデル(第14章)を取り上げ,細胞や個体の相互作用が重要となる生態系と進化に視点を移している.大腸菌株のフラックスバランス解析と適応度地形をもとに,「変異」と「選択」を経て遺伝形質の進化ダイナミクスを計算する遺伝的アルゴリズム(第15章)にも豊富な図解があり,細胞内代謝から生態系・進化までを一望できる.
本書には専門的な内容だけでなく,物質科学的な普遍性(第8章)など一般的な興味を惹きつける論考もあり,著者らの挑戦的精神が読者への期待と共に綴られているのも好奇心を駆り立てるストーリーがあって面白い.本書を通じて,生命システムの本質を捉えた理論は分子生物学の進展と共に標準モデルとなり,一方で新たな分子機構の発見によって旧来のモデルが覆り再びシステムの本質が問われる,といったドラマがあったことを窺い知ることができる.システム生物学の発展の数々を学ぶ一冊として,専門家はもちろんのこと,生命科学と物理学の双方に関心を持つ学生や非専門家にもお勧めしたい.
(2024年8月13日原稿受付)