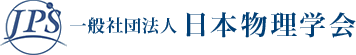会誌Vol.80(2025)「新著紹介」より
このページでは、物理学会誌「新著紹介」の欄より、一部を、紹介者のご了解の上で転載しています。ただし、転載にあたって多少の変更が加わっている場合もあります。また、価格等は掲載時のもので、変動があり得ます。
準結晶の科学;構造と物性
佐藤憲昭,石政 勉 著
名古屋大学出版会,名古屋,2024,viii+348p,22 cm×16 cm,5,940円[専門~学部向]ISBN 978-4-8158-1140-2
紹介者:北原功一〈防衛大学校〉
本書によると,「準結晶」とは「準周期性」を持つ物質のことである(IUCrの定義とは少し異なる).本書は準結晶の構造と物性に焦点を当てたもので,物質科学研究者にこの不思議な物質の面白さを広く伝えることが目的であるとしている.物性といってもいろいろあるが,低温の電子物性が主であり,準結晶の特徴的な高温熱物性などの記述は限定的なので注意が必要である.準結晶の低温電子物性,特に超伝導や強電子相関効果は,著者らの研究を皮切りとして,現在進行形で発展の目覚ましい分野であり,その内容を概観できるというだけでも,類書にはない,本書ならではの価値があるだろう.
第1章は「準結晶入門」として,比較的平易に「準周期性」のイメージが説明されている.一変して,第2章と,第4章から第6章では,準結晶やその近似結晶の構造を理解するための基礎が,多くの数式を伴って説明されている.準結晶の構造に馴染みのない読者には読み応えがあると思われるが,著者も述べている通り,分かりにくいと思った箇所を読者自身で作図してみることなどが,理解を深める近道となるだろう.第7章では実験的に発見された様々な準結晶や近似結晶が紹介され,第8章では準結晶の形成条件について,簡潔ではあるが,様々な視点から解説されている.著者らの研究と関連してか,構造パートでは正12角形準結晶の記述が類書と比較して充実していると思われる.
第3章では物性パートの基礎が解説されている.第9章から第12章までの各章では,準結晶の電気伝導,超伝導,局在磁性,強電子相関効果について,著者らの研究を中心に比較的最近の成果を概観することができる.具体的な項目は目次を参照されたい.学部4年生から大学院修士課程の学生を念頭に,他書を参照しなくても理解できるようになっているとされているが,概要を知るだけではなく,研究のために本格的に学ぶのであれば,第3章の冒頭に提示されている文献などの参照は必須だろう.
参考文献番号の振り間違い,数式や論理,概念図の誤りなどが散見されるのは残念である.参考文献の図を改変した図で,改変の内容が書かれていないものがあることも望ましくない.例えば,図4.16(b)に点群m35の誤った概念図が示されているが,参考文献にあるのは(d)の点群235の図だけであり,(b)は著者により加えられたようである.しかし,読者は原論文の図が間違っていると誤認するおそれがある.また,各物性の章では,紙面の都合で深掘りできないとしても,関連する研究を一通り参考文献として挙げてほしかった.例えば,準結晶の電気伝導について,マヨウらの理論的な研究に全く触れていないのは違和感がある.
本書や関連する研究分野では,観測された現象が「準結晶特有」であるかどうかがしばしば議論されている.この「準結晶特有」という言葉の正確な意味は本書で述べられていないが,「この現象は近似結晶においても見出されているから準結晶特有ではない」といった趣旨の記述からすると,それは,「準周期性」を持つ「準結晶」では起こり得るが,「周期性」を持つ「結晶(近似結晶を含む)」では起こり得ない現象と位置付けられていると思われる.そうであれば,近似結晶の格子定数よりも短いスケールでは,準結晶と近似結晶は非常に似ていることから,そのスケールで特徴付けられる現象は「準結晶特有」にはならないだろう.また,少なくとも理論的には,準結晶にいくらでも似ており,格子定数がいくらでも大きな近似結晶を想定できることから,「準結晶特有」の現象が存在するとすれば,それは無限大の長さのスケールで特徴付けられるものに限られると思われる.しかし,その実証に必要な超巨大近似結晶と準結晶を作り分けることは現実的ではない.そもそも現実の物質は有限サイズなので,それが準結晶の一部を切り取ったものなのか,超巨大近似結晶の一部を切り取ったものなのかを区別できない.IUCrによる「準結晶」の定義は,言わば「実験的に準結晶と区別できないもの(前述の超巨大近似結晶を含む)を準結晶とみなす」というものであり,「準周期性」を前提とする定義に代わる現実的な落とし所となっている.「準結晶特有」にも,何らかの実証可能な意味づけが必要であり,それは個々の研究者がそれぞれの考えや目的に沿って設定すればよいのであるが,本書で著者なりの落とし所が提案されていてもよかったのではないかと思われる.一方で,この基本的な問題に安直に答えを与えるのではなく,これからの研究者に委ねようという考えも支持できる.今後のこの分野の発展に期待したい.
(2024年8月8日原稿受付)
真空ハンドブック(3訂版)
株式会社アルバック編
オーム社,東京,2024,xxv+348p,26 cm×18 cm,13,200円[専門・大学院向]ISBN 978-4-274-23177-3
紹介者:荒川一郎〈学習院大〉
本書は,真空機器開発者と利用者を対象としており,A)真空科学・技術に関する基礎知識,諸現象を記述する公式・数式,真空装置に用いる機器部品と諸材料の規格,関連する物質・材料の物性データを網羅したものである.また,B)真空環境のもとに行われ,真空技術が本質的に重要な役割を果たす,薄膜作成,表面分析,プラズマ応用技術に関する基礎知識と諸データをまとめてある.
オーム社からは,1992年に第1版,2002年に新版,そして2024年にこの3訂版が出版されているが,このハンドブックの前身は,日本真空技術株式会社(現株式会社アルバック)内で1963年にまとめられた『真空技術資料』に遡る.1972年に"Vacuum Handbook"として作成されたものは,A4判,96ページである.その内容は,前述のA)の範囲にほぼ限られていた.この本は,同社内で真空機器の設計・開発の場でまさにハンドブックとして活用されたのはもちろんであるが,社外(大学,研究機関)でも真空実験装置等の設計にあたって利用されていた.
本書は,アルバック社内で編集チームが組まれ,各部署から最新情報を集めて,旧版に対する記事の追加,改訂,データの更新・修正を積み重ねてきている.1978年には同社創立25周年を記念して,前述のB)の分野を含む『真空ハンドブック』A4判,300ページがまとめられた.この版に携わった社内の40名ほどの方の氏名が記されている.これらは非売品であったが,前述のように社外の需要も多く,必要に応じて外部にも配布されていた.1992年にオーム社から出版されるに至った経緯にも,そのような事情があったのではないかと想像している.なお,オーム社からの出版となっても,アルバック社内の人員によって編集が行われる方針は継続されている.
内容についてもう少し詳しく紹介する.本書が目指したのは,真空科学・技術とその応用に関する情報をできるだけ網羅的に集積することであろう.真空技術で用いられる用語と定義は,2021年に改正されたJIS Z 8126による最新のものが冒頭にまとめられている.真空装置を構成する諸機器を表す図記号は,2023年にJIS Z 8617に定められたが,本書にはほんの一部しか載せられていない.著作権が壁となったらしいが,JIS記号の普及のためには収録してほしかった.
真空技術の中で,真空の作成と計測は,対象となる気体の連続流体としての,また分子流体としての性質に関わる.気体の性質を表す諸公式・計算式等は簡潔にまとめられているが,その導出にまでは立ち入っていない.真空計の原理,様々な形状の配管の気体のコンダクタンスに関しても同様である.それらの詳細は,真空科学に関する教科書等に任せることとして参考書が挙げられている.気体種ごとの諸定数に関しても,出典が明示され表にまとめられている.ただし,例えば四極子形質量分析計のように,一般的な教科書に詳しく触れられていない事項に関しては,その原理が解説されている.ハンドブックではあるが,必要に応じて教科書的な解説も載せるという方針は,本書全体を通して貫かれている.
真空を作成する技術,すなわち真空ポンプに関しては,真空ポンプを開発する側の情報ではなく,利用者のための情報に徹している.必然的に同社の製品の仕様の列挙になっており,教科書的記述とは異なるが,より具体的な数値が与えられているという点で利用者の役に立つ.
真空を保持する技術は,容器に関する問題である.真空装置を構成するための真空フランジとガスケットに関しては,世界標準がほぼ確立されており,その規格がまとめられている.真空装置の気体導入に広く使われている小口径の管継手の規格は,同社の製品でないゆえに載せられなかったと思われるが,利用者の便のためには載せて欲しかった.
容器を構成する材料についても詳しい情報が得られる.純金属,ステンレス鋼,アルミニウム合金,その他の合金,セラミックス,ガラス,エラストマー,等々の,機械的,熱的,電磁気的,化学的性質が,網羅的とまでは言えないが,おそらく入手可能な限り集積されている.材料からの気体放出は,真空に関わる最も大きな問題である.種々の材料の気体の吸蔵,透過,放出,表面処理による違い,などの実測値が集められている.もとよりそれらは材料の履歴,環境により変化するので,注意が必要であるが,実用的に大変参考となる.
真空技術は,研究,開発,生産,それぞれの分野での基盤技術となっているゆえに,他の技術との交錯が必然となる.低温,高温,電磁場,電子,イオン,光を真空の中で扱うときに必要な諸データは大変便利である.
本書の後半には,真空技術が開拓の一翼を担ってきたプラズマ・放電,表面分析,成膜,表面加工などの応用分野に関する基礎知識,諸データがまとめられている.それらの分野の教科書に比べると,実用的諸データが集積されているのが特徴と言える.これらの分野の発展は速いので,引き続き内容の更新が続けられるべきであるが,それぞれの分野に携わる研究者・技術者に役に立つものとなっている.
(2024年8月26日原稿受付)
解析力学;基礎の基礎から発展的なトピックまで
渡辺悠樹 著
共立出版,東京,2024,xv+332p,21 cm×15 cm,3,630円[専門~学部向]ISBN 978-4-320-03631-4
紹介者:中嶋 慧†〈電通大院情報理工〉
本書はその副題「基礎の基礎から発展的なトピックまで」が示すように,偏微分,ベクトル解析,行列などの基礎事項の復習から始まり,自発的対称性の破れや電磁場のディラック括弧などの発展的内容までを取り上げた本である.また,オーソドックスな内容についても,類書にあまり見られない詳しい解説があり,参考になる.例えば正準変換の解説が詳しい.この点は著者も強調しており,「はじめに」にも「母関数によって変換されること,ポアソン括弧を不変に保つこと,正準方程式を共変に保つこと,という正準変換の種々の定義の関係は,結局どうなっているのか」について「類書の記述を改善できたのではないかと自負している」とある.隠れた対称性についての解説も優れていると思う.
本書は第0章から第12章までと3つの補遺からなる.第0章は偏微分,ベクトル解析,行列の復習である.第1章から第3章までが第I部「ラグランジュ形式の解析力学」である.第1章は「ニュートン力学の復習と変分法の導入」である.変分の記号としてδqを使わず,代わりにεを使っている.無用の混乱を与えないようにするための配慮であろう.仮想仕事の原理とダランベールの原理は取り上げていない.ラグランジアンの存在条件としてヘルムホルツの定理が解説されている.第2章は「ニュートン力学のラグランジアン」,第3章は「拘束条件の取り扱い」である.第4章と第5章が第II部「対称性」である.第4章「ニュートン力学の対称性」では,ラグランジュ形式の対称性が詳しく解説される.自由質点のラグランジアンを対称性から導く議論では,空間の一様性,時間の一様性,空間の等方性を要請しただけでは等速直線運動が導かれるとは限らないことを指摘している(演習問題となっている).隠れた対称性の解説があり,ルンゲ・レンツベクトルの例が演習問題となっている.第5章は特殊相対論である.
第6章から第8章までが第III部「ハミルトン形式の解析力学」である.最初に述べた正準変換の解説をはじめ,この部分が非常に詳しく解説されているのが本書の特長であろう.脚注で他の文献についての注意(間違いの指摘や,著者が納得いかなかったことなど)が述べられている.
第9章から第12章までが第IV部「発展的内容」である.第9章は「剛体運動」である.第10章「自発的対称性の破れ」は本書の大きな特徴であろう.著者は,非相対論的な系の自発的対称性の破れに関する理論の開拓者の一人であり,10.2.5節で著者らの研究が解説されている.10.3.2節「時間結晶」も著者の専門分野である.この章は初学者には難しいかもしれないが,よい刺激を与えるだろう.第11章「古典場の理論」では,電磁場だけでなく,ゴールドストーン模型やグロス・ピタエフスキー模型,ギンツブルグ・ランダウ理論が解説される.11.1.4節「ラグランジアン密度の不定性」では,他の文献であまり見ない内容が解説されている.この議論は,例えば(4次元時空において)電磁場のラグランジアン密度に ε μνρσFμν Fρσを含めなくてよいことを説明するのに必要である.第12章は「特異系の取り扱い」であり,電磁場のディラック括弧も解説される.
第1章から第12章までの各章に演習問題が1問から4問あり,理解を助ける.どの問題にも補遺Cで解答が与えられている.また,本書はスピンの解析力学についても解説している.本書にはWebのサポートページがあり,著者に質問したり誤植を報告したりできるようになっている.これも本書の大きな特長であろう.
本書は,解析力学の入門書として利用できるだけでなく,既に解析力学を勉強した人や,解析力学を教える立場にある人が読んでも得るものが多いであろう.今後の定番の教科書になるのではないだろうか.
(2024年9月16日原稿受付)
†現所属:筑波大数理物質
物理実験のためのアナログ回路入門
谷口 敬,笹尾 登,森井政宏 著
コロナ社,東京,2022,viii+187p,21 cm×15 cm,2,860円[専門~学部向]ISBN 978-4-339-00982-8
紹介者:八幡和志〈防衛医科大〉
電子回路は物理学だけでなく社会全体を支えている基盤技術である.もちろん物理学と電子回路も密接で,実験をするにも理論計算をするにも電子回路なしでは済まされない.もちろん,電子回路は電磁気学や量子力学,物性物理学,電気化学に基づいているので,物理や化学で理解できるものである.しかし,大学で電子回路学科が成立するほどに,大規模で多彩,構造的な知を持つので,物理学者が電子回路に通暁するのは難しい.とはいえ,アナログ的に観測される量子現象を利用した量子計算機と,従来のコンピューターをインターフェースし融合させた新規な計算機を開発するためには,物理現象としてのアナログ回路の理解と技術がますます必要になっているであろう.ここで,電子回路をアナログ回路とデジタル回路と対立的に分けて扱うことも多いが,デジタル回路もアナログ回路技術に立脚しているので,デジタル回路を扱う際もアナログ回路の技術を学ぶことは重要である.
さて本書,『物理実験のためのアナログ回路入門』は,主に著者の一人で2011年に逝去された谷口敬氏が電子回路セミナー用に記されたテキストに基づき,笹尾登氏と森井政宏氏が入門的な解説や追加修正を補って作られた.まえがきに記されたように,大学初年次程度の数学と物理の知識を前提として書かれており,実用的な使用可能な回路の設計能力を身につけることを目標としている.具体的には,受動部品を使った周波数フィルター回路や市販のオペアンプを使った電圧増幅回路を学んだうえで,研究用のアナログ回路を開発するために必要となる内容が物理学者向けにコンパクトにまとめられている.
なお,例として高エネルギー物理学で使われるプリアンプが取り上げられており,一方で水晶発振回路,ヘテロダイン,ロックインアンプやアナログメモリーといった回路は取り上げられていない.これらについては別に学ぶ必要があるが,本書の知識があれば理解が容易いであろう.
この本の構成は,プリアンプを作るために必要な知識としてのアナログ回路を,物理学者のセンスでブレークダウンされている.まず,アナログ回路の基礎事項として,オームの法則やキルヒホッフの法則から始まって,伝達関数や電圧源と電流源・入出力インピーダンス・伝送線がまとめられている.ここでも具体的な同軸ケーブルをとりあげ,伝送線としての性質,特性インピーダンスを示しているのは,初学者にとって親切であろう.
次にトランジスタは,電子回路の中核でありながら物理学的に理解しにくい.このトランジスタの動作は,粗視的にはベース電流によるエミッタとコレクタ間の抵抗の変化である.これを,実験を通してより詳しく,微視的な電流増幅率,エミッタ抵抗,アーリー効果,温度依存性,端子間寄生容量まで取り上げている.さらに,トランジスタを組み合わせた基礎回路として,オペアンプを構成する差動アンプ,定電流源と電流ミラー,カスコード接続などを取り上げている.なかなか,他の電子回路の入門書では,まとめて解説されていないのでこれらはとても有難い.なお,オペアンプについては,市販のオペアンプのデータシートを読みとり,回路を設計するために必要十分な基礎的な解説がコンパクトにまとめられている.製品としてのオペアンプは市場寿命があり,例えば,本稿を書いている時点で物理学実験の教材として親しんできたTexas Instruments社のLM741(uA741)も新規設計について非推奨となった.*1このように,個々のオペアンプの機種について解説をしても,時とともに陳腐化していくので,これは良い判断に思う.
さて,本書の一番の特色は,例として取り上げている検出器用プリアンプと波形整形アンプの開発であろう.つまり,光検出器や放射線検出器からの電流信号を電圧信号に変換し増幅する回路と,増幅された信号を成形する回路の設計である.まず,熱雑音とショット雑音,これらの合成と信号電流を比較することで,アンプのS/N比の設計を示している.次にプリアンプの基本回路として,エミッタ接地,コレクタ接地型の増幅回路とJFETを入力段に用いて入力インピーダンスを高くした回路を取り上げている.また,増幅した信号をポール・ゼロ補償回路,多段積分回路とベースライン再生回路を組み合わせて,測定しやすい信号波形に整形する回路も示している.これらについて,トランジスタなどが7個程度まで使われた少し複雑な回路の具体例がいくつも例示されている.初学者がトランジスタの数が多い回路を考え付くのは難しいので,これらの回路例はとても有難いものである.
巻末では,増幅した信号をコンピューターに取り込むためのアナログ-デジタルコンバーター(ADC)について触れられている.本書で触れられているようにADCはいろいろなアーキテクチャーがあるが,いずれもコンパレーターを基礎技術としているため,変換結果は四捨五入ではなく切り捨てになっていることと,ADC自身の変換エラーがあることを付け加えておく.また,おそらく本書の執筆以降にFPGAを含むSoCに14 bit-5 GS/sといった高性能なADCが内蔵され,再配線可能なデジタル回路とアナログ回路を混載したPSoCなども登場した.
このように,本書は入門書というより,高エネルギー物理学実験だけでなく,一般物理学実験や物性実験,あるいは計算機物理学といった広い分野で,研究用の電子回路を開発する際に,是非,目を通しておきたい専門書である.
(2024年9月25日原稿受付)
*1 2025年3月5日時点では,LM741CN/NOPBとLM741C-MWCのみが入手できる.
What Is Energy?; An Answer Based on the Evolution of a Concept
R. L. Coelho著
Springer Nature, Cham, 2024, ix+195p, 24 cm×16 cm, €117.57(History of Physics)[一般向]ISBN 978-3-031-51854-6
紹介者:小長谷大介〈龍谷大経営〉
「エネルギーとは何か」.タイトルが示すように,本書はエネルギーが何であるかを探っている.主な題材は19世紀に行われたエネルギーの関連研究であり,その歴史を踏まえて,タイトルの問いに応えようとする.「エネルギー」の物理的な意味を辞書で確認すると,「物体や系がもっている仕事をする能力の総称」,「閉じた系で普遍的に保存されるという意味で最も基本的な物理量」とある.「エネルギー」は科学で広く使用される用語であり,様々な物理現象の理解に有用な概念であるが,つきつめると何なのか?となってしまい,実は難しい概念である.
著者のコエーリョ(Ricardo Lopes Coelho)は力学の歴史を専門とする科学史・科学哲学の研究者であり,ポルトガルのリスボン大学理学部の教員である.力学概念史を扱う論文に加えて,「エネルギー概念について:その歴史を理解することで物理教育をどのように改善できるか」といった物理教育への活用を視野に入れた研究も進めてきた.これまでの彼の研究がいかんなく発揮されたのが本書である.
第1章では,エネルギー概念をめぐる歴史的な問題が示される.1840年代以降,エネルギーを考えるうえで重要な研究が数多く現れたが,それらを経た1901年,ポアンカレはエネルギーの「一般的な定義を見出すことは不可能である」と結論づけ,ファインマンは1963年の著作のなかで「今日の物理学では,エネルギーとは何かについて私たちは何も知らないということを認識するのが重要である」と述べた.エネルギーは,エネルギー保存則やエネルギー変換で説明されるが,一部の物理学者はエネルギーとは何かは分からないとしている.とはいえ,これまでエネルギーは研究されてきたのである.1840年代以降にエネルギーの何が研究され論じられてきたのか.
第2章では,1840年代に集中的に行われたエネルギー保存に関する熱の仕事当量の研究が紹介されている.登場する物理学者たちは,マイヤー(Julius Robert von Mayer),ジュール(James Prescott Joule),コールディング(Ludvig August Colding),ヘルムホルツ(Hermann von Helmholtz)である.彼らはともにエネルギーに関する熱研究を行い,「熱は力の一形態(a form of force)」,「熱は運動(motion)」,「熱は自然の力(a force of nature)」とする諸見解を打ち出した.
とくに,本書はマイヤーとジュールの研究をエネルギー研究の主要な起点として扱っており,第2章で各20頁ほどかけてマイヤーとジュールの研究を紹介している.「力(force)」を諸現象の原因と規定し,25種類の実験と通じて力を,重さ,運動,熱,電磁気,化学的作用の5形態に分類し,熱の仕事当量の算出を試みたマイヤーが「熱は力の一形態」と考えた背景が詳細に語られる.また,落下作用によって回転するパドルによる水温の変化の実験などを繰り返し行い,精緻に熱の仕事当量を決定したジュールが「熱は運動」と考えた背景も詳細に知ることができる.
第3章以降は,マイヤー,ジュールらの研究からの発展という視点でその後の展開が語られ,19世紀のエネルギー研究が概観される.彼らの研究が起点となり,諸現象を関連づける「力」が「エネルギー」の概念へと発展し,熱が物質であるか,運動であるかを研究する延長線上にトムソン(William Thomson,後のケルヴィン卿)やクラウジウス(Rudolf Clausius)の二つの熱力学法則の誕生も見られる.諸現象のエネルギー研究が実り豊かな物理的成果をもたらしたのである.結局のところ,「エネルギー」は何か実体があるわけではなく,知的に実体化されたものであるが,実験結果にもとづくエネルギー保存の原理を支持すべく諸研究がもたらした重要な概念が「エネルギー」なのであった.
エネルギー保存則の確立に貢献したマイヤー,ジュールたちとその後の関連研究を詳細に知ることができる書籍は稀有であり,そうした点で本書は貴重である.また,エネルギー研究史の詳細を繙くと,19世紀に試行錯誤されたエネルギーの複数の言説が現在の物理教育における説明の仕方に活かされていることが分かり,今に至っても意見の分かれる「エネルギー」の定義の有無は,こうした歴史的背景を踏まえると納得できる.一方で,「エネルギー」という言葉を初めて使用したとされるヤング(Thomas Young)は脚注で多少触れられる程度である.本書の視点では重要でなかったからかもしれないが,扱い方に偏りがあるという印象も受ける.とはいえ,エネルギーの重厚な歴史は物理教育で有用な教育資料を与えると考えられ,その貴重な材料を本書は提供してくれる.高価な一般書ゆえにアクセスする機会は限られてしまうだろうが,物理教育にたずさわる方々に一読を勧めたい.
加えて,本書が収録されるSpringerの物理学史シリーズには興味深い書籍(『ボリス・ゲッセン:1927-1931年のソビエト連邦における物理学と哲学』,『乱流:知的探求の旅』,『ミラノ物理学研究所』など)が揃っており,機会があれば手に取っていただきたい.
(2024年9月1日原稿受付)
Evolution Seen from the Phase Diagram of Life
S. Mitaku,R. Sawada 著
Springer Nature, Singapore, 2024, x+144p, 23 cm×15 cm, €107.55(Evolutionary Studies)[専門・大学院向]ISBN 978-981-97-0059-2
紹介者:藤原久志〈広島市大情報科学〉
遺伝情報の主体となる細胞内DNA全体をゲノムと呼ぶ.DNAの構成要素は,A(アデニン),C(シトシン),G(グアニン),T(チミン)の4種類の塩基である.ちなみにRNAの場合,Tに相当するのはU(ウラシル)であり,遺伝暗号表参照の際には注意が必要である.
生物ゲノムデータは,典型的なビッグデータ(たとえばヒトゲノムは約30億の塩基対)である.本書の著者の一人である美宅成樹氏は,物理学の視点に基づく独自のバイオインフォマティクス(ゲノムデータの意味を読み解く方法論)研究を40年近くの長きに亘って進めている.もう一人の著者である澤田隆介氏は,美宅氏の共同研究者である.
本書は,美宅氏とその共同研究者達(澤田氏を含む)による研究の集大成であると共に,塩基組成の偏向に基づく新たなゲノムデータの読み解き方を提示するものである.
本書を読まれる前に,できれば美宅氏による『ゲノム系計算科学』(2013),『生物とは何か?』(2013),『モダンアプローチの生物科学』(2015)といった前著に目を通されると良い.本書の11章の最初(11.1)までは,主としてこれまでの研究の総括であり,これらの和著を予習しておくことで,見通し良く読み進めることができると考える.本書の11章の途中(11.2より)からは,より進んだ新しい方法論が提示され,本書評ではこの新たな方法論に焦点を絞って論ずることにする.
遺伝暗号表には,塩基3文字(コドン)でのアミノ酸の指定以外にも規則性があることが知られている.たとえば,『ヴォート生化学(上)第4版』の遺伝暗号表(76ページ)では,コドン2文字目がU(ウラシル)の場合に非極性アミノ酸が指定されることを褐色の升目で表現している.著者らはこうしたコドン2文字目の特徴に加えて,1文字目にもタンパク質の柔軟さに関する規則性があると主張する.そして,コドン表の1文字目と2文字目でほぼアミノ酸が特定されることに基づき,ある組成の塩基配列(生物ゲノム)と完全に乱雑な組成との距離D12を定義するd1及びd2を提唱した(下記参照).ここでx1及びx2はコドン1文字目及び2文字目の塩基(A, T, G, C)組成である.
実際の計算では,当該生物ゲノム全体の中からタンパク質遺伝子(コーディング領域)を抽出し,それら遺伝子全体でのx1及びx2を計算し,d1及びd2を算出する.結果として,ある生物ゲノムは2次元座標上の一点(d1, d2)で表される.
こうした生物ゲノムの2次元への射影を2,551種の原核生物及び113種の真核生物で行った例が本書101ページの図11.4である.一部例外はあるが,データ点(生物ゲノム)の存在領域―著者らによれば"habitable zone(生存可能領域)"―と非存在領域が明確に分かれており,d2値が大きくなるにつれてGC含量(塩基配列のG+Cのモル百分率)が小さくなる傾向も見てとれる.
この図11.4は,著者らの提唱する「生命の相図(phase diagram of life)」の2次元版である.その8次元版は図11.1と11.2であり,これらの図は著者らによる2018年の原著論文(Biophys Physicobiol 15: 75-85)の図1と2に対応している.この原著論文にも「2551種の原核生物及び113種の真核生物を解析した」との記述があるので,時期で言えば2018年から2024年,本書で言えば11章(11.1から11.2)のどこかで,同じゲノムデータセットの前で著者らの思考に言わば「相転移」が生じ,「生物ゲノムデータの2次元への射影」を手にするに至っているのである.
図11.4を「生命の相図」と呼ぶことの妥当性は,今後の重要な論点である.しかし,評者としては,その議論を可能とする「生物ゲノムデータの2次元簡約化」に敢えて着目したい.「人間が次元数の多いデータについて考えるのは難しい(ダイテルPythonプログラミング)」ので,優れたデータの2次元化には研究推進への飛躍的な効果が期待できるのである.そして,改めてd1とd2の算出方法を見ると,「0.25(4つの塩基が均等に出現する確率)での減算」が秀逸である.この減算により,著者らが主張する「生物ゲノムデータが完全に乱雑な組成(d1d2座標の原点)から著しく偏っていること(=低エントロピー状態)」が鮮やかに示されるからである.
本書評を締めくくる前に,GC含量(コーディング領域)を含めた評者による計算例(Biopythonを活用)を「実際に用いたゲノムデータの識別子」と共に紹介する.GC含量51%のヒト(GCF_000001405.40)のd1d2座標値は(0.11, 0.096)であり,D12値は0.14である.これに対し,GC含量24%の熱帯熱マラリア原虫(GCF_000002765.6)のd1d2座標値は(0.26, 0.33)であり,D12値は0.42である.実は,ヒトを含めた哺乳類(数種は実際に計算)は恐らくD12値が最も低い生物の一群である.これに対して,「生物の相図」に慣れてきた目(=実際にいろいろな生物種で計算を実施)で見るとD12値0.42は異常に大きく,熱帯熱マラリア原虫(低GC含量で知られる)は「徹底的な偏り」を選んだとても変わった生物である.
本書は,物理学を活かして生命科学に挑もうとする研究者に是非読んでいただきたい.特にこれから独自の学問確立を目指す研究者(大学院生を含む)にとっては,本書と上述の2018年の原著論文との読み比べは,独創性(相転移)の育み方の良い参考となるであろう.また,ご興味を持たれた熱力学・統計力学の専門家には,本書をご一読いただき種々の批評をお願いしたい.そのような批評こそ,著者らの望むところと考えるからである.
(2024年9月20日原稿受付)
たのしい物理化学2;量子化学
山本雅博,池田 茂,加納健司 著
講談社,東京,2024,vi+148p,26 cm×18 cm,3,080円[学部向]ISBN 978-4-06-534043-1
紹介者:大谷 実〈筑波大〉
本書は,『楽しい物理学1 化学熱力学・反応速度論』に続く第2巻である.タイトルは「量子化学」だが,1巻・2巻を通して物性物理学の実用的な基礎知識を身につけることができ,物性物理を学ぶ読者にも有益な内容となっている.これは,著者が長年,物理と化学の境界領域で活躍してきたことが関係していると思われる.本書は150ページと比較的薄い教科書であるが,式変形は丁寧に追われており,学部学生でも容易に理解できる点で優れている.
物理系の学生が物理化学を学ぶ際には,化学系の学生向けに書かれたものが多いが,本書は,物理系の学生が物理化学の入門書として手に取るのに適した教科書である.内容は基礎的であるが,発展的な話題もふんだんに散りばめられており,込み入った式変形などはWeb上に解説を載せている(正誤表もWeb上で頻繁にアップデートされている).また,コラムや脚注の解説なども多く,読者の興味を惹きつける工夫がなされている.
本書の最初の章である第15章「緒言」でも述べられているが,最先端の量子化学・物質科学の研究においては,対象となる方程式はコンピュータシミュレーションを用いて解かれることが多く,解析解が得られる現実系は少ない.そこで,本書では解析解が得られる系に関する記述は最小限に抑え,実践的な近似法や密度汎関数理論(DFT)に基づいた第一原理計算に関する記述を充実させている点も特徴である.
第16章から第18章までは量子力学の導入が行われる.量子力学発展の歴史に沿った解説がなされ,前期量子論からシュレーディンガー方程式を導入し,18章では量子力学の形式論が述べられる.ここではディラックのブラケット記法と不確定性原理が詳しく紹介されている.不確定性原理を交換関係から導くためには,幾つかの数式上の難関があるが,これらもWeb上の解説記事で詳しく説明されているため,初学者でも理解しやすいと思われる.
第19章と第20章は上述の解析解が得られる系のシュレーディンガー方程式の解法に当てられており,19章では1次元系を主に考えている.ここでは,いくつかのポテンシャル障壁の問題が考察されている.モデルは簡単な系に限定されているが,後半ではSTM実験に関する記述と演習問題が用意されるなど実用的である.20章では水素原子が扱われている.極座標のラプラシアンや特殊関数などが出てくるところであり,通常の教科書では行間が大きくなってしまいがちであるが,Web上の解説記事が充実しており,読者にとって大いに助けとなることが期待される.また,得られた透過係数や波動関数などは図示されており,視覚的にも理解を深めることができる.
第21章では,摂動論などの近似法を学んだ後,変分法を導入し,2原子分子から多原子分子にわたる分子軌道の理解を試みている.LCAO法にヒュッケル近似を適用し,分子軌道を可視化するダイアグラムを導入する点は,物理系の読者にとって新鮮に映ると思われる.
第22章では,DFTに基づいた第一原理計算法についてまとめられている.本章では,ファンデルワールス相互作用をDFTで扱う方法論など,最新の第一原理計算で用いられる標準的な理論までがコンパクトに整理されており,初学者が全体像を把握するのに役立つと思われる.コンパクトさゆえにそれぞれの説明は必要最小限の記述となっており,飽き足らない読者は他書をあたるのが良い.本章最後のヘルマン-ファインマンの定理に関する記述は,現代の分子や結晶の構造最適化や第一原理分子動力学も含め,最も良く使われている定理の一つについての興味深い内容となっているので,ぜひご一読いただきたい.
第23章は物質の光応答についてまとめられている.21章で学んだ摂動法を駆使して,光(電磁波)と物質の相互作用を詳細に学べるようになっている.振動子強度,赤外吸収,ラマン散乱など重要な計算技術に関して,式変形も丁寧に示されているので,手を動かしながら学ぶことができる.
以上のように本書では,物理化学を学ぶ上で必要となる知識が,理論研究者の観点から丁寧に記述されている.物理と化学の境界領域は,物質科学の観点からも重要であり,その応用は,触媒,化学電池や腐食の研究・開発など多岐にわたっている.したがって,物質科学を学ぶ物理系の学部生・大学院生にとっても一度手に取って読んでみる価値のある一冊である.
(2024年10月15日原稿受付)