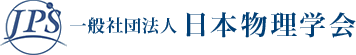2019年ノーベル物理学賞は,物理的宇宙論における数々の理論的発見に対してジェームズ・ピーブルズ教授に、 また太陽と似た恒星の周りを公転する太陽系外の惑星の発見に対してミシェル・マイヨール教授とディディエ・ケロー教授の3名が受賞した。
公開日:2019年10月8日
解説
2019年度のノーベル物理学賞は、「物理的宇宙論における数々の理論的発見に対して」(for theoretical discoveries in physical cosmology)米国プリンストン大のジェームズ・ピーブルズ教授に、また「太陽と似た恒星の周りを公転する系外惑星の発見に対して」(for the discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star)スイス・ジュネーブ大のミシェル・マイヨール教授と同大(英国ケンブリッジ大学兼任)のディディエ・ケロー教授に授与されることになった。この3名の業績は「宇宙の進化と宇宙におけるこの地球の立ち位置に関する人類の理解への貢献」( contributions to our understanding of the evolution of the universe and Earth's place in the cosmos)であると総括された。
ピーブルズは、現代標準宇宙論の理論的枠組みの確立に大きな貢献を果たした。1965年にベル研究所のペンジアスとウィルソンが偶然、宇宙マイクロ波背景輻射(CMB)を発見した際に、そのすぐ近くのプリンストン大学でディッキー教授率いるCMB探査グループの一員だったのがピーブルズである。それ以降一貫して、ビッグバン宇宙論の基礎理論の確立に大きな貢献をしてきた。今やCMBは、観測的宇宙論を支える最も精度の高い基礎データとなっているが、ピーブルズはその温度非等方性を定量的に計算する方法論を作り上げた。さらに、宇宙誕生約3分後に形成されたヘリウムの存在量、約38万年後に起こった宇宙の再結合(電離水素が中性化する過程)、膨張宇宙における密度揺らぎの線型成長とその後の非線形成長モデル、相関関数を用いた銀河分布の統計的記述など、現代宇宙論で当たり前のように用いられている数々の基礎過程の理論的定式化を確立したのがピーブルズである。また、彼はダークマターや宇宙定数の存在を早い時期から積極的に支持し取り込んだ研究を主導することで、どちらかといえば保守的な天文学者の間で、それらの革命的な概念が受け入れられることにも貢献した。
一連の研究の集大成とも言える彼の教科書、Physical Cosmology (1972)、The Large-scale Structure of the Universe(1980)、Principles of Physical Cosmology(1993)が、世界中の宇宙論研究者を育て上げたと言っても良かろう。このようにピーブルズは、1960年代以降現在に至るまでの宇宙論の発展と興隆に多大な貢献を果たした巨人の一人である。
一言付け加えておくならば、1980年代末頃まで、ゼルドビッチ(故人)が率いるロシアの宇宙論グループも独立に優れた研究を展開しており、東側と西側が相互に競争しつつ世界の宇宙論研究をリードしていた感がある。特に今回の主な受賞対象の一つとされているCMBの基礎理論に関しては、ゼルドビッチとその弟子であるスニャーエフもまた、同時期にほぼ同じ結果を発表している。その意味で、ピーブルズにノーベル賞を与えるのであればスニャーエフも共同受賞すべきだとの意見もありえよう。
マイヨールとケローは、太陽以外の恒星の周りを回る惑星を初めて発見し、太陽系外に無数の惑星系が存在しているという全く新たな世界観を切り拓いた。
太陽系以外に惑星が存在するかどうかは、極めて根源的な問いである。しかし、その観測的検証は容易ではない。例えば、太陽系を遠くから観測した場合、最も大きい木星ですら、その明るさは太陽の1億分の1以下でしかない。すぐ横にある太陽光を完全にブロックしない限り、木星の直接検出はほぼ絶望的である。一方で、惑星をもつ恒星はその共通重心の周りを公転しているから、ドップラー効果を利用して恒星の視線速度の周期運動が検出できれば、惑星の存在は間接的に証明が可能となる。
ただし、太陽系の木星の公転周期が12年であることを思えば、本当に惑星が存在すると確信しない限り、研究人生の長期間を無駄に過ごしてしまうハイリスクの研究となる。実際、1995年8月、ブリティッシュ・コロンビア大学のウォーカーらのグループは、毎年連続した2晩の観測を3回から6回行うという方針のもと、21個の恒星を12年間にわたり継続的に観測したものの、15年以下の公転周期を持つ木星の質量(木星質量)の1から3倍の惑星は存在しないとの否定的な結果を発表していた。
マイヨールは、1977年から13年間かけて291個の恒星の視線速度を定期的に観測し、37個の恒星の視線速度の周期変化を検出したものの、それらは惑星ではなく恒星を伴った連星系ばかりであった。そこで、有意な視線速度変化が検出できなかった142個の恒星を選び、新たに開発したフランスのオートプロバンス天文台のELODIE分光器を用いて、1994年4月からさらに高精度の観測を開始した。そのわずか1年後、当時大学院生であったケローとともに、ペガスス座51番星(51Peg)の周りをわずか4.2日の周期で公転する0.47木星質量の惑星51Peg bを発見したのである(bはその恒星の最初の惑星であることを示す。以降、同じ恒星に別の惑星が発見されれば、c、d、として区別される)。
この予想外の発見は、大きな衝撃をもって迎えられた。51Peg bとその中心星との距離は、太陽と木星のわずか100分の1でしかない。そのため、51Peg bの表面温度は1300ケルビンにも達するはずで、ホットジュピターと呼ばれる新たな種族の初発見でもある。その起源はまだ明らかになってはいないが、はるか遠方で形成されたガス惑星が、何らかの理由で中心星のごく近くまで落ち込んできたものと考えられている。つまり、惑星系は決して安定なものではなく、時間をかけて様々な力学的進化を経ていることが結論される。
マイヨールとケローの発見以降、現在までに約3000個の系外惑星系が発見され、うち600個以上は多重惑星系であることもわかっている。今や、太陽に似た恒星のほとんどは惑星をもつのみならず、それらは我々の太陽系の"常識"からは考えられないほどの多様性を有していることが明らかとなっている。そして、天文学者は、生命を宿す惑星の発見をさらなるゴールとして見据えている。
このように、マイヨールとケローは、太陽系外惑星という新たな研究分野を創設したのみならず、宇宙における地球の存在を相対化し、我々の世界観に革命をもたらしたのである。
(東京大学理学系研究科物理学専攻 須藤靖)
専門的な解説は、日本物理学会誌に掲載された以下の記事も参照してください。
杉山 直「宇宙論の大展開」
日本物理学会誌 74巻6号, 362-363, 2019年
井田 茂「系外惑星の多様性と遍在性」
日本物理学会誌 70巻9号, 672-673, 2015年
平野照幸「太陽系外惑星探査:見えてきた多様性とその起源」
日本物理学会誌 72巻2号, 105-110, 2017年
日本物理学会は,今後,受賞業績に関する情報をホームページ,日本物理学会誌を通して発信していく予定です。また,受賞理由のより詳しい解説がノーベル財団のサイトで見られます。