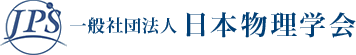[解説追加しました(10/8)]2023年ノーベル物理学賞は、「物質中の電子ダイナミクスを研究するためのアト秒パルス光の生成に関する実験的手法の業績」により Pierre Agostini 氏(The Ohio State University, USA)、 Ferenc Krausz 氏(Max Planck Institute of Quantum Optics, Germany)、Anne L'Huillier氏(Lund University, Sweden)の3氏が受賞することに決定。
公開日:2023年10月3日
2023年のノーベル物理学賞は「電子のダイナミクスを研究するためのアト秒パルスの生成に関する実験手法」に貢献のあったPierre Agostini(米国), Ferenc Krausz(ドイツ), Anne L'Huillier(スウェーデン)の三氏に授与。
解説
近年のレーザー技術の発展は目覚ましく、超短パルスレーザーのパルス幅は、今や数フェムト秒(1フェムト秒は10-15 秒)に達している。このフェムト秒パルスを使ったポンプ・プローブ計測によって、分子や固体内での原子の移動過程を時々刻々追跡することができるようになった。一方、物質に光が照射される際に最初に「瞬間的に」応答するのは物質の中の電子であって、その電子の光応答の結果として、原子が動き出すことを考えれば、この瞬間的な電子の動きを時々刻々捉えることこそが物質の光応答の本質を理解することにつながることになる。しかしながら、数フェムト秒の時間内には、すでにその瞬間は終わっているため、1フェムト秒を切るアト秒領域(1アト秒は10-18 秒)の光パルスの生成とそのアト秒パルスを使ったポンプ・プローブ計測の実現が待ち望まれていた。
このアト秒パルスの実現は、短パルスレーザーの高出力化への技術開発に伴って原子の光イオン化過程が調べられるようになったことに端を発する。1979 年にAgostini らはXe の多光子イオン化の光電子エネルギースペクトルを計測し、イオン化するのに最低限必要な数の光子によるイオン化の信号だけでなく、それよりも多くの光子が関与した超閾イオン化(above threshold ionization, ATI)を示すピークの並びを観測した。その後、この光電子のエネルギー構造には面白い特徴があることが明らかとなった。光電子のエネルギーが増加しても信号量が大きく減少しない「プラトー領域」の存在とその信号量が急激に減少する「カットオフ」の存在である。このATIの観測は、そのメカニズムの理論研究の発展を促した。そして、ATIにおいては、光の場の中での電子の再衝突過程が重要な役割を果たすことが理解されるようになり、1987年にKuchiev は強い光電場の中でトンネルイオン化によって原子領域から離れた電子が、光電場の中で原子イオンに戻ってきて衝突を起こし、そして、原子系を高く励起することを量子力学に基づいて明らかにした。
ちょうどその頃、超短パルスレーザーを希ガス中に集光すると高次高調波とよばれるレーザー周波数の奇数倍の周波数を持つ光、すなわち、奇数倍の光子エネルギーを持つ光子が発生することが相次いで報告されるようになった。1987年には Rhodesらのグループが、そして、1988年には L'Huillier、Mainfrayらのグループが高次高調波の生成を報告している。この高次高調波は、ATIの構造と類似する特徴をもっていた。すなわち、低次数の高調波は次数が上がるにつれて強度が下がるが、その後、広い次数に亘って強度が変わらないプラトー領域があること、そしてその先に、急激に強度が落ちるカットオフの領域があることである。この高次高調波の発生が報告されて以来、多くの研究グループがそのメカニズムを理論的に説明することを試みた。1992年に Kulander らのグループは数値計算によってプラトーとカットオフを説明し、1993年には、プラトーとカットオフが3つのステップによって説明されること、すなわち、トンネルイオン化、レーザー電場による加速と再衝突、そして、再衝突に伴う高次高調波の発生というステップからなることを報告している。また、同じ1993年には、Corkum は Kulander とは独立に高次高調波の発生が3つのステップによって説明されることを示している。この「強レーザー場での電子の再衝突のモデル」は、高次高調波を説明するための標準的なモデルとして受け入れられている。
一方、1992年には、Farkas とTóth が、超短パルスレーザーによる高次高調波が時間領域においてコヒーレントであることに着目し、異なる次数の高次高調波を重ね合わせればアト秒パルスが発生できるという提案を行った。これは再衝突のモデルで言えば、トンネルイオン化された電子が原子イオンに戻って来て再衝突する度にアト秒パルスが生成することに相当する。
2001年、Agostini のグループは、高強度フェムト秒パルスをArガスに集光することによって、高次高調波を発生させ、2波長2光子干渉法を用いて、一つ一つのアト秒パルスの時間幅が250 as のパルス列が生成することを確認した。そして、同じ2001年、Krausz のグループは、数サイクルの高強度フェムト秒パルスを用いてKrガスに集光することによって、単一アト秒のパルスを発生させ、光電子ストリーキングという方法によって、そのパルス幅が650アト秒であることを確認した。
ATIから始まった一連の仕事の流れは、2001年になってようやくアト秒パルスを発生させること、そして、それがアト秒パルスであることを実証するという一つのゴールに到達した。そして、原子から電子が放出する際に、どの軌道から電子が放出されるかによって、わずかなアト秒領域の差が存在することが明らかにされるなど、今まで、「一瞬で起こる」と思われていた現象を、アト秒の精度で実際に確認することができるようになった。このアト秒パルスの生成のおかげで、人類は物質の中で電子が、あるいは電荷分布がどのように変化していくかを実時間で観測することができるようになった。Agostini、Krausz、L'Huillierの三氏は、実験と計測の立場から、このアト秒科学の黎明期に大きな貢献をしたのである。
我が国でも、高次高調波が発見された1980年代末から、多くの研究者がこの分野の発展に寄与してきた。2004年、渡部俊太郎氏(東京大学物性研究所)らは、自己相関法により950asの孤立アト秒パルスの計測に成功した。また、緑川克美氏(理化学研究所)らは、2002年にそれまでの高次高調波の強度を2桁以上増強する技術を開発し、アト秒領域での様々な非線形現象の観測を進めた。特に、2006年には、電場干渉自己相関測定によって、高次高調波の発生原理を実証している。緑川氏らの一連の実験は、アト秒パルスだけを使ったポンプ・プローブ実験のさきがけである。
今、アト秒科学では、物質内の電子の運動の実時間計測によって、次々と新しい現象が発見されている。そして、アト秒パルスを用いた今後の研究によって、化学反応の機構や電子デバイス機能の解明が可能となるものと大きな期待が寄せられている。
(東京大学アト秒レーザー科学研究機構 山内 薫)
日本物理学会誌に掲載された以下の記事もご覧ください。
「アト物理:超高速現象にどこまで迫れるか」(物理学70の不思議)
日本物理学会誌71巻7号, p.449, 2016年
石川顕一「電子の超高速運動を観測する・操作する」
日本物理学会誌71巻12号, pp.818-819, 2016年
関川太郎, 渡部俊太郎「極端紫外アト秒パルス発生と非線形光学」
日本物理学会誌60巻7号, pp.527-534, 2005年
小栗克弥
「ペタヘルツエンジニアリング創出に向けたアト秒光物性~NTT物性科学基礎研究所における超高速光物理研究~」
日本物理学会誌70巻12号 pp.936-940, 2015年